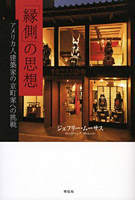

2──『団地の見究』
建築は生きている。建築は使われることで老いるものではなく、命の輝きを増してゆく。そうあるべきものだと思っている。
ジェフリー・ムーサス『「縁側」の思想』(祥伝社)は建築を学ぶために来日した著者が、数奇屋大工の工務店や日本を代表する設計事務所で経験を重ねながら、日本固有の建築や文化に接し、京都の町屋と向き合うようになり、改修や再生を手がけるに至る半生の自叙伝である。町屋という建築形式は1000年以上の歳月を引き継がれ、進化を繰り返しているという。その町屋という時を超越した、歴史そのものに現代の命を吹き込み、日本建築の精神性を体現し生業としている氏を、日本人としても正直羨ましく思う。
建築に限らず、都市で静かに息づく構造物・構築物に注目が集まったのが2008年の特徴である。ダム、工場、水門、そして団地等など。大山顕著『団地の見究』(東京書籍)は、高度成長期に供給された団地というビルディングタイプの核心に迫る。団地といえば近代の象徴として、その間取りの研究は多く紹介されてきたが、こと外観に関しては「団地のような……」というネガティブな視線がその配棟計画に注がれるだけで、団地単体のファサードに着目した著書も少なかったように思う。氏の写真からは、風化にさらされながらも使い込まれ、味わいを増している団地のファサード、否、というより骨太な「構造」と呼ぶべき力強さが伝わってくる。地味ながらも都市のインフラとして生き続ける団地は、商品として消費される建築を横目に、都市の成熟に静かに寄り添う。


4──『川の地図辞典』
東京を題材とする書物は相変わらず多く出版されているが、塩見鮮一郎『貧民の帝都』(文春新書)の発刊に合わせるように、同氏の著作『弾左衛門の謎』『弾左衛門とその時代』『江戸の非人頭車善七(いずれも河出文庫)』などが2008年に相次いで文庫化された。
江戸時代におけるエタ・非人などと称された被差別民の首領であった弾左衛門とは、名であるとともにひとつながりの職掌をあらわしている。徳川の入国以前から続く身分制度に不可欠な制度(弾左衛門制度)でもあったが、『貧民の帝都』ではその身分制度から生じた、革命(維新)の負の産物をどのように救済したのか、近現代の暗黒行政を教えてくれている。氏の多くの著作から、江戸の世の華やぎを持続させるには、賤民制という、文化・社会・経済に組み込まれた影の体制が不可欠だったことに気づかされる。停滞を必死で持続しようとする、江戸という社会の特殊性を振り返る機会をいただいた。
また、古地図と比較しながら東京の歴史や文化を解説する本がガイドブックさながら、書店を賑わしているが、菅原健二『川の地図辞典』(之潮)は、自分も含め多くの地形マニアの支持を集めている待望の一冊である。山の手台地を刻んだ河川や「失われた川(旧水路)」、時代を支えた上水道の数々を紙面に蘇らせてくれた。東京の街の骨格は江戸の町割りを下敷きとしているが、江戸の町は武蔵野台地東端の特徴的な地形を巧みに利用し造られていた。水の流れという原地形を辿れば、江戸と東京は地続きであることを実感できる。山の手の「失われた川」を追いかけるのも興味深いが、はりめぐらされた運河網からも、川の手(下町低地)が「水の都」として、いかに魅力に溢れていたかも想像できる。余談ではあるが終戦時に緊急処置的に埋められた多くの運河遺構を、今世紀に発掘するのはいかがだろうか。公共事業ではなく、ボランティアによる町ぐるみの発掘イベントなんていかがでしょう。