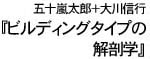ただいま紹介いただいた中村です。偶然ですが、今年の4月から私も名古屋にある中部大学の建築学科でデザインを教えていて、五十嵐さんとは同僚ということになります。
実は今年の初めに五十嵐さんの2冊目の著書である『新宗教と巨大建築』の書評を共同通信で書かせてもらったので、五十嵐さんの著書の書評は2冊目になります。
ルイス・カーンの初源への問いかけ
ビルディングタイプという言葉を聞くと私がいつでも思い出すのは、「私は始まりを愛する」というルイス・カーンの語った言葉です。彼が例としてあげていたのは、例えば学校を設計するとき、そもそも学校がなぜ始まったのか、その起源に思いをめぐらすということで、1本の樹の下で、ある事柄についてよりよく知っている人に、そのことについて知りたい人が問い掛けた、という場面を想像して、その場にふさわしい空間を構想するわけです。そのとき当然現在の学校がどのようなシステムなのか、つまり既存のビルディングタイプは最初から考えられていません。意図的にそうしたものを無視して、その建築がなぜ、どのように求められているのかを常に初源にかえって検討し、空間を構想するわけです。ルイス・カーンはそうした初源への問いかけを最も意識した建築家のひとりでしたが、カーンに限らずそれまでの古典建築へのアンチテーゼとして出発したモダニズムは、最初からビルディングタイプへの問いかけを含んでいたといってもよいと思います。
プログラムの複合性/ビルディングタイプの解体
ビルディングタイプは同時に建築計画学という専門分野を生み出したわけですが、プランニングの効率化、標準化によって機能的なレベルを上げるという役割は大きいのですが、逆にそうした標準化によって現実に作られる建築が硬直化してしまうという弊害もいろいろな場面で指摘されてきました。そして特に現代では、政治・経済・教育・文化さまざまな領域で戦後のシステムを見直さざるを得ない状況になっていて、これまでわれわれが当たり前のものとして捉えてきた学校、美術館、市民ホールといったビルディングタイプの区別が曖昧になってきています。それは私が設計の現場にいても、プログラムの複合性というかたちで日々痛感するようになってきました。SOHOという言葉に代表されるように、住宅と事務所というタイプすらその境界が曖昧になってきていますし、仙台メディアテークに典型的に表現されたように、それまで図書館とか美術館とか単独に計画されてきた公共建築というビルディングタイプそのものが解体されつつあるわけです。
特に、皆さんよくご存知だと思いますが、学校建築に関しては早くからタイプの見直しがおこなわれていて、1980年代から教室を廊下がつなぐという単純なタイプをオープンスクールという名で、さまざまな試みがなされ、最近では多くの教室や運動場を持った小・中学校が平日しか使われないのはおかしいのではないかという議論から、学校をいかに開放して例えばコミュニティセンター的に使えるかという試みがさまざまになされていますし、最近の建築家による作品としては、体育館という小学校の持ちうるもっとも大きな内部空間を中心に据えた小島一浩さんの吉備高原や打瀬の小学校、青木淳さんの御杖小学校なども、学校というビルディングタイプの解体過程の大事なステップとして考えることもできるわけです。
ペブスナー、フーコー、ベンヤミンを背景として
このように設計の現場では既存のビルディングタイプを見直すために試行錯誤を繰り返しているのですが、そのためのガイドラインはもちろん全くなく、それこそルイス・カーンの直感的な言葉を手がかりにするしかない。そうした中でこの「ビルディングタイプの解剖学」は、すばらしいタイミングで出版されたといってよいと思います。
もちろんこの著作にはいくつかの背景があって、ペブスナーの有名な「ビルディングタイプの歴史」(これに対する批判として本書は出発しています)や、権力と空間の関係を見事に描き出したミッシェル・フーコーの『監獄の誕生』があるのですが、本書はそれまでの建築史がゴシックやバロックといった様式を中心に建築を分類してきたことを批判し、建築史が語ってこなかった教会や学校というタイプの起源、そして変遷を、体系的にとはいえないまでも多くのエピソードを集積させることによって、これまで自明のものと思われてきたビルディングタイプを解体しようとしています。
全体は教育、生産、矯正、収集という大きく4つの章に分かれています。最初の3つの章に学校・教会・クエーカー教と近代施設、倉庫・工場、そして監獄・病院があてられ、最後の4章は少しシフトして収集というテーマのもとに、動物園・万博・パサージュがとりあげられています。
最後のパサージュは90年代に都市論というと必ずとりあげられたベンヤミンの「パサージュ論」を下敷きにしているので、ご存知の方も多いと思いますが、アレゴリー(寓意)をキーワードとして、ビルディングタイプの越境をテーマに彼の著作を読み返すという試みで、ベンヤミンにこれまでとは違った光をあてており、本書の執筆の上では実は精神的背景ともいうべき部分で、一番最後にひっそり置かれていますが、実は最初にこの章を読むのがよいのかもしれません。
それぞれのビルディングタイプが生まれてきた起源にまでさかのぼり、まだシステムとして確立されていなかった時の試行錯誤が語られているわけですが、特に「病院」の章で語られた空気を循環させるという環境装置がいかに重要な役割を果たしていたか、そしてそれをペブスナーがどのように見過ごしていたかを語った部分が最も印象に残ります。病気は悪い空気から発生すると信じられていたために、すでに18世紀後半から病院内の空気をいかに循環させるかというまさに「機能主義」としかいいようのないアプローチで病院が計画されていたわけですが、その外観は全くの新古典主義ですから、これまでの建築史においてはまったく取り上げられることがなかったわけです。新古典主義の建築が実はその内部の空調システムから変革を始めていたというエピソードはとても刺激的で、ポンピドーセンターのあのダクトを露出させるスタイルを生み出すまでに人類は200年をかけたのか、と思わず感慨にふけってしまいました。
新しい空間の可能性を考える刺激的な視点
これまで近代建築を語ってきたギーディオン、ヒッチコック、ペブスナーという歴史家たちの著作は、実は客観的な歴史などではまったくなく、近代建築というスタイルをいかに擁護するかというきわめてイデオロギー的な著作であったことが、今ではますます明らかになっています。東西の冷戦構造が崩壊し、もはや世界を動かすのはイデオロギーではないという成熟した資本主義社会において、われわれ建築家が新しい空間の可能性を考える上で、本書は多くの刺激的なヒントを与えてくれますし、これから行われるであろうさまざまな人々のビルディングタイプ解体の試みを体系化していく上で、きわめて貴重な一歩となる著作であることは間違いありません。
もちろん五十嵐さん、大川さんへの注文もまだまだたくさんあります。ビルディングタイプが未分化な時代の事例ももっと取り上げてほしい。例えば日本の中世で寺院の果たした役割。「寺院」という言葉が今とはまったく異なる意味を持っていたはずです。さまざまな謀議や宿泊の場、あるいは学習の場として、現代のホテルや会議場、学校の役割を果たしていたと思うのですが、その実態がほとんどわからないので、私個人としては是非教えて欲しい。
また今ではあまり語られなくなってしまいましたが、さまざまな用途に改修されながら何百年にもわたって愛され使われ続ける建築の価値を語ったアルド・ロッシの「都市の建築」は、ある意味では最初にビルディングタイプの解体を提唱した著作でもありますから、その功績はきちんと評価されるべきだと思いますし、ロッシを五十嵐さんがどのように考えているのかもお聞きしたい。
こうした注文をつけたいのも、五十嵐さんがこれからの時代を代表する歴史家として活躍してもらえるのではないか、という期待があるからです。私は五十嵐太郎さんのような新しい視点を提案できる歴史家を同時代に持ちえたことを誇りに思いますし、またさまざまな人々が五十嵐さんに刺激を受けて「ビルディングタイプの解剖学」の持っている射程をどんどん延ばしていってもらいたいと思います。