| □ | . | □ | |
| □ | 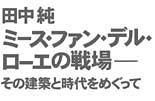 |
.□ |
|
| □ | .□ | 勝矢武之 |
|
| □ |  彰国社
彰国社2000年10月10日発行 定価:本体2500円+税 ISBN4-395-00580-2 |
.□ | ミースの建築とは何なのか。 そのあまりにも単純でそして掴みどころのない問いに対し、われわれは容易に「ミース」=モダニズム、インターナショナルスタイル、ユニヴァーサルスペース、レス・イズ・モア……と教科書的な言葉を列挙することができる。だが、それが語る「ミース」は果 たしてミースのすべてなのだろうか。「ミース」を語ることは、ミースを喪うことに繋がりはしないだろうか。そもそもわれわれは「ミース」を語ることについて考えねばならないのではないか……。 ミースは、近代の主体を収容する空間をデザインした建築家として、まさしく近代の体現者として扱われてきた。ミースを語ることは近代を語ることを意味し、それゆえ近代の批判と超克を目指す者たちにとって、ミースはつねに歴史化される必要があった。だが、過去を透明に語る批評などありえず、歴史にはつねにそれを語った主体の名が署名されている。ミースはいわば彼を語る者自身を映し出す鏡として存在し、建築家は「ミース」を語ることで、近代に対する己の位置づけを明らかにしてきた。それは裏を返せばそれぞれの主体の位置取りが遡及的にミースを「ミース」として定義してきたことを意味している。だが、モダニズムを批判し継承したポストモダニズム建築が終焉を迎えた現在、これまで語られてきたミースの歴史とそれを語った者たちは審判にかけられねばなるまい。ミースを読むことは、いままた新たなアクチュアリティをもとうとしている。 ミースはすでに亡く、世界にはただミースの建築が残されている。それゆえわれわれはミースの痕跡を通じてミースを再構成することになる。だが建築はあくまで沈黙したモノでしかなく、ひとつの決断によって空間に固定されたその姿は、決断に踏み切った建築家=主体の歪みや揺らぎを覆い隠してしまう。では、ミースはいかに語られねばならないだろうか。 さて、本書は言うまでもなくミースについての書である。だが、本書は次なる「ミース」=Xなる定義付けを拒否している。本書は言うなれば「ミース」=Xという記述の残余についての書であり、ミースをめぐる新たな問題構成を提起するのではなく、その問題構成の構図そのものの分析を目的としている。著者はミースの戦いの歴史を物語ることを放棄し、ひたすら戦場=廃墟を彷徨い、歴史に抹消された者たちを甦らせ、ミースが戦った戦場の地形を、ミースの基底面を浮かび上がらせていく。そのため本書は、通常の歴史書の体裁をとることなく、地理学的・考古学的にミースの生きた時空を併走し、哲学的に同時代の思想を分析し、精神分析的にミース自身の無意識に転移していくことになる。かくして本書は、「ミース」=Xという記述がこぼれ落としてしまう、ミースの生と建築がもつ亀裂や歪みを描き出していく。ミースはなにゆえ戦いそして躓かねばならなかったのか。本書はそれを語り、そしてその戦場へとわれわれをいざなうのである。 批評は透明ではありえず、批評の批評もまたしかりである。そしてあくまで重層的にミースを語る本書は、手短な要約をもってその内容を単線化しうるような類の書物ではない。そのことを承知のうえで、ミースがただひとり戦い続けた戦場の見取り図を一枚描いてみよう。果たしてミースは何と戦い、何を超えようとしたのだろうか。 著者は建築家ミースの誕生を、ダダイズムらが過去のあらゆる因習を否定し、新たな論理の構築を図っていた時代にあって、「建てること(バウエン)を建てること(バウエン)にする」というトートロジー構造の宣言に見出している。ミースは建築(バウクンスト)を具現化させるため、ダダイズム的な還元のなかから「建てることに固有の論理」を探求していく。そしてミースは、徹底した即物性のもとで、素材に内在する論理によってのみ建築を構成することを選択する。かくしてミースにとって、「建てること(バウエン)」は時代の技術に導かれることになる。だが、ミースが技術を時代の所与として肯定したのは、ひとえに技術を建築(バウクンスト)へと変容させるためであった。ミースにとって、技術は「時代を形成し表象する歴史的運動」であり、建築は時代の技術の表現となることで「空間に捕捉された時代意志」へと昇華されえたのである。 この「時代意志」をめぐり、著者はミースが迎えたひとつの転回を指摘している。著者によれば1920−30年代のドイツはひとつの危機の時代であった。その危機を乗り超えるべく、主体は「決断することを決断する」こと、すなわち合理的には基礎づけられない「決断する」という行為の引き受けを迫られていった。ここで主体はこの精神的決断の審級を占有することで、己を確立することになる。ここにあって建築家はもはや時代の操り人形ではない。建築家こそが、時代の所与のもとで精神的決断を超越論的に空間化するのである。建築家は時代精神というイデアを具現化するデミウルゴス(造物主)であることを求められたのである。 ここにひとつのアポリアが生じる。この転回は建築に写像・再現される「時代精神」というイデアが、超越的かつ先天的な原像ではないことを意味している。「時代精神」はあくまで決断者としての建築家=デミウルゴスの働きによって、建築(バウクンスト)が開示される過程で建築(バウクンスト)=エルゴン(作品=仕事)のなかに生成する。イデアのオリジナル(原像)など存在しない。そこにあるのは起源においてそれ自体が写像へと分割され遅延されたシミュラークルなのである。著者はミースが建築の追求の果てにこの根源的な問題に直面すると説明する。 ミースの躓きは「時代精神」のこのような超越論的な構造と、それを支えた「技術」の離反に起因する。「建てること」の決断を引き受けた建築家=デミウルゴス(造物主)は、やがて「建てること(バウエン)」の術として肯定した「技術」それ自体の発展の前に打ち砕かれたのである。近代化とともに圧倒的に発展した技術はいつしか建築家の手を離れ、建築は己の真理を技術の展開によって表現することができなくなる。だがそれでもなおミースは執拗に建築(バウクンスト)を追い続けた。技術の産物であったはずの建築のディテールは、やがて虚構の建築(バウクンスト)を現実に繋ぎとめる装飾と化して反復され続ける。そこでは建築は建築家=デミウルゴス(偽金作り)のもと、己の真理を己に語りかけながら秘教化していくほかない。 ミースにとって「技術」は時代の所与であり、超越論的なものに到達するための術であった。その技術が彼の脅威となったとき、ミースの戦いはすでに終焉を宣告されていたといえる。ミースの建築はまさしく闘争の記念碑として、その闘争の終焉の時を果 てしなく遅延させた狭間にこそ打ち建てられていった。終わることを遅らせ続け泥沼化するこの戦線は、ひとえにミースの死によってその幕を降ろすのである。本書は、重厚に織り上げられた記述のなかで、近代の真っ只なかで、ただひたすら近代的であることで近代の超克をめざしたひとりの近代人の姿を浮かび上がらせていく。 グロピウスはミースを「孤独な真理の探究者」と呼んだ。建築に精神的なる卓越(アレテー)を求めて戦い続けたミースを待ち受けていたのは、己の求めた精神(ガイスト)がその起源においてそもそも亡霊(ガイスト)でしかないという冷酷な事実であったろう。だが、誰が彼ほどにこの戦場を苛烈に戦いえようか。確かにミースは戦いの果てに躓いた。だがミースの建築がもつ紛れもない「強度」が、この孤高で気高い闘争の遺産であることは疑いようもない。われわれにとってミースがいまなお鮮烈でありうるとすれば、それは本書が測量するこのミースの戦場が、いまだ最前線であり続けているからではないだろうか。 |
