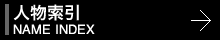ENQUETE
特集:201101 2010-2011年の都市・建築・言葉 アンケート<日埜直彦
建築や都市界隈で今年最も華々しいトピックと言えば、まずはSANAAや石上純也をはじめとする日本人建築家の活躍を挙げるほかないだろう。妹島和世がディレクターを務めた今年のヴェネツィア・ビエンナーレ建築展は、ここ最近社会的なテーマに向かっていたビエンナーレに祝祭性を取り戻し、建築のなしうることのごく基本的で即物的なありかたをあらためて提示した。近年都市や倫理を問うどちらかと言えばややこしいテーマ設定が続いていたが、どうしても閉塞するそうした指向とは異なった水準に、建築にできることのオルタナティブな可能性をあっけらかんと見せてくれた。評判もおおむね好意的で、近年になく多くの観覧者を集めたとのこと。まさにビエンナーレが掲げたテーマ通り、People meet in Architectureというところだろう。また未見ではあるが、SANAAとしての活動においても、ロレックス・ラーニングセンターの空間の分節と連結の新しさは疑いないし、西沢立衛の豊島美術館も彼の代表作のひとつにふさわしい強度がある。
ヴェネツィアで金獅子賞を勝ち取った石上純也の国内で開催された2つの展覧会も特筆すべきだろう。資生堂ギャラリーでの展示はとりわけ面白く、フォーカシングとスケール、展示の密度がすばらしかった。個々の展示物の小ささがプレゼンテーションのフォーカスを明確にし、同時にそのスケールがモノとして成立させることとアイディアの緊張関係をうまく引き出していた。それぞれのプロジェクトはおおむね共通のアプローチから始まっているが、それが喚起するイメージは多様な方向へ向かい、全体としてあの小さなスペースにひしめき合っているような充実した展示だった。豊田市美術館での展示は個人的には幾分持て余し気味に感じられたが、徹底してアイディアをモノに定着しようとする姿勢には誰もが脱帽せざるをえないだろう。それがどこに向かうのかがここから問われるにしても、まずは見事と言うほかない。
都市に関する展覧会「Struggling Cities」にこの1年取り組んでいたからとりわけそう思えたのかもしれないが、世界的な傾向として都市への問題意識が量的にも質的にも積み上がってきたのを実感する1年でもあった。都市人口が世界人口の50%を突破した今年、都市論の周辺にいくつか重みのあるトピックがあったように思う。
ポンピドゥ・センターでの「Dreamlands」展は20世紀に組み立てられてきたさまざまな都市論をひとつのストーリーに編み上げ、包括的かつ明確なヴィジョンを打ち出していた。ロバート・ヴェンチューリ『ラスべガス』やレム・コールハース『錯乱のニューヨーク』のような過去の都市論は、多かれ少なかれケーススタディとして、徴候を読み取るべき先鋭化した事例として書かれていた。しかしもはやそのように読むことはできない。それは世界中に伝播し、コピーされ、より徹底されている。本質的には同じものが、しかしさまざまに翻案され、都市の前景を覆う。要するに見えるもの一切がダックでグリッドでスペクタクルなのだ。コールハースが言う「ジェネリック・シティ」が、投資対象としての都市であることがあからさまになり、だからこそ目論見書で評価されるジェネリックな紋切り型に自己完結する。権力と資本と欲望の循環が都市を規定する文脈となり、スター建築家のアイコニックな造形がデコレイテッド・シティのビルボードとなる。都市は大衆化することで巨大な人口をかき集め、場当たり的にスペースをでっち上げ、秩序や文化などお構いなしに肥大する。善悪の彼岸というよりは、ただの現実だ。もはやそこからネオリベ批判に向かう構図もクリシェに過ぎない。
都市を論じることにかけては人後に落ちない磯崎新が最近唱える一種の都市三段階論も、そうした認識から始まる。故あってほぼ同じ内容のレクチャーを何度か聴講したが、現代都市の状況をこのように対他的に捉えた論はそう多くはない。『新潮』2010年10月号に掲載された論文「〈やつし〉と〈もどき〉」でその概要を読むことができる。著書『建築における「日本的なもの」』書評への応答として書かれているため論文自体は幾分複雑になっているが、基本的なレトリックは非常に単純であり、19世紀的なシティ、20世紀的なメトロポリス、21世紀のハイパー・ヴィレッジという図式に尽きる。古典的都市、近代主義の都市、それぞれわれわれは知っているが、今目にしつつあるのはそうした既知の都市像には収まらない様相を呈し始めているのではないか、というわけだ。情報技術により空間的障壁を取り払われた「グローバル・ヴィレッジ」の裏側において、道路やゾーニングなどの物理的インフラよりも携帯電話やITデバイスに支えられ柔軟性を獲得した都市様態としてのハイパー・ヴィレッジである。そう要約してしまえばあまりにわかりやすいお話だが、しかし現実にわれわれの生活のどれほどがこうした技術によってサポートされているか考えると、レトリックとばかりは言ってられないだろう。twitterやfacebookのようなSNSは、たしかに世界中を繋ぐが、それ以上にむしろ身近な知人との距離を縮めている。古典的なリアルとヴァーチュアルの二分法が意味をなさないのは無論だが、個々の人間の都市の使い方はコミュニケーションツールによって急速に変化しており、しかも変化の質は不可逆に思われる。都市構造が都市生活を規定する、ということはあるレイヤーにおいて依然として事実であるにせよ、他のレイヤーが重みを増し、都市の物理的な水準の意味合いはずいぶん変わってきているはずだ。
そうした文脈を幾分カリカチュアしながら現実化したものとして、《完全避難マニュアル 東京版》を考えてみるとどうだろうか。もちろん期限を区切られて開催される演劇・パフォーマンスであり、つまり作品ではあるのだが、同時にその縁は都市生活そのものに接し繋がっている。都市のインフォーマルな現実、言ってしまえばハイパー・ヴィレッジ的な様相そのものがそこでステージとなる。本来昨年の《個室都市》と《完全避難マニュアル》の真っ当な評価は別の角度からなされるべきなのかもしれないが、それでも断片化した都市に向けられた意思において、磯崎の論と共振するところは少なくないのではないか。
その延長には、昨年刊行されたジャン=リュック・ナンシー『遠くの都市』(原著1999、邦訳2009、青弓社)、あるいはジョルジュ・ペレック『さまざまな空間』(原著1974、邦訳2003、水声社)といった人文系では昔からある空間論的関心が連なって見える。『遠くの都市』はいわゆるテクノロジーそのものにフォーカスしているわけではないが、粗く言えば磯崎の『見えない都市』(河出書房新社、2003)+マイク・デイヴィス『要塞都市L.A.』(青土社、2008)といったおもむきで、やはり非古典的都市観を言語的に定着しようとするナンシー流の挑戦として印象に残っている。同じくナンシーの『無為の共同体』(以文社、2001)、モーリス・ブランショ『明かしえぬ共同体』(筑摩学芸文庫、1997)、あたりに伸びていく文脈は今となっては文学的に消費されてしまったようではあるが、あまりにも視覚偏重になった都市観をリセットするためにもこのあたりをひとしきり落ち穂拾いしてみるのもよいのではないだろうか。ペレック『さまざまな空間』はウリポ・グループ独特の言語ゲームとも見えるのだが、その離散的なテクスト群は見事な訳文ともあいまって場のリアリティを見事に浮かび上がらせる。そちらからはイタロ・カルヴィーノ『見えない都市』へと繋がり、さらに佐多稲子『私の東京地図』(講談社、1989)や後藤明生『挟み撃ち』のような日本の都市を舞台とした文学作品へも繋がってくる。さほど有名でもない『私の東京地図』についてだけ簡単に説明しておくと、プロレタリア文学の女流作家である作家が幼少の頃から東京の各地を転々とし戦後に至る日々を断章的に綴った作品だ。関東大震災前の東京下町、青春時代を過ごした駒込、結婚し家庭生活を営んだ三田界隈、労働運動に身を投じた王子、といったように場の記憶と個人史が折り重なって、東京のある時代の切実な空気が生き生きと描かれている。都市の全体像とは無縁の、むしろ生活にぴったりと張り付いた場の感覚が積み重なり、断片化しつつ、こちらの記憶にあるその場の記憶とそれが交錯し、時を隔てた距離の断絶と共にざらりとしたリアリティを残す。それは《個室都市》や《完全避難マニュアル》にかなり近いのではないだろうか。
-


- ジャン=リュック・ナンシー『遠くの都市』/ジョルジュ・ペレック『さまざまな空間』
即物的には結局のところ地面はどうあれ連続し物理的空間も連続している。しかし経験的には、あちらとこちらが短絡し、あるいは分断され、まさに離散的な場しかわれわれは見てはいない。そのような現象としてわれわれの生活において立ち現われるパッチワーク状の都市があり、しかしそれを記述する方法をわれわれは未だ持ちあわせていないのではないだろうか。永続的かつフォーマルな都市構造が都市のサスティナビリティを支える基盤であるとわれわれは思ってきたが、もっと偶発的で離散的な過去が、過去ゆえの動かしがたさで現在を規定している。グローバル・ヴィレッジが唱えられたのがインターネット前夜だったように、必ずしも現代的な情報技術がそうした状況を発生させたというわけではなく、都市生活そのものに潜在してきたこのモードが顕在化せざるをえないような現代都市のエコロジーがあるのだろう。「ブラタモリ」や「ちい散歩」に見られるような場所への関心、それに応えるiPhoneアプリの「時層地図」のようなツールの出現、それぞれはばらばらのこうした出来事だが、総じて都市を考える前了解の更新へ向けての一歩一歩の歩みなのかもしれない。
しかしながら、そのような断片の無為の堆積をいわば「自然主義」的に享受するだけでよいわけがない、とようやく復刊された白井晟一の『無窓』(晶文社)を傍らにすると向き直らざるをえない。「コロイドを木型の中で成型するときの、にがり投入の契機をつかむ決断」を語る白井は、単に混沌を退けて超然とするでもなく、もちろん混沌に溶け合い弛緩するのでもなく、その只中から「あらゆる部分が弁別できないほど、緊密に結合して一つの全体のうちにとけこ」む、「渾然たる調和」を祈念する。どのような古典も単なる自然の堆積ではなく、永々たる歴史の彫琢を経て古典と呼ばれたはずだ。そのうえで、ハイブリッドで離散的で重層的な現代都市が単に蕪雑のままであるばかりでなく、自ずと深い文脈を刻みつけそこから新たな変異を導くような地力を蓄えることがあるだろうか。先述の磯崎論文もそこへと手を伸ばそうとしてはいたが、もっとマッシヴで精緻な像によって立ち向かわなければ、この不透明を見通すことはできないのではないか。「友よそんな調子でなく、もっと力強い調子で」という白井の叱咤はそこでなんとも重い。
かならずしも都市への関心と白井の古典性への指向は対立するものでもないだろう。もっと離散的でありながら包括性をもった、未だ野性的な古典性があるはずなのだ。2011年とは言わないまでも近い将来、そのしっぽぐらいは捕まえることができるのではないか、そんな期待を持っている。
-

- 白井晟一『無窓』
さて長くなりすぎた。あとはざっと列挙するにとどめる。IZU PHOTO MUSEUM「時の宙づり──生と死のあわいで」展、横浜美術館「束芋──断面の世代」展、原美術館「ヤン フードン──将軍的微笑」展、東京都庭園美術館「ロトチェンコ+ステパーノワ──ロシア構成主義のまなざし」展、川村記念美術館「アメリカ抽象絵画の巨匠 バーネット・ニューマン」展は今年見た展覧会のなかでも記憶に残った。書籍ではKen Tadashi OshimaInternati『onal Architecture in Interwar Japan: Constructing 』Kokusai Kenchiku(Univ. of Washington Pr.)、笹岡啓子『PARK CITY』(インスクリプト)、マイク・デイヴィス『スラムの惑星』邦訳(明石書店)、ジェイン・ジェイコブズ『アメリカ大都市の死と生』全訳(鹿島出版会)、『ハンス・ウルリッヒ・オブリストインタビュー1[上]』あたりを挙げておきたい。少し毛色の違ったものとしては『Hong Kong: 160 Years' Development in Maps』(Victor F. S. Sit、聯書店[香港]有限公司)は160年の香港のあらゆる側面のマッピングという偉業。歴史的にも領域的にも明確に境界づけられているからこそできることではあるが、大変感銘を受けた。やれることをやる、というのは偉大な態度である。