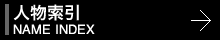ENQUETE
特集:201201 2011-2012年の都市・建築・言葉 アンケート<RAD(川勝真一+榊原充大)
[川勝真一]
●A1
震災とそれに続く出来事は、住む場所、家族構成、職業などによって、それぞれに異なった現実を突きつけた。阪神大震災を記憶し、関西に住み、建築に関わる、単身者の私にとって、直接的当事者性という意識は薄い。それは、沖縄の、ツバルの、スーダンの人々の現実が、じつのところいまの自分に地続きなのだということを感じつつも、自分のこととして受け止めるということが困難であるということと同じようとらえている。。そのことは否定も肯定もできないし、人間という存在の限界として、事実を受け入れることからしか始まらない(ではなにが事実なのか?)。他者を自分のこととして受け入れるためには、痛みの、そして苦しみの共有が少なくとも必要になるのではないか。さらに建築という場においてこの共有をどう考えればいいのか? 2011年はそんなことを考えさせられ、またそのことを「恊働」というキーワードでとらえる機会が何度か私のもとを訪れた。震災直後の4月、ある展覧会の企画書を書いていた。それは「SPACE OURSELVES」というタイトルの「公共」をテーマに16組の建築家に参加してもらった展覧会だ。建築家に依頼した提案の条件として、その建築の利用者によって建設可能な規模、工法であるということを設定した。つまり、建築家とユーザーとの恊働のあり方、つまり作り手としての建築家がいて、その対局に利用者がいるではなく、両者を隔てない「私たち」としたときに建築がどう変わるのかについて考えることをうながすきっかけになったのである。
初夏、スタジオ・ムンバイのジェイン・ビジョイ氏に京都を案内する機会を得た。スタジオ・ムンバイは広い敷地のスタジオ内で建築家とドラフトマン、職人が恊働しながら建築をつくっている。通常行なわれるような、建築家が構想し、ドラフトマンが線を引き、職人がつくるという線形なプロセスではなく、非線形に組織が渾然一体となって仕事が進められている。彼らのつくる建築も部分と全体が常に包含関係におかれている。
京都で若手芸術家支援を目的とした事業があり、京都の町家を改修してその拠点をつくるというプロジェクトに設計者としてではなく、コーディネート役で参加した。ここでは、ひとつの建築プロジェクトにどういう主体を巻き込み、それによってその後の運営も含め、なにができるのかを考えるきっかけとなった。現在も職人さんと学生とアーティストと建築家との恊働のあり方について模索している。
11月、初めて被災地を訪れた。先に書いたように当事者性の感覚を強く持てなかったので、ただ見に行くということがどうしてもできなかったが、とあるプロジェクトの調査のために現地入りした。プロジェクトの目的は漁師さんのための作業小屋を建設するというもので、漁師さんとの作業とインタビューを通じて、建築の輪郭をあぶり出していくというアプローチをとった。美しい設計図を書くことではなく、いかに意味のある答えを引きだすか、情報をキャッチするか、それまとめることがわれわれに課された役目であり、そのためには漁師さんとの恊働がかかせない。現在も恊働はつづいている。
というようなばらばらに起った出来事が「恊働」というラインで繋がったように感じている。
●A2
震災とそれ以降の出来事とすこし距離をとって、とはいえ密接に関係もしていると思われる私個人にとって身近な出来事として、京都会館の改修問題がある。ここでの問題というのは改修それ自体ではなく、改修へと至る経緯そのものが問題として取り上げられている。その意味で「A1」の話しとも連動している。つまり今回の京都会館をめぐっては、大規模なオペラができるだけの改修が本当に必要かどうかを、その根拠や、その決定のプロセスが透明性を持って明示されたうえで私たちの問題として考えられるかどうかが最大の焦点である。80億円近い改修費と確実に増加するであろう施設維持費(現状で明確な試算は算出されていない)には、税金があてられることになるだろうし、そうした費用が増えることで地道に活動をつつけている若いアーティストの活動環境が悪化することも考えられる。得をするのは一部の利権者だけという、どこかで見たようないつものパターンになってしまうのか? この構図は、建築家と建築への信用を貶めた「ハコモノ」と言われる公共建築のあり方と同じだ。建築家が社会的な信用を取り戻し、都市や街をつくっていく主体となりたいのなら、長い目を持っていまある計画への疑問や妥当性、その先に生み出される状況を考える必要がある。今回の京都会館を巡る取り組みはそのようなものとして理解されるべきだと思っている。そして、京都会館での取り組みそのものを、公共性を開いていくためのケーススタディとして、その不透明な部分へいかにアプローチできるのかを学んでいかなくてはならない。原発問題しかり、当然のようにこの問題は、日本の至るところに存在している。それを理解したうえで、合理的かつ透明性を持って議論されれば、建設時の理念を都市の資産として引き継ぎつつ、少ない予算での改修の手が見出されるはずだ。
●A3
2012年は今年行なわれていたさまざまな公共や恊働といった議論が、どのように建築家の活動のなかに取り込まれていくのかに注目したい。なので作品ではないが、乾久美子さんがプロポーザルでデザイン監修者に選ばれた「延岡駅周辺整備プロジェクト」の経過報告を行なうためにつくられた「延岡駅周辺整備日誌」と、同じく青木淳さんがプロポーザルで選ばれたプロジェクトにおいて始めた「<三次市民ホール>設計ノート」という二つのblogを挙げる。これまでも建築家によるblogは数あれど、市民とのコミュニケーションを目的としたものはめずらしい。「延岡駅周辺整備日誌」では、乾さんだけでなく事務局や市民団体の方の書き込みもあり、乾さんが記されているように掲示板のような使われ方もしていて面白い展開を見せている。「<三次市民ホール>設計ノート」は始まったばかりではあるが、青木さんの親しみのある文章で、提案の説明や住民説明会での意見に対する応答などが記されており、今後は市民からの意見も紹介するとのことでどのような応答がなされるのか楽しみだ。また建築家にとっても市民にとっても、直接コミュニケーションがとれる環境がつくられることで(よくわからないけれど市民の前に現われるのは、つねに市の担当職員)、意見交換とフィードバックが目に見えるようになり、そのことがその後の運営のされ方を含め建築にどのような影響を与えていくのだろうか。また、この2つのプロジェクトは震災後の公共の建築のつくられ方を考えるうえでもとても重要だと感じている。こうしたメディアの使い方によって先にあげた恊働の感覚がどのようにアップデートされ設計が進んでいくのか楽しみである。
*
[榊原充大]
●A1
2011年2月に行なった地域経済学者・岡田知弘氏へのインタヴューのなかでこういう話をしてもらった。2007年の中越沖地震、2008年の能登半島、そして宮城・岩手内陸地震と最近あった地震は、中山間地域それも大規模市町村合併地域の周辺が多かった。合併にともなう役場の消滅によって、どこで被害が起きているのかをキャッチできなくなり、復興にも手間がかかってしまうという二次被害が起こっている、と。同じインタヴューでは、一方で、各地域で地域自治区なるものを設けて各所2千万円まで自由に裁量できるようにした市もあるという話を聞いた。合併によって大きくなりすぎたひとつの市のなかには、例えば雪かきが必須のところもあれば、雪がふらないところもある。それぞれがそれぞれの裁量で決めるべきことを決められる仕組みをつくったというわけだ。ちなみにその「地域」規模は昭和の合併以前のものだった、とのこと。このとき以来「地域がうまくまわる規模というものがあるかもしれない」ということが頭から離れない。
当然のことながら、地域のことは地域の人のほうがよく知っている。地域の人は地域が直面するミクロな問題に対して「私たちの問題だ」として対処し、一方でその地域が被るマクロの問題は日本全国の構造的な問題として、この島に生きる人々が「私たちの問題だ」とあまねく意見を出せる、整理された状態が望ましいと考えている。東北が農産物や電力の、産地、供給地となっていることの「当たり前さ」が、産業革命以降に成立した日本の構造的問題であり、当たり前でもなんでもないことが3月11日以降に起きている一連の出来事から知らされた。かといって、自分自身、日本の問題を「私たち」のものとしてとらえる想像力を持っているかと聞かれると、「はい」とは言いづらいのが正直なところではある。それにしても考えてしまうことは、ミクロのことはミクロで対処できる、というマクロな仕組みはどうやって実現することができるのだろうか、ということ。そして、ミクロのことはマクロの反映でもある、ということだ。
今回の震災復興に限らず、これからも、どこにいても、考え続けなければならない問題を提起するための機会として、私たちは「SPACE OURSELVES」という展覧会を企画した。「私たちの/による/のための建築」とはどのようなものか、がテーマとなっている。それを「公共建築」と呼ぶべきなのだろうが、いまのところそう呼ばれている建物のどれほどがそういう役割を担えているかわからない。不当なイメージに貶められている「公共の」建築のかたちについて再考したい。ここで言う建築とは建物そのものに限らず、なにか達成すべきゴールのようなものになるのか、あるいはなにかを共有するための手段となるのか、そうした点を含め、これを見た人たちが実践や思考を進めていくための機会となればと考えている。
●A2+3
2011年6月に「Political Equator 3」というカファレンスがアメリカとメキシコの国境で行なわれた。見捨てられたような周縁的地域から新たな想像力を生み出すための、行動と議論からなるノマディックなイベントだ。参加者は専門家であるなしに関わらない。彼らは、9.11以後の米国テロ対策国防戦略「ホームランドセキュリティ」保護下にある用水路を横断し、アメリカはサンディエゴからメキシコのティファナまで横断する。なぜ用水路かというと、ここが公的な通関手続きを行なう場所だからだ。アメリカ側の端ティファナ河口を通り、メキシコ側の国境壁に衝突する、おおよそ8万5千人のインフォーマルな居住地となっているスラム地区へのパブリックウォーク。「領域横断的な」とはよく言うが、物理的に国境を横断するカンファレンスなんて聞いたことがなかったのでとりわけ印象に残っている。
「Political Equator」とは、オーガナイザーであるサンディエゴの建築家テディ・クルズによって概念化された架空の「境界線」のこと。ポスト9.11の世界を「ファンクション・コア」と「ノン・インテグレーティング・ギャップ」という二つへと地理的に区分し、現在問題なのは「危険な地域」ではなく、この二区分間の断絶にこそあると説いた、トマス・バーネットによる『ペンタゴンの新しい地図』を援用したものだ。舞台となったアメリカ/メキシコ(サンディエゴ/ティファナ)の境界を出発点とし、北緯30度から36度間をベルト状に地球一周する線を引く。すると他にもスペイン/北アフリカ、イスラエル/パレスチナ、インド/カシミールなど、上記二区分間の問題を抱える地域が浮かび上がってくる。「ファンクション・コア」とはいわば経済的社会的に相互連結したグローバリゼーションの「機能するコア」地域。対して「ノン・インテグレーティング・ギャップ」はグローバリゼーションに背を向ける「統合されないギャップ」地域のことを言う。後者は貧困が広がり治安も悪く、ありていにいえば次世代テロリストの温床とされるような地域。グローバリゼーションを背景にした地球規模の地域間問題に対して、その一部であり縮図でもあるところから行動を起こしていこうという問題意識がこの試みにはある。
空間を再編する方法として「補助線を引く」ということは極めて単純なものながら、その結果として生まれた明快な図表によって地球の見方が上書きされるように感じた。バーネットによる「新たな地図」を下地に、クルズは「Political Equator」という補助線によってより効果的な問題設定を行なっている。そしてこうした情報の編集とともに、具体的な風景を参加者と物理的に分かち合いながら議論を進めたという点も、たんに「現場」を見せるということにとどまらないこの試みの特徴だろう。「Political Equator」は、専門特化し室内で行なわれるような既存のカンファレンスという形式を覆し、多義的な意味での領域横断性を実現していると思われる。同じように人々による対話の可能性を広げる取り組みとして、パブリック参加型の移動する都市ラボ「BMW Guggenheim Lab」も2011年にスタートした事例として印象的。来年のベルリン、再来年のムンバイへの移動にも注目したい。
翻って、島国である日本にとって上のような地域間問題は遠い話にも思われるかもしれない。でも物理的境界を接しているか否かに限らず、人、もの、金は入ってくる。「出稼ぎ」もそのひとつだろう。年末のサッカー中継でブラジルチームの応援が大勢いることを横目に見ながら、舞台となったスタジアムを擁する地にはTOYOTAの下請け企業で働くブラジル人が多くいることを思い出していた。豊田市駅から電車で数駅のところにある地区には住民の半数がブラジル人という団地がある。団地内の看板にも、近所のスーパーの店内放送にもポルトガル語がある。だが、同地における日本人とブラジル人のコミュニティはほぼ分断されているのが現状のようだ。異文化の同居問題は愛知とブラジルだけではなく、局所的かつ万遍なく日本全国に広がっているし、なによりも世界規模で取り組まれている解決すべき課題でもある。よりよい同棲をいかにはかるかという問題はこれまでもこれからもある一方で、「ご近所」からの文化流入とそれを巡る現地での政治が歪なかたちで取りざたされる「嫌韓デモ」も印象に残る2011年だった。
「100年前に日本からブラジルに渡った日本人の子孫たちのコミニティは国内において大きな規模を成している。移民の問題は世界的な課題であり、そこでは差別や経済格差、文化間の衝突は避けられない」「不況によって中心街が"シャッター通り"と化した日本の地方都市を舞台に、そこで生きる土木労働者や海外からの移民労働者の姿をとおして、文化摩擦や差別、経済格差の問題を描く」というのは「goo映画」からの引用。来年、インディペンデントな映画制作集団「空族」率いる富田克也氏の最新作『サウダーヂ』が近所の映画館で公開予定。制作費としてカンパを募りながら映画をつくる彼らの姿勢、ならびに前作『国道20号線』からテーマにしている「地方」をリサーチし、そこで生活を営む人々をキャスティングしながら撮影を進めるその制作方法がとりわけ興味深い。彼らのつくった映画が見たい、ということにも増して、映画という手段をとおして行なわれる彼らの活動に注目していきたいと思っている。[榊原]
- 『サウダーヂ』予告編
URL=http://www.youtube.com/watch?v=9dlaZcbfrqA