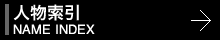ENQUETE
特集:201201 2011-2012年の都市・建築・言葉 アンケート<長島明夫
●A1放射能汚染や電力不足といったことを別にすれば、私自身や私の家族、近い親類に、この震災による直接的な被害はなかった。しかしそうした認識が得られたのは、地震が起きてからしばらく経った後でのことだ。少なくとも3月11日から数日間は、余震や東京電力の爆発事故が自分に直接的な被害をもたらすだろうことを予感していた。その間は寝るときも洋服を着て、ポケットには財布や携帯電話を入れていたし、咄嗟に持ち出せる最低限の荷物をリュックサックにまとめてもいた。私は自分が住む場所と、そこにあり、その場所を構成する、私個人にとっての歴史的な持ち物とを失うことを想像していた。この経験は今回の震災において比較的取るに足らないものだろうが、建築関係の出版編集に携わる私の意識を変えることにはなり、この12月に刊行した『建築と日常』No.2では「建築の持ち主」という特集を組んだ。そこでは建築と所有について考えている。
現代の社会で建築や都市に関しての専門的な立場にいる人ならば、建築の私的な側面よりも公共的な側面の重要性を強調することに必要を感じる場面が多いのではないかと思う。つまり都市の開発において、あるいは建物の保存において、その建築はけっして所有者だけの物ではなく、公共的・社会的な存在であると言うことが有効な場面である。基本的に『建築と日常』誌もそのようなスタンスで編集してきたのだが、しかし震災で多くの人たちが自らの建築を失ったなか、あらためて建築を私有することの意味や価値を考えてみる必要があると思われた。それは特集を終えた今もなお、継続的に考えるべき問題であることを実感している。特集内で12ページにわたり「近現代日本の建築と所有」という実にとりとめない年表を作ってみたのだが、そのとりとめなさが示すように、問題は心的な内容から政治的・経済的な内容まで広くかつ深い。
ところで、私は東日本大震災を指して3.11と呼ぶことには、ほとんどなんの利点もないと考えている。3.11という呼び方がまずインターネット上で散見されるようになったのは、おそらく地震から2週間ほど経ってからのことだと思う。そこにタイムラグが生まれた理由のひとつは、人々がそれぞれ固有に経験したどうしようもなく暴力的な出来事に対して、それを上空飛行的な視点から抽象化し、名づけることに後ろめたさがあったからではないだろうか。正直なところ最近は3.11という呼び方にもずいぶん慣れてしまったし、震災に対して誠実な活動をする人たちがその呼び方をしていたとしても、わざわざそのことを指摘して水を差すのはどうかと思う。しかし3月に3.11という言葉が目につきだした頃には、論理的というより先に感覚的に、間違っているという気がした。
東日本大震災が3.11と呼ばれるに至った背景には、言うまでもなく2001年のアメリカ合衆国における同時多発テロ──9.11の存在があるだろう。しかし私にはそのふたつの出来事の共通点は、想定外の大惨事で多くの人が命を落としたというくらいしか思い当たらない。そしてそのような出来事は世界中でほかにいくらでもあるはずだ。たとえば阪神・淡路大震災は1.17とは呼ばれない。それは阪神・淡路大震災が東日本大震災と比べて被害の規模が小さく、日付で呼ばれるほどの画期的な出来事ではないからだろうか。私にはそうは思えない。むしろ東日本大震災は、たまたまある月の11日に起きたから3.11と呼ばれているのだと思う★1。3.11という呼び方は、それが10日でも12日でもなく、11日に起きてよかったという無意識さえ感じさせる。そしてそのような安易あるいは無自覚な物語化には、震災とはまた異なる暴力性があると思えてならない。たとえ私個人の取るに足らない経験に限ったとしても、はたしてあの数日間の不安でいたたまれない気持ちは、10年前、テロリストたちがアメリカ合衆国に恨みを持ち、飛行機で超高層ビルに突っ込んだことと、なんの関係があるのだろうか。
けっして名づけることができない、名づけようとしてもつねにその言葉からはみ出してしまう、そんな誰かの固有の出来事を、別の誰かが名を与え、一般化し、共有すること。ここにも所有の問題があるのかもしれない。
★1──しかし、もし11月か12月の11日に起きていたなら、11.11や12.11では語呂が悪いので、そうは呼ばれなかったかもしれない。
-

- 『建築と日常』No.2
●A2
多木浩二氏の逝去(4月13日)
多木浩二氏は建築への旺盛な関心に対して、建築界で一定の位置を占めようとする意志がほとんどなかったため、というよりも自らの自由な活動のために、建築の領域に限らず「界」というものから意識的に距離をおいていたと言えるのかもしれないが、その活動の重要性に比べて建築界での受容の範囲は限られているように思える。孤独を貫く氏の知識人としての強固な姿勢は、ある程度世代的なものでもある一方、いつの時代にも存在する少数の信念としても受け取ることができるだろう。多木氏の著作の内容とその生き方とは不可分であり、建築や都市は、そうして自らの生をかけるに足る、あるいはかけることが求められる、抜き差しならない対象だったのだと思う。古谷利裕氏の写真
2011年は、画家の古谷利裕氏が日々の散歩のなか、携帯電話のカメラ機能で積極的に写真を撮り始めた年でもあった。それらの写真は古谷氏のブログ「偽日記@はてな」で不定期に公開されている。なにしろケータイカメラなので、一見して誰もが美しいと感じる写真ではないのだが、その画質的な貧しさやパンフォーカスの制約もおそらく作用して、抽象であり具体であるような、まさに抽象画の画家が撮った写真だと思いたくなる固有の質を獲得している。それは古谷氏自身がブログで書いているように★2、〈関係としての空間〉がそこで捉えられているということなのだろう。そこに写る場所を私は知らないし、地形も家も、人も木々も陽の光も知らない。にもかかわらずそれらの写真が真に迫るのは、そうした事物同士による関係が抽象化されて、そこに示されているからではないだろうか。抽象化された関係は、私のなかで私がこれまで経験してきた事物同士の関係と重なり、響きあう。★2──たとえば8月5日、9月2日、10月3日、12月5日の記述。
●A3
石上純也建築設計事務所《グループホーム》
多木浩二『生きられた家──経験と象徴』(岩波現代文庫、2001)の増刷(現在品切れ)
-

- 多木浩二『生きられた家──経験と象徴』