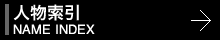ENQUETE
特集:201201 2011-2012年の都市・建築・言葉 アンケート<小澤京子
●A1東北地方の在住者でも出身者でもなく、係累すらいない私は、今回の一連の災禍については完全な部外者であった。そのような立場の者に突きつけられたのは、災禍(disaster)を語ることの「権利(資格)」への問いである。それは自分のような「部外者」が、悲惨な出来事について、知的な文脈に依拠して、あるいは倫理的な態度をよそおいつつ「語る」ことが、直接被害を受けた人々に対して、一種の「搾取」になるのではないかという疑問であり、また状況を言語化することによって「救われて」しまうことへの罪悪感でもあった。
今年10月に刊行した拙著『都市の解剖学──建築/身体の剥離・斬首・腐爛』(ありな書房)は、廃墟について、また廃墟表象が留める暴力と災厄の記憶について論じたものである。多かれ少なかれ「審美化」された対象である廃墟表象を研究している者にとって、震災と津波で根こそぎ崩壊した街並の姿は、どこか自分自身の態度を責められているような気持ちにさせられるものであった。拙著では結局、震災後に執筆した部分でも筆者あとがきでも、敢えて「3.11」について言及することは避けた。例えば、著作のなかでも取り上げた1755年のリスボン大震災には、21世紀の日本に生きる私にとって歴史化、言語化、対象化可能な「距離」がある。少なくとも、「距離」を取って論じ、分析の対象とすることに倫理的な呵責を感じずに済む対象である。「3.11」に対しては、時間的な意味でも空間的な意味でも、このような「距離」を取ることが許されないのではないかという思いがずっとつきまとっている。
ここからさらに考えさせられたのは、「廃墟」のもつ意味作用に、互いに断絶した複数の次元があるということだ。災厄の結果生まれた廃墟を、美的鑑賞の対象にすることは可能なのだろうか。文脈が断ち切られれば、あるいは可能なのだろうか、という問いである。
今回の震災にまつわるさまざまな報道で印象に残ったのは、もうひとつ、写真と記憶(個人的・身体的・物質的な記憶──の問題であった。それは写真──被写体と時間と場所を共有することで生み出される、その意味で固有性を帯びた表現の形態)のもつ一種の力と言い換えてもよい。「写真」にもさまざまな次元があって、私自身がコミットしている芸術学の分野で取り上げられるのは、もっぱら「作品」として聖別されたもの(芸術写真や、著名性のあるフォトグラファーによる報道写真)で、それらはしばしば、撮影者や撮影された文脈の固有性・有限性から離れて、分析や批評や記述の対象となる。しかし、今回の震災・津波後の、例えば「写真洗浄ボランティア」の存在が示唆するのは、写真が個人的な記憶のトークンであり、複製技術とされつつも実は物質的固有性や一回性を帯びたものでもあることだった。歴史学がもっぱら扱うのは「集団的な記憶」という一種の擬制である。「個人の思い出の《よすが》としての写真」という側面を改めて目の当たりにして、なにか虚を突かれたような気がした。
●A2
・ 表象文化論学会での全体パネル「災厄(カタストロフ)の記録と表象──3・11をめぐって」(畠山直哉氏、中谷礼仁氏によるシンポジウム(2011年11月12日)。
・ 「メタボリズムの未来都市展」(森美術館、9月17日~2012年1月15日):メタボリズムの思想やキーコンセプト、担い手やフェイズごとの差異と変遷を辿りつつ、現在的な問題意識から捉え直した、言葉の正しい意味での「レトロスペクティヴ」な展覧会であったと思う。戦後の「復興」の時期と、本格的な経済的低成長の時代に大震災・津波被害と原発事故の重なった今日の状況との間の、むしろ差異と断絶について考えさせられた。
●A3
美術やアートという「制度」が、現在の日本でどのような方向へ向かうのか。私の出身地である群馬県前橋市では、ここ10年来シャッター街化が深刻化していた市街地を舞台として、最近アートプロジェクトが勃興している(アートプロジェクト前橋、前橋美術館構想、前橋アートスクールなど)。観光客誘致による地域経済振興とのシナジー効果を狙った、地方でのアートフェスティヴァル開催はここ10年くらいのモードだったが、前橋シャッター街でのこの試みも、大筋ではこの流れに位置づけうるだろう。その一方で、現行の大阪市長による大阪市立近代美術館構想の白紙化のように、「文化・芸術=社会の余剰物」のような立場が実効力を持つ例も出ていきている。しかし、この美術館建設中止・コレクション売却に反対する意見の一部にある、すでに何らかの制度によって権威づけられた「文化」に無批判に価値を認めるかのような、あるいは単純に人文系・芸術系のプロフェッションに携わる人間にとっての「ポジション・トーク」に過ぎないような言説には、違和感を覚えてしまうのも事実である。そんななか、たまたま今秋邦訳が刊行されたキャロル・ダンカンの『美術館という幻想──儀礼と権力』を読み、芸術・アートという制度を批判的に再考するうえで、なかなか示唆的なポレミックを提起していると思った。
自分の関わっている活動で言えば、2012年にはまず、本邦で初と言ってよい本格的なファッション批評誌『fashionista』が創刊される。工学技術でも歴史でもなく、「身体とその周囲」というテマティックへの問いのひとつとして「建築(の表象)」へと向かった私にとって、「衣服」もまたかつてから関心を持ってきたテーマである。物であり商品であり、表象であり、ときに作品でもありうる服について、また社会現象としてのファッションないしモードについて、知的に語るための基盤が急速に固まりつつあることに引き続き注目していきたい。
狭義のアクチュアリティからは離れるが、現在クロード=ニコラ・ルドゥーによる理想の都市・建築構想と、同時代の自然科学的・生理学的な認識や言説(とりわけ身体規律と性の問題)との相互関係について論じた書物を計画中である。
-

- 『都市の解剖学──建築/身体の剥離・斬首・腐爛』/キャロル・ダンカン『美術館という幻想──儀礼と権力』