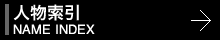ENQUETE
特集:201201 2011-2012年の都市・建築・言葉 アンケート<山岸剛
●A1
この何年かで、自分が制作している写真が建築写真であると考えるようになった。その考えは津波被災地での経験でいっそう確かなものになった。写真術を自覚的に手にした当初からアタマではそのように考えていたが、できあがった写真がそうでなかった。つまり、建築を撮った写真とそこいらの風景を撮った写真が質として一致しなかった。
ここでいう建築写真は、いわゆる現代建築だけでなく、まちにひしめく建物や都市風景、さらに土木的なそれを含む風景一般、もっと言えば、あらゆる種類の人工的な力によって造形されたすべての風景を扱うものだ。建築とは、そのような人工性の最たるものだろう。
2010年から二年間、歴史工学家・中谷礼仁委員長のもと、日本建築学会の会誌である『建築雑誌』の編集委員を務めた。ここでの編集作業をとおして垣間見たのは、まさに人工性の極みである建築に、いかに膨大な「学」と「術」の蓄積が注ぎ込まれているかということだった。それはまさに人知を尽くした途方もない蓄積であり、わたくしはそれを文字通り垣間見たに過ぎないが、そのように「人知を尽くした」ものだけが、ひるがえって「人知を超えた」ものに触れることができるのではないかと考えていた★1。
かの災厄の発生後、2011年5月に岩手県の沿岸部で目にしたのは、まさに建築が、人工性の切尖である建築が、津波という絶対的な外部性に洗い尽くされた姿だった。わたくしは建築がそのようなものに触れているのを見て、この上ない満足をおぼえた。それは爽やかな光景だった。建築はかつてないほど健康に見えた。アッパレと感じた。それらを撮影してまわった。

- 「岩手県宮古市田老青砂利、2011年5月1日」
二つ目。上述した『建築雑誌』2010年7月号で、編集委員として「建築写真小史」と題した写真特集を担当した★2。そこでの対談に登壇いただいた建築家・西沢立衛氏の発言が忘れられない★3。それは、昨今の現代建築が「建築写真」に似てきている、それは「軽い」「優しい」といった旨の発言だった。「軽い」はまだしも「優しい」とはいかなる事態なのか。
ここ何年か、個人的に、東京にある西沢氏設計の住宅である《森山邸》を撮影している。《森山邸》には「獰猛さ」とでも言うべきものがある。もちろんここは人間が住むべく設計されたすまいであり、ここに佇むと身体に快が満ちてきて、わたくしは時に多幸感にさえ包まれる。しかしその一方で、ここに住むのは人間じゃなくてもいいような、たとえば動物たちの群れが住み着いてもよさそうな、そんなワイルドさがある。この建築には、どこか人間を突き放したようなところがあって、いわゆる「ヒューマン」なものから遠く、人間をヒトに戻すかのようだ。この建築は、ここに住む人間たちが、わたしたち現代人が向きあうべき「自然」の姿を剥き出しにして経験させる。そんな否応のない風通しの良さがある。それは、布切れ一枚だけ身につけたほとんど裸の状態で東京の「自然」に向きあうような、厳しくも清々しい、動物としてのヒトの経験なのかもしれない。自然が、都市の自然が、東京の自然が、この建築の人工性によって逆に発明されているのではないだろうか。

- 「森山邸、2010年4月6日」
建築写真は、人工性の結晶である建築が、どのように自然と対峙しているかを、それら二つの力の即物的なぶつかり合いを、力の関係性こそをその主題とする。建築がいかなるかたちにせよ、またどこに建つにせよ、自然と交渉をもち、その交渉の切尖として結晶化するのであれば、自然との抜き差しならない関係をもたない建築はないはずだ。そして、津波被災地の岩手県宮古市田老と森山邸のある東京都大田区と、福島第一原発のある福島県双葉郡大熊町とでは、建築という人工性が向きあう自然の姿はまるでちがったものであるはずだ。建築写真家は地球上のあらゆる場所で、あらゆる種類の力関係を見出していかねばならないと考えている。

- 「北上川、2011年10月25日」
★1──「人知を超えた」ものは文字通り人間的なものを超えた、人間にとっての外部である。それは時にかろうじて「触れる」ことができるのみである。よって「想定内/外」といった人間的な判断とはロジカルタイプが異なる。
★2──音楽家の柴原聡子委員と共同で担当した。
★3──「建築写真以後」と題した建築家・鈴木了二氏との対談。ホンマタカシ、畠山直哉、ヴォルフガング・ティルマンスの写真をめぐってのもの。
●A2
写真家・畠山直哉氏の東京都写真美術館における個展
畠山直哉氏は建築写真の偉大なる先達であると考えている。建築ジャーナリズムに囲い込まれた感のある建築写真を、写真術の原点にまで遡行して「巻き返し、世界を建築写真化する」(鈴木了二)★4かのような氏の仕事には、つねに大きな影響を受けてきた。その回顧展が行なわれた。「Natural Stories」という大きな流れのなかでこれまでの仕事を見通すとともに、氏の故郷である陸前高田の写真が、被災前と被災後の風景の写真が発表された。この被災後の写真が、氏がこれまでに注意深くなぞり、結果として時に、ある恩寵とともに描きだしてきた「製図家の鉛筆」の「線」にどのように収斂していくものなのか★5、わたくしにはまだわからない。氏はあの風景を必ず撮影しなければならなかっただろう、それは絶対に。しかし「撮影」することと、それを「発表」し「展示」することのあいだにある道のりは遠く、そこにはとても厳しい「選択」が介在するはずで、その選択の必然性がわたくしにはまだわからない。その厳しさを氏の仕事から学んだ者として、今後も自分自身の問題として考え続けたい。
建築家・隈研吾氏の発言「ある困難が、自分に偶然ふりかかった困難ではなく、理由があり、深い根っこがある歴史的、構造的困難であるということがわかると、人は逆に気分が明るくなる」★6
ツイッター上で、いつだったか偶然に流れてきたことば。もちろん3月11日以後に。たしかなにかの建築コンペの審査評だったと記憶している。読んでこの一文だけコピペして保存した。上述の、自身の津波被災地での経験と気分にも共鳴して、強い印象を残した。
ウェブサイト「三陸海岸の集落 災害と再生:1896, 1933, 1960」★7
かの大津波発生後ほどなくして、明治大学建築史・建築論研究室によって発表されたサイト。「三陸海岸地域の集落が1896年、1933年、1960年の三度にわたり経験した津波災害と再生に関する先人の記録をまとめ」たもの。
「その復興においては歴史観が問われると私たちは考えます。それはこの地域の津波被害が反復的で自然的なものであると同時に、人文・社会学的にも工学的にも歴史規定的であるという、その両面をいかに捉えるかが問われるという意味においてです」(「当サイトの主旨」より)
東北に、とりわけ三陸沿岸になんの縁もなければ地理感覚もないわたくしは、昨年5月はじめて被災地入りした際、道路地図とこのサイトだけを手がかりにして国道45号線をひたすら上下した。
建築家・日埜直彦氏の仕事
(国際交流基金海外巡回展「Struglling Cities」★8の企画監修、『建築雑誌』2011年1月号「未来のスラム」★9編集作業、原宿VACANTにおけるイベント「Unknown Tokyo」★10の企画など)
「未来のスラム」編集作業を比較的近くで見せていただいて、当初は素朴に遠大な企画と息を呑んでいたが、残念ながら参加できなかった「Unknown Tokyo」の意図を知り、これら一連の仕事のパースペクティブが腑に落ちた。一連の企画が、ひたすら「この東京」の面白さに発していることに感銘受けおおいに共感するとともに、それがメガシティやら現代スラムやらの問題に軽やかに連続することにいまさらながら驚いた。2012年も続々と企画されるようなので積極的に参加したい。「この東京」の面白さからの連続、という意味では『建築雑誌』の「未来のスラム」特集の三部構成は秀逸このうえないと感じた。
長渕剛の曲「俺たちのキャスティング・ミス」
東日本大震災後のあらゆる局面での醜態を見るにつけ、これは他ならぬわたしたちの行動の結果であると思わざるをえなかった。そんな思いを抱えた年末に、友人で以文社の編集者である前瀬宗佑氏が教えてくれた曲。どんな曲なのかどんな歌詞なのか知らないが、タイトルが事態を端的に突いていて、強く印象に残った。
★4──『建築雑誌』2010年7月号(特集=建築写真小史)第三部「建築写真以後」
★5──畠山直哉「線をなぞる」(「HATAKEYAMA NAOYA, Draftsman's Pencil」展カタログ、神奈川県立近代美術館、2007)
★6──http://www.kendoseibi.pref.gunma.jp/chiiki/tomioka/1G/jousyutomioka/sonota/kouhyo.pdf
★7──http://d.hatena.ne.jp/meiji-kenchikushi/
★8──https://www.10plus1.jp/monthly/2010/11/issue1.php
★9──http://jabs.aij.or.jp/backnumber/1612.php
★10──http://vacant.n0idea.com/post/11471399313/unknown-tokyo-update-text-by