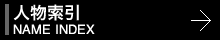ENQUETE
特集:201301 2012-2013年の都市・建築・言葉 アンケート<唯島友亮
「茅山が動いてきたような茫漠たる屋根と大地から生え出た大木の柱群、ことに洪水になだれうつごとき荒々しい架構の格闘と、これにおおわれた大洞窟にも似る空間は豪宕なものである。これには凍った薫香ではない逞々しい野武士の体臭が、優雅な布摺れのかわりに陣馬の蹄の響きがこもっている。(...中略...)私はかねてから武士の気魂そのものであるこの建物の構成、縄文的な潜力を感じさせるめずらしい遺構として、その荒廃を惜しんでいた。最近は蟻害ことに激しく、余命いくばくもないといわれているが、『友よ、そんな調子でなく、もっと力強い調子で』と語ってくれるこのような建物は何とかして後世へ伝えたいものだと思っている」(白井晟一「縄文的なるもの──江川氏旧韮山館について」『無窓』、晶文社、2010)。2012年を代表する《東京スカイツリー》《みんなの家》《東京駅》のややもすれば縄文的とも言えるような力強い容姿が象徴しているように、震災後の日本は、「はかなさ」に対する「確かさ」、「細さ」に対する「太さ」の感覚へと移行しながら、「都市的なもの」から「土着的なもの」へ、「官僚的なもの」から「民衆的なもの」へと立ち還ろうとしているかのように見える。
「現代建築は民衆を獲得することから始まる」という川添登の言葉に象徴される戦後日本の「民衆論争」や「伝統論争」の議論は、流動する民衆的エネルギーの受け皿としての「都市のコア」の創造へと向かい、各地に華々しい公共建築群を産み落とした。しかしながら、戦後の民衆が実際に向かった先は、空間的なコアとしての広場やピロティではなく、経済的なコアとしてのショッピングモールであり、戦後日本の民衆のエネルギーは、「空間」に対する「経済」の圧倒的な勝利をもって、消費社会の彼方へと消え去った。
遠く離れた全てのものをある一点へと集合させるような引力的な空間を目指した「民衆のための公共空間」は、そのあまりに無防備で全方位的な開き方ゆえに、民衆から居場所の感覚を奪い、彼らを日常的に留めておくことができなかった。そうした広大でユニヴァーサルな公共空間は、日本の民衆が自らの拠り所とするには、あまりにナイーヴに開かれすぎていたとは言えないか。
グローバリズムが占拠する「経済」の領域を離れ、原初的な環境やコミュニティのあり方が問い直されている現在、「空間」の側に問われるのは、民衆や環境といった他者に対しての開き方、受け入れ方の作法であり、その精度であるように思われる。
「16世紀には、朝顔はまだわれわれには珍しかった。利休は庭全体にそれを植えさせて、丹精こめて培養した。利休の朝顔の名が太閤のお耳に達すると太閤はそれを見たいと仰せいだされた。そこで利休はわが家の朝の茶の湯へお招きをした。その日になって太閤は庭じゅうを歩いてごらんになったが、どこを見ても朝顔のあとかたも見えなかった。地面は平らかにして美しい小石や砂がまいてあった。その暴君はむっとした様子で茶室へはいった。しかしそこにはみごとなものが待っていて彼のきげんは全くなおって来た。床の間には宋細工の珍しい青銅の器に、全庭園の女王である一輪の朝顔があった」(岡倉覚三『茶の本』、岩波文庫、1961)。
一輪の朝顔をめぐる利休の極めて作為的なこの行動は、彼の茶の精神、すなわち他者と対峙する作法の具現化であり、その作法は茶室「待庵」において空間化され結実する。 利休はそこで、床に飾るに足る十分な数の茶道具を持たぬ民衆のために、慣習化されていた床の間のサイズを大きく削り取り、四畳半の茶室をわずか二畳に絞り込み、縁側を捨て、下地材が剥き出しにされた荒々しい壁面で外部を遮断した洞窟のような闇の中に、全ての人に開かれながらも、他者の安易な侵入を許さない、冷厳たる極小の開口を穿つ。 縮小しながら開いていくかのような、その空間的な身振りを通じて、待庵はいわば自ら境界そのものへと変貌し、そこを跨ぐ全ての他者を拒絶することなく限定し、穏やかに歩み寄ることなく張りつめた態度で律し、斥力的な力を発散させながら自らの内部を通過させたかに見える。
ロシア構成主義者たちはかつて「建築は社会のコンデンサーである」と語ったが、待庵はまさにコンデンサーの抵抗力を極限にまで高めることで、火花を散らしながらあらゆる種類の電流を変質させ、それでもなお自らの内部を通過させ続けるような、そんな「開くこと」「通過させること」の凶暴で緊迫したあり方を提示したのではなかったか。 あるいは待庵の二畳とは、時の権力者を朝顔の影を追う孤独な遊歩者へと変質させ、縮小を重ねることで生まれた自律的な夢の空間へと迷い込ませながら、そこに穿たれた孔を通じて自らの最深部を広大無辺なる外部へと反転させてしまうような、極限まで圧縮されたパサージュの姿であったとも言えるかもしれない。
全方位に向かってあらゆる外部を無制限に引き寄せる引力的な公共空間ではなく、縮小を通じて極微なる個を遥か遠方の広がりの彼方へと運び出すような斥力的な場の在り方を模索しながら、「開くこととは何か」を日本の伝統に向かって改めて問い直す時、待庵は、荒々しい縄文的な潜力も、陣馬の蹄の響きも、何もかもを喪失しながらゆっくりと下り坂を下っていく21世紀のこの国に、「友よ、そんな調子でなく、もっと力強い調子で」と語りかけるのである。