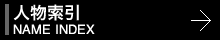ENQUETE
特集:201301 2012-2013年の都市・建築・言葉 アンケート<榑沼範久
ふるさと、僕はまずここで(逆立ちして)見ることから学んでゆくつもりだ志村ふくみ『晩禱──リルケを読む』(人文書院、2012)、『薔薇のことぶれ──リルケ書簡』(同)に導かれてリルケを読み始めた。大学生の頃、母から志村ふくみ『一色一生』(講談社文芸文庫、1993)を教わって以来、染色家・志村ふくみさんの存在はいつも憶えていた。自分の幼い頃に一緒に暮らしていた亡き祖母も、染色をしていたからかもしれない。第二次世界大戦でシベリアから戻らなかった祖父のことは私に語らなかったが──享年30歳なのだろうか、写真だけは知っている──、一緒に絵を描きに近くの植物公園によく連れていってもらった。祖母は祈りの場である教会にも独りで、あるいは母や私や弟とともに、よく出かけた。祖母と過ごした時間のことを思い出すと、今でも強い情動とともに「純粋過去」(ベルクソン)がそこにあるような感触に身体が包まれる。同時に、穏やかな時間が流れていた家のなかにも、ひとつ「世界史」の闇穴が口を開けていたのだということを、自分が祖父の年齢を越えそうになる頃から意識するようになった。そのことを教えてくれたのは父だったと思う。写真は空白の升目になった。
-

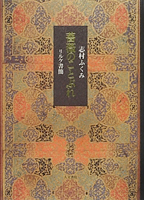
- 志村ふくみ『晩禱──リルケを読む』/『薔薇のことぶれ──リルケ書簡』
リルケ『マルテの手記』、「この本ほど私を虜(とりこ)にし、悩まし、絶望させ、今もまだその不安の中にいる。こんな本ははじめてだ」(『晩禱』125頁)。書き写すこと=祈ることのように、『マルテの手記』が引用される。「空気の一つ一つの成分の中には確かに恐ろしいものが潜んでいる。呼吸するたびに、それが透明な空気といっしょに吸い込まれ──吸いこまれたものは体の中に沈殿(ちんでん)し、凝固し、器官と器官の間に鋭角な幾何学的模様のようなものを作ってゆくらしい。──(中略)──僕の生命の細かく分裂した先の先へ、何か得体のしれぬものが吸いあげられてゆくような気持ちである。そして、とどのつまりまで押しあげたものが、なお体の外へ突きあげ、僕がそれを最後の拠点としてのがれてゆく呼吸まで、とうとう押しふさいでしまう。ああ、僕はどこへ行けばよいのだろう。どこへ逃げて行けばよいのだ。僕の心が僕を押出す。僕の心が僕から取残される。僕は僕の内部から押出されてしまい、もう元へ帰ることができない。足でふみつぶされた甲虫(かぶとむし)の漿液(しょうえき)のように、僕が僕の体から流れ出てしまうのだ」(リルケ『マルテの手記』大山定一訳、新潮文庫、1953/2001、88-90頁)。「人々は生きるためにこの都会へ集まってくるらしい。しかし、僕はむしろ、ここではみんなが死んでゆくとしか思えないのだ。僕はいま外を歩いて来た。──(中略)──子供は眠っていた。大きく口をあけて、ヨードホルムやいためた馬鈴薯や精神的な不安などの匂いを平気で呼吸していた。僕は感心してじっと見ていた。──生きることが大切だ。とにかく、生きることが何より大切だ」(同8-9頁)。
2012年10月26日、上野発の常磐線列車のなかで畠山直哉『気仙川』(河出書房新社、2012)を開いた。12月1日、東京藝術大学(取手校地)で行われる「取手ARTPATH2012『いっそ、さあ』」展のゲスト討論会で、畠山さんと対談することを引き受けたからだ。以前から横浜国立大学や東京藝術大学の授業で畠山さんの写真集『LIME WORKS』(シナジー幾何学、1996/青幻社、2008)や『Underground』(メディアファクトリー、2000)、そして『話す写真──見えないものに向かって』(小学館、2010)を取り上げることは度々あった。「ひとはいかにして作曲家になるか──武満徹の場合」の続編として、「ひとはいかにして写真家になるか──畠山直哉の場合」と題した講義をしたこともある。そこでは、「私は日本列島を形作る4つの島のうちで最大の、本州の北部、岩手県の陸前高田(りくぜんたかた)市というところで1958年に生まれました」の一文を含む講演記録「私の仕事について」(『話す写真』)を取り上げた。写真を撮り続けるなかで重要になっていったという「自然」の概念(121─129頁)。「きっと『自然』とは、人間の精神に対して徹底的に無関心を装うものたちに、僕たちの先人が、最後にどうしようもない気持ちになって与えた言葉なのだ。空も山も水も光も、そして写真さえも、人間に対して無関心で、僕たちをどうしようもない無力感にいざなうからこそ『自然』と呼ばれているのだろう。僕たちはいつも、世界のすべての事象に対して『人間』を投影しようと企て、そしていつも、最終的に挫折を味わう。『自然』はその挫折の地点に出現する」(『Underground』、5頁)。
-


- 畠山直哉『気仙川』/「大森克己写真展 すべては初めて起こる 郡山・会津若松」
それはリルケ『ドゥイノの悲歌』(手塚富雄訳、岩波文庫、1957/2010)で詠われる天使のように、人間の生死や願望に無関心な「自然」だ。「天使たちは(言いつたえによれば)しばしば生者たちのあいだにあると、死者たちのあいだにあるとの別に気づかぬという。永劫(えいごう)の流れは生と死の両界をつらぬいて、あらゆる世代を拉(らっ)し、それらすべてをその轟音(ごうおん)のうちに呑みこむのだ」(13頁)。また、それは坂口安吾「文学のふるさと」で論じられる「ふるさと」のように、人間を突き放す「自然」だろう。そして、突き放されたときに闇穴や空白となって前景化する、「生存それ自体が孕(はら)んでいる絶対の孤独」がある(坂口安吾「文学のふるさと」『堕落論・日本文化私観 他二十二篇』岩波文庫、2008、99頁)。講義では、須賀敦子『時のかけらたち』(青土社、1998)や同じく須賀の「ザッテレの河岸で」(『地図のない道』新潮社、1999)に記されたパラーディオ設計のレデントーレ教会の秘密、そして海都ヴェネチアの実在の根源に話は及んだ。その終盤にヴェネチアが登場する『マルテの手記』を、ここに追加することもできるだろう。
しかし、この『気仙川』を読んだあとに畠山さんと対談するとは、どういうことなのか途方に暮れた。2002年8月4日から2010年8月15日まで折に触れて撮影された故郷の写真の断片を眺めることと、「何かが起こっている」の一文で始まる切迫した言葉の連続を動悸とともに追うことを、『気仙川』の頁をめくるなかで同時に行わなければならない。そして、連続するはずの世界を描くと思われた言葉も、しかし、故郷へとオートバイで急ぐ途上で崩落し、別の世界に切り替わってしまう。頭というか身体が茫然とし、悲しいとしか言いようのない感情がこみあげ、北千住の駅に停車したあたりで本を伏せてしまった。同時に『気仙川』を読んでいた時間の濃密さが肉体に染みわたる。切迫感や悲しみとともに、この感触も自分の記憶に保存された。このことは畠山さんにも電子メールで送った。しかし公開の対談でいったい何を話せばよいのか本当にわからない。『気仙川』と無関係の話で終わらせることはありえないし、本人とともに『気仙川』を作品として冷静に吟味することも自分には想像できない。何を話したらよいのかわからないと畠山さんからも返信があった。畠山さんこそ本当のところは、もっとそうだったはずだ。
『気仙川』を読んだ(受け止めたとは言えないが、そうした意味で読んでしまった)、そして、しばらくは自分自身の問題として考えたい。そうとしか言いようがないと思った。放射性物質に直面した知覚の無能について、不能性と思考・表現について、写真の瀕死のユーモアについて、知覚の恩寵について、芸術の跳躍について、「自然」について。12月1日は対話なのか誰に向けられた言葉なのか分からない、何か奇妙に混乱した場になったはずだ。終わったあとの記録になれば、そうした闇穴や空白は整理され、「芸術の『いま』そして『これから』についての討論」(取手ARTPATH2012パンフレット)になるのかもしれない。終わったあと10日経てから、畠山さんとメールの往復をした。2013年以後、対話はその対話に見えないところでも続くのだと思う。第5回恵比寿映像祭「パブリック⇆ダイアリー」(2013年2月8日─2月24日)カタログ収録の鼎談(坪井秀人×榑沼範久×岡村恵子「日記、プライヴェート/パブリックの境界にある『ゆらぎ』へ」)も、そのひとつになるはずだ。2012年12月1日と同じ取手のメディア教育棟で2012年1月20日、長時間にわたっていろいろな話をした大森克己さん──当日の模様は『小説すばる』(2012年3月号)目次写真・「目次月記」に掲載されている──と、また話をしたい。
「僕はまずここで見ることから学んでゆくつもりだ。(...中略...)僕には僕の知らない奥底がある。すべてのものが、いまその知らない奥底へ流れ落ちてゆく。そこでどんなことが起るかは、僕にちっともわからない」(リルケ『マルテの手記』10-11頁)。
「Everything happens for the first time/すべては初めて起こる」(ボルヘス/大森克己『すべては初めて起こる』、マッチアンドカンパニー、2011)
-


- リルケ『マルテの手記』/『パウル・ツェラン詩文集』
「逆立ちして歩くものは、足下に空を深淵として持ちます」(パウル・ツェラン「子午線」『パウル・ツェラン詩文集』飯吉光夫編訳、白水社、2012、118頁)。