【第2回】[インタヴュー解題]第2世代の「アーバンデザイン」
CIAM的な都市像とアーバンデザイン会議
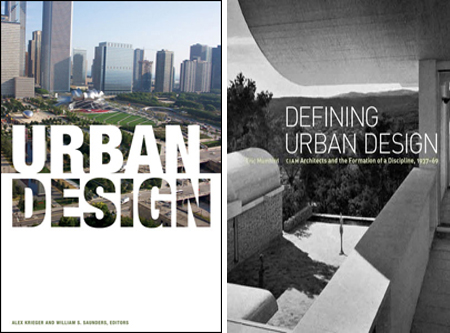
- アレックス・クリーガー+ウィリアム・サンダース『Urban Design』、エリック・マンフォード『Defining Urban Design CIAM Architects and the Formation of a Discipline, 1937-69』
ここ数年、アメリカにおいて、「アーバンデザイン」の原像や史的展開を主題とした書籍の出版が相次いだ。なかでも、ハーヴァード大学GSD(Graduate School of Design)でアーバンデザインを教えるアレックス・クリーガー氏とハーヴァード・デザイン・マガジンのエディターであるウィリアム・サンダース氏が編集した『Urban Design』(University of Minnesota Press, 2009)と、ワシントン大学教授のエリック・マンフォード氏の単著『Defining Urban Design CIAM Architects and the Formation of a Discipline, 1937-69』(Yale University Press, 2009)の2冊は、非常に示唆に富んでいる。
前者『Urban Design』は、デニス・スコット・ブラウン、ジョナサン・バーネット、ピーター・ロー、そして槇文彦といった著名な建築家やアーバンデザイナー、そして研究者たち20名のそれぞれの論考のオムニバスであるが、その論考群の前後をハーヴァード大学で開催された2つの会議の議事録が挟みこんでいるのが特徴である。冒頭に配されたのは1956年5月に開催された第1回アーバンデザイン会議、巻末に配されたのは2006年5月に開催されたラウンドテーブルディスカッションである。そう、この書籍は、アメリカにおけるアーバンデザインの原点として知られているアーバンデザイン会議の開催から50年を記念して編まれたものである。個々の論考はいずれも興味深く、ここで内容を紹介したいところだが、そこまで中身に入り込まなくても、冒頭の第1回アーバンデザイン会議の参加者の顔ぶれを再確認するだけでもいろいろと教えられるところがある。ハーヴァードのGSDのディーン、ホセ・ルイ・セルトのコーディネイトのもと、稀代の都市思想家のルイス・マンフォード、フィラデルフィアのアーバンデザインで名をあげた都市計画家のエドマンド・ベーコン、ケヴィン・リンチの『都市のイメージ』にまとまる研究の基礎をなした、ロックフェラー財団の助成による「都市の認知形式」研究のリンチの共同研究者であったMIT教授のジョージ・ケペス、都心部の歩行者空間化を主張していたショッピング・モールの発明者ヴィクター・グルーエン、そして後に『アメリカ大都市の死と生』をまとめることになるジェーン・ジェイコブズらが集っていた。その後、アーバンデザイン会議は、1970年までに計13回、開催されたが、例えば『形の合成に関するノート』や『パターン・ランゲージ』で知られるクリストファー・アレキザンダーや、『建築の多様性と対立性』『ラスベガス』を著わすことになるロバート・ヴェンチューリら、現在においても参照されることが多い「ビックネーム」が次々とスピーカーとして登場している。つまり、アーバンデザイン会議は、1960年代から1970年代にかけて、近代建築や近代都市計画の批判的再検討、その乗り越えの最前線に立っていた人々の知が集結した場であったといえる。

- エドマンド・ベーコン+ケヴィン・リンチ『都市のイメージ』、ジェーン・ジェイコブズ『アメリカ大都市の死と生』、クリストファー・アレキザンダー『パターン・ランゲージ』、ロバート・ヴェンチューリ『建築の多様性と対立性』

- ル・コルビュジエ『輝く都市』
中野氏は、自分の目指したアーバンデザインを、上の世代の「CIAM的な都市像」の否定という言葉で歴史に位置づけられたが、ここで紹介した両書で描き出されたアーバンデザイン誕生の歴史的文脈からすれば、当事者でない私たちは、もう少し慎重な理解が必要であろう。ただし確かに言えるのは、中野氏より上の世代(戦前生まれの世代)は、CIAMからアーバンデザイン会議へと至る大きな転換期をほぼ同時代的に体験した第1世代であったのに対して、中野氏はすでに転換後の状況からキャリアを出発させることができたアーバンデザインの第2世代であるということだろう。その2つの世代の間には、時代感覚、世代感覚に大きな違いがある。
槇事務所と『都市住宅』
では、わが国において、ハーヴァードのアーバンデザイン会議に相当するような、第2世代のアーバンデザインを支えた知のフォーラムはどこにあったのだろうか。中野氏のインタヴューで興味深いのは、まず、そうしたフォーラムのひとつが槇総合計画事務所(槇事務所)そのもののなかにあったということである。ハーヴァードのアーバンデザイン運動の当事者であった槇文彦氏や、ハーヴァードのGSDを卒業した長島孝一氏や小沢明氏が草創期を支えていた。彼らを通じて、当時の同時代的なアーバンデザインの動向は、槇事務所内で相当程度共有されていた。そうした場で、自ずから若き中野氏らは刺激を受けていたのである。
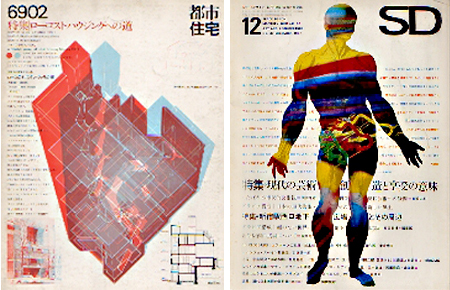
- 『都市住宅』、『SD』
一方で、そうしたアクセスが限定された空間ではなく、また、アメリカのアーバンデザインの直輸入でもない、日本独自の近代建築や近代都市計画の批判的再検討、その乗り越えを実践する場、知の原石が集積していた場は、『都市住宅』というひとつの雑誌であったと思われる。アーバンデザインの探求をテーマに掲げて1965年に『SD』誌を立ち上げていた平良敬一氏が、『SD』の別冊として企画し、創刊した『都市住宅』は、1970年代に時代を担う若者たちを次々と発掘し、アーバンデザインを巡る多様な論点を描き出し続けた。ハーヴァードのアーバンデザイン会議の参加者の著作がほぼ現代のアーバンデザインの原典カタログとなるのと同様の役割は『都市住宅』が果たしている。特に植田実氏が編集長として、年間テーマを設定し、「都市住宅」から想像される守備範囲を超えて、都市や地域の課題や実践を大きく取り上げていった1970年から1975年までの『都市住宅』は、アーバンデザインの観点からは非常に興味深い内容の特集号ばかりが並んでいる。中野氏は、この植田氏編集の『都市住宅』の時代に、学生時代を過ごしている。

- 『都市住宅』1975年9月号、1981年10月号
そして、槇事務所時代の中野氏が関わった仕事も、『都市住宅』における多様な知の集積のひとつとして記録されている。1975年9月号「ミニ・アーバンデザインの試行」、1981年10月号「横浜シーサイドタウンの実験──アーバンデザイン的手法と協同設計の試み」、そして、1984年8月号「日本の都市デザインの現在」の3冊である。
1975年9月号「ミニ・アーバンデザインの試行」特集号では、槇事務所のアーバンデザイン部門の初期の仕事、とりわけ、長島孝一氏が主担当であった1968年の羽衣スタディと1974年の東京の住環境スタディが紹介されている。後者は中野氏が槇事務所で最初に取り組んだ仕事である。槇事務所を代表して、長島孝一氏が論考を寄せているが、そこでは、「1960年代は経済成長と強者の論理に支配されたメガ・アーバン・デザインの時代といってよい」とし、今後は「物的環境のストックを大事に使い、かつそれを漸進的に増やしていくことである。すなわち、住環境の問題を肌目細かくひろい上げて、現状にドラスティックな変化を加えることなく、漸進的にミクロな改良を積み上げていくことが、当面最も実現可能な方法として浮かび上がることになる」とした「〈あるもの〉をベースとしたミニ・アーバンデザインの手法の提案」が重要であるとした。1970年代半ばの未来感覚として、「たとえばゼロ成長あるいはマイナス時代のもとでは新たな大規模開発や再開発といった事業に依存した都市問題の解決は、次第に困難となってくることが予想される」とまで述べているのは、現代の状況がすでに40年近く前に的確に見通されていたようで正直驚くが、ここでは、アーバンデザインの第2世代ならではの原風景は、右肩上がり、経済成長の終わりが見えた時代にあり、それが現在の私たちが置かれている状況と似ているところがある、とだけ言っておこう。
一方で、1981年10月号の「横浜シーサイドタウンの実験──アーバンデザイン的手法と協同設計の試み」特集では、槇事務所がマスタープランとその後の一部の基本設計を担当した横浜の埋立地金沢シーサイドタウンをめぐって、低層の住宅と歩車共存のコミュニティ道路といった「街らしさ」「都市らしさ」を生み出すための空間構成技法とともに、槇事務所と実際の事業主の日本住宅公団、横浜市、さらには造園会社やインダストリアルデザイン事務所等との協同のプロセスのなかで、アーバンデザインの役割についての考察が深められている。アーバンデザインが、単に都市像を描き出すというだけでなく、横浜市の実践のなかで、いかなる役割を果たすのか、という論点が提示されている。当時の中野氏の仕事は、例えばアメリカではジョナサン・バーネットがニューヨーク市で、アラン・ジェイコブスがサンフランシスコ市で、それぞれ1970年代に展開させた「公共政策としてのアーバンデザイン」とこうした点でも同期するところがあった。
そして、1984年8月号は、「日本の都市デザインの現在」特集である。中野氏がインタヴューでも言及していたアーバンデザインの勉強会のメンバー、つまり中野恒明氏、故北沢猛氏(当時横浜市都市計画局都市デザイン室)、六鹿正治氏(当時日本設計事務所)、陣内秀信氏(当時法政大学助教授)の4名が編集協力に名を連ねた「図説・日本の都市デザイン」では、1960年代、1970年代、1980年代のアーバンデザインの成果が、幾つかのキーワードで総括されている。1980年代は、「70年代から続く〈量から質へ〉という動きが、全国的な広がりを見せ始める」「〈地方の時代〉にいよいよ突入したのかも知れない」と語られた。「〈都市景観〉という概念」の一般化、「都市空間へ仕掛けをうち、また、まとめてゆくという、いわばプロデューサーとしての建築家の役割」の浮上が、1980年代のアーバンデザインを巡る気運であった。中野氏自身は、1970年代の「ショッピング・モール」、1980年代の「歩車共存道路」の2つのキーワードを解説していた。
中野氏が槇事務所から独立し、槇事務所で同僚であった建築家・大野秀敏氏とともにアプル総合計画事務所を立ち上げたのは、まさに『都市住宅』の「日本の都市デザインの現在」特集号が発刊された1984年8月である。独立後の中野氏の仕事はインタヴューで語られたとおりである。第2世代のアーバンデザインの第一人者として、多様な活躍をされたのは確かだが、その仕事には、この槇事務所時代のアーバンデザインの時代感覚、世代感覚が通底しているように思われる。
第2世代のアーバンデザインの展開
中野氏が編集に関わった『都市住宅』「日本の都市デザインの現在」特集が刊行されてからすでに四半世紀が過ぎた。しかし、この四半世紀の日本のアーバンデザインを歴史として描くのは、あまりに多くのことが現在進行形であり、難しい。ここでは、この『都市住宅』特集号に編集協力として携わり、「第2世代のアーバンデザイン」の担い手として期待されていた中野、北沢、六鹿、陣内の各氏のその後を追ってみることで、いくつかの重要な筋道だけでも見つけておきたい。中野氏のその後の仕事については、今回のインタヴューでほぼ網羅されているので、ここでは繰り返しになってしまうが、ポイントのひとつは、土木のデザイン分野の確立に立ち会ったということであろう。日本のアーバンデザインが建築分野から始まったのは確かだが、1990年代以降、都市環境デザイン、景観デザインというかたちで、街路や広場等の都市の公共空間のデザインの分野が実務ベースで育っていった。また、土木学会としても、2001年よりデザイン賞を創設し、土木施設、公共空間のデザインを競いあう土壌づくりを行なった。篠原修氏らを中心として2005年に設立されたGSデザイン会議、そして2010年に発足したエンジニア・アーキテクト協会の設立などに象徴されるように、着実に組織的にデザイン分野が開拓されてきている。この土木分野からのアーバンデザインへの本格的参入は、わが国のアーバンデザインのこの20年の歴史において、重要なトピックのひとつであろう。
北沢猛氏は、2009年12月、志半ばでこの世を去ってしまわれたが、アーバンデザインの20年史に大きくて力強い足跡を残された。北沢氏は1990年代半ばまで、横浜市の都市デザイン行政を牽引しつつ、同世代の仲間たちとアーバンデザイン研究体を立ち上げ、アーバンデザインの思想、技術の向上とその社会的な普及に尽力した。横浜市での北沢氏の実績は多岐にわたるが、特に力を入れたのが、歴史を生かしたまちづくりであった。1980年代前半から、横浜市は、歴史を生かしたまちづくり要綱の整備や、山手地区における歴史的建造物や、日本大通地区の旧商工奨励館(現横浜市情報文化センター)や旧市外電話局(現都市発展記念館)の保存活用、更には赤煉瓦倉庫や汽車道の保存活用、旧横浜船渠2号ドック(現ランドマークタワー・ドックヤードガーデン)の保存活用など、挙げだすときりがないほどの数々のプロジェクトを通じて、横浜の中心部の魅力をなす歴史を現代に活かすためのアーバンデザインを主導した。これらの歴史資源が、個別の魅力の発揮に留まらず、地区、都市のスケールで互いに結びついて界隈や回遊を形成している現在の横浜の姿は、これぞアーバンデザインの成果と言うにふさわしいものである。北沢氏は自治体の立場でアーバンデザインがどのように展開できるのか、その可能性を徹底的に追求していった。しかし、行政マンとしてそのキャリアを終えることはなかった。1997年には母校である東京大学の都市工学科に助教授として戻り、新たな活動を開始した。大学の研究室として地方都市の活性化プロジェクトを立ち上げ、同時に、アメリカにおけるアーバンデザインの最新動向に関する現地調査を行なっていくなかで、次第に自治体が主導するアーバンデザインから、自治体と大学、そして民間、市民が協働するアーバンデザインのありかたを探求するようになっていった。2007年には、千葉県柏の葉にて、官民学による新たなアーバンデザインの姿を具現化する柏の葉アーバンデザインセンター(UDCK:http://www.udck.jp/about/110501_UDCK.pdf)を立ち上げ、さまざまな実践を精力的に展開し、かつ、他の地方都市や横浜においてもそれぞれの地域にあったかたちでアーバンデザインセンターを設立し、わが国におけるアーバンデザインの未来を実践的に説得的に提示していった。おそらく、アーバンデザインをめぐる北沢氏の運動的、実践的、社会的な行動の変遷は、わが国のアーバンデザインの20年史の大きな流れの幹を成したように思われる。最後の最後までアーバンデザインの可能性、その未来を展望し続けた北沢氏の志は、氏と活動をともにした多くの人々や教え子たちに継承され、少なくともこの後の20年のアーバンデザインの進展を後押ししてくれるだろう。
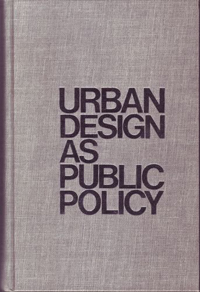
- ジョナサン・バーネット
『Urban Design as Public Policy』
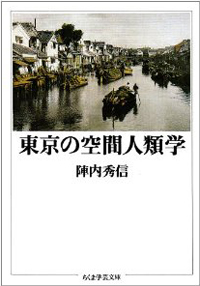
- 陣内秀信『東京の空間人類学』
以上のように、かつて「第2世代のアーバンデザイン」を議論した4名は、それぞれの場でアーバンデザインを確かに先導し、20年史の大事な道筋を切り拓いてきたのである。
私たちの世代の課題へ
さて、最後に、改めて私たちの現状に立ち返ってみると、さまざまな面で心もとないことに気づく。例えば、第2世代にとっての植田氏の『都市住宅』のような、アーバンデザインの知が蓄積するような場、組織あるいはジャーナリズムを持っていない。そして、中野氏をはじめ、第2世代の誰もが仮想敵とすることができたCIAM的都市像のような単純に対抗すればいい都市像も、いやそのために逆に明確になっていないといけない望むべき都市像も、いまいち漠然として、曖昧であるようにも思われる。「第2世代のアーバンデザイン」から多くのことを学びつつ、その継承の先で、自分たちの世代、時代ならではの感覚との接点を生み出せるはずだと直感しているものの、まだ、それを名指すことも描くことも十分にはできていない。どこから、手をつけていいのか。「まちデザイン」という言葉やこのささやかなウェブサイトが、いつかアーバンデザインのフォーラムとなり、都市像なるものを磨いていくための(おそらくそれぞれの実践を言語化し、共有可能なものにしていくための)仕掛けとして機能していくことが期待されるし、私もそういう仕事をしていきたいと思う。
◉ 中島直人 なかじま・なおと/慶應義塾大学環境情報学部専任講師
※「新しい『まちデザイン』を考える」は隔月で連載を行ないます。
201110
連載 Think about New "Urban Design"
【第5回】[インタヴュー]新しい「まちデザイン」を考える 5──創造都市論の現在【第5回】[インタヴュー後記]小都市の実験可能性【第5回】[インタヴュー後記]多様で寛容な創造都市論、そして日本の文化【第4回】[訪問対談]Learning from 富山市──まちはデザインで変わる【第4回】[特別寄稿]富山市の都市特性と都心地区の活性化概要 【第4回】[特別寄稿]まちなかの超一等地を「広場」にする
──アイがうまれるグランドプラザ【第4回】[訪問後記]富山の都市再生から建築を考える【第4回】[訪問後記]オーラを放つまちデザイン【第3回】[インタヴューを終えて]まちデザインを連歌のように【第3回】[インタヴューを終えて]あらためて歩行者空間を思う【第3回】[インタヴュー解題]ヨーロッパのアーバンデザインの歩み【第3回】[インタヴュー]新しい「まちデザイン」を考える 3──ヨーロッパの都市デザイン20年史【第2回】[インタヴュー]新しい「まちデザイン」を考えるための、アーバンデザイン20年史【第2回】[インタヴュー解題]第2世代の「アーバンデザイン」【第2回】[インタヴューを終えて]アーバンデザインの青春と私たち【第2回】[インタヴューを終えて]都市居住なくして都市の繁栄はない、のかも【第1回】[連載にあたって]建築やアートでは限りがある【第1回】[連載にあたって]建築家、まちへ出る【第1回】[対談]新しい「まちデザイン」を考える


