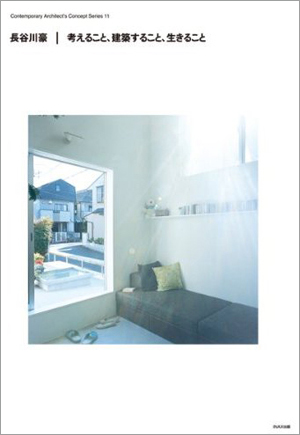身体の果敢な行動のなかからしか世界は立ち現われない──長谷川豪、書籍、展覧会、近作をめぐって

- 乾久美子氏、長谷川豪氏(青山ブックセンターでのトークイヴェントにて)
六本木の夕方5時。長谷川豪展を見終わり地下鉄乃木坂駅に下る階段にさしかかろうとしたその瞬間、頭上でカァーン、カァーンと鐘の乾いた音色が鳴り響いた。展示されている仮設の鐘楼の鐘を鳴らすというイヴェントの情報を見落としたままギャラリーを後にしたようだ。そのギャラリーが入居するビルを見上げると、中間階の屋上テラスに設営された鐘楼の周りに観覧者が群がっているのが見える。しまった、あと数分長く滞在していればなあと反省しながら聴いていたのだが、途中からギャラリーで体験するよりもよいのではないかという気分になった。というのもこれから石巻で毎日鳴る(であろう)教会の鐘の音が生み出す環境の奥行きが六本木のまちかどに出現したことに立ち会い、それにより都市のなかで萎縮していた身体が、空間のなかに伸びやかに拡大したような感覚を得ていたからだ。この鐘の音をギャラリーのなかで味わったとしても、展覧会という保護された枠組みのなかでのちょっとしたアトラクションにしか感じなかったと思う。身体の解放という長谷川豪が追い求めているはずのテーマを、展覧会という枠組みを超えたリアルな体験として味わったことは貴重であった。

- 六本木のまちかどからギャラリー・間の鐘楼を望む(撮影=長谷川豪建築設計事務所)
数年前、筆者が設計した集合住宅の見学会の時のことである。まだ知りあって日の浅い長谷川豪が、この住宅には身体のよりどころとなるようなきっかけがまったくない。腰壁を設けるだけで容易に解決できる問題なのに、なぜわざわざ掃き出しのサッシュなのかというようなコメントを投げかけてきた。形式がそのまま立ち上がったような極端な建築を目指していた。身体的な体験というよりは、視覚的な体験を重視していたのでサッシュに対して批判の声があがることはわかっていた。そういう意味で長谷川が投げかけてきたタイプの質問は想定範囲内のものだったのだが、自分と同じように形式性への興味を強くもっていると思っていた長谷川豪という建築家が、吉村順三スクール的ともいえるような素朴な身体的体験を要求してきたことに驚いた記憶がある。極度に形式的な手続きにより生まれた建築に対して、何のためらいもなく愚直な身体性を要求する感覚とは一体何なのか。そこに長谷川豪という建築家像が現われているのではないかと筆者は考えるようになった。
身体性とはいってもいろいろある。抽象的なもの、ウェッブ上に広がる仮想的なもの、動物性といわれるような無意識的なものなど、私たちの身体はさまざまに分裂している。そのなかでも長谷川が信じるのはあくまでも素朴な生身の身体である。それこそ吉村順三のように見る、触れる、使うなどあらゆる日常的な体験のひとつひとつに対して丁寧に快適さを紡ぎ出していき、そのなかに生き生きとした生活世界を描こうとするような類いのものだ。ただし吉村時代には日常的な体験を取り巻く「生活」そのものが処女地として存在していたことに対して、私たちの目の前にひろがるそれにはすり切れた印象すら覚える。現代では生活をとりまくあらゆる資源や機会はバラバラに解体され商品化されているため、私たちは消費者としての立場を余儀なくされるからだ。そして私たちの身体は商品世界の包囲網のなかで、その可能性を広げる機会を失ったまま最低限の機能しか果たさない存在へと容易に落ちこんでいく。そのようななかでいくら吉村的に素朴な身体的体験を追求したとしても、商品世界におけるひとつのオプション以上のものになりえない。下手をすると、例えば吉村スクールや象設計集団的なものなどかつて身体性を重視した建築観がそうであったように、ドグマティックな思考回路に陥る可能性もある。それでも長谷川は素朴な身体をあえて信頼しようとする。困難な挑戦といってよいと思う。けれど長谷川は驚くべきさりげなさでそれをこなす。
素朴な身体の現代における行き場、長谷川建築における問題を仮にこのように設定してみたとして、それを解く鍵は彼が設定する身体がいつもかなり忙しいことにあるように思う。J・アプルトンの「眺望─隠れ場理論」のような生理的欲求をみたした室内環境のなかでぬくぬくと過ごすだけの受け身の身体は許されない。例えば《森のピロティ》ではとてつもない高さにまで身体を這い上がらせなくてはならない。《桜台の住宅》では「行儀が悪い!」と怒られることもいとわずに巨大なテーブルの上で走り回ることが期待される。あるいは《五反田の住宅》では家のなかで過ごしているにもかかわらず、部屋を移動するたびにまちかどに出なくてはならない。そんなふうに身体のまわりに広がる場所の可能性を発見するべく、行動に出ることが要求される。そうした身体の果敢な行動のなかからしか世界は立ち現われないと言っているかのように。そして──ここが一番大切なところだが──長谷川の建築はというと、身体がこうした行動を嬉々としてとってしまうような状況をつくりだしてしまうのだ。身体は動いてしまうけど、壁や床などがつくりだす拘束力によって無理やり何かを体験させられているわけではない(そうした体験マシーン的な建築として荒川修作による《三鷹天命反転住宅》などの例が思い出されるだろう)。建築はあくまでも無骨といえるほどに建築らしい操作だけでつくられつつも、身体を動かし解放する動機づけにあふれたものとなる。その動機づけを確実なものとするために、長谷川は彼のもうひとつの興味である強い形式性を導入する。

- ギャラリー・間の展示(撮影=長谷川豪建築設計事務所)
超高床、巨大なテーブル、なぜかインテリア化している外階段室など、長谷川は既存の建築ヴォキャブラリーのスケールやレイアウトを操作することだけで、これまでにない建築体験と新しい形式をつむぎだそうとする。こうした建築という古いメディアがもつ文脈を解体し再構築するという方法論は長谷川に限ったものではなく、筆者を含めて坂本一成、妹島和世、青木淳、アトリエ・ワン、そして西沢大良などに影響を受けて建築をスタートした世代に広く見られる傾向だと思う。そのなかでも長谷川が突出しているのは、形式のなかに盛り込まれた身体的体験の圧倒的な魅力だ。建築の形式が身体をのびやかに解放すると同時に、そうであるがゆえに形式がもつ力を再確認させてしまうようなループが存在する。こうした形式と身体との幸福で有機的な関係は、例えて言うならば楽器に近いあり方を提示している。楽器のようにとてつもなく強い形式を持ち、客観的にみるとその形式は得体が知れず、しかし同時にかかわりたくなるような魅力を放っており、そしてちょっとしたコツを得ることで身体と同化し、さらに身体の能力を際限なく引き延ばす可能性に満ちているのだから。また楽器がそうであるように、何かを解決するために生み出された道具なのではなく、使うことそのものがよろこびとなるという点も近いのかもしれない。そこで思い出すのは、長谷川の設計した新しい家に入居した子どもたちのエピソードだ。子どもたちは、人が変わったように明るく解放的な行動をとるようになると聞いた。そのなかでも特に素晴らしいのは、引越し当日に新しい家に足を踏み入れると、これまで人前で歌ったことなどない子が皆の前で突然歌い出したというもの。彼(もしくは彼女は)この住宅を最も活かすためには「歌わねばならない!」と感じとってしまったのだろう。こうした子どもたちは住宅建築という楽器の天性のプレーヤーとして、住宅をぞんぶんに味わい奏でる術を一瞬にして体得したのではないか。
このように形式と身体とが有機的に結びつくことのリアリティを伝達しようとしても、それが体験的なものであるが故にとても難しい。筆者も胡散臭いテキストになることを恐れながら、今まさに書いている。言ってみれば現象学的な建築などにつきまとう問題だ。そのことを察知したのか、例えば長谷川豪展では身体性という問題がほとんど強調されていなかった。展覧会はちょっと硬すぎるのではないかと思わせるほどに形式的な手続きの積み重ねで構築されており、全体的にやや図式的だと感じたのは筆者だけではないだろう。しかしながら、鐘楼というまさに楽器=建築そのものを提示することで、まわりくどい手続きをとびこえて一点突破的に身体という問題を私たちにつきつけることを試みたのではないか。その目論見通りに筆者はたまたま鑑賞してしまったのかもしれないが、その後味たるや爽快だった。私は長谷川が意図していたはずの世界が現象する瞬間を確かに味わうことができたのだから。
そうした明るさというか、思い切りの良さは長谷川建築のすべてに通底する特徴だが、そこから筆者が感じるのはとてつもない楽観性だ。彼の住宅は生を謳歌するエネルギーにあふれており、人生が時に抱えてしまう苦悩や困難から無縁であるかのように見える。実のところ筆者は、彼のクライアントの多くが若夫婦であることとあいまって、人生のステージのなかでも特に楽しい時期だけにあわせて設計しているのではないかと心のなかで少しばかり批判していたりした(長谷川さん、申し訳ありません)。しかし、今回、展覧会を鑑賞し、著書を読み、作品集を眺め、長谷川建築を俯瞰的にみる視点をもつ機会を得て改めて気づいたのは、楽観的であろうとする彼の強い意志の存在だ。たまたま楽観的につくられてしまっているのではない。再び鐘樓を引き合いにだしてしまえば、鐘の音により小さな町の日常を塗り替え、建築の枠組みを超えて、まちそのものを幸福な生活世界へと更新しなくてはならないという強い決意すら感じた。
そう、もっと自由で快適であり、世界と一体化できるような、そこにいるだけで嬉しさが極まるような建築や場所をつくろうとすること。そうしたある種の楽観性を受け入れたものをつくるにはまさに決意が必要である。アランがかつて『幸福論』で唱えたように楽観的であることにこそ意志が必要であり、不断の努力を必要とする。長谷川豪はそうした楽観性の必要性に気づき、それを獲得することに努力を惜しまない稀有な建築家なのではないか。
※ 長谷川豪氏、乾久美子氏によるトークイヴェントは、2012年2月11日、青山ブックセンターにて行なわれました。