戦争をめぐる発見の旅──古市憲寿『誰も戦争を教えてくれなかった』
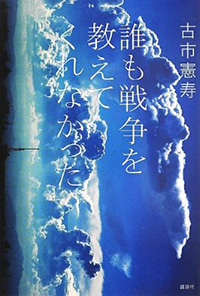
- 古市憲寿『誰も戦争を教えてくれなかった』
(講談社、2013)
1985年生まれの著者・古市憲寿氏は、《ハワイでパールハーバーを訪れたことをきっかけに、...新しい土地へ行くたびに戦争に関する博物館を訪れるようになった》。中国の南京大虐殺紀念館、偽満皇宮博物院、九・一八歴史博物館、二○三高地、...。ポーランドのアウシュビッツ、ベルリンのユダヤ博物館、ローマの解放歴史博物館、韓国の独立紀念館、日本各地の平和記念館、...。それらを順に経めぐって、感想をしるし、戦争がどう語り継がれる(いや、語り継ぐのに失敗する)か、について考察したのが本書である。
戦争について自分の頭で感じ、考えること。そして、戦争について表現し、語り伝えること。戦争世代にとっては切り離すことのできないこのふたつのことが、筆者にとっては別々のことである。そして、前者をあえてカッコに入れ、後者についてだけに考察をしぼったところに、本書は成立した。その素材が博物館だった。
戦後世代にとって、そこに戦争がある(あった)ことは自明だった。否定しようもないが、自分たちには隠されている。そこで、その戦争がどんなものだったか、それを体験した上の世代が、それを体験しない下の世代に語り継がなければならない。戦争の体験が、語る権利を語り手に与えるのは当然、とされている。戦争の体験がない聞き手は、それを「継承」することが求められる。
こんなことが半世紀も続いたあと、空回りが始まった。戦争を語る側がもはや、戦争を体験していない。戦争を語り継ぐことは、空虚な儀式のようになる。内実のない言説が、内実があるかのように再生産される。「王様は裸だ」と、だから著者は叫んでいる。著者は戦後世代よりもうひとつ下の世代、すなわち、ポスト戦後世代なのだ。
本書のポイントは、国境をまたいで、戦争の異なる語られ方を比較していることだ。パールハーバーの記念館は、《とても「爽やか」で「楽しい」ものだった。》これまで教えられてきたのと違って、《戦争自体は忌避すべきものではない。》それなら、わが国の戦争の語られ方(戦争は悪である)は、ただの思い込みの産物ではないのか。空回りの実相があばかれる。世界のさまざまな戦争博物館を経めぐるその矛先は結局、わが国に向けられる。
だから本書は、世界各地の施設をめぐる著者の、発見の旅である。戦争を語り継ぐとはなにかといった、大上段からの「理論的考察」は、とりあえずない。そのかわり、施設をひとつめぐるたびにあらたな発見が積み重なり、著者も読者もともども新しい場所に連れ出される、という構成になっている。
パールハーバーでは、《多くのアメリカ人にとって、第二次世界大戦は「よい戦争」として記憶されている》こと、《真珠湾攻撃自体は負の歴史だが、国家として行うべくは犠牲者への弔いと、彼らのおかげでアメリカの勝利は導かれたという物語の提供》であることを知る。戦勝国の歴史は、考えてみれば当然だが、戦争を肯定するのである。
同じ戦勝国でも、中国はまた異なる。南京大虐殺紀念館は《日本軍の「残虐さ」を強調した上で、中国共産党の寛大さによってもたらされた日中友好が提示される》。戦争博物館は小中学生の「愛国教育」の定番コースになっている。生徒たちは退屈し、教師たちはやる気がない。《戦争から遠く離れてしまったのはきっと、中国も同じなのだろう。》
アウシュビッツは、実物をそのまま保存する、という方針を貫く。過剰な説明やメッセージは極力避けられている。事実に語らせ、来場者の想像力にまかせる、厳粛な空間だ。歴史は記録し記憶することだという、原則がはっきりしている。そして、現場をありのままに保存するために、たいへんなコストがかけられている。
ほかにも多くの施設を訪れた著者は、どのような考え方の道筋を導き出すか。第一に、戦争を体験した人びとの証言は、「小さい記憶」である。すべてが正しいわけでも、互いに整合的なわけでもない。戦争の渦中にあった個人が戦争の全貌をみることができたわけではないし、その人なりの主観的な偏りもあるだろう。第二に、博物館は、《「ちいさな記憶」を拾い集めて、「大きな記憶」として次の時代へ残していく試み》、すなわち、戦争の記憶をつくり出す装置にほかならない。なにかを展示することは、なにかを切り捨てることでもある。博物館である以上、なにかの方針なしに、展示を構成することはできない。そして、どうやってその記憶を構成するべきなのか、正解というものはない。
第三に、わが国の博物館(たいていは、平和祈念館みたいな名前がついている)は、特定の立場や価値観にコミットするのを避け、抽象的な一般化を好む傾向がある。《予科練平和祈念館では...1億人以上の人が命を落としたことに触れた上で、「今、私たちが生きている世界はこうした多くの犠牲の上にあるのです」と続ける。ここまで一般化されると批判のしようがない。》でもメッセージとしては、意味不明ではないか。
第四に、それでも、戦争を語り継ぐ施設はつくられ続ける。《日本では、1980年代から1990年代にかけて平和博物館ブームが起こった。》その多くを、乃村工藝社という会社が受注した。乃村工藝社は沖縄平和祈念資料館も遊就館も手がけ、その昔には「支那事変聖戦博覧会」や「墜落敵機B29展」を担当した大手である。任せておけば間違いがない、のである。
第五に、日本が経験した第二次世界大戦の総力戦は、歴史上あまりに特殊なケースで、将来に向けての教訓にならないのではないか。これからの戦争は、無人兵器やサイバー攻撃を主体にした、従来の戦争とはかけ離れたものになりそうだ。それならいっそのこと、「戦争を知らない」ほうがよいのかもしれない。
評者も、軍事博物館をいくつか訪れたことがあり、著者の感性に共鳴する。アメリカのあちこちの軍事博物館は、すぐにもまた戦争をやりそうな気迫がこもっている。中国では、南京の虐殺記念館、ハルピンの七三一部隊記念館、柳条湖の九・一八記念館、撫順郊外の平頂山虐殺紀念館、盧溝橋抗日戦争記念館、ほか。現地の雰囲気は本書の伝える通りだ。
日本人は、歴史という「大きな記憶」を紡ぎ出すことに、失敗しているのではないか。本書の重要な結論だ。
この結論はまことに正しいと思うが、感慨ぶかくもある。「大きな物語は終わった」が合言葉だったのは、ついこの間のこと。ポストモダンの時代、みなが「大きな物語」みたいなものから背を向けた。時代はやっと、まっとうな揺り戻しを迎えたのだろうか。
本書はひろい意味での、言説分析の書物である。言説分析は、対象そのものではなく、対象の語られ方を問題にする。対象に没入しないですむための、デタッチメントの技法である。ポストモダンの好んで用いるアプローチだ。著者・古市憲寿氏の立ち位置とこのアプローチとのねじれた関係をどうこれから整えていくのか、興味をもって見守りたい。
はしづめ・だいさぶろう
1948年生まれ。東京工業大学名誉教授。著書=『言語ゲームと社会理論──ヴィトゲンシュタイン・ハート・ルーマン』『はじめての構造主義』『民主主義はやっぱり最高の政治制度である』『なぜ戒名を自分でつけてもいいのか』『世界は宗教で動いてる』ほか。
201311
特集 ブックレビュー2013
群像の貴重な証言集めた労作。私たちはその声をどう聞くか──豊川斎赫『丹下健三とKENZO TANGE』
人間学としての都市・建築論──槇文彦『漂うモダニズム』
モノ作りムーヴメント:その現状と新たな可能性 ──田中浩也編著『FABに何が可能か「つくりながら生きる」21世紀の野生の思考』
建築計画とコミュニティデザイン──小野田泰明『プレ・デザインの思想』
古代ギリシャからの視線──森一郎『死を超えるもの──3・11以後の哲学の可能性』
戦争をめぐる発見の旅──古市憲寿『誰も戦争を教えてくれなかった』
放射性廃棄物はどこに隠されているのか? ──『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド』
「コモン化」なる社会的実践から空間について考える──デビッド・ハーヴェイ『反乱する都市──資本のアーバナイゼーションと都市の再創造』


