takram Directors' Dialogue 02:田川欣哉 × カズ米田
ただいま「現代建築家コンセプト・シリーズ No.18|takram design engineering」編集中。2014年8月までのプリプレス連載企画「takram Directors' Dialogue」。
takramの4人のディレクターが語る「デザインエンジニアリングの思想と未来」。
連載「takram Director's Dialogue」第2回は、田川欣哉さんとカズ米田さんの対談を掲載します。
「Design "and" Engineering」から「"not" Design "nor" Engineering」へ。より多様性を持ちはじめたtakramにとって、建築への取り組みは新鮮なチャレンジです。takramはこのチャレンジを「Problem Reframing(プロブレム・リフレーミング)」や「振り子の思想」などの延長線上に位置づけます。結果として見えてきた建築分野での新しい可能性や、takramが「越境し、試行錯誤を続ける」ことで今後どのように展開していくか、伺いました。
カズ米田──建築家の私やデザインエンジニアの緒方壽人さんがtakramに参加したことで変化したことはありますか。
田川──ええ、変化は大きいですね。ベン図でいえば、たとえば私と緒方君は重複する部分が多いですが、カズや渡邉君はそれほど重複していません。さらにまた別の領域を押し広げるメンバー々も入ってくるでしょう。それぞれの持つ領域の外縁が、takramの外縁をオーガニックに形成していきます。
カズ──アメーバ的ですね。
田川──デザインの現場によくあるパターンとして、スター・デザイナーとその下に複数のアシスタントが並ぶ、という鍋蓋型の組織が挙げられます。それはそれの良さがありますが、takramは外縁が自然に広がっていく方法を考えています。
カズ──私は大学までずっとアメリカで生まれ育ったのですが、大学の建築学科を卒業後に日本へ来て、藤本壮介建築設計事務所で設計の仕事をしていました。しかし建築だけでなく、より広い領域や別のデザインの現場も体験するため、アメリカへ戻るまで藤本事務所に籍を置きながら、別の活動の場を探すことにしました。そこで以前から《furin》(2008)や「Water」展(《furumai》2010)を見て面白いと思っていたtakramに履歴書とポートフォリオを送りました。1カ月後連絡がきて面接を受け、建築の仕事はないけれど一緒にやってみよう、ということで参加する運びとなりました。最初にご一緒したのは、親指入力キーボード《tagtype》(2004)をMoMAのパーマネントコレクションとして登録するためのプロジェクトです。
田川──カズがMoMAとの複雑なやり取りをこなしてくれて、最終的にはパーマネントコレクションとして、めでたく選定されました。これは山中俊治さんや本間淳さんなど、プロジェクトに関わった方々にもいい知らせになりました。
カズ──そのあとアメリカへ戻ってハーバード大学大学院へ進学しました。じつを言うと卒業後はニューヨークの建築計事務所に入る予定だったので、日本に帰るつもりはなかったのですが、伊東豊雄さんと一緒に、東京で海外留学生に向けた1セメスターの授業を立ち上げるため再び来日することになりました。同時期にコラボレーターとして取り組んでいたtakramのプロジェクト《Shenu》(2012)がその年の6月にドイツ「ドクメンタ」で発表され、その後の私の進路とtakramの活動が空間へ広がっていく時期が重なり、正式に参加することになりました。 ちょうどその時、takramの事務所を引っ越す計画もあったので、事務所設計を私の処女作とする計画が立ち上がりました。欣哉さん、渡邉さんと、外部からは高塚章夫さん(aaat 高塚章夫設計事務所)という建築家の方を交えたデザインプロセスを経て、2013年の11月に引っ越しをしました。それがtakramの建築、空間系分野の始まりです。したがって、建築分野はtakramのなかで最も若いインハウス・ベンチャーだと言えます。
「解答」は「問い」の質と解像度に大きく制約を受けるという考え方がありますが、クライアント・ワークをしていると、テーマやアジェンダ等を徹底的に考えて、この「問い」しかないというレベルまで純化して依頼してくる人はそれほど多くないように思います。その「問い」を鵜呑みにしてしまうと、「問い」には答えているけれど実行してみたらあまり上手くいかなかった、ということが起きてしまいます。「問い」は、絶対的で動かせないものではありません。逆に動かしたほうがよい。
「問い」に対する「解答」を考える時のエネルギーを、「問い」に対しても注ぐべきかもしれないと思い至ったのが《Shenu》というプロジェクトでした。
「問い」と「解答」を振り子のように行き来させ、「解答」に行きづまるようであれば、そもそも「問い」に間違いがあるのではないか、と疑問視してみます。そうすると「問い」を進歩させることによって得られるであろう「解答」、答えるべき「解答」によりふさわしい「問い」、という「問い」と「解答」の両方で試行錯誤が起きます。こうして、所与の条件として引かれていた思考の境界線も動かせるということに気がつきます。これが「Problem Reframing(プロブレム・リフレーミング)」の考え方です。
カズ──そこに「メタシフト(Meta Shift、超越)」と「トランスシフト(Trans Shift、越境)」はどのように関わってくるのでしょうか。
田川──「Problem Reframing」は「問題を再定義する」ということなので、非常に広い意味を表す言葉です。われわれが生きている活動地平があり、そこに入ってくるさまざまな問題をイメージしてください。その地平の上に超越平面があり、超越平面から見下ろすと問題が地平で見えていた場所とは別の場所にあることがあります。視点を活動地平から超越平面へと垂直方向に動かしてみること、これが「メタシフト」です。
もうひとつは、境界線自体を同じ地平上で水平に動かすこと。「トランスシフト」と呼んでいますが、普通はなかなかできないことが多いですね。たとえば、デザイン部門の輪郭を少しずらして、エンジニアリング部門にまで触れていくといったことです。これは超越視点ではなく、近傍に対して輪郭を押し広げていくというイメージです。
「メタシフト」と「トランスシフト」は対象を見る解像度が異なります。メタ視点では俯瞰で見る代わりにディテールは見えなくなりますが、トランス視点では高い解像度で話が進みます。
こうした論理が必要とされる背景には、物事が細分化されすぎている現状もあります。産業革命以降、産業の細分化・分業による効率化が進み、方法が確立されるやスピードもコストも大幅に下がりました。
私が東大工学部機械科で教わった「問題は因数分解が可能である」というドグマはとても象徴的です。大問題は小問題に分解可能で、小問題はさらに小さな小問題に分解可能ということなのですが、これが機械工学の基本的な考え方で、これ以上分解できないところまで問題を分解した後で、それを設計に転写します。体内の細胞と器官の関係のように、細かな問題が統合されることで大きなシステムができるというような、まさに機械論的なアプローチでした。考えてみれば昔の機械はどれも小さな部品に分解できましたから、このテーゼが成立していたのだと思います。
しかしその方法で進みすぎてしまったために、本当はもやもやした状態で考えなければいけない、インテグレーション(Intergration:部分を有機的に統合すること)が必要になるような複雑なプロダクトや、サービスを考えることが難しくなっています。にもかかわらず、現在の企業は基本的には細分化・分業の構造で構成されています。あらゆる物は分解可能で、分解を重ねてソリューションを組成するという考え方です。つまり企業構造は出来上がった物事を運用するにはとても向いているが、新しい物事を生み出すには、それほど向いていない構造である、という見立てをしています。ベンチャーや創業者のいる企業などでイノベーションが起こりやすいことも、このような見方をすると腑に落ちる部分が多くあります。
カズ──よく言われるもうひとつのドグマが「形態は機能に従う(Form Follows Function)」です。アメリカの建築家ルイス・サリヴァンの、19世紀末の言葉です。しかしいまではソフトウェアのような形態の無いなものが登場し、事態にあてはまらなくなりました。因数分解、部品分解が不可能な時代なのです。
田川──そうですね。さらにもうひとつ、細分化された先にある、テクノロジーによる手段・方法が洗練されてきているということもあります。たとえば「音楽を再生する」行為のなかに、コンピュータで好きな曲だけをランダムに再生するCGM(Consumer Generated Media、消費者生成メディア)など、消費者のモチベーションを掘り起こす手段・方法がありますよね。いまやさまざまな手段・方法があり、選択肢が昔に比べるととても増えています。こうしたことがリフレームが効果を発揮する理由になっています。以前はリフレームしても能力的に特定の専門家にしかできないという壁がありましたが、現在ではそれが誰にでもできてしまう状況が、ネットやソフトウェアの力で実現されつつあります。
カズ──その意味でも《Shenu》は最も面白い例だと思います。さまざまな矛盾に直面した際に、そもそもの「問い」と「解答」の内容と質を変更しないとイノベーションに到達しえないということがよくわかるプロジェクトでした。お題として投げられたテーマは「100年後の水がない荒廃した世界のための水筒をデザインせよ」というものでしたが、そもそも水がないのになぜ水筒が必要になるのかなど、いくつもの矛盾が含まれていました。100年後の世界の水量を測ってみたところ、人口がたとえ現在の1割になっていたとしても、総人口を生存させるための一日あたりの水分供給量や水道設備を整備するのは困難であるということが見えてきました。つまり世界は干涸び、人間のエコシステムや身体能力をはるかに向上させない限りは、1日2リットルの水分を補給するのは不可能だということです。
そこで水というのは人間の体に対して一体どういう意味を持つのだろう、というシフトが起きました。身体における水の循環を効率よく、再生可能にすれば、よりサステイナブルな水との関わり方がつくりえるのではないかと考えたのです。そしてその先で、身体の水分はどこから入り出ていくのかという身体的、物理学的な話に繋がっていきました。
当然そのほかのプロジェクトでも部分的にリフレームは起こっていたと思いますが、作品の基本のコンセプト自体を動かすような大胆なリフレームは《Shenu》に代表されるでしょう。
《Shenu》はテーマ設定からの飛躍を「ドクメンタ」から求められました。われわれが優等生的に水筒をつくることで解答を出すことも可能でしたが、それに対し、展覧会のディレクションを務めた韓国人アーティストのムン・ギョンウォンとチョン・ジュンホがわれわれに対して「もっと何かないか」という注文をずっと言い続けてくれたおかげで、リフレームが起こったのだと思いますが、いまはクライアント・ワークの場合にも、takramからリフレームを提供できる状況になってきています。
ただ実際に実務に携わると、世界は複雑にできているので、自分がすべきことを特化したほうがわかりやすいという状況が見えてきました。建築というものは、建築家が自身の考えを「建物」に反映する、とてもわかりやすい関係で成立していますが、私はやはり幼い頃に思い描いていたように、ただ建物を建てるだけではなくアートもすれば本も書く、考えることを絶やさない存在でいたい、と思っています。
一方でそれは人に説明するのがとても難しい。建築家だというと、クライアントから「建物をつくりたい」というストレートな前提をいただくわけです。takramで担当した《Shenu》や有機ELを扱った《Habataki》(2013)といった仕事は、建築事務所にいたら関わるチャンスはないとは言えないですが、可能性は低かったでしょう。
建築は最大のUI(ユーザー・インターフェイス)/UX(ユーザー・エクスペリエンス)であると言われます。つまり床や壁、天井、照明などが、生活者と何らかの関係を持つということですが、この概念をどのようにして空間ないし都市空間に落とし込んでいけるのかを模索すること、また同時に、多くの思想から刺激を受けるこのが可能なtakramという組織環境のなかで新しい建築のあり方を模索していくことがこれからの私の課題です。そしてアーキテクトとしての職域を「建物」をつくることに限定せず、文化を創造することと捉えていきたいと考えています。そして社会の在り方を示すものとして、世界に発信していきたい。
欣哉さんは、takramにおける建築をどのような位置づけとして育てたいと思っていますか。
田川──基本的には「takramにおける建築」は「takramにおけるソフトウェア、ハードウェア、プロダクトデザイン」と同じ話です。つまり、takramでは建築を特殊な分野として考えないようにしたいと思っています。以前、同年代の建築家とよく話をしたのですが、彼らには建築が絶対的なものだという信念があることを感じました。しかし絶対性に酔うということは、建築のすばらしさを意味すると同時に、分野としての脆弱さも示していると私は思っています。たとえば、Skypeのようなサービスで遠隔地同士を繋ぐと、空間に擬似的なトンネルができます。このトンネルが空間ではないのかというと、そうとは言えないだろうと考えています。そういうことがこれから先にたくさん起こるだろうと思います。それゆえ、自分たちがつくらなければいけないものをつくりあげていく媒介のひとつとして建築を位置づけたいと思っています。これはデザインを重要と思い、エンジニアリングを重要と思うことと同じです。takramの持っている相対化能力やリフレーム能力を活かして独自の建築観を提示できるかもしれない。そんな夢を持っています。
カズ──建築を相対化するプロセスを経てtakramの建築観を確立するということですね。
田川──最も望ましいのは、建築という分野を愛しながら相対化することです。なぜならわれわれが取り組む問題が極めて複雑で多様だからです。空間へのアプローチにおいても、分野を相対化して振り子を振りながら問題に挑むことがtakramらしいやり方だと考えています。
カズ──takram事務所を設計した時は、グラフィックデザイナーや照明デザイナーと共働したり、家具もコクヨと一緒につくりしました。捉えようによっては総合プロデューサーみたいなものですね。
田川──建築は総合芸術ですよね。takramという組織環境はじつに多様なのでさまざまな可能性があります。
カズ──必要とされているのは、建築だけに頼った解決策ではなく、もっと大きな世界観の体現として建築を含めた解答を導くことです。たとえば、コニカミノルタ社と共同した《Cradle of Light》(2014)は「建築×演出」「建築×プロダクト」「建築×照明」だったように、さまざまなもののなかに建築もキー・プレイヤーとして入った状態が面白いのだと思っています。
アメリカではTheory(理論)とPractice(実践)の違いについてよく述べられますが、本当に良いデザインは、その部分がシームレスでなくてはならないと思うのです。欣哉さんはどのようにお考えですか。
田川──理論とは「一般化」ということだと思います。理論と実践というのは、サイエンスでは理論と実験ですね。目の前で起こっている現象とそれを説明するに足る数式とを突き合わせながら、完全に一致するまで、実験器具を改修していく場合もありますし、理論面を改修していく場合もあります。研究において、理論だけの論文は存在しないし、実験だけの論文も存在しません。理論と実践・実験というのは、基本的には互いが裏表になるものであって、双方を磨いていくことで初めて高みにいけます。
カズ──takramにおける「Prototyping」は一般的に「プロトタイプ」と呼ばれているものとどう違うのか、そして建築に「Prototyping」があるとしたらどのようなものものだとお考えですか。
田川──プロジェクトの初期に行なうプロトタイピングは、アメリカのデザイン・ファームIDEOが「Quick and Dirty Prototyping」という考え方を示して以来知られるようなりました。一般的なプロトタイピングは抽象設計を具体化する際に行なうもので、イメージが具体的に成立するか、つまりフィージビリティを確かめるための試作です。しかし、プロジェクトの初期に行うプロトタイピングは抽象思考のためのものです。試作品としてのプロトタイプ自体を問題にしているのではなく、それを超えたレベルでの様々な気付きや発見、そして議論を巻き起こすものでなければ意味がないと思っています。
大きな企業には試作部という部署があり、図面を受けて試作をしています。しかし試作するうえで気づいた疑問点があっても企画に戻したりできない構造――企画→設計→製造というウォーターフォール型の構造――になっている。私は「抽象は具体にそのまま転写可能である」という考え方に違和感を持っていますが、「Prototyping」はそれを打破するための思考フレームです。その語源からしても「Proto(原型になる前の、前型の)」Typeですから、本来はプリ・プロダクションではないはずです。しかし、一般的なプロトタイプの多くがプリ・プロダクションやプロダクション・アセスメントであり、コンセプト面を鍛え上げるための「Prototyping」はあまり行なわれていないように思えます。
建築は古くからスケッチを描き、模型をつくってきましたよね。スケッチ、エスキスと模型が思考ツールになっているという意味では、「Prototyping」と本質は同じだと思います。なぜなら、建築は実物をプロトタイプすることができないので、事前にあらゆる問題を整理しておく必要があるからです。ただし、それゆえにtakramのリアルなスケールとマテリアルによる「Prototyping」とは異なります。スチレンボードでできたプロトタイプと、ワーキングプロトタイプは体験の品質が大きく異なります。建築では、模型と実物の建築はあらゆる意味で異なるわけで、その間を精密に埋められるところに非常に大きなエクスパティーズがあると思います。
カズ──特に日本はスチレンボードで模型をつくらないと検証できないとされているようなところがありますが、乱暴に言えば、それは前時代的だと思います。いまはコンピュータのなかでモデリングし、その場で「この柱をもっと長くしよう」といった変更がすぐにできるので、模型に頼らなくてもよくなりました。デジタル空間内で本当に検証できるのか、という問題は挙げられますが、それはセンスによるでしょう。スチレンボードで模型をつくることとコンピュータのなかでモデリングすることは、私にはそれほどの違いはありません。
もうひとつ、私は「Prototyping」とは、主流になる前の実験的なアイデアを実体化するメソッドです。これは、新しい社会を作り上げていく方法論のベースになるようなものだと思っています。すでにネットやソフトウェアの世界では、プロトタイプをそのまま世に問いかけてしまうという方法が一般化しています。takramという組織環境でこそ可能な「Prototyping」建築ができれば、それは次の世代に大きな影響を与えることになるのではと考えています。
takramの「Prototype」の面白いところは、仮説ベースで、なおかつ最初の仮説は結果的に半分ぐらい間違っていても試していくというところです。「Prototype」はいわば、あるものをポンと投げ、そこから返ってくる音で周囲の状況認識するようなソナーのような役割を果たします。
作家性も、そういった手探り状態における強い指針になります。作家性は外部に依拠しないので、五里霧中であっても自律的に進んでいくことができます。作家性こそが貫通力である場合には作家性で勝負すべきだと思っています。逆に作家性が結果を生まない場面も多分にあります。そういった時に「Prototyping」を用いて自らの作家性から離脱し、別次元に遷移していく。そういうことを、takramのデザイン・エンジニアたちはやっています。
最初にゴールはわかりませんし、スタートしてからも経路は随時変化します。しかし、精度はプロジェクトの後半、終盤になるにつれて加速度的に上がっていきます。takramでの建築の課題はそのようなプロセスをいかに自覚的に取り入れていくかだと考えています。takramの建築家達は新しい手法を用いて、作家性の強い建築家とはまったく違うプロセスでクリエイションに入っていくかもしれません。そのような状況を見てみたいと思っています。
カズ──いま建築は、モダニズムのような大きなひとつの潮流に収束することのない、混迷期に入っています。大きく言えば、混迷を抜け出すべく新しい時代を築く潮流を生み出したいと考える人たちと、多様なままでよいと考える人たちに分かれています。いずれの立場もありうると思いますが、最も大事なのは、建築が社会にどう利するのか、どういったインパクトを与えることができるかを考えることです。しかしいまの建築がその役割を果たしているか、私は心許なく感じます。
社会づくりに関するものには、建築もあればUI(ユーザーインターフェース)も、プロダクトもあります。「空間」があるのと同様に、社会や私たちの周りには「時空」があって、それに対してどのような理論が必要で、どのようなデザインを提示できるのか、実践を積み重ねていくことが大事です。仕事をしながら考え、考えながら仕事をすることで、デザイン、ひいては新しい社会空間や環境空間を見出さなくてはなりません。たとえば街をトータルでデザインする、家や車、インフラシステム等全てをデザインする仕組みを考えられる多様性を体現する集団でありたいと考えています。
2013年12月5日、takram表参道オフィスにて
田川 欣哉(たがわ・きんや)
takram design engineering ディレクター/デサインエンジニア 1999年東京大学工学部卒業。01年英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修士課程修了。デザインエンジニアリングという新しい手法で、ソフトウェアからハードウェアまで幅広い製品のデザインと設計を手掛ける。07年Microsoft Innovation Award 最優秀賞、独red dot award: product design 2009など受賞多数。
カズ米田(かず・よねだ)
takram design engineering アソシエイトディレクター/アーキテクト。建築と都市デザインを専門とし、takramでは《Shenu》《takram Omotesando》《Chicago Laboratory》を手がける。新たな建築セオリーをはじめ、より革新的な文化創造に興味を持っている。シアトル市生まれシリコンバレー育ち。コーネル大学B.Arch修得ハーバードGSD大学院M.Arch2修士課程修了。終了後2011年、建築家伊藤豊雄氏率いる同大学院東京スタジオにてTeaching Associateに着任。2013年、東京大学工学部建築学科で学部生に設計課題を指導するUnit Master(非常勤講師に相当)に着任。
takramの4人のディレクターが語る「デザインエンジニアリングの思想と未来」。
連載「takram Director's Dialogue」第2回は、田川欣哉さんとカズ米田さんの対談を掲載します。
「Design "and" Engineering」から「"not" Design "nor" Engineering」へ。より多様性を持ちはじめたtakramにとって、建築への取り組みは新鮮なチャレンジです。takramはこのチャレンジを「Problem Reframing(プロブレム・リフレーミング)」や「振り子の思想」などの延長線上に位置づけます。結果として見えてきた建築分野での新しい可能性や、takramが「越境し、試行錯誤を続ける」ことで今後どのように展開していくか、伺いました。
多様性
田川欣哉──takramは、さまざまなタイプの人たちが集まることで形成される多様性のなかでものをつくっていきたいと考えています。現在の社名には「design engineering」が入っていますが、将来的にはデザイン/エンジニアリングを包含する更に多様な輪郭を目指していくだろう、という実感があります。カズ米田──建築家の私やデザインエンジニアの緒方壽人さんがtakramに参加したことで変化したことはありますか。
田川──ええ、変化は大きいですね。ベン図でいえば、たとえば私と緒方君は重複する部分が多いですが、カズや渡邉君はそれほど重複していません。さらにまた別の領域を押し広げるメンバー々も入ってくるでしょう。それぞれの持つ領域の外縁が、takramの外縁をオーガニックに形成していきます。
カズ──アメーバ的ですね。
田川──デザインの現場によくあるパターンとして、スター・デザイナーとその下に複数のアシスタントが並ぶ、という鍋蓋型の組織が挙げられます。それはそれの良さがありますが、takramは外縁が自然に広がっていく方法を考えています。
カズ──私は大学までずっとアメリカで生まれ育ったのですが、大学の建築学科を卒業後に日本へ来て、藤本壮介建築設計事務所で設計の仕事をしていました。しかし建築だけでなく、より広い領域や別のデザインの現場も体験するため、アメリカへ戻るまで藤本事務所に籍を置きながら、別の活動の場を探すことにしました。そこで以前から《furin》(2008)や「Water」展(《furumai》2010)を見て面白いと思っていたtakramに履歴書とポートフォリオを送りました。1カ月後連絡がきて面接を受け、建築の仕事はないけれど一緒にやってみよう、ということで参加する運びとなりました。最初にご一緒したのは、親指入力キーボード《tagtype》(2004)をMoMAのパーマネントコレクションとして登録するためのプロジェクトです。

-
《tagtype》
Photographs by Yukio Shimizu
© 2004 takram design engineering
田川──カズがMoMAとの複雑なやり取りをこなしてくれて、最終的にはパーマネントコレクションとして、めでたく選定されました。これは山中俊治さんや本間淳さんなど、プロジェクトに関わった方々にもいい知らせになりました。
カズ──そのあとアメリカへ戻ってハーバード大学大学院へ進学しました。じつを言うと卒業後はニューヨークの建築計事務所に入る予定だったので、日本に帰るつもりはなかったのですが、伊東豊雄さんと一緒に、東京で海外留学生に向けた1セメスターの授業を立ち上げるため再び来日することになりました。同時期にコラボレーターとして取り組んでいたtakramのプロジェクト《Shenu》(2012)がその年の6月にドイツ「ドクメンタ」で発表され、その後の私の進路とtakramの活動が空間へ広がっていく時期が重なり、正式に参加することになりました。 ちょうどその時、takramの事務所を引っ越す計画もあったので、事務所設計を私の処女作とする計画が立ち上がりました。欣哉さん、渡邉さんと、外部からは高塚章夫さん(aaat 高塚章夫設計事務所)という建築家の方を交えたデザインプロセスを経て、2013年の11月に引っ越しをしました。それがtakramの建築、空間系分野の始まりです。したがって、建築分野はtakramのなかで最も若いインハウス・ベンチャーだと言えます。
「Problem Reframing」、境界線の越境と超越
田川──外から入ってくる仕事はテーマが決められています。自分たちが考えるフレームや輪郭は、基本的にはテーマによって仕切られていて、無意識的にその境界線のなかで考えてしまうことがあります。国語の試験問題で「これは何を意味していますか」という質問があった時に、解答で「質問が間違っています」「そもそもこういう質問であるべきだ」ということを書けば採点不能で点が付きませんよね。それは、仕方のないことでもあります。「解答」は「問い」の質と解像度に大きく制約を受けるという考え方がありますが、クライアント・ワークをしていると、テーマやアジェンダ等を徹底的に考えて、この「問い」しかないというレベルまで純化して依頼してくる人はそれほど多くないように思います。その「問い」を鵜呑みにしてしまうと、「問い」には答えているけれど実行してみたらあまり上手くいかなかった、ということが起きてしまいます。「問い」は、絶対的で動かせないものではありません。逆に動かしたほうがよい。
「問い」に対する「解答」を考える時のエネルギーを、「問い」に対しても注ぐべきかもしれないと思い至ったのが《Shenu》というプロジェクトでした。
「問い」と「解答」を振り子のように行き来させ、「解答」に行きづまるようであれば、そもそも「問い」に間違いがあるのではないか、と疑問視してみます。そうすると「問い」を進歩させることによって得られるであろう「解答」、答えるべき「解答」によりふさわしい「問い」、という「問い」と「解答」の両方で試行錯誤が起きます。こうして、所与の条件として引かれていた思考の境界線も動かせるということに気がつきます。これが「Problem Reframing(プロブレム・リフレーミング)」の考え方です。
カズ──そこに「メタシフト(Meta Shift、超越)」と「トランスシフト(Trans Shift、越境)」はどのように関わってくるのでしょうか。
田川──「Problem Reframing」は「問題を再定義する」ということなので、非常に広い意味を表す言葉です。われわれが生きている活動地平があり、そこに入ってくるさまざまな問題をイメージしてください。その地平の上に超越平面があり、超越平面から見下ろすと問題が地平で見えていた場所とは別の場所にあることがあります。視点を活動地平から超越平面へと垂直方向に動かしてみること、これが「メタシフト」です。
もうひとつは、境界線自体を同じ地平上で水平に動かすこと。「トランスシフト」と呼んでいますが、普通はなかなかできないことが多いですね。たとえば、デザイン部門の輪郭を少しずらして、エンジニアリング部門にまで触れていくといったことです。これは超越視点ではなく、近傍に対して輪郭を押し広げていくというイメージです。
「メタシフト」と「トランスシフト」は対象を見る解像度が異なります。メタ視点では俯瞰で見る代わりにディテールは見えなくなりますが、トランス視点では高い解像度で話が進みます。
こうした論理が必要とされる背景には、物事が細分化されすぎている現状もあります。産業革命以降、産業の細分化・分業による効率化が進み、方法が確立されるやスピードもコストも大幅に下がりました。
私が東大工学部機械科で教わった「問題は因数分解が可能である」というドグマはとても象徴的です。大問題は小問題に分解可能で、小問題はさらに小さな小問題に分解可能ということなのですが、これが機械工学の基本的な考え方で、これ以上分解できないところまで問題を分解した後で、それを設計に転写します。体内の細胞と器官の関係のように、細かな問題が統合されることで大きなシステムができるというような、まさに機械論的なアプローチでした。考えてみれば昔の機械はどれも小さな部品に分解できましたから、このテーゼが成立していたのだと思います。
しかしその方法で進みすぎてしまったために、本当はもやもやした状態で考えなければいけない、インテグレーション(Intergration:部分を有機的に統合すること)が必要になるような複雑なプロダクトや、サービスを考えることが難しくなっています。にもかかわらず、現在の企業は基本的には細分化・分業の構造で構成されています。あらゆる物は分解可能で、分解を重ねてソリューションを組成するという考え方です。つまり企業構造は出来上がった物事を運用するにはとても向いているが、新しい物事を生み出すには、それほど向いていない構造である、という見立てをしています。ベンチャーや創業者のいる企業などでイノベーションが起こりやすいことも、このような見方をすると腑に落ちる部分が多くあります。
カズ──よく言われるもうひとつのドグマが「形態は機能に従う(Form Follows Function)」です。アメリカの建築家ルイス・サリヴァンの、19世紀末の言葉です。しかしいまではソフトウェアのような形態の無いなものが登場し、事態にあてはまらなくなりました。因数分解、部品分解が不可能な時代なのです。
田川──そうですね。さらにもうひとつ、細分化された先にある、テクノロジーによる手段・方法が洗練されてきているということもあります。たとえば「音楽を再生する」行為のなかに、コンピュータで好きな曲だけをランダムに再生するCGM(Consumer Generated Media、消費者生成メディア)など、消費者のモチベーションを掘り起こす手段・方法がありますよね。いまやさまざまな手段・方法があり、選択肢が昔に比べるととても増えています。こうしたことがリフレームが効果を発揮する理由になっています。以前はリフレームしても能力的に特定の専門家にしかできないという壁がありましたが、現在ではそれが誰にでもできてしまう状況が、ネットやソフトウェアの力で実現されつつあります。
カズ──その意味でも《Shenu》は最も面白い例だと思います。さまざまな矛盾に直面した際に、そもそもの「問い」と「解答」の内容と質を変更しないとイノベーションに到達しえないということがよくわかるプロジェクトでした。お題として投げられたテーマは「100年後の水がない荒廃した世界のための水筒をデザインせよ」というものでしたが、そもそも水がないのになぜ水筒が必要になるのかなど、いくつもの矛盾が含まれていました。100年後の世界の水量を測ってみたところ、人口がたとえ現在の1割になっていたとしても、総人口を生存させるための一日あたりの水分供給量や水道設備を整備するのは困難であるということが見えてきました。つまり世界は干涸び、人間のエコシステムや身体能力をはるかに向上させない限りは、1日2リットルの水分を補給するのは不可能だということです。
そこで水というのは人間の体に対して一体どういう意味を持つのだろう、というシフトが起きました。身体における水の循環を効率よく、再生可能にすれば、よりサステイナブルな水との関わり方がつくりえるのではないかと考えたのです。そしてその先で、身体の水分はどこから入り出ていくのかという身体的、物理学的な話に繋がっていきました。

-
《Shenu: Hydrolemic System》
Photographs by Naohiro Tsukada
Video by takram design engineering
© 2012 takram design engineering
当然そのほかのプロジェクトでも部分的にリフレームは起こっていたと思いますが、作品の基本のコンセプト自体を動かすような大胆なリフレームは《Shenu》に代表されるでしょう。
《Shenu》はテーマ設定からの飛躍を「ドクメンタ」から求められました。われわれが優等生的に水筒をつくることで解答を出すことも可能でしたが、それに対し、展覧会のディレクションを務めた韓国人アーティストのムン・ギョンウォンとチョン・ジュンホがわれわれに対して「もっと何かないか」という注文をずっと言い続けてくれたおかげで、リフレームが起こったのだと思いますが、いまはクライアント・ワークの場合にも、takramからリフレームを提供できる状況になってきています。
takramの建築/アーキテクチャ
カズ──建築の勉強を始めた頃、レオナルド・ダ・ヴィンチなどが「ルネサンス・マン」呼ばれていたことを知りました。絵画、彫刻、都市計画、武器、そしてもちろん建築といったさまざまな芸術や街、具体的でフィジカルな世界をつくることができる人を総称して「ルネサンス・マン」や「アーキテクト」と呼んでいたのです。その言葉は現在の日本の「建築士」ではなく、思想家や考える人という意味合いに近かったのだと思うのです。ただ実際に実務に携わると、世界は複雑にできているので、自分がすべきことを特化したほうがわかりやすいという状況が見えてきました。建築というものは、建築家が自身の考えを「建物」に反映する、とてもわかりやすい関係で成立していますが、私はやはり幼い頃に思い描いていたように、ただ建物を建てるだけではなくアートもすれば本も書く、考えることを絶やさない存在でいたい、と思っています。
一方でそれは人に説明するのがとても難しい。建築家だというと、クライアントから「建物をつくりたい」というストレートな前提をいただくわけです。takramで担当した《Shenu》や有機ELを扱った《Habataki》(2013)といった仕事は、建築事務所にいたら関わるチャンスはないとは言えないですが、可能性は低かったでしょう。
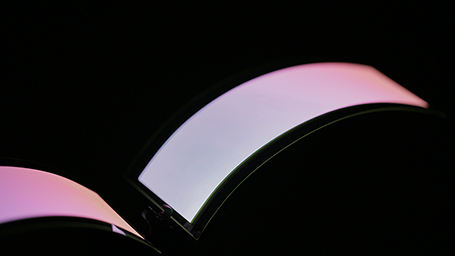
-
《Habataki - Light, Leap to the Future》
with Konica Minolta
© 2013 takram design engineering
建築は最大のUI(ユーザー・インターフェイス)/UX(ユーザー・エクスペリエンス)であると言われます。つまり床や壁、天井、照明などが、生活者と何らかの関係を持つということですが、この概念をどのようにして空間ないし都市空間に落とし込んでいけるのかを模索すること、また同時に、多くの思想から刺激を受けるこのが可能なtakramという組織環境のなかで新しい建築のあり方を模索していくことがこれからの私の課題です。そしてアーキテクトとしての職域を「建物」をつくることに限定せず、文化を創造することと捉えていきたいと考えています。そして社会の在り方を示すものとして、世界に発信していきたい。
欣哉さんは、takramにおける建築をどのような位置づけとして育てたいと思っていますか。
田川──基本的には「takramにおける建築」は「takramにおけるソフトウェア、ハードウェア、プロダクトデザイン」と同じ話です。つまり、takramでは建築を特殊な分野として考えないようにしたいと思っています。以前、同年代の建築家とよく話をしたのですが、彼らには建築が絶対的なものだという信念があることを感じました。しかし絶対性に酔うということは、建築のすばらしさを意味すると同時に、分野としての脆弱さも示していると私は思っています。たとえば、Skypeのようなサービスで遠隔地同士を繋ぐと、空間に擬似的なトンネルができます。このトンネルが空間ではないのかというと、そうとは言えないだろうと考えています。そういうことがこれから先にたくさん起こるだろうと思います。それゆえ、自分たちがつくらなければいけないものをつくりあげていく媒介のひとつとして建築を位置づけたいと思っています。これはデザインを重要と思い、エンジニアリングを重要と思うことと同じです。takramの持っている相対化能力やリフレーム能力を活かして独自の建築観を提示できるかもしれない。そんな夢を持っています。
カズ──建築を相対化するプロセスを経てtakramの建築観を確立するということですね。
田川──最も望ましいのは、建築という分野を愛しながら相対化することです。なぜならわれわれが取り組む問題が極めて複雑で多様だからです。空間へのアプローチにおいても、分野を相対化して振り子を振りながら問題に挑むことがtakramらしいやり方だと考えています。
カズ──takram事務所を設計した時は、グラフィックデザイナーや照明デザイナーと共働したり、家具もコクヨと一緒につくりしました。捉えようによっては総合プロデューサーみたいなものですね。
田川──建築は総合芸術ですよね。takramという組織環境はじつに多様なのでさまざまな可能性があります。
カズ──必要とされているのは、建築だけに頼った解決策ではなく、もっと大きな世界観の体現として建築を含めた解答を導くことです。たとえば、コニカミノルタ社と共同した《Cradle of Light》(2014)は「建築×演出」「建築×プロダクト」「建築×照明」だったように、さまざまなもののなかに建築もキー・プレイヤーとして入った状態が面白いのだと思っています。

-
《Cradle of Light》
with Konica Minolta
2014 takram design engineering
理論と実践をシームレスにつなげる
カズ──私は、理論と実践を分けてはいけないと考えます。双眼的でありたい。takramが育む理論フレームに「Prototyping(プロトタイピング)」や「Problem Reframing」などという言葉がありますが、いずれにも"ing"がつきます。"ing"は、行動をしてこそ結果を得るという意味を内包しており、理論とともにある実践がデザインに繋がっていくのだと私は思っています。私にとって、"ing"というコンセプトはとても大事なものです。アメリカではTheory(理論)とPractice(実践)の違いについてよく述べられますが、本当に良いデザインは、その部分がシームレスでなくてはならないと思うのです。欣哉さんはどのようにお考えですか。
田川──理論とは「一般化」ということだと思います。理論と実践というのは、サイエンスでは理論と実験ですね。目の前で起こっている現象とそれを説明するに足る数式とを突き合わせながら、完全に一致するまで、実験器具を改修していく場合もありますし、理論面を改修していく場合もあります。研究において、理論だけの論文は存在しないし、実験だけの論文も存在しません。理論と実践・実験というのは、基本的には互いが裏表になるものであって、双方を磨いていくことで初めて高みにいけます。
カズ──takramにおける「Prototyping」は一般的に「プロトタイプ」と呼ばれているものとどう違うのか、そして建築に「Prototyping」があるとしたらどのようなものものだとお考えですか。
田川──プロジェクトの初期に行なうプロトタイピングは、アメリカのデザイン・ファームIDEOが「Quick and Dirty Prototyping」という考え方を示して以来知られるようなりました。一般的なプロトタイピングは抽象設計を具体化する際に行なうもので、イメージが具体的に成立するか、つまりフィージビリティを確かめるための試作です。しかし、プロジェクトの初期に行うプロトタイピングは抽象思考のためのものです。試作品としてのプロトタイプ自体を問題にしているのではなく、それを超えたレベルでの様々な気付きや発見、そして議論を巻き起こすものでなければ意味がないと思っています。
大きな企業には試作部という部署があり、図面を受けて試作をしています。しかし試作するうえで気づいた疑問点があっても企画に戻したりできない構造――企画→設計→製造というウォーターフォール型の構造――になっている。私は「抽象は具体にそのまま転写可能である」という考え方に違和感を持っていますが、「Prototyping」はそれを打破するための思考フレームです。その語源からしても「Proto(原型になる前の、前型の)」Typeですから、本来はプリ・プロダクションではないはずです。しかし、一般的なプロトタイプの多くがプリ・プロダクションやプロダクション・アセスメントであり、コンセプト面を鍛え上げるための「Prototyping」はあまり行なわれていないように思えます。
建築は古くからスケッチを描き、模型をつくってきましたよね。スケッチ、エスキスと模型が思考ツールになっているという意味では、「Prototyping」と本質は同じだと思います。なぜなら、建築は実物をプロトタイプすることができないので、事前にあらゆる問題を整理しておく必要があるからです。ただし、それゆえにtakramのリアルなスケールとマテリアルによる「Prototyping」とは異なります。スチレンボードでできたプロトタイプと、ワーキングプロトタイプは体験の品質が大きく異なります。建築では、模型と実物の建築はあらゆる意味で異なるわけで、その間を精密に埋められるところに非常に大きなエクスパティーズがあると思います。
カズ──特に日本はスチレンボードで模型をつくらないと検証できないとされているようなところがありますが、乱暴に言えば、それは前時代的だと思います。いまはコンピュータのなかでモデリングし、その場で「この柱をもっと長くしよう」といった変更がすぐにできるので、模型に頼らなくてもよくなりました。デジタル空間内で本当に検証できるのか、という問題は挙げられますが、それはセンスによるでしょう。スチレンボードで模型をつくることとコンピュータのなかでモデリングすることは、私にはそれほどの違いはありません。
もうひとつ、私は「Prototyping」とは、主流になる前の実験的なアイデアを実体化するメソッドです。これは、新しい社会を作り上げていく方法論のベースになるようなものだと思っています。すでにネットやソフトウェアの世界では、プロトタイプをそのまま世に問いかけてしまうという方法が一般化しています。takramという組織環境でこそ可能な「Prototyping」建築ができれば、それは次の世代に大きな影響を与えることになるのではと考えています。
社会のあり方と向き合うデザイン
田川──建築は作家性が作品を保証するという側面もありますから、自らの作家性を克服するのは難しいですね。ですから、自身の建築的手法、アプローチのなかに、自身の作家性さえも相対化してしまえるような装置を持っておくことは一つの見識だと思います。takramの「Prototype」の面白いところは、仮説ベースで、なおかつ最初の仮説は結果的に半分ぐらい間違っていても試していくというところです。「Prototype」はいわば、あるものをポンと投げ、そこから返ってくる音で周囲の状況認識するようなソナーのような役割を果たします。
作家性も、そういった手探り状態における強い指針になります。作家性は外部に依拠しないので、五里霧中であっても自律的に進んでいくことができます。作家性こそが貫通力である場合には作家性で勝負すべきだと思っています。逆に作家性が結果を生まない場面も多分にあります。そういった時に「Prototyping」を用いて自らの作家性から離脱し、別次元に遷移していく。そういうことを、takramのデザイン・エンジニアたちはやっています。
最初にゴールはわかりませんし、スタートしてからも経路は随時変化します。しかし、精度はプロジェクトの後半、終盤になるにつれて加速度的に上がっていきます。takramでの建築の課題はそのようなプロセスをいかに自覚的に取り入れていくかだと考えています。takramの建築家達は新しい手法を用いて、作家性の強い建築家とはまったく違うプロセスでクリエイションに入っていくかもしれません。そのような状況を見てみたいと思っています。
カズ──いま建築は、モダニズムのような大きなひとつの潮流に収束することのない、混迷期に入っています。大きく言えば、混迷を抜け出すべく新しい時代を築く潮流を生み出したいと考える人たちと、多様なままでよいと考える人たちに分かれています。いずれの立場もありうると思いますが、最も大事なのは、建築が社会にどう利するのか、どういったインパクトを与えることができるかを考えることです。しかしいまの建築がその役割を果たしているか、私は心許なく感じます。
社会づくりに関するものには、建築もあればUI(ユーザーインターフェース)も、プロダクトもあります。「空間」があるのと同様に、社会や私たちの周りには「時空」があって、それに対してどのような理論が必要で、どのようなデザインを提示できるのか、実践を積み重ねていくことが大事です。仕事をしながら考え、考えながら仕事をすることで、デザイン、ひいては新しい社会空間や環境空間を見出さなくてはなりません。たとえば街をトータルでデザインする、家や車、インフラシステム等全てをデザインする仕組みを考えられる多様性を体現する集団でありたいと考えています。
2013年12月5日、takram表参道オフィスにて
田川 欣哉(たがわ・きんや)
takram design engineering ディレクター/デサインエンジニア 1999年東京大学工学部卒業。01年英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修士課程修了。デザインエンジニアリングという新しい手法で、ソフトウェアからハードウェアまで幅広い製品のデザインと設計を手掛ける。07年Microsoft Innovation Award 最優秀賞、独red dot award: product design 2009など受賞多数。
カズ米田(かず・よねだ)
takram design engineering アソシエイトディレクター/アーキテクト。建築と都市デザインを専門とし、takramでは《Shenu》《takram Omotesando》《Chicago Laboratory》を手がける。新たな建築セオリーをはじめ、より革新的な文化創造に興味を持っている。シアトル市生まれシリコンバレー育ち。コーネル大学B.Arch修得ハーバードGSD大学院M.Arch2修士課程修了。終了後2011年、建築家伊藤豊雄氏率いる同大学院東京スタジオにてTeaching Associateに着任。2013年、東京大学工学部建築学科で学部生に設計課題を指導するUnit Master(非常勤講師に相当)に着任。




