ユーザー・ジェネレイテッド・シティ
──Fab、GIS、Processing、そして未来の都市
──Fab、GIS、Processing、そして未来の都市
21世紀、建築・都市の2つの大きなムーブメント

- 左から、太田浩史氏、古橋大地氏、田中浩也氏
太田──では鼎談に移っていきましょう。21世紀の最初の15年の文化状況を見たときに、なによりもユーザー参加型のコンテンツが増え、かつ、それがサブカルチャーとして大きな影響力と実験性を持った点ではないかと思うんですね。それが、都市・建築分野でも確実に現われていたと思っていまして、そのひとつの代表が田中さんがFabLabでやられているような手法を使った「Make」的なムーブメントであり、もうひとつが古橋さんがされてきたOSMや、オープンデータのような都市スケールのムーブメントであった。これらがどういう意味を持つのか、またこの2つはどのようなスケールで出会うのかということが、「ユーザー・ジェネレイテッド・シティ」を考える際のテーマになってくると考えました。
都市再生の研究をやるようになって、僕も日本のいろいろな都市に行きましたが、状況はここ数年で圧倒的に変わりました。どの街にもあたりまえのようにまちづくりの拠点があって、そこで若い人たちが起業スクールをやったり、リノベーションでまちづくりを行なったりしている。そのこと自体は非常に歓迎すべき状況です。しかしその一方で、駅前再開発を中心市街地活性化法で行おう、または相変わらず郊外都市の開発を行おうというような流れがあり、それらは職能として明らかに分かれている。リノベーションまちづくりを担う建築家たちは都市全体の政策からは外れていて、都市空間のデザイン自体は都市コンサルや組織事務所の仕事として、手の届かないところにある。そこをどうやってブリッジするかということを、この10年間考えてきたわけです。

- fig.26──日本建築学会編
『コンパクト建築設計資料集成 都市再生』
(丸善出版、2014)
古橋──マップではなくGISなんですね。
太田──念頭においているのは三次元情報なので、GISと言うほうが適切な気がします。
田中──FabLabが実践している「Make」については、これまでは一人ひとりがパーソナルなものをつくることがほとんどでしたが、いまでは違うフェーズに来ています。従来のいわゆるものづくりという段階から、それぞれ専門の異なる5、6人──GISが使える人、センサーの専門家、ドローンを操作できる人、等々──のスモールチームが協同して都市生活のなかで使うものをつくるというフェーズに来ている。ひとりの作家やアーティストでもなく、大企業でもできない、スモールチームこその創造性が発揮される領域がある。ファブシティで目指しているのはそういう方向性です。
しかし、ローカルバスのバス停をつくろうとか、放置自転車を再利用しようとか、どちらかというと目に見えやすい「もの」の問題に飛びつきやすいという弱点はたしかにありますね。
地図を広げて、「どこ」に「なに」をつくるのかということから考えていけないだろうか。都市的な想像力を広げながら、街のためのものづくりのようなことができないだろうかと思っているんですね。そうした都市生活のパブリックなものづくりをやっていくためには、「Make」とGISの両方が必要になってくるわけですね。
太田──昔、渋谷のハチ公を駅前広場の拡張工事に伴って移動させるときに、人の流れのパターンを調べてどこに置いたら流れを妨げないかを調査して決めたと聞いたことがあります。パブリックスペースのデザインは、建物の外形線や道路中心線だけではなくて、人の動きや広告物レイアウトなどの空間情報をふまえながら、それを再編成していくことができる。そういう意味でも、僕がOSMで一番あったらいいなと思ったのは、建物の出入り口データですね。
古橋──エントランス情報は、海外では結構集まっていますね。国内でも、その建物にどう入っていけるかという地図情報をGISとして整備し始めているところです。
太田──それは素晴らしいですね。建築側から言うと、どこに出入り口をつくったらお客さんが来やすいかというデータになりますし、災害時には避難情報にもなります。また、建物を通り抜けるときに、現行のGISだと建物の中に入るとわからなくなってしまう。そういう意味では、出入り口の情報は建築とアーバンデザインをつなぐデータになりうると期待できます。
ファブリケーションとGISがシビックプライドを育む

- 田中浩也氏
FabLabもこれと同型の問題を抱えています。Fabに多様性を生み出すエンジンのようなものを埋め込まないと、世界中どこのFabLabに行っても同じようなものしかできないのです。3Dプリンタやレーザーカッターでどこでもつくることができる似たようなものが溢れて、フランチャイズの「コンビニ」化してしまったら、僕にとってそれは悪夢に近い出来事です。世界中の人たちがシェアできるグローバルなインフラやオープンデータはもちろん必要ですが、しかし他方で、ローカルな独自性を見つけ出して、その土地ならではの活動に根を降ろす部分が必要です。そのための戦略として、素材やマテリアルを強調して、そこでローカリティを発見していくやり方を実践しています。ただ、それとは別にGISと絡めるやり方もあるはずで、その土地の人々の活動のスタイルや生活時間が見えてくるような方向性を打ち出せれば、もう少し別の可能性が開けてくるように感じ始めました。
古橋──地図をつくっているといろいろな地域を訪れるわけですが、どの土地でも自分たちが住んでいる場所に対する地域愛がありますよね。昨日も大阪でワークショップをしたのですが、とりわけ大阪の人は「大阪、大好き」という傾向が顕著で、最後はウクレレショーが始まって、「オー・シャンゼリゼ」を「オー・御堂筋」ともじって歌っていたり(笑)。そうした地域への思いは、大阪に限らずどの地域にもあります。ただし、地域愛を言いたいのだけれど、日本人特有の恥じらいから大声で言えないというときに、モノに仮託して表現するということがありうるのではないか。さらに言えば、そうしたモノのなかにGISのデータが入り込んでいくということも十分あるのではないかと思っています。
太田──そうですね。プレゼンテーションで主観情報と客観情報という説明をされていましたが、LocalWikiのような主観情報は今後増えていくのでしょうか?
古橋──期待しています。僕たちがつくったLocalWikiのキャッチコピーに「編集しているうちにその街を好きになる」という言葉があるんですね。「この街に住んでいるから」などの漠然とした理由からマッピングを始めて、やっているうちにいろいろな発見があって、街を知れば知るほど好きになっていくわけです。一度LocalWikiに参加すると、ハマる人が多いのも頷けます。
太田──シビックプライドのきっかけとしてのWikiなのですね。個人情報に属するような情報もアップロードできるんですか?
古橋──それは個々人の判断でできます。少なくともWikipediaのような厳しさはありません。現在のようにフェイスブックやSNSでネットワーク化されていると、同窓会のように過去の話で盛り上がることがあります。僕もプライベートな仲間内で「あの公園の、あのベンチでこんなことがあった」という過去の恋愛話を耳にして、OSMの地図上でベンチを書き加えたことがあります(笑)。文脈がわからなければただのベンチですが、ストーリーを知っている者が見ると「ああ、あのベンチか」となるわけです。
田中──私もノマド気質があって、いろいろな地域を移動します。そのなかで気づいたのが「トランスローカル」の可能性でした。ある日、東京でセンサー技術やロボット技術の使い道について考える会議があり、それが終わったあと次のミーティングが静岡であって、これからの地域の課題として農業の人材をどうやって確保すればいいかという話になりました。そのときに、だったら2つをくっつければ同時に解けるんじゃないか?と自然に思ったわけです。概して、都市部では技術はあるけれど「ニーズがない」という話が多く、地方ではニーズはあるけれど解決するのに「テクノロジーを使おう」という発想がない場合が多い。また、シーズの話をするときは技術者が多く、まちのニーズの話をするときは行政の関係者が多いのですが、そこでは全く会話の言語が違います。しかしそこにこそ可能性を感じるんですね。
いま「地方創生」は「地方」という単位が強調されすぎているきらいがある。すぐ「うちの地域は」と言ってしまうことには疑問を感じています。むしろ、ひとつの地域だけで完結するソリューションではなくて、ほかの地域と補完的に組み合わせて問題を解決していくような取り組みが必要であると思うのです。外部との交流がないと新しい風は吹かないので。 姉妹都市ってあるじゃないですか。あれを最初に考えた人はなかなか鋭いと思うんですね。あの発想のまま、単位を細かくして、ある地域とある地域を「姉妹地域化」し、技術とニーズをうまく再編成させることで価値を生み出し、Win-Winの関係を築くことができるのではないか。いま、私は総務省の有識者会議でそういう提案をしてみています。
古橋──そのときに「たまたま名前が近かった」など、ある種どうでもいい理由づけがあると、なおいいですね。以前、東大で「ISAC Tokyo」という宇宙に関するイベントをやったときに、僕が一番印象に残ったのは、地球というのは北半球と南半球とを磁力線が結ぶかたちになっていますが、ちょうど日本から延びる磁力線の先にオーストラリアがあると。そうなると、「あなたと私は磁力線でつながっています」といって、無理やりにでもつなげることができる。そういう、人と人とが偶々につながる接点をどうやってつくっていくかが問われてくるんじゃないでしょうか。
田中──どこか情報化社会におけるつながりの形成に似ていますよね。情報技術によって既存のスタイルとは違ったつながりができるわけですから。
太田──そういうランダムなつながり方がある一方で、大きな災害が起こったときに、シンパシーによって遠く離れた場所がつながるということもありますね。2010年のハイチ沖地震のときには、みんなでOSM上で被災地の地図をつくるということが起こりました。フィリピンのFabLabプロジェクトについても、同じように大きな可能性を感じました。
ゲリラ戦から持続可能性を考えていくフェーズへ

- 太田浩史氏
古橋──そうですね。自分たちの手で自分たちの街をよくしていこうという試みは、僕の仲間でも「Code for Japan」というチームが一生懸命やっていて、個人的にも応援しているのですが、同時に難しいなと感じるのは、サステイナブルなものとしてその活動を続けていくときに、支援の仕方をどうするかということです。いまはみんな盛り上がっているのでベースクロックが高いというか、やれば反応もあるのだけれど、それをどこまで維持できるかというところのインセンティブがまだまだ弱い。ひと昔前であれば寄付や募金のような金銭的なかたちでの支援が主だったのが、いまでは「お金は出せないけれど地図はつくれます」「モノはつくれます」というかたちで選択肢は増えている。しかし、そこがうまくつながっていない。出資の仕方にしても、最近はビットコインなどのように、ウェブを経由していろいろなお金のやりとりが可能になったので、お金そのものの回しやすさもベースクロックが速くなっていると感じます。どこかでそのタイミングが来るだろうかと思いますね。
田中──そこは課題ですね。FabLabも多くは大学が支えてなんとか回っているというのが現状です。しかし、FabLabも大学との関係だけでは回していけないくらいの数になっているし、大学が支え続けるというモデルも一見理想的なようでいて問題もあるので、もう少し20世紀型のデヴェロッパーを巻き込んでいく仕組みを考えないといけないとは思います。ゲリラ戦のフェーズから、持続可能性を考えていくフェーズなのです。
古橋──ひと昔前、例えば私たちの親の世代であれば、国家というのはぶつかる対象だったのが、僕たちは国土地理院ともうまく手を結んでやっているところがあります。国とも地方自治体ともある面では手を結びながら、ある面では勝手にやっているところもある。いまの距離感は、自分にとってちょうどいい感じです。
田中──ITの場合はうまくいくケースが多いんです。建築などの物理空間になると規制や利害の網に縛られて、なかなか難しいことも多いような気もしますが。
太田──結局、現実的には合意形成というのが一番厄介なんですよ。例えば街に出て、街のサインのペンキが剥がれているところを見つけたとしても、勝手に塗ったら怒られるわけでしょうですから、ある程度までは住民に委ねるというレイヤー、「自己修復」できるレイヤーが現われてくるといいと思うんですね。歩道の砕けた縁石は自分たちで直そうとか。
田中──そうそう、3Dプリンタで自分の家の前の道路のデコボコを自分で直すと、その道路に自分の名前がつけられる、という提案が2014年の「ファブシティーコンソーシアム」(http://fabcity.sfc.keio.ac.jp/)のなかでありました[fig.27]。そういうことにFabLabの技術は役立つはずです。
道路に空いた穴を埋める際にセンサーを組み込んでを補修すると、サービスの普及に伴って複数のセンサーが人や車の位置情報を感知し、ほかの情報や情報技術と組み合わさることによってさまざまな危険性を排除してくれる未来を映像化。道にある穴やくぼみを3Dプリンターで同じ形にプリントして塞ぐというシナリオ。
太田──明治以前には橋を住民たちが架けたり、運河を街の有力者が整備したりしていたわけですね。いまのFabLabであれば、橋くらいはつくれるわけでしょう?
田中──基本的には専門家が揃えばなんでもできますね。
太田──合意形成さえできれば、技術的には可能なわけですよね。
田中──さきほども言いましたが、自分の直した道や橋に自分の名前が付けられたりすると、もっとインセンティブが複合的なものになっていくと思うんです。IT的な新しい自尊心と言いますか、自分が世界に関わった痕跡がデータで残っていくというような新たな魅力をつくるということかもしれません。FabLabは「もの」をつくっていますが、これまでの「ものづくり」とは、価値の現れ方が決定的に違うのです。それは機能ではなくて、コミットメントやエンゲージメントなのです。単に「橋」をつくるというより、「橋」をめぐってどれだけの才能やコンテンツを結集できるかが大切になると思います。
21世紀の新しいデザインを都市のリポジトリでつくること

- 古橋大地氏
田中──電気自動車はFabにとっても本命ですね。昨年もFabとソーシャル・モビリティを考える「ハイパーネットワーク別府湾会議」が大分で開かれました(http://www.hyper.or.jp/bbc2015/)。
古橋──10年後にはFabでつくられた車が走っている世の中が実現していると思いますか?
田中──十分ありうるでしょうね。そこで言われるFabは、いまのFabLabとは違うかたちで、もっと金属関係が扱える工房に進化しなければならないのですが(それをMetal Fabと呼んでいます)。実際「OSVehicle(オープンソース・ヴィークル)」(https://www.osvehicle.com/)のTin Hang Liuとは去年かなり議論をしました。 具体的には、鎌倉のように道が狭く高齢者が多い地域では、時速40kmくらいまでしか出ない車が走っていたり、あぜ道が多い農村地域ではタイヤが丈夫な車が走っていたり、地域の特性に合わせた多様な車が全国で出てくるようになればいいと思います。電気自動車であれば、タイヤ、バッテリー、モーター、シャーシというフレームの部分と、デザインの部分との二層に分けたうえで、後者のほうは地域なりユーザーなりに委ねるということになるかもしれないでしょうね。
古橋──日本の都市に限って言えば、今後は車を排除するような流れになりそうな気もするのですが、それについてはどうお考えですか?
太田──自動車を排除する流れは世界的なもので、むしろ日本はまだ緩いです。
古橋──そのときにモビリティとしては自転車が主流になるのですか? それとも路面電車のようなものが普及する?
太田──政策的には路面電車を、と思っている人が多いでしょうね。自転車社会は働きかけはされているけれど、いざ運用するとなると事故が起きたり、自転車専用道を整備するためのコストの問題もあったりして、難しい面も多いと聞きます。特に東京は坂道が多いので、そうした地形的特性も影響しているかもしれません。 東京に関しては車の保有率も低いので問題ないでしょうが、地方都市では車をどうマネージしていくかについて、カーシェアリングにしてもUberのようなシステムにしても、これからもっと考えていく必要がある。バスの運行なども、いまはオンデマンドで予約できるバスが注目されていて、実際に運用されている地域もあります。
古橋──僕たちは地図をつくるときに、車なり自転車なり徒歩なり、なんらかの手段で移動をするわけです。ボトムアップ的に街を知るうえで、車も自転車も人も、マップをつくるためのデバイスとして考えてみたい。将来的にそれはドローンやロボットに取って代わられるのかもしれませんが、いずれにせよなにかが街を巡回していくような仕組みまで辿り着きたい。そういう意味でも、去年トヨタがOSMを使い始めたというのは非常にいいニュースです。
田中──逆に自動車がスキャンしてデータを取ってくるということも起こりうるでしょうね。
太田──それは自動運転とて実に興味深い点ですよね。2年前、アップルが3Dカメラの技術開発会社のPrimeSenseを買収しました。ポイントクラウド処理をアップルも始めたということですが、MicrosoftのKinect、インテルのRealSense、それを用いたGoogleのProject Tangoなど、ポイントクラウドまわりの技術開発は非常に活気づいています。これはどういうことかというと、深度センサーがが車載カメラなどに搭載されて、進路が安全かどうかをリアルタイムでセンシングしながら車が走ることになる。その時、周辺の建物情報も一緒にスキャンされている訳ですから、マッピングも同時になされる、ということですよね。その先には、当然スマートフォンにポイントクラウドのセンサーが載る状況も見えてきます。街で人がポイントクラウドのデータを取りながら歩くようになるんじゃないでしょうか。ポイントクラウドのブロードキャスティングだって実現するかもしれない。例えばサッカー中継であれば、いまはピクセル情報で送っているようなものですが、ポイントクラウドのデータであれば、視点は事後的に決められるので、選手がドリブルする視点で試合を観ることもできる。面ではなく、点群であらゆる対象を見る量子力学的な世界観が訪れそうですね。
田中──MITを中心にした「センサブル・シティ」という、都市をセンシングしてみんなで見るというユーザー参加型の試みがあります。ただ、そういうITの世界のダイナミックな活動と、利害関係が根強く残る物理的な環境が、それぞれ独立したバラバラの二層構造にならないように、僕は中間的な領域を確保したいという気持ちが強くあります。センサーデータから物理的な都市のほうに具体的なものをフィードバックして、返していくことも大事だと思うのです。データアナリシスからデザインにつなげられないだろうか。
実はそういった問題意識を15年前くらいから持ち続けていました。OSMもそうですが、IT系の人はみんなリポジトリ化、つまりデータベースにして誰もが活用できるようにしましょうと言いますよね。しかし、データベースをつくることはこの15年くらい盛んに行なわれたわけですが、つくったデータベースが活用されているかといえば疑問があるわけです。いまはリポジトリ化されたものを使って、目に見えるかたちで21世紀の新しいデザインを具体的につくっていくことが求められていると思うんです。FabLabが描く絵のひとつとして、情報の世界と物質の世界を横断して、相互に結合する領域におけるスキルをいち早く磨き、そこにビジネスやベンチャーを立ち上げていくことというのがあります。そこは5年前と軸は変わっていません。ITとものづくりをつなぐためのデザインが求められているのです。
人類の都市とIoT(Internet of Things)

- fig.28──北河大次郎
『近代都市パリの誕生
──鉄道・メトロ時代の熱狂』
(河出書房新社、2010)
都市再生の文脈から言うと、この20年間の都市像の傾向は、ジェイン・ジェイコブズ的な、都市に「迷路」をつくろうという方向性が強くなっています。車の流入を排除して、歩いていて次になにが出てくるか予想できない都市空間という意味で、要は下北沢や渋谷のような街をつくろうということですね。現在では、そういう都市像が評価されている。ところが、その先がまだほとんど出てきていないわけですね。直観的には、スマホを使って隠れた店やイベントを探し出す一方で、逆に誰にでもアクセス可能な都市のスペクタクルが用意されているなど、見えることと見えないことの同時存在が重要になってくる、そういう都市像が出てくるのかなという気はしています。
古橋──どういう都市が自分にとって居心地がいいのかということもありますよね。ちょっと話は変わりますが、田中さんはご自分が引退されたあと、ここ(鎌倉)に住んでいると思いますか?
田中──僕は北海道の出身なので、引退後は田舎にUターンして野菜でもつくりたいとでも言えばかっこいいのでしょうが、おそらくそれは無理でしょうね。なぜ鎌倉がいいかと言うと、観光地なので外国人を含め外からいろいろな人が来る。そうなると観光客の目があるから、そこに暮らす人たちも半強制的かもしれませんが笑顔になるんです。外の目を意識することで、結果的に中からも活力が湧いてくる。それは都市生活の重要なエッセンスのひとつだという気がします。そういう意味では、外の人と内の人の混ざり方が良い場所こそが、僕にとっての「都市」の定義で、そういう場所に身を置いていたいですね。
古橋──僕は逆に田舎で暮らしたいんです。もともと陶芸をやっていたこともあり、かまどを持ちたいのですが、渋谷で持てればそれはそれでいいのかもしれませんが、いまの都市では無理だろうなと。そういう意味では、これからの都市にはあまり期待していないのかもしれません。
太田──僕も都市は必ずしも居心地がいい場所とは思いませんが、これを何百万という人たちがつくってきたんだと思うと、巨大な作品を見ている感じがして、人間ってすごいなと感動してしまうんです。整然とつくられている都市を目の当たりにすると、人間に対する信頼のようなものが湧いてくる。自然はもちろん信頼していますが。
田中──なるほど。最近はIoT(Internet of Things)ということが盛んに言われていますが、その解釈はいろいろありますね。ITの人が考えるIoTと人文系の人が考えるIoTとでは、その解釈は違ってくる。僕の解釈はいまの太田さんの話に近くて、過去何世紀にもわたって人類は都市をつくってきたわけですね。でも、人口が縮小傾向にある現在の日本で、残された傑作であるハードウェアとしての都市を、誰がメンテナンスして誰がマネージメントしていくのかというときに、人間だけではもはや無理だろうと思うわけです。そのときにIoTの力を借りて、人間にはできない部分をスマートなシステムに置き換えていこうと。僕は基本的にはそういう解釈なんです。
太田──都市そのものがリポジトリになっているわけですね。
田中──ええ。人間は作品をクリエイトすることができるし、ときに傑作といえるものが現われるけれども、できた作品を維持することに関しては、なるべくテクノロジーにアウトソーシングしていこうということです。
「解決」は次の「問題」の種である
太田──一方で、IoTにしても地図情報にしても、着々と超・監視社会化が進んでいると捉えることもできるじゃないですか。個人情報をどこまで紐づけるのかという問題や、カメラ付きのドローンを飛ばすにしても「見られている」という気持ちの悪さがつねにつきまとう。それについてはどうお考えですか?古橋──シンプルに答えるならば、時間が解決する部分はかなりあると思います。ひと昔前に「デジタル・ネイティヴ」という言葉がありましたが、「ドローン・ネイティヴ」とでも言うべき世代、つまり生まれたときからドローンが当たりまえのように飛んでいる環境で育った世代と、それ以前の人たちとでは、ドローンに対する考え方はまったく変わってくるはずです。どんな技術でもいい面と悪い面はあります。車は交通事故や環境問題など、さまざまな問題に直面しながらも、それを超える利点があったからこそ世の中に流通したわけですね。地図に関しても、国土地理院の前身は陸軍参謀局で、軍事機密などの理由で人々が自由に使えない時代もあったわけです。ですから、ドローンにしても地図にしても、世の中でどう使うかということとのバランスで考えていく必要があると思っています。
とはいえ、問題を指摘する人たちは依然としているでしょうから、その人たちの意見を排除することはないようにしたい。例えば、ゼンリンは表札データを公開しています。公道というパブリックな空間から取得できる情報を集めただけなので、たしかに法的には問題ない。僕たちも情報を入力しようと思えばできるのですが、それをやっていないのは、「なんとなく気持ち悪い」という直感、皮膚感覚を大事にしたいからです。もちろん自宅を晒してもいいという人は、自分で書き込むことはできますが、その辺の線引きはきちんとしたいと思っています。
田中──パブリック/プライベートの問題というのはデジタル技術だけの問題ではなくなっていて、鎌倉ではAirbnbなどを介して自宅を宿として貸し出したいという人がたくさんいるんですね。しかし、多くの人が外国人を含めた見ず知らずの人に貸し出すことになんの抵抗ももっていない。ですから、デジタル技術ではなくても、自分をオープンに晒して社会と一体化したいという動きは今日顕著になっている気がするんです。監視というのは一方通行ですが、オープンというのは、自分を外に開くことによって、リターンとして得られるものがあるから、人は進んでそうするわけですね。そのリターンのメリットが大きくなって、うまくバランスされたときに、新しいカルチャーや環境になっていくと思うんです。
太田──それこそ「馴れ」の問題かもしれませんね。19世紀後半に海水浴場という文化が登場して以来、水着の露出度もどんどん上がっていった訳ですし。ただ、他方でコストの問題はつねにつきまといます。今度導入されたマイナンバー制度にしても、監視社会化のひとつの帰着としていろいろ問題が指摘されますが、なにしろ社会コストがものすごくかかるわけでしょう。
田中──ただ、問題が起きて、それを解決する速度も速くなっていますよね。テレビがデジタル放送になったときも問題だと言われましたが、FabLab鎌倉から生まれたデバイス「IRKit」のように、リモコンのボタン増殖問題を解決することでビジネスにしようという動きも出てくるわけです。それは発明的な成果だと思います。「問題」は「解決」の種であって、「解決」は次の「問題」の種である。そういう感覚です。そういうサイクルにどれくらいの距離感でつきあい、どれくらいの速度で乗るかという問題ではないかと思います。
いま都市はなにをすべきか
太田──それぞれ専門の異なる領域からの意見が、これからの都市や街のあり方に向けていくつも焦点を結びそうで、まだまだ続けたいのですが、そろそろ鼎談を結ぶにあたって、最後にひと言ずつ話しましょうか。まず私ですが、「いま都市はなにをすべきか」という話をするときには、どうしても美談の類いが多くなってしまいます。どんな提案であれ、つねにさまざまな評価と結びついていて、だからこそ歯の浮くような話ばかりがもてはやされる。それはそれで大事な側面もあるでしょう。しかし、そもそもなぜパーソナルコンピュータが生まれたのか、なぜインターネットが生まれたのかということを考えると、人類史的な革命のためにあったのではないかという気がするんですね。それは耳ざわりのいい美談とはほど遠い、人間を解放する発明であり、ヒューマンな革命であったはずです。そういう都市への視点を維持することが、現在とこれからを支え続けるだろうと私は考えています。
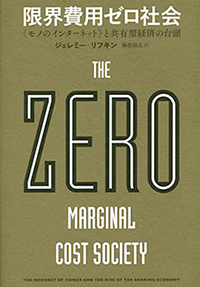
- fig.29──ジェレミー・リフキン
『限界費用ゼロ社会
──〈モノのインターネット〉と
共有型経済の台頭』
(柴田裕之訳、NHK出版、2015)
ジェレミー・リフキンという、ドイツのアンゲラ・メルケル首相をはじめとする世界各国の首脳・高官の政策アドバイザーを務めている批評家が書いた『限界費用ゼロ社会──〈モノのインターネット〉と共有型経済の台頭』[fig.29]という本があります。ドイツの「インダストリー4.0」産業政策の叩き台になったテキストなのですが、そこで彼は「これから経済は2階建てになる。1階は従来通りの資本主義、2階はシェアエコノミー」と論じています。そして、その引き金を引いたのがIoTインフラだというのです(今月開かれる世界経済フォーラム「ダボス会議」の全体テーマが「Mastering the Fourth Industrial Revolution(第4次産業を使いこなせ)」です)。
その場合、資本主義から生まれる都市というのは誰もが知っていますが、シェアエコノミーから生まれる都市というのは何なのか。どういう姿なのか。その実現には何が必要なのか。 私はもともと社会基盤工学で博士号をいただいた人間です。「ものづくり」からもうちょっと引いた目で、これからの社会の基盤としての、拡張Fabインフラを考えることが自分に課せられた仕事であると思っています。
古橋──都市というスケールと社会全体の関係を考えたときに、日本のように人口が減少していく社会では、マッピングできるリソースそのものが減っていくと考えることもできます。ゼンリンでは最初に説明したように、年間29万人、1日あたり800人近いリソースを投入しているわけですが、それも人口が減ってくると維持できなくなってくるでしょう。加えて、使う側はもっと細かい情報、3Dで付加価値の高い情報を求めるようになると考えられます。そうなると、どこかで人がマップデータをつくる限界にぶつかってしまうはずです。
そうした事態をふまえ、僕たちは「一億総伊能化」──日本人みんなが世界中のみんなが伊能忠敬になれる!──という言葉を掲げて、日本人の1億人全員を伊能忠敬にするということを目指しています。それは生活すべてをマッピングに充てるという意味ではなくて、人生のほんの一部の時間をマッピングにコミットしてもらう、そういうユルい参加の仕方をどう考えていけばいいかということなんですね。ボランティア・ベースでどこまでできるのか、ビジネスモデルを想定したマッピングはどこまでできるのか、そのときにロボットなりセンシングなりIoTなりがどこまでサポートしてくれるのか。僕自身まだ答えがないなかで走っているというのが正直なところです。ほかにも、ロボットが必要とするマップデータはより高度なものになる可能性も高いですし、自動運転の車によって採られた3Dデータは誰に帰属するかといった問題もあります。自分たちの活動がどこまで続くのかということに絶えず頭を悩ませつつ、最先端の技術を使って街をどれだけ細かく記述できるかというチャレンジは、簡単には捨てたくない。そうした街への思いはロボットにはもてないはずで、そういう意味では、愛が感じられる地図をつくることができればわれわれの勝ちかなと思っています。
太田──まだまだ進化の過程にあるという、お二人ならではの実感ですね。ぜひとも今後の展開についても知る機会を設けさせてください。Web上に掲載されるこの鼎談が、まさにユーザー・ジェネレイテッド・シティのひとつのリソースになれたら嬉しく思います。本日はどうもありがとうございました。
[2016年1月11日、FabLab鎌倉にて]
田中浩也(たなか・ひろや)
1975年生まれ。FabLab Japan発起人。慶應義塾大学環境情報学部准教授。慶應大学SFC研究所ソーシャル・ファブリケーション・ラボ代表。『設計の設計──〈建築・空間・情報〉制作の方法』(共著、LIXIL出版、2011)、『オープンデザイン―参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』(Bas Van Abelほか、監訳、オライリージャパン、2013)、『FABに何が可能か──「つくりながらいきる」21世紀の野生の思考』(共著、フィルムアート社、2013)、『SFを実現する──3Dプリンタの想像力』(講談社現代新書、2014)ほか
古橋大地(ふるはし・たいち)
1975年生まれ。OpenStreetMap Foundation Japan理事。青山学院大学地球社会共生学部教授。マップコンシェルジュ株式会社代表、東京大学空間情報科学研究センター特任研究員、OSGeo財団日本支部理事。地図学、森林リモートセンシング。地理空間情報活用のためのさまざまな技術コンサルティング、教育指導を行なっている。
太田浩史(おおた・ひろし)
1968年生まれ。建築家、ヌーブ共同主宰。東京ピクニッククラブ主宰。2009─15年、東京大学生産技術研究所講師。主な作品=《DUET》(2002)、《久が原のゲストハウス》(2004)、「PopulouSCAPE」(2004)、《AGCスタジオ》(2010)など。主な共著書=『世界のSSD100──都市持続再生のツボ』(彰国社、2007)、『シビックプライド──都市のコミュニケーションをデザインする』(宣伝会議、2008)、『つくること、つくらないこと──町を面白くする11人の会話』(学芸出版、2012)、『シビックプライド2──都市と市民のかかわりをデザインする』(宣伝会議、2015)ほか。


