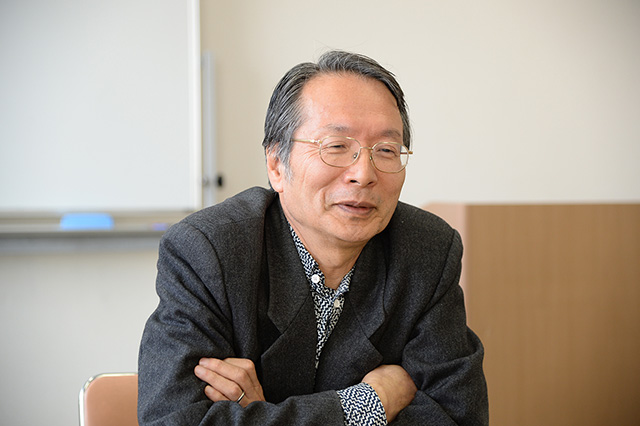ウォーフェアからウェルフェアへ──戦中と戦後、空間と言説
戦後民主主義と言説空間
青井──戦後の言説空間については、まず戦後間もなくの頃は共産党がすごく強かったということを大前提として押さえないといけませんね。
八束──ある時期までですね。
青井──長く見て1950年代までですね。でもあの頃の構図が後々まで尾を引いているように見えます。いずれにせよ戦後の十年強は共産党が少なくとも知識人にとって大きな精神的権威であったということは、建築ではあまり言われませんが、政治や思想あるいは文学などの分野では常識ですよね。彼らが存在感を持ったのは、共産党だけが戦時体制の中でも主張を貫いたという評価が背景にありました。その共産党の勢力を見ないことには、戦後の言説空間はほとんどわけがわからない。それに対抗して、リベラル派というか、自由主義的な近代主義者がいるわけですが、それも戦前派と戦後派がある。まずは戦前・戦中の論壇でかなりの発言力を持ち、終戦時には40--50代以上だった人たち。美術の長谷川如是閑はだいぶ年長ですけど、建築だと堀口捨己などが大きくはオールド・リベラリスト的な位置付けになると思います。エリート的・文化人的な教養主義者で、共産主義を嫌悪し、全体主義も嫌いだけれど文化的には国粋的という感じでしょうか。あまり単純化してもいけませんが。彼らは戦後も一定の影響力を持ちました。
八束──岩波文化人的な?堀口も如是閑もそうでしょう?戦前からの岩波派。堀口の戦中はちょっと危ないけどね。
青井──彼らオールド・リベラリストがひとつの軸だとすると、彼らより若い世代のリベラリストがいて、その代表が思想で言えば丸山眞男ですよね。多かれ少なかれ、戦前にマルクス主義の洗礼を受けたけれどもそこから距離をとり、戦後民主主義の思想的な担い手になる。文学でいうと、「政治と文学」論争というのが終戦直後にあって、マルクス主義者は共産党的な体制変革の方針に合致する小説しか評価しませんが、それに対して近代文学同人の作家たちは戦争経験から自律的個人の確立が重要だと考えるようになり、個人の内面を重視しました。戦時中は「近代の超克」が言われましたが、戦争が終わってみると、日本には超えるべき近代などなかったのではないか、個人の自立性を獲得するところから始め直さなくてはいけないのではないか、というかたちで近代の再評価にいく。それが作家としての自律性、文学という芸術の自律性の主張ともつながるわけですね。マルクス主義者にとっては、あくまで社会体制を変えなければ民主主義もない。リベラリスト的な立場からすれば、個人の自律なしには民主主義もないし、だいいち党の組織的規律を押し付けるような共産党の体質こそ全体主義的じゃないかというわけで、熾烈な論争になったわけです。建築分野で1948年におこった「近代建築論争」(「浜口・図師論争」ともいう)も、これとよく似た構図ですね。浜口隆一ら若いリベラリストが「近代建築」の民主主義的な再確立と芸術的意義をいい、図師らオールド・レフトたちはそんなものはブルジョア的な近代(つまり資本主義礼賛)であって体制批判になっていないと応じたわけですから。
八束──「伝統論争」もそれを引きずっていると言えます。哲学における主体性論争なんかも関係する。僕らの世代だと辛うじて梅本克己とか読みましたもん。
青井──個人の主体性か、マルクス主義的な歴史法則性か、という論争ですね。いまの「政治と文学」論争はそこから派生したものです。あと、今からは分かりづらいことですが、当時知識人はごく一握りのエリート階級でした。建築も含めて高等教育が大衆化するのは1960年代以降ですものね。同じ戦争経験を国民全体で共有していたとしても、知識人と大衆との距離は大きかった。当時の知識人としては、戦争経験をどう思想化するかという問題があったけれども、そのとき、民主主義といいながら自分たちの議論と民衆はいかにも遠いわけだし、どうしたら彼らに近づけるか、彼らを代表できるか、という切実な問題を抱えます。建築の民衆論争や伝統論争はこういう問題ですね。縄文的なものが民衆のエネルギーを代表するのだとか。縄文か弥生かというのは伝統と近代の意匠的な調停問題のようにみえますが、やはり左派の存在感と、戦後民主主義、そしてエリートの特権性みたいな文脈のなかで、それらに絡むかたちで意匠が主題化されていたわけですね。その意味で近代建築史はもっと思想や文学の分野とつなげたり比べたりしないといけないのですが、僕も含めて全然やれていません。また、それを踏まえないと、なぜ神代雄一郎が高度成長期の建築家たちに失望して漁村のサーヴェイをやり、巨大建築論争を闘ったのか、なぜ戦後民主主義の理念を通そうとして地域主義に辿り着くのか、そういう回路も理解できないでしょうね。今だと、地域主義は当たり前に正しい、たんに正しい。けれど、それがどういう道筋を辿って出てきたのかを考えておきたい。ちなみに神代は、終戦時に23才ですから太平洋戦争はまさに青春時代で、親友が応召したりして、その頃は日本浪曼派的な、厭世的な詩を書いたりしていたようです。だからこそ戦後民主主義に期待があって、共産党がらみのNAU(新日本建築家集団)の活動にも参加したわけですが、彼は基本的にはリベラリスト的な軸に立ちますね。そして、高度経済成長をもうひとつの戦争、もうひとつの大衆動員だと捉えるようになります。巨大建築論争(1974−76)の背景にはそういうこともあったわけです。
八束──川添登さんは、特に1950年代半ばはマルクス主義者でしたし、少なくともキューバ危機まで彼の意識の中では通じていると思います。縄文/弥生の話で言うと、彼のイデオロギー的な位置づけのもとに丹下健三も方向を修正していったところはあります。イデオローグ川添登はまず丹下健三を先導し、続いてメタボリストたちを先導したと思う。皇室の神社である伊勢を、マルクス主義者である川添が民衆の造形意欲の現れみたいにいってしまう力技は、戦中と戦後の捻れを伴う連続性の好例かもしれない。
青井──共産党に対する距離の取り方で、言説空間の中での大体の位置が組み立てられていたんじゃないかと思います。左派でも共産党絶対という人たちへの違和感があったわけですし。川添さんもそのひとりですよね。
八束──あまり知られていないことですが、左派の一部──確か池辺陽さんもそこに入っていたと思います──に1960年の世界デザイン会議を潰そうという動きがあったんですね、58年くらいに。その人たちは当時の新左翼にも繋がっていたのかもしれない。この点で一度話を聞いてみたいと思っているのは田辺員人さん。丹下研から丹下さんに言われて『国際建築』の編集部へ入り、菊竹清訓さんを見出した人です。港湾の土木的技術に関心を持っていたのは田辺さんですね。菊竹さんにそれをインプットしたかは知りませんが。浅田孝が事務局長、川添さんがメタボリストたちをまとめた世界デザイン会議の初期の頃は、田辺さんも中核にいたのですが、今では表には出てきません。証言がとれないのです。世界デザイン会議を潰そうとした左派の動きを田辺さんが止めたという話も聞いたことがあります。多分そこで色々と屈折した思いを抱え込んでしまったので表に出てこなくなったのではないかと思います。そのあたりは誰も調査していませんし、調査しないうちに関係者が誰もいなくなってしまうのはまずいですね。
当時はソ連への幻想があった時代ですので、1960年の少し前に建築学会が住宅関係のプレファブ技術を視察に行って研究会をやっています。『建築雑誌』なんかにレポートが出ていますが、結構有力な建築家がソ連へ行っています。前川さんの構造を多く担当していた横山不学さんとかも入っている。その流れの最後の方に名前を連ねているのは黒川紀章さんです。1958年に世界建築学生会議でソ連へ行きますが、当時のソ連のプレファブ住宅事情を仕入れてきて、黒川さんの最初の本になります(『プレファブ住宅 組み立てコンクリート住宅』住宅研究所 1960)。コンクリートの箱をヘリで輸送するみたいな奴ですね。確か川添さんも絡んでいる。プレファブのユニットですから、メタボリズムのカプセルにもつながります。黒川さんは右翼論客の代表のように見られていますが、先ほどの「近代文学論争」や哲学の領域における「主体性論争」のあたりは読んでいたみたいです。磯崎さんもそうしたものを読んでいたと思いますが、そのあたりから自分の行く筋を考えていったところがあると思います。
青井──そうでしょうね。少なくとも戦後10年くらいは、思想や文学の世界の議論をなぞるところがあります。なぞるというよりも、言説空間が同型の議論しかありえないような構造をしていたということでしょうね。だからこそ、その構図からどう距離を取るかが模索された側面もあるわけで、後からみれば、その位置取りに独自性を持ちえた人が後々まで残ったというか、歴史をつくる座標になりえたともいえるでしょうね。
その後についてですが、50年代を通じて体制の保守化が進んで共産党も権威を失い、1960年代になると敗戦直後のような言説も説得力を持たなくなっていきます。民主主義、戦争の反省、個人の主体性・自律性、あるいは責任・モラルといった規準から戦前とは違うナショナリズムを組み立て直そうという戦後思想の線が後退するんですね。ナショナリズムは経済成長と技術力とで満たされるようになりますし。さらに70年代中盤には欧米先進国は新自由主義に移行します。日本はかなり事情が違いますが産業経済や社会編成が国家から民間に手渡されるという意味ではやはり70年頃に大きな転換があったのだと思います。30年代以来の体制が終わるわけですね。丹下さんにせよ、メタボリストにせよ、なぜ50--60年代にあれほど包括的なプロジェクトを担って活躍できたかといえば、やはり国家が産業経済や社会の編成を主導する体制と、開発や建設に対する国民的期待があったからでしょう。もう少し丁寧にいえば、戦時期の全体主義+統制経済の段階ではまだ古い陣営が生き残っていてモダニストたちは部分的にしか仕事ができなかったわけですが、戦後の民主主義+開発独裁の段階ではプロジェクトの担い手がモダニストに移ったということだと思います。