「モノ」が先行する空間のつくり方
──『島田陽|日常の設計の日常』刊行記念対談
──『島田陽|日常の設計の日常』刊行記念対談
極北に振れない、表裏をつくらない
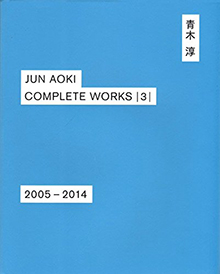
- 『JUN AOKI COMPLETE WORKS |3|
2005-2014』(LIXIL出版、2016)
青木さんの最新作品集『JUN AOKI COMPLETE WORKS |3| 2005-2014』(LIXIL出版、2016)では、『青木淳 JUN AOKI COMPLETE WORKS|1| 1991-2004』(同、2004)にも収録されていた《馬見原橋》(1995)と《御杖小学校》(1998)が再録されていますが、青木さんの作品のなかでもこの2つは素直につくられた感じがします。ものの組み立て方が見えたとおりにあるというか。 なんとなく、最近の作品である《大宮前体育館》(2014)や《三次市民ホール きりり》(2014)を拝見していると、謎が謎を呼ぶようなつくりというよりは、素直なつくられ方に青木さんの意識が向いているように感じました。
青木──ええ、そうだと思います。いわばテクトニクス──技術に基づき構築的につくられている面──への意識ですね。しかしその一方で、島田さんのつくったものにも、ぼくのつくったものにも、その逆のセミオティクス──記号論的に意味を持たせようとする面──への意識もある。つまり、そのふたつのあいだで振れているわけです。そして、なぜか極北に振れることは避けている。
島田──たしかに、構築と意味のあいだで振り子のように考えているところがありますね。《青森県立美術館》(2004)は、グランドホテル方式の映画のようにさまざまなキャラクターを持ったモノ、ディテールがいろいろなふるまいをしながら、全体としてひとつのストーリーをつくりあげているとも言えます。これはすごいことだと思うのですが、拝見させていただいたときに自分の建築リテラシーを試されているような気がして、とても疲れたんです(笑)。心地のいい疲労感ではあったのですが。
青木──ええ、その通りですね。まあ、ぼくとしては「グランド・ホテル」(1932)よりは、もっと新しいデヴィッド・リンチ監督の映画「マルホランド・ドライブ」(2001)を意識していましたけれど(笑)。一般的に映画を観るとき、ぼくたちはそれぞれの登場人物やエピソードを、話の展開に関係する意味のある記号として読み取って、内容を理解しようとします。しかし、あの映画では前半で起きている話と後半で起きている話が結びつかず、途中で意味が入れ替わってしまうため、内容はまるでわからず、ただ記号の関係性だけが残ってしまう。ぼくも《青森県立美術館》で意味を消したかったのですが、何の意味ももたない、「意味の零度」状態をつくることは不可能だから、この映画のように、むしろ意味を操作し、伏線関係を肥大させ、結果的に記号の関係性だけが残るようにしたかったのです。しかし、今おっしゃった通り、設計している本人でさえもすごく疲れるんです(笑)。それで、これでいいのかなというふうにも思った。
島田──たしかにデヴィッド・リンチの作品のように、見るたびに、また、見る人のリテラシーによっても、見え方の変わる建物ですね。おそらく子どもが見れば煉瓦造りのかわいい建物に見えるでしょう。建物との距離によっても違う印象を持ちます。遠くから見ると白い塊に見えていた建物が近づくと煉瓦であることに気づき、さらに近づくと煉瓦は構造ではなく、貼りついていることがわかる。
じつは昨日、《三次市民ホール きりり》(2014)へ行ってきました。《青森県立美術館》とは違って、あまり意味や謎を感じさせない、即物的なつくられ方であるように感じました。なんとなく、それが震災後のフェーズなのかもしれないとも思いました。
また、学校のような廊下からホールに突然つながったりと、いきなり裏と表がつながったり反転したりするような場所がありますね。
青木──そうですね、基本的に即物的なつくりです。ただ、普通のホール建築と違うのは、表と裏の区別がないことです。普通は、観客が入れるのは、ロビーやホールといった表だけで、楽屋やリハーサル室などの裏には入れません。でもこの建物では、その区別をなくそうと、むしろ奥に進めば進むほど表になっていくようにしています。だから、その先がもっと暗いはずの倉庫やトイレの扉を開けると、逆に明るい部屋になっている。もしかしたら、搬入口がもっとも劇的な空間かもしれません[fig.4]。

- [fig.4]青木淳《三次市民ホール きりり》内観 ©川畑杏子
島田──《青森県立美術館》でも裏側のデザインがとても充実していますね。青木さんの設計には欠かせない要素なのでしょうか。
青木──裏と表の反転は、「陰影礼賛」以来の建築の原理です(笑)。
島田──なるほど、たしかに(笑)。《三次市民ホール きりり》は廊下が主役であることから、「動線体」が戻ってきたようにも見受けました。しかし、その廊下がぼくを戸惑わせた理由でもあります。青木さんの説明では街のような建物だとのことでした。街であれば、道のような廊下をつくることを想像してしまいますが、リビングのように快適な室内であることを意識させる立派な木の床でつくられていました。やはりここでも、裏側であるべきところが表になっています。
青木──おそらく島田さんと似たことを考えている結果だと思います。島田さんは本のなかで「自分のいる場所」が一番いい場所になるようにつくると書かれていますね(「それまでいた場所が異なった風景に見えるということ」同p.50)。つまり、家のなかのどの場所へ移動してもそこが一番いい場所になるようにつくる。これはつまり、表と裏がずっとひっくり返り続けるということですね。今自分がいるところがいつも表で、その先の裏だと思って見ているところに行ってみると、今度はそこが表になっている。道に相当するから裏だとか表だとかいう話ではない。
周辺のバラバラさを受け入れる
島田──「表と裏をつくらない」ことは、建物の建ち方にも言えますね。《石切の住居》(2013)の周辺は、新旧の要素が入り混じった住宅地です[fig.5, 6]。そうした場所で瓦屋根を評価した設計をすると、隣に建つ新建材の住宅を否定するような建ち方になってしまう。ぼくは、そのモザイク状のあり方自体を評価できるように建てたかったのです。そこで、バラバラさがよく思えるような建物を建てようと考えました。
- [fig.5, 6]島田陽《石切の住居》ともに©新建築社
青木──バラバラさを受け入れ、それをひとつの価値として評価していくことは、ぼくも《大宮前体育館》くらいから、意識しはじめました。できた建築はまったく違いますけれど(笑)。
「表と裏をつくらない」ことのほかにも、共感するテキストがいくつもあります。例えばひとつの住宅に対し、ひとつの暮らし方しかないあり方はもったいなくて、日によって発見的に暮らし方が変わることができるといいな、という話(「住宅と住居」同p.74)。たとえ建築をつくっていく段階で意味を考えずにつくれたとしても、できた建築に対する読み解きには、何らかの意味が入ってきてしまいます。例えば、家型とか。しかし、そうした使い古された建築言語でも、それを紡ぎ方で次第で新しい文章になるのではないか(「日記」同p.108)、とも書かれていました。
そうした島田さんの関心の持ち方で思い出したのが、ぼくがずっと前に「広義のリノベーション」と呼んでいた方法のことです。優れたデザインというのは大抵、タブラ・ラサ=白紙からスタートするものですね。例えばファッションで言えば、イッセイ・ミヤケは、「1枚の布」というコンセプトを掲げています。これは、既存の「服」という前提条件を一度捨て、もう一度布から考えようとするものでした。よいデザインは前提を疑うものです。しかし、2000年前後から、前提を受け入れたデザイン──広義のリノベーション──が次々と目に入るようになってきました。マルタン・マルジェラは、服の歴史が脈々と続いてきたことを受け入れた服のリノベーションを行ないました。リノベーションとはつまり、函数をいじらずに、変数をいじることです。プロポーション、サイズ、袖を付ける位置など、何を変数とみなすか、そしてそれをどうずらすかということに重点が置かれます。マルジェラのつくった巨大なTシャツは、着ると深いドレープの入ったドレスのようです。大きさという変数をいじることで、Tシャツという形式の読み替えた例ですね。ひとつの形式にひとつの意味が固定化された状況をデザインすることで解きほぐし、別の意味を与える。そうしてまた意味が固定化されると、誰かがリノベーションを施して解きほぐしていく。同じことが絵画の世界でも、リュック・タイマンスなどに見られました。いろいろなジャンルで、こうしたリノベーション的方法が行なわれていて、ぼくは「そうだよなあ」と思って見ていました。ただ、2000年頃は、建築だけがまだ「広義のリノベーション」ではありませんでした。
島田──ぼくはもともと、タブラ・ラサからデザインをスタートすることにあまり興味を持っていませんでした。今あるものの意味を読み替えるほうが、ものが持っていた意味を利用して人の意識を変えることができるのでおもしろいと感じています。
青木──広義のリノベーション──いまある形式を読み替えていく方法──は、この本の主役と言ってもいい《ハミルトンの住居》(2015)[fig.7]にも通じているようです。この住宅は、形式的にはクイーンズランダーというオーストラリアの様式に則っているんですよね。

- [fig.7]島田陽《ハミルトンの住居》©Christopher Frederick Jones
島田──そうです。しかし《ハミルトンの住居》では、異邦人だからこその誤読を含めたかったのです。本当のクイーンズランダー様式について自分が理解してものをつくりかったわけではなく、異邦人であるぼくが感じたこととクイーンズランド様式とのハイブリッドをつくってみたかった。設計はつねにハイブリッドになるように考えていますが、それが直接的に形に出てきてもいいのかなと思っています。青木さんはハイブリッドであることがわからなくなるほど捻る設計をされていますね。
青木──ときにやりすぎだと思います。ある時点で操作を止められるのは羨ましいです(笑)。今誤読とおっしゃいましたが、この本には《ハミルトンの住居》のクライアントであるスティーヴ・ミノンさんが寄稿していますね。この方が本当に知的な方であることは、その文章からよくわかるのですが、彼も島田さんのことを「日本のミニマリスト」だと誤読しているところがおもしろい。島田さんはクイーンズランダーという形式を誤読し、クライアントは島田さんのことを誤読している。「ミニマリスト」の意味が日本での意味とは少し違うのかもしれませんが。
ただ、彼は《六甲の住居》をウェブサイトで見て仕事を頼んでくれたのですが、日本へ来たときに案内したら生活用品の多さに驚いていました。「彼はミニマリストじゃないんだね」と(笑)。
青木──《ハミルトンの住居》について、島田さんはこう書かれています。
建築を設計していると時代や地域の違いを越え、似たような問題を見つけた先達に出会い、無名の知性たちに励まされるような気分になることがある。それはこの連綿と続く建築の歴史、無名の知性の集積に触れるような、素晴らしい瞬間だ。
「無名の知性とつながること」同p.18
人によって、建築の楽しさをどこに見出すかは人それぞれだと思いますが、島田さんの場合は「無名の知性とつながること」を挙げました。食べる欲求と並ぶほど、人間にとってごく普通の行為が「建築をつくる」という島田さんの理解。そのなかで、みんなが少しずつ問題としてとらえ、解決しようとしてきた歴史が建築の歴史であると。
島田──そうですね。設計をしていると、人間が築いてきた歴史の流れに参加できている幸せを感じます。脈々と続く流れの先に自分がいて、2016年にひとつの建築が付け足されたと思える建築をつくりたい。クイーンズランダーを観察すると、短い歴史が凝縮され蓄積されていることを実感します。数種類しかない住宅の形式を住民が改造しながら、自ら歴史を積み上げていることを感じ、いろいろな知性が建物に発露している様を読み取ることができます。
- 終わりのない状態をつくる
- 極北に振れない、表裏をつくらない
- 矛盾を許容する




