第3回:美術と建築の接線から考える
美術館のつくり方
美術館のつくり方
それぞれのリサーチ手法
浅子──具体的にどのような作品をつくっているのか教えてもらえますか?
田村──時代を反映してか、最近では政治的なテーマを与えられることが多くなっています。たとえば、2014年にソウル市立美術館で行なわれた「SeMAビエンナーレ:メディアシティ・ソウル」のテーマはアジアの歴史に着目したものでした。そうしたなかで、ソウル市立美術館は日本の統治時代に裁判所として建てられた建築なのですが、ビエンナーレのディレクターには日本人の作家にその歴史を扱ってもらいたいという思惑があったようで、僕がこの美術館の建築の歴史を担当することになりました。実際には、かつての裁判所の大法廷を映画のセットのように実物大で再現した《世話料理鱸包丁》[fig.5]という映像を含むインスタレーション作品をつくりました。再現した大法廷では、江戸時代に朝鮮通信使で来日した韓国の役人が、対馬藩の通訳に大阪で刺殺された事件の裁判をもう一度俎上に載せるということをしています。

- fig.5──田村友一郎《世話料理鱸包丁》(ソウル市立美術館蔵、2014)
西澤──制作するにあたってはどのようにリサーチをしたのでしょうか。
田村──日韓併合の歴史を知ることから始めました。それらに関する複数の本を持ってソウルに行ったのですが、ディレクターからは、読んでいい本とだめな本とを区別されました。おそらく先方なりの政治的思想が強くあったからではないかと思います。そのときにどちらの側に立つかという問題が浮上しますが、自分としてはどちらかに立つのは不自然だと考えました。どちらでもないものをつくらなければならない。制作中は、ビエンナーレのスタッフの半数が、日本人がソウル市立美術館の建物の歴史を扱うことに懐疑的だったそうです。
西澤──読んではいけないと言われた本についてはどのようにしたのですか。
田村──ある事象があったとしてもいろいろな見方がありますから読みました。とはいえ、特定の見方をチョイスするというわけにはいきません。さまざまな見方を含めつつどれでもないものを返す。それが自分のアーティストとしての仕事だと考えています。
浅子──もう少し作品についてお話をお聞きしたいのですが、時代も場所も異なる事柄を扱い、架空の物語をつくるというようなことをされていますね。

- 田村友一郎氏
田村──いつもはそうですが、この作品では史実が含まれる部分があり、そのあたりで苦労しました。実際には、殺人に使われた凶器である──岐阜の関でつくられたほとんど刀のような──包丁を再制作し展示したんですね。韓国の人たちからすると殺人事件をもう一度蒸し返すのだからショッキングだったと思います。ですがそういったショックがないと表現として歴史的事実といったものに、もう一度向き合うことができないように思いましたし、そういった史実に付随する違った側面を現代に提示することが難しいようにも思いました。
森純平──過去の作品から通底していますが、制作のプロセスを記録した映像を上映するほかに、具体的なモノ、例えば《世話料理鱸包丁》であれば包丁や裁判所の実物大セットなどを展示空間に配置することの意図はどこにあるのでしょうか。
田村──シアターで上映するのではなく、空間にインスタレーションとして展開する際には、映像だけでは弱いと思います。包丁のようなモノや、ディテールのつくりこみによって物語の断片がつながれていくと考えています。架空の物語であってもある意味での「真性」が強化されていくと思うんです。
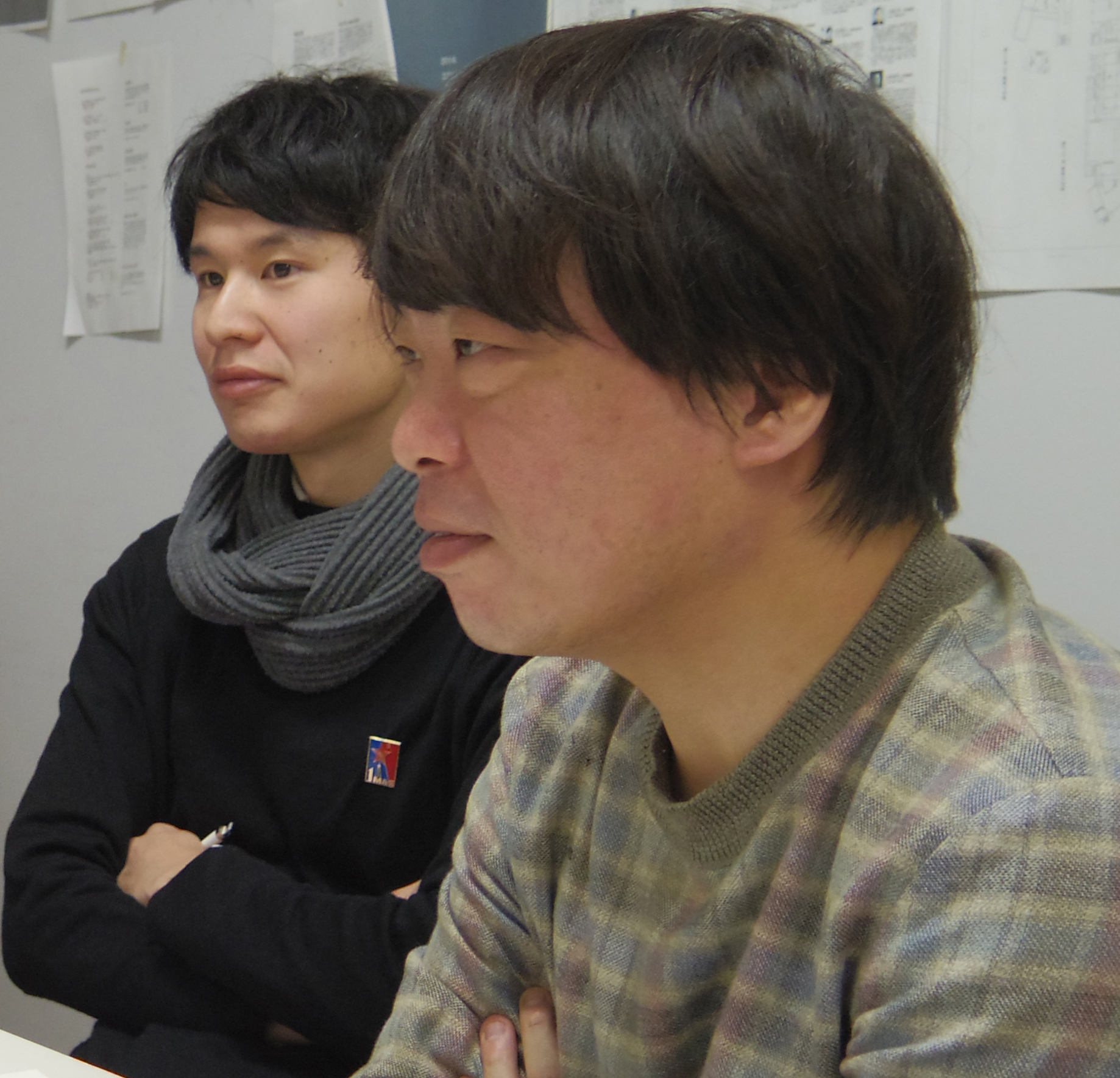
- 森純平氏[左] 西澤徹夫氏[右]
西澤──なるほど、確かに現前するブツと架空の物語を重ね合わせ、資料展示のかたちを採ることで、アーカイブのもつ「本当っぽさ」を逆手にとっているのですね。作品が複数のメディウムで構成されるもののあり方については後ほど議論することにしましょう。一方、山城さんは訪れた場所の人たちとのコミュニケーションを基にして作品を制作されることが多いわけですが、どのようなリサーチをされるのでしょうか。
山城──先ほど田村君から、企画した人の依頼に応えて作品をつくっていくという話がありましたが、僕にも同じような認識があります。そして、なぜこの依頼が生まれたのかということに僕はすごく興味があります。その土地のことを知るよりも前にまず依頼内容を厳密にリサーチをすることから始めます。
浅子──建築の設計における前提条件の洗い出しと同じですね。
西澤──なぜ自分に頼んでくれたのかという潜在的な欲望までをリサーチしているんですか。
山城──そうですね。
西澤──先行する状況、環境、人間関係のすべてを創作の契機にするのですね。受動的であるともいえると思うんですが、積極性がないということとは違うと思います。与えられたテーマがどういうものなのかを考えるときに、どういう展示室なのか、あるいは学芸員がどういう人なのか、自分のところにきた発注がどういうところから生まれてどこに届けられるのかを俯瞰して見る。それはなぜかというと、自分も自分のつくった作品の観者もニュートラルに捉えたいからだと思うのですが、いかがでしょうか。
山城──そのとおりですね。たとえばアーティストがそういうスタンスであることについてどう考えられますか。
西澤──腑に落ちる感があります。ここまで世界が複雑であると、クリエイターの内発的な考えやアイデアがすべての状況を好転させるということは大変難しくなってきています。むしろあらゆる状況の網目をどのように調停するかという手つき自体をクリエイティブとみなさざるをえないのかもしれません。そういう意味では、建築家とアーティストが似てきたのは必然かもしれませんね。
キュレーターである服部さんの場合は、具体的な作品として形を残すことを求められているわけではありませんよね。自分が展覧会に呼ばれるのには、どんな理由があるのだと思いますか。
服部──もちろんケースバイケースだと思います。とはいえ、山城君の場合と同じで、なぜ自分が呼ばれたのかを最初に考えます。美術館で行なわれる展覧会なのか、あるいは芸術祭のようなものなのか、どんな人たちがどのようなかたちで関わっているのかなど、状況を観察し与条件を洗い出します。法規や土地の条件から建築の形態がある程度導き出されていくのに近いと思います。「いま」「ここ」がどのような状況なのかを身体的に把握しつつ、その先の行動を考えます。ただ、僕の場合は自分ひとりで完結できるわけではないので、そのような状況を受けて「誰と」出来事を築いていくかを考えます。じつは、その段階では結構直感に頼っている部分も大きくて、それはおそらく予測不可能で未知ななにかを期待しているからだと思います。
西澤──どういう判断をするときに直感に頼るのでしょうか。
服部──答えるのは難しいですね。
たとえば、アーティスト・イン・レジデンスの場合は、アーティストが創造する現場を観察している感じが強いんです。テーマに応じた展覧会を組み立てるのとはまた違って、なにかが生まれることを誘発する環境をつくっているという感じです。「ここでこの人はこう動くだろうから、あの人と出会ったらいいかもしれない」とか、「こういう情報を提示したらどう反応するだろうか」ということをいつも考えているのですが、それは経験というか勘によるところが大きいです。そのための土台を築くことや引き出しを増やせるように、リサーチや関係づくりを普段からしているところはあります。
浅子──なるほど、MACで川床をつくった話とつながりますね。


