歴史叙述における「キマイラの原理」
──カルロ・セヴェーリ『キマイラの原理』、ティム・インゴルド『メイキング』ほか
──カルロ・セヴェーリ『キマイラの原理』、ティム・インゴルド『メイキング』ほか

- カルロ・セヴェーリ『キマイラの原理
──記憶の人類学』
(水野千依訳、白水社、2017)
『キマイラの原理──記憶の人類学』(水野千依訳、白水社、2017)で著者カルロ・セヴェーリは、病人を前に治療者としてのシャーマンが朗誦する歌の効果を分析するにあたり、それを一種の「図像」として解読している。それはすなわち、歌を構成する言葉の意味の次元ではなく、聴覚的な表現形式そのものに注目することである。セヴェーリがそこで依拠しているのは、エルンスト・H・ゴンブリッチの『芸術と幻影』におけるイメージの心理学であり、具体的には知覚プロセスがもとづく視覚的投射のメカニズムだった。たとえば、白い平面に4つの点が配置されているとき、われわれはそこに四角形を視覚的に投射する。物質的には存在せず、暗示されている四角形をそこに「見る」のである。
闇のなかで唱えられるシャーマンの歌の場合、4つの点の配置に当たるものが、同じ定型表現ないしそのヴァリエーションの規則正しい繰り返し(ロマーン・ヤーコブソンの言う「パラレリズム[並行法]」)である。この構造によって、歌声は知覚可能な規則性を得て「音のロールシャッハ・テストの染み」(p.269)のようなものと化し、患者の聴覚的投射を導いた結果、病人はそこに純粋な音としての精霊の呼びかけをおのずから「聞く」のである。4つの点の背景をなす白い平面に対応する「語られないもの」の余白が下地となり、歌のなかから断片的に拾われた徴候的な言葉をきっかけとして、知覚のイリュージョンがそこに投射される。セヴェーリは、患者が経験している、通常の言語的コミュニケーションによっては癒やされないほどの激烈な苦痛がこの機制を強化している、と言う。
セヴェーリがアメリカ先住民の絵文字に見出している、口承伝統と密接に結びついたキマイラ的イメージを媒介とする視覚的推論による記憶術も、これと同様のプロセスにもとづいている。この場合には、単純化された諸要素からなる「顕著さ」を特徴とする絵文字的形態が「秩序」だった配置をなすことを通じ、そこに働く同様のパラレリズム的想像力が、言語によって明示的に物語として語られてはいない記憶を呼び覚ますのである。セヴェーリはさらに、アメリカ大陸におけるキリスト教の受容過程では、強度あるキマイラ的イメージ内の矛盾する諸要素の共存を通してこそ、先住民文化との激しい社会的・文化的葛藤そのものが結晶化されていたことを示している。

- ティム・インゴルド『メイキング
──人類学・考古学・芸術・建築』
(金子遊ほか訳、左右社、2017)
『キマイラの原理』のこうした議論は、同書でも理論的先達として論じられているアビ・ヴァールブルク由来のものであるとともに、これに続くセヴェーリの著書『人格としての物質』の書名も示しているように、アート作品のような人工物を行為主体(エージェント)ととらえるアルフレッド・ジェルの議論やブリュノ・ラトゥールのアクターネットワーク論、あるいは、ホルスト・ブレーデカンプの像行為(Bildakt)論と問題関心を共有している。その点で、同じく今年邦訳が刊行されたティム・インゴルドの『メイキング──人類学・考古学・芸術・建築』(金子遊ほか訳、左右社)やラトゥールの『近代の〈物神事実〉崇拝について──ならびに「聖像衝突」』(荒金直人訳、以文社)などと合わせて読まれることによって、その共通性と差異(一例として、『メイキング』にはエージェンシー概念への直截な批判がある)からこそ、イメージ、像(Bild)、あるいは人工物一般をめぐる総合的な議論の展開が期待されよう。英訳(Horst Bredekamp, Image Acts, De Gruyter, 2017)がつい最近出版されたブレーデカンプの『像行為論(Der Bildakt)』(初版2011、改訂新版2015)についても邦訳が強く望まれる。

- ヘイドン・ホワイト『実用的な過去』
(上村忠男監訳、岩波書店、2017)
さて、だがここでは、これらとは異なる分野の著作における議論とセヴェーリの指摘とを関連づけてみたい。その著作とはヘイドン・ホワイトの『実用的な過去』(上村忠男監訳、岩波書店、2017)である。「実用的な過去」とは哲学者マイケル・オークショットから借りられた概念であり、ホワイトはそれを歴史学が対象とする「歴史的な過去」と対比させる。そこで問題になるのは、歴史学が再構成を目指すような「唯一の事実」としての、それ自体で価値をもつ過去ではなく、われわれ自身の問題解決の土台として役立つような過去である。その「実用性」の概念には、カントの『実践理性批判』を背景とする倫理的な含意がある。厳密な科学を標榜して、いわば「過去そのもののための過去」を追究する歴史学とは対照的に、「わたしたちは何をなすべきか」という倫理的な問いと結びついた実用的な過去を提示する場となってきたのが歴史小説であり、ホワイトはW・G・ゼーバルトの『アウステルリッツ』(鈴木仁子訳、白水社、2003)をはじめとする現代文学のうちにそのポストモダン・ヴァージョンを見出している★1。
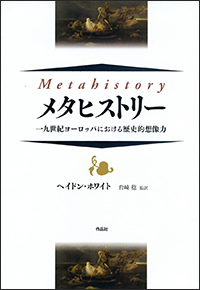
- ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー
──19世紀ヨーロッパにおける
歴史的想像力』
(岩崎稔監訳、作品社)
主著『メタヒストリー──19世紀ヨーロッパにおける歴史的想像力』(岩崎稔監訳、作品社)や『歴史の喩法──ホワイト主要論文集成』(上村忠男編訳、作品社)といった著作の邦訳が本年相次いで刊行されたホワイトの関心は、もっとも新しい著書『実用的な過去』においても一貫して、過去の出来事という指示対象に忠実であろうとしながらも、文字通りの記述以上の意味を生み出している歴史叙述の文学的性格にある。『実用的な過去』について端的に言えば、歴史から文学的慣習を徹底して排除しようとする──歴史が自然言語で書かれるかぎり、そんなことは実際には不可能だが──歴史学による「歴史的な過去」ではなく、文学による「実用的な過去」の叙述法こそが、とくにホロコーストをめぐるそれのような歴史叙述にはふさわしいのではないか、という認識がホワイトにはある。かつて彼がホロコーストの歴史叙述における「プロット化」を論じたとき、それは歴史の相対主義化としてカルロ・ギンズブルグの激しい批判を招いた。『実用的な過去』ではその点に関わる問題が自己批判を踏まえて執拗に考察されている。そしてそれは、ホロコーストが「わたしたちはそれをめぐって何をなすべきか」という巨大な倫理的=実用的問いと結びついた過去であるからにほかなるまい。

- ヘイドン・ホワイト『歴史の喩法
──ホワイト主要論文集成』
(上村忠男編訳、作品社)
『実用的な過去』でホワイトは、歴史家ザウル・フリートレンダー(Saul Friedländer)の著書『絶滅の歳月──ナチス・ドイツとユダヤ人(1939−1945年)』(The Years of Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939-1945, HarperCollins, 2007)における歴史叙述の方法を詳しく分析している。フリートレンダーはこの本で、当事者であるユダヤ人たちの日記などからの引用に語らせる手法を採り、事件の並置と逸話の列挙からなる年代記(クロニクル)の形式に拠っている。ホワイトはそこに歴史叙述の「脱ナラティヴ化」「脱ストーリー化」(p.177)を見て取り、フリートレンダーの歴史書をプルーストやカフカ、ジョイスのモダニズム文学の同類と位置づけ、さらにそのなかに、ベンヤミンの言う「星座的布置」による歴史の「イメージ」の提示を認めている。
ホワイトの分析は、『絶滅の歳月』全体の冒頭に置かれたエピグラフ、序文における写真のエクフラシス的描写、本編第一部のエピグラフ、そしてさらに、列挙されてゆく逸話・注釈・フィグーラ(比喩形象)の細部にまでわたり、精緻さを極めている。それは、フリードレンダーによる歴史叙述が、たしかに事実についての記述でありながら、さまざまな技法を駆使して、文学的な、とくにモダニズムの文学に接近した──けっして見世物的なフィクションでも審美化でもない──ものとなっていることを明らかにしている。
では、その叙述はどのような点で「実用的な過去」と結びついているのか。われわれはそれを、フリートレンダーが自分の著書の目論見としている「違和」や「不信」といった「内臓的」な──すなわち深く情動的・身体的な──反応の喚起に求められよう。この著者によれば、『絶滅の歳月』の目的はホロコーストを理性によって了解可能な歴史的事実として叙述する──それによって結果的に「馴致」してしまう──ところにはない。この書物が求めるのはむしろまったく逆に、ホロコーストがまさに「信じがたい」出来事であり続けているという、一種の非現実感──「違和」や「不信」──の持続なのである。
このようなフリートレンダーの叙述法は、セヴェーリが『キマイラの原理』で言うパラレリズムにもとづく絵文字的なものではないだろうか。「絶滅」の脅威に晒され、その犠牲となった人々の断片的なテクストからなる「星座的布置」をあの4つの点のような徴候として、その余白に投射されるかたちで発見されるのは、われわれが日常的に「現実」と信じているものとの「違和」であり「不信」(信じられないという「内臓的」感覚)そのものである。ホワイトは書いている──「パトス、とりわけ受難のパトスは、概念によってよりもイメージによっていっそう効果的に生み出される」(p.190)。そして、フリートレンダーの大著が集約されるのは、そんな一連のイメージである、とも。セヴェーリがシャーマンの歌をめぐって、その聞き手である患者が抱えた、言語化を越えたところにある極限的な苦痛について述べていたことが思い合わされる。『絶滅の歳月』という書物は、受難のパトスを伝えるためのパラレリズム的な形式で編まれた年代記であり、それは歴史叙述の「情念定型」(ヴァールブルク)のひとつのあり方を示すものと言えるかもしれない。
さらにまた、フリートレンダーの文学的叙述が提示しているものは、「歴史的な過去」の歴史学的「事実」ではなく、ラトゥールが近代的な事実/物神の区別を批判して唱える「物神事実」(事実faitと物神féticheの合成語であるfaitiche)ではないか。ホワイトとラトゥールの両者がいずれも「中動態」に注目していることを指摘しておこう★2。「物神事実」もまた人工物なのであり、ホワイトが参照する言語行為論とブレーデカンプの像行為論はこの点で相互浸透する。そして、ホワイトがなぜか言及することを避けている『アウステルリッツ』における写真の使用もまたここで、いわば「人工物行為論」の統一的な観点のもとに論じることが可能になるのではないだろうか★3。

- 上村忠男『ヴィーコ論集成』
(みすず書房、2017)
周知のように、人間によってつくられた文化的産物の認識可能性を深く問うたのは、『新しい学』のジャンバッティスタ・ヴィーコであった。ホワイトによる歴史の喩法論(トロポロジー)や像行為論の背景をなすものもヴィーコの思想である。その意味で上村の『ヴィーコ論集成』(みすず書房、2017)はこの碩学のヴィーコ研究の集大成であるばかりではなく、あらたな人工物行為論の礎としても読まれるべき大著と言えよう。
註
★1──『歴史は現代文学である──社会科学のためのマニフェスト』(L'histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, Éditions du Seuil, 2014.)の著者イヴァン・ジャブロンカ(Ivan Jablonka)も、今年邦訳が刊行された『私にはいなかった祖父母の歴史──ある調査』(田所光男訳、名古屋大学出版会)において、まさに『アウステルリッツ』を彷彿とさせるような、文学にかぎりなく接近した歴史叙述をみずから実践している。アウシュヴィッツで死んだ祖父母をめぐる客観的事実解明のプロセスと著者の主観的な語りが交錯するそのテクストは、ローラン・ビネ『HHhH──プラハ、1942年』(高橋啓訳、東京創元社、2013)をはじめとする、文学の側からの歴史叙述への接近と通底している。
★2──『実用的な過去』の解説で上村も示唆しているように(p.267)、ホワイトによる中動態への言及をこの概念の「神秘化」とのみ切って捨てることはできないとわたしも思う。
★3──ゼーバルトの小説における写真と歴史叙述の関係については、拙著『過去に触れる──歴史経験・写真・サスペンス』(羽鳥書店、2016)ですでに或る程度論じている。
田中純(たなか・じゅん)
1960年生まれ。表象文化論、思想史。東京大学大学院総合文化研究科教授。著書=『都市表象分析I』(LIXIL出版、2000)、『アビ・ヴァールブルク 記憶の迷宮』(青土社、2001;新装版、2011)、『都市の詩学──場所の記憶と徴候』(東京大学出版会、2007)、『政治の美学──権力と表象』(東京大学出版会、2008)、『イメージの自然史──天使から貝殻まで』(羽鳥書店、2010)、『冥府の建築家──ジルベール・クラヴェル伝』(みすず書房、2012)、『過去に触れる──歴史経験・写真・サスペンス』(羽鳥書店、2016)、『歴史の地震計──アビ・ヴァールブルク『ムネモシュネ・アトラス』論』(東京大学出版会、2017)ほか。翻訳=サイモン・クリッチリー『ボウイ──その生と死に』(新曜社、2017)。
201801
特集 ブック・レビュー 2018
歴史叙述における「キマイラの原理」──カルロ・セヴェーリ『キマイラの原理』、ティム・インゴルド『メイキング』ほか
オブジェクトと寄物陳志──ブリュノ・ラトゥール『近代の〈物神事実〉崇拝について』、グレアム・ハーマン『四方対象』ほか
中動態・共話・ウェルビーイング──國分功一郎『中動態の世界』、安田登『能』ほか
器と料理の本──鹿児島睦『鹿児島睦の器の本』ほか
21世紀に「制作」を再開するために──ボリス・グロイス『アート・パワー』、中尾拓哉『マルセル・デュシャンとチェス』ほか
ミクソミケテス・アーキテクチャー──『南方熊楠──複眼の学問構想』ほか
「建物」を設計している場合ではない──Samantha Hardingham『Cedric Price Works』、久保田晃弘『遥かなる他者のためのデザイン』ほか
シークエンシャルな建築経験と(しての)テクスト────鈴木了二『ユートピアへのシークエンス』ほか
歴史の修辞学から建築へ──ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー』、マイケル・ディラン・フォスター『日本妖怪考』ほか
中動態の視座にある空間 ──國分功一郎『中動態の世界』ほか
建築理論の誕生、建築家の声に──『磯崎新と藤森照信の「にわ」建築談義』、『内田祥哉 窓と建築ゼミナール』ほか


