谺(こだま)するかたち
──岡﨑乾二郎『抽象の力』、ダニエル・ヘラー=ローゼン『エコラリアス』
──岡﨑乾二郎『抽象の力』、ダニエル・ヘラー=ローゼン『エコラリアス』
本年(2018年)の春、東京大学中央食堂壁面に展示されていた宇佐美圭司の作品《きずな》(1977、所有権者は東京大学生協)が、昨年の9月に廃棄処分されていたことが明らかとなった(文中、敬称はすべて略す)。この事実とそこにいたる経緯は社会的な関心を呼びもしたし、少なくともこの事件を比較的身近で経験した筆者にとっては一種の衝撃であり、いまだに鎮められない鈍い痛みとなって心底に沈澱している。
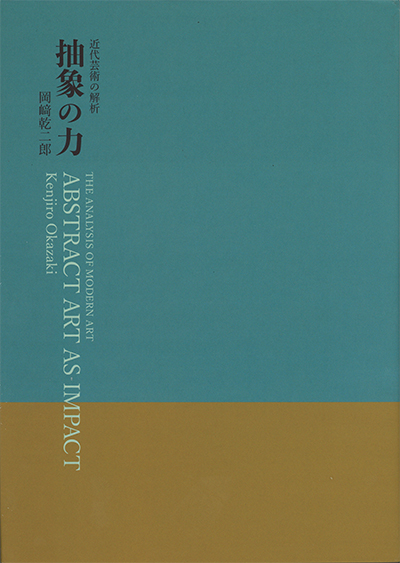
- 岡﨑乾二郎『抽象の力──近代芸術の解析』
(亜紀書房、2018)
この出来事をきっかけとしたシンポジウムやワークショップでは、宇佐美の作品および著作がふたたび活発な議論の対象となった。そのなかで宇佐美の業績の再評価を先導したのが、とりわけ1970年代に宇佐美と密接な関係にあった岡﨑乾二郎である。そこでその一端が披露された岡﨑の歴史観は、『ルネサンス 経験の条件』(筑摩書房、2001)以来の久方ぶりの単著『抽象の力──近代芸術の解析』(亜紀書房、2018)において、圧倒的なダイナミズムと魅力的な細部を備えた姿で提示されている。
岡﨑は同書のあとがきでこう書いている──「重視したのは場所と時間を隔てた作家たちの仕事の間に張り巡らされたさまざまなラインを可能な限り拾い上げることであり、そのネットワークがいかに『世界』を掩う架空の場として編み上げられていたかを描くことだった」★1。この一節を読みながら筆者は、かつて宇佐美が『20世紀美術』(岩波新書、1994)で語っていた、「絵画とは歴史に他ならなかった(...中略...)。歴史を語る場は共時的である。みんな〔過去の画家たち〕が一せいに私のそばで仕事をしている。それらをどう織り合せて一枚のタブローをつくるか」★2という言葉を思い出していた。岡﨑は「編み上げ」「織り合せ」て作り上げられる「タブロー」としての歴史を書こうとした点において(もまた)宇佐美の後継者なのかもしれぬ。それは岡﨑が述べるように、作品などの結果物それ自体の差異ではなく、その差異を生み出した制作過程や「設計思想」──あるいは宇佐美の言う「思考操作」──にこそ関心を寄せる、制作者=作家としての姿勢の共通性に拠るのであろう。
岡﨑は内間安瑆の版画作品を論じるなかで、最終的に仕上がった画面に見られる垂直線が、個々の版木には一本の連続した線としては存在していないことを指摘している。内間の版木は噛み合ってひとつの平面にまとまってしまうのではなく、あくまでそれぞれが別の平面、別の空間であって、それらが重ね合わされたときにはじめて、複数の異なる平面・空間の齟齬としての「間」が出現し、光や空気で満たされ諸形態がそこに浮遊するかのようなその「間」が画面に生気を与えている。すなわち、一本の連続した垂直線と見えるものは同一平面上の直線ではなく、この「間」においてこそ生じる、いくつもの異なる線の複合体なのである。内間はそんな自身の版画を「色面織り」と呼んだという。
『抽象の力』という書物は、近代芸術を貫く歴史の「線」をまさにそうした「間」において浮かび上がらせようとした「色面織り」に譬えられよう。岡﨑はたとえば、日本で独自に展開してきた熊谷守一の仕事が、ミルトン・エイヴリーをはじめとする他の画家たちの仕事と──直接的な影響関係なしに──同期(シンクロ)していたことをきわめて説得的に示している。この共時性=世界性は制作者たちの設計思想から構造的に生じたものだった。本書は、こうした思想が有していた世界性のネットワークを美術作品の解析を通じて明らかにした、斬新な「思想史」の織物(テクスト)なのである。
その手法は、本書で幾度も言及される漱石の文学論における「f+F」の図式★3に倣えば、固定観念と化している美術史(焦点化された観念としてのF)を個々の作品(感覚印象としてのf)へといったん解体し、個別作品に体現された設計思想の分析を通して、あらたな歴史の線(F')を生成させようとしたものと言えようか。そのときに際立つのは、F'という複合体を生み出す色面織りのために、制作者=作家としての著者・岡﨑が重ね合わせる複数の版木の絶妙な関係性であろう。『抽象の力』本論・補論のみならず、白井晟一論をはじめとする論考はそうした多様な「版木」となって、「間」の創造に大きく寄与している。その点でこれらが一冊の書物という形態にまとめられたことの意義は大きい。
そのような「版木」のひとつに、恩地孝四郎が抽象表現を手がける下地になったと思われるフリードリッヒ・フレーベルの幼児教育遊具(「恩物(ガーベ)」)をはじめとする、教育遊具からの影響の系譜がある。岡﨑はまた、ゾフィー・トイベル=アルプらに代表される前衛芸術家たちの創作活動において、抽象芸術と玩具とが通底していた点を指摘している。前衛芸術と玩具はそこでともに、子どもにも働きかける具体的な力を追求していた。「抽象の力」とはそうした「具体力」なのである。
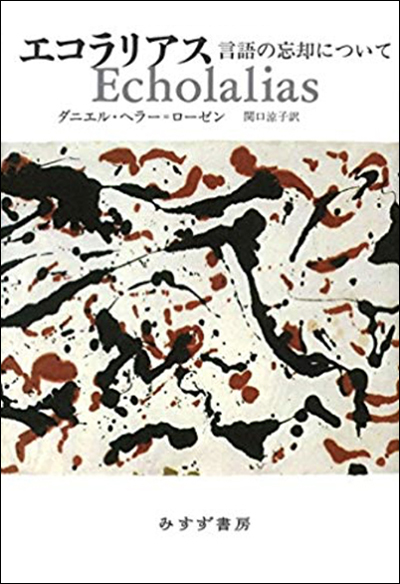
- ダニエル・ヘラー=ローゼン
『エコラリアス──言語の忘却について』
(関口涼子訳、みすず書房、2018)
この力をめぐって連想される書物がある。ダニエル・ヘラー=ローゼンの『エコラリアス──言語の忘却について』(関口涼子訳、みすず書房、2018)である。「エコラリアス」とは「谺する言語」の意味であり、そこで谺となるのはそれ自体としては消滅して忘れ去られた言語、たとえば、言葉を話すようになる前に幼児が発する雑音めいた喃語である。喃語の谺はオノマトペや或る言語の発話者が別の言語を模倣しようとするときの「異言語の音」、あるいは感嘆詞のほか、人間ではないものを人間が模倣しようとして発する音声のうちに聞き取れる、と著者は言う──「言語は、それ自身の音から離れ、言葉を持たない、あるいは持ち得ないものの音、すなわち動物の鳴き声、自然や機械の出す音を引き受ける時にこそもっとも言葉そのものになりうる」★4。この表現を借りれば、「抽象の力」とは「具象的イメージがそれ自身の形態から離れ、形態を持たない、あるいは持ち得ないものの形態」になったときの形態の力ではないだろうか。幼児用遊具や玩具とは「人間ではないものを人間が模倣しよう」とするときに手がかりとする事物ではないか。つまり、抽象とは「谺するかたち」ではないだろうか。
ヘラー=ローゼンは同書のなかで言語学や文学から哲学、宗教学、医学にいたる広範な領域にわたる古今のテクストを縦横に渉猟しながら、或る言語を忘却することによってこそ人間は言語を獲得するのであり、そこで獲得された言語は前者の言語を谺として残存させている、というテーマの変奏を通じて、「谺する言語」の諸相を21の章で示している。たとえば、フランス語の無音の「e」のような「消滅危惧音素」やもはや発音されないがゆえに無用視されることもあった「h」という文字(そのなかに痕跡として残る気息)が、あるいは、言語学において「*(アステリスク)」の記号を付けて表される、「言語形態が確立されるのに必要だが、それ自体は実例を持たない」用語がそこで取り上げられてゆく。
谺が執拗に残存するがゆえに、いかなる言語も完全に死滅することはない。しかし逆に、忘却をまったく免れている言語もまた存在しない──いわゆる母語でさえも。そして、失語症患者が示すのは、「かつて決して書かれたことがなく、これからも言われえない」原初の言語の、消すことのできない「記憶」こそが、「話せない」という彼らの「能力」の源であるという事態にほかならない。「谺する言語」と「谺するかたち」の交点のひとつは、『抽象の力』の或る註で言及されているガートルード・スタインの詩──岡﨑はそれを「キュビズム的曲芸」と呼ぶ──であろう。さらに、われわれは熊谷の多くの作品のなかにも、「話せない能力」の痕跡である喃語の谺を聞き取ることができそうに思う。
「喃語(babble)」で始まったヘラー=ローゼンの書物は、英語では同じ発音の「バベル(Babel)」をめぐる章で閉ざされる。このように起源の言語の忘却へと回帰する構成をもつ同書のうちに、一神教的な否定神学を認めることはたやすい。だがここではむしろ、バベルの塔は廃墟と化してなお生き延び(残存し)、われわれ人間はその存在をまったく忘却したまま、そこに依然として住み続けている、という著者の叙述に注目したい。『エコラリアス』と『抽象の力』を異なる版木のように重ね合わせるとき、前者の「バベルの塔」に対して、後者におけるイサム・ノグチの《ヒロシマ・モニュメント》案や白井の《原爆堂》が折り重なって、それらの狭間から、われわれがいまだにその内部に居住し続けている廃墟のイメージが浮上するのを覚えるからである。
『抽象の力』に収められた白井晟一論が発表された2011年2月、岡﨑を中心とする白井をめぐるシンポジウムに、筆者自身も発表者として参加したことを思い出す。終了後の談話のなかで、誰となく乱世の到来について語った。そこには1カ月後の事態への予感があったのだろうか。『抽象の力』に引用された寺田寅彦によれば、人為的な制度が統制し固定しようとする領域が大規模になればなるほど、自然の変化による被害は大きくなり、無理に固定された制度や形態は崩れ去るのだという。
寅彦に学んだ中谷宇吉郎の娘・中谷芙二子による霧の彫刻をめぐって岡﨑は、「霧、いや水の微粒子たちの群れが作り出す運動、それは確固とした自由意志そのものである」と書く★5。その群れはあのfであり、赤ん坊が備えている、いかなる限界も知らぬ音声能力の産物としての喃語のざわめきでもあろう。岡﨑が「自由な連帯(association)」をそこに見ようとする空中に漂う雲塊は、バベル/ヒロシマ・モニュメント/原爆堂が複合してかたちづくる、地中に洞窟を抱えた廃墟の姿と対をなすような、微粒子たちの群れからつかの間立ち現れる「谺するかたち」である。そのとき、抽象芸術は自由意志を体現する抵抗の力となって、制度というFに抗う。ワッツ暴動の写真から取り出された4つの身振りの人型によって形成された《きずな》もまた、物質的には瓦礫となってしまいながらもなお、見えない力線によって結ばれた作品群のなかに「谺するかたち」として残存し、そのような力を発揮し続けることを信じたい。
註
★1──岡﨑乾二郎『抽象の力──近代芸術の解析』(亜紀書房、2018)415頁
★2──宇佐美圭司『20世紀美術』(岩波新書、1994)193頁
★3──岡﨑乾二郎『抽象の力──近代芸術の解析』190頁
★4──ダニエル・ヘラー=ローゼン『エコラリアス──言語の忘却について』(関口涼子訳、みすず書房、2018)19頁
★5──岡﨑乾二郎『抽象の力──近代芸術の解析』250頁
田中純(たなか・じゅん)
1960年生まれ。表象文化論、思想史。東京大学大学院総合文化研究科教授。著書=『都市表象分析I』(LIXIL出版、2000)、『アビ・ヴァールブルク 記憶の迷宮』(青土社、2001/新装版、2011)、『都市の詩学──場所の記憶と徴候』(東京大学出版会、2007)、『政治の美学──権力と表象』(東京大学出版会、2008)、『イメージの自然史──天使から貝殻まで』(羽鳥書店、2010)、『冥府の建築家──ジルベール・クラヴェル伝』(みすず書房、2012)、『過去に触れる──歴史経験・写真・サスペンス』(羽鳥書店、2016)、『歴史の地震計──アビ・ヴァールブルク『ムネモシュネ・アトラス』論』(東京大学出版会、2017)ほか。翻訳=サイモン・クリッチリー『ボウイ──その生と死に』(新曜社、2017)。
201901
特集 ブック・レビュー 2019
1968年以降の建築理論、歴史性と地域性の再発見 ──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、五十嵐太郎『モダニズム崩壊後の建築』ほか
谺(こだま)するかたち ──岡﨑乾二郎『抽象の力』、ダニエル・ヘラー=ローゼン『エコラリアス』
現代日本で〈多自然主義〉はいかに可能か──『つち式 二〇一七』、ティモシー・モートン『自然なきエコロジー』ほか
ゲノム編集・AI・ドローン ──粥川準二『ゲノム編集と細胞政治の誕生』、グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学』ほか
「建築の問題」を(再び)考えるために──五十嵐太郎ほか『白井晟一の原爆堂──四つの対話』、小田原のどか編著『彫刻1』ほか
あいだの世界──レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』、上妻世海『制作へ』ほか
モノ=作品はいま、どこにあるのか──『デュシャン』、ジョージ・クブラー『時のかたち』ほか
堕落に抗する力──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、ジョゼフ・チャプスキ『収容所のプルースト』ほか
オブジェクトと建築 ──千葉雅也『意味がない無意味』、Graham Harman『Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything』


