いま地域の変化を許容し、価値を認めること
──文化的景観の課題と可能性
──文化的景観の課題と可能性
「都市の文化的景観」の捉え方
清水──私はおふたりとはちがい、おもに選定候補地を調査する側から文化的景観を見てきた立場です。とくに、専門とする建築史の分野から、都市や集落に重きをおいた対象を多く見てきました。文化的景観はもともと農林水産業に関わる景観を中心にはじまった制度です。集落よりも農地や山林、河川計画を考えることが出発点にあり、農学や地理学、造園学、考古学といった学問の専門家を中心に議論がなされてきました。他方、それぞれの地域には景観を維持している人たちが住む場所があります。そこで集落という視点が入り、建築学の専門家として私もサポートする立場で参入しました。
文化的景観の制度が整えられる過程で、農林水産業だけではなく工業や製造業、流通業なども景観を形成する主要な要素と見なされるようになりました。文化的景観の選定基準がこうして厚みをもつようになるなかで、これらの産業を表す要素として、採掘や製造、流通、往来、居住といった営みについても文化庁内で研究会が立ち上がり、検討が進みました。
文化的景観というときには人が居住する地域が中心となります。そこで農林水産業以外の産業を対象とする「(仮称)都市の文化的景観」の調査研究がはじまりました。そこではどのようなものが主要な要素になりうるか、私たちはまず全国で対象となりそうな景観地を挙げてもらうアンケートを行い、これをもとにディスカッションしました。その過程で農林水産業を軸にした景観との相違点も見えてきました。都市の特徴として、地域の歴史が折り重なっている様子がわかりやすく見えるという点があります。もうひとつは複合的な要素によって成り立っていること。農林水産業のつくる景観は、例えば棚田のように単一の産業や生業に基づく場合がほとんどですが、都市の場合はさまざまな要素が互いにある関係をもって存在し、ひとつのまとまりをつくり出しています。また、人のアクティビティが農村ではお祭りなどを通じて日常非日常で起こるのに対し、都市部ではより高度に文化的なかたちで現れます。
文化的景観を都市部へ展開する際、最初に考えたのは歴史的な町並みを残す地域でした。しかし、こうした町はすでに多くが伝建制度の対象になっています。では、そうではないところはどこか。議論に上がったのは神田の古本屋街や巣鴨のとげぬき地蔵などでした。古い要素は希薄でも、つねに人が動いている、そのまとまりを景観と捉える可能性を探っていきました。そうして、都市の文化的景観を選定するための4つの強化指標を定めました。それが「重層性」「関係性」「一体性」「象徴性」です。2010年にはそこまでの議論を報告書にまとめ、『都市の文化と景観』として出版しました。「都市の文化的景観」が実質的にスタートしたのはこのときではないでしょうか。私自身は宇治市のほか、四万十市や京都市、岐阜市、佐渡相川の鉱山町、葛飾柴又などの調査に携わりました。2009年に文化的景観の選定を受けた宇治市は、都市部における最初期の代表例のひとつです。
「都市の文化的景観」を成り立たせる要素として大きく2点挙げられます。ひとつはサービス業(第三次産業)の存在。第一次、第二次産業はわりと素直に生業が建物の形に現れるのに対し、サービス業は生業の特徴が見えづらくなります。もうひとつは、都市化が進んだ地域では人工的な要素がはるかに大きく、人為的な変化に負うところが大きくなること。こうした条件が四万十川流域のような自然の要素が大きい文化的景観と異なるのは、これからの景観を考えていく際に、必ずしも保存を基本とした考え方にならない点です。
こうした違いをどのように捉え、選定に結び付けていけるか。今、第三次産業においては生業が建物の特徴にほとんど現れないと申しました。それはつまり、これまでの様式論的な民家調査の手法はほとんど通用しないということです。そこで調査では、生活・生業の痕跡を読み取ることを徹底的にやることになりました。そのためには建物の姿や敷地の中でのおさまり方だけでなく、道路や街道、都市的なアクティビティとの関係から読み解く視点が必要になります。建築史の分野でもこうしたアプローチからの研究はおそらくあまり例がありません。
生活と生業を建築の形から読み解くという課題に対しては、もうひとつ「建物のふるまい」から読み解くということも可能なのではないかと思います。このキーワードは一緒に調査をした北海道の建築家、宮城島崇人さんから出てきたもので、彼によれば、建物に人が介在するとき、町に対して建物がふるまいを見せる。こうした視点をもつことで、町に新しい建物をつくるときでも古いものを変えてしまうと見なすのではなく、「アクションを変える」という捉え方で解決できるのではないか。
さらにもうひとつの見方に、建物がいかに住みこなされているかという視点があります。岐阜県で長良川中流域の調査をした際に遭遇したのが町家の「木部洗い」でした。この地域では格子など表構えの木部を1年に2回、一生懸命洗う風習が残っており、これを長年続けることで木材が黄褐色に変わっていく[fig.13, 14]。この色が景観の重要な要素になっているのです。この町並みを見たとき、こんな住みこなし方があるのかと感嘆しました。形自体に変化はなくとも、ある慣習や行為を長く続けることによって建築に表情が与えられるようになる。それが地域全体に伝わることで、都市に明らかな性格を与えるようになることを示した例と言えるでしょう。

- fig.13──岐阜市東材木町の町家での木部洗いの様子 撮影=桜木美幸

- fig.14──木部洗いによって黄味がかった町家の表構え 撮影=惠谷浩子
こうした調査はこれからの地域づくりの基本となるものです。文化財の分野では保存をベースにした考え方があり、そこでは景観をコントロールするときに伝建のように様式を整える手法か、あるいはボリュームのコントロールのような手法かの二者択一に限られます。そこに新しい活用型の手法を打ち出すことが、都市の文化的景観の課題と言えます。地域を読み解くとき、歴史が重層しているというだけでは意味を持ちません。地域に変化が起これば、そこには必然的な理由もあるし、変わらないものにもまた理由がある。そういう事象にきちんと目を留める必要があると思います。とくに都市のなかには空き地もあれば農地もあり、水路や道路、家屋がある。こうした要素がどのような関係を持ちながらひとつのまとまりを形づくっているのか見きわめなくてはなりません。そうでなければ、単に景観を構成する要素を個別に守り、コントロールすればそれで十分となってしまい、それでは他の文化財制度と変わらなくなるからです。まとまりを見出すことによって地域が流動する方向や、根本的な理念を抽出でき、町の将来像へとつなげられます。
私が文化的景観の調査活動のなかで学んだことのひとつに「環境の中に建築がある」という考え方があります。建築を専門とする人たちは「建築と周辺環境」という表現をよく用いますが、そうではなく、建築や都市もまた環境の一部として見る必要があると思うのです。なぜなら、それらも刻一刻と変わるものであり、環境とともにひとつの生態系を形成しているからです。こうした視点からは建築や都市の論理を生態系のアナロジーとして見ることも可能なのではないかと、文化的景観の調査を通じて教えられました。しかし、これは口で言うほど簡単なことではないように思われます。というのも先ほどから話題に出ているように、文化的景観とは変化を扱う制度だからです。自然も相手にする以上、ある程度の変化を許容しなくてはなりません。その変化はどこかで許容できる限界値に達します。つまり、許容できる変化と許容できない変化の見きわめが行われるわけですが、そこで線引きをするのではなく、変化の必然性の有無や、連続的な変容や進化の意味づけの問題に置き換えられるのではないか。変化することを前提に置き、その意味を考えることが、とくに都市の文化的景観の議論では必要になるのではないかと思います。
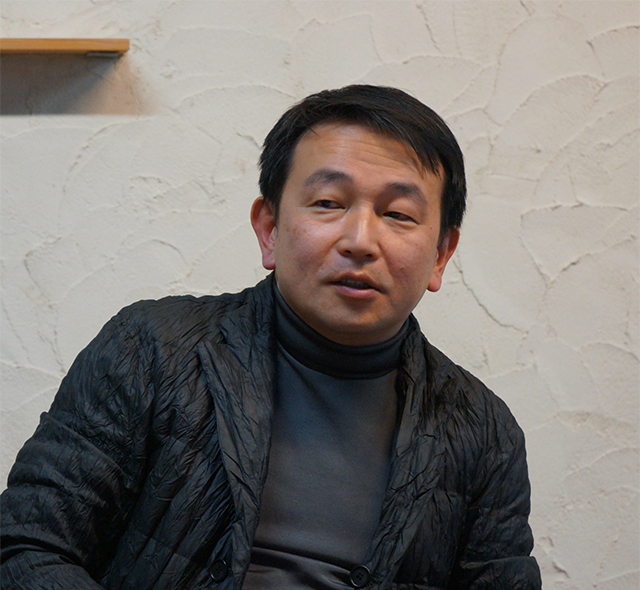
- 清水重敦氏
形態から機能へ──地域への視点を転じること
惠谷──景観にある軸を見出し、町の将来づくりの手がかりにするというとき、清水先生の感じる難しさというのは、枠をはめることでその外側のまったく違う可能性を排除してしまうかもしれないということでしょうか。
清水──いえ、そうではなく、これまで多様性をもちながら時間をかけてじわじわと広がっていった伝統的な要素が、ある軸を与えられることで変化の角度がふりきれてしまうおそれがあるということです。私も調査に関わった「葛飾柴又の文化的景観」を例に挙げると、柴又帝釈天の参道では商店がショーケースを軒先に張り出して商っている姿が見られます。映画『男はつらいよ』でも知られるこうした景観はそれぞれの店の裁量でつくられているものです。ところがショーケースを張り出すやり方が制度の側から共通ルール化された場合、かえって画一的な町並みを生むことにもなりかねません。
惠谷──それは私が宇治で感じていることでもあります。重要文化的景観の選定と連動して景観計画が策定され、色彩の統一が行われています。昔はもっと多彩だった町並みが茶色っぽい町になりつつあります。ルールがない時代に豊かな多様性をのぞかせていたものが均されてしまう危険性は大いにあります。
清水──先ほど景観のコントロールを行うときの手法が二者択一に限られるとお話しました。町並みに規制がかかる場合のほとんどは形態のルールづくりです。ヨーロッパの場合は、既存の町並みのなかに新しい建物をつくる際に、史的様式をまとった形態を採ることが禁止されている場合が多いのですが、日本の都市はそこまで厳密ではなく、かえって町並みに偏りが生じる可能性がある。そこで形態ではなく機能に目を向ける視点の必要性も感じています。
杉本──文化的景観は景観法と連動しているので、どうしても形態に統一感を与える方向に働きますね。文化的景観が自立しながら町の景観形成に関わりあえれば、清水さんの言うように、建物のふるまいがもっとクリアに見えるのではないかと思います。
清水──景観法が扱うのはあくまで形ですよね。形をつくる仕組みを扱う文化的景観は機能からアプローチすべきだと思うんです。景観法と文化的景観は必ずセットで語られるのだから、それならば景観法こそ文化的景観に引き寄せて解釈できるようにすればいいんです。関係性というのは形や色以外にコントロール可能な要素を見つける視点ですから。

- fig.15──柴又帝釈天の参道の様子。ショーケースを通りに張り出して商う 撮影=清水重敦
惠谷──サービス業は建築に特徴が現れにくいというお話が出ました。文化的景観は生活と生業の両方に着目するものですが、生業は捉えやすく比較もしやすいのに対し、生活のほうはなかなか見えづらいように感じられます。例えば、生業があまり目立たない水郷の町などで他の町とのちがいを探すとき、水路の形から生業の特徴は語れても、生活の姿のちがいはなかなか指摘しにくい。こうしたことを感じるケースはこれまでに多々ありました。
清水──集落の場所が四万十川との関係で決まっている例などは、生活が自然との関係に現れていると言えるかもしれませんが、こうしたことはどこの町でも見受けられますよね。そのなかで岐阜の「木部洗い」は興味深い事例と言えますが、これもまた特別な瞬間に設えが変わる典型ではあります。日常の暮らしが形として現れているところを探さないといけない。生活にしろ、生業にしろ、形に現れた結果が価値をもち、それが地域の持続にプラスになるというのが文化的景観の基本的な考え方で、人のアクティビティと自然の特性が形に現れている部分を追求して、その関係のルール作りをしようとしている。それが地域の特性をさらに高めることになり、住民のプライドを醸成したり、生産者に付加価値を与えたりして持続性を高めることにつながると考えていますが、実際は難しい面もあります。
編集──里山に残る農家住宅などには田畑だけでなく、牧畜や養蚕といった生業の痕跡が現れているということは想像できるのですが、では生業を都市の文脈で見ていこうとする場合、どのような捉え方ができるのでしょうか。
清水──例えば、単一の生業が支配的な都市の場合、同じような捉え方ができると思います。宇治ならば街中に農家もあれば、茶問屋もあり、小売店もあり、そのなかに産業のダイナミズムがある。一方で城下町みたいなところは基本的にサービス業の内容も単一ではないので、産業から都市の構造を読み解くには無理が生じます。そういうときに生活の視点からのアプローチが有効だったりします。岐阜などはその例ですね。文化的景観に馴染まない類型があるとすると、古い建物は残っていても産業が完全に消失した後で、住宅地化が進み、近郊の都市に就労の拠点が集約されているところです。こうした地域は景観を評価する必要性があまり感じられない。ただ、こういう地域はまったく新しい機能を導入して地域おこしをするのに向いていたりします。文化的景観に馴染むかどうかは別として、神山町(徳島県)や善光寺(長野県)の門前町のように、実際にそういう事例も少しずつ現れはじめていますね。
- 郷の文化的景観──四万十川流域の文化的景観/「必然的な変化」をいかにみきわめるか
- 都市の文化的景観──世界遺産の町、宇治市が直面した転換点/変化するものの価値を認めること
- 「都市の文化的景観」の捉え方/形態から機能へ──地域への視点を転じること
- 文化的景観の担い手問題


