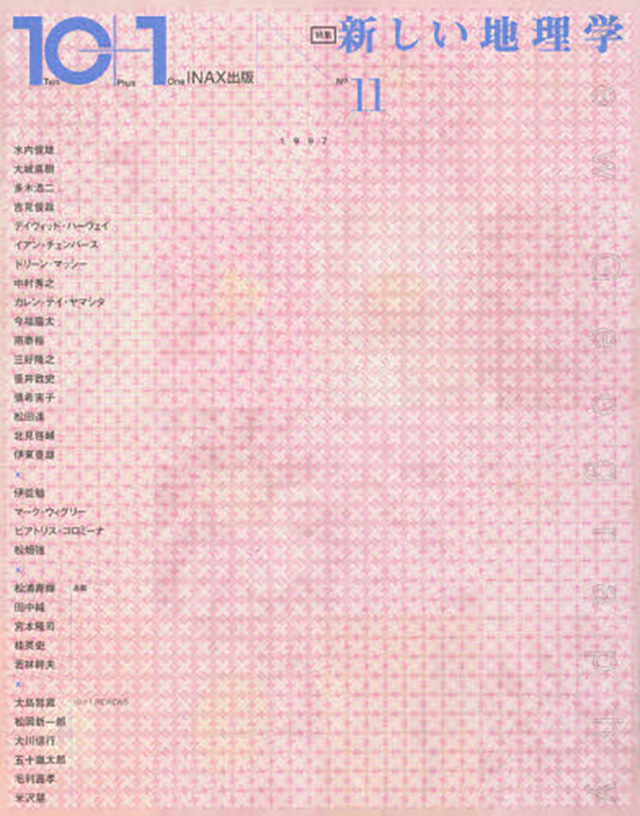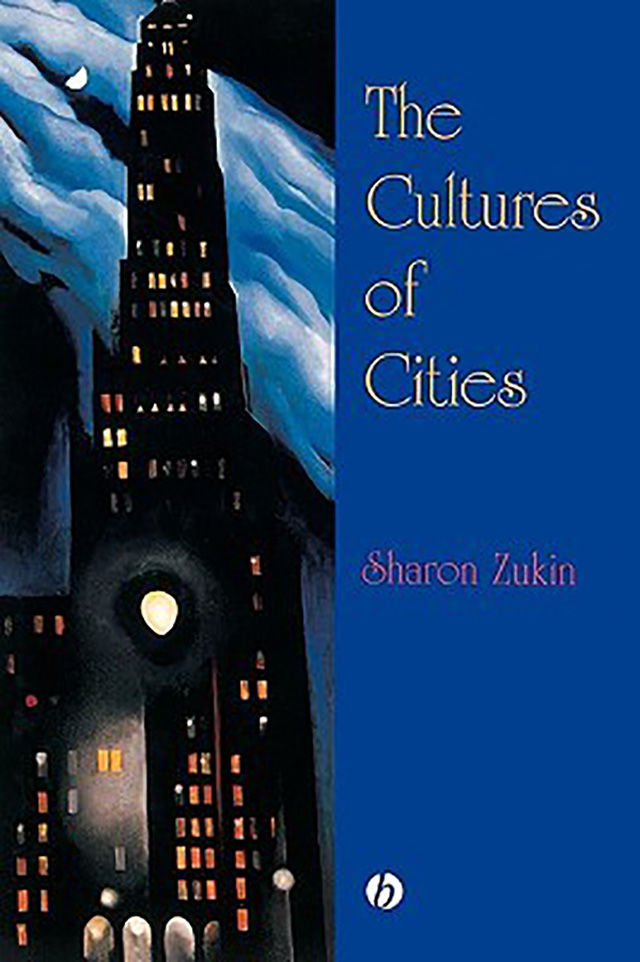進行形の都市研究を立ち上げる──プラネタリー・アーバニゼーションは遷移、侵犯する
現代の地理学的な問題系
編集──平田さんと、「10+1 website」11月号でもご寄稿いただいた北川眞也さん(「『広範囲の都市化』が生みだす不均等な地理──後背地、ロジスティクス、地域闘争」)が論考を寄せられた『現代思想』2017年9月号の特集名には「地政学」(「特集=いまなぜ地政学か」)が冠されていました。地政学の問題を地理学のディシプリンで読むことも可能でしょう。だとすると、いま地理学こそが先行研究を超えて共有し、顕在化すべき問題系とはどういうものでしょうか。
平田──ご質問に対して、先ほどの仙波さんの制度的には何の専門家でもないという話の関連で言えば、私も地理学の領域において何者でもないわけなので、お答えするのは何だか躊躇します。しかし手前味噌な解釈かもしれませんが、地理学者でもない者が地理学的対象である場所や空間を語ってもいいということを、今回の特集に収録された大城直樹先生の論考(「ポストモダン地理学とは何であったのか?」)は論じてくれている気がします。『10+1』No.11(1997)の「新しい地理学」特集に収められた座談会の冒頭、日本で「文化論的転回」をリードされてきた吉見俊哉先生は、場所や空間を扱う地理学から刺激を受けていることを語っておられます。この座談会に参加し、「新しい地理学」、すなわちデヴィッド・ハーヴェイやエドワード・ソジャの名の下に語られる「ポストモダン地理学」を日本に翻訳・紹介した貢献者のひとりである大城先生は、ポストモダン地理学を実践したのは、デレク・グレゴリーだと語っておられます。というのもグレゴリーならびにポストモダン地理学の貢献とは、戦争と密接な関係にあった地理学というディシプリンのなかでレトリックとポリティックの関係を再考しながら、地理学的な対象である空間や地理を地理学の外にまで広げたことにあるからです。こうした理論的実践なくして、プラネタリー・アーバニゼーション研究もありえなかったでしょう。
グレゴリーが『地理学的想像力』(1994)のなかで行なったこうした試みと呼応するかたちで、フランスの人類学者マルク・オジェは、1992年に刊行された『非-場所──スーパーモダニティの人類学に向けて』(中川真知子訳、水声社、2017)のなかで、まさに地理学の外から地理学的な対象を扱っているのだと思います。オジェは、人類学の対象を現代のグローバル社会に広げて、いま・ここによって規定されてきた近代的な場所概念とは異なり、いま・ここと言うことができない一時的にのみ滞在するような日常生活の空間──メトロの駅、空港などのトランジット、巨大商業施設などの空間──を「非-場所」と名づけ、考察の対象にします。ルフェーヴルを参照しながら、時間や歴史を特権化した社会批判に対するソジャの「空間の再主張」が空間を理論的対象とする流れだとするならば、オジェは、グローバル化によって空間の変化がありふれたものとなり、それが経験的対象としても浮かびあがってきたことを示すのだと思います。
仙波──まさにオジェのタームで語れば、「スーパー・モダニティ」と形容できる現代社会において、近代を特徴づけていた「場所」に代わり、より抽象的な「空間」について人々は語るようになる、という話ですね。今の平田さんのお話は地理学というよりも地理学的対象である場所性や空間の変化それ自体を研究することが重要なのだ、というものだと思います。僕も同じように、専門家としては「何者でもない(nobody)」けど、都市を対象とする研究領域において「何者か(somebody)」でありたい。あくまでも自分の見立てでいえば、現行の都市研究には大枠として2つのタイプがある。ひとつはスコット&ストーパー的な考え方──都市-内-空間の本質的な構造に対応し、生産活動の集団/人々の生活集団としての「都市の二重の性質」を導出しようとするアーバン・ランド・ネクサス論 Urban Land Nexus──で都市を再定義していく、というそれです。アレン・スコットのほうはマイク・デイヴィスともかつて仕事をしていて、個人的にはLA学派の重鎮のひとり、という位置づけですけれど、スコット&ストーパーはポスト構造主義なんて知ったことかと論文のなかに書いていたりする(笑)。かなり論争的です。
2015年と16年に彼らは2つの論文をそれぞれ『City』と『IJURR』に掲載していますが、大雑把にまとめると、都市研究があまりにも多岐的、ないしは「蛸壺化」してしまった現在において、ひとつの「線」のようなものをもう一度つくることができないか、といった論陣を張っています。そこで都市理論の源流をロバート・E・パーク、ルイス・ワース、ハーヴェイ・ゾーボーといった人々に求め、そこから1960年代から70年代にかけてのマニュエル・カステルによる都市イデオロギー批判、その後の80年代以降のジェンダー的な都市研究、サスキア・サッセンの世界都市論、そしてブレナーのスケール論へと至る流れを手際よく整理している。
その系譜の先に、彼らは現在3つの係争点があると見立てています。1つめはポストコロニアル都市研究、2つめはANT(アクターネットワーク理論)からのアプローチ、そして最後がプラネタリー・アーバニゼーション論です。そのうえで彼らはその3つをそれぞれ徹底的に批判するのですが、その批判には面白い部分もあるにせよ、ではその代替案を出しきれているかというと微妙ですよね。論敵のひとりに配置されたアナンヤ・ロイというポストコロニアル都市研究に属する学者などは、彼らのことをまたもや徹底的に再批判しています。彼女はそのリプライのなかで「So what?(だから何なの?)」といった文言を何度もリフレインしながらやり返す。これらの応酬を受けて、ブレナーは2018年にもうそろそろ喧嘩はやめようぜっていう感じの調停を図ったわけです。
ですから、きわめて大雑把に言うなら、一方にはスコット&ストーパーに代表される、計量経済学的にアプローチする都市研究の流れがあり、他方にはブレナーらに代表されるプラネタリー・アーバニゼーションやロイに代表されるポストコロニアル都市研究や新たなジェンダー地理学などの流れ、その2つがあるのかなと見立てています。
平田──都市研究がこれまで辿ってきた歴史の見取り図をきれいに提示してくださったと思います。ブレナーは、スコット&ストーパーがやっているような都市の計量的分析を放棄するつもりはないと言っています。「喧嘩はやめようぜ」というのは、そうした背景を端的に示しているわけですね。ブレナーとシュミットは従来の区切られた領域における「高密度の都市化」だけでなく、「広範囲の都市化」、つまり地球規模で広がる都市化を見ていこうと主張します。そのときにブレナーとシュミットが依拠しているのは、ルフェーヴルが『都市革命』で示した、「都市の織り目(「英語:Urban Fabric」「仏語:tissu urbain」)=都市組織」などの概念を通じて都市化という過程に力点を置く考察です。この概念によって、ルフェーヴルは都市の交通網や情報網とそれを前提したライフスタイルが「都市的なもの」として、「織物」のように、あるいは細胞の集合体としての「組織」のように、都市ではない農村地域を編み込んでいくことを記述します。このような都市的なものが広がる過程に焦点を当てる分析は、ギリシャのポリス、ローマの都市、産業都市としてのロンドンといったマックス・ウェーバー的な都市の類型学とは違ったかたちで都市研究を推し進めるものです。
仙波──逆にスコット&ストーパーには、すごくウェーバー的なものを感じます。
平田──そのことは、2人が「広範囲の都市化」は存在しないと論陣を張る点で符号しますね。しかしポスト構造主義のレトリック云々という次元ではなく、素朴なレベルでも、広範囲の都市化というのは、すべてが従来の都市と農村という区分を超えて、どんどん巨大な交通網、情報網、エネルギーなどのインフラストラクチャーのなかに取り込まれていることを振り返っても、一定の説得力をもっているのではないでしょうか。
それともうひとつ、シュミットがスコット&ストーパーを批判するかたちで援用しているのが、ドリーン・マッシーです。マッシーは1993年の論文「権力の幾何学と進歩的な場所感覚──グローバル/ローカルな空間の論理」(加藤政洋訳、『思想』933号、岩波書店、2002)で、ある場所はどのように規定できるのかといったときに、その場所を超えて広がる人、モノ、情報、資本の関係性だと言っている。つまり、ローカルな場というのはつねにグローバルなものと不可分なかたちで結びついている。ブレナーが論文「都市革命?」のなかでカナダのアルバータ州の森林地帯におけるオイルサンド採掘を取り上げて、エネルギー産業による先住民の土地収奪を論じながら示すように、ひとつの都市だけを見ていても、いかに「非都市」と見なされていた後背地が都市経済のなかに組み込まれているか、もっと言えば従属させられているかを問うことはできない。そういう動きは、従来の高密度の都市化というモデルだけでは見えてこないわけですね。
仙波──今触れられた後背地にまで広がる広範囲の都市化とマッシーの理論に関して、それぞれさらなる論点が見えてきますね。前者の議論に関しては、本特集の渡邊論文がレイ・パール研究を通じて後背地を視野に入れた研究を進めようとしています。バールは、先駆的に都市と農村のあいだの曖昧さ、不分明さ、不明瞭さを分析対象とするのですが、その際に都市開発の担い手である組織主体に焦点を当てるネオ・ウェーバリアン的な新都市社会学に依拠します。こうした分析視角を導入することで、渡邊さんは、ブレナーらの研究には欠けていた主体の問題を提起しています。
マッシーについては、「権力の幾何学と進歩的な場所感覚」から引用すれば、場所は「ある特定の位置で一まとめに節合された諸関係の特定の布置」である、という部分ですね。このことをより広く見ればプラネタリー・アーバニゼーションの議論へつながっていきます。
マッシーが同じく「権力の幾何学と進歩的な場所感覚」に記す「場所に対する単一のアイデンティティの否定」という問題系も、プラネタリー・アーバニゼーションの議論を呼び込む素地があるように見える。彼女はこの論文で、場所、空間が生成されていくプロセスをどう捉えるかというときに、水平的思考に沿って考えるだけではなく、垂直的な構造として捉え返しながら、場所が複数の痕跡と現在の視点からの絶えざる読み替えや書き換えによって、プロセスとしてのイメージ=言説のダイナミズムに注視するよう呼びかけている。僕はそのように読みました。ですから、それは水平的にも垂直的な堆積としても、「場所感覚、『その特徴』の理解というものは、この場所を、その他のさまざまな場所と結びつけることによってのみ築き上げられる」。それは逆説的に、場所の単一性を否定する議論になっているのです。一側面だけを見れば、時間と空間の圧縮というデヴィッド・ハーヴェイの有名なテーゼに対する批判に終始にしているように見えますが、やはり場所という対象に対するきわめて批判的かつスリリングな議論が展開されている。だからこそマッシーの1993年の論文(邦訳=2002)はよく引用されるわけですね。
個人的に重要視しているマッシーのもうひとつの観点は、『空間のために(For Space)』(森正人訳、月曜社、2014/原著=Sage、2005)で行なっているミシェル・ド・セルトー批判です。セルトーは「戦略」と「戦術」を分けることの重要性を説いたり、地図を上から見ることを「問題」にしたりしますが、マッシーが言うにはそういうことは実は重要ではない。地図を上から見ることが問題だというのは、じつは僕のフィールドである広島でおおよそ2000年代から言われていたことで、米山リサという人類学者が『広島 記憶のポリティクス』(小沢弘明ほか訳、岩波書店、2005)で「同心円の想像力」という話をしているんですね。われわれはある場所をつねに同心円状にしか語ることができない。自分が爆心地から何キロ地点にいるかなんてことさえわからないのに、つい原爆を「落とした」人の視点から語ってしまう。それが同心円の想像力というもののきわめて粗雑な概要です。けど、マッシーはそうした視座自体は問題ないと言い切ってしまう。というのもそういった考え方自体が、「空間を時間の静的な一断面、表象、閉じられたシステム等々として考えること」であり、それらは「どれも空間を飼い馴らすための仕方である」からです。
僕がこうした考え方をもって広島と対峙するのは、この街が──いかなる都市空間もそうであるように──複雑かつ多様な痕跡をもってできあがっているためです。それこそ公文書館などに行けばわかりますが、毎年膨大な量の地図が残されている。つまり問題は、一枚の地図からのみでは思考しえないところにある。そういった量塊としての地図と現実のそれぞれのモメントはつながっているようでつながっておらず、われわれはその両方をキャッチ・アップすることができない。断面ではない、動態としての都市空間のプロセスを、いかなる視点から掴まえることができるのか。この問いに答えるための多くの示唆が、『空間のために(For Space)』のなかにはあります。
「広範囲の都市化」とロジスティックス──なぜ広島研究で理論が必要なのか
平田──よくわかります。いまの話から2つお話ししたいことが生まれました。1つはもう一度「広範囲の都市化」に戻る話です。いま大学の講義で学生から「難しい」と激しい憎悪と呪詛を投げかけられながらも(笑)、フランスの社会学者ピエール・ヴェルツの経済地理学に属する著作を読んでいます(Pierre Veltz, La société hyper-industrielle: le nouveau capitalisme productif, Paris, Le Seuil, 2017)。ちなみにこの著作は、日本でも最近翻訳紹介が進んでいる政治学者ピエール・ロザンヴァロンと歴史家イヴァン・ジャブロンカが監修する叢書「思想の共和国」から刊行されていて、この叢書は読者に本を読み切ってもらうことを意図しているので、ヴェルツの本もそれほど厚くないです。ヴェルツは、アラン・トゥーレーヌが提唱し人口に膾炙することになった脱工業化社会に対して、超工業化社会ということを主張しています。最初に工業化が起こったのち、社会が第三次産業としてのサービス産業へと移っていくというトゥーレーヌの議論に彼は強く反対する。むしろ現代社会の動向を見ていくと、工業とサービス業は結びつくというのです。それは何も経済に限ったことではなくて、きわめて地理にも関わるものです。そこで例として挙げられるのが、アップル社のiPhoneの製造工程です。よく知られているようにiPhoneの裏側には「Designed by Apple in California, Assembled in China」と書かれていて、頭脳労働と肉体労働の分業やiPhoneの売り上げの利潤率の分配が暗に示されています。彼が言うには、現代の社会システムというのは基本的にアダム・スミス以来の分業と変わらない。けれど、その分業が世界規模になっていることを想像してくれと言うわけです。それを可能にしたのは関税障壁の撤廃や情報化で、さらにそれが経済規模や市場サイズを大きく変える。そうした物の流れのマテリアルな基盤となるのは、港のコンテナ化であり、そこで重要な役割を果たしているのは、前回の特集に寄稿された北川さんの論考でも中心的に扱われていたロジスティックスです。2つともまさに今回の特集で原口さんが扱っているテーマです(「忘却された空間からの視角──ロジスティクスと都市のインフラストラクチャー」)。ヴェルツは、アップルの成功が、よく言われるようなデザインや技術的イノベーションによるものというよりも、かつて企業のなかで副次的な役割しか果たさなかったロジスティックスに戦略的な役割を担わせるようになったからだと述べています。それゆえ彼は、スティーヴ・ジョブズを引き継いだティム・クックが評価されたのは、まさに企業間の部品調達やサプライチェーン構築といったロジスティックスをうまくやったからだということを強調するのです。そうした社会システムのなかで、アップルはiPhoneをつくる際に、地理的に拡散した世界中の地域から最も安く、最も質がよく、最も速くパーツを納入できる企業を選ぶ。「あらゆる場所で買って、つくって、売れ」という効率的なロジスティックスの合言葉は、非常に流動的なかたちで、部品の調達から生産、販売に至るまでの一連の流れを組織して管理するということです。
こうなると、これまでのように国内市場の拡大を前提として機能していた「方法論的なナショナリズム」が機能しなくなる。アップルが儲かってもアメリカの工場は海外移転され、労働者に仕事はないのですから。そういったかたちで、グローバルな地理のなかで営まれる群島経済──飛び地をつないで動かすような経済──は、アメリカ国内で見た場合には、格差を広げることにしかならないわけですね。GAFAが税金を払わないということが問題視されますが、企業の最適化が社会の調和をもたらすわけではないということは現代の経済と地理の関係を見ても言えるわけです。このような製品の生産過程とそれを支えるロジスティックスに関するヴェルツの分析は、広範囲の都市化という問題系とも結びつく話だと思います。
それからもう一点は、もう少し仙波さん個人の研究に関わる話です。最初に仙波さんから共同研究をもちかけられたときに、なぜそんなに「理論」ということを言うのか僕はわからなかったのですが、『忘却の記憶 広島』(仙波希望ほか編、月曜社、2018)に収められている仙波さんの論文(「〈平和都市〉空間の系譜学」)を読んで、腑に落ちたところがあるんですね。私の解釈が間違っていたら修正していただきたいですが、この論文では「平和」や「復興」ということがどういうアクターによって、どういう歴史的状況のなかで論じ始められたのかを、一次資料を丹念に読み解きながら掘り起こしていき、次にそれが現実の空間にどのように投影され、実現されたかを検証し、最後にその結果として「平和都市」が実現したあかつきに、そこから排除されてしまう人たち──同書に収録されている別の論文のタイトルを引いていうと「そこにいてはならないものたち」(西井麻里奈「〈そこにいてはならないもの〉たちの声──広島・「復興」を生きる技法の社会史」)──の存在に光を当てています。
この議論のなかで仙波さんは、シャロン・ズーキンやフランスのブルデュー学派に属するシルヴィ・ティソなどの社会学的な著作を参照するわけですが、素朴な疑問として、なぜ1940〜50年代の広島を論じるのに、1960年代からロンドンやニューヨークを起点に始まるジェントリフィケーションに関する研究を参照するのかと思わなくもない。端的にこの時代の広島を分析するのに後の時代に展開した都市理論を応用するのはアナクロニックです。しかしよく考えてみれば、起きた現象としては、ルース・グラスが述べるような、都市中心部の開発のなかで労働者階級が排除されるという事態と同じことが広島でも起こっていたわけですね。『The Cultures of Cities』(Wiley-Blackwell、1995)で論じられたズーキンの議論を敷衍するならば、アメリカの連邦政府によって芸術家や美術館に対する支援制度が打ち切られるのと並行して、政治家のほうはリチャード・ニクソンのウォーターゲート事件以後、公共空間に働きかける力を低下させていく。そこで公共空間がどういうふうに再編されていくのかというと、美術業界が企業などと結びつくことで生み出されるわけですね。そのときに重要なキーワードとして出てくるのがズーキンの「象徴経済」と「空間の生産」であると仙波さんは書かれている。言われてみれば広島の復興というのはまさにシンボリックな次元を介して進められるのであって、そういう意味ではズーキンの議論とも非常に結びつくわけですね。こういう解釈で合っているでしょうか?
仙波──いま読み返すと赤面するばかりの拙稿を、そのようにていねいに読み解いていただいてありがとうございます。ご指摘いただいたとおり、自分が考えたいことはすごく単純で、「平和都市」はどういうイメージや言説によってつくり上げられ、どういうかたちで場所を規定していくのだろう、それらが往還するプロセスはどうなっているのだろうということです。つまり、「平和都市」はそもそもひとつではない。「平和都市」という言い方が広島の「根拠」として定着するのは1950年代後半以降のことであり、ある日突然平和都市になったわけではない。言い換えれば、1945年の8月6日には、広島は「平和都市ではなかった」はずなのです。それが平和都市に「なった」というのはどういうことだろうか。
それを最初に感じたのが、平田さんがフランスに留学される1年前の2008年に、Chim↑Pomが原爆ドーム上空に飛行機雲で「ピカッ」という文字を書いた騒動です。Chim↑Pomのメンバーである水野俊紀さんとはいまは飲み友達になっていますが。ともあれ、僕は、どうして「ピカッ」で人は怒るのだろうか、という素朴な疑問を当時抱きました。というのも、「ピカッ」という象徴がなんらかの侮蔑を意味しているという合意がなされていなければ、人は怒らないはずだからです。当たり前ですが、1945年の8月6日にはまだ「ピカッ」という言葉はありませんでした。一方で、同じくアーティストの蔡國強がその4日後に原爆ドームのすぐそばで黒い花火を打ち上げましたが、こちらは誰からも怒られない。僕は当時大学3年生でしたが、その「違い」を考えれば考えるほどよくわからなかった。ロバート・J・リフトンが言ったように、原爆という強烈なトラウマ的体験によって傷が疼くのだとしたら、むしろ蔡國強の作品のほうではないか。なぜなら原爆そのものを再現(リプレゼント)しようとしているわけだから。つまり、「ピカッ」という表現は、原爆体験のなんらかの表現のなかで、後天的に、事後的に形成されたものなのです。このような磁場/地場をもつ「平和都市」とはいったいいかなる言説、理念、象徴、そして都市空間なのだろうか。これが、私が「平和都市」について考えだすきっかけとなりました。
では、そのときになぜ広島という固有の対象に当てはまらない、多様な「都市研究」の成果を参照するのか。もちろんいくつかの理由があって、まずは「広島研究」というものがあるとするならば、誤解を恐れず言えばそれが現状行き詰まっているからだと思います。先述の『広島 記憶のポリティクス』が「広島研究」の嚆矢だとされ、そのあと集合記憶論的観点からの広島研究が花開いていく。しかし、記憶というのは数にもできなければ、簡単に変形してしまうものであり、ましてやAR(拡張現実)で簡単に再現できるものではないですよね。メディアが変われば、記憶さえも変わってしまうはずです。
広島は変動をつづけている。「ピカッ」が存在しない街が、それがある種「禁忌」となる街となり、中心地は幾度もリビルドされ、長岡省吾がこつこつ集めた遺品展示のために開かれたた原爆資料館では現在、被爆再現人形は撤去され、代わりに原爆投下にまつわるCG映像や先端のメディアテーブルが配置される。端的に被爆の前からも、後も、そしていまも、世界史体験に遭遇した広島という街はつねに変動しつづけているわけです。
だからこそ、中にいながらも、より普遍的な視点や理論に開かれていく必要がある。中にとどまりながら、つまり対象とするフィールドにしっかりと足を置きながらも、外に/外との関連で何があるのかを考えなければいけない。それこそがいま広島を研究するわたしたちに求められる姿勢なのだと考えています。先述のアナンヤ・ロイによるスコット&ストーパーに対する再批判のなかでは、「〔彼女のフィールドである〕カルカッタのような場所から都市理論をつくりあげることはできるのだろうか」「都市理論はカルカッタのことを説明できるのだろうか」と問いかけています。同様に、きわめて特殊かつ普遍的な広島という街をもう一度考えるためには、地球規模で展開される都市研究を参照する必要が大いにあると思うのです。
比較的最近でいえばラン・ツウィゲンバーグというユダヤ系アメリカ人の研究者が書いたもの(『Hiroshima: The Origins of Global Memory Culture』Cambridge University Press、2014)など「歴史書」としてすごく面白いものはあるのですが、それ以降、では何があるのかと問われれば返答に困ってしまう現状がある。他方で、先ほど平田さんが論文タイトルに触れた西井さんや『「不法」なる空間にいきる──占拠と立ち退きをめぐる戦後都市史』(大月書店、2019)を書かれた本岡拓哉さんなど着実に新しい世代が出てきつつあり、旧来とはまったく異なる視点、アプローチでやっていこうという流れもある。そのなかで、たまたま僕は広島という「都市」のことを考えたいと思った。昔のことだろうと言われればそれまでですが、いまに連綿とつながる都市の「過去」をどう考えることができるのか。都市研究とはその繰り返しだと言ったのがまさにマッシーであるという視点から、自分自身はひとつの実践としてこうした思考を行なっていこうと素朴に思ったわけです。
ここには都市の一般性・普遍性と固有性をめぐる問題があります。たしかにこの場所にはこの場所の歴史があって、それは交換不可能なものである。けれども他方で、先ほどの平田さんのプラネタリー・アーバニゼーションの議論で言うならば、その外には至るところに「飛び地」があって、けっして無関係の外部ではいられないわけですよね。こうした都市のアンビバレンツな側面を考えていったときに、僕は広島のことだけを考えるのでは広島のことはわからないと思うようになった。それが都市を考える視点、つまり「理論」という道具立てをつねにキャッチ・アップしなければいけない理由なのだと思います。
- ルフェーヴルから辿れるもの、切り開かれるもの/進行形の都市研究を立ち上げる
- 現代の地理学的な問題系/「広範囲の都市化」とロジスティックス──なぜ広島研究で理論が必要なのか
- ジェントリフィケーションが示唆するもの/「プライベート化」の進展/ジェントリフィケーションとクリエイティブ・シティ/「プラネタリー」という形容が意味するもの