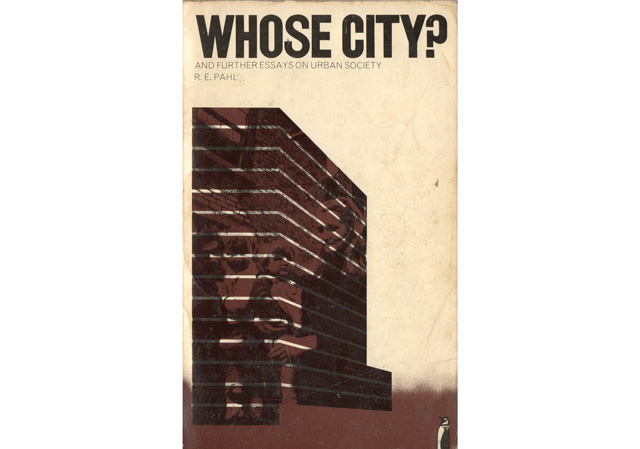都市はだれのものか?──レイ・パールの都市社会理論の現代的再構成に向けて
都市はだれのものなのだろうか? いっけん自明で、素朴にみえるこの問いに答えることは、かならずしも容易ではない。本稿は、"Whose City?"という問いを書名に掲げた英国の社会学者レイ・パール(Raymond Edward Pahl, 1935-2011)の都市社会理論の検討を通じて、こんにちの都市問題を考察するための手がかりを得ることを企図する。パールの都市社会理論のなかでも、とくに本稿では、(1)都市-農村、都市-郊外といった境界領域にみられる「あいまいさ」「拘束要因」「固有性」への着目、(2)アーバン・マネジャリズム論(Urban Managerialism、以下"UM論"と表記)を中心にみていきたい。
これまで社会学、地理学といった領域を中心に展開されてきた日本の都市研究、とりわけ新都市社会学の受容について、アンリ・ルフェーヴル、マニュエル・カステル、デヴィッド・ハーヴェイらがあまた参照されてきたのとは対照的に、パールの都市社会理論は、後述する一部の社会学者による仕事をのぞけば、その重要性に比して参照される機会が多くなかった。しかしながら、1960年代から70年代にかけての英国社会を対象としたパールの都市社会研究とそれにもとづく都市社会理論は、近年の都市研究の主流をなすプラネタリー・アーバニゼーション研究を推進していくうえで多くの示唆に富んでいる。本稿では、パールの都市社会理論がもつ現代的な意義を提示するとともに、プラネタリー・アーバニゼーション研究をはじめとするこんにちの都市研究への接続/応用可能性を考察したい。
パールの都市社会研究の軌跡と要諦
まず、パールの社会学者としてのキャリアを簡潔にみておこう★1。ケンブリッジ大学で地理学の学士号、修士号を取得したパールは、1959年に同大学のレジデント・チューターとして採用されて研究・教育にかかわることになる。具体的には、マネジャー・コース(官民の管理職の再教育コース)で会社員、公務員を対象とした教育に従事した。ここで1960年代初頭に彼がたずさわった最初の本格的な調査が、ロンドン郊外に位置する通勤者居住地域の調査であった。ロンドンに通勤する人々が居住することによって、かつての村落から、都市とも農村とも表現しがたい地域へと変容したハートフォードシャーを対象として調査を実施することになったのである。この調査の結果からは、郊外化のプロセスには村落のあいだで相違があること、村落内の階層の構成比が異なっていること、村落が変容するプロセスには地域社会に蓄積されてきたさまざまな社会的資源が反映されていること、これらの社会的資源をもとに固有の変容過程をたどっていることが明らかにされている。
ここで注目すべきなのは、武田尚子が指摘するように、のちのパールの都市研究で繰り返し登場することになる「あいまいさ(ambiguity)」「拘束要因(constraint)」「固有性(distinctiveness)」といった鍵概念が、すでに研究キャリアの初期の時点で提示されていることである(武田 2009)。すなわち、ロンドン郊外の調査から、土地所有、住宅供給といった地方自治体の地域開発計画、ならびにそれぞれの村落の歴史に由来する「固有性」が、郊外化のプロセスの「拘束要因」として大きく影響しており、そこには定義不能な「あいまいさ」という特徴をみてとることができる。そしてこれらの特徴は、のちに展開されるパールのUM論にも引き継がれることになる。
アーバン・マネジャリズム論の展開
ケンブリッジ大学でチューター業務に従事するのと並行して、LSE(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)の博士課程(地理学)に進学したパールは、上述のロンドン郊外の調査研究内容を博士論文として刊行したのち、1960年代後半にケント大学に転職する。この頃からパールは、英国中央政府の都市計画、地域開発計画、地方自治体の行政にかかわりはじめる。行政・地方自治体の職員、デベロッパー、建築家、都市プランナー、そのほかの学術領域の研究者とともに都市計画、地域開発計画に関与した経験から、パールは都市の希少資源に関心をいだくことになる。
1970年、『都市はだれのものか?(Whose City?)』(1970)が刊行される。カステルが「都市の権力関係の研究にパラダイムシフトをもたらした」★2と評する『Whose City?』(以下『WC』と表記)では、階級の空間的分布の不均衡、中産階級と労働者階級のあいだに生じるコンフリクトといった都市問題へのパールの関心にもとづいて、ネオ・ウェーバー主義的アプローチ、アンディ・メリフィールドのことばを借りれば「ウェーバー左派」的なアプローチ(Merrifield 2013)から分析がなされている。
パールのUM論の着想は、ジョン・レックスとロバート・ムーアが提起した「住宅階級(housing class)」の概念に由来している(Rex and Moore 1967)★3。彼は「住宅階級」の概念を手がかりとして、住宅市場、公共サービスへのアクセスといったさまざまな資源を「生活機会(life chance)」という概念でとらえる。アーバン/ルーラルの境界領域では、コンフリクトが生じやすい。なぜならば、これらの境界領域には、中産階級と労働者階級が混在しているからである。この「生活機会」はさまざまな要因で「拘束」されるものである。都市の希少資源は、かならずしも平等に配分されていないからである。パールによれば、この「生活機会」をとらえるうえで重要な役割を果たすのが、都市システムの運営にかかわる専門職アーバン・マネジャー(urban manager)である。具体的には、地方自治体の公務員、地方自治体の首長、議員、都市計画プランナー、金融機関・保険会社の管理職、不動産業者、デベロッパー、ソーシャル・ワーカーなどの職業がアーバン・マネジャーとして挙げられている。パールによれば、都市ではアーバン・マネジャーが、行政手段をもって希少資源を配分するプロセスへ関与することにより、資源の配分に影響を与えている。ときにそれは「拘束要因」ともなりうるものである。
『WC』の第1版で発表されたUM論は、刊行後に批判を受けて、加筆修正のうえ、『WC』第2版で再定義されている(Pahl 1976)。『WC』第1版で大きな自己裁量権を有するとされたアーバン・マネジャーは、第2版では都市の住民と資本主義社会のあいだにあって資源の配置を決める「媒介者」と修正されている。さらにパールは、アーバン・マネジャーについても修正を加えている。彼はアーバン・マネジャーとゲートキーパー(gatekeeper)に分類したうえで、前者を相対的に強い権限と自己裁量権をもつ媒介的存在としての上級職員、後者を住民に身近な権力である下級職員と規定している(Pahl 1977)。パールのUM論の特徴としては、従来の都市社会理論が看過してきた都市の機会不平等の問題に焦点をあてたこと、都市官僚制にみられる権力の問題への分析視角を提示したことがあげられる。
現代の都市社会研究への接続/応用可能性
パールが1960年代から70年代にかけて展開してきた都市社会理論や都市をとらえる概念装置は、それから約半世紀ほど経過したこんにちの都市社会研究に、いかなる示唆を与えうるだろうか。近年パールの研究を再評価する機運が高まるなかで、たとえばレイ・フォレストとバート・ウィシンクは、パールのUM論を参照して現代都市の動向を検討している(Forrest and Wissink 2017)。彼らは現代の都市にみられる新しいタイプのアーバン・マネジャー、ゲートキーパーとして、国際金融資本やグーグル、アマゾンなどのIT企業を規定して議論を展開している。他方で、マギ・メイヤーは、現代の新自由主義的な都市の構造改革とニューヨークなどの都市にみられる社会運動を念頭において、パールの『WC』を参照している(Mayer 2017)。
これらの論者の検討をふまえたうえで、本稿では近年のプラネタリー・アーバニゼーション研究への接続/応用可能性を考察するという観点から、パールの都市社会理論の現代的再構成の可能性を提起したい。先にみたパールの都市社会理論にみられる「あいまいさ」「拘束要因」「固有性」への着目は、ニール・ブレナー、クリスチャン・シュミットらを中心として進められているプラネタリー・アーバニゼーション研究と親和的であると思われる。ルフェーヴルの都市理論にもとづいて、都市-農村、都市-郊外の境界領域が融解しつつある現代の都市化の定義を試みるプラネタリー・アーバニゼーション研究は、その理論的な基礎づけとともに、今後いっそう実証研究のプログラムとして推進される段階にある。平田周が指摘するように、ブレナーとシュミットによるプラネタリー・アーバニゼーション研究では、これまでの都市研究者が取り組んできた第1の都市化、すなわち人口、資本の集積を分析対象とする「高密度の都市化」に加えて、第2の都市化である「広範囲の都市化」が分析対象とされる(平田 2018)。「広範囲の都市化」で主たる分析対象となるのは、これまでは都市の「外部」と理解されてきた諸資源の供給元、物流などのインフラストラクチャーの場たるヒンターランド(hinterland、後背地)である。ブレナー自身が述べるように、プラネタリー・アーバニゼーション研究のなかで、ヒンターランドは重要な位置を占めているにもかかわらず、それを対象とする研究は端緒についたばかりである(Brenner 2016)。それらを緻密に分析するための有力な手法のひとつは、たとえば都市領域の「特殊性(specificity)」の生成に着目してシュミットらが進めてきた研究プロジェクトであろう(Schmid 2018)。
本稿で検討してきたパールの都市社会理論もまた、こんにちますます複雑さをきわめるとともに、その「主体」が不可視化されがちな都市問題を読み解くうえで大きな示唆を与えうるものである。とりわけ、アーバニゼーション、ジェントリフィケーション、ハウジングといった都市をめぐる問題の「主体」を明確にして批判的に考察するさいに、パールの都市社会理論と一連の概念装置はきわめて有用である★4。すなわち、それらは「アーバニゼーションを進める主体はだれか?」「ジェントリフィケーションを進める主体はだれか?」といった問いを考察するための手がかりとなりうる。パールがつむいだ都市社会理論から現代の都市を観察/考察することこそが、「都市はだれのものか?」という根源的で現代的な問いへの応答を可能にするにちがいない。
註
★1──パールの都市社会研究の足跡にかんする本稿の記述は、武田尚子の研究に多くを負っている(武田 2008,2009)。そのほかに重要な邦語文献として、パールの都市社会理論と福祉国家/ポスト福祉国家を関連づけて論じた西山八重子によるものがあげられる(西山 1986,1994)。また、生前のパールに行なったインタビュー調査にもとづいて、社会学者としてのキャリアを中心に彼の研究業績を検討したクロウと武田の論文も参照されたい(Crow and Takeda 2011)。
★2──2011年にパールが逝去したさいに、カステルが国際社会学会(International Sociological Association)RC21のウェブサイト"Remembering Ray Pahl"に寄せた追悼文による(International Sociological Association Research Committee 21 2011)。
★3──レックスとムーアは、英国バーミンガムの遷移地帯の移民労働者を対象とする調査を実施した結果、たとえ労働市場での状態が同一であるとしても、英国人と移民労働者のあいだには住宅資源へのアクセス、ひいては居住空間の不平等がみられることを明らかにするとともに、「住宅階級」の概念を提示している。
★4──都市の「主体」をめぐる問題の一例として、ここでは「国家のリスケーリング」論(Brenner 1999)をあげておきたい。資本蓄積の低下と財政危機によって存立基盤がゆらいでいる国家が統治の正統性を確保するために、都市・地域にたいする政策介入の空間的範囲の調整を行なっていることを説明したブレナーの「国家のリスケーリング」論は、ポスト福祉国家の権力と空間の関係をとらえる重要な概念として論じられてきた。その一方で、「国家のリスケーリング」論では、リスケーリングの「主体」がしばしば「あいまい」であることが指摘されている(齊藤 2014)。齊藤麻人の指摘は「国家のリスケーリング」論に限ったものではあるが、都市をめぐる問題の「主体」の明確化は、プラネタリー・アーバニゼーション研究の進展にあたっても免れない問題であろう。都市の「主体」を明確にするという問題の克服なくして分析概念の彫琢はありえまい。パールの都市社会理論と概念装置は、それらの問題を乗り越えるための橋頭堡となる可能性を有するものである。
参考文献
- Niel Brenner, "Globalisation as Reterritorialisation: The Re-scaling of Urban Governance in the European Union", in Urban Studies, 36(3), 1999, pp. 431-451.
- Niel Brenner, "The Hinterland Urbanised?", in Architectural Design, 86(4), 2016, pp.118-127.
- Graham Crow and Naoko Takeda, Ray Pahl's Sociological Career: Fifty Years of Impact, in Sociological Research Online, 16(3), 2011.
- Ray Forrest and Bart Wissink, Whose City Now?: Urban Managerialism Reconsidered (again), in The Sociological Review, 65(2), 2017, pp.155-167.
- 平田周「プラネタリー・アーバニゼーション研究の展開」(「10+1 website」2018年11月号
- International Sociological Association Research Committee 21,"Remembering Ray Pahl",2011.
- Margit Mayer, "Whose City? From Ray Pahl's Critique of the Keynesian City to the Contestations around Neoliberal Urbanism", in The Sociological Review, 65(2), 2017, pp.168-183.
- Andy Merrifield, "Intervention ? 'Whose City? The Parasites', Of Course...", 2013
- 西山八重子「都市資源の管理──福祉国家の都市自治」(吉原直樹+岩崎信彦編『都市論のフロンティア──《新都市社会学》の挑戦』有斐閣、1986)
- 西山八重子「ポスト福祉国家と新都市社会学の展開」(日本地方自治学会編『都市計画と地方自治』敬文堂、1994)
- 武田尚子「都市社会学からwork論への転回──Ray Pahlの軌跡とイギリス社会学へのインパクト」(『ソシオロジスト』10、武蔵大学、2008、19-49頁)
- 武田尚子『質的調査データの2次分析──イギリスの格差拡大プロセスの分析視角』(ハーベスト社、2009)
- Ray Pahl, Whose City? And Other Essays on Sociology and Planning, Longman, 1970.
- Ray Pahl, Whose City? And Further Essays on Urban Society, Revised and Expanded Edition, Penguin, 1976.
- Ray Pahl, "Managers, Technical Experts and the State," in Michael Harloe ed., Captive Cities: Studies in the Political Economy of Cities and Regions, John Willey, 1977.
- John Rex and Robert Moore, 1967, Race, Community and Conflict: A study of Sparkbrook, Oxford University Press.
- 齊藤麻人「『リスケーリング論』の射程と都市圏政策」(玉野和志+船津鶴代編「東アジアの社会変動と国家のリスケーリング 調査研究報告書」アジア経済研究所、2014、10-17頁)
- Christian Schmid, Journeys through Planetary Urbanization: Decentering Perspectives on the Urban, in Environment and Planning D: Society and Space 36(3), Pion, 2018, pp.591-610.
東京大学大学院博士課程。社会学。論文=「会社共同体にみる「コミュニティ」の諸相」(『地域社会学会年報』第30号、2018)、「都市計画家にみるコミュニティ概念の受容」(『日本都市社会学会年報』第35号、2017)、「日本社会におけるコミュニティ問題の形成過程」(『ソシオロゴス』第39号、2015)など。