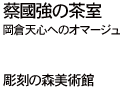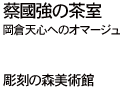| □ |
 ▲蔡國強展・茶室 ▲蔡國強展・茶室
「蔡國強の茶室−岡倉天心へのオマージュ」
撮影:村上慎二
※画像はクリックすると拡大します。
 
▲蔡國強展・茶事シーン
点前=千方可(武者小路千家)
撮影=村上慎二

▲蔡國強氏
|
.□ |
まだ梅雨空の晴れぬ7月初旬、小田急から登山鉄道を乗り継いで箱根山中へと向かう。5月末より彫刻の森美術館で開催されている「蔡國強の茶室——岡倉天心へのオマージュ」展を見に行くためである。確か連休直後ではなかったかと記憶しているが、拙宅に同展の招待状が届いた或る日のこと、私は開封した中身のチラシを読んで強い興味を引かれ、是が非でも出かけねばと思い立った。蔡國強と岡倉天心という取り合わせの意外さもさることながら、多くの野外彫刻が点在する彫刻の森美術館の広大な敷地の中に、茶室があることを今さらながらに知って、驚いたからである(実は箱根は私好みの観光スポットで、訪れるたびに同館にも足を運んでいるのだが、展覧会だけを目的に日帰りで出かけたのは実は今回が初めてだった。既に多くの展示品を見たことがあるにもかかわらず、妙に新鮮な気分だったのもそのためだろう。片道約3時間。観光地としてはほど近い半面、気軽に出かけるには遠く感じられる立地条件がなせる技なのだろうが、このような付き合い方をしている美術館は、ほかになかなか思い浮かばない)。
彫刻の森はなだらかな丘の上に位置する美術館である。入り口で手続きを済ませ、エスカレーターを下って屋外に出ると、多くの野外彫刻が点在する広々とした視界が開けるが、一見して茶室がどこにあるのかはわからないし、受付で配布された地図を見ても要領を得ない。「雲霓(うんげい)」と呼ばれるその茶室は、敷地の奥まった一角で茂みの中に身を隠すように立っていたのである。
この茶室は開館間もない1972年に設けられ、流派に関係なく様々な茶事のために用いられてきたそうだが、諸々の事情のために1997年の夏を最後に閉鎖されてしまったのだという。ただ美術館の側も茶室の閉鎖は残念に思っていて、なんとかこの独特の小世界を現代美術を発信するための「場」として活用する機会をうかがっていたところ、強い興味を示した蔡国強の協力を得ることができて、成立に至ったらしい。肌寒い11月に、作品の構想を練るために2泊3日でこの茶室に泊り込んだというのだから、蔡の意気込みがうかがい知れるというものだ。
蔡國強の名は、一般には爆破のスペクタクルによって知られているだろう。多量の火薬を用いた壮大なスケールの演出によって、しばしば「アジア的」とも「大陸的」とも称されるあのスペクタクルである。だがひっそりとした茶室のたたずまいを最大限生かすことを主旨とした今回に限っては、もちろんそのような刺激的スペクタクルは期待すべくもない。事実蔡はただ、茶室の襖や障子を取り払った以外には、茶室の造作そのものには全く手をつけなかった。茶室の壁には、庭にすえつけられた映写機によって勅使河原宏監督の映画『利休』の茶会の場面が延々と上演されているのだが、その不鮮明な映像と小さな音声はおよそ臨場感とは無縁だし、また庭に設置された赤、紫、青緑の舞台用スポット照明も、辛うじて木立ちの先端を色づけているに過ぎない。夜ともなればまた違うのだろうが、茶室の公開時間はまだ日の高い日中に限られてい
るので、光を用いた演出にはおよそ効果らしい効果は期待できないのだ。案の定、私の隣に立っていたカメラをぶら下げた老夫婦は、何か拍子抜けしたような面持ちで足早に茶室を去っていった。かくいう私にしても、お世辞にも刺激的とはいえない光の演出よりも、茶室を吹き抜ける微風の心地よさの方が印象に残ったくらいである。
ところで、この拍子抜けするような演出は、私にとっては大いに既視感を伴うものであった。昨秋の横浜トリエンナーレで、蔡は主会場のパシフィコ横浜の一角に、10脚ほどのマッサージ・チェアを円形に並べたその真上で、花火状の蛍光管を鮮やかに点滅させる風変わりなインスタレーションを出品していた。花火のスペクタクルは、リラクゼーションのツールへと転用されていたのである。また98年には、瀬戸内海の直島で、様々な國の観客が風水で設置場所を決めた湯船に浸かる「文化大混浴」のプロジェクトも実行していた。アジア的な混沌もまた、リラクゼーションの対象に転じていた。このように、蔡の花火のスペクタクルは、一見無縁と思えるほかのプロジェクトとも通底しているし、蔡がそのようなボキャブラリーを好むかどうかはともかく、その共通の関心は、「癒し」とか「ヒーリング」と呼ばれる環境との対話によって語られ、媒介されることになるだろう。そして茶室もまた、この共通の関心の一環を為しているはずである。
ただし、曲がりなりにもこの茶室プロジェクトを「展評」するには、ただ展示の様子や蔡の他の作品との関連付けだけで事足れりとせず、本展のもう一つのテーマである岡倉天心についても一瞥を与える必要があるだろう。実のところ、この展示を見るまで、私は蔡の天心に関する関心がもっぱら「東洋の理想」に向いているものだとばかり思っていた。福建省出身で、上海の大学で学んだ後で日本に留学、コンテンポラリー・アーティストとしての基礎を確立し、国際的名声を博するようになった今はニューヨークに拠点を構えるようになった。今なお西洋中心主義的な規範が幅を効かせるアート・シーンにあって、まるですごろくの上がりのような蔡のサクセス・ストーリーは大いに異彩を放っているが、当然その渦中にあって多くの理不尽な思いも経験したはずであり、恐らくはその経験が、ときには「Asia is one」と、ときには「ヨーロッパの栄光はアジアの屈辱である!」と述べる岡倉思想(考えようによっては、それはヘーゲルの「世界史」と見事な対照を成している)への関心へと連なっていったのであろう——私はおよそこのように考えていたのであり、またこのような「大きな物語」の理解の仕方は、それ自体決して誤ってはいないはずだ。だが少なくとも、この展示が「岡倉天心へのオマージュ」と命名された理由はこの「大きな物語」とはまた別のところ、すなわち、茶室という空間や茶道という儀式に潜む蔡の本質的な関心との接点と、その多大なヒントを孕んでいるであろう『茶の本』の著者・天心に対する深い敬愛の念にある。
茶の湯は、茶、花卉、絵画等を主題に仕組まれた即興劇であった。茶室の調子を破る一点の色もなく、物のリズムをそこなうよその音もなく、調和を乱す一指の動きもなく、四囲の統一を破る一言も発せず、すべての行動を単純に自然に行なう——こういうのがすなわち茶の湯の目的であった。そしていかにも不思議なことには、それがしばしば成功したのであった*。
『茶の本』のなかで、天心は各国の喫茶文化や茶室建築など、様々な角度から千利休を以って完成されたと目される茶道の解釈を試み、その本質を道教や神道からの影響によって独自に発達した禅仏教の精神性に見出している。上に引いた天心の説明には、まさにその精神性のエッセンスが凝集されている。そしてそれは、「一期一会」と呼ばれる茶道独自のコミュニケーションや、「シンプリシティ」と呼ばれる伝統的美意識のあり方にも対応していることまで述べれば、もはやそれ以上の説明は必要あるまい。刹那的で非再帰的なスペクタクル然り、リラクゼーションを基本とした環境との対話、剛直で繊細な美意識然りで、蔡の本質的な関心は、天心が解き明かした茶道の本質と深く共鳴しているのだ。カタログのテキストによれば、昨年11月に展覧会の準備のために「雲霓」に泊り込んでいた蔡は、その最中に武者小路千家家元の後継ぎである千方可の点前で喫茶したという。茶道の心得はなかったという蔡だが、その際に交わした様々なやり取りやアーティストとしての嗅覚によって、この茶室という空間が自分の関心を具現するのにもってこいの場所であることを直観していたはずである。
もっとも、ではこの展覧会が成功だったのかと問われれば、異見がないわけではない。「雲霓」での展示に当たって、蔡は「空間の完璧さを崩す」ことに最も留意したという。襖や障子を取り払った吹き抜けや、淡い映像や光の投影はそのための工夫だったというわけだが、茶室全体を作品に見立てたこのインスタレーションは、総じて茶文化への深い共感に支えられた控えめなものだっただけに、「空間の完璧さを崩す」という意図は必ずしも達成されなかったように感じられるのだ。『茶の本』において、天心は「茶室は簡素にして俗を離れているから真に外界のわずらわしさを遠ざかった聖堂である。ただ茶室においてのみ人は落ち着いて美の崇拝に身をささげることができる」*とも述べている。今回の展示によってもたらされる経験が、「空間の完璧さを崩した」この展示が、天心の言う茶室本来のオーソドックスな在り方と本質的なレベルで違っているなどとは、私にはどうしても思えないのだ。
*『茶の本』の引用は岩波文庫版による。
彫刻の森美術館 URL=http://www.hakone-oam.or.jp
蔡國強の茶室——岡倉天心へのオマージュ展/2002.5.25〜2002.9.23
|