|
||||||||||||||
| 渡辺聡の作品は無数の白い点(ドット)で切り抜かれた風景が描かれた、不思議な魅力をたたえた作品である。そこに対面したときの不思議な感覚は、たとえれば目にゴミが入って目の前が霞んだような感じだろうか。この奇妙さを考える前に、これらの作品の制作過程の説明から始めたい。 まず白いキャンバスに直径1cm程度(作品によって多少大きさが異なる)の白いドットのシールを碁盤目状に貼り込み、その上に絵を描き、次にそのシールを一枚一枚ピンセットで丁寧にはがす。すると、その絵の上に規則的な白い水玉模様が表われる。 ここで選ばれている題材には有名な美術館建築が多く、どれも観光写真や建築写真のようでもある[図1]。たとえば、ルーヴル美術館のガラスのピラミッドや大英博物館、なかには今回の展示会場となった三鷹市芸術文化センターもある。これらは美術館であるため、おそらく鑑賞者にとって最も近しい建築であり、決して珍しいものではない。それゆえになおさらそこに描かれている風景よりもドットという形式が注目されることになるだろう。 ニコライ・ハルトマンによると、芸術作品は重層構造をなしており、現実に実在している前景層と非現実的な後景層とがある。これはごく単純に言えば、絵画においては、前景層が絵の具ののったキャンバスであるのに対し、そこに描かれている風景なり人物が後景層に相当するということになる。前景層、後景層は共に芸術作品の持つ一側面であるが、芸術作品の本質は、後景層にあるといえよう。しかし渡辺の作品においては、この異なる層のずれあるいは異なる次元が、もっと複雑に現われている。画面上の色彩の層がハルトマンのいう前景層とすると、その剥がしたドットの内側に見られる白いキャンバスは、なにに相当するのだろうか。前景層のさらにひとつ手前の層と言ってもいいかもしれない。なぜドットという形式で制作しているかという問いに対して、作者は次のように答える。「ドットのシールを抜いていくと違う次元の表面ができる。剥がした後の白い部分と描かれた部分の微妙な段差が肉眼で確認できるんですよね。それが観念的にも興味深いし、視覚的にも刺激があって不思議な見え方をする」★1。実際、ドットによって切り抜かれた隣接する2層間には0.2mmほどの厚みが確認でき、ここで風景が風景ではなく物理的な存在として確認される。 また、画像から言えば風景が明らかに図であるのだが、造形的に見るとその逆で、ドットを図として見ることもできる。つまり、ドットの形がきれいな円形であるがゆえに、両者の関係はあたかも反転するかのように入れ替わり、図と地の奇妙な依存関係が現われるのだ。そしてドットの配列により、風景の上に人物や家などを描いた作品は、この二重性をさらに顕著に示している[図2−4]。剥がしたドットの内側に見られる白いキャンバスは、物理的には色彩面の背後にあり、しかし時間的には色彩面に先立つ。この重なり合う二つの面は、全く別のレベルであるはずなのに、シールを剥がされることにより、潜んでいた地の要素が画面の背後から突如として現われ、さらには水玉模様となって自らが図であるかのように振る舞い、絵画面を浸食するのだ。 ところで写真と絵画の違いとは何だろうか。まず、絵画は模写することによってしか複製できないのに対し、写真はいったん像を陰画として捉え、それを陽画に変換して焼き付けることによって何枚でも正しい像を得ることができる。この陰画と陽画との関係は、版画における原版と刷られた作品との関係にも似ているが、写真の場合は、密着から引き延ばしまでいろいろなサイズの同じ画像を得ることができる。あるいはフィルムを焼き付ける際、左右逆にすることにより、裏返しの像を得ることもできる。すなわち、ここには陰と陽のみならず、オリジナルと異なる大きさ、あるいは鏡像のペアなど、多様な二重性が存在している。一方渡辺の作品にも、類似の二重性が見られる。ひとつの作品をつくる際に剥がしたシールをもう一枚のキャンバスに貼り込めば、水玉の色柄が反転した2次画面が出来上がる。2次画面に貼る際に左右を逆にすれば、鏡像対称の図柄にすることもでき、拡大、縮小も自由自在である[図5、6]。あるいは、極端にはランダムに並べて全く意味を成さない画面をつくることも可能である。しかし中でも特に奇妙なのは、整列せず、かといってランダムでもなく、やや乱れるように貼られた二次画面である[図7]。そこには現実の世界が故意にゆがめられて再構成されたような、そこはかとなく不確かな世界が現われる。それは、印象派の例えばスーラの点描画に見られる浮遊感にも似ているかもしれない。 ここで美術史を振り返るならば、写真の出現によって、絵画は大きな岐路にさしかかったと言えるだろう。正確に本物らしく描くことにかけてはもはや写真にかなうわけもなく、画家は新たな道を選ばざるをえなくなった。そのなかで印象派のような、全く異なる描写方法が生み出されると同時に、複製芸術にはない一回性が強調された。 一方の写真は逆に印刷物として大量に複製されることにより社会に普及する。ただし、ここで印画紙の写真と印刷写真には小さな断絶があることに注意したい。印画紙の写真が隙間なく一面に連続する色彩面だとすると、印刷写真は白い画面に規則正しく並んだ色鮮やかなドットの集合体である。印刷写真を拡大コピーすれば、それはあたかも渡辺の一連の作品のごとく整列したドットが現われるだろう。 つまりここでは、二重の意味で写真が模倣されている。渡辺の作品では描かれる風景が紋切り型の観光写真ならば、その表現形式はまるで印刷写真なのだ。しかし印刷された写真とは異なり、その渡辺作品のドットは画面そのものの一部が物理的に第二の画面に移植されたものであり、いわば身を切り売りしているようなもので、写真のようにいくつでも複製が作れるわけではない。1次画面と2次画面のワンペアのみ。こうして絵画の持つ一回性は、奇妙な形で守られた。 渡辺の作品に対峙したときにまず感じる、眼の前のぼやけた感じとは、どこにピントを合わせていいのか一瞬分からないことからくるのかもしれない。ただし、ここでずれているのはその像の物理的なピントではない。今見るべきものは何なのかという観念的なピントとでも言えばいいのだろうか。図と地の反転。同一面に描かれた二つの画像。そして絵画のような写真のような形式。いくつもの二重性の中でいつまでもピントが定まらない。 一方、マクシム・デュ・カンは19世紀に生きたフランスの文学者である。彼は数編の小説を残し、またジャーナリストとしても活動した。しかし、今日ではむしろ『ボヴァリー夫人』を著したフロベールの友人として、また東方の遺跡を初めて写真に収めてヨーロッパに伝えた写真家として、その名が知られている。彼は1849年から50年にかけて、当時まだ無名だった友人フロベールを伴い東方を旅行し、その1年半の間に2000枚もの写真を撮った。そして帰国後、その中から125点を選び、写真集『エジプト・ヌビア・パレスチナ・シリア』として出版した。写真がまだ一般的ではなく、また東方の風物も未知のものだった時代である。当時の社会で驚きをもって受け入れられたであろうこの一冊の写真集の全点が、2001年3月に三鷹市芸術ギャラリーで展示された。 現代の我々から見ればどれもが風景絵画とみまがうような構図だが、デュ・カンにとって自分の撮影する写真は美術作品ではなく、あくまでも考古学的な資料であった[図8−10]。彼の目的は未知のものを、広くそして正確に人々に伝えることだ。ほとんど全ての写真には、遺跡の傍らに豆粒ほどの大きさの人間の姿が写し込まれ、巨大な遺跡のスケールを、本物を見たことのない人にも正確に伝えようという工夫がみられる。 ところで、彼はわざわざこの旅行のために、当時まだ一部の専門家のものであった写真技術を専門家ギュスターヴ・ル・グレー(1820−1882)から学んだ。というのはそれより5年前の初めての東方旅行を振り返り、こう考えたからだ。「この前の旅行では記憶に残しておきたいと思う記念碑や眺望はいちいちスケッチしていたので、ずいぶん貴重な時間を無駄にしたと思った。(…中略…)それに、建物でも風景でも後に描写するためにと思ってとっておいたメモのたぐいは、距離を置いて読み返してみると混乱しているように思え、正確な再構成を可能にするイメージを持ち帰るためには、精密な器具が必要なことを痛感していたのである」★2。つまり、彼はなによりも時間の節約と正確な描写力を写真技術に求めていたのである。 確かに映像を正確に写すことに関しては、写真はスケッチの比ではない。その圧倒的に正確な描写力は「対象が尿瓶であろうが煙突掃除人であろうが、あるいはベルベデーレのアポロであろうが、いっさい差別せずに、それらを描き出」してしまう★3。また当時の技術では、今日のように一瞬のうちに撮影することは不可能だとしても、紙と鉛筆でスケッチするよりははるかに短時間であったことは明らかである★4。デュ・カンのどの写真を見ても、まるで時間が停止した一瞬に焼き付けられたかのようにみえる。実際には何枚かの写真のかすかにぼやけた木の枝が、そこに吹く風と露光時間の長さを示しているのだが。 しかし、この比類ない速度と正確さの代償は軽くはなかった。それどころか写真技術にしろ、旅行中に撮影するための機材にしろ、その煩雑さは今日の比ではない。「そのころ、グタペルカ製の容器はまだ知られていなかった。そこでガラスびんや水晶のフラスコや磁器製の鍋などを使わざるを得なかったのだが、これらは一旦事故ともなると粉々になってしまう。そこで私は、まるで王冠のダイアモンドでも入れるような小箱をつくらせることにした、そして何度も行われた荷物の積み換えの際の衝撃を緩和して、何ひとつ壊すことなく、オリエントを旅する途中で見たさまざまな記念碑の写真の焼きつけを、初めて無事ヨーロッパに持ち帰ることに成功したのである」★5。 考古学資料作成のためのスピードと正確さを求めていた彼にとって、写真は夢を叶える理想の道具であり技術であったはずだ。少なくとも旅を始めるまでは。しかし旅の終わりには、何かが変わっていた。一年半もの間、遺跡の中をさまよい2000点ものショットをカメラに収めながら、彼はなにを考えたのだろうか。多量のガラスびんやフラスコ類を持ち運ぶことの不便さに耐えかねたのか。それとも写真そのものに対する興味を急速に失ったのだろうか。とにかく、宝石並のデリケートさで扱われ、あれほどまでに重宝したはず撮影道具は、結局どれひとつフランスに持ち帰ることはなかった。それどころか旅の終わりにその一切をベイルートで処分したのちには、彼は二度と写真家ではなかったのである。 |
  図1=ビーム・インビーム・アウト Beamed in beamed out 1999 (set of 2)
図2=プレハブハウス Prefab House 2000 図3=透明なおともだち An Invisivle friend 2000 図4=エステート・カー Estate Car 2000   図5=ルーブル美術館 Le Musee' du Louvre 2000 (set of 2) |
|||
  図6=テート・モダン Tate Modern 2000 (set of 2)  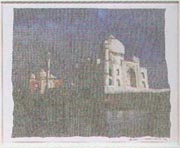 図7=タージ・マハル Taj Mahal 1999 (set of 2)    図8=トトメス4世の命令で造られたスフィンクスの正面像 (第18王朝) 図9=カルナック、コンス神殿の列柱 図10=イブサンブール、ラメセス2世大神殿、中間の巨像(砂に埋もれている)
1——作者インタビューより(『渡辺聡展カタログ』、荒木夏美編、三鷹市芸術文化振興財団発行、2001年) 2—— マクシム・デュ・カン『文学的回想』、戸田吉信訳、冨山房百科文庫30、冨山房発行、1980年、130頁〜131頁 3—— ダグラス・デイヴィス「Introduction」水上峰雄訳、(『世界写真全集第1巻』、集英社発行、1982年) 4——彼自身の回想によれば「使用する化学薬品とレンズの力がどれほど強くても、光線の加減が申し分ないときでさえ、少なくとも二分間ポーズをとっていなければ像が浮かんでこなかった」。マクシム・デュ・カン前掲書、131頁 5——マクシム・デュ・カン前掲書、131頁〜132頁
小倉孝誠「オリエントの誘惑−マクシム・デュ・カンの東方紀行」(浅倉祐一郎+(財)三鷹市芸術文化振興財団編『マクシム・デュ・カン—150年目の旅—展 カタログ』マクシム・デュ・カン展実行委員会発行、2001年)
図1〜7——『渡辺聡展カタログ』(三鷹市芸術文化振興財団発行)2001 図8〜9——『マクシム・デュ・カン—150年目の旅—展 カタログ』(マクシム・デュ・カン展実行委員会発行)2001
●渡辺聡展——隠された風景 2001年3月3日(土)〜3月25日(日) 於:三鷹市芸術文化センター 主催:三鷹市芸術文化振興財団 ●マクシム・デュ・カン—150年目の旅—展 2001年2月10日〜3月25日 於:三鷹市美術ギャラリー 2001年6月8日〜7月4日 於:せんだいメディアテーク 2001年12月1日〜2002年1月27日 於:伊丹市美術館 |


