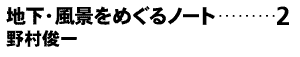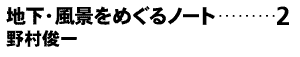 |
地下の標識、地上の光景

|
|
■大手町駅
|

|
大手町駅にはざっと列挙するだけでも、営団丸ノ内線、営団東西線、営団千代田線、営団半蔵門線、都営三田線の駅が交差し、複合している。そしてこの複合体は、地下道を伝って二重橋前駅、日比谷駅、有楽町駅、銀座駅、最終的に東銀座駅まで、地上へ出ることなく徒歩で移動が可能な長大な場となっている。
この長大な複合体は帝都高速度交通営団と都営地下鉄(東京都)の管理下にあり、またそれぞれの駅を結ぶ地下道は、都の交通
計画局により計画された箇所とそうでないところが交差し複雑な構造になっている。さらにこれらの地下鉄駅や地下道は何度も補修を繰り返されているため、どの箇所がどの設計主体により、どの時期に設えられたのかということを確定することが困難である。実際、地下道の壁面
や天井、床は様々な材料で設えられており、一定のデザインコードがあるとは決して思えないくらいだ。継ぎ接ぎされ続け、全体を把握することが困難な地下道。 |
■地下の標識、地上の光景
|
|
このような状況で、地下道に設置されている標識にはフォントや色、大きさなど統一感のあるデザインが(ごく一部を除いて)施されており、地下道の中でも妙に目立っている[fig.1]。この標識は地下道に設置されている地図とワンセットで機能する。地下と地上を表象した地図はコンテクストとして捉えられ、標識は初めて歩行者のナヴィゲーターとなる[fig.2]。
歩行者は標識・地図をもとに地上へ出る。しかし、標識・地図による経験と地上の光景との差に遭遇するだろう[fig.3]。なぜなら標識・地図の情報と地上の光景とでは、情報の質が異なるからである。標識・地図をもとに、これから行くであろう地上の光景を想像し目標を定めるとしても、その差を完全に埋めることはできない。故にさまざまな想像が可能になるとも言える。出口の先に何があるのかという不安と期待。 |
|
   |
|
 |
|
| 地下の標識にはほかにも写真と文字による「フォト インフォメーション」[fig.4]と名付けられたものがある。それは標識・地図の情報と地上の光景による経験の差を埋めるかのように、類推を促し、想像の矛先を定める。にもかかわらず、「フォト
インフォメーション」による類推と出口に至ったときの印象との違いに驚く。地下に設置された写
真は出口からの眺めを撮ったものではなく、別の場所から出口を撮ったものだからである[fig.5]。それを確認するためには、写
真を撮った視点をしばらく探し求めなければならない[fig.6]。しかし写
真と似ている光景を探し当てたとしても、レンズと実際に見える画角の違いは形象が似ている/似ていないという判断を越えて、完全に埋めることができない。かろうじて、「似ている」と言うしかないのだ[fig.7]。なぜなら写
真が打ち立てるのは「対象がそこにあるという知覚ではなく、そこにあったという知覚」(ロラン・バルト)であるために、ここにおいても「フォト
インフォメーション」による情報と地上の光景とでは情報の質が異なるのである。「かつて」の光景を撮った「ここ」にある写
真は、今の光景とは違うのだ。 |
   |
|
  
|
|
大手町駅周辺の長大な地下をめぐると、地図や写
真を含めて標識の多さに気づく。それにもまして、地下の標識による経験と地上の光景による経験との差には驚きを隠せない。それらがもたらす差を埋めようとすればするほどなおさら不安と期待が生じる。
しかし、この事態はひとえに、地下/地上という前提によって引き起こされるとも言えないだろうか。全体を把握することの困難な場であるにもかかわらず、地下/地上という判断のもと、なぜ今いるところを「地下である」と想定してしまうのか。なぜこの判断が要請されたのか。 |
|
■地図のない文字に対する処方について
|
|
大手町駅周辺の長大な地下道には、全く異なる出口に対して同じ文字による標識が存在する[fig.8,9,10]。まるで同じ文字がその場に寄生するかのように。この事実を理念的に捉えようとすると混乱してしまう。行為の手がかりになると思われていた標識が重複すると、その配置計画に一定のコードを見出せず、全体の認知地図の構想が困難になるからだ。しかし、歩行者は近辺に限っては迷うことがないだろう。再び、新たな地図を別
の場所で発見するからだ。同じ文字は新たな地図のもと再び標識としての機能を担い、やがて標識はそれぞれ異なる出口を示すだろう。
一方で再び地図を詳しく見ると、それは地下道全体ではなく部分を表象しているにすぎない。そして、一枚の地図上では標識が重複していないので、その中に限り標識の配置計画は矛盾しない。つまり地図は部分的であるがゆえに機能する。またこれら地図はそれぞれ離れて設置されているため、全部を同一の場所で見ることができない。このことは、歩行者が地図の範囲外で「A1」などの標識に遭遇したとき、別
の地図を発見するまで「A1」が何を指示しているのか理解できないという事態を引き起こす。
このような事態は地下に限らず地上でも十分起こりうる。「A1」という文字は日常生活においてよく目にするし、かつその文脈が見つからない場合「A1」が何を指示し、何を意味しているのかわからないということにしばしば遭遇するからだ。地上でも地下でも、地図や文脈が見つからない限り文字は文字であり、意味を理解することが難しい。
地図や文脈を発見できない時の文字に対する不安は、同時に歩行者のいる場所をも喪失させる。そしてこのときにこそ、地下/地上という文脈が要請されるのではないか。つまり歩行者は、自分の位
置を喪失しながらそれでも現地点を把握するために、無理矢理「そこが地下である」と言いきかせ、ひとまず安心感を得るのだろう。 |
|
   |
|
 |
|
地図=文脈のない文字が引き起こした、現在地の喪失という不安。歩行者はこの不安を解消させるための処方のひとつとして、地下/地上という上位
の文脈を要請し、「A1」という文字を地下で機能するものとして解釈した。そしてこの上位
の文脈こそが地下の標識と、地上の光景との差を生じさせたと言えるのではないか。
しかし地下/地上という判断は、それが意識の所作によるものであるがために絶えず揺らぐだろうし、さらに歩行者は別
の文脈を想定することもできる。地下/地上という判断基準に必然性はなく、文脈は遡及的にいくらでも拡張しうるからである。ここは地下にも地上にも、そして他の場所にもなりえるのだ。
フィールドワークを始めたころ、同じ場所でも行くたびに印象が変わっていたが、このような文字に対するその都度の処方が理由のひとつになっていたのではないか。そう考えると、前号で書いたように地下は決して「退屈だ」とは言いきれない。文字にとどまらず大手町駅周辺の場にあるそれぞれの要素は、私たちの解釈を絶えず待っているからだ。
|
|
| |
|
▲TOP
← SERIES →
■HOME
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|