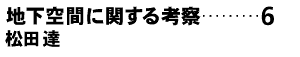
地下空間としてのメトロポリス
インテリア都市とビッグネスは、どちらも巨大化した建築物における外形と内部空間の古典的関係の消滅を指摘している。地下空間も同様に外形と内部空間の対応関係が消失した空間である。逆に言えば、外形と内部空間の対応関係が崩れた空間は地下空間的特性をもっており、そのため例えば東京のようなメトロポリスにおいては、地上空間そのものが地下空間化していると言えるだろう。これが出発点であった。
第2回「 underground、5冊の写真集をめぐる冒険」では、写真集を取り上げた。本論とのロジカルな関係では、特に中野正貴の『TOKYO NOBODY』と金村修の『SPIDER'S STRATEGY』に注目した。
『TOKYO NOBODY』の風景は、人々が活動する内部空間から剥離した外皮だけの東京のようだ。人が消えることによって、東京自体が巨大建築として立ち現われる。エクステリアだけの都市。それと対照的に、『SPIDER'S STRATEGY』の風景は、外皮が意味を失った雑多な東京の風景だ。ゴミ捨て場のゴミのようにすべてが等価になったジャンクスペース。インテリアだけの都市。
どちらも地下空間的な地上空間であり、形式と内容が一致しない。ここからメトロポリスについて考えた。巨大化することによって形式と内容、外部と内部の対応関係が溶解してしまった都市をメトロポリスだと定義した。ビッグネス、ジャンクスペース、インテリア都市、地下空間、どのように呼ばれようと、それらはいずれも巨大化して収拾のつかなくなったメトロポリスを指し示そうとする言葉であるに違いない。形式と内容が古典的関係を保っている都市=ポリスに対して、その対応関係が溶解してしまったのが巨大都市=メトロポリスである。
第3回「 堤防的、放水路的」では、首都圏外郭放水路を取り上げた。具体的な地下空間を取り上げたにもかかわらず、実はこの回の内容は、本論の展開から外れている。ここで思考されたのは計画概念に関する問題だった。起こりうる事故を事前に抑圧して回避しようとする計画を堤防的計画と呼び、逆に事故を抑圧することなくそれが起こった時に作動するような装置を設けておく計画を放水路的計画と呼んだ。
この区分が示唆するのは都市と自然との関係だ。都市の中に不可避的に入り込む自然をスタティックなものとして閉じこめようとする計画が堤防的計画であり、逆に自然が都市に入り込むことをダイナミックなものとして肯定する計画が放水路的計画である。前者は都市と自然が切り分けられるという理想に基づく計画であるが、後者は都市と自然を分離することができないという前提のもとでの計画である。この回での都市/自然の関係についての考察は、次回の地上/地下の関係の考察への布石となった。
第4回「 ヴォイドの表面 転倒する地上と地下」では、秋吉台/秋芳洞を取り上げた。ここでは実際に地上と地下との関係性が非常に複雑だ。カルスト台地では雨水が地上と地下を溶解させ、接触させている。また地層の逆転という構造も見られた。それらはこの論考にとって非常に示唆的だった。
コールハースは内部空間を利用するためヴォイドの表面を設計した。ヴォイドはマッスの対立項であるが、ヴォイドの表面はヴォイドとマッスを転倒させ続ける。ヴォイドの表面は肥大化することによって内部/外部という対立を無効化する。どういうことか?
内部空間がヴォイドの表面へと折りたたまれることによって、有限の空間は無限の潜在的表面積をもつ。内部が内部へと折り込まれる。逆に、有効に利用された空間とはヴォイドの表面が折り込まれた空間である。潜在的内部空間が増大し、インテリアでしかない都市が生まれる。東京は、だから、ヴォイドの表面が極度に肥大化した都市だと言える。以上をまとめ、次のように言えるだろう。地下空間には外部がない。それは内部が内部化し、潜在的内部空間が肥大化したからである。
第5回「 非対称的論理空間」では、首都高を取り上げた。ここでは観測者と対象物、見る/見られるという関係から考察した。首都高では観測者がつねに移動し続ける。そのため見る/見られるという関係がずらされ続ける。また海ほたるという見られることのない建築の存在も示唆的だった。さらにコールハースの巨大建築での戦略を参照しつつ、もう一度地下空間を新しく定義した。
ここで視点の対応関係をもとに三つの空間形式を整理した。第一、見る/見られるという関係が相互に入れ替えることができる空間、そこでは内部と外部が対応している。第二、見ることはできても見られることがない空間、それは外部の視点がない内部だけの空間だ。これが第4回までで考えてきた地下空間だ。インテリア都市とほぼ同義で用いてきた。第三、これに対し第5回では、見る/見られるという関係が複数の関係をとりもつような空間の可能性を考えた。内部と外部は一対一には対応せず、その関係は非対称的だ。それを一般化させ、複数の論理形式と単数の論理形式が対応する空間を地下空間だと再定義した。
第二のものと第三のもの、二つの地下空間が現われた。その区別は本論において重要だが、いずれも内部と外部の対応関係が崩れているという意味で共通している。第5回での用語法にならい、第一のものを一対一の論理空間、第二のものを一対ゼロの論理空間、第三のものを一対多の論理空間としておこう。本論で考察してきた地下空間とは、一対一の論理空間にあてはまらない空間のことであった。そしてそれは一対ゼロの論理空間、一対多の論理空間に分けられる。
一対ゼロの論理空間は、インテリア都市とほぼ同義である。外部のない空間。ビッグネス、ジャンクスペースといった概念が示す内部と外部の論理的破綻を生じた空間もここに含まれる。
ここにはもうひとつ亜種がある。第2回で触れたエクステリアだけの都市だ。見るための外部の視点がないのではなく、内部から見る視点が欠けている。しかしインテリア都市は、外部がないという時点で内部とは言えないのだから、エクステリア都市もインテリア都市も、形式的には全く同じなのである。
第4回では、内部でしかない空間が生じる理由として、建築の巨大化のほかに、内部の内部化を挙げた。ヴォイドの表面が折りたたまれていくことによって、内部が内部へと多重に繰り込まれる。
一対多の論理空間は、内部と外部のより自由な関係を成立させる。実は、この空間形式が最も一般的な関係である。厳密には、このなかに一対ゼロの論理空間が含まれていると考えられる。どちらも内部と外部が非対称な空間だ。さらに言えば、一対一の論理空間は一対多の論理空間の特殊な場合に過ぎない。
内部と外部、あるいは内容と形式が対称的である空間が一対一の論理空間である。それに対し内部と外部が非対称的である空間をわれわれは考察してきた。それをずっと〈地下空間〉と呼んできた。第2回を振り返ろう。内部と外部の対応関係が成立しているのがポリスであって、対応関係が溶解してしまっているのがメトロポリスであると考えた。〈地下空間〉とはメトロポリスのことである。この地下空間論はメトロポリスに関する形式的考察でもあった。メトロポリスとは非対称的二項対立を成立させる論理空間である。
一対ゼロの論理空間は、形式的思考の産物である。けれどもそれは思考のツールにすぎない。一対多の論理空間は、コールハースによる巨大建築のプロジェクトから抽出された。それはメトロポリスにおける設計のツールである。前者は特異点を見つけることによって二項対立を崩そうという思考であり、後者は複数の特異点を設定することで二項対立を組み替えていこうとする運動である。
最後に確認しておこう。一対多の論理空間とは、還元できない複数性をはらんだ空間である。還元できない複数性とは、一元的なものでも多元的なものでもない。それらはいずれも還元可能なものである。一元的なもののうちにこそ多元的なものが存在するという前提によってのみ、一対多の論理空間が見えてくるのである。(了)
この論考は〈地下空間〉をめぐって展開されたが、それは必ずしも具体的な地下空間を指していたわけではなかった。東京、あるいはメトロポリスが地下空間的な特性をもっているのではないだろうかという漠然とした考えが出発点であった。また本論の骨格は、磯崎新とレム・コールハースの都市に対するパースペクティヴに多くを負っている。両氏に多謝したい。そのわりにはあまりに稚拙な論考となってしまったが、いくらかでもそのパースペクティヴを整理し、新しいアーバニズムの可能性への見通しがよくなったならば、とりあえずの目的は果たしたものとしたい。
← SERIES
■HOME