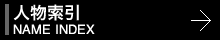ENQUETE
特集:201201 2011-2012年の都市・建築・言葉 アンケート<門林岳史
●A1東日本大震災以降の状況は、年の暮れに1年を振り返るという慎ましい営みを台無しにしてしまったように思う。端的に、2011年の出来事として3月11日以前のことを思い出そうとしても、遠い過去の出来事のようでなにか意義深いものとして回顧するのが難しい。そして、それにもまして1年間という人間的な時間のスケール自体、圧倒的な自然の力を前にしてかすんでしまっているように感じられるのである。もちろん、このような考え方も、それ自体貧しいものかもしれない。そこで、この1年を振り返って私自身の関心を惹いた物事を挙げてみると、まず震災関連では、震災と原発問題を反省的に捉え直すための機会としていくつかの映画祭が催されていたことが思い起こされる。
『Image.Fukushima』は、放射能という(物理的にも政治的にも)不可視の現象を「イメージする=可視化する」ために震災以前と以後の映画を上映するプロジェクトである。この映画祭は、8月9~14日に福島市で開催されたのち、東京(9月17~23日)、金沢(11月26、27日)を巡回し、12月29日に再び福島市で開催される予定である。私自身は東京での上映会の一部に参加しただけだが、上映にあわせて連日開催されたトーク・イヴェントでは、会場の観客も交えて積極的な意見の交換がなされていた。
山形国際ドキュメンタリー映画祭2011(10月6~13日)においても、「ともにある Cinema with Us」と題された東日本大震災復興支援上映プロジェクトが開催され、早くも制作された震災をテーマとするドキュメンタリー映画が数多く上映されていた。この企画で上映された作品の一部は、第3回神戸ドキュメンタリー映画祭「3.11後を生きる 早く、遅く。」(12月3~11日)というかたちで、神戸映画資料館でも上映された。また、1月14~27日には神戸映画資料館と神戸アートビレッジセンターの二会場で「Cinema with Us ともにある in 神戸」も開催され、さらに多くの作品が上映される予定である。
私自身は、映像メディアの研究教育に携わる人間として、震災の問題を映像の問題として捉える思考がいま必要とされていると考えている。その点で、反省的な思考を促すこれらの映画祭は、3月11日から数日間テレビ画面を埋め尽くした災害映像の洪水の対極に位置づけられるかもしれない。もちろん、これら二種の映像のあり方を、映画対テレビという安易な対立構図に収めることは慎みたい。けれども、それぞれに上映に合わせた討議の場が用意されていたこれらの映画祭は、同じ会場で映像を分かちあうというささやかな経験のかけがえなさを再認識させてくれるものであった。
●A2
東日本大震災関連以外でこの1年を振り返ってみると、私の研究上の関心からは、2011年はマーシャル・マクルーハン生誕100周年であった、ということがある。『KAWADE道の手帳 マクルーハン 生誕100年 メディア(論)の可能性を問う』には、私自身もインタヴューなどのかたちで協力させていただいた。また、この1年間に生誕100周年を記念する多くの国際会議やイヴェントなどが世界中で開催されており、私もバルセロナで開催された「McLuhan Galaxy 2011」(5月22~25日)とベルリンで開催された「Re-touching McLuhan」(5月27~29日)に参加した。マクルーハンが生涯の長い期間を過ごしたトロントでの国際会議に参加できなかったことは悔やまれるが、私が見聞きした範囲内でも、この生誕100周年はマクルーハン研究にとって大きな節目になったという実感がある。それは、マクルーハンがいよいよ決定的に過去の人になったということであり、その結果、時代的背景を脱色した理論的応用可能性が広がった一方、文化歴史学的なマクルーハン理解がより一層必要とされ始めている、ということである。
私自身の関心からすると、とりわけマクルーハンにおける「触覚」概念の重要性が再認識され始めていることが印象に残っている。概説的なマクルーハン理解は、視覚(文字の文化)対聴覚(口承の文化)の枠組みに落とし込まれがちであり、そのなかでなおざりにされてしまう触覚概念がマクルーハンのテクストにおいて担っている修辞的な役割については私自身論じたことがある(拙著『ホワッチャドゥーイン、マーシャル・マクルーハン?──感性論的メディア論』第2章)。それでは、なぜいま触覚概念が注目を集めているのか。今回の一連のマクルーハン関連のイヴェントにおいて、多くの発表者がマクルーハンの触覚概念に言及する背景には、もちろんスマートフォンやiPadなどの電子デバイスの普及がある。実際、会議の場で3割ほどの研究者たちがiPadを机に出してメモを取ったり関連情報をブラウズしている状況を見ると、きわめて素朴に触覚の復権を実感せざるをえない。けれども、ほんの少し前まで、彼ら/彼女らはiPadのかわりに、やはり触覚的なメディアである紙とペンを手にしていたのである。触覚概念の重要性には私自身与したいと思うものの、新しいテクノロジーとともに新しい感性が到来している、というタイプの技術決定論(これ自体は使い古された構図である)を反復するだけではないメディア論的思考の枠組みを粘り強く模索し続ける必要があるだろう。
もうひとつ、2011年を回顧して印象的なことを挙げておくと、この秋に関西圏で広い意味でのメディアアート関連の展覧会が数多く催されていたことが記憶に新しい。国立国際美術館の「世界制作の方法」展(10月4日~12月11日)、大阪と神戸の2会場で同時開催された梅田哲也展(「大きなことを小さくみせる」、神戸アートビレッジセンター、11月12日~12月4日、および「小さなものが大きくみえる」、新・福寿荘、11月12日~12月4日)、文化庁メディア芸術祭京都展「パラレルワールド・京都」(10月29日~11月23日)、神戸ビエンナーレ(10月1日~11月23日)の一環として開催された文化庁メディア芸術祭ネットワークス、大阪の商業施設ブリーゼブリーゼで開催されたアルス・エレクトロニカによる展覧会「Poetry of Motion」(12月10~18日)などである。
すべての展覧会をくまなく観てまわれたわけではないが、とりわけネルソン・グッドマンの同名の著作に着想を得た「世界制作の方法」展は、キュレーションの意図も明確で見応えがあった。それとともに印象に残ったのは、クワクボリョウタの作品「10番目の感傷(点・線・面)」が、上述の「世界制作の方法」展、「パラレルワールド・京都」展に展示されていたほか、「六甲ミーツ・アート 芸術散歩2011」展(9月17日~11月23日)でも同作品の別バージョンが展示されていたことである(この秋、それに加えて世界中の数カ所でこの作品は展示されていたようだ)。もちろん、同じ作品が同時期に複数会場で展示されるという状況を受けて、複製技術時代における芸術作品の唯一性・真正性の崩壊にいまさら感慨を抱く必要はない。暗い展示空間には洗濯ばさみやプラスチック製のカゴといったチープな素材で作られたミニチュア都市が配置され、その合間を運行する鉄道模型に積載された光源がそれらの都市風景を叙情たっぷりに壁面に映し出す、というこの作品においては、作品制作の条件は、複製可能性を越えていわば日用品化されているのである。
それにしても、Twitterのタイムライン上に現われる展覧会の感想などを見ても、各展覧会でこの作品ばかりがどうしても観客の印象に残ってしまうという現象は起こっていたようであり、この件もまた考えさせられるところが大きい。実際、「10番目の感傷(点・線・面)」は現代アートになじみのない観客にも親しみやすい訴求力を備えている。いわばこの作品は「癒し系」アート作品なのであり、ヒリヒリ・チクチク・ピリッなどと痛覚を刺激するような要素が徹底的に欠如している。そして、その結果、現代アートの文脈ではむしろ異質な作品に感じられてしまうのである。
現代アートにおいて、もはや「美」そのものは主要な価値基準ではない。むしろ、観客にどのような感性的経験を与えるか、という点に作品の質は規定されていると言ってよい。いわば現代アートにおいて、美学(エステティクス=感性の学)は、より語源に忠実に感性論という意味合いを深めているのである。そして、感性論的な次元で現代アート作品を評価する基準が存在するとすれば、おそらくその主要な一項目として、(比喩的に転位された次元において)痛覚を刺激するかどうか、というものがあるのではないだろうか。「10番目の感傷(点・線・面)」が優れて喚起力の強い作品であることは間違いないが、それでもこの作品をどう評価すればよいのか、一現代アートファンとして考えあぐねてしまう背景には、現代アートにおける痛覚の系譜といったものが横たわっているような気がするのである。
-

- 門林岳史『ホワッチャドゥーイン、マーシャル・マクルーハン?──感性論的メディア論』
●A3
最後に2012年に向けた抱負についてだが、ここに来て再び、まだ収束したわけではない地震と津波による複合災害を前にして、次の1年について語ることのむなしさを覚えてしまう。今回の震災で私たちが目の当たりにしたのは、歴史という人間が構想しうる時間観念の埒外にある自然の力の噴出であった。そのことに対峙して強く感じるのは、1年間という短い時間の単位で物事を捉えることに対する無力感である。せめて、数年から数十年というもう少し大きな単位で私自身がなにをなしうるかを真摯に受け止めなければいけないといまは考えている。