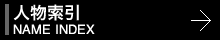ENQUETE
特集:201201 2011-2012年の都市・建築・言葉 アンケート<村上祐資
●A1+A2
東日本大震災が起きた3月11日、僕はアメリカに向かうために成田空港にいた。すでに出国手続きを済ませ、出発ロビーでは僕が搭乗する予定のデルタ航空ポートランド行きの機内への誘導が始まっていた。やがて人の列は落ち着き、ベンチに座って待っていた僕もそろそろ機内へと乗り込もうかと思ったその矢先に、あの地震は起きた。震度5強を観測した成田空港の、震災直後の状況が客観的にどのようなものであったかは、2011年11月にNAA(成田国際空港株式会社)が発刊した『成田空港──その役割と現状』の「東日本大震災への対応状況(PDF)」のなかに簡潔にまとめられている。
長く感じられた揺れが落ち着いてすぐに、まるで平静を装うかのような口調で機内への搭乗をうながすアナウンスが出発ロビーに流れたが、やがて「機内のほうが安全ですから」という言葉に緊急性の色を帯びるように徐々に雰囲気は変わっていった。
アナウンスの話し口調からポジティヴな性格であることが伺える機長から、僕ら乗客へと告げられた情報は「まだ錯綜していますが」という前置きがあったうえで、「東北を震源とするM7クラスの(その後何度か震度に関する情報訂正のアナウンスがあった)大きな地震が起き、成田空港も被害を受けた模様。現在被害状況を確認中で、当機は安全が確認されるまではこのまま待機となります」といったものだった。数時間が経ちフライトはキャンセルの決定がされたようで、いずれ飛行機を降りてもらうことになることが告げられたが、安全確認がとれるまでは依然としてこのままの状況が続くとのことだった。しかし結局9時間以上の機内待機の後、飛行機はポートランドへ向けて出発した。離陸決定を知らされてから離陸までわずか15分あまりしかなく、僕はそうなったことを家族に告げることもできないまま日本を離れた。
成田上空から見た日本は、渋滞中の車両がつくる灯列のほかに、陸と海との違いを教えてくれるものがない闇の世界だった。初めて目にする異様な日本の姿を眺めながら僕は、これでもうアメリカに到着するまでのあいだは、安否確認の連絡をとることも、情報収集を行なうこともできないと気持ちを切り替えにかかった。
と同時に、いつのまにか僕にとっての緊急時の情報が「次へアクションのための判断材料」から「したがうしかない命令」という存在へと変化していることに気付いた。第50次南極地域観測隊員として約15カ月を南極で過ごしていたあいだは、僕を含めた28人の越冬隊員だけですべてを賄わなければならなかった。消火活動やレスキューもすべて僕らだけで行なわなければならない。助けは来ないという覚悟が必要だった。だから万が一なにかが起きてしまった際の情報が、自分のアクションをより確かなものにするために必要な、重要な判断材料だったのだ。
それが南極という「自」と「共」しかない環境から、「公」が存在する環境へと帰ってきたことで、僕にとっての緊急時の情報という存在が大きく意味を変えていた。
震災が起こる3カ月ほど前に、僕は防災士になった(「防災士は語る(村上祐資)」)。防災士教本の最初のページには以下のようなことが書かれている「──防災士とは、"自助""互助""協働"を原則として、社会の様々な場で、減災と社会の防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として認められた人のことである。」
災害被害の軽減という考えるうえで「自助、共助、公助」の効率的な組み合わせによって実現されるという考えかたがある。自助とは「自分の身は自分で守る」、共助とは「共に協力して守る」、公助とは「国の公的機関が国民を守る」ことである。さらに防災士制度では共助を、地域住民同士による"互助"と、企業団体による"協働"とに分けて認識している。
僕はいま新米の地域消防団員としても活動させていただいているが、消防団とは、もともと江戸時代からある地域独特の自主消防組織が警防団を経て地方公共団体に附属する消防機関と規定され、今日における自治体消防のもとでの消防団の仕組みとなったものだ。つまりボトムアップから生まれた共助システムである。それに対して南極観測隊員や宇宙飛行士は、国家事業というトップダウンから生まれた共助システムという見方ができるのではないかと思う。いかに安全で確実な方法をもって観測成果を生み出すかという観測事業戦略のもとに、僕ら南極観測隊員は国内でさまざまな事前訓練を積み、南極にわたったあともその習熟に努めてきた。
このボトムアップとトップダウンの共助の現場が、僕の経験が接点となってお互いに融合するような活動を、僕はいま模索している。その思いがかたちになった活動として、文化学院創立90周年記念プロジェクトの一環として始まった「連続講座&研究会『スイーツよりペン──生きる・東京・未来』」や、子どもに向けた連続ワークショップ「秘密基地ヲ作ロウ。」を巣鴨小学校で、現在行なっているところだ。

- 子どものためのワークショップ「秘密基地ヲ作ロウ。」
- URL=http://www.fieldnote.net/playfort/
- URL=http://www.fieldnote.net/playfort/
●A3
2012年1月14日に、巣鴨小学校で行なっている「秘密基地ヲ作ロウ。」がフィナーレを迎える。2012年の「秘密基地ヲ作ロウ。」は、新しい試みとしてワークショップそのものにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスをつけることによって、僕以外の個人や企業が主催者となって展開可能なワークショップにしていきたい。ほかにも巣鴨小学校で行なったワークショップのように、固定された参加者で連続全7回を実施するようなスタイルではなく、衣/食/住のような分け方で1〜2日で実施可能な内容に分割し、それぞれを個別に異なる場所や参加者に向けワークショップを行なうことで、トータルで「秘密基地ヲ作ロウ。」の名に沿う学校にしていくような展開も面白いかもしれないと考えている。
他者のプロジェクトとしては、NOSIGNERのOLIVEプロジェクトに関心を持っている。OLIVEを含めて震災直後にはさまざまな被災地支援プロジェクトが立ち上げられたが、そのうちの多くが被災地の支援状況の変化とともに活動を終了したりまったく別の展開へとシフトしている。OLIVEのように最初のコンセプトを保ったまま活動を継続し、また各方面からの注目も高いプロジェクトは、震災直後の「緊急性」というフェーズから「信頼性」というフェーズへと移っていかなければならないと思っている。OLIVEに掲載されているアイディアのなかには僕の目から見て使い方を誤ると事故になりかねないアイディアもあった。もちろんアイディアの多くは素晴らしいものであるし、なによりも多くの方々の「被災地に向けてなにかアクションを起こしたい」という気持ちで支えられていること自体が、このプロジェクトのもっとも素晴らしいところだ。しかし、安全や生命に関わるプロジェクトである以上、間違いは許されない。
OLIVEのポリシーのなかにはユーザは、アイディアの信頼性を「自身で検証し」とあるが、本当の検証がどれだけ困難であるかは、作家の井上靖の小説『氷壁』のモデルともなった昭和30年に起きた「ナイロンザイル事件」と、それに端を発したナイロンザイルの安全性を巡る社会論争をいま一度思い出したい。事故以来50年にわたってナイロンザイルに関わってきた石岡繁雄さんの遺作『石岡繁雄が語る氷壁・ナイロンザイル事件の真実』は名著である。登山に関わる人たちにだけではなく、ぜひたくさんのデザインに関わる人たちにもこの本を読んでもらいたいと思う。
すこし厳しい主張をしてしまったかもしれないが、OLIVEプロジェクトがより信頼性の高い情報システムへと展開し、被災地に暮らす方々だけでなく、世界中の多くの人々の暮らしがこのプロジェクトを通して豊かなものになることを願っている。

- 石岡繁雄+相田武男『石岡繁雄が語る氷壁・ナイロンザイル事件の真実』(あるむ、2007)