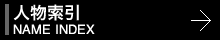ENQUETE
特集:201301 2012-2013年の都市・建築・言葉 アンケート<今村創平
●A1今年は50くらいの展覧会に足を運んだが、そのなかから特に良かったものを挙げてみると、以下のようになる(順番は訪問順、企画展のみ)。
- 悠久の光彩 東洋陶磁の美(サントリー美術館)
- 野田裕示 絵画のかたち/絵画の姿(国立新美術館)
- 生誕100年 ジャクソン・ポロック展(東京国立近代美術館)
- 杉本博司 ハダカから被服へ(原美術館)
- セザンヌ パリとプロヴァンス(国立新美術館)
- テマヒマ展 東北の食と住(21_21 DESIGN SIGHT)
- 第5回 大地の芸術祭(十日町市)
- 「具体」 ニッポンの前衛18年の軌跡(国立新美術館)
- 与えられた形象 辰野登恵子 柴田敏雄(国立新美術館)
- スタジオ・ムンバイ(ギャラリー間)
- 数寄屋展(ギャラリーエークワッド)
- 坂田和實の40年(松濤美術館)
実は、ベスト10に絞り込もうとしたのだが、難しかった。上記以外にも優れた展覧会がいくつもあったから、今年は展覧会を十分に楽しんだ1年であった(このアンケートの締め切りには間に合わなかったが、東京国立近代美術館の60周年記念展「美術にぶるっ!」も年内に観る予定で、この同館のコレクションの良品を集めた展覧会も、リストに挙がるものであろう)。一方で、私の専門である建築の展覧会は、上記のなかではムンバイ展と数寄屋展と2つ挙げているものの、「白井晟一展」「メタボリズム展」「バレリオ・オルジアッティ展」など強く印象に残る展覧会があった昨年に比べると、全般的には低調であった。小規模のものなので、上記のリストには加えなかったが、新宿OZONEにて開催された木内俊克さんと砂山太一さんによる「Amorphous Form」展は、今日では貴重な建築のフィールドの前衛といえる試みであった。
書物に関しては、一冊を通しで読むよりも、執筆や授業の資料として本の一部に目を通す割合の方がずっと多い年であり、その大半は今年出た新刊ではなかったが、出たばかりの評価も定まらない本を斜め読みするよりもは、昔出た本をじっくりと読む込む方が充実した読書となることが多い。
とはいえ、この1年くらいの間に出た本で、かつこちらは建築・都市関連に絞って読了したもののなかから良かったものを挙てみる(順序は読了順)。
- 藤森照信『茶室学──日本の極小空間の謎』(六耀社、2012)
- 市川宏雄『山手線に新駅ができる本当の理由』(メディアファクトリー、2012)
- 伊東豊雄『あの日からの建築』(集英社、2012)
- 三宅理一『限界デザイン』(TOTO出版、2011)
- 山崎亮『コミュニティデザインの時代──自分たちで「まち」をつくる』(中央公論新社、2012)
となる。新しい書き下ろしではないが、伊藤ていじ氏の晩年のエッセイを集めた『ていじ手帖』(建築画報社、2012)と多木浩二遺稿集『視線とテクスト』(青土社、2012)は、このような企画を実現された関係者の方々に敬意を表する。
上記の通り2011年にメタボリズム展が開催され、この建築・都市の展覧会は、10年に一度の規模と内容のものであったものの、国内ではほとんど全く論評されることがなく、相変わらずの日本における建築批評の不毛ぶりが実感された。シンシア・ディビッドソンが主宰する建築批評誌『Log』では、2012年のwinter/spring号にて、Ioanna Angelidouによる八束はじめさん(メタボリズム展の企画代表者)に対する中身の濃いインタヴューを掲載している。また、同号には、ケン・タダシ・オオシマさんによる同展のレヴューや、トマス・ダニエルさんによる磯崎新氏の《孵化過程》の40年後の再製作についてのエッセイが掲載されている。
2012年の秋には、ハーヴァード大学でメタボリストの菊竹清訓氏の展覧会が開催され、同地では関連して伊東豊雄氏がレクチャーを行なった。こうした日本建築への再評価が世界各地で進んでいるなかで、その状況が日本に伝わってこないことはもどかしい。
日本の建築メディアの衰弱ぶりは、ここ10年以上に渡って繰り返し指摘されてきたが、2012年にはついにここまでと思うことが度々あり、近い将来日本から建築雑誌がすべてなくなるのではという考えをはじめてリアルに抱いた。
また、以前南後由和さんが指摘したように、日本にはかつて数多くの建築メディアが存在しそれが一種のコミュニティを形成していたが、そのような構図は近年ではすっかり崩壊してしまった。わかりやすい例は、大学などで設計製図を教えていると実感することだが、年配の教員と学生とでは日々目にしているメディアが異なっている。以前であれば、教授も学生も『新建築』や『建築文化』の最新号に目を通しており、そこで共通のバックグランウンドがあったわけだが、今の学生は紙のメディアをあまり読まず、一方彼らが頻繁にアクセスするネット上の「Arch Daily」をはじめとするメディアを、教員は知らない。世代間の明らかな情報断絶が進んでいる。
そうしたなかでも、『a+u』はマイペースというか、思わず手に取る特集をいくつか出している。6月号はシンガポールの今を伝える特集を、9月号は『El Croquis』でその評価が確立された建築写真家鈴木久雄さんの特集を組み、11月号のポスト・クライシスの特集の巻頭論考により、金融危機以降のスペイン建築家を取り巻く壊滅的な状況をしり驚いた。 また、『住宅建築』は、ここ数年編集方針を変え、こちらもマイペース路線を展開し、特に新作紹介とは別に、吉田五十八、村野藤吾、江戸千家の建物の詳細な紹介や、数寄屋(《待庵》ほか)、詳細図(《吉田五十八邸》ほか)や実測図の連載など、実務家にとっては思わず唸らせる内容の記事を毎号掲載している。
また、『新建築』9月号に掲載された、槇文彦氏による長文の論考「漂うモダニズム」は、氏のこれまでの航路を反芻しながらも、現代の建築の置かれた状況を鋭く分析している。槇氏の状況認識は、レムと共通するところがあることに思いいたって少々その組み合わせに驚き、レムはそれを「ジャンクスペース」とよび、槇氏は「漂うモダニズム」と表現している。
●A2
すでに、ここまでの文章が長くなってしまったのでごく簡単にひとつだけ。
明治大学が、2013年の春から英語のみの大学院の建築コースを始めるように、いよいよ建築教育における国際化が進むのではないかという期待がある。これまで、10年、20年、建築教育の国際化がなされるべきだと思い続けて、しかし状況はほとんど全く変わらなかった。しかし、ここ数年建築教育の国際化といったトピックでレクチャーを頼まれたり、シンポジウムに参加を要請されることが増えており、各大学も真剣に国際化に向けての対応を考え始めているように感じられる。おそらく、ここ5年くらいで大きく状況は変わるのではないか。これは、期待も含めて。
●A3 直接被災地の話ではないが、3.11以降、一般の方々のエネルギーに対する関心が高まり、またそのためには、互いの協力が必須という意識が高まったことはとても好ましいことだと思う。21世紀は、環境の世紀といわれてきたが、単なる数合わせではなくて、われわれの環境をどうともにデザインしていくかということだろう。
一方で、震災復興にも絡めて、スマート・シティといったことが大きな話題となり、そのこと自身は進めるべきだと思うが、現時点ではスマート・シティの議論は、システムを構築することによっていかに効率を上げるかということしか語られていない(それがビジネスモデルであれば乗り、でなければ撤退するというのが、参加企業のスタンスである)。新しいフェーズで地域環境を構想するにあたって、どのような街がつくられるかという議論に、建築家や都市計画家は積極的に参加すべきだと思う。