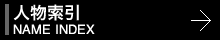ENQUETE
特集:201301 2012-2013年の都市・建築・言葉 アンケート<門林岳史
●A19月に東アジアの映画理論史についての学会(Permanent Seminar on Histories of Film Theories)に参加するため、ミシガン大学を訪れた帰りに、束の間トロントに立ち寄った。トロントを訪れるのは、トロント大学に滞在していた2001─02年以来である。その目的のひとつは、それぞれダニエル・リベスキンドとフランク・ゲーリーによって増改築されたロイヤル・オンタリオ博物館(ROM)とアート・ギャラリー・オヴ・オンタリオ(AGO)を訪れることであった。両美術館の増改築部分が開館したのはROMが2007年、AGOが2008年のことなので、特に2012年の話題というわけではない。けれども、私がトロントに滞在していた頃に発表されたそれぞれのプロジェクトが実現した姿を、10年振りに再訪して確認することができたのだから、個人的な感慨は大きい。
では、ともにカナダを代表する両ミュージアムは、ともに脱構築主義を代表する2人の建築家によってどのように生まれ変わったのか。外観を一瞥したところでは、両者のトレードマークとも言える典型的なファサードを既存の建物にとってつけただけとも見えたのだが、なかに足を踏み入れると、それだけにはとどまらず内部の空間を再文脈化(あるいは脱文脈化?)する作業がなされていることを確認することができた。
-


-
1──ロイヤル・オンタリオ博物館外観(著者撮影)
2──アート・ギャラリー・オヴ・オンタリオ外観(公式HPより)
AGOの場合、フランク・ゲーリー的な要素は、木とガラスを主調とするファサードの有機的なフォルムにとどまらない。エントランスを通り抜けたところにある吹き抜けの広場には、やはり木を基調とする階段が増築され、上階の展示室への効率よいアクセスを与えている。既存の空間内を這いずりまわるそのフォルムは、まるで親木を内部まで侵食する寄生植物のようである。他方、ROMの場合、上から見るとH型をしている既存の建物が作り出しているコの字上に建物で囲まれたテラスにリベスキンドによるアルミとガラスの建築物が増設され、新しいエントランスと企画展用の展示スペースを与えている。既存の展示室の多くはそのまま残されているのだが、エントランスが東側から北側に移動した結果、既存の空間が備えていたヒエラルキーは脱臼させられてしまったという感が強い。
-

- 3──アート・ギャラリー・オヴ・オンタリオ内観(公式HPより)
トロント在住の知人から、ゲーリーによるAGOは素晴らしいが、リベスキンドによるROMは展示を楽しむ経験を台無しにしてしまっているとの評を事前に聞いていた。それもうなずけるところはある。おそらくそこにはやむをえない事情もあったのだろう。ROMは、マーシャル・マクルーハンとの共著作でも知られるハーリー・パーカーがデザイン・キュレーション部門のチーフを務めていた1960年代から、今では体験型ミュージアムと呼ばれるような展示スタイルを先駆けてきた。単にブツを展示するのではなく、展示と空間が一体化してしまっているそれらの展示室には、増改築にあたって手をつけようがなかったのではないかと想像されるのである。
いずれにせよROMは、すべての展示を丁寧に観ようとしたら途方に暮れてしまうような巨大な博物館である。増築部分を起点としてさまざまな展示室を行ったり来たりする新しいROMの経験は、この博物館がもともと備えていた方向感覚の喪失を加速させており、それはそれで興味深いものであった。
●A3
『ヱヴァンゲリヲンQ』と同時上映されていた短編映画『巨神兵東京に現わる』を観て、震災後の現状で、このような作品が制作され、数多くの観客の目に触れるかたちで公開されていることに大きな戸惑いを覚えた。そのことを知人に話してみてもあまり共感を得られないことに気づき、小さな戸惑いを感じ続けている。
『巨神兵東京に現わる』では、都市破壊の特撮シーンに、自らの心情を語る女性の声のヴォイス・オーヴァーが重ね合わせられ、破滅の結果、人類がより高次の存在へと止揚されるという『ヱヴァンゲリヲン』シリーズの「人類補完計画」と同型のナラティヴが構築される。ここでは個人的な印象を披露するにとどめ、詳細な批評的分析を展開するのは差し控えたいが、それは煎じ詰めて言えば、ユートピア的であれディストピア的であれ、破滅以後の世界を人間以後の世界として描くことの場違いさである。
震災と原発事故以降、時間が経つにつれて徐々にはっきりと浮かび上がってきたのは、自らが生み出した文明の帰結をただただどうすることもできない人間たちの姿ではないだろうか。近代的な人間観の批判としてポストヒューマニズムの言説が提示する人間以後の世界の可能性は、それでもやはり私たちは人間であるという認識との緊張関係においてはじめて批評性を持ちうる。
多くのドキュメンタリー映画が震災後の人間の姿を描いてきたが、2012年に公開された舩橋淳『フタバから遠く離れて Nuclear Nation』はその優れた事例のひとつである★1。福島第一原子力発電所のメルトダウン事故後、避難を余儀なくされた近隣の福島県双葉郡双葉町は、埼玉県の旧県立騎西高校に自治体ごと移転することを決めた。2011年4月以降、旧騎西高校に通い続けた舩橋監督は、本作品で、将来を宙づりにされた住民たちの心の機微を記録すると同時に、原発推進派から一転して住民の安全を守るため奮闘している井戸川克隆町長の活動を追った。新潟水俣病に冒された阿賀野川流域に移り住んで『阿賀に生きる』(1992)を制作した佐藤真監督の精神を継承する力強い作品である。
- 舩橋淳『フタバから遠く離れて Nuclear Nation』予告編
震災後の人間に焦点を合わせたもうひとつの重要な事例として、水戸芸術館で開催された「3.11とアーティスト」展(2012年10月13日─12月9日)も紹介しておきたい。「3.11とアート」ではなく「3.11とアーティスト」と慎重に言葉を選んだ展覧会タイトルにはっきり表われているように、本展覧会は、震災を題材とした芸術作品の展示ではなく、震災後の状況にそれぞれ当事者として関わったアーティストたちの活動の記録である。震災後の状況に(大文字の)アートがどのように貢献ないし介入しうるか、という抽象的な問題に対してはあえてパースペクティヴを提示することをせず、あくまでひとりひとり人間であるアーティストたちが何をしてきたのかを淡々と記録しているのが潔い。
★1──先行して発表された一連の震災ドキュメンタリーについては以下の拙稿をお読みいただきたい。「カタストロフに寄り添う映像──震災ドキュメンタリーをめぐって」また、カタストロフと映像をめぐる広範な問題をめぐっては、2012年1月28日に勤務先の関西大学で「震災と映像」と題したシンポジウムを開催した。参加者の堀潤之氏、林田新氏による報告がウェブ上で読める。
●A2
12月29日に大阪のオルタナティヴ・スペースadandaで開催されたイヴェント「スカートの中の『ジャパン・シンドローム』」で、高嶺格の映像作品「ジャパン・シンドローム」を観る機会を得た。震災後に市井で採取した会話を舞台で演じなおすシリーズであり、これまでに京都、山口で制作された2作品に加えて、水戸芸術館で開催中の「高嶺格のクールジャパン」展(2012年12月22日─2013年2月17日のために水戸で制作された最新作を観ることができた。この作品において、人々の日常からにじみでる震災後の空気感は、装飾を廃したミニマルな舞台に載せられることで奇妙に抽象化された次元を獲得している。
「芸術家は民族のアンテナである」と述べたのはハイ・モダニズムの詩人エズラ・パウンドだが、「3.11とアーティスト 進行形の記録」展から垣間見えたのもまた、高い感受性を備えた人間としてのアーティストたちの姿である。けれども、パウンドがもとの文脈で主張していたように、現状診断や未来予測としての価値を即座に持つから、それらの活動が貴重なのでは必ずしもない。彼らの感受性が作品へと沈殿し結晶するのには時間を要する。高嶺格の作品に、そのプロセスがすでに進行していることを意識させられた。未見の「高嶺格のクールジャパン」展を含め、今後も現われてくるであろう震災後のアートのあり方を注視していきたい。