フィールドワークと在野研究の現代的方法論
大学のなかの在野
荒木優太──まずは自己紹介から。私は日本近代文学、とりわけ有島武郎を中心に研究をしている「在野」の研究者です。修士課程を出てから、フリーターをしながら余暇を研究に当ててます。そんな研究生活のなかで、なぜ自分がこうなったのか(そしてどうしていくべきなのか)、また、これから先、自分の後輩たちが大学に所属し続けることが果たしてできるのだろうかということを不可避的に考えざるを得なくなったんですね。それで、大学機関に属さずに勉強や研究を続けるために、過去の人たちのやってきたことをちゃんと調べてみようと思って、「エン-ソフ」(En-Soph)というインディペンデントのウェブサイトで、2013年に「在野研究のススメ」という連載を始めました。大学に属さなかった研究者たちの略歴と研究内容をコンパクトにまとめて紹介する、という仕事です。過去から学んで未来に活かすというのが人文系の大きな魅力なのに、私たちは全然そういうことを知らないんじゃないか、と。その成果を去年、書籍『これからのエリック・ホッファーのために──在野研究者の生と心得』として出版しました。

- 加藤文俊氏

-
加藤文俊『キャンプ論──あたらしいフィールドワーク』(慶應義塾大学出版会、2009)
荒木優太『これからのエリック・ホッファーのために──在野研究者の生と心得』(東京書籍、2016) - fig.1──「基山キャンプ」の様子(2016年10月、佐賀県基山町)
[撮影・編集=檜山永梨香、菅原千夏(加藤文俊研究室)]
「基山キャンプ」の概要については、http://camp.yaboten.net/entry/kiyamap を参照。 
- fig.2──墨東大学京島校舎での講義(ナタプリの会)の様子(2011年10月、東京都墨田区)

- fig.3──三宅島大学本校舎(御蔵島会館)での成果報告会の様子(2013年6月、東京都三宅村)

- 荒木優太氏

- fig.4──「フィールドワーク展XIII:たんぽぽ」の様子(2017年2月、神奈川県横浜市・BUKATSUDO)
毎年度末に開催している成果報告の展覧会は、13回目をむかえた。「フィールドワーク展」の概要については、http://vanotica.net/fw1013/を参照。 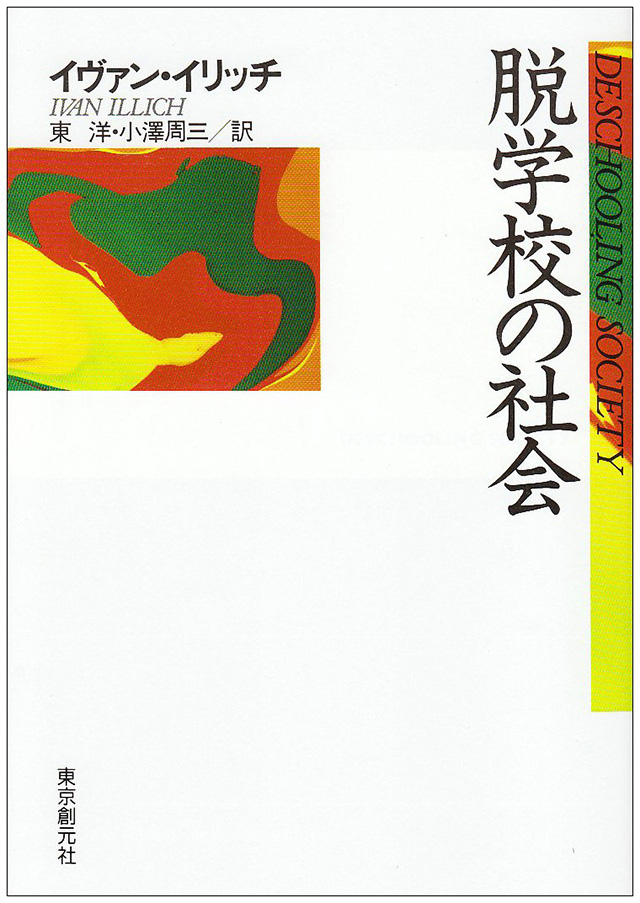
- イヴァン・イリイチ『脱学校の社会』
(東洋ほか訳、東京創元社、1977) 
- fig.5──SBS(新宿文藝シンジケート)読書会の様子
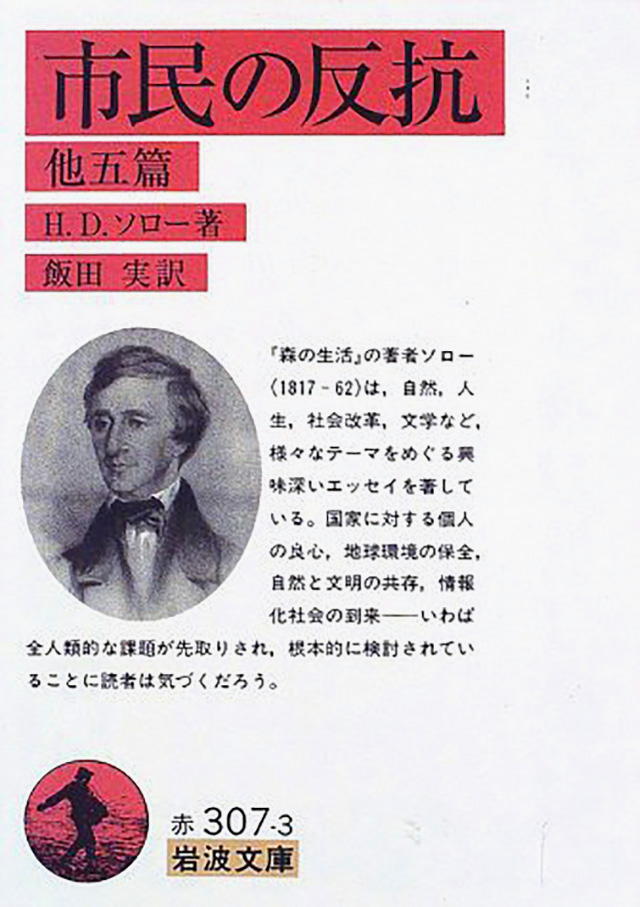
- ヘンリー・デイヴィッド・ソロー
『市民の反抗』 (飯田実訳、岩波文庫、
1997) 
- fig.6──カレーキャラバンの様子(2016年11月、茨城県常陸太田市)
KENPOKU ART 2016(茨城県北芸術祭)の会期中、6つの市町でカレーをつくった。当時の雑感についてはhttp://blog.cloveken.net/archive/category/in%20KENPOKUを参照。 
- アラン『四季をめぐる51のプロポ』(神谷幹夫、岩波文庫、2002)
アラン『芸術論20講』(長谷川宏訳、光文社、2015)
ゲオルク・ジンメル『ジンメル・エッセイ集』(川村二郎訳、平凡社ライブラリー、1999) 
- オスカー・ルイス『サンチェスの子供たち──メキシコの一家族の自伝』(みすず書房、1986)
ウィリアム・ホワイト『ストリート・コーナーソサエティ』(有斐閣、2000)
佐藤郁哉『暴走族のエスノグラフィー──モードの叛乱と文化の呪縛』(新曜社、1984)
加藤文俊──対談の企画をいただいてから『これからのエリック・ホッファーのために』を読みましたが、大変面白かったです。本のなかで紹介されているのは、名前は聞いたことがあるという程度の人物も多く、あたらしい発見がたくさんありました。「先生が嫌い」という話も出てきますが、僕はまさに教員の立場で日々学生を相手にして過ごしていますから、大学のことを改めて考える良い機会になりました。
僕はもともと経済学部出身で、経済地理学を専攻していました。当時の経済学部では、大半が理論中心のアプローチで、あまり関心をもつことができず、「地理」という名前が入ったゼミを選んだのです。経済地理学は、「野に出る」現場に密着したものだと思っていました。そして、実習課題で野に放り出されたときに感じる面白さからフィールドワークの世界に入っていきました。学生のときは、それほど意識していませんでしたが、フィールドワークの醍醐味は、距離を縮めながら、少しずつ人に近づいていくのを味わうことだと言えるでしょう。
教員になってみると、大学は想像していた以上に窮屈なところだと感じるようになりました。しかし、裏返せばとてもよくできた仕組みだと言えます。例えば、教員たちはそれぞれが個人的な都合で出講日の希望を出しているにもかかわらず、調整が行なわれて時間割ができ上がります。それによって教員と学生が規則的に移動し、決められた教室に集まり、授業が可能になる。そして、講義をくり返しながら、所定の単位を取得すると卒業できるという、とても完成度の高い仕組みだと改めて思います。学生の頃は、無自覚なままそうした仕組みのなかに入り、受け入れていたことにも気づきます。教員という立場になって、初めて自分なりに考え始めたことがたくさんあり、『キャンプ論──あたらしいフィールドワーク』を書くきっかけになりました。
「キャンプ」は、大学の既存のカリキュラムとは矛盾しないことを前提にしつつ、もう一歩、大学の外へと踏み出してみようという試みです。制度的な制約はあるのですが、この10年ほど「キャンプ」を続けています。『これからのエリック・ホッファーのために』を読むと、自分はまだ大学をはみ出しきれていないというか、中途半端で思い切りが足りないんじゃないかと思えてとても刺激的でした。
加藤──「キャンプ」と称して行なっているフィールドワークは、いわゆる「野営」ではありませんが、時間割も教室もない実習環境だと言えるでしょう。典型的には、2泊3日のフィールドワークに出かけて、まちに暮らす人びとの取材を行ないます[fig.1]。そして、滞在中に成果をまとめて、調査対象となった人びとにその成果を報告してから帰るというものです。かなり慌ただしいのですが、「キャンプ」のテーマは「まちに還す」ということです。調査に出かけて、戻ってから文章を書いたり、写真を整理したりするつもりでいても、なかなかうまくできないことがあります。「忙しい」などと言っているうちに、新鮮な記憶が失われていくし、取材先にお礼さえしないまま時間が過ぎてしまう。そこで、滞在中にひととおりの作業を終えて、「宿題」を持ち帰らないようにするというわけです。だから、かなり粗削りではあります。
当然のように、「わずか2泊3日程度で何がわかるのか」「もっと丁寧にデータを扱ったほうがいい」といったコメントをもらうこともあります。たしかに、何度か現場に足をはこんで、少しずつ信頼関係を築いてゆくというやり方が「正統」かもしれません。でも、その一方で2泊3日だからこそできることもある。そう考えています。もう来ないかもしれない、もう会えないかもしれないという状況で、僕たちがどこまで人びとやまちのことを理解できるのか。そこが「キャンプ」の面白さかもしれません。
加藤──
『キャンプ論』をまとめようと思って調べていたところ、「キャンパス」も「キャンプ」も、「カンプス(campus)」というラテン語から派生しているらしいということがわかりました。「カンプス」は、平らな場所や広場を意味します。「キャンパス」も「キャンプ」も、いずれも人びとが集い、コミュニケーションが発生する場所です。それで、両者を対比させて考えることになったのです。カリキュラムという仕組みで整えられた「キャンパス」とはちがう、仮設的でアドホックでインフォーマルな性質をもった学習の機会として「キャンプ」を構想しました。行き先もやり方も、その都度調整をしながらすすめていますが、これまでに、たくさんのまちを訪れました★1。
ちょうど『キャンプ論』を出した頃に、「東京文化発信プロジェクト室(現・アーツカウンシル東京)」とのご縁があって、墨田区で「墨東大学(ぼくとうだいがく)」というプロジェクトをはじめました[fig.2]。「キャンプ」のような短期集中型の活動ではなく、もう少し時間をかけて現場に通いながらすすめるというものだったことから、今度は、この際「キャンパス」をつくってしまおうという発想になったのです。「墨東大学」は、墨東と呼ばれるエリア(隅田川と荒川、そして東京スカイツリーの横を流れる北十間川によって囲まれた、墨田区の北半分を占める地域)を「キャンパス」に見立てた大学です。言うまでもなく、つくるのは(学校教育法上で定められた)「正規」の大学ではありません。
加藤──そもそも、「キャンプ」を始めるきっかけになったのは、日頃から「キャンパス」についてあれこれと疑問や不満を感じていたからでした。今度は「キャンプ」とは別のやり方で、「キャンパス」について考えることになりました。大がかりな「大学ごっこ」のようなものですが、プログラムとしてゼロからデザインしようとすると、大学のロゴから、履修案内、時間割、学生証にいたるまで、「キャンパス」がさまざまな〈モノ・コト〉によって成り立っていることをあらためて実感しました。もちろん、一定数の授業を揃えなければならず、知り合いの大学教員やアーティストにお願いしてプログラムを整えました。商店街のなかの空き店舗を校舎(教室)にして、「墨東大学」は、2年間続けました。
その流れで、「三宅島大学」プロジェクトが生まれました。こんどは、外周が山手線とほぼ同じくらいの三宅島全体を「キャンパス」に見立てた実験です。「墨東大学」での経験をふまえつつ、誰もが学生になり、誰もが教員なるという関係づくりを模索しました[fig.3]。船で6時間半という移動もふくめ、島という環境は、人間関係やコミュニケーションのあり方について、いろいろなことを考えるきっかけをあたえてくれたように思います。このプロジェクトは、3年で終了し「三宅島大学」は閉校となりましたが、さらにもう1年かけて、その意義や意味について問い直す「三宅島大学誌」プロジェクトを行ない、活動内容をふり返りました。
加藤──「墨東大学」「三宅島大学」の経験は、とても勉強になりました。フィールドワークは、調査者が「聞きたい」「知りたい」という想いで出かけると思うのですが、これらの試みをとおして、調査される側、つまり出かけた先々で暮らす人びとの「話したい」「知らせたい」欲求に向き合うことになりました。まちや島を「キャンパス」に見立てたとき、「学ぶ」機会だけではなく、「教える」機会の提供も重要だったことに気づいたのです。つまるところ、それは、人びとのコミュニケ--ションへの欲求なのでしょう。
「本物」ではないにせよ、大学という見立てをすることで、一連の複雑な仕組みが説明しやすくなるという、いわば「メタファーとしての大学」のインパクトも実感しましたし、同時に、このような枠組みがなくても、人びとは普段の生活のなかで「教わる」「教える」という場面を、絶えずくり返しているということを再認識しました。今回の「在野」というテーマとつなげると、まさに「野」は、切実な課題と、それに向き合おうという創造力に充ちているということです。
荒木──『キャンプ論』を読んで思ったのは、大学のなかでも工夫次第で在野的なことにチャレンジできるんだ、ってことですね。いや、読んでいて自分の学生時代のことを思い出しました。森鷗外『舞姫』をベルリンという都市のコードから読み解く論考「BERLIN 1888」なんかで有名な前田愛『都市空間のなかの文学』(筑摩書房、1992)って本がありますよね。それに影響を受けた佐藤義雄という学者がいます。『文学の風景 都市の風景──近代日本文学と東京』(蒼丘書林、2010)という本を書いてます。明治大学の先生で、私はよくその授業を受けていたのですが、彼は文学作品に描かれた実際の土地、その都市空間を自分の足で歩いてみるということを大事にされていた。私自身も何度かご一緒させていただきました。まあ、俗にいう文学散歩なんですけど、私にとって天啓だったのは、文学研究ってものがけっして文献を集めて読むだけ、図書館のコピー室にこもるだけの営みじゃないということだったんですね。現在、都市空間は自分の研究のテーマではないのですが、そうした経験がある種の遠因となって、自分のなかの「在野」をかたちづくっているような気がします。
加藤──荒木さんの本を読んでいて、雑誌『東京人』(都市出版、2014.5)の「フィールドワーカーになる」という特集を思い出しました。藤森照信さん、中谷礼仁さん、石川初さんによる鼎談があり、そこでは「フィールドワーク=野良仕事」という言い方がされています。「野良仕事」と対比されているのが「紙仕事」で、いわゆる文献研究です。「紙仕事」を前提にしてフィールドワークをやると、どちらかと言えば文献で読んだことを確認しに行くだけになり、つまらないのです。やはり、役に立たないかもしれないし、何があるかもわからない「野良仕事」から何かを立ち上げていこうという議論がありました。僕は同じ号で、「まちの変化に『気づく力』を育むきっかけづくり」という文章を書きました。ちょうど同じ頃に日本建築学会『建築雑誌』2014年12月号でも「フィールドワークとツール」という特集があり、論考「ツールを考えること」を寄稿しています。フィールドワークを教えるということ、そのなかでさまざまなツールを活用することは、「キャンプ」の実践と直結しているので、つねに関心を持っています。
先ほど荒木さんは「大学のなかで在野的」と言ってくれましたが、『キャンプ論』のあと、いくつも場数を踏んで、経験が蓄積されてきたので、即興的な対応ができるようになったり、勘が養われたり、物事が動かしやすくなってきたと思います。一方では、慣れてきたことで、つい惰性ですすめてしまうような、たるんできている感じもあります。つねに破壊しながらやらないとすぐ「カリキュラム化」してしまいますね。大学のカリキュラムに疑問を持ち、冒険を試みるのですが、しばらく経って落ち着いてくると、整然と分業や役割分担することが増えて、「紙仕事」のようになってしまうのです。いまはまさに転機、考え時なのかもしれません。
他方で「キャンプ」を面白がってくれる人は確実に増えてきているように思います。いま、まちづくりや地域活性化が盛んに言われ、大学の研究室がまちに入り込んで何かを提案するというケースも多いですが、僕たちはそういうことはしないという宣言をしています。学生が2〜3日まちに入ったところで、何か提案をしたり、責任を持って企画を最後までやり遂げたりすることは難しいし、場合によっては無責任だと思えるからです。できるだけ自由に振る舞える環境をつくり出し、自由なことを言って、むしろ無責任に帰ってくることをアイデンティティとして標榜しています。そういう態度に共感してくれる人も少なからずいます。ここで言う無責任というのは、のびのびやるという意味で、礼節に欠くようなことはしません。
註
★1──http://camp.yaboten.net/entry/area_index、http://camp.yaboten.net/
フィールドワークとコミュニケーション
荒木──直感的にいえば、キャンプに参加する学生は女性が多数を占めるのかなと思いましたけど、実際はどうなんでしょう? 『キャンプ論』で紹介されている学生のコメントも女性のものが多いですし、文化祭とか、ああいう催し物ってたいがい女性のほうが積極的じゃないですか。正直、自分が学生だったら「めんどくさいな」とか思うと思うんですよね(笑)。そういう意味で、学生の反応はいかがでしょうか。
加藤──お察しの通り女性が多く、「キャンプ」に参加する学生の男女比は1:2くらいです。自分のことを棚に上げて言いますが、僕も学生だったら嫌だと思います(笑)。ゼミの活動であるとはいえ、見知らぬまちに行かされて、初めて会う人の取材をして、さらに、まめなコミュニケーションを求められますから。物怖じするし、叱られることもある。相当面倒なことを要求しています。ただ、学生はゼミの活動内容を一覧できるシラバスで選んでいるので、それを引き受けるつもりの学生たちが集まっているはずです。
荒木──一般化はできないでしょうが、女子学生のコミュニュカティブな性格と相性が良いのかもしれませんね。逆に言えば、コミュニケーションに対して意欲的ではない人はちょっと入りにくいところがあるのかな、と。私自身そうでしたけど、なかなか難しい人っていて......。彼らはもう少しコミュニケーションがうまくなるように努力したほうが良いのでしょうか? 加藤さんは『会議のマネジメント──周到な準備、即興的な判断』(中央公論新社、2016)でも、コミュニケーションに大きな可能性を感じていらっしゃいますよね。言葉を発さずともコミュニケーションせざるを得ない不可避的な条件のなかで、どう「場」をつくるのかという問題意識です。たぶんそこは私との一番の違いかな、と思ったんですが。
加藤──自らの経験から言うと、僕はほとんど社交性も愛想もなく、挨拶もできないような大学生でした。時間が経てばできるようになる、きっかけは必ずあるはずです。なので、おとなしい学生を無理矢理しゃべらせるようなことはしたくないですね。「ゼミで一緒にやっていればコミュニケーション上手になるよ」と、もっと積極的に言ってもいいのかもしれませんが、それはおせっかいかもしれず、やりたい人がやればいいと考えています。
ただ、コミュニケーションには期待をしています。人生の経過とともに人間関係や行動範囲が広がり、喋らざるをえないことが増えますし、黙っていてもわかってくれる人が現われることもあります。その意味では、諦めないほうがいいと思います。「自分は口下手だし、人見知りだから」というモードの学生も多いのですが、自分でそんなふうに決めつける必要はないと思います。普通にしていれば、大丈夫だと思いますね。
荒木──私が大学に対して、嫌だったのは、あるコードに則った型通りのコミュニケーションをしなければならない場面がしばしばあるところなんですね。ゼミの空間で、先生とお喋りする面談室で。必要があればこなしていくわけですが、型通りのものはたいてい面白くないし面倒なので、そこに前向きになれなかったという反省があります。そういえば、飲み会も遠慮していたな。いや、大学の外に出てから改めて振り返ってみると、もう少し工夫していれば自分の能力をもうちょっとバリエーションに富んだ方向に伸ばすこともできたのかな、とか思ったりもしますけど。
加藤──教員のキャパシティの問題もあります。僕も、学生に対してあれこれと苦言を呈することが多いのですが、、最近ようやく自分の思い通りにならないことがたくさんあることを「許せる」ようになってきた気がします。何年もゼミをやってきて、いい意味で「ゆるさ」を持って間口を広げておかなければ、見えないところで人を窮屈にさせてしまっているかもしれないことに思い至るようになりました。教員側も少しずつ自分のやり方を工夫していけば、状況は緩衝されていくと思います。
荒木──また直感的にいいますけど、そうした柔軟な姿勢はフィールドワーク先でのコミュニケーションでも大事なんじゃないですか。硬直しているとコミュニケーションの難易度は一気に上がる。例えば、コミュニケーションの経験値が少ないと、どういったところで失敗しがちなんでしょうか? 相手に迷惑だと思われてしまった時の対処法は?
加藤──基本的なことですが、やはり「こんにちは」「さようなら」「ありがとう」「ごめんなさい」といった挨拶と、言い方が下手であっても思いを伝えるというコミュニケーションへの意志が道を開きます。諦めない執着心です。うまくいかなかったと反省したり、嫌な思い出として刻まれたりすることの大半は、じつはコミュニケーションに関することです。「あの時になぜあの一言が言えなかったのだろうか」とか、「あの時、おじさんに言われたことがモヤッと残っているんだよね」ということがしばしばあります。やはり、コミュニケーションはフィールドワークの本質に関わっていると思います。
学生であっても、大学名の入った名札を提げているだけで、ある種の関係をつくってしまいます。どう工夫しても、人びとの日常に踏み込んで邪魔をしていることは間違いないので、すごく丁寧かつ慎重にやらなければならないと伝えています。終了後には、お礼状を書くとか、(可能なら)また訪ねてみるようにと背中を押すこともあります。本当は、僕に言われてやるのではなく、ごく自然にできると良いのですが。不思議なもので、そういうやりとりを心がけていると、より自然なかたちで関係が育まれていくようになりますね。
宮本常一と安渓遊地による『調査されるという迷惑──フィールドに出る前に読んでおく本』(みずのわ出版、2008)には、自戒を込めて「人文科学ではなく、尋問科学になってはいないか」という批判、反省が書かれています。散々インタビューをして写真を撮って帰っていき、お礼のハガキすら来ないこともある、報告書が送られてきたところで、難解な言葉ばかりが並んでいて面白くもない、というわけです。フィールドワーカーは、知らず知らずのうちに高圧的になってしまい、傲慢さが際立ってしまう場面があるのかもしれません。
荒木──分析する側とされる側の非対称性は、精神分析でもよく指摘される問題ですね。
加藤──「キャンプ」を続けているうちに、「47都道府県すべて行こう」という不思議な欲求が出てきています。いまは大学の半期、つまり前期後期でそれぞれ2回くらい、かつ夏休みに1回というペースですから、年間で5カ所ほど。ゼミで2年間活動していれば、10カ所くらいに出かけることになります。そうした体験をした学生は、やはりたくましくなります。友達との旅行ではなく、言われなければ一生行かないようなところへも行き、やりたくないこともやるという「キャンプ」の実践は、彼ら彼女らにとって、この先良い経験だったと振り返ってもらえるような気がしていますし、期待もしています。
在野の方法あるいは「無知のヴェール」
荒木──年度ごとに学生が変わっていくわけですが、フィールドワーク先との信頼関係はやっぱり「加藤研究室」というカンバンが担保しているのでしょうか?
加藤──そうだと良いですね。何年かやってきたおかげで、過去の成果物が蓄積されてきたので、それをお手本にして、違うことをやろうという思考になります。一方で「去年並みを目指せばいいか」という感じも生まれるので、難しいところです。
フィールドワークの先達として、今和次郎の方法は参考になると思います。対象を追って野に出るだけではなく、書店で展覧会を開いたり、成果を在野で見せています。僕もそれに憧れて、毎年一度、大学の外で場所を借りて「フィールドワーク展」を開催していますが、通りすがりの人から素朴な疑問を投げかけていただくこともあります[fig.4]。大学のゼミだと、どうしても教員である僕が唯一の評価者だと思われがちです。そうではない、と言っても学生は第三者からの評価についてあまり意識していないようにも見えます。評価者としての教員の立場を相対化することは、とても大事だと思います。
加藤──あと、チームで調査をすすめていたことも参考になります。どうしても、今和次郎の名前が前面に出てきてしまうようですが、銀座の調査なども、たくさんの協力者を動員して、グループプロジェクトとしてやっていたところが重要だと思います。フィールドワークは孤独な作業というイメージが強いのですが、じつはそうではなく、みんなが散らばって集めてきたものを束ねたり、整理したりしながら知をつくっていくという仕事です。
今和次郎の文章にはところどころ、「あとは任せた」と言わんばかりの無責任な印象を受けるところがあるのも、面白いですね。でも、それは単に言いっ放しということではなく、調べものの方法や調査マニュアルに近いものはまめに残しています。だから、何十年経っても、当時の調査をトレースしようと試みることができる。それが大事だと思います。
荒木──そう、一般公開の機会はやはり大切ですね。大学で行なわれるシンポジウムなんかでも、メンバーズオンリーであるかのような告知の場合と、一般参加者歓迎が明示されている場合とでは、やっぱり開かれ方がまったく違うものになります。去年なんかだと「大学の危機」がとても話題になったわけですが、そうした公開性のディスプレイの仕方をちゃんと整えることで、大学の存在理由に関する市民の納得もずっと得やすくなるのかな、と感じています。
加藤さんのフィールドワークの方法と私の研究方法に似ている点があるとするならば、なにも知らない状態を大切にするということだと思います。あるテクストを読む時に、その作家がどういうものを書いてきたか、文学史においてどう評価されてきたか、先行研究ではいかに解釈されてきたか云々、といった予備知識をあまり入れ過ぎてはいけない。まず読んでみてあなたが何を感じたのか。それを大事にするべきです。細かい情報はあとから学べますが、初めての出会い(第一印象)は、繰り返すことも、他人が代行することもできない。かけがえのない財産なんですよ。あえて無知のままフィールドワークに飛び込んでいくという加藤さんの方法に通じ合うものを感じます。
加藤──明確な目的を持ってフィールドワークを行なっている人や、教科書的な「問題解決」を目指してフィールドワークをすすめている同業者からは、無知のままで現地へ行くことを疑問視されることが多いです。まちの人からも「人口や故事来歴くらいは調べてから来い」と叱られることもありますが、僕はあえて調べずに行くことが大事だと思っています。紙に書かれていることを確認したり、ガイドブックに載っている名所でそれらしい写真を撮ったりすることが目的ではないですから。完全に先入観を捨てることは無理ですが、不勉強のまま行くことで見えてくるものがあります。
荒木──無知だからこそ見えてくるものがある。私はときどき文芸評論のようなものも書いているのですが、第59回群像新人評論賞優秀賞をいただいた「反偶然の共生空間」で取り扱ったアメリカの政治哲学者のジョン・ロールズは、『正義論』において「無知のヴェール」というアイディアを提出したことでよく知られています。これは、あえて無知になる(情報を制限すること)ことによってみんなが同意できるような偏りのない正義の原理が発見できるだろう、という仕掛けです。専門外ながら私がロールズという思想家を魅力的に思えるのは、たぶん、自分のテクストへの姿勢とつながり合うものを感じるからなんですよね。あえての無知。
加藤──ゼミの学生がどんどん入れ替わる激しい新陳代謝は、無知を可能にする仕組みとして、もっとポジティブに捉えてもいいのかもしれません。一般的には、企業などでは研修や訓練をとおして新人が成長していきますが、ゼミ生たちは、ようやくいろいろ覚えたというタイミングで卒業してしまいます。学生には「何度言ったらわかるんだ」などとは言えないのです。でも、(その構造のおかげで)つねに経験ゼロの人を相手にすることになり、初心を忘れないようになります。
荒木──面白い。自分をつねにビギナーと照らし合わせてリセットしていくということですね。入門者に対する自分を専門化していく、という感じ。イヴァン・イリイチの『脱学校の社会』では、「プロメテウス」神話が否定されています。プロメテウスとは、「先に・前に・予め pro」と「知恵 metheus」でできていて、「先見の妙」の象徴を意味します。「プロ」はプログラムやプロジェクトなどの接頭語に使われているものですね。イリイチがそれに替わって提言しているのは「エピメテウス」、つまり「後知恵」の象徴です。「エピ」の接頭語は、エピローグみたいな言葉に活きてますね。何かを経験したあとで改めて学ぶ(学び直す)ことの重要性をイリイチは主張していました。この方向でみると、いまの社会や学校制度はあまりに硬直的です。まだインターネットが現在のように確立していなかった1970年代に、彼は「ネットワーク」という言い方で学習機関の代替案を提示しようとしました。ウェブにアクセスすることで誰もが教師であり誰もが学生になれる、同一の人間が教師であると同時に学生でもある、そんな社会です。
学校制度をなくそうという主張はきっと共感が得られないでしょう。ただ、イリイチが構想した未来像はある程度真剣に考えられていい。往々にして、人は仕事に就いたあとでこそ学びたくなるものです。社会人(というよりも会社人)が学生を羨ましがるのは、社会のなかで仕事をし、さまざまな経験を経たことで、では理論的にはどうなっているのか、という関心が刺激されるからでしょう。経験のない時代では、やっぱり彼は怠惰な学生として過ごす。だから、最近の学生が勉強しない(もちろんこれ自体マユツバなわけですが)、と責めるのはお門違いです。経験だけでもダメだし理論だけでもダメ、そういう経験的に得た意識自体が、ものを改めて学ぼうとする意欲や態度にとって大事なわけです。
できれば、もっとフレキシブルな学習の選択肢が、たくさんあるといいですよね。当然、それは働き方の問題にもつながります。鶴見俊輔はアカデミズムにもジャーナリズムにも分類できない小集団の知の営みを、サークルイズムとして高く評価しました(「サークルと学問」)。そういったこともひとつの選択肢でしょう。私は毎月1回、新宿で開催される読書会に参加していますが、そのような小さなコミュニティ単位での学習が、ささやかな一例になればいいなと思っています[fig.5]。
ツールと仲間、継続性
荒木──『キャンプ論』は2009年の本ですが、「ケータイ」の画期性に触れてますよね。現在のスマホであれば、例えばフィールドワークの現場と関係ない人たちとSNSでコミュニケーションしたり、ソーシャルゲームに興じたりする学生もいるのかなと思いますが、どうでしょうか?
加藤──確かにそういうことはありますが、ケータイはツールとして依然メリットがあると思います。『キャンプ論』のなかでは、ケータイがカメラやボイスレコーダーの機能をもつという話だけでしたが、さらに技術が進歩しました。最近便利だと思うのは、現場での調整です。僕も学生もフィールドワークの最中にはバラバラに動いているので、どこかでドタキャンがあったり、交通機関にトラブルがあったりした時などは、臨機応変に対応できます。「マイクロコーディネーション」とも言われますが、フィールドワークでケータイやスマートフォンを活用すると、ローカルなコーディネーションができます。以前は、あらかじめ紙に書いた予定通りに動かなければ駄目でしたが、いまはもっと細やかな調整がスムーズにできます。
また、録音ツールを「回しっぱなし」「常時オン」にしておくことで、フィールドワーク自体に集中できるのです。僕がフィールドワークの作法を習った時代の、メモを取る、音を録るといったいささか煩雑な手続きから解放されます。定期的にカメラのシャッターを切る設定にしておいたり、GPSのログを取っておいたりすることで、昼間は現場に飛び込み、夜は宿泊先でそれを見直すことができます。「野良仕事」と「紙仕事」が、メディアの橋渡しによって連動するわけです。
荒木──なるほど。つねに「オン」にしておくことでむしろ集中できるというのは面白い。ポータブルな情報技術は、ある現実をクローズアップしますが、他方で別の現実をフィルタリングすることもありますよね。例えば、「Pokémon GO」をやっているわけですね、ニドラン♂とか連れながら(おかげさまでニドキングになりました)。で、アイテムを得るために街の各所に登録された「ポケストップ」に導かれて、いろんなところを歩く。その過程で「あ、この街にはこんな姿があったのか」と気づくことがある。ただ、そこで同時に思うのは、だとするならば「ポケストップ」に登録されていない街の細部は自分にとって不可視なものになっているな、ってことなんです。発見がある、と同時に、その背面で強力な無視が仕掛けられている。
加藤──「Pokémon GO」は、そのゲーム空間を受け入れた時点で見えなくなるものがあるのはしょうがないと思います(笑)。でも、やはりそれによってあらたな発見をする人もいるはずです。誰がどう仕組むかによって、見向きもされなかった場所を発見する手助けにもなります。
いまはとにかく技術の進歩が早いので、『キャンプ論』の頃は、1台のケータイにさまざまな機能が集約されれば、ボイスレコーダーやらカメラやら、諸々の機材でカバンのなかがごちゃごちゃにならず便利だ、というくらいの認識でしたが、状況はまた随分変わりましたね。いまの学生は、レポートもスマートフォンで書いて送ってくるので、それは想像の圏外でした。
荒木──いや、私は基本的にインターネット礼賛の人なんですよ。資料が探しやすくなったし、論文そのものがダウンロードできる場合すらある。とても良い時代です。そもそも、ネットがなければ私は文章を書いていないですしね。そのうえで、あえてデメリットを挙げるとすれば、手ごろな情報を手に入れたことで拙速に理解してしまう、この危険性ですね。ネットに上がっていないような書物や風景はたくさんある。当然のことながら、世界はネットよりも広いわけですから。私自身も気をつけなければならない。
制度との交流
荒木──ヘンリー・デイヴィッド・ソローという人がいます。『森の生活』が有名ですね。私の本のなかでは女性史家・高群逸枝が、彼の生活に憧れて世田谷の住まいを「森の家」と命名していました。彼には「ウォーキング」(『市民の反抗』所収)というエッセイがあって、そのなかで、散策すること、「ソーンタリング sauntering」の語源について言及しています。つまり、それはフランス語の「サン・テール sans terre」、「土地なし・地所なし」に由来しているのではないか、というんですね(ただ、それよりも結局は「聖地」を意味する「サン・テール Sainte Terre」のほうの語源説を自分はとりたい、と直後に述べるんですが)。土地に根づかずに逍遥しながら考える、まさに「キャンプ」的な思想です。他方、私がそこで立ち止まってしまうのは、本当に土地・地所(テール)を持たずにキャンプ的なものが持続可能か、ということなんです。もしかしたら、長く継続していくためには大学という物理的な土地を伴う強固な制度が必要なのかもしれない。
加藤──そうかもしれません。当初は「キャンパスからキャンプへ」「キャンパスを捨てよう」というスローガンを構想していましたが、両方が必要だと実感しています。現実的には、何らかの成果をまとめることや、持続可能性を考えると、どちらかを捨てるのではなく、両者があってこそ成り立つのだと思います。大学の教員というポジションに就いてしまったことが安定や安心をもたらし、だからこそはみ出そうという発想が生まれます。キャンパスの窮屈さ、息苦しさもモチベーションになっているので、つねに対比的に外の面白さを味わうことができます。先ほど紹介した「墨東大学」や「三宅島大学」の試みも、あえて「大学っぽいもの」をつくって運用してみたおかげで、「本物」の大学の成り立ちについて、あらためて考えるきっかけになりました。
荒木──ある種マゾヒスティックですね。窮屈だからこそ開放を求める。
加藤──どちらか一方だと苦しいかもしれません。
荒木──『これからのエリック・ホッファーのために』を書いている時、これは所属をもたない者の「大学に属すよりもずっと在野がよいのだ」というルサンチマンの表現なのかもしれない、少なくとも私の意図とは無関係にそういうふうに読まれてしまう可能性はあるのかもしれない、そんなことを考えていました。しかし、自分自身としてはそういった理解からは距離をとりたかった。私の本はもしかすると、東日本大震災以降の、例えば坂口恭平さんの「モバイルハウス」論や安藤美冬さんの「ノマド」論といった一連の流れのなかにあるのかもしれない。つまり、属さないことが逆にいいんだ、という逆転の発想です。しかし、在野だからできることはもちろんあるにしても、同じことは大学に関してもいえるはずです。大学でしかできないことがあるのではないか。それは何なのか。酸っぱい葡萄みたいな話じゃなくて、土地をもった大学というものを、所属なしの在野でも利用可能な公共的なツールにしていくことはできないのか。大学と在野の相互のシナジー効果を私は期待しているのですが。
加藤──少子化にともなって、学生数も大学教員のポストも減りつつあるという現実的な問題も関わってきますし、対立ではなく、積極的に相互交流すべきですね。『これからのエリック・ホッファーのために』でも、「文士(literary men)」という言葉が出てきますが、承認の問題が関係します。学位も承認されるものですが、「現場の知恵として折り紙つき」というような、「学位」に替わるものもあるはずです。少なくとも、僕について言えば「紙仕事」の成果ともいうべき「学位」が、毎日の生活に役立っていると実感することはほとんどありませんが、「野良仕事」のほうは生活であり暮らしですから、そういう意味でインテリジェントな市民として「暮らす力」あるいは「生き延びる力」を後ろ盾して承認する方法について考えることは大切だと思います。
荒木──かつては出版ジャーナリズムが学位に代替するような承認を与えていたように思います。山本七平なんかは学位を持っていませんでしたが、着眼点の鋭い書き手として出版の世界で尊敬を集めていました。天才と誉れ高い在野社会科学者・小室直樹もよく褒めていましたね。そうしたルートはけっして否定しませんし、おそらく、『これからのエリック・ホッファーのために』自体がそういったタイプの仕事とみなされているでしょう。ただ、出版ジャーナリズムは商業(カネ)と結びついているぶん、多数の読者を集めるために研究のもっていたデリケートな部分が無視され、話題先行的になりがちな点は依然として注意が必要だと思います。そうなると、「ほら見ろ、やっぱり学位がない奴はダメなんだ」という下らない論調に回収されてしまう。これは良くない。
アウトプットと宛先
荒木──博士号を取っていないのに学術研究をしていることにそもそも疑問を感じる人もいます。ただ、私は博士号が学者にとって必須の要件だとは思っていません。比較文学者で物書きとしても著名な小谷野敦さんなんかは、博士号がないのに大学教授をやっている人をよく批判してますね。それについてすら、私はあまり関心がありません。誰が大学教授になろうがどうでもいいことです。
アカデミックな人たちは私の論文を学術論文として認めず、文芸批評に近いものだと見なすはずです。他方、文芸批評の人からすれば、形式的な窮屈さを感じるかもしれません。単純に私自身がそういったタイプの文体が好きでそうしているのですが、そもそもで考えてみると、文学研究は文芸批評と密接に関係していて明確に分割できない歴史を経てきたように思います。例えば本多秋五や平野謙は、研究者に分類すべきなのか文芸批評家のほうに振り分けるべきなのか。同じ人物でも、ある文章は研究的だけど、別のものは評論っぽい。文学の領域にはこういう微妙なラインがたくさんあるわけです。そういったものを読んできた人間としては、アカデミズムの中心にいる人にも一般の人にも届くものを書きたい、そういう欲をどうしてももってしまうんですね。
加藤──僕は、文章を書くのは好きなのですが、学術論文はフォーマットに収めなくてはいけないという点を窮屈に感じることがあります。もちろん、必要に応じて書きますが、学術論文ではないかたちで書いているときのほうがハッピーです。
荒木──なるほど。フォーマットから自由という話でいえば、ウェブ・メディアの良いところは無制限に書けることで、検索してもらえれば分かりますが、私は結構な量のテクストを公開しています。ただ、ある時期以降、紙だからこそできることにも自覚的になりました。私が出した最初の著作は『小林多喜二と埴谷雄高』(ブイツーソリューション、2013)という本で、ウェブ上に書き散らした文章を、戦前の共産党運動というテーマの下にまとめ直したものです。過去のテクストを再編集し、自費出版してみて思ったのは、ある一定の紙幅のなかに収めなくてはいけないという制約によって、情報の取捨選択や知の整理整頓がかなりクリアにできたということです。つまり、重複を除いたり、引用の優先順位をはかったり、主張をよりスマートに表現したり......。紙の有限性がもつ力を痛感しました。今後ともウェブの無限の感覚と紙の有限の感覚を行き来して、自分の知にいい循環が起ればいいなと思っているのですが。
加藤──受容する読み手の問題もありますね。学術論文は、おそらく最初から比較的狭い範囲で読み手が想定されているので、読者が見えすぎてしまいます。誰が読むかわからないところに書くのも、面白いと思います。
荒木──確かに。私もある特定の人間に向けて書くのではなく、誰も読まないかもしれないけど、誰かに読んでほしいという感じで書いていますね。
加藤──僕自身は、学部生と大学院生とのあいだに明確な線引きをして、指導の方法を意識的に変えています。学部生は、論文を書いて暮らすのでなければ卒業論文は書かなくてもいいと思います。学部のカリキュラム上は「卒業制作」であって、論文である必要はありません。例えば、映像作品やプログラムをつくって卒業することも認められています。もちろん、論文を書きたい人は書けばいいし、その場合は指導もします。一方、大学院生の場合はかなり細かく論文の指導をします。分野によっては、論文という形式で書くことによって、むしろオーディエンスが広がります。学会と呼ばれる「業界」への入口になりますし、それがモチベーションにもなります。
荒木──論文的形式性はじつは社会生活において結構役立つと思うんですよね。ある種のフォーマットに基づいて一定のルールに違反せずに文章をつくり上げるという作業は、意外といろんな場面で応用可能性がある。
加藤──そうですね。そういう意味では、学部生にも論文を書かせたほうがいいのかもしれませんが、必要な状況になればやらざるを得ないわけだから、僕に言われてやらなくてもいいかなと思っています。 出版については、いまは本が売れない時代なので企画を持ち込んでも通らないことのほうが多いです。幸いにして面白がってもらえる場合は、さほど売上を期待しないという前提があるのかもしれません(笑)。『キャンプ論』は、もちろん中身を見て書棚を選んでくれている書店もありますが、「アウトドア」のコーナーに置いてあることも。著者として、もう少しコントロールできるといいのかもしれませんが、あまり気にしていません。
荒木──誤配が起こるのがいいですね。私も最初は、若い学生が読んでくれたらいいかなと思って書いたのですが、いざ出版してみると、仕事をしながら自分のやりたいことも実践したい、という「新しい働き方」系の観点から受け取ってくれた読者もたくさんいて。そうした予期できない出会いが実感できると本を出して良かったなとつくづく思います。
加藤──『つながるカレー──コミュニケーションを「味わう」場所をつくる』(フィルムアート社、2014)という本も、いろいろな書棚に入っています。3人組で「カレーキャラバン」という活動をやっているのですが[fig.6]、ご縁があって出版のチャンスをいただきました。軽い内容ですが、書いていてとても楽しかったです。自分自身、いきいきとしながら書けた感じがしました。『キャンプ論』(2009)、『つながるカレー』(2014)、『お弁当と日本人』(草思社、2015)という流れがあり、僕のなかではあるストーリが象られています。
荒木──次の本の構想はありますか?
加藤──「ワークショップ」について、まとめようとしています。近年「ワークショップ」という言葉が氾濫していますが、そもそも「ワークショップとは何か」について、日頃疑問に思っていることを綴っています。
先達の生き方と著作に学ぶ
加藤──僕は宮本常一、柳田國男のような民俗学の著作に触れて、その観察力、深み、記述量、描写力に憧れを持っていました。圧倒的なボリュームで、読む度に理解が深まるところがあります。その深さは大事で、なんらかのかたちで継承したいと意識しているかもしれません。
現在のフィールドワークは良くも悪くもカジュアルになっていると思います。時代だけのせいにはできませんが、それこそ「土地を持たず」長期にわたって歩き回ることができた時代がありました。いまは探検家であっても、あるところで留まってある仕事をして、また続きをやるというスタイルで、かつての探検家のイメージは崩れています。民俗学、文化人類学のふるまいが、いろいろな事情で断片化され、相対的にコンパクトになっているのかもしれません。かつては博士論文の執筆に際して、例えば1年間どこかに移り住んで調査するということもありましたが、最近はあまり聞かなくなっています。方法自体が大きく変化したとは思えませんが、流行り廃りはあって、いまは定性的なものや、ライフストーリーを聞くようなものが好まれている印象があります。
荒木──そのような学のカジュアル化に対して学問的な体裁を保ちにくくなることはありませんか? 例えば(民俗学に対してよく言われる悪口ですが)「単に旅をしているだけじゃないか」とか「それって研究なの?」といった質問に対してはどう対応されているんですか?
加藤──そういった質問には、答えようがないですね。自分の方法や態度を信じて耐えるしかないと思います。孤独かもしれませんし、理解者はいないかもしれませんが、数十年先の読者に向けて仕事をするという精神です。多くの理解者を得るカリスマ的資質を持った研究者がいますが、僕はそうではないので、「仲間とツール」が重要だと思っています。例えば、テレビの街歩き番組で言えば、タモリや笑福亭鶴瓶が歩けば、みんな喜んでしゃべってくれるし、家にも入れてくれます。彼らには、バリアなど感じることもなく、いきなり現場に入り込むカリスマ性があるわけです。それには敵わないわけですから、大人数でツールを駆使して、できる限りいろいろなものをたくさん記録し、持ち帰って何かを紡ぎ出していくしかありません。
荒木──私は、常々、批評家や評論家ではなく研究者になりたいと思っていました。いまもそうです。その理由は、批評家や評論家が知的スターの役回りを求められがちなのに対して、研究は天才でなくても続けられるからです。誰も興味を持っていなくても、ある題材について根気よく調べて、それを書き残しておけば、生きているあいだかどうかはともかく、いつか誰かが読んでくれて役立つことが現実にある。私自身、文献を探すなかで、あまりにマイナーな対象すぎて誰も注目していないだろうと思っていても、探してみればやっぱり過去には必ず言及している人がいて、そのこと自体に感動したりするんですよね。
研究って意外と時間と努力を裏切らないんですよ。ニッチな分野ならば、ときに大学教授以上に詳しくなってしまうことすらある。私が在野と研究という言葉をつなげるのは、その敷居の低さ、凡人でも参加できることの魅力に憑かれているからです。現在、「研究者」という言葉は、多くの場合、(悲しいことですが)大学教授を指します。しかし、当然のことながら大学の先生でなくったって研究はできる。そういう理解が常識になるような未来への願いをこめて「在野研究者」という言葉を全面に出しました。アカデミシャンとの対立を煽っているわけではありません。
加藤──フィールドワークとも共通しますが、カジュアルであってもとにかく続けることですね。10年継続すれば、必ずその道のフロントランナーになってしまいます。
僕たちがフィールドワークに行くと、例えば地元の郷土史家などの先行者がいます。商店街でも、そこに生まれ育ってずっと暮らしている人のほうが、当然のことながら街のことをよく知っているので、その人たちから話を聞いて理解することが少なくありません。得るべき情報、役に立つ知恵は大学の外にこそたくさんあり、それを持った人たちと良好な関係を築くべきです。
荒木──ある意味でフィールドワークとは在野での師匠を探し出すような営みなのかもしれませんね。
『これからのエリック・ホッファーのために』では、誰をセレクトするべきかでなかなか悩みました。自分に課した条件としては、主たる収入を大学から得ていないこと、文章に論文的な形式性があること、故人であること、この3つですね。例えば、「吉本隆明が入っていないのはおかしい」という意見をよく言われるのですが、私の理解としては吉本は研究者ではなく詩人だろう、と。だから入っていません。ただ、選びながら思ったのは、類は友を呼ぶというか、在野は在野で集まってくるというか、彼らは多くの場合、ネットワークをつくっていて、1人を取り上げると必然的に彼を支えた周囲の在野人たちの姿がパッパッと見えてくるんですね。芋づる式に。実際、吉本隆明は三浦つとむを扱った第1章で登場しています。三浦は吉本の雑誌『試行』に発表機会をもらったわけです。ほかに、森銑三なんかも民間アカデミズムのネットワークをうまく活用していましたね。森を掘っていくと、三田村鳶魚や柴田宵曲といった固有名に出会うことになる。こうした横に広がる関係性を知れたのも私にとって大きな成果でした。
若い人にぜひやってみてほしいのは、『これからのエリック・ホッファーのために』のなかで、「あ、この人、面白そうだな」と思った著者のものを実際に読んでみることです。そのために参考文献もページ数も結構細かに記しておきました。この本を入門編にして、ある研究者のスピリットに触れ、その姿勢を学んでいただけたら私としても慣れない小伝を書いた甲斐があります。
加藤──40の「在野研究の心得」というアイディアはどういうところから生まれたのですか。
荒木──個々の伝記が続くと一貫性が希薄になりがちなので、通読に耐えないと思ったんです。在野生活で重要そうに思えるポイントを抽出して、使いやすいかたちで皆さんの記憶に残ればいいな、と。気になった心得はありましたか?
加藤──先行者や理解者を見つけるとか、自分の世界を外へ広げてアクティブにしていくというのは、いろんな心得に通じていて、すごく大事だと思いました。仮に身近な理解者がいなかったとしても、本というかたちで師匠がいればいいし、勉強会や飲み会などで、仲間とゆるやかに結びつきながら、孤独さを味わうということですね。
荒木──入学シーズンですからオススメの1冊を紹介して対談を締めるのもいいかもしれない。私はアラン(本名はエミール・シャルティエ)が好きで、よく読み直しています。『幸福論』が有名ですね。彼は大学ではなく小学校の先生をしながら「プロポ」と呼ばれる短い文章を毎日書き継いでいた哲学者でした。学問的な形式を持った文章ではないですし、専門的なタームがあるわけでもありませんが、こういうかたちでも知的伝統に参加できるんだ、ってことを実感してほしいですね。入手しやすいところだと『四季をめぐる51のプロポ』かな。芸術論だと『芸術論20講』もいい。これは自宅で学習塾を開いている在野の哲学者、長谷川宏さんが訳してます。
ああ、学問的文体ではないけれど......、という意味でいえば、社会学者のゲオルク・ジンメルもいいですね。彼はずっと大学に就職できずに、私講師という身分で活動していました。身分が安定しないから、面白い講義・面白い文章でもって学生を引き付けなければならない。だから、彼のテクストには色艶があって、論じる対象も「取っ手」とか「橋と扉」とか変なのが多いんですよね。しかし、そうした着眼点がユニークな研究の糸口になる。私が初めて彼に触れた『ジンメル・エッセイ集』を推しておきます。こういう文章がこの世界にちゃんと残っていることを知っておいてほしいですね。
加藤──僕のおすすめは、オスカー・ルイスというアメリカの人類学者の『サンチェスの子供たち──メキシコの一家族の自伝』です。「読み物」として人類学に接することができるものです。ものすごく個別具体的な記述でありながら、深い洞察があります。人類学は、なんとなく遠く離れた島に行くようなイメージを持ちがちですが、ごく身近なところに住まう家族のもとへと通い、お父さんの目線や子どもの目線で詳述していて、すごく興奮して読みました。自分の知らない世界であっても、観察に基づいて記されているものに感情移入さえしながら読める、という意味で、このような方法があるのだとものすごく印象深かったです。すごく大事な1冊です。
ほかにはウィリアム・ホワイトの『ストリート・コーナーソサエティ』など、地元に密着しながら綴られた、あるコミュニティの物語みたいなもの、そういうタイプの本が原点であり、刺激を受けました。
日本のものだと、佐藤郁哉さんの『暴走族のエスノグラフィー──モードの叛乱と文化の呪縛』がよく定番として挙げられますが、それには確かな理由があると思います。
荒木──学問じゃないと言われても孤独に耐えるしかない、という話もありましたが「自分の1冊」を見つけておくと、「俺はこいつみたいになりたいから書いているんだ」と自信の根拠をもつことができる。そうなれば、たとえ外からヤイノヤイノ言われても、結構挫けることなく乗り切れたりするものです。
加藤──本当にそうだと思います。自分にとってのヒーロー、ヒロイン、師匠を見つけることですね。
[2017年3月1日、神楽坂にて]
加藤文俊(かとう・ふみとし)
1962年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部教授。慶應義塾大学大学院経済学部研究科修士課程、ペンシルバニア大学大学院修士課程、ラトガース大学大学院コミュニケーション研究科Ph. D課程修了。専門はコミュニケーション論、メディア論、定性的調査法。共著=『X-Design 未来をプロトタイピングするために』(慶應義塾大学出版会、2013)、『つながるカレー──コミュニケーションを「味わう」場所をつくる』(フィルムアート社、2014)ほか。著書=『キャンプ論──あたらしいフィールドワーク』(慶應義塾大学出版会、2009)、『おべんとうと日本人』(草思社、2015)、『会議のマネジメント』(中央公論新社、2016)。
荒木優太(あらき・ゆうた)
1987年生まれ。在野研究者。専門は有島武郎。明治大学文学部博士前期課程修了。受賞=「反偶然の共生空間──愛と正義のジョン・ロールズ」第59回群像新人評論賞優秀作。論文=「有島武郎『卑怯者』における子供/達の群れ──〈他者〉論のパラドックス」(『有島武郎研究』18号、2015)。著書=『小林多喜二と埴谷雄高』(プイツーソリューション、2013)、『これからのエリック・ホッファーのために──在野研究者の生と心得』(東京書籍、2016)。


