音を通して考える──あるいは公共性からのオプトアウト
公共問題としての騒音

- 松山直希氏
松山直希(以下、松山)──この特集は、音と公共性の関係を探ることを目的としています。なぜ音に関心を持っているのかというと、当たり前のことのように見過ごされることが多い「前提」を問うきっかけを与えてくれると思っているからです。この特集では、そのような前提である「公共性」という概念を、音を通して新たに問うことができないか、と考えております。「公共性」というとき、わたしたちはいったい何を指しているのか? 「公共」は、すでにそこにあって利用できるようなものと想像されがちですが、ベイストゥルフェルトさんの著作は、公共性の概念や、公私の境界が複雑な力学のなかで形成され、歴史的な変遷を経てきたことを明らかにしています。では、公共性とはどのように構築されているのか?
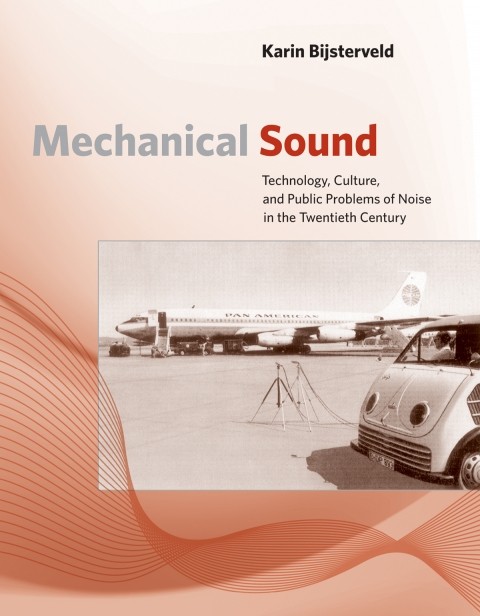
- Karin Bijsterveld『Mechanical Sound:
Technology, culture,
and public problems of noise
in the Twentieth century』
(MIT Press, 2008)
この問いに答えるために、まずは、『Mechanical Sound: Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century』★1における騒音についての議論から始めたいと思います。この本は、19世紀後半の産業化による音をはじめとする、近隣や航空機の音など、さまざまな音の分析を通して、20世紀を通して騒音が問題としてしつこく存続してきた様を紹介しています。同書で説明されている通り、例えば悪臭が衛生の概念の台頭などで都市から追放されたのとは対照的に、騒音問題は根絶されるに至りませんでした。これは現在の日本でも明らかであり、例えば保育園の建設にこどもたちの声や出す音を騒音とする観点から反対する記事などがメディアに登場することも珍しくありません。さて、まずお聞きしたいのは、騒音がいかに私的な問題ではなく、公的な問題であったのか、ということです。

- カリン・ベイストゥルフェルト氏
カリン・ベイストゥルフェルト(以下KB)──最も簡単な答えは、積極的に遮断しないかぎり、音以上に簡単に空間を伝わっていくものはないということでしょう。音以上に、公の生活があることを認識させるものは思いつきません。音を聞いた瞬間、自分と同じ空間にほかの人や、動物や、ものが存在していることに気づきます。空間を共有しているという認識は、聴覚に大きく依存しているのです。今ひとりでいると思っていたとしても、少し音に耳を傾けてみると、外で建物の回収作業をしている人たちがいることがわかります。音は、公共性の概念、他者との空間の共有を裏づけるものなのです。

- Karin Bijsterveld, Eefje Cleophas,
Stefan Krebs, Gijs Mom
『Sound and Safe:
A History of Listening Behind Wheels』
(Oxford University Press, 2004)
そういった意味では、音について考え始めた途端、公的空間とは何なのか、私的空間とは何なのか、またどのようなプライバシーのかたちが享有され、それはどのような意味を持つのか──そのような問いにすぐに直面することになります。これは、音が公的・私的とみなされるものの境界を容易に侵害し、かつその両方の定義に加担しているからです。これは、車の音の歴史に焦点を当てた『Sound and Safe:A History of Listening Behind Wheels』★2でも考えたことです。そこでは、プライバシーの概念を「誰があるいは何が自分の空間にアクセスできるのかをコントロールできる度合い」として捉えました。もちろん、車がこれほどまでに重要になった理由は多々ありますが、聴覚的プライバシーを確保しづらい世の中において、車が音環境をコントロールし、「音響的繭(acoustic cocoon)」と形容できるような空間をつくることを可能にするという観点は不可欠でしょう。この性質は、モビリティの自由の拡張など、車のほかの成功要因と比べて十分に理解されているとは言い難いものです。音は、人々が車を通して獲得する、ほかのかたちの自由に注意を向けてくれるのです。
松山──ベイストゥルフェルトさんは、公共問題としての騒音に取り組むうえで、社会学者のジョセフ・ガスフィールド(Joseph R. Gusfield)などが展開する「公共問題」論(public problem theory)★3を参照されています。これは、1970年代に、公共問題の文化と構造を同時に分析するために社会構築主義の考え方を導入して社会的な問題を扱うために浮上した観点です。公共問題論が、どのように公共性を概念化し、それが騒音問題を紐解くうえでどのように有効だったのかを説明していただけますか?
KB──まず、何よりも参考になったのが、「社会問題」と「公共問題」の区別です。これは、私にとって非常に重要でした。すべての社会問題が公共問題になるわけではないことに気づかされたのです。人は多くの問題を体験しますが、そのすべてが公的な議論の場に浮上するわけではありません。騒音を取り扱ううえでこの洞察はきわめて有効でした。どんな時代でも騒音に対する不満があったことはわかっているのですが、顕著な公共問題になったのは19世紀後半が初めてで、その後20世紀に本格的に公の舞台で関係当局や、専門家、多種多様な活動家の議論の対象になりました。「社会問題」と「公共問題」の区別を理解するには、いじめの例が役に立ちます。いじめは、長い間、私的に対処されるべきものとされていました。しかし、現在では、さまざまなプログラムが学校に導入されたり、専門家が関わったりすることによって、公共問題になっています。
何らかの事象が公共の場で実体化するには、特定のアクター(行為主体)に「所有」される必要があります。「所有者」とは、問題を定義し、その原因を特定し、解決の責任の所在を断定する者です。そうする力を持った者、というよりも集団のことです。しかし、問題によっては、公に浮上した後に、個人に押し返されるものもあります。例えば、近隣騒音の問題では、デシベルメーターの使用など、あらゆる取り組みが提案され、検証されましたが、西洋を含むほとんどの文化圏では、そのような解決策が受容されませんでした。その代わりに何が起こったかというと、問題の「再個人化」です。つまり壁を厚くしたり、バッファーとして大きな庭を設置したりという個人的な解決策にたどり着きました。言うまでもなく、これはそのような手段を採るためのお金がある人のほうが対処しやすいことになります。航空機騒音など、公となったその他の問題では、「客観的」な計測を導入することで対処することがありますが、このような計測は一般人には理解できないことが多く、騒音が「コントロールのパラドックス」に囚われることにつながります。すなわち、定量化をベースにしたマネージメントの考え方が、逆に問題に対する人のコントロール感を奪ってしまうのです。
階級と「礼儀正しい」ふるまい
松山──この公共問題の個人化について、『Mechanical Sound』では、部分的な「脱政治化」という表現もされています。
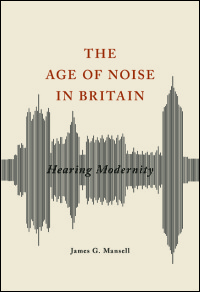
- James Mansell
『The Age of Noise in Britain』
(University of Illinois Press, 2016)
KB──ええ、公共問題が個人化されると、それは部分的に政治性を失うのです。心理学の例がわかりやすいかと思います。いくつかの公共問題は、その問題に耐えることができない人を病的だとする心理学者によって対処されました。騒音の場合、騒音に敏感な人が病的な状態にあると診断されました。ジェームズ・マンセル(James G. Mansell)が書いた『The Age of Noise in Britain : Hearing Modernity』★4という素晴らしい本があるのですが、このような動きの文脈をきわめて詳細にあぶり出しています。彼によると、医師が心理学ではすでに廃れていた「近代的な都市が感覚に刺激を与えすぎる」という考え方を借用して、騒音問題に介入しました。しかし、同時に複数の心理学者が騒音に敏感な人を、単純に「近代に対応ができていない」という理由で、病的だとしました。これが、部分的脱政治化です。
松山──なるほど、公共の問題が公の場から引き下ろされ、私的な領域に位置づけられることによって共同的に扱うことが不可能になるということですね。騒音問題のほかの経路として、騒音発生者が「礼儀正しくない(uncivilized)」ふるまいをしていると糾弾する現象がありました。これは特に騒音がヨーロッパで公共問題として実体化した初期、19世紀後半から20世紀前半にかけて観察されることです。静寂が「貴族的」なものであり、すべての人々が求めるべきで、その実現に向けて教育されるべきものとして提示されました。階級や権力の要素がここに色濃く出ていますね。

- John M. Picker
『Victorian Soundscapes』
(Oxford University Press, 2003)
KB──おっしゃる通り、騒音が初めて広く議論されるようになった19世紀末前後、「礼儀正しい(civilized)」ふるまいという考え方は顕著なテーマでした。医療関係者、エンジニア、作家など、あらゆる「専門家」がこれに関与し、ほかの人がどのようにふるまうべきなのかを公の場で定義しました。ジョン・ピッカー(John M. Picker)が『Victorian Soundscapes』★5で論じたように、19世紀には家で執筆する作家のような、集中するためにある程度の静寂を必要とする新しい階級が台頭しました。静寂が重要な資源となったこの新しい階級は、下層階級が鳴らす音を自信を持って揶揄することで、それを守ろうとしました。
しかし、糾弾された側も徐々に反撃を開始します。例えば、オランダでは社会主義政党や共産主義政党が、エリートがコンサートホールに行ったり家で楽器を演奏できるのに、ほかの人の音へのアクセスを制限することは不公平だという議論を展開しました。この時代に最も騒音問題の対象となっていたのは、ラジオや蓄音機ですが、下層階級の間では楽器に等しいものとしてみなされていました。さらに、個人的に開「耳」的だったのは、下層階級は騒音を発生させているのではなく、ただ音を共有しているのだという論法です。この議論は、プライバシーや私的空間に関してさまざまな考え方があることを浮き彫りにしたわけです。このような抗議のため、騒音に関する地方条例はかなり曖昧になりました。伝統的な音楽楽器と機械的なものを含む双方の「楽器」は「迷惑にならない程度で使用しなければならない」などの言い回しがその典型例です。この曖昧さのせいで、苦情があっても明確な解決に至らないことがほとんどでした。
これらは、すべて階級社会に関連することです。ある階級が、ほかの階級の「声」を制限しようとし、その制限が拒否された。これは、上層階級が問題の定義に成功することが多かったため、異例のことです。階級の影響を示すもっとも明確な例は、1920年代と30年代の騒音に関する大規模な議論において、産業音がまったく問題にならなかったことでしょう。焦点は、街路の騒音だったのです。工場で働く人にとっては、音が実際に聴覚に害を及ぼしていたのですでに問題だったのですが、その認識が共有されるには時間がかかりました。特徴的なのは、やはり自分たちの耳にとっての騒音を発生させる人を侮辱することに対して、エリートが何の抵抗も感じていなかったことでしょう。記録に残っている言葉の攻撃性は特筆すべきものがあります。これは、現在では考えられないことです。
松山──はたして、そうでしょうか。他人のふるまいを正しくないものとして侮辱するという現象は、今でも見られるような気がします。音について考えていると、メタファーとして現代の状況をつかむのに役立つのではないかという気がしています。例えば、ひとつの公共空間として考えることができる、ソーシャルメディア。ソーシャルメディア上のコミュニケーションを、不協和音や共鳴として捉えることができないか。ソーシャルメディアに対してよく用いられる「エコーチェンバー」という表現も、聴覚を示唆させます。これに関連して、注目したいのは、ソーシャルメディアに蔓延する情動的で攻撃的なコミュニケーションです。今お話しいただいた、他者のふるまいを定義する「権利意識」という観点は、このようなコミュニケーションに当てはまるかと思います。そして、現在の政治的状況を鑑みると、違ったかたちでの階級問題の再浮上ということもできる。
KB──私にとっては、それは別の話です。もちろんソーシャルメディアでも攻撃はありますが、それらが匿名で行なわれることが多いことは念頭に置くべきでしょう。私が描写している状況では、例えば大学教授のようなエリートが、公の場で何が「礼儀正しいふるまい」であるのかを定義する権利があると感じていたわけです。今日、ある大学教授が例えば「オートバイに乗る人は愚かで無神経な野蛮人だ」と言ったら、次の日さまざまな人たちから脅されるに違いありません。そういった意味では、権力関係は完全にかたちを変えています。
- 公共問題としての騒音/階級と「礼儀正しい」ふるまい
- 騒音の法律化と科学化/「オプトアウト」する権利/入り口としての音


