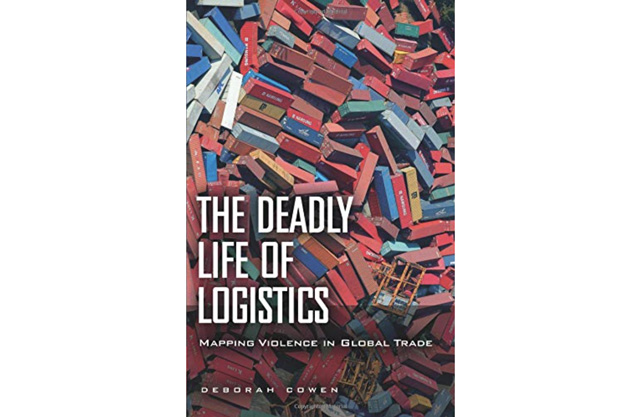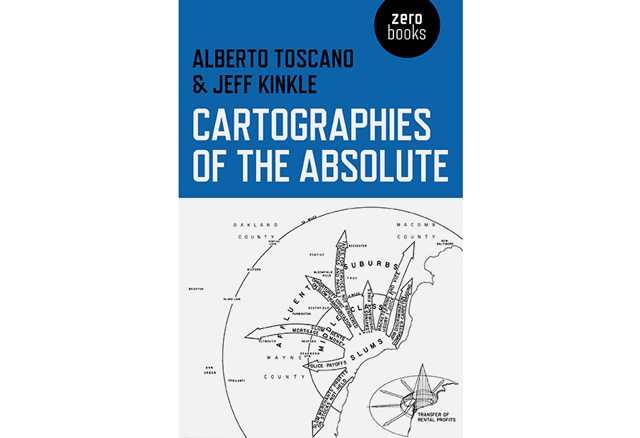忘却された空間からの視角──ロジスティクスと都市のインフラストラクチャー
1970年代初頭にアンリ・ルフェーヴルは、いまや資本主義は「モノの生産」から「空間の生産」へと移行しつつあると論じた。このなかで空間は、多様な質をもつ土地から切り離され、抽象化された量へと還元される。ルフェーヴルにとって、規格化された住戸を積み重ねた集合住宅は、抽象空間の生産を具現させる建築だった。ところで同じ時代に、海上では「物流革命」が急速に進展していた。それを具現するのは、コンテナという抽象化された箱である。「比較可能性の必要を満たしてくれたのは、ほぼ似たような『細胞』を生産することであった」★1。ルフェーヴルのいう「細胞」とは、陸面にあっては集合住宅の住戸であり、海面にあってはコンテナであった。
こんにちコンテナは、あらゆる場所に姿を現す。コンテナを搭載した貨車やトラックが通り過ぎる光景は、さして目を引くこともない。コンテナが簡易的な店舗や住宅として転用される姿も、見慣れた光景である。だが、それは日常生活からかけ離れた世界のなかにも出現する。コンテナは、ときに難民を強制的に収容する「収容所」ともなる。戦地の報道では、軍事物資を運搬するコンテナの姿が映し出される。同じかたちの箱が地球上に遍在するという事実は、私たちの目を海という「忘却された」空間へと導いていく★2。その空間からの視角は、プラネタリー・アーバニゼーションを展望し、批判するための手がかりを与えるだろう。
コンテナと暴力
かつて都市には、「波止場」と呼ばれる場所があった。数々の歌謡で歌われたように、その言葉は、別離や悲哀といったほの暗い抒情を孕んでいる。またその奥底には、暴力の影がつきまとう。たとえばマーロン・ブランド主演の映画『波止場』(1954)は、港を支配するマフィアに抗う、若き港湾労働者の姿を描いた。同時期の1957年に神戸港で起きた労働者のリンチ殺害事件(花本事件)が示すように、この物語は当時の波止場の社会的現実を映し出したものだった。
ところで『波止場』の原題は、「On the Waterfront」である。「波止場」と「ウォーターフロント」は、同じ意味内容を示す表記の違いでしかない。けれども、2つの言葉がもつ語感は、大きく異なる。1960年代末以降のコンテナ化は、「波止場」の社会的世界を葬り去り、「ウォーターフロント」と称される空間を生み出した。この新しい空間には、ショッピングモールが建ち並び、商品化された場所のスペクタクルで満たされている。他方でコンテナ化は、まったく対照的な、もうひとつの空間をも生産した。巨大なガントリー・クレーンと倉庫が延々と並ぶ、コンテナ・ターミナルの無機的な景観である。この透明で広大な空間において、「波止場」に特有の暗い抒情は、見る影もなく消し去られている。それでは、かつて港を支配した暴力は、過去のものとなったのだろうか。
ここで私たちは、コンテナ化の起源を思い起こすべきだろう。はやくも1957年に、マルコム・マクリーン率いるシーランド社は、ニューアークからマイアミへのコンテナ船の航行を成功させた。だが現実にこのシステムが席巻するのは60年代末以降であり、そこに約10年のインターバルが差し挟まれている。それは、ヴェトナム戦争の時代にあたる。コンテナはヴェトナムの戦地で実用性を見事に証明し、この経験を経て「物流」という用語は、「ロジスティクス」という軍事的かつ経済的用語へと塗り替えられた。ヴェトナム戦争の兵站基地とされた沖縄の那覇港は、コンテナが到来した最初期の港であるが、そこには大量の軍事物資が運ばれたのである★3。この時代にコンテナに積み込まれ持ち込まれた枯葉剤(エージェント・オレンジ)は、いまなお住民の身体を脅かしている★4。
したがって物流革命と戦争は、切り離せない関係にあった。コンテナ化が世界各地の港湾を席巻していく過程を、デボラ・コーエンは「社会戦争」と表現する★5。この「戦争」が標的とするものは、労働者の身体だった。コンテナは、まず労働者の集合的身体に攻撃を仕掛けた。つまり荷役を機械化することにより、多数の労働者を不要化し、失業に追いやった。それだけでなく、一人ひとりの労働者の身体の有機性をも解体しようとした。コンテナ化によって港湾には、「大量病気製造工場」と表現すべき状況がもたらされたのだという★6。たとえば「新しい港湾病」の典型である「フォークリフト病」とは、たんに座りすぎによる症状ではない。それまでの機械では考えられないほど縦横無尽に動くフォークリフトの過度にスムーズな動作が、操縦する労働者の諸関節を痛めつけたのである。
戦前期にチャップリンは、『モダン・タイムス』(1936)のなかでベルトコンベアに縛りつけられた労働者の姿を描き出した。同じように戦後期のコンテナ・システムは、しばしば工場のベルトコンベアになぞらえられる。この「システム」は、船舶や港、トラックや鉄道など、箱に詰め込まれた商品が消費地に届くまでのルートを構成する要素を、ひとつらなりのインフラへと組織した★7。いまや工場は、「社会工場」となった。またベルトコンベアの固定性とは異なり、コンテナ・システムはすぐれて柔軟である。移動可能性を手にした産業資本は、ひたすらに労働力の費用削減を求めて国内外を移動するようになった。やがてそれは、ウォルマートやアマゾンに代表されるような低賃金工場を、世界規模で増殖させていった。この新たな「倉庫労働」のなかで、労働者たちはスマートな情報監視システムに繋がれ、「人間の否定」と表現されるような過酷な労働を強いられている★8。
現代のコンテナ・ターミナルには、たとえばドン・コルレオーネ★9のような、人格的な暴力の影は見当たらない。たしかにコンテナは、マフィアやヤクザの「シマ」を根元から掘り崩した。だが、暴力支配が過去のものになったわけではない。マフィアに代わって港湾を支配したのは、機械とインフラのアレンジメントからなる「システム」だった。このシステムのなかで、暴力はどこか特定の場所に身を置いたりはしない。それは、コンテナ・ターミナルの環境そのものと化したというべきだろう。権力は、インフラのうちに存在する。「誰もそれを見ないのは、それがつねに視角に入っているからである」★10。
ロジスティクスと都市のインフラストラクチャー
またコンテナ化を皮切りとする運輸革新と建造環境の創出とは、マルクスが論じた「時間による空間の絶滅」という資本の傾向を実現させる、大規模な企てでもあった★11。ところで情報技術がどれだけ発達しようと、流通時間がゼロとなることはありえない。超大型コンテナ船の沈没事故の報道は、いまだに諸商品の移動が地表の重力から自由になるわけではないことを、痛烈に認識させる。だからこそ、「資本の規定のうちには、一方で連続性が含まれていれば、他方では同じく、連続性の中断が含まれている」★12という命題は、いっそう重みを増す。
ロジスティクスの都市空間への適用と拡張は、新たなインフラストラクチャーの創出を伴っていた。それらのインフラが狙いとするのは、フローの連続性をかく乱するリスクからの防御である★13。かつて波止場では、労働者が積荷から食糧や酒を抜き取る「荷抜き」の行為は「ニゴ」と呼ばれ、低賃金を補う権利として慣習的に認められていた。だが1950年代に「荷抜き」は、一転して撲滅されるべき犯罪とみなされるようになった★14。この出来事は、ロジスティクスの世界の到来を告げる、最初の兆候だったといえよう。この世界のなかでは、ストライキから電車の遅延にいたるまで、流通を中断させる要素はすべて潜在的な脅威とされ、非難にさらされる。ロジスティクスの都市空間への適用とは、都市インフラが「シームレス」のスローガンに覆われていく過程でもあった。
そう考えたとき、「波止場」という言葉が、ある重要な響きをもっていることに気づかされる。それは、「波」が「止」められる「場」であり、海面と陸面という相異なる空間が衝突する場である。海面をつたう物流の流れは、ここでいったん中断されなければならない。この中断ゆえに、形成される場所であった。いま手元に、「港の掛け声歌」を紹介した資料がある★15。そこには、たとえば次のような歌が紹介されている。「辛抱しなさい、金貯めなさい、そしてあんたは死になさい。ヤートコサンヤ、ドッコイサンヤ」。この歌詞は、かつての港湾労働がいかに過酷であったかを伝える。だがそれだけでなく、これらの歌詞が歌われていた事実から、労働が集団的な身体のリズムを奏でていたことを知ることができる。
この当時のグローバル経済とは、抽象的であると同時に、身体的に感受しうるものでもあった。それは、触り、嗅ぐことのできるなにものかであった。それゆえ「波止場」とは、グローバルな連帯が繰り広げられる場ともなった。朝鮮戦争当時の大阪港では、港湾労働者として働いていた反戦活動家たちは、「はしけに乗ってる船漕ぎのおっちゃんおばちゃん」の支援を受けながら、軍事物資と思しき荷物を海に投げ捨てたのだという★16。そこには、自分の身体行為が国境を超えた連帯へ直結することへの、たしかな感覚があったはずだ。
認知地図を求めて
私たちが「波止場」へと立ち戻るのは、郷愁に誘われてのことではなく、都市の理論的展望を切り開きたいがためである。流通がせき止められる地点を、チョークポイント(Choke Point)という。注目すべきは、都市と資本主義を批判する新たな理論の地平が、このチョークポイントから生み出されていることだ。
たとえば、2011年のオキュパイ・オークランド闘争から生み出されたジャスパー・バーンズの論考は、「下からの理論」を求めながら、現代世界を構成するインフラはその本質からして労働者に敵対的かつ有害なものでしかないことを論じる★17。また彼の主張に対し共感的な批判を繰り広げたアルベルト・トスカーノは、ジェフリー・キンクルとの共著のなかで、ロジスティクスに覆われた現代資本主義を把握するための表現技法を探究している★18。重要なことに彼らの議論は、ときに対立しながらも、「認知地図」を生み出す切迫した必要性をともに訴えかけている。ロジスティクスは、失業と低賃金を押し広げただけでなく、かつてないほど世界を不透明なものにした。認知の混乱は人々の実存を脅かし、その不安につけこむように、場所の反動★19やナショナリズムが頭をもたげていく。
だからこそ私たちには、自分たちがグローバル経済のどこに位置しているのかを見定める地図が必要なのだ。その地図は、デジタル的なものではありえないだろう。シチュアシオニストの漂流の地図がそうであったように、連帯の感覚を呼び覚ます「質」をもたなければならない。あるいは、ルフェーヴルのいう「出会いの政治」を、実現可能にするものでなければならない★20。かつて波止場でたしかな手ごたえをもっていたあの感覚を、いかにして取り戻すことができるか。いま、そのことが問われているのである。
註
★1──アンリ・ルフェーヴル『空間の生産』(斎藤日出治訳、青木書店、2000)485頁
★2──Allen Sekula, Fish Story, Mack, 2018.
★3──那覇港に向けたコンテナ輸送は1966年7月に供用が開始され、翌67年4月にはフィリピンのスービック湾へと輸送網は拡張された(Joint Logistics Review Board, "Containerization: Based on Lessons of the Vietnam Era [Executive Summary]", 1970, 2-22)。
★4──ジョン・ミッチェル『追跡 沖縄の枯れ葉剤──埋もれた戦争犯罪を掘り起こす』(阿部小涼訳、高文研、2014)。
★5──Deborah Cowen, The Deadly Life of Logistics: Mapping Violence in Global Trade, University of Minnesota Press, 2014.
★6──六大港統一情報センター『六大港統一情報』第2号(1977)76頁
★7──マルク・レビンソン『コンテナ物語──世界を変えたのは「箱」の発明だった』(村井章子訳、日経BP社、2007)
★8──ジェームズ・ブラッドワース『アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した──潜入・最低賃金労働の現場』(濱野大道訳、光文社、2019)
★9──映画『ゴッドファーザー』(1972)の主人公ドン・コルレオーネのモデルは、実在するニューヨークの大物マフィアであったと伝えられる。
★10──不可視委員会『われわれの友へ』(HAPAX訳、夜光社、2016)84頁
★11──デヴィッド・ハーヴェイ『空間編成の経済理論──資本の限界(下)』(松石勝彦+水岡不二雄ほか訳、大明堂、1990)
★12──カール・マルクス『資本論草稿集(2) 1857-58年の経済学草稿 第2分冊』(資本論草稿集翻訳委員会訳、大月書店、1997)427頁
★13──Cowen, op. cit., pp.76-79.
★14──宮崎学『近代ヤクザ肯定論──山口組の90年』(筑摩書房、2010)153頁
★15──永井一郎『港の思い出話』(2003)
★16──西村秀樹『大阪で闘った朝鮮戦争──吹田枚方事件の青春群像』(岩波書店、2004)、136頁。
★17──Jasper Bernes, "Logistics, Counterlogistics and the Communist Prospect", in Endnotes (3), 2013.
★18──Alberto Toscano and Jeff Kinkle, Cartographies of the Absolute: An Aesthetics of the Economy for the Twenty-first Century, Zero Books, 2015.
★19──ハーヴェイが警告するように、「場所の再発見はあらゆる進歩的ポリティクスの構築と同じだけ多くの危険をも提出する」。すなわち場所に根を下ろすことへの渇望は、テーマパークのような商品的な場所のファンタジーへとたやすく結びついたり、ゲイティッド・コミュニティのような排他的・共同体主義的ポリティクスへと陥ったりしかねないのである。(デヴィッド・ハーヴェイ「空間から場所へ、そして再び──ポストモダニティの条件に関する省察」中島弘二訳、『空間・社会・地理思想』第2号、大阪市立大学、95頁、1997)
★20──アンディ・メリフィールド「都市への権利とその彼方──ルフェーブルの再概念化に関するノート」(小谷真千代+原口剛訳、『空間・社会・地理思想』第21号、大阪市立大学、107-114頁、2018)。
原口剛(はらぐち・たけし)
1976年生まれ。神戸大学大学院人文学研究科准教授、都市社会地理学、都市論。主な著書=『叫びの都市──寄せ場、釜ケ崎、流動的下層労働者』(洛北出版、2016)、『Marxism and Urban Culture』(共著、Lexington Books、2014)、『釜ヶ崎のススメ』(共著、洛北出版、2011)。主な訳書=ニール・スミス『ジェントリフィケーションと報復都市──新たなる都市のフロンティア』(ミネルヴァ書房、2014)。