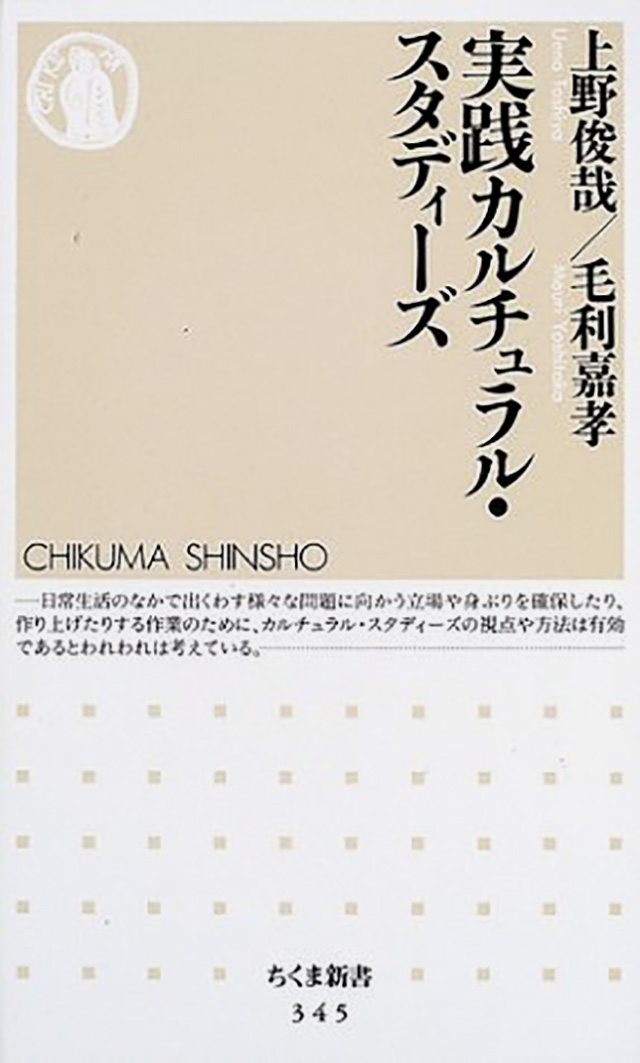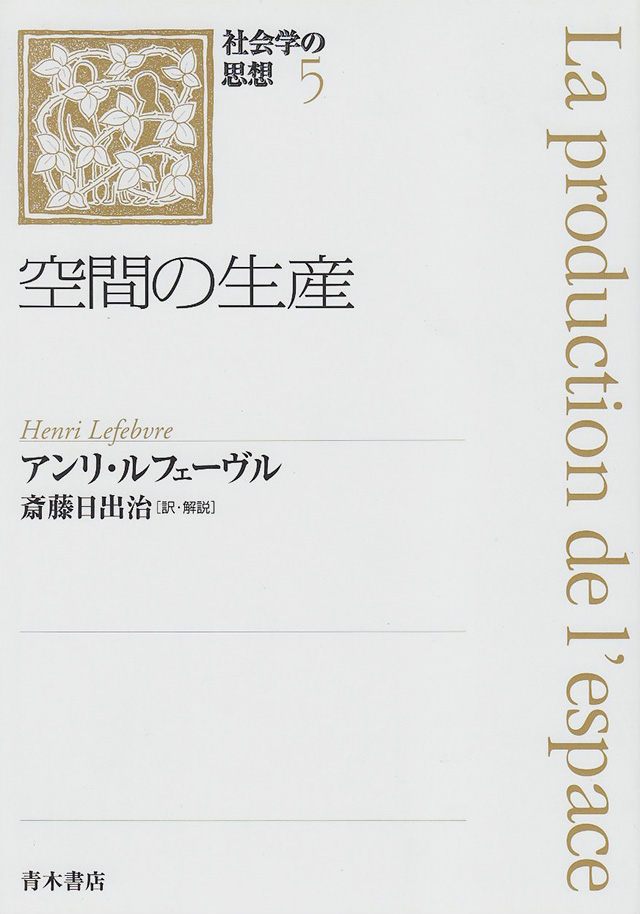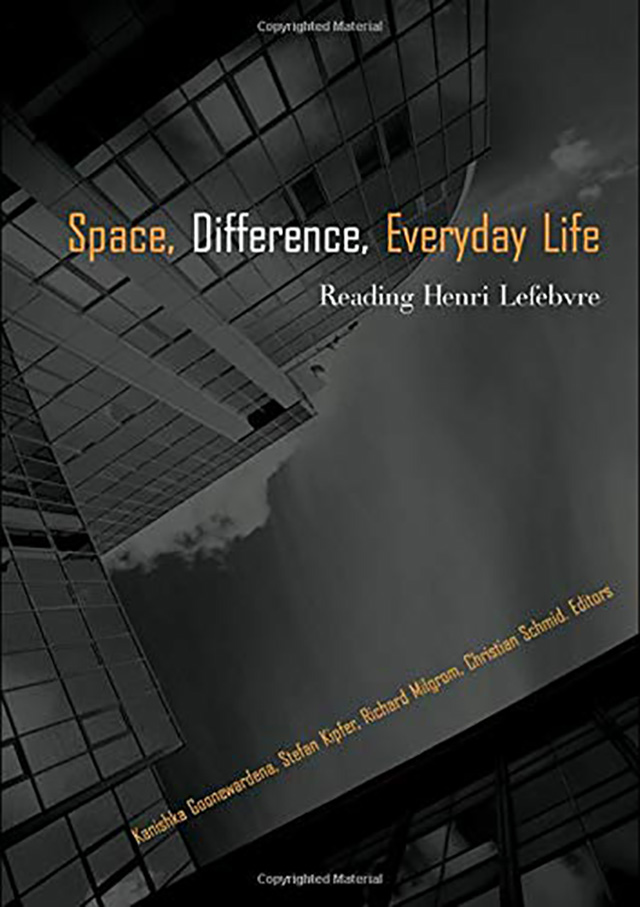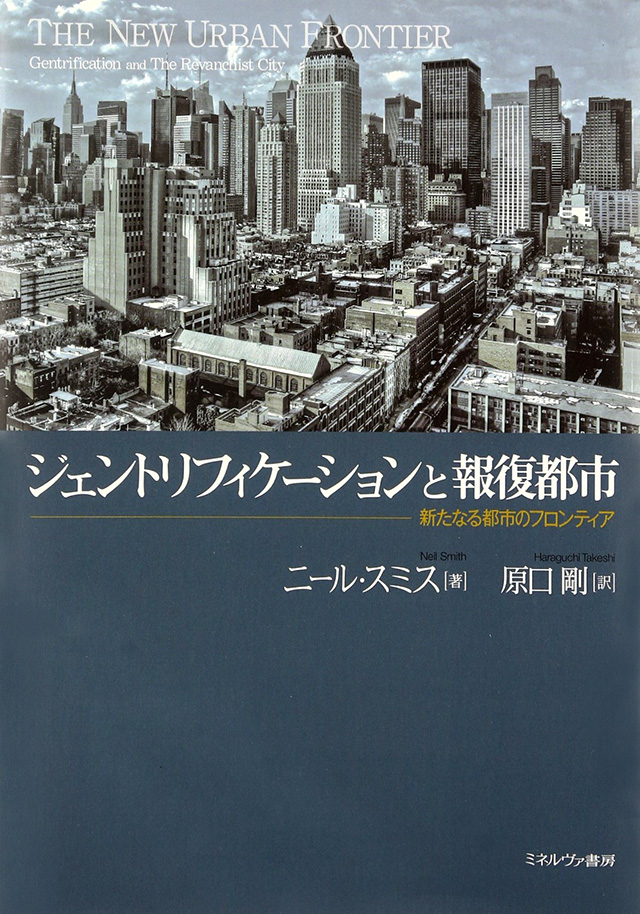進行形の都市研究を立ち上げる──プラネタリー・アーバニゼーションは遷移、侵犯する
ルフェーヴルから辿れるもの、切り開かれるもの
編集──本日はよろしくお願いします。2018年11月号で「プラネタリー・アーバニゼーション──21世紀の都市学のために」を特集しました。この6月号は続編です。11月号では、議論を牽引するニール・ブレナーによる批判的都市理論をはじめ、アンリ・ルフェーヴルなどの都市論を参照しつつ、従来の都市中心的(「グローバル」)ではない「プラネタリー」な変化の現れについて広範な議論が紹介されました。例えば、平田さんによる「プラネタリー・アーバニゼーション研究の展開」における一節、
この概念は地球というスケールからトップ・ダウン式に都市のスケールを考察するものでもないし、都市に普遍的な理論モデルを適用することでそのモデルとの合致や逸脱を検証しようとするものでもない。それゆえ〔クリスチャン・〕シュミットがドリーン・マッシーに依拠しながら強調するように、プラネタリー・アーバニゼーション研究は、日常生活が営まれるローカルな場から、都市、国家、超国家的な地域に至るまで(...)さまざまな場の連関とそれに変化をもたらす過程を検討する「関係論的」アプローチを採用するのである。
といった整理は、とても21世紀的な研究視座を差し出していると思います。余談から入ることになりますが、『現代思想』2019年5月臨時増刊号「現代思想43のキーワード」のことを思い出しました。「Philosophy & Ethics」をめぐって選ばれた複数のキーワードは、いずれもがポスト構造主義の諸理論からの切断面を見せていると感じます。なかでも、門林岳史さんが書かれた「新しい唯物論」の項における、ポスト構造主義とは単純に整理すれば「社会構築主義」と「テクスト中心主義」であり、バイオテクノロジーや情報技術が再構築する具体的身体の経験科学的説明図式や、グローバル経済による格差拡大や強大国による政治的介入、経済活動が引き起こしている地球環境破壊など、物質的次元での問題に対する批評理論の構築への意志が各所で切断線を引き、乗り超えようとしているという状況認識に首肯し、プラネタリー・アーバニゼーションの議論もまたこうした状況から遠くない場所から立ち上がっていると感じました。今日はお二人がどのように研究を始められたかというお話をはじめ、さまざまなご関心や議論の課題などを伺いたいと思います。
仙波希望──よろしくお願いします。いまのお話は感覚的にもよくわかります。ポスト構造主義的なるものを乗り超える、というのは、僕が大学に入学した2006年くらいでも頻繁に耳にした気がします。その頃はカルチュラル・スタディーズ隆盛期の後半にあたり、上野俊哉さんと毛利嘉孝さんによる『実践カルチュラル・スタディーズ』(ちくま新書)が出たのが2002年でした。同じ年には太田出版から錚々たるメンバーが寄稿した『必読書150』も出ています。これを片手に何とか掲載された書物を読んでみようとして、挫折を経験したのが僕や友人たちでした(笑)。僕たちはいわゆる「思想」的なるものに触れなければならないという雰囲気のあった最後の世代といえるかもしれません。
私より6歳年長の平田さんは、昨年亡くなったポール・ヴィリリオの研究から大学院でのキャリアを開始されて、後にアンリ・ルフェーヴルに注目され、パリで哲学の博士号を取得されたわけですよね。そもそもなぜルフェーヴルだったのでしょうか。

- 仙波希望氏
平田周──運よく2009年から私はフランスに留学する機会を得たのですが、その頃はポスト構造主義がアカデミズムのなかでも制度化されていくのを目の当たりにした時期でした。基本的にいわゆる古典的な哲学者を研究対象としてきた東大の本郷でもジル・ドゥルーズなどが研究対象として「解禁」になったと言われた時期です。フランスでは2000年代前半からポスト構造主義、というかミシェル・フーコーやエマニュエル・レヴィナスが大学の研究プログラムのなかに採用されて、ポスト構造主義の「スター」たちに関する研究書も続々出版されていきます。そういう制度的な動きと関連するかたちで、それまであまり読まれていなかったジュディス・バトラーやスラヴォイ・ジジェクなどの本が一気に読まれ出し、彼らについての論考も次々に刊行されていくという状況でした。
ですから、その当時、カルチュラル・スタディーズの終わりとかポスト構造主義の乗り超えというよりも、そこで参照されていた哲学者たちのテクスト読解を通じて、その思想的原理を明らかにすることを目指す研究が盛んになったというのが実感です。たしかにその研究成果によってポスト構造主義の内実は明らかになりましたが、他方でまさに仙波さんが学生の頃までにはあったような、理論を使って社会に発言していくような試みは少なくなっていった面が、少なくとも日本ではあるのかもしれません。
私の印象はあくまで一面的なものでしかないですが、こういった流れからすると、門林さんが的確に整理された「新しい唯物論」は、一度理論的な源泉に遡行した研究動向の後でまた新たな理論的潮流を巻き起こそうとするものなのだと思います。ブレナーらは、新しい唯物論の着想源のひとつであるブリュノ・ラトゥールによるANT(アクターネットワーク理論)の都市研究への応用に対して批判的な論文を執筆しています。この点は、ナイジェル・スリフトの「複雑性の場所」を訳され、ANTと都市研究との接続を図るキー・マクファーレンに至る流れを紹介されている林凌さんの議論と突き合わせて考える余地があります(「解題 把握しがたいものとして都市を記述すること」『空間・社会・地理思想』(22号、2019))。いずれにせよプラネタリー・アーバニゼーションも新しい唯物論も世界的な変化に批判的にコミットとしながら、新たな理論の方向性を打ち出そうとする点で、同時代的な地平にあることは間違いないでしょう。
そして「10+1 website」で2回にわたって機会を与えてくださった本特集に関わる質問をいただき、ありがとうございます。なぜルフェーヴルなのかというと、まずヴィリリオが、「フレンチ・セオリー」をアメリカに導入することに寄与したシルヴェール・ロトランジェとの対談のなかで、ルフェーヴルの影響を受けていることを明言していたことにあると思います(Paul Virilio and Sylvère Lotringer, Crepuscular Dawn, Semiotext(e), 2002.)。それがすごく新鮮に感じたんです。というのも、ヴィリリオといえばドゥルーズやフェリックス・ガタリの『千のプラトー』で取り上げられ、フランス現代思想に位置づけられるのが一般的ですが、他方で、ルイ・アルチュセールなどの構造主義が紹介された後では、ルフェーヴルはマルクス主義的人間主義者や疎外論者としてみなされ、いわゆるフランス現代思想に分類されていなかったからです。ルフェーヴルが時代遅れなものとみなされるのは、日本での翻訳状況から確認できることで、1970年代まではルフェーヴルはかなり訳されているのですが、それ以降はアルチュセールなどのほうが訳されるようになる。

- 平田周氏
仙波──2000年に『空間の生産』(青木書店)の邦訳書が出たのが最後ですね。
平田──『空間の生産』を訳され、その後、レギュラシオン学派との接続を図られた斎藤日出治先生の仕事は日本におけるルフェーヴル・ルネサンスに寄与するものでしたが、それまではどちらかといえば「終わった人」という扱いだったわけです。しかしヴィリリオとルフェーヴルのつながりは、単に人間関係だけでなく、都市論、より抽象的に空間のテーマ系を強く浮かび上がらせます。2人の理論的線を描くことで、それまでとは違ったフランス現代思想の流れや配置が見えて、そこから新しい思想が展開できるのではないかと考え始めました。もちろん、ドゥルーズ=ガタリの『千のプラトー』などにしても、資本主義の世界史という枠組みのなかで「領土化」や「脱領土化」といった空間的な語彙がたくさん用いられ、空間的表現と現実空間のハイブリッドな様態が分析されていったわけですね。こうした考えから、ルフェーヴルを中心にもっと広く空間の問題系を考えてみようと思い立ったのです。
そのときに研究の方向づけをしてくれたのが、フランスの現代史を専門とされる中村督さんと一緒に翻訳したクリスティン・ロスの著作(『もっと速く、もっときれいに──脱植民地化とフランス文化の再編成』、人文書院、2019/原著=1995)でした。ルフェーヴルの著作では、空間の生産にしても労働者階級の排除にしても、当時の社会関係と空間との関係に変化が起きているということが問題として捉えられているわけですが、それが具体的にどういう歴史的な出来事や過程を想定して語られているのか、彼の著作だけを読んでいてもなかなか見えてきませんでした。そう思っていると、ロスの本のなかで「第2のオスマン化」というタームが出てきます。フランスでは、第二次世界大戦後、「栄光の30年」と呼ばれる経済成長のなかでパリの都市改造が行なわれます。当時、フランスではアメリカから遅れるかたちでモータリゼーションが進行し、それと同時にアメリカン・ウェイ・オブ・ライフの浸透によって一般家庭に白物家電などが大量に入ってくる。また、商品によって彩られた生活様式が雑誌などを通じて喧伝されていく。ルフェーヴルの空間論は、そうした近代化の過程と労働者階級の排除という並行する動きを念頭に置いて書かれているのです。日本ではルフェーヴルは人間主義という括りで語られることが多かったのですが、そんな底の浅い、文字通り観念論的な話ではないだろうと。そこではルフェーヴルが直面していた社会的なリアリティが抜け落ちているように思えました。このような認識を出発点としてルフェーヴルの思想の全体像を再構成できないかと研究しているなかで、昨年11月の特集でも取り上げているニール・ブレナーなどの仕事を知り、ルフェーヴル思想は現代においても考える材料となるし、もっといろいろなテーマに接続できるのではないかと考えるようになったのです。
進行形の都市研究を立ち上げる
仙波──前回のプラネタリー・アーバニゼーションの特集で平田さんが整理されたように、「第3のルフェーヴル解釈の波」ともいうべき動き、具体的にはヨーク大学(カナダ)のステファン・キプファーやスイス連邦工科大学チューリッヒ校バーゼルスタジオのクリスチャン・シュミット、マンチェスター大学のルーカス・スタネックといったすでに建築や都市研究の領域で一線級の活躍をしている論者たちによって、まさに「惑星規模」でルフェーヴルの読み直しが行なわれたわけですよね。その成果として『Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre(空間、差異、日常生活──アンリ・ルフェーヴル読解)』(Routledge、2008)という本も出ました。そうしたルフェーヴル再評価の流れとプラネタリー・アーバニゼーションというのはどう結びつくのか、いま一度考えてみたい。
ですが、先に少しだけ僕たちの立ち位置の説明、というか自己紹介をさせていただければと思います。平田さんは仏語圏を中心とした思想史研究に取り組まれていて、僕のほうはいちおう日本都市社会学会には属しているけれど、自分のことを「社会学者」であると紹介できたことはありません。社会学科を出たわけではないし、学位は博士(学術)だし、少し自虐的に言えば、制度的に何が専門なのかよくわからない。しかし考えてみれば、ブレナーにしてもシュミットにしても、あるいはアナンヤ・ロイにしてもスコット&ストーパー(アレン・J・スコット+マイケル・ストーパー)にしても、自分たちを○○学者であると積極的には規定してないと思う。
少なくとも、都市研究(urban studies)に関する論文を読んでいるかぎり、『City』だろうが『Urban Studies』だろうが『IJURR(International Journal of Urban and Regional Research)』だろうが、これは地理学者としてとか、これは社会学者として、というフレームを前提とした議論はありません。一橋大学の町村敬志先生の2013年の論文(「都市社会学という『問い』の可能性──構造と変動から30年を振り返る」[『日本都市社会学会年報』2013(31)])も、「社会学研究者であることを出発点にする一方、都市研究(urban studies)という領域に従事する者として」という導入から始められています。僕にはそれがすごくしっくりきました。
さまざまな学知の営みはきわめて重要であり、大学という教育研究機関を維持していくためにも、「○○学」というディシプリンが必要であることは言うまでもありません。かといってそれを再生産することだけが目的になるのは違うと思う。極端に言えば、仮に「社会学」という枠組みが不要な世界や時代になるとすれば(私はけっしてそうなるとは思いませんが)、「社会学に従事するひとを養成する」ことそれ自体が目的になっても意味がないでしょう。僕は「総合国際学研究科」という正直何をやっているのかわからないところを卒業しましたが(笑)。まとめれば、ディシプリン自体が変形したり、あるいは潰えたりしたとしても、人文・社会・自然のいかなる領域であれ、学知それ自体がなくなることはない。
また、都市的な問題というものも、人間がいるかぎりなくならない。繰り返せばこうした仮定は極論であって、むしろ英語圏では伝統的な学問領域が教養教育を支え、それを強固な基盤にアドホックなかたちで、さまざまなディシプリンに属する人の集合により「○○スタディーズ」を立ち上げている現状がある。つまり言いたいのは、都市の現代的ステータス、つまり現在進行形で変化している都市の様態を対象として、過去の伝統を引き継ぎつつも、違う枠組みでの「研究」が立ち上げられるのではないか、ということです。だから僕は、必ずしも専門を同じくしているわけではなくとも、都市という同じ対象に関わる研究をしている平田さん、そして人文地理学や都市社会学で今述べた関心を共有できると思えた研究者の方々に思い切って声をかけて、共同研究プロジェクトを組織しました。
平田──都市という対象の変化に合わせてプラグマティズム的にディシプリン間の再接続を図る必要があるというお話だったと思います。個人的に思い返すと、2016年に原口さんが『叫びの都市──寄せ場、釜ヶ崎、流動的下層労働者』(洛北出版)を上梓されたときに、仙波さんが東京外国語大学でその本の書評会を組織されて、私はコメンテンターを務めさせていただきました。原口さんと最初にお会いしたのはそのときです。
仙波──同じ年に僕が『日本都市社会学会年報』に論文「『平和都市』の『原爆スラム』」を載せていただいたときに、立命館大学の加藤政洋先生にたまたまお声掛けいただき、人文地理学会地理思想研究部会での研究報告の場にお呼びいただいたのですが、北川慎也さんとはその打ち上げの席で初めてお会いしました。
加藤先生が後に研究会に参加していただく大城先生と編んだ『都市空間の地理学』(ミネルヴァ書房)が出版されたのも、2006年のことです。非常に挑戦的かつ画期的な仕事であり、今読んでもその度に新しい刺激を与えてくれる本ですが、そこからもう10年以上経ってしまった。この10年の間をどのように「読む」ことができるだろう。こうした話を北川さんや原口さんとした記憶があります。現代の都市状況を研究するにあたり、理論的な参照軸が必ずしも全面的にはアップデートされておらず、そもそも現行の世界的な研究動向が日本語圏のなかで共有されているのかという疑問を、懇親会に参加した人々のなかで話し合っていました。
平田──原口さんはニール・スミスの『ジェントリフィケーションと報復都市──新たなる都市のフロンティア』(ミネルヴァ書房、2014)を訳され、その後ジェントリフィケーションは『日本都市社会学会年報』18号(2017)で特集が組まれたりしました。ですから、原口さんは少なくとも日本語環境のなかでは、翻訳で紹介されることは大きな波及効果を生むということを実感されている。それと同時に、昔に比べて、本当に翻訳や紹介がなくなったよねともおっしゃっていました。『空間・社会・地理思想』にしても『10+1』にしても、あれほど翻訳論文が詰め込まれていたのに、自分たちの世代はそれができているのか。そこで原口さんが、もう一度広く共有できるものを翻訳するために、ニール・ブレナーが牽引する議論を紹介するのがいいだろうと薦めて下さりました。ブレナーの議論が引き起こす賛否両論を含めて、アジェンダのようなものとして投げかけられないかと考えて、『空間・社会・地理思想』で「プラネタリー・アーバニゼーション」の翻訳特集を行ない、それをご覧になった「10+1 website」の編集者さんから声をかけていただき、11月号でも翻訳紹介できたわけです(「インタビュー:都市化の時代におけるデザインという媒介作用」)。
仙波──どうしてもひとつの「論文」をつくろうと思うと、個別のケーススタディに終始してしまうきらいがある。これはもちろん自身の研究に関しても同様です。他方、そうした個々のケーススタディは、単純に読んでいて楽しいけれど、それをほかの事例やもっと大きな地理的スケールにいかに繋げるのかという問いがどうしても残る。個々の対象、方法論に従属する「先行研究」群を超えたより大きな問いを、乱暴な言い方をすれば最大公約数的なるものを共有していかなければ、自分たちの仕事の意味がわからなくなるのではないか。個別に深められた論点を結びつけるプラットフォームを構築するために、フレデリック・ジェイムソンがケヴィン・リンチの『都市のイメージ』の読解から提唱した「認知地図」をつくる必要があるのだと思います。
- ルフェーヴルから辿れるもの、切り開かれるもの/進行形の都市研究を立ち上げる
- 現代の地理学的な問題系/「広範囲の都市化」とロジスティックス──なぜ広島研究で理論が必要なのか
- ジェントリフィケーションが示唆するもの/「プライベート化」の進展/ジェントリフィケーションとクリエイティブ・シティ/「プラネタリー」という形容が意味するもの