1968年以降の建築理論、歴史性と地域性の再発見
──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、五十嵐太郎『モダニズム崩壊後の建築』ほか
──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、五十嵐太郎『モダニズム崩壊後の建築』ほか
まず「1968年以降の建築理論」をテーマにとりあげる理由を説明しておこう。1968年に日本を含めて全世界の大学で同時多発的に学生運動が勃発した。それを担ったのは主に戦後生まれの団塊世代だった(僕もその一人である)。同時期に中国でも若者による文化大革命が勃発した。このため1968年は世界中の若者たちによる〈文化革命〉の年として歴史に刻まれている。同時期に連動して、建築においても思想的、理論的な転換があった。2018年はそれからちょうど半世紀が経過した年である。
第一次大戦後の1920年代にヨーロッパで勃興したモダニズム建築運動は、歴史的な視点を持つことを拒否した。モダニズムにとって19世紀の歴史主義や折衷主義は乗り越えるべき過去の思想だった。過去の様式は新しいデザインの参照源から除かれ、その建築思想は拒否された。さらに、モダニズムの背景にはマルクス主義の社会・経済思想があり、19世紀のブルジョワ資本家による社会を社会主義社会に変革しようとする潮流があった。モダニズムは過去よりも未来に目を向ける思想だった。第二次大戦でヨーロッパのモダニズムが挫折した後、モダニズムの建築理論はアメリカに移入され、戦後アメリカの経済力・政治力とともに世界中に拡散した。一方、ロシア革命によって成立したソヴィエト連邦にも、過去を否定する社会主義的な建築理論が浸透した。こうして第二次大戦後の復興と住宅不足の解決のために、世界中の都市に、歴史性と地域性を欠いた均質なモダニズム建築が建設された。1960年代になると、大量に建設されたモダニズムの建築と都市において社会的矛盾が噴出する。歴史性と地域性を持たない白紙状態の都市は、社会的なアイデンティティを失い、急速に荒廃した。そのような状況に対する反省と抵抗が、世界的な文化革命を誘発したのである。
そのとき、建築理論においては何が変わったのだろうか。一般的には、20世紀初頭から1960年代まではモダニズムの時代、1970年代以降はポストモダニズムの時代と言われている。2000年代になると、ポストモダニズムは終焉し、ポスト・ポストモダニズム、ポスト・クリティカル、オルタナティブ・モダンの時代に移行したとも言われている。そうした思想的な変化は多種多様な名称で呼ばれているが、底流には、はっきりした共通点がある。1968年以降の建築理論に共通する特徴は〈歴史性〉と〈地域性〉、すなわち建築を歴史的、地域的に捉える視点である。
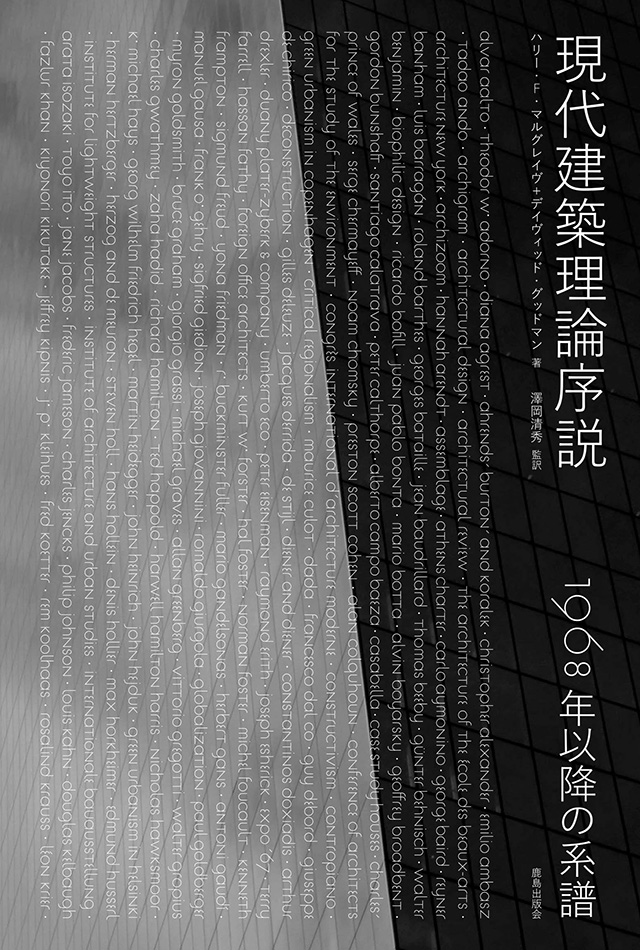
- ハリー・マルグレイヴ
+デイヴィッド・グッドマン
『現代建築理論序説──1968年以降の系譜』
(澤岡清秀監訳、鹿島出版会、2018)
『現代建築理論序説──1968年以降の系譜』(ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン著、澤岡清秀監訳、鹿島出版会、2018)は、そのような視点で辿った1968年以降の建築理論の通史である。本書は、同じ著者(僕と同世代)による『近代建築理論全史1673-1968』(ハリー・マルグレイヴ著、加藤耕一監訳、丸善出版、2016)の続編であり、1968年を建築理論の歴史的転換点と捉えている。冒頭では、1968年前後にモダニズム批判の端緒となったレイナー・バンハム、ジェイン・ジェイコブズ、クリストファー・アレグザンダーらの建築・都市理論が紹介され、1970年代では、ポストモダニズム建築理論の決定的なマニフェスト『建築の多様性と対立性』を書いたロバート・ヴェンチューリを初めとして、アルド・ロッシや、マンフレッド・タフーリのイタリアのマルクス主義的な建築理論、コーリン・ロウとニューヨーク・ファイヴの記号論、さらにはモダニズムの継続的発展形であるシカゴの超高層ビルや英国ハイテックなどが紹介される。1980年代では、ポストモダン歴史主義に対抗する批判的地域主義、ポスト構造主義とデコンストラクショニズムが紹介され、1990年代には、社会主義諸国の崩壊に呼応して、ポストモダニズムの批評性を超越したポスト・クリティカルでプラグマティックなレム・コールハースの建築理論が紹介される。最後に2000年代では、持続可能性を追求する科学とテクノロジーの可能性が検討されている。本書の魅力は、建築理論の変遷を、時代の社会・政治状況の変化に対応させながら紹介している点にある。さらに丹下健三以降のメタボリズムや、最近の日本の建築家の世界的な仕事が紹介されている点は、これまでの欧米の歴史書には見られない新しい視点だろう。
私見では、歴史観には対照的な二つの立場がある。漸進的な歴史観と断続的な歴史観である。前者は歴史を漸進的な変化と見なし、後者は不連続な転換の連鎖と見なす。本書は明らかに漸進的歴史観に基づいている。ポストモダニズムにおける歴史性と地域性だけではなく、モダニズムの発展形としての超高層やハイテック、持続可能性のデザインを支える生態学や科学技術を同列に論じているからである。

- 五十嵐太郎『モダニズム崩壊後の建築
──1968年以降の転回と思想』
(青土社、2018)
一方、『モダニズム崩壊後の建築──1968年以降の転回と思想』(五十嵐太郎著、青土社、2018)は、タイトルからも読み取れるように、断続的歴史観で捉えた1968年以降の日本の現代建築史である。1968年ではパリの5月革命にともなう建築運動に焦点を当て、1970年の大阪万博以降は、住宅への内向の時代と記号性(家型)の復活について論じている。1980年代のバブル期では、ファッションと建築の関係に焦点を当て、1990年代のポストバブルの時代では、オルタナティブ・モダンやリレーショナル・アーキテクチャーについて論じている。本書で注目すべき論文は、建築史家、鈴木博之についての「建築史と建築批評」と、磯崎新についての「『〈建築〉という基体』を読む」だろう。僕の知る限り、この二人の建築思想に関するまとまった評論は、本書が嚆矢ではないだろうか。

- 山本理顕+仲俊治著
『脱住宅──「小さな経済圏」を設計する』
(平凡社、2018)
歴史的な視点ではないが『脱住宅──「小さな経済圏」を設計する』(山本理顕+仲俊治著、平凡社、2018)は、文化革命以降の新しい家族像と集合住宅のあり方を提案している。これまで山本理顕は、『地域社会圏主義』(LIXIL出版、2013)や『権力の空間/空間の権力──個人と国家の〈あいだ〉を設計せよ』(講談社選書メチエ、2015)において、戦後モダニズムの社会的基盤である「一家族一住宅」制度の崩壊を指摘し、新しいコミュニティ像としての〈地域社会圏〉を提唱した。僕の考えは山本とは少し異なるが、彼の主張が1968年以降の建築理論の中核にあることは明らかである。現代都市のみならず、3.11以降の地方の復興においても、山本の〈地域社会圏〉の構想は、重要なヒントになると思う。
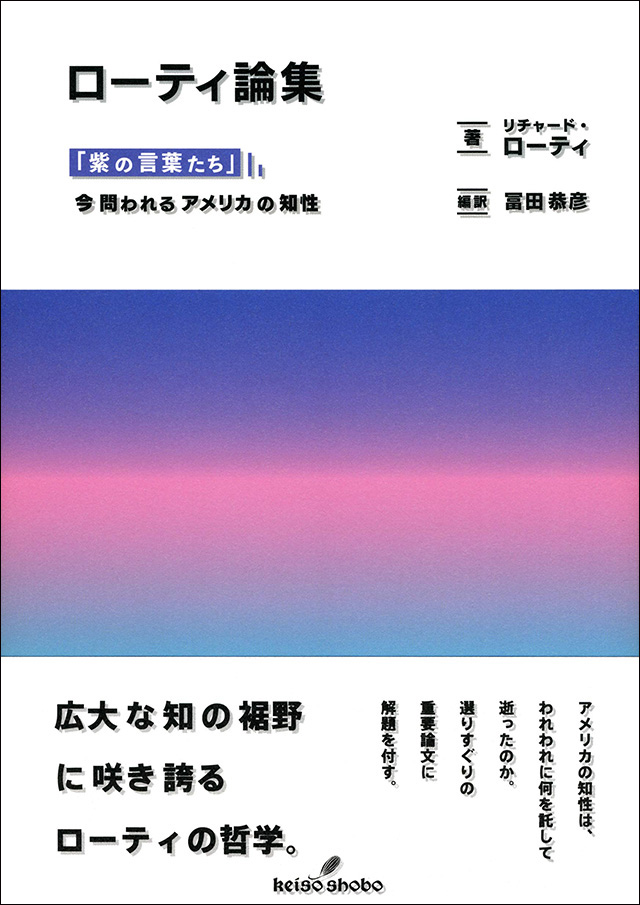
- リチャード・ローティ
『ローティ論集──「紫の言葉たち」
/今問われるアメリカの知性』
(冨田恭彦訳、勁草書房、2018)
建築理論と直接的な関係はないが、『ローティ論集──「紫の言葉たち」/今問われるアメリカの知性』(リチャード・ローティ著、冨田恭彦訳、勁草書房、2018)は、文化革命以降の建築理論の歴史性と地域性の底流にあるプラグマティズム思想について論じている。ローティが提唱するのは一種の歴史主義だが、その視野は、いわゆる人間社会の歴史を超えて、ダーウィンが提唱した自然史にまで遡っている。進化論は、あらゆる人間の能力は変化するという根源的な歴史主義をもたらした。ダーウィンを引き継ぐローティの歴史主義の核心は、物事を認識する認識図式、概念的枠組は、歴史的に変化するという主張である。カントが提唱した認識図式の普遍性・不変性を否定し、その歴史性・相対性を主張する点で、ローティのプラグマティズムは、文化革命以降の建築理論の根底にある思想だと言ってよい。
最後に、建築理論について2点だけ付言しておきたい。ひとつは、漸進的歴史観と断続的歴史観の相補性についてである。1968年は歴史的な不連続点であり、そこで理論的、思想的転換が生じたことは確かである。ジャン=フランソワ・リオタールは『ポスト・モダンの条件』(小林康夫訳、水声社、1986)で、ポストモダニズムは〈大きな物語〉としての科学やテクノロジーの終焉から始まると主張した。確かにクーンの〈パラダイム〉やフーコーの〈エピステーメー〉は、科学的認識の歴史的不連続性を明らかにしたが、科学自体を否定したわけではない。科学やテクノロジーは近現代を通じて漸進的に進化してきた。科学やテクノロジーは歴史や地域によって相対化されることはない。したがって漸進的歴史観と断続的歴史観は相補的な関係にある。近来のグローバリゼーションは、両者の相補性をますます強化している。もうひとつは、建築理論が言語によって記述されることである。言語で建築を記述する限り、必ず抜け落ちるものがある。建築をつくる技術、構法、エネルギーには、言語では掬い取ることができない物質的な過剰性がある。建築は論じられると同時に、つくられる存在である。仮説としての理論と検証としての実践も、相補的な関係にあることを忘れてはならない。
難波和彦(なんば・かずひこ)
1947年生まれ。建築家。東京大学名誉教授、難波和彦+界工作舍主宰。作品=《なおび幼稚園》(2004)、「箱の家」シリーズほか。著書=『戦後モダニズム建築の極北──池辺陽試論』(彰国社、1998)、『建築の四層構造──サステイナブル・デザインをめぐる思考』(INAX出版、2009)、『進化する箱──箱の家の20年』(TOTO出版、2015)ほか。
201901
特集 ブック・レビュー 2019
1968年以降の建築理論、歴史性と地域性の再発見 ──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、五十嵐太郎『モダニズム崩壊後の建築』ほか
谺(こだま)するかたち ──岡﨑乾二郎『抽象の力』、ダニエル・ヘラー=ローゼン『エコラリアス』
現代日本で〈多自然主義〉はいかに可能か──『つち式 二〇一七』、ティモシー・モートン『自然なきエコロジー』ほか
ゲノム編集・AI・ドローン ──粥川準二『ゲノム編集と細胞政治の誕生』、グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学』ほか
「建築の問題」を(再び)考えるために──五十嵐太郎ほか『白井晟一の原爆堂──四つの対話』、小田原のどか編著『彫刻1』ほか
あいだの世界──レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』、上妻世海『制作へ』ほか
モノ=作品はいま、どこにあるのか──『デュシャン』、ジョージ・クブラー『時のかたち』ほか
堕落に抗する力──ハリー・マルグレイヴ+デイヴィッド・グッドマン『現代建築理論序説』、ジョゼフ・チャプスキ『収容所のプルースト』ほか
オブジェクトと建築 ──千葉雅也『意味がない無意味』、Graham Harman『Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything』


