建築─ガレキ─映画

- 鈴木了二氏(左)、岡崎乾二郎氏(右)
岡崎乾二郎──『建築映画 マテリアル・サスペンス』の感想はたくさんあります。鈴木了二さんはいかに無双無敵の映画好きなのか。了二さんの文章力に引きずり込まれてしまいました。まずそのダイナミックに展開していく文章が映画そのもので、映画論としてのグンバツの説得力がある。映画論でなく、この本が映画です。で、この本の適切な箇所を紹介するとかすればいいのですが、そういうことにぶきっちょな僕がそれをやると、折角の映画が台無しに野暮なものにもなってしまう。今日、ここに呼ばれたのはこの「マテリアル・サスペンス」というタイトル。その「サスペンス」について考えを述べよと指名されたのだと思います。そして、この本が提示する「サスペンス」は、フィクションではない。それはリアルに実在する。恐ろしいものなんですね。
この本には幾つかのキーワードがあって、まず「建築映画」というコンセプト、それから「物質」、そして「瓦礫」の三つが際立っている。建築に物質性があるのでも、現われるのでもなく、「建築映画」にこそ、はじめて物質性が現われるというのがこの本の主張です。たとえば映画のなかでは建築の実物ではなく、模型が(実物以上に)、物質性を表出することがある。それにゾクッとする、というような普通想定している「物質性」があっさり乗り越えられてしまう考えが示されてもいます。
「建築映画」とは簡単に理解すれば、「鉄道映画」とか「恋愛映画」と同じで、建築を主題、サブジェクトとする映画となると思います。つまらないことのようだけれど建築家にとっては、これが深刻な問題に繋がっています。建築の問題とは、建築をつくってもそこに住む人間=主人公、主体つまりサブジェクトまではつくり出すことができないということですから。そこが小説とも劇作家とも違う。建築は主題がつくり出せない、ということは主人公をつくり出すことができない、ということですね。それで作品足りうるだろうか? これが建築の悩み。ところが建築をサブジェクトとする「建築映画」は建築に主人公、サブジェクトを与えることができる。その建築に住み込んでいるのは、いかなる主人公でありうるのかを示すことができる。
鈴木さんは「内部/外部」「部分/全体」といった補助線を引きつつ、ベンヤミンの「複製技術時代の芸術作品」から「気散じ」という概念を引いています。「気散じ」とはdistraction、気が散って、そのつどバラバラ、支離滅裂に情報が断片的に入ってくること。相互に無関係で全体がつかめない、不連続な断片としてしか知覚できない、この部分的、断片的知覚情報からいかに一つの像、対象を摑むのか? この条件において映画と建築は同じ問題を共有している、とベンヤミンは述べたのでした。 けれどその建築を映像で撮ると、たとえば吉田喜重監督によるかつての『美の美』(1973─77)という番組、ではないけれど、建築のなかをカメラが、「こつこつ」と足音をたてながら歩きまわる映像をつくる、すると建築に主体が生まれてしまうのですね。一つの視線の連続、意識の流れがつくられる。アウシュビッツの廃墟を撮影しても、主体は幽霊のように浮かび上がる。アラン・レネの『夜と霧』(1955)のように。
僕は建築がそれ自体で一つの全体像をつくりだすことができなくなったときに映画が要請されたのではないかと思います。鈴木さんが『建築映画』で書いているのは、「かならずしも主人公やストーリーがなくとも、幽霊のようなかたちであれ、主体が浮かび上がってくる」ということですよね。そしてルイス・カーンの、「建築は使っている間は実は建築が見えていない。人間が去って廃墟になってしまったときにはじめて建築の建築的なところが現れる」という言葉を引用されている。このような純粋な建築性を示す視点を与えうる特権的存在として映画があるのではないか。鈴木さんはそう提言されているように思えます。
で、次に出てくる問題は、果たして映画はいまでもそのような存在なのか、です。いま、映像作家たちは「建築映画」ではなく、反対に「映画建築」をつくりたがっているのではないかしら。「映画建築」とは少し陳腐に聞こえる例をあげると、メディア・アートのようなジャンルで、インタラクティヴな作品をつくる時、線的なストーリーをつくるのではなくて、プロットの単位を、小さなブロック=部屋のようにして、そのネットワークとしてつくっていく。物語は線的な流れでなく、ブロックのネットワークになる。建築のプランのように。
鈴木了二──ゲーム的だね。
岡崎──ゲームそのものですね。建築に引き寄せれば、アドルフ・ロースの「ラウム・プラン」的と言えます。
これはどこから始めてもいい。同時にたくさんの流れがそのプランのなかで生起してもいい。それが時にはぶつかって事件も起るだろう。けれどそれを超越的に俯瞰する一つの視点はありえない。あるのは空間配置だけ。整理すると、建築だけでなく映画においても、いまや外部の視点がなくなったということです。「遠くから引きで見てみると、全体はどう認識できるのか」という外部の視点がない。遠くから見ているつもりの視点も含めて、すなわち視点は全部が内部の視点になっている。映画にはもともとそういう特徴こそがあったのですが、それが徹底されるとその内部の視点が一つではなくなった。そして、ゆえにもはや映画作家は建築をつくりたがっている、と。これが第一の話。ちょっと思いつくまま続けていいですか?
鈴木──どうぞどうぞ(笑)。
でも少し岡崎さんの話されたことを僕なりに整理させてください。本来は人間が生み出したはずの建築なのに、建築のほうはそこに住む主人公=人間を結局つくりだすことができないんですね。それに気が付いてしまうともう建築がそれ自体で一つの総体には成りえないと思うしかない。建築の内側で考え、建築について語り続けていると、思いとは裏腹に建築からどんどん遠ざかってしまうという逆説がある。これは人間と建築とのあいだに前提としてあった「つくる/つくられる」という無条件の信頼関係が崩壊しているからです。
そこで僕は岡崎さんがいまご指摘くださったように「建築映画」という概念装置をつくってみたわけです。そのなかでは建築がはじめて主人公になることができます。人間と建築とが、限定的ではあるものの、一瞬フェアな関係に置かれる。この概念装置を通して建築を見ると、たとえばいま岡崎さんの言われたルイス・カーンの「人間が去って廃墟になったときにはじめて建築の建築性が現れる」という、いままでの常識からだと極めて倒錯的に思える言葉の意味がごく自然に理解できたんです。
問題はこのあとです。そこからひるがえって建築の歴史を見直してみると、はたして建築がそれ自体として自足するような自律的なものとしてあったことなど実は一度もなかったのではないかという疑問が湧いてきた。
戦後復興と「瓦礫映画」
岡崎──2002年、J・L=ゴダールが高松宮殿下記念世界文化賞をもらったとき、彼は日本に住む人が不愉快になるようなことを言いました。「日本映画は存在しない」と。鈴木──あったねぇ、怒っている人いましたよね(笑)。
岡崎──「フランス映画はあった、ドイツ映画はあった、イタリア映画はあった、アメリカ映画はあった、でも日本映画は存在しない」と。ところがね、ゴダールの発言をよく読み直してみると、彼の言う「日本映画」は「日本」を主題にした映画、すなわち「日本が何だったのか、日本が何になりたいのかを表現する」映画ということです。日本以外の国には、これからその国そして、そこの国民がどこに向かおうとしているのか、どうありたいのか、そのあり方を定義しようとした映画があったが、日本にはそれがなかった、というんですね(http://www.eris.ais.ne.jp/~fralippo/module/Translation/JLG021023_interview2/index.html)。
そこで、これをまた補足すると、第二次大戦のあとの西ドイツの映画をまさに「瓦礫映画」(Rubble film)と呼んでいたんですよね。
鈴木──それは知らなかったですね。「建築映画」の次は「ガレキ映画」だ!と思って、今日はそれについて話そうと映像もいくつか準備してきたんだけれど、もうすでにあったのね......。(笑)
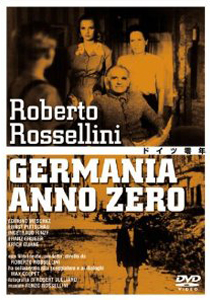
- ロッセリーニ『ドイツ零年』DVD
(販売元:アイ・ヴィ・シー)
鈴木──まさしくそうです。『最後の橋』と『ドイツ零年』とのあいだにある瓦礫の意味の隔たりは重要ですね。前者が「復興」の物語であるとすると、後者は「絶句」してしまってその先が始まらないんだね。零年のまま。そこが「瓦礫」と「ガレキ」の違いかな。


- 鈴木了二「Figaro 計画」その1、「Figaro 計画」その2
「戦後日本」を表象する
岡崎──で、また話がとびますが、昨年末に亡くなった東松照明は1930年生まれです。同じく最近なくなった大島渚もほぼ同年の1932年生まれ。1930年代に生まれて戦後の1950年代にデビューしている純粋に戦後の作家たちの第一世代です。ゴダールも1930年生まれ。ゴダールは先ほどの「イタリア映画」とか「ドイツ映画」とかのネーション映画が存在しえたのは1930年代から60年代までで、自分たちはその後始末をしている」と言いました。鈴木──あたっていますねぇ。映画のはじまりは光の明滅のサスペンスであったものが、1930年頃からネーション=国家的な物語を語るまでになってしまった。国家を宣伝するにせよ批判するにせよ。言い換えるとサスペンスが国家に独占されていたことになる。ヌーヴェルヴァーグは終わったあとの後始末だったのね。若いのにませていた。
岡崎──ゴダールはやっぱり優秀でした(笑)。磯崎新さんも同世代ですが、その上には丹下健三が、大島渚の上には黒澤明という人がいる。丹下と黒澤もほぼ同年齢。東松照明の場合、その上の世代に土門拳と名取洋之助がいました。この2人はある意味対立していたのですが、東松照明は両方から可愛がられていた。土門拳は写真と対象がジャストミートして、写真自体が完結した物質と化し、全体として完結する。つまり部分が全体を象徴すると考えた。名取洋之助はもっとも普遍的というか共有されたストーリーを表象するのが写真だと言った。それに対して東松照明は「写真には嘘も本当もありません」と言う。バラバラなイメージをどう統合するかが写真家に課せられた役割だと。写真を見るとき、そもそも、実体との確定的結びつきは保障されていない、写真自体に嘘も本当もない。後から、事実は感知される。だから、やらせも事実を提示するためには、必要ともなることがある。ロバート・フラハティとかロッセリーニとかと共通した考えがありました。けれど、本当に後からその全体との結びつきを欠いた断片群の連なりから事実は生起するのか? 一つの対象は把握されうるのか? そこで彼らが依拠していたのは作品を見る、見ようとする観客、つまり民衆だったのですね。ゴダールの言う意味での「日本映画」であれば、日本はどうなるべきか、どこに向かうのか、その像を知りたい、見たいと願う民衆が必要で、かつてはそのような「日本」を希求する視点があった。いまはそれがない。だから「日本戦後史」というものも終わった。「日本」という主題がたたない。
で話を戻すと、この「日本」という主題だけではない、「建築」というジャンルもそれだけでは自立できなくなっているのだと。東松照明は写真家であり、また写真集をつくる編集者でもありました。『やきものの町 瀬戸』『水害と日本人』『戦争と平和』などの写真集でデビューした。写真と本という2つのメディアを入れ子にして、かろうじて主題を浮かびあがらせてきた。編集の力。これは建築においても映画においても似ていますよね。建築の主題はメディアのなかでしか浮かび上がらない。「建築映画」「映画建築」というのが深刻なのは、建築だけでは主題として自立できないから映画を、映画だけでは主題として自立できないから建築を持ってきているということです。

- 黒澤明『悪い奴ほどよく眠る』〈普及版〉DVD
(販売元:東宝)
いわば戦後日本を表象しようとした、いま思いだした日本における「瓦礫映画」二作品(もっと適切なものもあるでしょうが)は、いわば全体像を提示すること、共有することの不可能性を示している。映画みずから、「みなさんの願望にはお応えできません」「共有できるのはこの不可能性だけです」と。
鈴木──いやあ、岡崎さん全開だね(笑)。ありがとうございます。岡崎さんと僕は観ている映画がずいぶん違う。それに、ほとんど真逆の方向から観ている。岡崎さんは意味の問題から映画に侵入していく。その反対に、僕は物性とか触覚といったところから入る。でもこの二つの方向が目指しているポイントは同じような気がします。またいま岡崎さんが話してくださった「日本」や「戦後」という視点も僕の本には出てこない。そこが面白いです。
僕の思っている写真史では土門拳や名取洋之助が第一世代とすると東松照明は第二世代、そして第三世代は森山大道や中平卓馬のプロヴォークでしょうか。建築だと丹下健三が第一世代、磯崎新が第二世代かな。第二世代の東松照明や磯崎新は岡崎さんがいまご指摘されたように「本」というメディアを建築や写真と連動させつつ主題を持続しようとしてきたように思います。しかしその次の世代はその主題そのものが成り立たなくなってきたんじゃないのかな。森山さんの写真に「日本」や「民家」や「人民」といったような主題を求めても、彼の写真は少しも分からない。森山さんの写真が面白いのはそういう主題の外でしょ。
今日はテーマを「建築─ガレキ─映画」としたのですが、それは、今回「建築映画」のその先を考えてみたい、という感覚があったからです。というのも岡崎さんの話に添わせると、主題そのものが成り立たなくなった状態がガレキであるということだから。まさに歴史の外ですね。この本を書いている最中に震災がありました。その後被災地に行く機会もあったのですが、あの状況は簡単に表現できるものではなく、「建築映画以後」があることを予感しました。本のあとがきに「『終わったあと』は残された」と書きました。新聞やテレビでは「はじまり」が強調されますが、はたしてそうだろうか、目の前には「終わったあと」が残っているのではないか。岡崎さんが指摘したように「零年」の先には「はじまり」がない。
では『ドイツ零年』が「ガレキ映画」の起源かといえば、これがそうではなかったんですね。実は映画はサイレント映画の段階から「ガレキ映画」が存在した。そうなると映画はもともとその奥底にガレキを孕んでいたことになる。『ドイツ零年』はガレキの第二世代ということになる。そういう観点でもう一つの建築映画史が描けるのではないかと考えていて、岡崎さんとそれについて話したいと思いました。
岡崎──ちょっと『ドイツ零年』の話を続けていい(笑)? この映画のはじめのほうで、主人公の少年が嘘をついて大人に交じって働こうとする。小学校の先生に相談するとね「生き残るためには親だろうと......」みたいなことを言われる。それで少年は病気の父親を毒殺してしまうのですが、先生からも見捨てられ絶望し、ここで終わってもおかしくないのですが、ここからが映画として素晴らしい。少年はひとりでベルリンを散歩する。まぶしい教会を見上げたり、水たまりをよけながらぶらぶらしたり。最後は廃墟で滑り台で遊んでいるみたいに、ぱっと飛び降りて自殺してしまう。つまり少年は死を覚悟してから、はじめて無目的に遊ぶのですね。それを追う映画も無目的にベルリンを撮っているとも言える。この遊びの時間は(映画の観客以外は)誰も見ていないし知り得ない。おそらく少年の死体が発見されるだけでしょう。一切の社会への帰属を失った瞬間から、遊びが始まる。この時間が「零年」なのではないかな。タルコフスキー『僕の村は戦場だった』(1962)の少年も、この零年を生きていた。彼は歴史上では死んでいたとも言えるでしょう。
ガレキの映画史
鈴木──あっそうか。そういえば『ドイツ零年』の少年が遊ぶのは自殺する直前だったんだね。すべての社会的な帰属を断ち切られたあとの少年にとってはもはや主題そのものが瓦解していたわけだ。そこから真の遊びは始まるんですね。その意味で「ガレキ映画」は第二次大戦が大きな転機にはなってわれわれの目の前に歴史の外の意味をリアルに見せてくれた。しかし瓦礫への眼差しは映画のはじめから実はあったのね。これは僕にとっての新発見です。僕は「ゴダールの映画史」の向こうを張って「ガレキの映画史」と言いたいのだけれど(笑)、そこではとくに何人かの作家が重要になる。今日は瓦礫映画作家を10人挙げますので、これは皆さんにぜったい観てほしい。まず「ガレキ映画」の起源。これはバスター・キートンとチャーリー・チャップリンです。彼らは斜めになったり、場所を変えたり、強風で吹き飛ぶ小屋を撮っていますが、すでにそこで瓦礫の問題に遭遇し、実際に瓦礫を映像に収めている。これは撮影所のセットだからもちろん本物ではない。しかし木でつくられた偽の石造っぽい書割が崩壊すると、これは二重の意味でガレキ化を孕んでいることになりますね。使う目的から切り離されているという意味ではセットがすでにガレキだから。
その次は先ほど岡崎さんの挙げた第二次世界大戦後のロッセリーニの『ドイツ零年』。敗戦国のイタリアから、機材もないのに同じ敗戦国のドイツへ撮影しにいって、瓦礫をとんでもなくエモーショナルに横移動で撮る。セットではない現実に直面したのがロッセリーニのような第二世代です。
ところがアメリカにもガレキ映画第二世代がいたんです。フランスからアメリカに帰化したハリウッドの監督、ジャック・ターナーの『ベルリン特急』です。『ドイツ零年』と同じ年に撮られました。ベルリンと区別のつかない壊れかたをしているフランクフルトの瓦礫と廃墟が映り、そこに「20th Century Modern Order」という、きわめてクールなナレーションがつく。「20世紀型」の都市の様式がどこに行ってもよく似ているのはどこもかしこもガレキだからだと言っている。占領軍側から撮っているのに、復興の物語にはしていない。そしてアメリカ人、ドイツ人、フランス人、イギリス人が乗り込んだ列車の四つのコンパートメントの窓をトラベリングで映しています。ここはまさに「ヌーヴェルヴァーグ・シークエンス」。『建築映画』を読んでくださった方はご存知でしょうが、この「ヌーヴェルヴァーグ・シークエンス」は「建築映画」の重要な手法です。これを『ベルリン特急』でジャック・ターナーが映画の冒頭でしっかりやっていた。「建築映画」を撮れる人はガレキ的感受性があるという証拠です。
岡崎──まだ4人(笑)。
鈴木──この4人が要するに第一、第二世代であり、「ガレキ映画」の起源と、第二次大戦後の「ガレキ映画」を撮った。さて、ここからはわれわれの問題になります。次に出てくる3人の映画監督は「20世紀末型」の瓦礫の新提案をした人たちです。『悪い奴ほどよく眠る』や東松照明のあとを受けて現れた人たちと言っていいでしょう。
まず1999年に死んだスタンリー・キューブリック。彼はわざわざ瓦礫をつくって『フルメタル・ジャケット』(1987)を撮りました。キートンのような書割ではなく、ロンドンにある工場跡に本物の瓦礫をこしらえた。僕は震災被災地の瓦礫を見て、瓦礫一つひとつの造作の複雑さに仰天しました。それに全方位的に取巻かれるという感覚。同じ断片は一つもない。多様という言葉では追いつかない。この恐ろしさをキューブリックはロンドンにわざわざ人工的につくった。これはいま見てもよくできている。そもそも大金を投入してまで克明に瓦礫をつくろうとすること自体が狂気じみている。それを低い位置からぐわーっと撮る。瓦礫をつくってみせたというところが史上初です。露骨にやってみせた第三世代のひとりがこのキューブリックです。
次は『マトリックス』(1999)を撮ったウォシャウスキー姉弟です。このなかで、われわれがいる世界は実は仮想現実なんだよと言ってスイッチを入れると、周囲が真っ白になるシーンがありました。真っ白い空間にテレビと椅子とテーブルがあるだけ。この何もない空間に若干の家具とテレビだけが置いてある光景は、実は被災地の仮設住宅のインテリアととてもよく似ていた。白の瓦礫というのが、ウォシャウスキーが提案したものでした。
そして3番めは、デヴィッド・フィンチャーの『ファイト・クラブ』(1999)。最後のシーンで金融会社の高層ビルが次々に崩壊していきます。9.11が起きる2年前に公開された映画です。ここには垂直に流れ落ちる流動化した瓦礫のアイデアが提示されていた。以上の3人が20世紀末に現れたガレキの第三世代ですね。
岡崎さんが話してくれた黒澤、ロッセリーニ、そしてジャック・ターナーたちの世代と、この「20世紀末問題」の三作家のあいだにはあきらかに切断がある。しかし共通していることは主題の代わりに瓦礫性という問題が現れたことです。
岡崎──鈴木さんの話を聞いていると、その映画を観たくていてもたってもいられなくなりますね。淀川長治さんの後を継ぐのは鈴木さんじゃないの(笑)。けれどね、映画って「ガレキ映画」が基本でしょう? バラバラで死んでいる物体=1コマを動かしてみせるわけだから。
鈴木──おぉーカッコいいな、岡崎さん。静止している瓦礫の断片を一つひとつ繋げると動くんですね。それが映画だと。
岡崎──エイゼンシュタインだって言っているよ。セットだって全部偽物だけれど、映画のなかでは本物になるっていう話だよ。いかなる瓦礫でもフランケンシュタインみたいに動くっていうのが映画の基本。
そして鈴木さんは恥ずかしがって言わないけど、そうなると「物質」とくれば「精神」でしょ。瓦礫にいかに精神をよみがえらせるか。今日は精神や魂の話をしなくてはいけないんですよ。きっと。
鈴木──魂という言葉は、発音したことすらないなぁ。言いづらいなぁ(笑)。
岡崎──鈴木さんの本では「幽霊」と呼んでいるでしょ。「幽霊」って言ってもいいよね。
さっきの『ドイツ零年』に話を戻すけれど、あそこでは深刻なことが起こっている。映画と観客のあいだには少年の気持ち=魂が召還され、その魂が廃墟のなかを孤独に歩いている。でも映画のなかの人たちはこの魂に気づかない。大地というか、建築に着地できない、現実に存在できない幽霊がたくさんでてきてしまったわけです。瓦礫問題というのはそういう主題のことだと思うんだけどね。アラン・レネもタルコフスキーも、現実世界にも歴史にも触れることのできない、魂をこそ、出現させてしまっている。
鈴木──まさにその通り。つまり難民ですよね。
さ迷う魂
岡崎──そうですね。ぼくが重要だなと思っているガレキ映画はね、第二次大戦のドレスデン爆撃をテーマにした、ジョージ・ロイ・ヒル『スローターハウス5』(1972、カート・ヴォネガット原作)。このヒロシマと同等の規模だったとも言われるドレスデンの爆撃を体験した青年がいて、記憶がフラッシュバックする。彼は宇宙人に出会い、自由に時間を行き来することができるようになったと言う。人生のあらゆる場面、自分が死ぬ瞬間も時間の前後関係なく行き来している。たくさんある部屋のどこにでも行けるように。だから死を恐れる必要もないわけです。死の場面のあとにまた生まれた場面に戻ったりもするから。ゆえに現在というリアルさに着地できなくなってもいる。先ほどの「映画建築」のように、部屋割りというかプランが決まったなかをダンテの神曲みたいに彷徨っている状態。魂が現実から遊離していれば、死は恐怖ではない。魂が時間をさ迷うことができるなら、10年も100年も違いがない。時間という観念が意味を失う。当然、都市計画なんかもほとんど意味をもたなくなる。そういう視点がこの映画以来現れてきたと思うんですね。それから最近ではね、『脳内ニューヨーク』(2008、チャーリー・カウフマン)。19世紀までの近代的理性は理念上のデカルト的均質空間にいかに現実空間を近づけるか。生産過程、交通過程をいかに短縮してゼロに近づけるか。場所の違い、時間の遅れを消去するかという目的に向かいますが、20世紀の哲学、芸術が示したのは、むしろこういう先験的な均質な時間も空間もない、ということでしたでしょう。時間も空間も想像的に生起する可塑的なものでしかない。映画という装置はその考えを実践的に現した。D・W・グリフィス『イントレランス』(1919)のように強引に時間をつくりだすものもありましたが、むしろ映画という瓦礫のなかで、結びつくべき特定の時間も場所も失って、魂が幽霊のように漂いだす、そういうリアルな状況を提示してきた。魂がつくり物のハリボテなのか、現実がハリボテなのか。カウフマンの関わった映画は『マトリックス』より面白い。瓦礫というのは時間と空間が入れ子状に錯綜した、もっともっと多層的なものである。計画というもの自体がそこでは瓦礫よりも先に物質として瓦礫になってしまう。まさに了二さんが模型こそが物質性を示すと書かれたように。
実は、鈴木さんは「ガレキ映画」という言葉で、戦後の復興でなく、こんどの震災で復興とは何でありうるのか、何であってはいけないのか、という深刻な問題こそを提示していた。この間頂いて、鈴木さんが書かれた素晴らしいエッセイ(「『建屋』と瓦礫と──『テクノニヒリズム』以後」、「みすず」2011年8月号)を読みました。福島の事故には終りがなく、延々とだらだらと続いていくことについて書いていましたよね。「福島第一原発という建物は、その恥辱を延々と生き続けなければならない。建築の新たな存在形式の誕生であることは間違いない」と。
鈴木──ジャック・ターナーが「20世紀型」都市と名付けた建築様式の次に位置付けられる瓦礫のニュータイプということにもなります。岡崎さんも原発事故と時間をめぐって書いていますよね。(「理性の有効期限──理性批判としての反原発」、「述5 反原発問題」、2012年3月)。
岡崎──僕が書いたのは、永遠に機能する判断枠はないという話でした。2013年から2053年を「現在」として選ぶのか、1013年から2013年を選ぶのか、2013年から2513年を選ぶのか、そういった選択をしない限り計画はできないわけで、そのすべてに通じる正しい答えはない、と。鈴木さんのエッセイが提示したのは、われわれの判断や理性を超えたところで瓦礫はあり続ける、と。そこで了二さんが示唆しているのですが、そうすると映画という行為も建築という行為も、いずれまた瓦礫になるのは必然なのに何をやっているのかということになります。永遠のものをつくれるわけではなく(デカルト的に時間と空間の差異がフリーズした理念上、静止した均質空間があるわけでもない)。また現在の皆に支持されるものがつくれるわけでもない。どの段階で瓦礫ではないか、瓦礫なのか、その判断枠をまず設置することを自覚しなければ建築とは言えない。
鈴木──もしくは瓦礫のガレキ性に関心を持っていくかですよね。どういうことかというと、表面的には瓦礫には見えないものであってもそこにガレキ性を感じる場合があるということです。でもそれはひと括りに瓦礫として一般化することではない。だって瓦礫ってひと言で言っても一様じゃないからね。
岡崎──深刻なのは、鈴木さんや僕は、瓦礫になにを読み込むか、そこからなにを復活させるか、なにを立ち上げるかという主題の問題こそが芸術だと思ってきたわけですが、そんな僕らの魂が遊離して幽霊のようになっていることです(笑)。
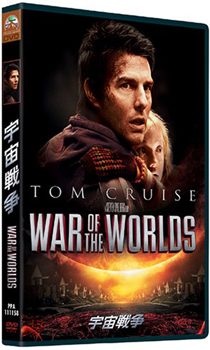

- スティーブン・スピルバーグ『宇宙戦争』DVD
(販売元:パラマウント・ホーム・
エンタテインメント・ジャパン)
ハーモニー・コリン『ガンモ』DVD
(販売元:ハピネット・ピクチャーズ)
そこで「ガレキ映画史」残りの3人に繋げたいと思います。次の3人はいよいよ「21世紀型」の瓦礫映画の作家たちです。その1人めがスティーブン・スピルバーグです。まさに着地できない人間の魂を描こうとしている。そして瓦礫のサスペンスを撮っているようにも見える。彼の『宇宙戦争』(2005)を観たら目先の都市計画なんて意味ないってことが分かりますよ。地中から巨大なものが現れて、殺戮と破壊を始めるシーンで、地面は波打ち、なすすべもない人間たちが映し出される。
また『宇宙戦争』には群集がさ迷える魂のように移動しているところに、列車が火を吹きながら走ってくるシーンがあります。遮断機が降りているところを、炎に包まれた無人の列車が猛スピードで走り去る。走り去ると遮断機はちゃんと上がります。ここには破綻した秩序と破綻していない秩序とが斑模様になって混在している。これこそ21世紀型のインフラの状態ではないでしょうか。そしてこの事態を大地から離脱した人間が呆然と見ている。そんな象徴的なショットです。
次に9人め。トニー・スコット『アンストッパブル』(2010)。誰も乗っていない列車が暴走して、それを止めるというだけの話です。すべてが瓦礫になりそうなところをすれすれで防ぐという展開です。すばらしい「建築映画」で、かつ「ガレキ映画」だと思います。線路上に止まった車を暴走列車が跳ね飛ばすシーン。カットの繋ぎ方をみてください。また車のなかの馬と線路を横切るスカンクにも注目してください。もう一つ暴走列車とそれを止めようとする列車がすれ違うシーン。この二つの列車の真正面からの面構えを見てください。超高層にも匹敵する長い列車という人工物が主人公ですからまさに「建築映画」でありながら、同時にガレキ感が横溢している。しかも爽快感があります。
最後、10人めはハーモニー・コリンの『ガンモ』(1997)です。お観せするショットは映画の最初のタイトルシーンです。竜巻が去ったあとの町、まさに「終わったあと」が残された状態を撮っています。ここに出てくる少年は、『ドイツ零年』のいかなる社会的な帰属も失ったあとに廃墟でひとり遊ぶあの少年なのかもしれませんね。だけど自殺はしない。ある意味ぎりぎりのところで着地しているのではないでしょうか。
瓦礫から世界を見る
岡崎──鈴木さんはガレキを意識して『宇宙戦争』のシーンを選んだのだと思うけれど、本当の意味での「ガレキ」性はボストンへ向かうマサチューセッツの波打つような丘陵を人が蟻のようにただただ蠢いている場面ではないかしら。16世紀のドイツの画家、アルトドルファーのような、安定を保障する地面などなく、確固たる視点もない。最近のスピルバーグの映画には、何を撮っていいかわからないとカメラの眼が、ただただ茫然自失としたような視線が現れてきますね。ハーモニー・コリンの作品は確かに竜巻の後の話で、ゴミはたくさん映っていたけれど、かならずしも瓦礫という感じではない(笑)。ちょっと野暮な質問をしてもいい? 映画のなかに出てくる瓦礫と実際の瓦礫はどこが同じでどこが違うと思いますか。鈴木──面白い問いだね。瓦礫はもちろん物質なんだけれど、それは自然の物質と違って一度は人間の手を通過したものという点で特徴的。それは現実にある瓦礫でも映画に出てくる瓦礫でも同じ。ただ、映画のなかではカメラの目によって、もう一度還元されているので他の物質と区別がつき難くなるね。だから『ガンモ』にはゴミしか映っていないのにそれがガレキにも見えている。
岡崎──瓦礫は人間との関係性で瓦礫になるのであり、言い換えれば瓦礫を有機的に結びつけている人間がいなくなると、その視点がなくなると急に瓦礫になるわけでしょう。鈴木さんのエッセイに共感するのは、瓦礫の一つひとつは細部が非常に充実しているということ。つまりは意味が充実している。けれどそれを読むことができない。意味が拾い上げられない。それは実は「壊れたもの」ではない。読む人がいなくなって本棚にあふれかえった本や資料のように。それを意味として受け取る能力がこちらにないから、瓦礫と扱うしかない。言い換えればそれは博物館の収蔵品のような事物だとも言える。むしろ意味に溢れたもの。
鈴木──瓦礫が過剰な意味に溢れ、充実していることはわかるんだけど、そこで充実しているものの正体はなんなのか、その充実をもってわれわれはどうすればいいのか、ということがまだわからない。ハーモニー・コリンの映画に出てくるゴミや、廃墟のような歩道橋には意味はある。というか、かつてあった。けれど少年にとっては、それがなんであるのかということに関心はないし、関心を持つ必要もない。じゃあ、なにもないのかっていうとそうではない。自分にとって必要な意味はもはや残っていないが、でも無意味ではない。しかし自然には属さずにどこまでも人間の傍にいる。持て余すようなこのやっかいな感じ。そこに言葉がほしいと思います。
岡崎──細部の輝きというのは、怖いものでもありますよね。つまりそれが何のためにあるか、あったか、ということと見ている人間が無関係になっている。あるいはもう理解できない。でもそこに充実した意味があった、まだ、あるということは分る。自分にはまだ/もはや、もう関われないのだけれども。意味と無関係に物としての細部が輝いて見えてくる、というのはそういう事。つまりこちらが『ドイツ零年』のエドモンド少年と同様に歴史の外にでてしまって、死の側にいるから見えてくるようなものでしょう。瓦礫が死の側にあるのではないかも知れない。瓦礫を見ている人間が死の側にいる。
読むことも使うことも到底不可能なほどの圧倒的な量の情報。そこに失われているのは、それを生き生きと使い、意味を発生させてきた主体、主人公ですね。見ているわれわれはその主人公になるには、あまりに無力である。こういう圧倒的な量の文明的遺物に囲まれてしまったとき、われわれはただ呆然とするしかない。自分ひとりでは到底、相手にできない。すると急に逆転して、「すべて大切なのはわかる、だけどもう無理だ、すべてをゴミとみなそう、瓦礫とみなそう」という認識が反転してしまう。開きなおってしまうということですね。けれど、そういう選択に直面させられるような過酷な状況がある。被災地。本当はそう思いたくない、けれどもう方法がない。われわれはあまりに無力である。意味の放棄。
本当はそれらが有機的に結びつき生き生きとした意味を発生させてきたことはわかっている。けれどそれを結びつけてきた無数の人たち、もうその人たちはいない。残されたわたしたちは、その圧倒的な量の事物そしてそれを生かす能力をもった、不在となった無数の人たちに対して、あまりに無力、少数者でしかない。でもこれは美術館に集められた事物と変わらないとも言える。そこで細部は輝いている。けれど、その事物同士の有機的な関連は断たれている。もう具体的使用は絶たれている。美術館では輝きだけが神聖化されている。膨大な事物、情報の増大という意味では、震災が来る前から事態はガレキにむかっていたのかも知れないね。ガレキ化の進行。あまりに情報量が多く可能性に満ちている膨大な事物。それを生かせる意味の連関なんか、もはやつくりきれないから放棄する。建築で言えば、鈴木さんの嫌いな真っ白い空間や、壁の薄さや柱の細さを競うような、そしてディテールがまるでないような建築。「ノーディテール」っていう建築雑誌こそをつくればいいじゃない(笑い)。
鈴木──あ、でも瓦礫ってディテールがないね。
岡崎──いや、ディテールが過剰にありすぎるってことでしょう。
鈴木──うん、確かに。でも瓦礫になってしまうと、ディテールの意味がすっ飛んでしまう。
岡崎──そうか。そう見えてしまうときには何か情けない。無力感、罪深さも感じる。ゆえに、それが瓦礫を冷酷な強さをもつ崇高な存在として見せる。70年代には多くの人がこのような問題について考えていましたよね。了二さんはその頃からずっと、この後ろめたさのようなものにつきあい「物質試行」をやってきたわけですが、いま多くの建築家は、もう完全に瓦礫については考えない、付き合えないという態度なのかしらね。
でもいま、了二さんが改めて、この時代に瓦礫に対峙し続けよう、と提起する。これは強い意志、勇気があることですね。「瓦礫を乗り越えて、何をいかに立ち上げるか」と言っている建築家がほとんどの時に。
鈴木──天邪鬼かもしれませんが、そもそも「立ち上げる」という言葉がいやだよね。だから「瓦礫からなにかを立ち上げる」のではなく、むしろ世界は最初から瓦礫だったんだという観点に立って、そこから世界を見直すのはどうか。瓦礫の状態は「何もない」という状況ではないからね。瓦礫を刷り込んだ眼で世界を見直したいと思う。
岡崎──鈴木さんが引用される先ほどのルイス・カーンの言葉----「建築の用途が消費され、廃墟になるとき、元初の驚異がふたたび甦ります。廃墟はからみつくつる草を気持ちよく受け入れ、ふたたび精神の高揚を取り戻し、苦役から解放されます」。クノッソス宮殿を襲ったという大津波やポンペイの火山噴火によって建築を含む文化は一瞬で滅びました。けれど、そのせいで、その何千年後のいまのわれわれはそこに留まった瓦礫とそこに生きた文化、人間たちに出会うことができた。滅ばずにリノベートして更新していった文化は歴史的には忘却されてしまう。つまり瓦礫が都合よく片付けられ、次のシーンに繰り込まれていくと瓦礫自身の文化的、物質的生命が奪われていくことになる。文化において再生力があるのは、人が手を触れていないときです。瓦礫という零度の状態が露呈した時間幅、そしてあの原発事故がつきつけた時間幅は、人間がふつう考えている幅よりはるかに長い。その途方もない時間の上にわれわれが何かをつくる、創造することがある。何かをつくるのは現在の問題だけではない(そうであればいずれ瓦礫として片付けられてしまう)、そこに表現されえない意味や、出現していない膨大な潜在性、可能であるものをまず引き受け、それとどう関係するのかを決断することである。了二さんのエッセイには震災に触れて「建築家はまず自分の無力、無責任を知るべきだ」と書いてあった。つまり普通の建築をつくるということは瓦礫の時間軸に対してほとんど意味のない行為でしかないって......。
鈴木──まずいなぁ。建築家としては話がどんどんまずい方向に行っている(笑)。
映画建築
岡崎──でもその先がある。ギリシアのパルテノンなどの神殿や、最近イタリアのチェルヴェテリという場所にあるエトルリア人の墓を見に行きましたが、共通しているのは、多かれ少なかれここで建築は、建築そのものではなく、あえて建築を彫刻として彫ったものであることです。パルテノンも木造建築の構造を石造にしている。エトルリアも普段の建築は木造でした。がその木造を岩盤に丸彫りしてつくっている。紀元前8−1世紀に建造されたエトルリアの墓の場合はさらに地下に掘られたまったくの内部空間ですから、外的視点もありません。そこに宿っているのは再生能力、データ力だと感じました。いつでも再生できる。ワインを飲んだら生まれ変われるのと同じように。墓に入ってきた人は1,000年後だろうと10,000年後だろうとそこから文化を読み取ることができるというか。ただし現在の実際に暮らしている人たちのためではない。先ほどの『宇宙戦争』も同じですよね。突然現れた敵は宇宙から来たものではなく、もともと地中に眠っていた。それを忘却していただけ。鈴木──そうね。いや、今度は急に壮大な話になってきた(笑)。いま生きている人たちのためにすべてがあるわけではないし、やるわけでもない。
岡崎──だから瓦礫についても現在の俺たちにはこれは扱いきれない。瓦礫として処理するしかない。使いきれない意味。能力を超えた意味、その無力感は同時に、自分の生の時間枠を超えた広大、長大な時間の可能性を実感させる、現在や現在の延長ではない。潜在性としての広がり。建築家は、建築に人間を取り戻そうという思いでやってきたかも知れないけれど、そこで発生させてきたのは、どこにも居場所のない、現実に結びつかない魂だった。そこが映画の宿命と結びつく。
鈴木──ベンヤミンも「どの詩も読者のために書かれたものではなく、どの絵も鑑賞者のために描かれたものではなく、どの交響曲も聴衆のために作られたものではない」と言っている。もはやいさぎよく人間をあてにしていない。でもこれは決してニヒリズムじゃないんだ。瓦礫の時間軸が途方もなく長いというだけでね。
岡崎──瓦礫を前にした圧倒的に取り残された感じ。能力を超えた事物と意味の物量に何もできない無力感。鈴木さんが言いたいのは、その無力感の意味することを引き受けて建築を考えろということでしょう。メタボリズムなんてもうやるな、と。
鈴木──みんな思い知らされているはずだよ。気がついているけれど口にしない。それでも復興再生と言わざるをえない。
岡崎──20世紀はいろいろな災禍があり何度も瓦礫状況を見てきたわけですね。時間と空間の枠組みから流出した瓦礫という問題群は20世紀以降の文化の核心だったとも言えるでしょう。これを忘却させるための都市計画というのも多かった。ほとんどだった。けれどそうではない都市計画も建築もあった。 ということで次は「映画建築」について話しましょう。「映画建築」建築家10人なんてすぐ挙げられます。まずはマレーヴィッチでしょ、アドルフ・ロースでしょ。最初に言いましたが、映画に撮るということは、外部の視点なしに内部的な視点から見るということなのね(映画ではどんな鳥瞰をとっても内部的な視点になってしまう)。場所がないところでつくるってことを最初に考えたのはマレーヴィッチですよ。
鈴木──それはまるで、このところ僕が考えている場所を選ばずにどこにでも出没する建築「DUBHOUSE」と同じみたいだね。それはともかく、ロースとマレーヴィッチから始まる「映画建築」の10人を辿っていくといままでの建築史とはまったく違う何かが見えてくるような気がします。しかもそれらはガレキの時間軸を内に持っているんだね。

鈴木了二によるガレキ映画史──瓦礫映画の10人
起源
1:チャールズ・チャップリン(1889−1977)
『黄金狂時代』(1925)
2:バスター・キートン(1895−1966)
『マイホーム』(1920)
『蒸気船』(1928)
大戦後
3:ロベルト・ロッセリーニ(1906−1977)
『ドイツ零年』(1948)
4:ジャック・ターナー(1904−1977)
『ベルリン特急』(1948)
20世紀末
5:スタンリー・キューブリック(1928−1999)
『フルメタル・ジャケット』(1987)
6:ウォシャウスキー姉弟(ラナ」1965−/アンディ:1967−)
『マトリックス』(1999)
7:デヴィッド・フィンチャー(1962−)
『ファイト・クラブ』(1999)
21世紀
8:スティーブン・スピルバーグ(1947−)
『宇宙戦争』(2005)
9:トニー・スコット(1944-2012)
『アンストッパブル』(2010)
10:ハーモニー・コリン(1973−)
『ガンモ』(1997)

起源
1:チャールズ・チャップリン(1889−1977)『黄金狂時代』(1925)
2:バスター・キートン(1895−1966)
『マイホーム』(1920)
『蒸気船』(1928)
大戦後
3:ロベルト・ロッセリーニ(1906−1977)『ドイツ零年』(1948)
4:ジャック・ターナー(1904−1977)
『ベルリン特急』(1948)
20世紀末
5:スタンリー・キューブリック(1928−1999)『フルメタル・ジャケット』(1987)
6:ウォシャウスキー姉弟(ラナ」1965−/アンディ:1967−)
『マトリックス』(1999)
7:デヴィッド・フィンチャー(1962−)
『ファイト・クラブ』(1999)
21世紀
8:スティーブン・スピルバーグ(1947−)『宇宙戦争』(2005)
9:トニー・スコット(1944-2012)
『アンストッパブル』(2010)
10:ハーモニー・コリン(1973−)
『ガンモ』(1997)

2013年3月15日、Bibliothèque
岡崎乾二郎(おかざき・けんじろう)
1955年東京生まれ。1982年パリ・ビエンナーレ招聘以来、数多くの国際展に出品し、2002年にはセゾン現代美術館にて大規模な個展を開催。また、同年「ヴェネツィア・ビエンナーレ第8回建築展」(日本館ディレクター)や、現代舞踊家トリシャ・ブラウンとのコラボレーションなど、つねに先鋭的な芸術活動を展開している。東京都現代美術館(2009-2010年)において特集展示。主な著書に『ルネサンス 経験の条件』(筑摩書房)、共著に『漢字と建築』(LIXIL出版)、『絵画の準備を!松浦寿夫×岡崎乾二郎対談』(朝日出版社)、『芸術の設計──見る/作ることのアプリケーション』(フィルムアート社)などがある。近畿大学国際人文科学研究所副所長、教授、四谷アート・ステュディウム ディレクター。
鈴木了二(すずき・りょうじ)
建築家。1944年生まれ。早稲田大学大学院修了。70年にfromnowを設立。83年、鈴木了二建築計画事務所に改称。73年より自身の作品を「物質試行」としてナンバリングし、建築はもとより、絵画、彫刻、インスタレーション、書籍、映像などの多領域にわたる「物質試行」は現在53を数える。作品は、建築に「佐木島プロジェクト」「金刀比羅宮プロジェクト」、映像に「空地、空洞、空隙」、「DUBHOUSE」、書籍に『建築零年』、『非建築的考察』(ともに筑摩書房)、『鈴木了二作品集1973-2007』(LIXIL出版)などがある。また映像作家、七里圭との共同監督映像作品「DUBHOUSE」は、2013年の第42回ロッテルダム国際映画祭短編部門に招待された。





