〈建築理論研究 03〉──コーリン・ロウ+フレッド・コッター『コラージュ・シティ』
-

- 左から、市川紘司氏、南泰裕氏、鈴木了二氏、天内大樹氏
『コラージュ・シティ』はどう読む?
-

- コーリン・ロウ+フレッド・コッター
『コラージュ・シティ』
(渡辺真理訳、鹿島出版会、2009)
鈴木了二──建築書は学生の頃から必要にかられて読むもので、文学や映画、批評を読んでいるほうが面白いと感じていました。建築書は、うまく語られているという印象のものはもちろんありますが、爆発的に笑わせるもの──建築に笑いの要素が入ると不謹慎だと言われやすいからかもしれませんが──がありませんでした。『コラージュ・シティ』は『マニエリスムと近代建築』(伊東豊雄+松永安光訳、1981、彰国社)とはあきらかに書き方の調子が異なって、ジャーナリスティックな文体で書かれており、他分野の書籍に私が感じていた面白さの要素を持った建築書でした。初めて読んだ頃の私には特に第1章「ユートピア、その衰退と解体?」と第2章「ミレニウム去りし後に」が圧倒的に面白く、鋭く深い批評と批判に頷きながら読んでいました。20世紀建築史を遡りながら古典までを含め、すべてを一網打尽にし、最後にはすごいユーモアで爆笑するような面白さですよね。
たとえば第2章ではケネス・バークが未来派に対し、「通りが騒がしいという抗議に対しては、われわれはその方が好きだ」と述べたことについて、それならば「排水溝が臭いという主張に対する反応は完全に予測どおりで、われわれは臭いのが好きだ」(p.67)と返している。いままで誰も言えなかったようなドライヴのかかったフレーズが随所にあります。
近代建築を「SF派」と「タウンスケープ派」という宗派に分ける方法も巧みで、アーキグラムやチームXを「宇宙服を着たタウンスケープ派」と評している箇所(p.69)などは、SFのように見えるけれど、思想はヒッピーやグローバル的な──バックミンスター・フラーにも通じそうですが──アーキグラムの特性をうまく言い当てています。さらにそれをスーパースタジオのユートピアとロバート・ヴェンチューリのディズニー・ワールドへと繋げていくなど、とにかく言葉の繰り出し方が絶妙だと感じました。
私はこれまでどちらかというと批評書としてこの本を読んできたので、逆に言うと後半ではロウの誠実さを感じてしまって(笑)、あまり笑えませんでしたね。もっと突っ走ってほしかった気もします。
天内──いま批評と理論を使い分けていらっしゃるように感じたのですが、それは磯崎新さんがおっしゃるような違いなんでしょうか。先日も東大でのシンポジウムでそのお話が出ましたが(「これからの建築理論」2013年12月1日、東京大学工学部1号館)、批評は歴史を学んだ人がさまざまな作品に対して行なう価値判断、理論とは建築家が自分の作品に関して行なう裏づけという違いなのですが......。
鈴木──ええ、ただ磯崎さんがおっしゃっていることと私のニュアンスは少し違うと思います。建築家が言うから建築の理論とは限らないし、私がこれまで書いてきたのは批評だと思っています。磯崎さんの文章もどちらかというと批評として読んでいて、正直にいえば建築家の思索がどうやって理論になるか、私にははっきりとはわからないところもあります。
市川紘司──『コラージュ・シティ』の1・2章と3・4・5章は明らかに異なる構成になっていますね。鈴木さんのお話を聞いていると、前半は文学的、後半は理論的とも峻別できるようにも思いました。じつは私は鈴木さんとは逆で、1・2章は目的がはっきりしないなあという印象で、『コラージュ・シティ』を読むときにいつも躓いてしまいます。比較的カチッとした3・4・5章を読んだ後にもう一度読み返してみて、1・2章は後半の理論を述べるための前提の話だったんだなと、ようやく内容が頭に入ってくるという感じです。
異質な文化を身体化した理論
天内──アンソニー・ヴィドラーの『20世紀建築の発明』(今村創平訳、鹿島出版会、2012)のコーリン・ロウの章を読んでいると、彼は美術史的な背景のある人だということに気づかされます。『ヒューマニズムの建築』(桐敷真次郎訳、中央公論美術出版、2011(原著1924)/邉見浩久+坂牛卓訳、鹿島出版会、2011)を書いたジェフリー・スコットが、アメリカ出身でフィレンツェ郊外の邸宅に住んだバーナード・ベレンソンという目利き(connoisseur)、つまり愛好者たちの伝統の下で育っています。西洋でまさに美術史という学問を駆動したものです。ロウもこれと同じ目線をウィットカウアーらに学んだはずで、ル・コルビュジエの《ラ・トゥーレット修道院》に行って現地に立って自分の眼で壁面の歪みを見つめて、それを『マニエリスムと近代建築』の一章に綴っています。そうした美術史の素養を持ってアメリカの都市と建築を見たのがこの本ではないでしょうか。1・2章には、イギリス的な目利きの伝統、歴史的素養に裏づけられた眼でアメリカを見た時の絶望のようなものがあり、その眼で歴史をザッピングしたり巻き戻した結果が「笑い」を生んでいます。3章以降ではその絶望の後に改めて理論をどう組み立てていくのかという試みがなされているのだと思います。-

- コーリン・ロウ『マニエリスムと近代建築』
(伊東豊雄+松永安光訳、1981、彰国社)
南泰裕──『マニエリスムと近代建築』はロバート・スラツキーとの共著ですし、『コラージュ・シティ』もフレッド・コッターとの共著です。そのためか、ロウの文体にはジャズのセッションのような開放感と重層性があって、ディスクールでもエクリチュールでもなく、あるいはそのいずれでもあるような不思議な表現の束になっている。それによって、凝り固まった思考を溶かしていくような感じがあります。批評とも理論ともつかない横断的な思考を展開しながら、最後にどこに着地するかわからないまま進んでいくところが、非常に面白い。
鈴木──そうですね。ロウの場合、結論を求めて読んでいくとよくわからなくなってしまいますし、案外結論は普通の着地点であったりもしますよね。本というものは、最後の結論が面白い本と、ヴァルター・ベンヤミンに代表されるような記述過程が面白い本に大別できます。『コラージュ・シティ』は、はじめて登場した、記述過程が面白い建築書でした。最近の映画で言えば、アメリカで起きた連続殺人事件をもとにした映画『ゾディアック』(ディビッド・フィンチャー、2007)も結末は謎のままですが、映像の緊張感が作品を際立たせています。ほかの分野ではそのようなプロセスを優先するものが好きでしたが、建築書でもプロセスの本を書いてもいいのだと気づかされました。
-
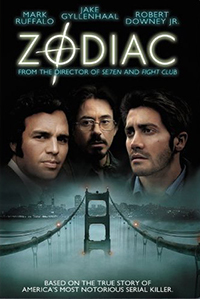
- 『ゾディアック』
(ディビッド・フィンチャー、2007)
ロウのこの本では、「タウンスケープ派対SF派」、「キツネ対ハリネズミ」、「ソリッド対ヴォイド」などといくつかの二項対立が出てきますが、そこにあたかも裁判官のようにロウがいて、最終審判を下すのかと思いきや、いつの間にか本人がいなくなってしまう。
1・2章あたりでは、SF派の問題点をあぶり出すことで、近代建築批判をしているように見えます。が、その後で、SF派に対抗するタウンスケープ派も、一種の教条主義であるとして批判しています。両方を批判しつつ賞賛するんですね。つまり、ロウ自身が二項対立の狭間でずっと揺れているので、最後までスリリングな展開になっている。
天内──「建築か革命か」でル・コルビュジエがどちらかを選択させるのだとすれば、コーリン・ロウはその中間位置を揺れ動く。
鈴木──むしろその動きのほうを尊重しているようなところがありますね。どちらか一方の答えを出すのではなく両方をガードするような立体的な視点を持っています。
コラージュ、フィギュア─グラウンド
鈴木──もうひとつ、視覚分析、絵画分析といった二次元の要素から建築へ入っているところが彼の持ち味ですよね。フィギュア(図)─グラウンド(地)やキュビズムの分析、いずれも面から入っています。そしてコラージュへ行き着く。コラージュは、ヴァルター・ベンヤミンが「引用」について語ったこととつながるものがあります。文章を引用した箇所と引用を挿入した箇所で二重の切断が起きると述べていますが、同じことがコラージュでも言えます。ロウがフィギュア─グラウンドという図版を使って、コラージュへと入ってくるところも面白いのですが、ただ現在のわれわれからすれば、コラージュということに関しては時代的であった気もしています。われわれの実感からすると、コラージュは20世紀絵画のはじめに勢いがあったもので、それが商業的に消費されてしまったために面白かったのは60年代のポップアートまでで、それ以降は俗っぽくなってしまう。思い切り単純化して言うとコーリン・ロウの場合には、近代以前と以降とをヴォイドとソリッドに分け、それが近代になった時点で逆転するという見方ですね。その反転で衝突が起きるわけです。その衝突を指摘するところははっとさせられるし、もちろん擁護したいと思っていますが、でも、現代の都市はコラージュでは追いつかないところまで来ている。あの時代にロウはとても鋭い指摘をしていましたが、それがそのままでは当てはまらなくなったてきたと思います。もし現在もロウが生きていればおそらくコラージュの次を考えるでしょうね。
市川──この本のなかでは、伝統都市と近代都市を大きく分類して、比較していますが、現代の都市状況はこの二分法ではたしかに捉えがたいところがありますね。近代都市のなかにも伝統的な要素とよりあたらしい要素が見出されるといったように、もっとこまごまといろいろな要素が並びあっています。
鈴木──ロウが実践しているようなアメリカやヨーロッパの都市は、大型のブロックでつくられているために輪郭がはっきりと見えます。一方日本では、以前六本木周辺のフィギュア─グラウンドをつくってみたことがありますが、一つひとつの建物が細かく、それぞれの境界線で隙間が空いているため、欧米の都市のようにくっきりとした都市の境界は見えてきませんでした。むしろ土地所有権や耐震問題に由来して空いている建物間の隙間の存在性が際立ちます。少なくとも東京は小気味よく分析する対象にはなりません。ロウが「東京陳列棚」だと批評していましたが、それはそういう意味ではないかと思います。ゴチャゴチャ建物を並べているだけで都市の構造やコンテクストはフィギュア─グラウンドとして見えてこない。しかしそのような、切断された破片を認識できるコラージュではなく、このアクションの形跡としての物質しか残っていないような東京は、ジャクソン・ポロックのアクション・ペインティングにこそ親和性を見ることができるかもしれません。ミクロに見ていくと、網目状の奥行きを持った織物のような差異の集合が見えてくる。ほかの絵画的手法も都市論に持ち込むことが可能だと考えています。マーク・ロスコではどうでしょう。
ロウのコラージュの背後にはグリッドがあります。グリッドの質、グリッドと地形の重なり方を分析することで古代と近代の意味の違いが見えてくる。ところがそういった見方で意味が捕まえられない「ジェネリック・シティ」(OMA/Rem Koolhaas and Bruce Mau『S,M,L,XL』)が現代ではできてしまっている。私は「ジェネリック・シティ」という語は差別用語だと思っているのですが(笑)、というか「ジェネリック・シティ」が今ではもはや都市の前提ですよね。特に断るまでもない。ということは「ジェネリック・シティ」という一言で一括りにしてしまうのではなく、それを所与のものとして捉えたほうがいい。すると「ジェネリック・シティ」のなかにもいろいろな違いが見えてくるような気がします。見方を変えさえすれば、それがなかなか新鮮なわけですよ。もちろん全部を肯定するというのではありませんが。現代は一見普通の家屋と見えていたものが、それぞれの違いを実は際立たせてくる、というような状況に向かっているのではないかと思います。最近の若いデザイナーたちは、アパートや住宅の単体の設計というよりもむしろ、建物自体はほとんど「普通」の要素でできていながら、その見え方や使い方を一挙に変えてしまうような操作に関心を持っているように見えますね。いままでの「創造」という概念がここにきて急に変わってきているんじゃないか。いまのぼくはそういう作り方をしている若い作家たちに関心が向いています。
-
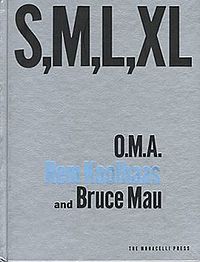
- OMA/Rem Koolhaas and Bruce Mau
『S,M,L,XL』
鈴木──ウィーンやザルツブルクのフィギュア─グラウンドでは、道のグリッド性や街区の塊がはっきりと記憶されます。東京ではそういったルールは隙間には表われず、むしろ秩序の希薄さが感覚に働きかけてくる。わずかな標高の差異のなかに折り畳まれている東京という都市は、槇文彦さんの『見えがくれする都市──江戸から東京へ』(鹿島出版会、1980)にも通じますが、ほかの都市に比べても多焦点的で、光の入り方や視線の抜けといった小さな変化が生まれてくるといったことはありますよね。むしろそこには可能性をそれ自体としては使えないあり方や意味を越えた物性──僕はそれを「ガレキ性」と呼んでいます──が考えられると思います。
-

- 槇文彦ほか
『見えがくれする都市──江戸から東京へ』
(鹿島出版会、1980)
しかし鈴木さんのお話は、日本の都市の文脈を考えた時には必ずしもハードエッジを持った2つの要素が衝突する必要はないということですね。2つに分断できない名づけがたいものがあり、それを21世紀型の思考として考える必要があるのかもしれません。
芦原義信さんの都市論でも、かつて1970年代に書かれた『街並みの美学』(岩波書店、2001)では、西洋都市を美学的な都市モデルとして捉え、それを中心的な規範としており、日本の都市の無秩序さ・乱雑さを問うニュアンスがありました。が、芦原さんも1990年代には、『東京の美学──混沌と秩序』(岩波新書、1994)などにおいて、東京のなかに「独自の混沌と秩序を認める」というふうに論点が微妙に変化していきます。やはりここでも、日本の都市においてここ数十年の間に、ユニヴァーサルな文脈では読解不可能な事態が起きている、と言わざるをえないんでしょうね。
コラージュの先、黒沢清の映画
-

- 鈴木了二
『建築映画 マテリアル・サスペンス』
(LXIL出版、2013)
南──私も黒沢さんの『アカルイミライ』(2003)を観た時は衝撃を受けました。中途半端な空間、名づけがたい空間が描かれていますよね。
鈴木──その中途半端さがはっきりと撮られているところが凄いですよね。黒沢さんは言葉にはしていませんが、彼のなかでははっきりと「ここだ」と決めて確信して撮っている。そこにロウが思考していた先の言葉がある気がします。
-

- 黒沢清『アカルイミライ』(2003)
南──その指摘は面白いですね。たしかに『マニエリスムと近代建築』でも『コラージュ・シティ』でも断面図はほとんど出てきません。透明性に関する論文「透明性 実と虚」でも、本来透明性について語ろうとすれば断面図が出てくるべきなのに、あるのは平面図、ファサード写真だけです。ロウはロンドン大学ヴァールブルク研究所で修士号を取得していますからね、図像分析、平面性が喚起する超越的視点に優位を置く姿勢は徹底していると思います。
天内──実物を見ることは目利きの素養としてもちろん重視されるので、フィールドワークのように現地に行っているはずですが、表現では平面とファサードだけを使っています。そのように考えたとき、彼はコラージュ同士をつなぐ糊のようなものとして、超越的視点から見た地面を採用したのではないか、という推測が成り立ちませんか。「透明性──実と虚」における「虚の透明性」は、眼と建物の間にある仮想のスクリーン=平面を糊として想定していますが、都市レベルで見たときには地面しかないと、ある意味であきらめてしまったような節がある。
映画におけるコラージュの糊としてはフィルムや時間があると思いますが、たとえば黒沢さんの映画における糊は何だといえるでしょうか。
鈴木──それもまた面白い指摘ですね。映画、なかでも黒沢さんの場合は、彼の独特の好みがいま天内さんの言われた糊にあたるのではないかと考えますが、それを言語化するのはとても難しい。ロウが東京を見てもつかめないような独特の都市論にもとづいて黒沢さんは撮っていて、普通は昼間のアパートなんてホラーになるはずがありませんが、彼が撮るとホラーになっている。そこに糊の正体があるのではないでしょうか。
天内──得体の知れないものが断片をつないでいる、そういう感じがしますよね。
キツネか、ハリネズミか、接続か、分断か
南──大江健三郎『あいまいな日本の私』(岩波書店、1995)のタイトルのように、日本独特のあいまいさがありますよね。「ambiguity」という語は「両義性」と「あいまいさ」という2つの意味を含有しています。ロウの衝突やコラージュという考え方は、都市の過密という条件がなければ要請されません。過密でなければ交通事故も起きないのですから。離散的に「キツネ」(たくさんのことを知っている人物)と「ハリネズミ」(大きなことをひとつだけ知っている人物)がいても問題は起こらないはずです。近くにいるからこそ「キツネ」なのか「ハリネズミ」なのかが問題となるわけですよね。過密がなければ衝突が要請されない、という問題系からはさほど遠くない場所に、コールハースのマンハッタニズムが見出せるような気もします。つまり、こういうことです。コールハースにおける「過密」と「ロボトミー」という概念は、表裏一体のものとして互いを支えています。都市におけるまったく異なった活動が、過剰な密度で共存できるのは、テクノロジーによって武装されたロボトミー的状態によって、都市生活者が互いにくっきりと分断されているからです。接続ではなく、分断こそが都市を都市たらしめるわけですね。 一方で、近づくからこそ「あいまいさ」という概念が浮かび上がってくる。ロウの立てた問題は、「タウンスケープ派」と「SF派」が、時代の要請に即して次第に近づき、互いを無視できなくなった都市的状況自体を描き出しています。もしもこれら対立するイズムが、互いに離散して存立していれば、曖昧さもなければ「キツネ」対「ハリネズミ」という対立も生まれません。二つの対立するイズムが、図像的に衝突する、という問題の立て方に、都市の過密と重合性が透かし見えます。
ここで、意図的に消去されていると思われる断面図の存在が気になってきます。マンハッタニズムは断面図がなければ成立しませんから、ロウの理論が平面図だけで構成されているところがひとつの鍵ではないでしょうか。
『コラージュ・シティ』のなかで使われる「アーバン・ポシェ」は、厚い壁を刳り貫いて建築をつくってきた西洋建築独特の概念です。しかしそれとまったく違った東京の空間を構成している概念を黒沢さんが撮り、鈴木さんが語られているのではないでしょうか。
鈴木──『見えがくれする都市』ではアカデミックに西洋の都市学の理論を用いながら東京を分析していますよね。なかでも「微地形」や「場所性」などの概念を用いることで、いくつかフィギュア─グラウンド的ではない視点が得られていると思いますが、しかし最後に「間」「奥」という日本の空間概念を固有のものとして軸に据えるのです。やはりそこから先でも西洋の文脈で語ってみせる、概念を鍛え上げることは必要ですね。
南──『コラージュ・シティ』の1・2章は、B級近代建築批判の系譜として、『建築の多様性と対立性』『ラスベガス』のロバート・ヴェンチューリや、『建築家なしの建築』『みっともない人体』のバーナード・ルドルフスキーを「ハリネズミ族」に対する批判の騎手として出しています。が、ロウ自身はそういったわかりやすい文脈とも違う視点から、ユートピアのできそこないとしての近代都市を批判している。その立ち位置は独特で、読解しづらさと同時に魅力を放っているのですね。
鈴木──そう、その立ち位置からずけずけ批判をしていきますよね。例えばクリストファー・アレグザンダーの『形の合成に関するノート』(2013、鹿島出版会)の「科学性」を問う場面では、「この作業が選別し抑制するといった性格の作業であり、とりわけ物質的な作業である割には、作業の産物がプロセスに比べていや応なく見劣りする」(p.154)とか(笑)。その通り。でもかなり辛辣ですよね(笑)。
ブリコラージュ、リノベーション、冷たいユートピア
鈴木──コラージュに比べるとブリコラージュには段違いの奥行きがあります。都市論をブリコラージュに接続したところがやはり凄みで、アンチ技術の立場と言ってもよいですよね。実際、未来派にあるような技術に対する興奮を批判している。ドラクロワやダヴィッドの描く興奮、サン・テリアの都市の興奮に対するイギリス経験論的な懐疑、冷たいユートピアと言っていいでしょうか。これは今のわれわれにも示唆的です。-



- サン・テリアと
マリオ・キアットーネによる都市
(1914)/
ドラクロワ《民衆を率いる自由の女神》
(1830)/
ダヴィッド『屋内球技場の宣誓』(1791)
鈴木──そう。それを全面化するためには、技術批判は避けられない道なのです。そのユートピアの無限延伸感はまさに20世紀の科学主義であって、今日の原発問題にも言えることですが、それを疑わなければいけないですよね。
南──『コラージュ・シティ』は、『マニエリスムと近代建築』のモチーフを引き継ぐようにして、ルネサンス期ユートピアに対する批判から始まっています。例えばそこで批判されているのは、フィラレーテによるユートピア的な八角形対称型都市計画《スフォルズィンダ》などです。ここでは根底には、技術に対する批判的視座を都市と建築のなかにどう組み込んでいくか、という問題が伏流しています。つまり、科学至上主義や技術への信仰から出発した、多くのユートピア思想や計画案が、現実にはうまく行かなかったどころか、逆にディストピアとして機能してしまうことに対する警鐘として、書かれていますね。
鈴木──それをこの時代にすでに言っていた。早い指摘です。
天内──20世紀初頭、建築界ではル・コルビュジエを中心として、科学を礼賛する社会の動きが革命的に現われました。それを止めるための方法が、アントワーヌ・コンパニョンが『アンチモダン──反近代の精神史』(名古屋大学出版会、2012)で挙げた「保守的になること」「革命ではなくゆっくりと前進すること(漸進)」、そして「反動=反対方向の革命」です。技術中心社会を反転させる、すなわち反―革命を遂行するうえでは何らかの旗印が必要とされるわけですが、それはドラクロワが描いた自由の女神に導かれる興奮とは違ったコラージュ/ブリコラージュになるはずであり、ではそれは何なのか。
-

- パルマノーヴァの《スフォルズィンダ》
引用=http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Palmanova1600.jpg
もう一度映画から例を挙げるとすれば、『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』(2001)、『ムーンライズ・キングダム』(2012)などウェス・アンダーソンの作った映画のシーンはどれもありふれた町のパターン化した風景からできています。けれど観客は彼が撮ったそんな風景に毎回わくわくさせられる。どれも童話のようなストーリー仕立ての映画ですが、一昔前の建築家なら物語も風景もすべてを一からつくってしまうようなところを、彼は今あるものを肯定してみせることで成立させている。これは現実を変えてみせる方法のひとつですよね。まさに、天内さんがおっしゃった「ブリコラージュは有限のなかの発見」なのです。
ウェス・アンダーソンは、そこにアパート部屋がひとつあれば新しい魅力的な世界を観せることができるのですが、われわれ建築家がいまリノベーションにすごく関心を持っていることともとても共通する感覚ではないでしょうか。『コラージュ・シティ』以後に始まっている動きと言えますね。
-


- ウェス・アンダーソン
『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』(2001)/
同『ムーンライズ・キングダム』(2012)
南──建築業界的に言えば、リノベーションが注目され始めたのはこの十数年ぐらいのことですね。かつて建築家はまっさらな土地に新築を建てたいと思っていましたが、いまは本当にリノベーションのほうがいいかもしれないと思える時代になりつつあります。さきほど挙がったジャクソン・ポロックのオールオーバーな抽象表現絵画が、フィギュアかグラウンドかという対立を超えて離散的な秩序を生成させている感覚に近い、と言ったらいいでしょうか。20世紀初頭にシンクロニックに社会の変化とコラージュという考え方が合致したように、いまいろいろな場所で「アフター・コラージュ・シティ」が胎動しているような気がします。
市川──若手の建築家たちの意識としても、いま目の前にある建築や都市をリソースとして利用していくことに対して非常に前向きですね。たとえば、連勇太朗さんは、東京に数多く残されている古い木造賃貸アパートに注目して、アレグザンダーのパタン・ランゲージのようなかたちでその改修アイデアを「レシピ」化することで、複数のアパートのデザインを同時進行させています(「モクチン企画」)。
-

- モクチン企画
鈴木──リノベーションの課題は既存の詳細図面がないと出せませんが、それがあればかなり面白くなりますよ。精密なデータがあると模型でも再現できるし、既存を忠実に再現して、あとはさらっとつくるといいものができるんです。「さらっとつくる」というのが新しいんですよね。
南──実は逆説的にリノベーション設計のほうが法規的には自由な部分もあります。新築は確認申請を通すためには本当にさまざまな規制がありますから。
鈴木──振り返ってみると、おもしろいものが生まれるきっかけは行き詰まって開き直るときにつかむことが多いですよね。
市川──ル・コルビュジエの《ヴィラ・ガルシュ》もそうですよね。ロウが高く評価したのは、パッラーディオの数学的な規律をずらすという点にあったのですから。
鈴木──リアリティをもった強制力をずらすのは大変な体力を伴うわけですが、その時になにかが生まれるんですよね。ところがそれがパターン化してしまうととたんに面白くなくなってしまいます。
ブリコルールたちの建築史、DUB建築
南──かつて磯崎新さんが20世紀の住宅建築の特異点として、アドルフ・ロースとチャールズ&レイ・イームズを挙げていました。そこにリートフェルトを加えれば、実は彼らは皆、家具から出発した人たちです。いわば家具職人が近代建築の名作をつくっている。それは見方を変えれば、近代建築の核となる部分には、建築を家具のように組み立てるものとして、ブリコラージュとして組成する、という視点があったということではないかと思います。 そして荒廃した《パリ・ノートル・ダム大聖堂》を復興させたヴィオレ・ル・デュクなどの修復建築家は、言葉の本当の意味でリノベーション建築家です。そしてこれから100年ぐらい経てば、誰もが建築家といえば、リノベーションの名手であったカルロ・スカルパの名前を最初に口にするような時代になっているかもしれません(笑)。天内──《水晶宮》のジョセフ・パクストンは造園家、《エッフェル塔》のギュスターヴ・エッフェルは技師です。近代建築の傑作はそれまでの西洋建築の流れのなかでは生まれなかった発想を他分野が形にしたものなんですね。
-


- ジョセフ・パクストン《水晶宮》
((cc) Paul Furst)/
ギュスターヴ・エッフェル《エッフェル塔》
((cc) Wikipedia)
鈴木──「DUB建築」は夢中でやっている段階でまだそこまでは考えていなかったですが、おそらくつながっていますね。ロウの分析自体はプロポーションを崩すと成立しないものなのでDUBをかけるとまったくうまくいきませんが、プロポーションを変えずにいくつか重ね合わせることでポリリズムを表現するわけです。僕自身「DUB建築」の「DUB」をいまだに言葉で表現し尽くせていないのですが、プロポーションを前提にせず、スケールを越えたものとして建築の正否を考える試みであって、われわれに取り憑く遠近法を超えたいという意味では『コラージュ・シティ』ともつながっているでしょうね。
市川──たとえば、具体的には《ヴィラ・ガルシュ》にDUBはかかるのでしょうか? ロウだけでなく、ヴェンチューリが『多様性と対立性』でも分析の対象とした特殊な建築ですが、DUB的にはどう見えるのでしょう。
鈴木──ル・コルビュジエとミースはどの作品もDUBがかかりそうでかからないですね。逆にジュゼッペ・テラーニは確実にDUBがかかる。幾つものシステムが層のように合成されたシステムでできているので、たとえひとつのシステムが壊れてもまた別の層にあるシステムが次々に出てくるんです。それに較べてル・コルビュジエとミースはシステムの層が少ししかない。分かりやすいがDUBには弱い。試しに《カサ・デル・ファッショ》にDUBをかけてみると、次々と新しいシステムが見えてきて、強度が崩壊するどころか持続する。いや、むしろそれらが複合してポリリズム的な効果さえ生む。ル・コルビュジエは唯一無二の堅固なプロポーションでできているので、かかりませんね。
ル・コルビュジエやロウが使っている平面・立面はプロポーションが規定しているものだと思いますし、またプロポーションが有効に使える。でも断面図はプロポーションだけではないんじゃないか。平面・立面は一枚の図面で把握しやすいが、断面図はどうしても複数の図面が必要です。二次平面上だけでは考えれない。そういう意味では断面で建築を考えていたアドルフ・ロースには、DUBがかかりますよ。 「ラウムプラン」はDUBの先触れだったんじゃないかという気がしてくるぐらい。
南──近代建築史のなかには「ブリコラージュ建築家」や「DUBがかかる建築作品」というような基準はまったくありませんでしたよね。こういった新しい基準、新しい系譜によって建築史を考えてみるのはとても面白いですね。
天内──建築設計のあり方を変えるものとしてもあるような気がします。
鈴木──情報過多のなかでシステム化とパターン化が進み、自由な身動きがとりづらくなってきています。そういう状況へのせめてもの抵抗としてサンプリングが頻繁に行なわれているわけですが、そこで二次的な操作を加えても残るものがあるとすれば少し救われるだろう、そういった気持からDUB建築の試みを始めたようなところがあります。だからDUB以外にも方法はあるはずです。
南──鈴木さんの関心の向かう先には、息の詰まった近代建築からの開放感があるというか、リリースされるものがあります。
鈴木──もともと近代建築が登場した背景にあったのは、それ以前の様式で固まった建築からの脱却への欲望だったわけです。ところが脱却の手法がパターン化されることによって再び行き詰まってしまった。 今日できることのひとつは、例えば同じキュビズムとして括られるピカソとブラックの差異を見つけ出すことと言えるのではないでしょうか。近代建築の外を再考するためにも、ル・コルビュジエの「白」とテラーニの「白」の出自の違いをもっと明らかにしていくべきでしょう。
南──前回の第2回「建築理論研究」取り上げた原広司さんの『空間〈機能から様相へ〉』(岩波現代文庫、2007)のなかに〈非ず非ず〉という考え方が出てきます。ゲストの西沢大良さんは弁証法ではないこの思考運動を「論理的な話というよりも、倫理的」であって、「弁証法で進むのならば歴史はナポレオンで終わ」っていたはずだと指摘されました。弁証法的展開を避け、結論のない状態に滞留するという意味では『コラージュ・シティ』もまた〈非ず非ず〉でしょう。近代や近代建築に対して「非ず」と言い続けるやり方に打開策があるのかもしれません。
鈴木──いま新築よりもリノベーションのほうが良く見えるというのは、近代建築に対する根深い疑念が社会に遍在していることを表わしていて、その感覚は黒沢清やウェス・アンダーソンの映画が映し出す都市にも表われている。その感覚とは一体何なのか、うまく名づけたいと思っているところです。
天内──ヨーロッパで学んだロウがアメリカへ渡り、ディズニー・ワールドを眺めた困惑が第2章最後のトピックとして書かれていることを考えると、われわれはこれから建築を議論したり批評するうえでどんな歴史を背景にしていけばよいでしょうか。
鈴木──直感でしか言えませんが、歴史はあまり近視眼的に眺めても多くを語ってくれません。さきほど話したように、例えばブリコラージュを軸とした歴史を編纂してみることでも、古代から現在までの通史観はがらっと変わるはずです。そのときに要請されるのは、ミシェル・フーコー『知の考古学』のように一次資料のアーカイヴを縦横無尽に繋ぎ直し、そこから歴史の無意識的な構造を引き出していくこと。これはひとつのモデルです。ロウが見出したのはフィギュア─グラウンドをすべてのものに適用するという方法で、ある意味では考古学的なアーカイヴと言えなくもありません。そういうものが必要となってくるんじゃないでしょうか。
南──いままでのお話は、既存の建物をどのように記述するかというノーテーションの問題も内包しているように思います。鈴木さんはかつて《絶対現場1987(物質試行24)》というプロジェクトで、まさに既存の木造建物を新しく記述する方法を試されていました。ロウはフィギュアとグラウンドだけで都市を記述するという非常にわかりやすい方法ですべてを均一に語ったわけですが、今あるものを注意深くかつ新しく記述する方法が大事だろうと思います。リノベーションがその鍵を握っているのならそれに対応した手法が出てくるような気がしますよね。
鈴木──そのとおりですね。先ほども言ったように「ジェネリック・シティ」が所与のものとして前景化してくると、これからはますます意味ではなく物質(オブジェクト)が全面化してくる時代になりますよね。そうなると人間のための世界を考える場合、ゼロからではなく所与としてある事物を構成し直すことによってどうやって実現するのかとことになるでしょうね。それは言い換えると結局はブリコラージュなんです。たとえばルドルフ・シンドラーもブリコラージュの作家でした。彼もロウと同じくいくつかの文化圏を経験した人物です。彼はエゴン・シーレとも同じ学校にいた生粋のウィーン人で、ロサンゼルスへ渡って自由な雰囲気に触れるのですが、アメリカでは最初にインディアンの遺跡を見ていて、キバ(宗教儀式を行なう部屋)をおそらく意識したのではないかと思われる設計もしていますし、さらに欄間などの日本の建築文化なども意識しているような気がします。ブリコラージュ的な目線で見ると、これからは、師匠のフランク・ロイド・ライトよりも前面に出てくるんじゃないでしょうか。
南──たしかに彼はモダニズムに対しても急進的で、世間の評価がついてこなかったという不遇から近代建築の傍流として位置づけられているきらいがありますが、ぜひブリコラージュ・アーキテクトの系譜を編纂して取り込みたいひとりですね。今日のお話からも、これからはスター・アーキテクトというシステムがさらに揺らぎ、物質(オブジェクト)としての建築史を編み直す時代だと感じます。
[2013年12月27日、LIXIL:GINZAにて]
書誌情報
Colin Rowe and Fred Koetter, Collage City, The MIT Press, 1978. 邦訳=コーリン・ロウ+フレッド・コッター『コラージュ・シティ』(渡辺真理訳、鹿島出版会、2009)
鈴木了二(すずき・りょうじ)
1944年生まれ。早稲田大学芸術学校校長。1982年、鈴木了二建築計画事務所設立。作品=《麻布EDGE(物質試行20)》(1987)、《成城山耕雲寺(物質試行33)》(1991)、《佐木島プロジェクト(物質試行37)》(1998)、《熊本県立あしきた青少年の家(物質試行38)》(1998)、《金刀比羅宮プロジェクト(物質試行47)》(2004)ほか。著書=『物質思考28「非建築的考察」』(1988)、『建築家の住宅論』(2001)、『物質思考49「鈴木了二作品集 1973-2007」』(2007)ほか。
南泰裕(みなみ・やすひろ)
1967年生まれ。建築家、アトリエ・アンプレックス主宰。国士舘大学教授。作品=《PARK HOUSE》(2002)、《spin off》(2007)、《アトリエ・カンテレ》(2012)ほか。著書=『住居はいかに可能か』(2002)、『トラヴァース』(2006)、『建築の還元』(2011)ほか。
天内大樹(あまない・だいき)
1980年生まれ。美学芸術学、建築思想史。東京理科大学工学部第二部建築学科ポストドクトラル研究員。共著=『ディスポジション』(2008)、『建築・都市ブックガイド21世紀』(2010)ほか。
市川紘司(いちかわ・こうじ)
1985年生まれ。東北大学大学院。2013年から中国政府留学生(高級進修生)として清華大学に留学。専門は中国近現代建築史。建築雑誌『ねもは』編集長。





