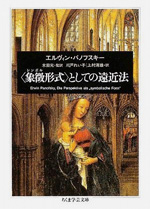経験としての建築研究室
──学んだこと学ばなかったこと、そして考えたいこと
──学んだこと学ばなかったこと、そして考えたいこと
書物から強い認識を得ること
──研究室で必読の文献や推薦図書について教えてください。
西沢──ある考えがあって、なるべく指定図書を選ばないようにしています。理想的には、学生たちが興味を抱いたことを、本を手がかりに考えるようになってほしいです。でも学生たちは僕の講義に出てくる本には興味を持ってしまうので、一切の指示なしというわけには行かないのですが、こちらから必読リストを渡すようなことはしないようにしています。
ただ、こうした僕の考えは、どんな本にもまだ書かれていないので、それを知るには本だけではなくて、僕のゼミに出る必要があります。そのうえで、本とゼミで得た知見を足がかりに、自力で考え始める必要があります。
ようするに、本を読むことの目的は、「考える」ようになるためですね。物事を真に「考える」ようになるために本を使ってほしい。ただ、本の読み方を間違えると、どんなに読んでも「考える」力はつかないと思います。最もよくない読み方は、書いてあることを鵜呑みにするような教科書的な本の読み方です。そんなふうに本に接しているうちは、「考える」力がつかないどころか、考えない力が身に付いてしまうのではないかと思います。本を読むのなら、書いてあることを全力で批判しながら読んだ方が、「考える」力はつきます。そういう批判的な読み方を、どうすれば学生たちが習得してくれるかを、教員としては考えるわけです。それで必読リストみたいなものは廃止した方がいいということになる。
全員共通の必読リストよりは、個別のアドバイスをします。せっかく研究室というひとつの空間にいるわけだから、個々の学生の気性や知性もわかってくるので、個別の処方箋を出しやすいわけです。
例えば、学生によっては良書だけではなく、悪書も読んだ方がいいんだよと言います。入手した本のどこがどの程度よいのか悪いのかという感覚を磨くには、悪書も必要な場合があるからです。そのかわり、学生たちが読んだ本を見つけたら、僕の評価を言うようにしています。その本のどこがよくてどこがよくないか、採点すると何点か、などです。わりと批判的な評価を言いますが、というのも、学生たちが目にするブックレビューには批判的なことが書かれてなくて、肯定的なことしか書かれてないからです。そうでない読み方の可能性を知ってほしいのです。
あるいは、学生が特定の本に手こずっているような場合は、自分の若い頃を思い出してアドバイスをします。例えば、マルクスの『資本論』は、学生たちも一度は読もうとするみたいですが、冒頭に一番難しい「価値形態論」が出てくるので、途中で放り出してしまう学生が多いようです。そういう場合は、全巻通しで読むのはもっと後にして、まずは第24章(岩波版の第3巻24章)の「資本の原始的蓄積」だけ読んでください、そうすれば近代都市の発生について理解できます、とアドバイスをします。
──西沢さんの学部生時代、あるいは院生に相当する年齢のときの読書方法について、教えてください。
西沢──当時はSD選書をよく読みました。それから思想書や理論書ですね。
SD選書は、ありがたいことに初心者向けの間口が広いから、興味を持ったトピックが出てくると、まずSD選書のなかから1冊を読んでみて、納得しなかったらそこに出てきた参考文献をまた読む、ということをしていました。ですから、いきなりベストな本に出会うということはなく、紆余曲折しながら一冊に辿りつくという感じでした。
基本的に僕の読書方法は、本を証明として読んでいるのですね。どこが証明のキモであり、どこが証明として成立していないのかを読んできました。当時読んだSD選書のなかでは、例えば稲垣栄三さんの『日本の近代建築』に感銘を受けました。あまり言及されない本なので、この本に辿り着くまで2年くらいかかったと思います。どうしてこの本に行き着いたかというと、僕は、日本の近代に起きたことの説明を探していたのです。明治期以降の建築の流れは、初心者ながらスッキリしないわけです。洋風建築があるかと思えば分離派があり、帝冠様式があるかと思えばインターナショナリズムがある。なぜそんな流れになるのかという、必然性の説明を探していました。稲垣さんのこの本には、それらはもちろん違うことは違うんだけど、別の意味ではほとんど同じであると書いてあったと思います。明治期の洋風建築であれ昭和期のインターナショナリズムであれ、その背後にある請負制度や生産体制や工業力はおおむね同じであり、どれも近代の産物と見なしてかまわない、みたいなことが述べられていたと思います。洋風建築とインターナショナリズムがおおむね同じだというのは、強烈な認識だと思います。しかも、それを裏付ける調査、例えば工業力の比較や請負制度の変化が延々と書かれていて、その膨大な実証にも感動しました。そういう本が好きなんですね。つまり証明として見事であり、その根底に強烈な認識があるような本が好きです。
八束さんの本は、初期の近代建築関連をよく読みました。ちょうど僕らの年代が建築書というのを読み始めたとき、八束さんは新刊本をコンスタントに出していて、毎月どこかの雑誌でインパクトのある文章を書いていました。初期の本はどれも好きなので、一冊に絞るのは難しいですが、『近代建築のアポリア』か『希望の空間』ですね。なにしろ近代建築や近代都市の意味内容が、建築界の常識とまったく違うのです。ほとんど別物と言っていいほど違うのですが、八束さんの考えたものの方に説得力がありました。しかも、その根拠として挙げられる建築家の実作や文章が、半分くらい聞いたことのない仕事で、読めば読むほど論駁不能というか、手をつけられないという感じでした。それ以外にも当時の八束さんは、著作に収録しなかった書評の連載や、海外作品の特集などもよく発表していました。『a+u』の「批評としての書誌学」や、『SD』の「フォルマリズム・リアリズム・コンテクスチュアリズム」などです。僕らの年代の建築家は、当時の八束さんの仕事にかなり影響を受けていると思います。
建築の古典理論も、ひととおり読みました。パウル・フランクルの『建築造形原理の展開』、サマーソンの『古典主義建築の系譜』、ウィットコウワーの『ヒューマニズム建築の源流』や『数奇な芸術家たち』などですね。どれも面白く読みましたけど、わりと淡白だなと思って読んでいました。データは充実していて勉強になるんですが、認識がほとんどないという印象でした。むしろ同時代の海外の理論誌、例えばアイゼンマンたちが出していた『OPPOSITION』などの議論の方に迫力を感じていました。当時の海外の理論誌は、『AAfiles』のセオリーもそうですが、かなり良質な議論をしていたと思います。
『AAfiles』のセオリーは、80年代はなんと言ってもロビン・エバンスです。エバンスはなぜか日本では黙殺されていますが、彼の初期三部作、つまりミース論、パースペクティブ論、ジョーンズ論は、非常に優れた仕事だったと思います。エバンスはもの凄い文章を書く人で、グウの音もでないような証明をなしとげてしまう書き手です。ぬるい文章は一行もなく、すべての文章が認識の連続です。もし93年に夭折していなければ、今日の建築理論のレベルが数段上になっていたかもしれません。確か90年頃に、エバンスがロシア建築の研究をしていると風の便りで聞いたんですが、結局それは発表されずに亡くなりました。ちょうどベルリンの壁が崩壊したり、ソ連邦が崩壊した頃です。その最中にエバンスが何を立証しようとしていたのか、僕はいまでも気になっています。いずれにせよ、そういう良質な理論を紹介する理論誌が同時代にあったことは、とてもありがたかったと思います。
──今後の大学はどうあるべきだと考えていますか。
西沢──今後の大学は、放っておけば就職予備校になるでしょうね。就職先も偏差値でほとんど決まってしまい、大企業に入れば勝ち組で、それ以外は負け組であるという、粗雑な指標が世の中に定着するでしょう。あるいは、お金のある者だけが教育を受け、そうでない者は教育を受けられなくて当然だという、近世的な思考に舞い戻るでしょう。もちろん大企業に行きたい人にはある程度行ってもらわないと、僕も理事会から怒られてしまうので、一定数の学生には入社してもらっていいのですが、問題は、大企業に入っても幸せにならないような世の中になっていることです。当人も社会も不幸になってしまう。もちろん短期的にはご両親も喜ぶでしょうし、収入も高卒よりはマシでしょうが、数十年後には悲惨なことになると僕は思います。こういう話は、学生たちには初耳の話でしょうから、まずは父母面談で、親御さんたちに落ち着いて説明するようにしています。
いまの親御さんたちは、僕より数歳上で、ほとんど同世代です。ですから説明すると皆さん気づくのですが、われわれの学生時代に就職先の人気ベスト10に入っていたような企業や省庁は、いまやほとんど消滅しています。長銀も興銀もつぶれたし、都市銀は合併を繰り返してわけのわからない名前になり、実質的に銀行業を放棄しています。省庁でさえ合併再編で人員削減されたし、企業も合併を繰り返して早期退職を正当化しています。合併や再編というのは、お金のかかる中間管理職をリストラするために行なわれるという側面がありますからね。その草狩り場になっているのがわれわれの年代で、その結果として世界でGDP3位の国であるのに年間自殺者3万人、ということになっています。僕の世代で、そういう目にあった知り合いをひとりおも持たない人は、どうかしています。少なくとも終身雇用制なるものは、僕の世代でも成立していないです。ですから、経団連や経済同友会傘下の企業に学生を送り出すことに、僕は希望を持てないです。
そうではない生き方としては、自分で起業する、人に雇われない生き方をする、ということが考えられますね。具体的には設計事務所を設立する、NPOやNGOを立ち上げる、海外の被災地支援に行く、あるいは設計施工の会社をつくってしまう、などです。もしそういう人生を歩みたいという学生が出て来たら、大学がサポートするといいのではないか、と考えています。大学を足がかりにして、人に雇われない人間になる、ということです。もちろん瞬間的な年収を考えれば、お金がざくざく貯まるようなことはないでしょう。ただし、そのお金が壊れつつあるのが、いまの世の中なのです。円やドルを公然と破壊している安倍晋三やオバマのようなリーダーが支持されているいまのような時代に、その壊れゆく円やドルをあいかわらず財産のごとく見なすというのは、どうかしていると思います。
いまの20代の人たちが行なうべきことは、円やドルが壊れても変わらない技能を身につけることだと思います。円やドルがまだ壊れていないいまのうちに、少しでもそういう技能を身につけること。これに尽きると思います。例えば、世界中どこへ行ってもキャベツを育てられるような技能を身につけた人は、今日の食糧事情を考えれば、すでに財産をもっているようなものです。砂漠だろうが工業地帯だろうが、キャベツを生育させられる技能を身につけていたら、仮にどこかの穀物会社に入ってリストラされたところで、悲惨なことにはならないでしょう。キャベツを育てることが好きならば、必ず充実した人生を全うできるでしょう。あるいは、まったく別の技能を挙げてみると、どんな相手に対しても落ち着いて対話したり交渉できる能力、凶暴なマフィアであれ知的障害者であれ、人として合意形成をはかれる対話能力を身につけた人も、生涯誰かに必要とされ続けるでしょう。最後はアフリカでどこかの部族のために働いているかもしれませんが、社会から排除されることはないでしょう。キャベツの生育力や対人能力といったものは、ハイパーインフレになろうが預金封鎖になろうが、変わらないからです。
先ほども少し言いましたけど、僕の所属している建築工学科には、そういうことを建築関連でやろうとする教員が一定数います。だから一学年の5%でも10%でもそういう技能をもった人たちを輩出できる学科になれないか、と考えています。もしそれができたとすると、大学という存在は、本当の意味で人生を変える場所になります。A社とB社の年収で人生を決めるといった地獄の選択肢ではなくて、別の人生を始めるという本当の選択肢が生まれます。今後の大学は、僕としてはそういう場所になってほしいです。
今日始めにお話ししたように、学生時代の僕は、1日でも早く図面を描かせてもらえるアトリエに潜り込むという、単純な行動原理しか持ちあわせていませんでした。なぜその希望が実現したかを考えると、究極的には、たまたま入った大学のおかげです。当時は僕も無名の学生のひとりです。でも早くからたくさんの建築家と出会うことができたし、いろんなアトリエを自由に覗かせてもらえたし、社会の側にも隙間が多かったから、自分の望んだとおりの人生を歩んでこれたというだけなのです。ですから、当時の自分と同じことを、いまの学生たちに薦める気にはなれないです。あんな建築学科、つまり同時代のどこよりも実験的なアーキテクト教育をそうと知らずにしていたような建築学科は、その後の東工大を含めて、もうどこにもないのです。そもそも時代や社会も違うし、経済や政治の状況も変わってしまったし、学生たちの適性も大きく変化しています。その意味では、当時の東工大のようなアーキテクト主導の教育をいまやろうとすることは、僕は直感的に意味がないという気がします。むしろ当時とは違う人材を育てること、当時は必要なかったし思いもつかなかった教育を、今後の大学はするようになってほしいです。
ようするに、大学の機能が変わったと思うのです。ですから、もし学生が本当の意味で人生を変えたいと望んだ時に、その選択肢を提示し、必要な技能を授けることを、大学がすればいいのではないかと考えています。他の行政機関、例えばハローワークなり社会保険庁なりにそんなことできないです。もちろん、大学には文科省の縛りがあり、理事会の経営判断もあるから、新米教師である僕にはわからないことも多く、そんなことができるのかどうかよくわからないところもあります。そんな大学はどこにもない以上、きっとどこかの抵抗を受けることになるのでしょう。だから少しずつでもいいから、大学が本当の意味で人間を育てる場所になってほしいです。僕の所属している学科だけでなく、いろんな大学でそうしたことがなされるようになれば、今後の大学には希望があると思います。
2015年3月27日 芝浦工業大学西沢研究室にて
西沢大良(にしざわ・たいら)
芝浦工業大学工学部建築工学科教授。建築設計・都市計画。1987年東京工業大学工学部建築学科卒業。1987年入江経一建築設計事務所入所。1992年西沢大良建築設計事務所開所。主な作品=《大田のハウス》1997、《諏訪のハウス》1999、《砥用町林業総合センター》2004、《沖縄KOKUEIKAN》2006、《駿府教会》2006、《宇都宮のハウス》2009、《今治港再生都市計画》2009、《直島宮浦ギャラリー》2013。著書=『現代住宅研究』(塚本由晴との共著、LIXIL出版、2004)、『西沢大良1994-2004』(TOTO出版、2004)、『西沢大良|木造作品集2004-2010』(LIXIL出版、2011)