小嶋一浩+赤松佳珠子出版記念トーク
建築写真を通して「背後にあるもの」を見る
建築写真を通して「背後にあるもの」を見る

連続した思考を表す本

- 現代建築家コンセプト・シリーズNo.21
『小嶋一浩+赤松佳珠子/CAt|
背後にあるもの 先にあるもの』
(LIXIL出版、2016)
皆さんそうだと思いますが、普段、建築設計の中で、延々と模型をつくったり壊したりしながら考えていることは、作品としてメディアに発表する際には語っていません。僕らは学校建築の専門家のつもりではありませんが、特に学校は、求められた与条件に対して何をしたかを書いていくと、すぐに800字くらいの解説文は終わってしまいます。けれど、本当はそれ以外のところにすごく時間を掛けているのです。それはこの本に載っているどのプロジェクトでも同じです。落選したコンペ案や、限られた会期で一部の人にしか体験してもらっていない展覧会なども含まれていますが、思考は連続しています。

- 赤松佳珠子氏
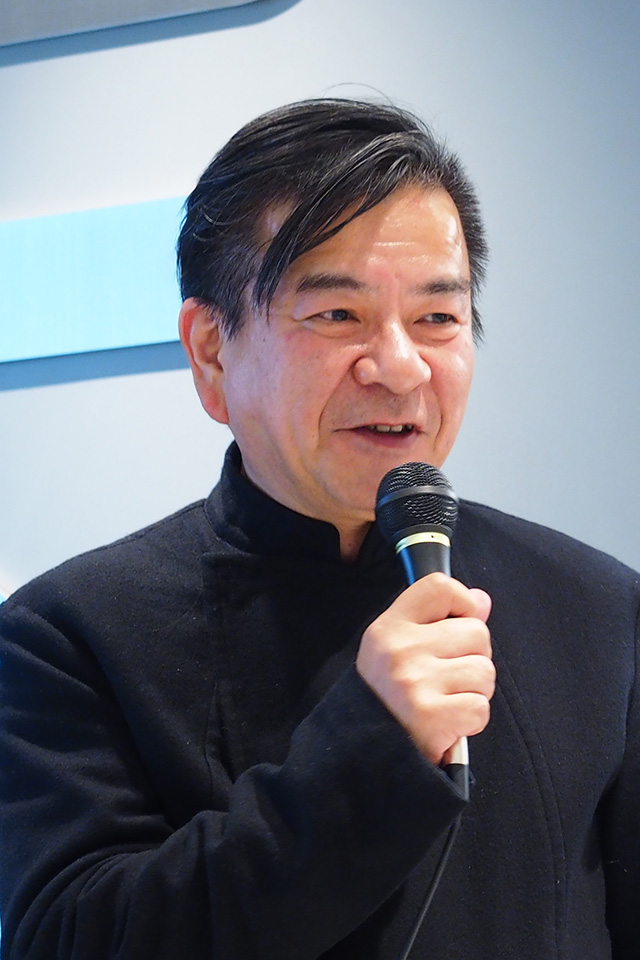
- 小嶋一浩氏
赤松──相互にツッコミを入れたりしながら楽しい会になればと思っています。
吉田誠
光・位置・タイミング

- 吉田誠氏
元々、私は写真ではなく映像に興味がありました。学生時代、イームズ夫妻の映像作品を見て、このように建築空間を伝えていけないかと思っていました。《HOUSE after five years of living》(1955)は、250枚ほどの写真をつないだ5分ほどの映像作品ですが、「イームズ自邸」をディテールや風景と交えて音楽も付けて見せています。
小嶋さんと赤松さんが設計した建物を初めて撮影したのは、『日経アーキテクチュア』の取材で《吉備高原小学校》(1998)の時でした。当時は写真を始めたばかりの頃でしたが、建物そのものよりも、元気な子どもたちの表情が印象的でした。
赤松──これはすごく良い写真でした。この『日経アーキテクチュア』掲載号はわれわれにとって宝物になりました。
吉田──その10年後の《富山市立芝園小学校 芝園中学校》(設計:シーラカンスK&H、2008)になると、残念ながら、個人情報の問題から正面から子どもの顔を撮れなくなってしまいました。建築写真は、光や撮影位置、タイミングが重要な要素です。撮影現場ではあまり自由に動けませんので、その中で何をどう組み合わせてひとつの空間を撮り切るかを考えています。
《流山市立おおたかの森 小・中学校 おおたかの森センター こども図書館》(2015)[fig.1-1]では、当初植栽の緑が足りなかったのですが、学校が始まって3カ月ほど経つと、緑も揃い、生徒も入って、建築のコンセプトがわかる場になっていました。ここからはほかの建築家の作品をはさみながらお話しします。《ひたちのリフレ》(設計:妹島和世、1998)は、特に光によってまるで違う印象の建物になります。《十和田市現代美術館》(設計:西沢立衛、2008)は、光が当たっていると立体感があって硬い感じになりますが、光の弱い時間では素材感がなくなって、より建物のおもしろさが表現されると思いました。建築写真には「夜景」がありますが、実はそのタイミングは1日の中で20分ほどしかありませんので、どこで撮るかはその日の昼間に考えています。ランドスケープの写真も撮っていますが、イサム・ノグチの《モエレ沼公園》でも、順光と夕陽の逆光によるシルエットでは、かなり違った表情になります。

- fig.1-1──《流山市立おおたかの森 小・中学校》
撮影位置ということで言えば、《宇土市立宇土小学校》(2011)[fig.1-2]では、生徒が上がれない屋上からも撮っています。L字型の壁によって空間が構成されていますが、地上レベルからはその壁を感じることはできても表情を出すことができなかったので、屋上に上がっています。

- fig.1-2──《宇土市立宇土小学校》
赤松──これを最初に見せていただいた時はすごく新鮮でした。われわれも考えていなかったので、新しい視点だと思いました。
吉田──《越後松之山森の学校キョロロ》(設計:手塚貴晴+由比、2003)でも、ひとつの長いワンルームの空間が屋根の上からはよくわかります。先ほどお話した《流山》では、近隣の高層マンションからの遠景も撮影しています。現場からよく見える高層マンションは実は撮影の邪魔なのですが、逆に言えば、そこからは現場がよく見えるということです。
人を入れるということも意識しています。例えば大橋富雄さんの写真にも、建物ではなく人をメインに撮っているような写真があります。やはり学校は、校庭や体育館などに生徒がいないと空間の良さが伝わらないですね。生徒の動きがあることによって梁の水平性がより強く見えてきたりします。また、空間の使われ方、レベル差、傾斜などがわかるようになります。《東大福武ホール》(設計:安藤忠雄、2008)では、100mの長さの壁の両側を人が歩いていることによって緊張感が生まれています。《安曇野ちひろ美術館》(設計:内藤廣、1997)では、ちょうど遠足の子どもたちがいました。《12のストゥッディオーロ》(2009)では、入居者の生活の様子も入れて撮影しています。
《流山》の時は、事務所の担当者が時間割を聞いて、メモをつくってくれました。休み時間に生徒が移動するので、そのタイミングを狙います。ただ、なかなか思うように生徒が動かないのでやきもきしますし、偶然の要素があります。駅舎の撮影も同様です。時刻表を見つつ、どの電車にするかまでも考慮します。
現場では、まず自分自身が楽しむことを重視しています。《吉備高原小学校》では、最後に生徒たちが「カメラマンのおじさんと一緒に撮りたい」ということで、先生にカメラの操作を教えて撮影してもらいました。楽しく、思い出に残る撮影の機会をいただいており、この場を借りて感謝申し上げたいと思います。
赤松──カメラを構えた時に、子どもが寄ってきてしまうと不自然になりがちですが、吉田さんは長時間同じ場所でシャッターを切っているので、子どもたちが自然と振舞っていますね。私たちの設計した建物は雑誌などで発表している写真だけでは、かなりリジットに構成が組み立てられていると思われがちなのですが、吉田さんの写真などによって実際にそこでの活動が伝わってくるなあと思いました。
小嶋──今の日本は異様と言っていいほど個人情報を気にしすぎていて、子どもが入った写真が撮れなくなっています。これまでもいろいろ理解がある人たちと一緒に仕事をしてきましたが、それでも難しくなっています。《流山》は竣工写真として生徒が入った写真を吉田さんに撮ってもらいましたが、いろいろな表情がありました。僕らも定点撮影の中の1枚しか見せてもらっていなかったので、生徒の写り込みが絶妙な「シャッターチャンスの神」だと思っていましたが、実は「背後」にこのような苦労があったことを知りました(笑)。
吉田──イームズの映像作品には音が入っていますが、建築写真にその場の生徒の声を入れて映像化するとすごく雰囲気が伝わってくるので、今年はそうしたことにもチャレンジしたいと思っています。
西川公朗
プロポーションで撮る

- 西川公朗氏
《立川市立第一小学校》(2014)[fig.2-1, 2]は、可動建具(間仕切り)が印象的で、その動きによって空間やアクティビティを変化させていくのが特徴だと思います。小嶋さんと赤松さんたちの建築は、プランやプログラムにスポットライトが当たることが多いと思いますが、僕はまずプロポーションの美しさに惹かれました。余計な形が出がないように、ディテールを苦労されたのだろうと思います。僕が感じたのは、建物をつくることで何ができるかということももちろんありますが、むしろ「何をすべきか」に重点が置かれていて、それがプロポーション(比率)に表れているということです。垂れ壁、空間、抜けのプロポーションが美しく、真摯さを感じました。


- fig.2-1, 2──《立川市立第一小学校》
赤松──そういう視点からのお話は初めて聞きました。プランだけでは立体的な関係があまり見えてきませんが、異なる場所のつながりを撮っていただいているので嬉しいですね。
西川──僕はある種病的なのですが(笑)、ひとつのことに固執してしまうところがあります。この建物は「プロポーションをきれいに撮らなくてはいけない」と思ってしまいました。デジタルカメラの縦2:横3のフォーマットで撮ると、水平方向の流れが強くなるので、梁が伸びやかに写ります。これを4×5のフィルムで撮ってしまうと空白部分に力が抜けていってしまいます。
赤松──可動の建具によって場面が転換していくので、それを同じアングルで撮っていただいてます。同じ場所の変化がよく捉えられています。
小嶋──建具のレールがすごく長いので、どの位置に設定して撮るかが難しかったと思いますが、西川さんの写真では建具による「モードチェンジ」がよくわかりますね。
西川──写真には通常説明のためのキャプションが入りますが、言葉で説明されると、カッコ悪くなってしまいます。写真は、説明しようとすればどこまででもできますが、そうするとカッコ悪くなるというのがプログラムを表現するときに難しい問題です。吉田さんが執拗にタイミングを計っているのも、説明的な部分を消そうとしているのだと思います。僕がプロポーションにこだわるのも、内容の説明ではなく、それを支える形が大切だということです。
小嶋──今日のトークイベントはまさに説明したらダメだという趣旨です。
西川──僕は現場では撮影に集中するので、基本的に片付けは事務所の方にお任せします。あまりきれいにし過ぎてしまう時には「やめてください」とお伝えしますが。人は見たくないものに目が行くので、たとえばこの写真[fig.2-3]では中央に水筒が沢山置いてあるのがわかると思いますが、これくらいの量だとちょうどいいと思います。

- fig.2-3──《立川市立第一小学校》
赤松──これはフィルムですか?
西川──デジタルです。僕はデジタルとフィルム(アナログ)を両方使います。また縦横比は、横長の2:3、絵画的な安定を持った4:5、それとその間の3:4を使うことがあります。
吉田──僕だったら開口の先を白飛びしないように抑えますが、西川さんはあえて飛ばしているというか、開口の先をイメージさせるように撮っていますね。デジタルだと、細部まで出すことができるので、平面的になってしまいますし、どうしても調整の段階で白飛びを抑える方向にしてしまうこともあります。これは性格の違いですね。また、微妙な「振り」を意識されていますね。
西川──最初は全部まっすぐ(正対で)撮っていましたが、変調が大事だと思います。写真を鑑賞できる時間は2秒くらいだと言われていますが、どうやって見る人の目を止めるかに神経を尖らせています。空間の全体を見せようとするとどうしても広い絵になってしまいますが、わざと建具の面を大きくして閉塞感をつくったりもしています。
小嶋──僕らがこの小学校の説明をするよりも全然おもしろいですね(笑)。
西川──いえいえ(笑)。吉田さんは先輩なので、吉田さんから教わっている部分もありますが、その運用方法が違うので違う写真になっていると思います。「構造体の中央に立つ」ということも基本ですね。
吉田──現場で他のカメラマンと一緒になると、人によってアングルはさまざまですが、やはり「この位置」というのはあり、そこは譲り合いだったり、タイミングの戦いがあったりします。
西川──これは初めてCAt設計の建物を撮らせていただいた時で、カタールの《リベラル・アーツ&サイエンス・カレッジ》(2003)[fig.2-4, 5]です。悩んでいたのでしょうか、不思議なフォーマットを使っています。


- fig.2-4, 5──《リベラル・アーツ&サイエンス・カレッジ》
小嶋──カタールまで撮りに行ってもらうのはなかなか大変です。西川さんはアラビア語が喋れると伺ったのが撮影を依頼したきっかけです。セキュリティの問題があったり、なかなか大変なのです。
西川──その節はお世話になりました。これは本当に美しい建物でした。すべてフィルムで撮っています。
赤松──太陽光が強いところなので、それを反射させながら内部に入れています。アルミダイキャストのパターンを持ったルーバーから光が入ってきていますが、その様子を撮ってくださっています。
西川──これは僕が大学に入る直前に撮ったカイロの「イブン・トゥールーン・モスク」[fig.2-6]の写真です。6×12のフィルムで撮っています。正方形だと動きがありませんが、それが二連になっているというプロポーションです。この写真を今日持ってきたのは、《リベラル・アーツ&サイエンス・カレッジ》にそっくりだと思ったからです。

- fig.2-6──「イブン・トゥールーン・モスク」
小嶋──そういうことをパッと掴んでくれるのはすごく嬉しいですね。これはモスクですが、《リベラル・アーツ&サイエンス・カレッジ》は、例えばイスタンブールのマーケットのように、建物の内部に街をつくろうとしていました。
西川──「イブン・トゥールーン・モスク」の周囲は二層三層の建物が多いので、まさに街の中という感じがあります。また、プランが点対称のようになっていて、かなり迷ってしまいます。
小嶋──まさに小さな都市のようですね。
西川──《リベラル・アーツ&サイエンス・カレッジ》では、ステンレスによる鏡面の柱が象徴的にありますが、迷路感を増長していました。
小嶋──イスラム建築は、中にどんどん入っていくと階層性があるのですごくおもしろいですね。僕はイスラム建築マニアだったので、カタールの仕事はチャンスだと思いました。先ほど指摘していただいたステンレスの柱は、実は中が空調ダクトになっていて、冷房を床下に回しています。本当の柱は壁の中に隠してあるので、通常とは逆転させているのです。
西川──そうだったのですね、今まで知らなかったです。
小嶋──西川さんは高校生の頃から写真を学び始めたのですか?
西川──高校の授業でやっていました。僕は内気で人見知りだったので、人を撮るのが苦手で、このモスクはよく撮影しに行った場所なのです。カイロ最古のモスクで、中央に広場があり、回廊があります。おじさんが寝ていたり、誰でも入っていける素晴らしい建物です。
堀田貞雄
独自の模型撮影

- 堀田貞雄氏

- fig.3-1
元々はファッションカメラマンのアシスタントをしていましたが、2007年に『CULTIVATE』(TOTO出版)が出る時に、模型を撮影するカメラマンを探しているという話がありました。普通のカメラマンが撮ると、模型がブツになってしまうということでした。
最初に小嶋さんたちと打合せをしたときは、専門用語がよくわかりませんでした(笑)。専門家は空間に入る光のラインや、壁面の質感などを気にしているのですが、素人は実は空間を何となく感じていて、どこにかわいい子がいるかとか、人が何をやっているかなどを見ていると思います。そこで、写真を40〜50カット貼り合わせて、模型の中にいる人にしかピントが合っていない写真を提案しました[fig.3-2]。町中で見るプロダクトの広告写真は、物が小さいのでピントの範囲が浅くなりますが、何枚も合成して絵をつくっています。その手法を逆手に取っているのですが、小嶋さんがおもしろがってくれました。

- fig.3-2
小嶋──堀田さんは建築の模型を見るのも初めてだったと思いますが、模型のブツ撮りではなく、その空間を撮ってほしいという要望を出しました。堀田さんは言葉ではなく、実際に写真で見せてくれました。建築はボケて写っていたのですが、僕らのやりたいことがちゃんと写っていたのです。
赤松──沢山の写真が凝縮されて得られる視点が新鮮でした。
堀田──2カ月ほど事務所に通って、模型とにらめっこしながら撮影し、その後1カ月間はひたすら篭って現像をしていました。その3カ月間は、建築を理解するための集中講義のような時間でした。
赤松──このイメージ全体を堀田さんがつくり出しているわけですね。
堀田──人の配置なども場面を想像しながらつくっています。小嶋さんと赤松さんは僕のプライドを立てつつ、「もうちょっとこうできるんじゃないの」とくすぐってくるので、僕もやりたくなってしまうのです(笑)。
これは事務所の屋上で夜中に撮ったものです[fig.3-3]。もう事務所に誰もいない時間帯まで掛かりましたが、決めのカットをつくるために、ストロボと定常光を使い、カメラを揺らして撮っています。独立したばかりで時間があったのですね。これは小嶋さんが絶賛してくれました。
小嶋──よく覚えています。

- fig.3-3
堀田──プロのカメラマンはボケを見るのですが、普通の人は逆にシャープなところを見ますので、これは一筆書き状の壁にだけピントを合わせています[fig.3-4]。デジタルで撮っていますし、デジタルでしかできないことですが、発想はアナログ的です。
本のための仕事の後、《グレインズ・シモメグロ》(2007)という建物を撮影しています。実際の建物を撮ったのはこれが初めてでした。気分が良い建物で、誰もいない部屋の床に寝転んだりしながら、ゆっくり考えて撮りました。
僕が生まれたのは広島県安芸郡熊野町という街ですが、日本でつくられる筆の8割が生産されています。いとこが前衛の書道をやっていて、幼稚園の時にそれを見て「小学生になったらやりたい」と言って始めました。半紙の周りに置いた新聞紙の上まで書いているので、最終的な作品としては文字の端部が切れています[fig.3-5]。ギリギリまで黒で埋めると緊張感が生まれる、人間はイメージを自分でつくるので全部見えなくてもいい、と教わりました。写真を始めて、構図がすぐ決められるようになったのはそのような書道の経験があったからだと思っています。

- fig.3-4

- fig.3-5
小嶋──堀田さんは建築写真家ではなかったのですが、《グレインズ・シモメグロ》[fig.3-6]が出来上がり、入居前にしばらく時間があったので、好きに撮ってくださいというお願いをしました。僕らの考えないことをやるから、見てみたいなと思ったのです。その後は結構建築の写真も撮っていますね。
堀田──建築写真と自分の性格が合っているような気がします。
赤松── 一気に人気フォトグラファーになりましたね。これは《国際交流基金情報センターライブラリー》(2008)[fig.3-7]で、普通のオフィスビルの二層分のインテリアをライブラリーにしています。逆光やハレーション気味の写真なども撮っていますね。

- fig.3-6──《グレインズ・シモメグロ》

- fig.3-6──《国際交流基金情報センターライブラリー》
堀田──僕は人の視界がわかるのです。三次元な視界で、好きな場所にスイッチングできるので、その位置に時間帯を合わせていくという考え方です。
赤松──《宇土小学校》のプロポーザル時に提案書に入れた模型写真も撮ってもらいました。
堀田──写真の仕事は撮影してから納期まで通常は1〜3週間くらいですが、建築はスパンが長くて、《宇土小学校》ではそれをずっと見させてもらったのがおもしろかったです。最初はコンペの模型を撮って、その後に実物ができて撮影し、賞をもらったり、いろんな人が使ったり、子どもたちの思い出になっていくのはすごく楽しいことだなと思いました。
赤松──オカムラデザインスペースRでやった《PARTY PARTY》(小嶋一浩×赤松佳珠子×諏訪綾子、2010)[fig.3-8]というインスタレーションも撮ってもらいました。

- fig.3-8──《PARTY PARTY》
堀田──写真で難しいのは、白い物、黒い物、写り込みという3つなのですが、それが《PARTY PARTY》には全部ありました(笑)。
これは《下北沢Apartments+Blocks》(2011)[fig.3-9]の遠景です。
赤松──密集した住宅地の奥に高層ビル街が見えるというのはおもしろいですよね。

- fig.3-9──《下北沢Apartments+Blocks》
堀田──僕はこだわって西新宿に住み続けています。西新宿には、近景より遠景が大きいという写真的なおもしろさがあります。そうした個人的な思いがこの写真には入っています。
これはURの《ヌーヴェル赤羽台》(2010)[fig.3-10]です。団地は開発の歴史があり、シンボリックですよね。古い団地に挟まれているのがおもしろく、この色ガラスと共に歴史を写そうとしています。僕は建物を撮りに行く時に、その土地の歴史博物館や、スーパーに行きます。スーパーではその場所にどういう生活があるかがよくわかります。熊本と東京では違うのですが、そうした普通の違いが知りたいのです。
今もファッションの仕事もやっています。僕の考えは「毛穴が見えるところから大都市計画まで全部撮る」というものです。所詮は人間の行為ですから。空間でも人間がつくっていますから、人間を感じます。自然物は仙人になるまでやらないと撮れないと思っています。

- fig.3-10──《ヌーヴェル赤羽台》
-
小嶋──今日はもう少しコミュニケーションしながら進めようと思いましたが、三者三様に情報量が多くて、写真家はよくしゃべるということがよくわかりました(笑)
僕も赤松も、今日の3人のお話は初めてでしたが、こんなことを考えているのかと、おもしろく聞かせてもらいました。
赤松──吉田さんと西川さんはある種先輩後輩の関係ですが、堀田さんは異色ですよね。
西川──堀田さんは考えていることが全然違っていておもしろかったですし、僕たちが考えつかない部分はすごく勉強になりました。模型写真はちゃんとコンセプトがあって、力強さと安定感があって素晴らしいと思いました。
吉田──やっぱり3人ともいろんな個性がありますが、現場に入った時の気持ちが一番大事だなと改めて感じました。写真にいかに気持ちを入れ込ませるかというのは、これからも頑張ってやっていきたいなと思いました。
赤松──建築はなかなか実際に体験してもらえないので、圧倒的に写真で伝えていくことになります。いくら説明があっても吹っ飛んでしまうくらいのインパクトを持った写真というものがあります。また、われわれが予想していない意外なシーンを撮っていただけると、「だったらこうしよう」というアイデアが出てきます。今回の『背後にあるもの 先にあるもの』という意味では、写真は建築の実物以上の何かを導き出していただけるものだなあとつくづく思いました。
小嶋──西川さんが言った「説明するとカッコ悪い」ということは、僕らもわかっているのですが、建築はこちらにやって来てくれないので、余計なことをしているのです。でも、今日はそれ以上の部分を、三者三様に、僕らもビックリするような形でお話してくださって嬉しかったです。ありがとうございました。

[2016年2月10日、LIXIL:GINZAにて]
吉田誠(よしだ・まこと)
1990年日本大学生産工学部建築工学科卒業。1990〜1995年 スパイラル勤務(写真撮影、ビデオ制作業務担当)。1996〜2000年 日経BP社映像部勤務(主に日経アーキテクチュア建築土木関連の撮影担当)。2000年 吉田写真事務所設立。
西川公朗(にしかわ・まさお)
1973年生まれ。幼少期をエジプト・カイロにて過ごす。1991年カイロアメリカンカレッジを卒業後、帰国。1996年日本大学芸術学部写真学科卒業。1996〜2005年株式会社新建築社写真部に在籍、雑誌『新建築』『a+u』等の撮影を担当。2005年西川公朗写真事務所設立。
堀田貞雄(ほった・さだお)
1978年生まれ。1996年大学を1年間休学し陸上自衛隊入隊、この頃写真を始める。2001年広島大学法学部を卒業。上京し外苑スタジオに勤務。2004年写真家宮原夢画氏に師事。2007年写真家として独立。広告、ファッション、ビューティー、ポートレートなど幅広い分野で国内外問わず活動。『CULTIVATE』 (著:小嶋一浩+赤松佳珠子/CAt、TOTO出版)の模型撮影をきっかけに建築の撮影に携わるようになる。


