アーバニズム、建築、デジタルデザインの実践とグラデュアリズム
政治的、産業的な意思決定の中心から疎外された建築家
谷繁玲央──今日はよろしくお願いします。「10+1 website」の4月号では八束はじめさん、市川紘司さん、連勇太朗さんによる鼎談「平成=ポスト冷戦の建築・都市論とその枠組みのゆらぎ」が行われました。そこではゼロ年代の建築家の動向や、今後の建築家の職能はどうあるかが議論されました。この20年ほどの間、建築の言説が停滞していることと並行し、建築家はひとつの大きな運動や主義としてまとまるのではなく、てんでばらばらに活動を展開してきと言えるでしょう。しかし今後都市は明らかに縮小・減退していき、空間、建築、物質の量が余剰していくと考えられます。ラディカルに縮小していく社会のなかで、とくに若い世代の建築家は、分母を減らして分子を増やすような「小さなプロジェクト」を積み重ねながら時間や量のスケールを横断し、確かな社会改良を展開しているのではないでしょうか。
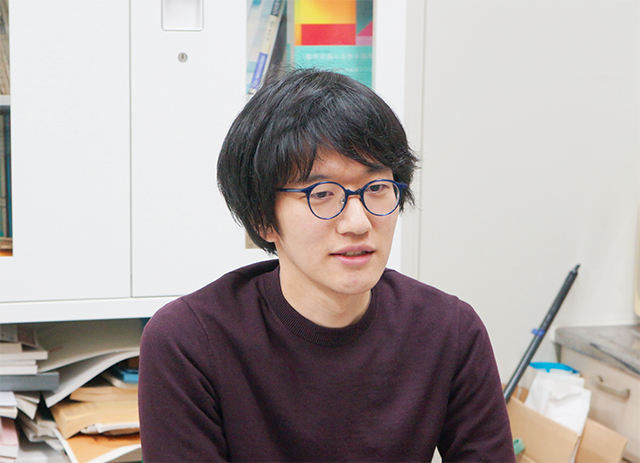
- 谷繁玲央氏
哲学者ジュディス・バトラーは、『アセンブリ──行為遂行性・複数性・政治』(青土社、2018/原著、2015)において街頭に集う身体や、現代における民主主義の条件について論じています。人々がデモに集まる場合には、運動として完全な意志統一が存在しているわけではなく、それぞれが意見の相違=「複数性」をもっている。そして世界的なデモに見られるような複数性をもった連帯は、代表議会制のオルタナティブとなりうる。バトラーの理論は政治的な立場を超えて連帯する方法論として機能しています。こうした連帯の方法論が建築の諸実践にも必要なのではないかと考えています。特に現在30歳前後の建築家の社会改良的な姿勢には複数性や共時性を帯びていると言えるのではないでしょうか。この諸実践を連帯させる概念である「グラデュアリズム(漸進主義)」を提案したいと思います。
今日建築家は、国家的な政策にテクノクラートとして参画できるわけでもありませんし、建築の技術開発は産業へと移行しています。つまり建築家は大枠の政治的、産業的な意思決定の中心から疎外された状況に置かれています。また、建築を従来の美学的な理論から科学的な領域に、つまりエンジニアリングやテクノロジーに紐付けようとする動きがあることも確かです。中央集権的なシステムに抗うように、非専門家も含めた人々と協同しながら小さな動きをつくっているとも言える。
今回は建築家と起業家を横断してメタアーキテクトという職能を拓いた秋吉浩気さんと、モクチン企画のプログラマーであり世界的なデザイン実践の動向に詳しい中村健太郎さんにグラデュアリズムという主題の下で諸実践についてご紹介いただきます。そして都市計画家の中島直人先生には、「タクティカル・アーバニズム」など民主的な都市計画の運動や実践についてのお話や、都市計画や都市論の視点からグラデュアリズム的状況の分析をしていただきたいと思います。さまざまな視点を皆さんからお借りしながら、グラデュアリズムと呼ぶ諸実践の連帯について議論できればと思います。
中村健太郎──よろしくお願いします。まずは議論の裾野を広げるために、谷繁さんのお話を少し掘り下げておきましょう。日本における建築家は明治政府が養成したテクノクラート(技術官僚)としての出自をもつわけですが、いまやそうした役割は求められていないという現状認識を提示してくれました。それに対しては、戦後日本において、政策イシューとしての建築や都市が政府主導で脱政治化されていった結果だよね、というのが素直な応答になるでしょう。ご存知の通り日本の建築・都市は戦後復興と高度経済成長を通して、内需拡大のための燃料としてくべられてきた経緯があります。住宅に関しては(住宅不足に対する苦肉の策とはいえ)戦後早々に金融とセットになった民間主導の住宅政策がとられていますし★1、都市空間についても1982年に発足した中曽根政権による「アーバンルネッサンス計画」を嚆矢に、バブル崩壊後も繰り返し規制緩和が行われています。こうした建築・都市をとりまく脱政治化の政治と新自由主義的な政策の常態化は、建築・都市の問題を公的な責任のもとに解決するテクノクラートの仕事領域を縮小させただけでなく、設計実務者の側にも巨大な建設市場という"消費の海に浸る"スタンスを取ることがあたかも優れた生存戦略であるかのような錯覚を与えてきたのではないでしょうか。しかしそれは再帰的に建築・都市の脱政治化を推し進め、政府や地方自治体の政策形成能力を徐々にスポイルし、究極的には一握りのスターアーキテクトとハウスメーカー以外の選択肢を排除してゆく緩やかな自殺行為にほかならなかった。そんな平成の成れの果てが現在だというのが、やや単純ですが僕の認識です。さらに言えば新自由主義と脱政治化が同時進行する傾向は日本一国だけでなく、程度の差こそあれ先進民主主義国家全般に見られる現象となっています★2。
「技術の民主化」は第2フェーズへ
中村──当然ながら、こうした状況への抵抗運動も世界各地で巻き起っています。グラデュアリズムを論じるための参照点として、まずは「技術の民主化」を背景とする動きを取り上げましょう。2000年代以降、レーザーカッターや3Dプリンター、電子工作ツールなどのデジタル工作機械が廉価化し、個人でも使える環境が整ってきました。こうした変化と連動して生まれた「メイカームーブメント」は、DIY文化やハッカー文化の流れを汲む、個人レベルでの"科学技術を用いたものづくり"を実践する社会運動です。市民による主体的な"ものづくり"を通じた、産業による技術の独占への抵抗活動とも見なせるでしょう。興味深いのは、ファブラボやハッカースペースなど、市民が技術を使いこなすための「メイカースペース」と呼ばれる市民工房がその発展を下支えしてきたことです。

- 中村健太郎氏
メイカームーブメントが耕した土壌の上で、グローバルな社会課題に取り組む事例もでてきています。廃棄プラスチック問題に取り組む「precious plastic」はその一例です。彼らは身近な廃棄プラスチックを再利用するための4つの機械(破砕機、押出成形機、射出成形機、圧縮成形機)の図面と制作方法をオンラインで公開することで、この問題にコミットするグローバルな共同体を構築しようとしています。メイカースペースという既存のインフラに"ツール"を配布するという方法の巧みさが目を引きますが、より重要に思われるのは、ツールを通した経験が各地の"メイカー"を廃棄プラスチック問題のステークホルダーへと変化させる効果を持っていることです。彼らはツールの制作を通して社会課題へのコミットを実践し、自らつくったプラスチックのリユース製品を通して地域に言説を拡散させてゆくでしょう。ハードウェアを通じて廃棄プラスチック問題の言説を補強してゆく彼らのアプローチは、"連帯"の基盤をつくる社会運動の戦術としても極めて独創的です。
政治的言説の構築に参与するタイプのデザイン実践は、近年急速に増加しているように思います。こうした文脈を引き継ぐならば、"グラデュアリズム"は日本の現状への冷笑的な諦観を退け、建築・都市をいかに「再政治化」できるか──ただしテクノクラートに復帰する以外の可能性も含めて──という問題意識まで踏み込んで問われるべきではないかと思います。
以上の認識を踏まえ、例えばメイカームーブメントの流れをくむVUILDの実践にも「技術の民主化」のミームが流れ込んでいるのではないか。また中島先生が研究されている「タクティカル・アーバニズム」も、市民の立場から都市計画を主体的に実践してゆく、ある種のアクティビズムとみなせるのではないか。そのようなことを考えてきました。まずは中島先生、都市計画における現状や、今いまの建築家たちの実践に関してお話しいただけるでしょうか。
中島直人──よろしくお願いします。いまの「技術の民主化」は、まさに秋吉さんが実践されていることだと思いますね。また、グラデュアリズムと定義されている状況の背景には、現状の都市的空間をどうするかといった問題があるのではないでしょうか。人口減少に伴って、目の前にある空き家や空き地、あるいは既存の街路の余剰空間など、あらゆる場所に「隙間」が大量に存在していますよね。とくに地方都市に行くと、タダでも借りてくれと言わんばかりの空間を多く見かけます。こうした話は空間のみならず、崩壊しそうな既存の流通システムなどにも当てはまる。要は高度経済成長期以降につくってきた大量のストックが「隙間」になっていたり、崩壊しかけているシステムがあるなかで、技術が民主化した基盤があるんだろうと感じています。

- 中島直人氏
まちづくりの分野について言うと、先ほどの「複数性の連帯」と対峙する概念として「合意形成」があります。まちづくりにおいては地域の主体はひとつであるべきだとする全体主義が強く、最終的に既存の政治・権力の構造を踏まえないと地域は変わらないと考えられていたふしがあるのです。地域で何かやろうとしたときには、合意形成がとられることでオフィシャルに認められたことになり、初めて実践ができる。このような構造の下では古い伝統的なシステムに乗っている人が影響力を持つんですね。ところが保守的な合意形成型のまちづくりは、最近SNSで話題になった「まちづくりは『クソダセェからやりたくない』とのこと」(Yahoo!JAPANニュース、2019年10月30日)という記事にあるように、いまの若い世代にとっては全然魅力的ではない。参加しても使われるだけの状況であり、実際地方の衰退を止められているかと言われるとそうでもないのです。近年はまちづくりにおいて、デジタル技術を使うことが新たな手法になりつつあります。そこには合意形成は必要なくて、やりたい人たちがチームをつくって活動していくことが許容される。チーム同士はネットワークで繋がっていてもいいし、繋がらなくてもいい。こうしたフラットなまちづくりは次々と実践を重ね成果を出しています。つねに皆で話し合い、プランの作成に5年、10年もかけて、という世界ではないので、若い世代も既存の街や抱える問題に対して、軽やかに入っていくことができる。例えば、神田祭で有名で、都内でも古いコミュニティが残っている千代田区の神田でも、映像系や不動産系などの若手人材が新しいコミュニティ形成に向けて独自の取り組みをしたりしています。外の人が入りやすい開放的な状況になってきていますね。
中村──ありがとうございます。即物的にどうにかしなければならない問題が目の前にあり、それに対してはアクションもフットワークも軽く実践していくことができる状況になっているわけですね。
中島──そうですね。また、いままで大手資本によって実践されていたけれど、利潤を回収しにくい小さな領域など、彼らが手放してしまったものがたくさんあるんです。そうした領域はいま建築家にとってはチャンスであるとも言えるでしょう。
中村──なるほど、市場化が行き着いた先でむしろ余剰が目につく状況になってきたと。先ほどメイカームーブメントについてお話ししましたが、こうした状況は、いま秋吉さんがVUILDで実践されていることにも影響があると考えられるでしょうか。
秋吉浩気──よろしくお願いします。まず技術の民主化については、第1フェーズは終わったと考えています。僕は2013年に慶應義塾大学大学院に進学し、ファブラボジャパンの発起人である田中浩也先生の下で学んでいたため、日本でファブラボが立ち上がっていった瞬間を経験してきました。そこでひとつ問題となったのが、いくら技術を民主化してデータをオープン化しても、一般の人がそれを自由に使う状態はなかなか実現しなかったことです。設備が導入されて、スキルやノウハウが共有されてもそれを応用することが最も難しい。やはり応用するための「デザイン」が不足しているのだろうと考えています。技術の民主化第1フェーズ以降、一部のギークな人たちが新しい先端的技術を日常的実践として用いる「パーソナル・ファブリケーション=工業の個人化」から、誰かのためにつくる、誰かと一緒につくる「ソーシャル・ファブリケーション=工業の社会化」のフェーズに移行しています。そのなかでデジタルファブリケーションの基盤を地域に介入させ、林業に代表される地場産業の問題を解決できるかという議論がありました。「precious plastic」のように、第1フェーズで構築された技術基盤に乗っかる形で新しいムーブメントを興そうとする実践が生まれたり、タクティカル・アーバニズムでもデジタルファブリケーションが使われていたりする。グラデュアリズムは民主化の第2フェーズと繋がっていると思います。

- 秋吉浩気氏
また、僕自身デジタルファブリケーション技術を活用したスタートアップ「VUILD」を2017年に立ち上げていますが、この業界にはリーン・スタートアップと呼ばれる方法論があります。これは、最低限の機能をもった試作品をユーザーに体験してもらい、その反応を分析し新たな試作品をつくるといった一連のサイクルを短期間に行い、事業の成功率を高める手法です。これは、特定の小さな市場にターゲットを限定し、その市場で成功したモデルをスケールアウトしていくという戦略です。この方法論の代表例としてFacebookがありますが、よく知られているように当初Facebookはハーバード大学の学生向けサービスとして始まりました。VUILDの実践は地方の製材所や工務店にデジタルファブリケーションを導入することから始まりましたが、今後は辺境から都市部へとスケールアウトするための方法論が課題としてあります。同様の課題は「Short-term Action for Long-term Change」を掲げるタクティカル・アーバニズムにも見出されるでしょう。まちづくりの文脈において思うこととしては、やりたい人が集まってアクションを起こす方法は、その人の人間性やスキル、拡散能力に依存してしまうことも多いため、あまり再現性がないと考えています。しかし共有可能なデジタル言語によって同じ基盤をシェアし、どこでも通用する拡がりをつくることができるのがデジタルテクノロジーの強みであり、これを無くして建築・都市の発展はないと思っています。また、既存インフラが整備されていない新興国で、地域通貨などの新しいサービスが実装されるリープフロッグ現象は現代いたるところで起こっています。そもそも住宅産業の工業化が届かなかった中山間地域には、後継がいないため行く末を悩んでいる工務店は多いんです。ところが、非工業化の未開拓地であることを逆手に取って、そこにリープフロッグのようにデジタルファブリケーションを導入することで、都市流通に依存することなく地域内でサプライチェーンが完結するデジタル時代の循環系が真っ先に実装できる。その循環系を連動させて、都市や社会といった大きな系に接続していくことが課題で、悩みつつ実践しているところです。
中島──「『デザイン』が不足している」と言われている「デザイン」とは何なのでしょうか。
秋吉──要素技術(シーズ)と社会(ニーズ)を橋渡しするための「構想力」のことを指しています。コロンビア大学のホッド・リプソン教授は『2040年の新世界──3Dプリンタの衝撃』(東洋経済新報社、2014/原著、2013)において、映画『スター・トレック』を例に取り、何でも出力してくれるレプリケーターに対して乗組員がつねにアールグレイしか注文しない状況を指して「アールグレイ症候群」と呼んでいます。目の前の多様な課題に対して、万能な技術はあるけれど、それをどう使って解いていけばいいのかわからない。私がデザインの不足と呼んだのは、そのような想像力の欠如を指しています。ここで求められるのが、具体的な構想を示し実行できる役割としてのアーキテクトなんだと思います。全体像を示して、非専門家たちをひとつのヴィジョンに向かって繋いでいくような、システムを含めて構築するアーキテクトですね。改めて語源に立ち返ると、アーキテクトとはそのような存在のことではなかったか。そんなことを主張したくてあえてメタ性を強調し、メタアーキテクトと名乗っています。
デジタル技術は中央集権的体制をつくる?
中村──なるほど。他方で注意したいのは、デジタル技術は技術の民主化を加速させ、グラデュアリズム的な実践を支えてきた一方で、無視できない負の側面も孕む、二面性を持ったものだという点です。都市に関わるところで言えば、スマートシティ関連の技術は注意して見る必要があります。「犯罪予報」のような問題含みの技術の例もありますし、卑近な例では行政が企業と組んで提供する無料の公衆Wi-Fi。この手のサービスは、利用者の行動履歴を別途マネタイズする仕組みになっていることが普通です。しかし行政が市民のデータを進んで私企業に提供するという構図が正しいのかはかなり疑問ですし、更に悪いことに通信量を抑えたい低所得者から選択的に行動履歴が吸い上げられてしまうという懸念が指摘されています★3。こうした状況を見ていると、デジタル技術はむしろ中央集権的な管理体制をつくり上げるのに適した技術なんだろうなと思ってしまうんですね。そのあたりはどのようにお考えでしょうか。
中島──そうですね、デジタル技術が中央集権的に働くというのはもっともだと思います。アーバニズムの発信地も、かつては一部の地域に限られていました。しかしタクティカル・アーバニズムのムーブメントは、例えばラテン・アメリカの国からも発信されている。同時代的に多発している状況があります。デジタル技術によってイニシアティブが分散している印象を受けますね。けっしてアメリカ中心主義、ヨーロッパ中心主義ではないのです。アメリカにおける古典的なアーバニズム、ここではニュー・アーバニズムになるんですが、それとタクティカル・アーバニズムの間をつなぐ「リーン・アーバニズム(lean urbanism)」と呼ばれる動きがあります。ニュー・アーバニズムはまじめに一からやろうと思うとコストも時間もかかるのです。タクティカル・アーバニズムは属人的な部分があるので、形は真似できても、本質的なところは真似できないし、またみんなに共有されているはずの技術を使えない層がいるといった問題もあります。この両者を繋ぐリーン・アーバニズムは、経済的、ローテクな実践ですが、小さな実践を重ねて大きな変化をもたらす動きです。技術が使えない層とは、移民のコミュニティなんですね。タクティカル・アーバニズムはみんながウェブへ投稿することで運動を形成していくなど、デジタル社会に合った運動なのですが、そもそも移民の人々は情報へアクセスすることができない。リーン・アーバニズムはタクティカル・アーバニズムやニュー・アーバニズムの考え方を簡素化したり、完璧を求めないようなかたちで、マニュアルやカタログをつくって配布したりする運動です。漸進的・継続的な社会改良を目標としている点を見ても、グラデュアリズムと似たような面がありますし、ひとつの国や地域のなかで格差をフェアにしていく重要な取り組みです。
中村──なるほど、やはり移民や低所得者層の格差問題は、アメリカの都市計画に深く根ざしているんですね。ちょうど、ニューヨークの「Center for urban pedagogy(CUP)」というNPO団体を思い出しました。彼らの実践の中でも興味深いもののひとつに「Vendor Power! 」があります。これはニューヨークで露天を営むうえで知るべきルールを美麗なグラフィックで描いた多言語対応ポスターです。「もし警察に接触されたらこのように対応しましょう」というような内容を含む実用的なものなんですが、これは1万人いると言われる露天商たちの一部に実際に配られると同時に、オンラインでの無料配布も行われています。彼らが団体名に"Urban Pedagogy(都市教育)"を掲げていることに象徴的ですが、CUPの取り組みが「都市における振る舞いについての知識ギャップ」の解消を指向していることは、都市実践において「テクノロジーによる課題解決を目的化しない★4」ことの重要性を暗に示しているように思います。
中島──いまのお話も含め、基本的にはパブリック・スペースの形成には社会的包摂が大きな目標としてあります。ニューヨークのパブリック・スペースといえば輝かしいハイラインやタイムズスクエアなどが取り上げられますが、ニューヨークは格差の問題が深刻なので、パブリック・スペースや広場づくりは実際のところ低所得者地区で率先して行われています。こうした話題は意外とグローバルには表出しない。おっしゃるとおりアメリカやヨーロッパは、日本以上に移民も多く格差問題が根強くあり、当然これらの問題は建築や都市計画の分野と密接に結びついています。
註
★1──住宅政策の問題についてふれた書籍として、平山洋介『住宅政策のどこが問題か』(光文社新書、2009)がある。あわせて参照されたい。
★2──新自由主義と脱政治化の関係については、コリン・ヘイ『政治はなぜ嫌われるのか──民主主義の取り戻し方』(岩波書店、2012/原著、2007)を参照のこと。
★3──スマートシティ関連の技術を批判する言説は近年急速に勢いを増している。以下を参照のこと。
Ben Green, The Smart Enough City: Putting Technology in Its Place to Reclaim Our Urban Future (Strong Ideas), 2019
中村健太郎「スマートシティ批判の始まり──『解決主義』を超えて」、建築討論、2019年7月1日
★4──テクノロジーによる課題解決を素朴に信頼する態度については、ジャーナリストのエフゲニー・モロゾフが「解決主義」と名指して批判を展開している。
エフゲニー・モロゾフ「シリコンバレーの解決主義」、10+1 website、2018年2月号
- 政治的、産業的な意思決定の中心から疎外された建築家/「技術の民主化」は第2フェーズへ/デジタル技術は中央集権的体制をつくる?
- 自治感覚を取り戻す/1970年代〜80年代の建築家、都市計画家の実践とグラデュアリズム/小文字の「政治的なもの(the political)」/中間的な役割を実装して、消費の海を泳ぐようにデザインする


