平成=ポスト冷戦の建築・都市論とその枠組みのゆらぎ
市川──今日は、もうすぐ平成が終わるということで、日本の「平成」を「ポスト冷戦」の時代と捉え、その建築論や都市論を振り返りつつ、単なるレトロスペクティブな話というよりは、現在から将来に向けて議論を展開していければと思っています。よろしくお願いします。
連──八束さんのいち読者としても今日は楽しみにしてきました。近過去を教条的に語るのではなく、現在の状況への関係を見出し、生産的なものにしたいと思います。平成あるいはポスト冷戦の時代の建築を振り返ると言っても、私は平成になるちょっと前に生まれた人間ですし、歴史家でもないので客観的に語ることはできません。あくまで個人の興味と感覚からお話することになるかと思います。
八束──僕は最近古希を迎えましたが、昭和を40年間、平成を30年間生きてきて、これだけ世代が離れた人たちと話をする機会は初めてです。おふたりとは時代に対する批判的な眼差しが、ある部分では一致しそうなのでお話してみたかった。一方で、そんなにきれいに話がまとまるわけはないとも思っています。そのあたりの異同が問題提起になることを期待しています。
基本的に昭和の人間である私から見ると、平成あるいは平成という括りを与えられた建築は、アイデンティティに乏しいと感じています。昭和のみならず、大正や明治に比べても。もうすぐ始まる次の時代が、もっと明確なアイデンティティをもちうるのかどうかはまったくわかりません。ほぼ平成の人生を送られてきたおふたりからすると、あまり愉快ではない評価かもしれないけれど、実際、僕はかつて教えた人に今の建築に興味がもてないと言ったら、「でもそのなかで私たちは仕事をしているのだから」と反発をされたことがあります。これは、平成の人間としては当然の反発でしょうね。教育に関わる者としてはいささか大人気ないことを言ったな、と悔いているのですが、昭和はいわゆるオワコンなのかもしれないけれど、平成は始まりもしなかった(と過去形で語ることにもうすぐなるわけですが)コンテンツになるのかどうか、そのあたりが今日の議論の対象になるのかもしれないと感じています。
「中間項」の不在と開発──1980年代生まれのふたりが見た平成
市川──今日の鼎談のひとつのきっかけとしては、日本建築学会による「建築学生サミット 2018 秋──平成の建築を考える」というイベントで★1、八束さんと豊田啓介さんと市川が登壇し、そのときの僕のプレゼンテーションに八束さんが興味をもってくださった、ということがあります。まずはそのときにお話したことを改めて紹介することで議論のきっかけになればと思います。僕は2004年に横浜国立大学に入って建築を学び始めた世代ですが、学会のイベントでは、その世代の視点から現在までの約15年(平成後期と言えますね)の同時代的な建築の状況を、3つの徴候としてひとまずまとめています(あくまでも実感ベースで実証的なものではありませんが)。それを簡単に紹介したいと思いますが、だいたい時系列順で、徴候1「自然のような建築」、徴候2「みんな」、徴候3「反ステートメント、反ヴィジョン」です。

- 市川紘司氏
徴候1の「自然のような建築」は、特にゼロ年代の日本建築に多く見られた、人工的に構築される建築物を自然環境のような状況にしようとする試みのことです。構築的・計画的であるよりは生成的、リジッドであるよりはフロー、あるいは身体的であることや空間と人がインタラクティブであることへの志向は、「森のような」とか「洞窟のような」とか、そういう「◯◯のような」という自然物をメタファーに建築を考える態度としてよく見られたと思います。建築家の固有名を挙げれば、伊東豊雄さんを代表として、妹島和世さん、石上純也さん、藤本壮介さんなどでしょうか。
徴候2は「みんな」です。これは2011年の東日本大震災以降、日本の現代建築に顕著に現れている、いわゆる社会性なるものへの関心の高まりです。建築の内在的な原理への注目からその外側にある諸種の建築的与条件への注目、自律的なものから他律的なものへと言ってもよいかと思います。MoMAが建築のソーシャル・プラクティスをまとめた「Small Scale, Big Change」展を2010年末に開催するなど、これは世界的な傾向とも言えますね。ここでも伊東豊雄さんがその担い手として挙げられますが、震災後に始めた〈みんなの家〉はご自身でも「転向」と当時言われていたように(『あの日からの建築』[集英社、2012])、それは徴候1との対比からしばしば捉えられています。ただ一方で、社会という人間にとっての「第二の自然」を目指し、あるいはそこから建築を発想しようという態度は、まったく別の意味ではありますが「自然」的であろうとする徴候1との連続性から捉えられなくもない。あと具体的には、コミュニティデザイナーの山崎亮さんの活躍や、それへの関心が非常に高まったことなども挙げられます。
徴候3は、1980年代生まれの今の最若手と言うべき建築家に最近見られる態度で、「反ステートメント、反ヴィジョン」です。個別具体の仕事(プラクティス)を統合する大きな仮説的な枠組みを設定すること──例えばステートメントを発したり、ヴィジョンを掲げたりすること──への拒否感があるように思います。例えば、403architecture[dajiba]という若手建築家ユニットは、連さんたちとのトークイベントのなかで「素朴に実践を繰り返すことでしか、やはりなにも見えてこない」(橋本健史)と明言して、建築家がヴィジョンを掲げることへの違和感を表明していますね★2。あるいは、僕も編集委員として参加している日本建築学会の『建築雑誌』2018年8月号の特集「1981年生まれ世代の建築家像」でも、近年活躍している若手建築家たちが、一般化やステートメントに回収されない個別具体性に留まることを主張しています。要するに、等身大で一人ひとりに寄り添うことや日常的なリアリズムを重視し、それらをメタレベルの一般的・抽象的な問題で括ることは不自然ではないかという態度が通底しているように思います。
連──今の市川さんの挙げられた3つの視点は肌感覚として共感・共有できるものです。それに重ねて、私が建築を学び始めた学生時代に国内の建築について対して感じていたことをまずは率直にお話したいと思います。ちなみにその前提として、私が建築に興味をもったのは、あくまで社会変革の手段としてであることをお伝えしておきます。社会を変えることへの関心から、建築家という職能や建築という知識体系に興味をもち、学び始めました。

- 連勇太朗氏
私が大学に入学したのは2006年です。その当時の建築家の仕事に対しては、つねに憧れと違和感のあいだを行き来するアンビバレンツな気持ちを抱いていたように思います。具体的に言えば、アトリエ・ワンやみかんぐみによる、都市を批評的に、アイロニカルに観察する態度や、そうした観察を踏まえてロジカルに建築をつくる手つきはおもしろいと思っていました。ただ、設計しているのは住宅単体であり、その批評性が美術カタログや書籍のなかで閉じていることに歯がゆさを感じた記憶があります。みかんぐみは、『団地再生計画/みかんぐみのリノベーションカタログ』(INAX出版、2001)というアイデアブックをつくっていますが、本のなかだけに留まっている、もしくは建築の領域内での言説で終わっているという印象を受けました(2019年の今、さまざまなかたちでそのエッセンスが実現されている状況を見ると、それはそれで社会変革のあり方として興味深いですが)。共通して、建築家的な批評眼による観察は興味深いけれど、持ち家制度といった根本的な問題に触れることがないので、何かを変えるというよりはゲーム的だという印象をもってしまいました。
また、私がいた慶應義塾大学SFCでは坂茂さんが教えていましたが、その存在感は大きかったです。坂さんが災害支援活動を始められたのは1994年のルワンダでの内戦における難民支援がきっかけのようですが、1995年の阪神・淡路大震災以降断続的に活動が続けられています。坂さんは被災地のボランティアについてさまざまなインタビューで、「建築家は富裕層のために仕事をしていて、そのことに問題意識を感じているから慈善として災害ボランティアをやっている」という趣旨の発言をされています。ここに強烈な違和感をもったわけです。そもそも社会と建築家の構造的な関係は未修復のまま、有事のときだけボランタリズムによって貢献するという態度はどうなのかと。それで社会に建築家が貢献したと言えるのでしょうか。同級生らが研究室でボランティアに行っているのを見て、その教育的効果は十分に理解できますが、研究室がなければ持続しないし、坂さん自身の発言から明らかなように、社会の構造的問題には未着手なわけです。当然、キリスト教圏的チャリティの精神と行動力は尊重されなければいけませんが。
最後にもうひとつ。学生コンペ、アイデアコンペなどが全盛で、それによって実際に有名になる学生が出てきたりと、コンペの前景化があったのではないかと思います。そのプレゼンテーションボードは限りなく薄く白く、ヒョロヒョロとした人間の添景があるというスタイルが流行していて、そのリアリティのなさに戸惑いました。
こうした3つの状況は私にとって建築を学ぶうえでのある種のフラストレーションでした。
市川──アトリエ・ワンについては、僕もある論文コンペへの応募論文のなかで、都市的規模の語りをしながら結局は住宅しか設計しないのはズルい、というようなことを書いたことがあり、連さんと同じような問題意識があったことをいま思い出しました★3。2003年から「せんだいデザインリーグ卒業設計日本一決定戦」が始まっていますが、ゼロ年代の日本の建築界では、若手建築家よりもさらに若い建築学生の作品がメディアに取り上げられる機会が多かったように思います。学生コンペの前景化ということで言うと、大学院生時代に研究室の仲間とつくっていた同人誌のなかで特集をしたことがあります。アイデアコンペは具体的な敷地がなく、ある種一発ネタが重視されるので、「A1のプレゼンテーションボード」に特化した表現が出てきました。それは現実の建築に結びつくのか疑わしいプレゼンテーションボードという「敷地」のなかに自閉した表現と言えると思います。そうした傾向に連さんは苛立っていたのだと思いますが、僕たちはむしろ新しい建築表現としておもしろがっていたようなところがありました。これは東北大学五十嵐太郎研究室にいたことも大きいかもしれませんが。
連──ゼロ年代は、建築においてもいわゆる「セカイ系」なるタームで説明可能な表現が数多く見られたと思います。建築家というものが、制度的な存在として位置付けられているにもかかわらず、社会を支える中間項を抜いて、個人の価値観、施主のライフスタイル、あるいは敷地のコンテクストを直接的に建築的表現や世界観の構築に結びつけるというアプローチは、先ほど挙げたアイデアコンペや卒業設計にも頻出していたと思います。「自然のような」という徴候もまさに、自然のメカニズムや環境問題などの理屈を抜いて、自然をメタファーとして扱うものです。ゼロ年代は五十嵐太郎さんをはじめ、そうした表現に評価を与えてきた面が強いと思いますし、言説空間においても少なからず「私性」と「社会性」の二項対立が議論になってしまうように、表現に価値を置くような建築のあり方が極端に肥大化した部分は少なからずあったと思います。学生も「スター」になるための方法として、そうした表現を反復演習し、マニエリスム化した部分もあったわけです。
あえて強引に話をまとめると、社会システムの話を抜いて、私の身の回りから始める建築は表現として一定の成果があったと思いますが、東日本大震災のような一連の出来事で課題が顕在化したように、それでは建築家はダメなのです。ポスト冷戦時代の建築家が、社会において何を成し遂げたか、何が限界だったのかは、今冷静に振り返って再考したい。
八束──「中間項を抜く」という総括はとてもおもしろい。東浩紀さんはそうした「セカイ系」の話をもっとうまく説明できるかもしれませんが。僕は若い人たちに社会的想像力が欠けているという印象がありましたが、東日本大震災のときにあれだけ多くのボランティアが出たので違っていたかと思った反面、どうも違和感もあって、それは中間項が抜けたコミットの仕方だと説明すれば納得がいくところがあります。僕的には、中間項は抽象化と言い換えてもいい。
市川──おもしろいですね。「転向」を言う伊東さんの振る舞いが象徴的ですが、東日本大震災を挟んでゼロ年代と2010年代の建築はしばしば対比的に語られがちですが、「中間項の不在」という点では同じだと。個人的には震災前後のカルチャーを断絶させずにアップデートしようとしている建築家として平田晃久さんに注目しています。よく知られるように、平田さんはゼロ年代から「襞」を構成原理とするような建築を試みています。ただし、原理を追求して「原理主義」的になると自閉してしまいますが、彼の場合は近年では市民ワークショップなどで市民や学芸員などの意見を巻き込んでいこうとしています。あくまでも原理を追求する態度を保持しながら、しかし不純物やノイズを積極的に投入しようとしているように見える。
連──平田さんの建築的想像力が、ワークショップや新しいビジネスと結びついて新たに展開し始めている状況は、私も個人的な嗜好としては関心があります。ただ、それはやはり表現の水準なので、どうしてもある種のコンフォーミズム(順応主義)に陥ってしまいます。「襞のような」形態は、建築論や形態論としては語ることができるし、それはおもしろいことだと思いますが、大局的に見れば、そうした形態は資本主義の大好物ですから。建築家の主体性を考えた場合に、「どうやって仕事をしていくのか」というスタンス表明、あるいは能動的に立ち振る舞うための活動モデルはますますクリティカルな問題になりつつあるのではないでしょうか。1999年にレム・コールハースらがAMOを設立するわけですが、レムはそうした問題を先回りして捉えていたのだと思います。単なるリサーチエンジンではなく、そこでは世界における建築家の主体性が問われているわけですから。
八束──確かに平成的なリアリズムには、たとえ善意に介在されているにせよ、コンフォーミズムの匂いがしますね。
市川──うーん、平田さんは中間項を開発しようという意欲があるのだと僕は思うのですが。あくまで「襞」や「からまりしろ」といった自分で開発した原理を携えた建築家として市民や社会の前に現れることで、それらと同一化・順応することを回避しようとしていると思いますし。ワークショップも段階的な方法をもって行っていて、自然メタファーをフックに共感を誘うようなワンフレーズ・ポリティクスでもないと思います。なにより、《太田市美術館・図書館》(2017)がモノとしてそれを証明できていると思うのですが。
八束──僕は昭和から平成にかけていろいろなものを見てきましたが、同じような話が繰り返されているという印象もありますね。例えば、自然というメタファーで言うと、伊東豊雄さんは《八代市立博物館・未来の森ミュージアム》(1991)の前後から「風」と言っていました。伊東さんの場合は篠原一男さんの影響から逃れるためにそうしたパラダイムに向かったというのは、ご両者とも知っている者からすれば理解できないではありません。ただ、篠原さんの「実存主義」は既存の社会や都市への抵抗の表現(ステートメント)だったのに対して、生成的で開放的なパラダイムに向かうとなると、篠原さんが立ち向かおうとした都市や社会が、いつの間にか連続性を確保すべき、肯定的な環境に転じていることになります。昭和から平成に転じていくなかで、都市はいつそうした被抑圧的なものに変化したことになるのか、僕はずっと不思議なんですよ。なんとなくずるずるとそうなったという印象しかない。それが「生成的」ということなんだ、「自然」は本来被抑圧的なもので、抑圧的なのは人為なんだと言うならば、何をかいわんやですけれどね。
で、その「風」が、「広場」や「公園」、「原っぱ」になったりしていくと、この抵抗感のなさはどんどん高まっていってしまいます。僕個人の時代への抵抗感とは逆比例して。平成は昭和より非抑圧的で開放的な時代になったのかというと、時期によって波はあるにせよ僕の生活実感ではそういうことはありません。社会でも、例えば格差社会などのいろいろな閉塞的な状況が語られ、そこから由来する秋葉原通り魔事件(2008)みたいなものが起こったりするわけでしょう。
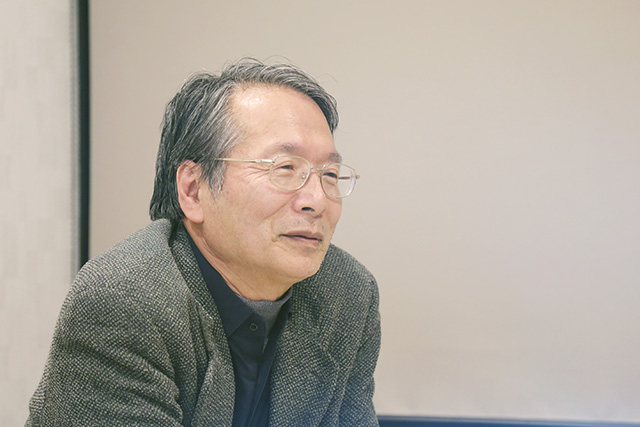
- 八束はじめ氏
「みんな」という徴候も、いわゆるトップダウンとボトムアップという二項対立の議論としてずっとあったものです。僕の学生時代にも、特権的な専門家としてプランニングやデザインをすることに対して否定的なモーメントがありました。専門に進んだのが1971年ですが、オイルショックがあり、メタボリストたちの元気がなくなった頃でした。植田実さんが編集していた『都市住宅』で紹介されていた「デザイン・サーヴェイ」もそのひとつで、啓蒙的建築家像を否定しています。
ただそうした議論は、繰り返されつつも、内容としてはだんだんつまらなくなっているように感じます。これは日本の状況に限らず、世界的にもそうで、反知性主義の流れとも関係しています。建築は知性的でなければいけないと主張する気はありませんが、「自然のような建築」「みんなの建築」といった否定神学的なものには出口がないという気がしてなりません。極論を言えば、昭和的というか、20世紀的な「構成」「構築」「計画」のパラダイムとそこは同じではないか、カジュアルな顔をしているだけなのではないかと。
市川──挙げた徴候に対して「否定神学的」と僕が言ったのは学会イベントでしたね。これも東浩紀さんの概念を借りたものです。建築はどこまでいっても人工物でしかありません。また、建築家が設計に参加している以上その主体性は取り除けない。にもかかわらず、徴候1と徴候2はそれらを否定して「自然」なんだ、「みんな」なんだと主張しているわけですね。それによって「平成建築」は確かに推進されたと僕は一方では思うけれど、具体的な方法論がなければ、計画・構築される人工物としての建築、「非みんな」としての(つまり「作家」としての)建築家が逆に強化されて温存されるだけではないか、ということでした。その意味では問題の枠組みは、昭和的なままなのかもしれません。特に「みんな」については、戦後すぐの「民衆論争」など、建築家が社会のリアリズムに向かうときに登場する非専門家(人民、民衆、市民......)の名指し方の一バリエーションにすぎないと思います。建築家は特権的・専門的な立場から降りてきてそれらのなかに分け入らなければならない、みたいな二項対立の設定は戦後日本建築史にずっとあるわけですが、その設定自体によって建築家を逆に神秘化してしまってきたのではないか。であれば、思考形式そのものを変えるか、両者をつなぐための具体的な方法論があるべきなのだと思います。例えば、長谷川新さんの論考でも触れられている兵庫県立美術館の「ヒーロー&ピーポー」展はこの点で面白かった。昭和と平成における政治的・社会的関心の強いアートやデザインなどをテーマ別に展示する展覧会ですが、「特別な人」(ヒーロー)と「無名の人々」(ピーポー)が絶対的に分割されるものというよりは、むしろ時代や場面や衣装によってその境界を大きく変化させうるものとして提示しており示唆的でした。建築家は、社会の外側からその社会を批評したり変革したりするエリート=ヒーローでもなければ、その社会の内側にいるみんな=ピーポーでもない。従来の二分法にとらわれないそういう建築家像は、実際のところすでに多くの建築家たちのあいだで認識されつつあると思うのですが、そのような建築家の専門家としての立ち位置を考え直すよい空間だったと思います。
★1──「建築学生サミット 2018 秋──平成の建築を考える」(建築会館ホール、2017.10.28)
★2──「都市を変える? 都市でつくる?──403architecture [dajiba]『建築で思考し、都市でつくる/Feedback』×モクチン企画『モクチンメソッド:都市を変える木賃アパート改修戦略』」「10+1 website」(2017.12)
★3──市川紘司「『2010年代=テン年代』的住居設計の在り方をめぐる小話」(第5回ダイワハウス住空間デザインコンペ優秀賞、2009)
- 「中間項」の不在と開発──1980年代生まれのふたりが見た平成
- 社会へ介入するための手法──ラピッドプロトタイピング、ビジネスモデルの刷新、ユーザーオリエンテッド、情報技術
- 建築家の職能はどこまで切り分けられるか──リアリズムとコンフォーミズム


