1960年代のロンドンの建築シーンを振り返る
──AAスクール、『Architectural Design』、セドリック・プライス
──AAスクール、『Architectural Design』、セドリック・プライス
今村創平──本日は、建築史家ロビン・ミドルトンさんをお迎えしてお話をうかがいます。今回来日されるのに際して、少人数のカジュアルな場でミドルトンさんのお話を聞こうと八束はじめさんが発案され、この機会を設けました。
まずは、ミドルトンさんの経歴です。ロビン・ミドルトンさんは、南アフリカに生まれ、ケンブリッジ大学にてヴィオレ・ル・デュクとラショナル・ゴシックの伝統について学び、博士号を取得しました。1964年から1972年にかけて『アーキテクチュラル・デザイン』誌(Architectural Design以下『AD』)のテクニカル・エディターを、ロンドンのAAスクール(Architectural School of Architecture、英国建築家協会建築学校)のジェネラル・スタディーズ(講義部門)の主任を務めています。また1972年から1987年まで、ケンブリッジ大学にて教鞭を執り、建築・美術史学科の主任を努めた後、1987年より、ニューヨーク、コロンビア大学の美術史の教授となっています。
ミドルトンさんのご専門は、18世紀と19世紀の建築であり、主著である『新古典主義建築・19世紀建築(『Neoclassical and 19th century architecture』1980)』には邦訳があり、新古典主義建築の基本書となっているために、読まれたことのある方も多いかと思います(デイヴィッド・ワトキンとの共著、『図説世界建築史』シリーズの中の2冊として、本の友社より1998年刊行)。
今回は、60年代のロンドンの目撃者として、当時のことをお話しいただくのが主旨です。ご存知の通り、当時のロンドンは、アーキグラムやセドリック・プライスがまさに活動を始めたときであり、その中心となっていたAAスクールに、ミドルトンさんはいました。また、『AD』誌は、今日まで続く、イギリスの(ひいては世界の)現代建築論をリードする雑誌であり、イギリスがきわめて熱かった時期に、ミドルトンさんはその編集に携わっていたことになります。
本日は、ミドルトンさんご自身について、『AD』、アーキグラム、そして特にセドリック・プライスについて、当時の状況の目撃者という立場から、さまざまなエピソードについて、お話しいただく予定です。『AD』の日本建築の特集は、当時のイギリスのアヴァンギャルドにどう影響を与えたのか、またセドリックのことを「セドリックになる前」からよくご存知だったというミドルトンさんに、セドリックがいかに彼の考えを展開するようにいたったかをお聞きします。では、ミドルトンさん、よろしくお願いいたします。
1──ウィットウォーターズランド大学──ぺヴスナーとの出会い
ロビン・ミドルトン(以下RM)──さて、まずは一番最初からお話しましょう。建築家になるべく教育を受けたものの歴史家になった私自身について、少々退屈な歴史をお話したいと思います。今日は多くのことを話しますし、たくさんの名前を挙げますが、皆さんはそれらをご存知かもしれないし、ご存じないかもしれません。ですが、知っているかどうかはたいした問題ではなく、それらの名前が互いに結びついて、いかにしてアイデアというものが、変形され伝えられるのか、影響はどのようなものだったかということを感じてもらえればいいのです。とりわけ、1960年代のロンドンというのは、本当にいつになくきわめて活気に溢れていた時代でした。そうしたことから、当時の情報を共有するためにも、私自身のことからはじめたいと思います。私は、1931年に南アフリカで生まれました。私は、南アフリカのウィットウォーターズランド大学で学んだのですが、そこの建築学科は、レックス・マーティンセン(Rex Distin Martienssen, 1905-1942)という人物によって、かなり早い時期に再興されていました。彼は、ギリシャの神殿建築やその他の教会などについて本を書いていました。しかし、より重要なのは、マーティンセンは若いときにパリを旅しており、そこでル・コルビュジエやフェルナン・レジェと知り合いになり、お金がなかったにもかかわらず、彼らのドローイングや絵画を購入し、それらを持ち帰って私たちのまわりに置いていたことです。彼はまた、ごく少数のヨハネスブルグの建築家たちの間に、ル・コルビュジェの作品への関心を引き起こし、ですから田舎の町にしては、建築やル・コルビュジエについてのかなり洗練された関心があったわけです。彼らが手がけた建物を目にすれば、今日でも時代遅れになっていないことがわかるでしょう。それらは、ある特定の時代の物に見えますが、実際、ル・コルビュジエ風モダニズムの良い例とも見なせるわけです。ですから、ル・コルビュジエは何かにつけ、私の中で意味があるものであり続けているのです。

- ロビン・ミドルトン氏
私が大学にいた最後の年、1951年か1952年のことですが、毎年一人海外から客員講師を呼ぶことが認められていました。実際、私たちはレックス・マーティンセンの伝統のものとで教えを受けていましたから、教えられた歴史というのは、ギリシャ建築、イタリアン建築を中心にそれ以外ものはわずかでした。われわれは皆、より幅広い歴史に飢えており、よって建築史家のニコラス・ペヴスナーを招聘することにしたのです。彼は、妻と一緒に、3ヶ月に渡って滞在しました。そして、私たちと本当にとてもよく関わってくれました。その最後の頃、私は卒業が近づいており、すでに建築の実務を始めていたのですが、ペヴスナーに「まだ若いのにお金を稼ぎ、建築を手がけるために落ち着くべきではない。まずは、ヨーロッパを見なさい、旅をすべきだ」と言われたのです。そして、私が3年間海外で過すための奨学金を払うように、大学を説得してくれたのです。そして、そのお金で、世界中のどこの大学や研究機関でも自由に行くことができることになり、私はイギリスに行きたいと伝えました。ペヴスナーは「君は、建築家になりたいのか?それとも、歴史家になりたいのか?」と聞いたので、卒業したら建築家になりたいと言うと、「それならば、コートールド・インスティチュート(ロンドン大学附属コートールド美術研究所、美術史や美術品保存で有名)ではなく、ケンブリッジ大学に行きなさい。きっとその方が良い」といわれました。
2──ケンブリッジでの出会い
そうして私はケンブリッジに行ったのですが、ペヴスナーはそこの教授であり、ですから彼は私の指導教官となりました。私は1953年にケンブリッジに到着し、それから5年間をそこで過ごしました。当時、ペヴスナーは、レイナー・バンハムの学位論文の指導をしており、つまり私たちは同じ時期にケンブリッジにいたのです。バンハムは、私にオーギュスト・ショワジーなどの情報を提供して欲しいといいました。私は、フランス19世紀を扱っていましたが、バンハムはそれほど関心を抱いていなかったからです。ですが、とても興味深いことに、その頃は決して顔を合わせなかったのです。というのも、私は植民地のスノビッシュな環境で育ち、ケンブリッジに着いたときは、さらにスノビッシュになっていたからです。仲間に対して、私は住所を浮き彫りにしたメモ用紙に手紙を書く習慣があり、私は「ペヴスナーに私たちは会うべきだと言われた」というちょっとしたメモをバンハムに渡したのです。バンハムはそれに対してかなり頭にきて、当然、わざわざ返事を書かなかったのです。後日、私たちはこのことを話題にしましたが、当時はそうだったのです。いずれにせよ、この段階では私たちは会わなかったのですが、とにかくバンハムとはペヴスナーによる関係であったわけです。また、当時、私よりも先にイギリスに来た人として、ルス・ラコフスキー(Ruth Lakofski,)がいました。AAスクールで学ぶために渡英した彼女の名前を、皆さんは聞いたことがないかと思いますが、彼女の姉が、デニス・ラコフスキー、後に皆さんがよく知るデニス・スコット・ブラウン、すなわちロバート・ヴェンチューリのパートナーとなる人です。デニスは、ルスより先にAAに来ていましたが、ルスが到着してすぐに、夫であるロバート・スコット・ブラウンと一緒にアメリカに渡りました。
AAに残ったルスは、ピーター・スミッソンの学生であったために、ピーターとアリソンのスミッソン夫妻ととても仲良くなりました。そして、私はまだケンブリッジの学校にいましたが、ルスを通じてピーターとアリソンと知り合い、友達となったのです。 私は、博士論文を書き終えると、所持品はビニールバックだけといった具合で、ルスと一緒に丸一年、イランなど中近東を旅しました。私たちは、パリからアテネ行きの航空運賃の帰りの分を持っていたのですが、それをアテネからテヘランの航空運賃に替えることができることに気づき、ベイルート、ダマスカス、バグダット、テヘラン、アンカラ、イスタンブールなどを、一年掛けて辿ったのです。当時はそうしたすごいことが可能で、私たちは小さな袋だけ持って旅をしたのです。帰国の途中パリに滞在していると、そこへピーター・スミッソンが訪ねてきて、「そろそろ働いてもいいだろう」と告げました。1961年のことです。そしてピーターは「テオが君に仕事をくれるよ」と言ったのです。
3──セントラル・スクール・オブ・アート
ピーターが言った「テオ」とは、テオ・クロスビー(Theo Crosby, 1925-1994)のことです。テオ・クロスビーもまた、ウィットウォーターズランド大学出身でした。彼は私より5歳年上で、イタリアの、ミケランジェロのラウレンツィアーナ図書館の前室でピーター・スミッソンと出会い、友達となっていました。テオはロンドンに着いたときには一文無しで、フライ・ドリュー・アンド・パートナーズで働き始めました。フライは、ル・コルビュジエのもとで働いていた建築家です。テオは、夜は、セントラル・スクール・オブ・アート(Central School of Art and Design、ロンドン中央美術工芸学校)で彫刻を習っていました。テオとピーターはすぐ近くに住んでいたため、ピーターと通じて、セントラル・スクール・オブ・アートと関係のある多くのアーティストや建築家と会うことができました。セントラル・スクール・オブ・アートは、歴史には出てきませんが、実際とても重要であり、なぜならレザビーと代ばれる人物によって設立されたからです。レザビーは、アーツ・アンド・クラフツの建築家の生き残りのうちの数少ない一人であり、建築についての思考を試み、いくつかのとても重要な本を書きました。それらは、とても控えめでありながら、本質を突くものです。とても穏当で、多くのことを語っていないように思われるかもしれませんが、きわめて特定のことを述べており、レザビーの考えは、当時のイギリスの建築文化に浸透していました。そのなかでも特に重要なのは、何か控えめで、常識的で、普通のものについてです。スミッソン夫妻は好んだ「普通さ ordinary」はレザビーに由来しており、さらには、デニスを通じて、ヴェンチューリ夫妻の「凡庸さ」もレザビーから来ているのです。レザビーの文体は、クリケットの試合やテニスの試合では誰もが白を着ているようなことを、良い建築の条件とみなすといった、魅力的なものでした。さらには、日曜の庭園でのお茶の時間に、すべてが端正で、正しく、控えめであるテーブルの周りに、皆が座っているというような。基本的に、彼は控えめという語は建築を特徴づけるのに相応しいと信じていました。こうしたことが、セントラル・スクール・オブ・アートの教育のひとつの側面であり、スミッソン夫妻は確かにそこから考えを得ていたのでした。この学校には、著名な人たちが関わっていて、エドワルド・パオロッツィや、リチャード・ハミルトンも教えていました。
4──『AD』誌の創刊とモニカ・ピジョン、テオ・クロスビー
テオは、かなり野心家であり、と同時に順応性も持ち合わせていました。例えば、彼は、ピーターとアリソンが結婚した際、新郎の付添い人を務め、彼の大き目のアパートをアリソンとピーターが越してこられるようにと提供し、代わりに彼は小さなアパートに引っ越したのでした。こうしたことは彼の実際的な側面ですが、1953年に『AD』の編集長となり、ある意味では、彼が『AD』をイギリスのみならず世界的に関心を持たれる建築雑誌としたのでした。『AD』はそれまでは、建築資材を扱うスタンダード社のカタログの付録でした。それが、スタンダード・カタログ社に大きな収入をもたらし、1930年に『Architectural Design』という名の薄い雑誌として始められたのです。それは、タウンドロー(F.E.Towndrow, 1897-1977)と彼の助手によって編集され、当時の秘書がモニカ・ピジョン(Monica Pidgeon, 1913-2009)でした。やがて、タウンドローは編集から手を引き、モニカ・ピジョンが編集長となったのです。それが何年のことだったが忘れましたが、まあたいした問題ではないでしょう。モニカは、主導権を握ることが大好きで、コントロールすることを決して諦めませんでした。彼女は、威張りちらす猛獣でした。実のところ、彼女は人の扱いにおいてはきわめて聡明であり、テオのことを彼女の雑誌を再生し重要なものにできる人物だと理解していました。彼女は、CIAMでの会議やヨーロッパのさまざまな建築の会議に出かけ、多くの人脈を持ち、多くの助言者を得、20世紀の建築の問題のあれこれをよく知っていました。とは言うものの、彼女は雑誌を刷新する人物を必要としており、テオがそれに相応しい人物だったのです。モニカはテオのことをとても気に入り、お互いにおおいに刺激し合ったのでした。テオは雑誌のグラフィックデザインをすっかり変え、表紙の大半をデザインし、特集を組みました。とは言うものの、『AD』誌は制作費が少なく、建築家が送ってくる素材の提供にすっかり頼っていました。彼らには写真家などへの支払いの余裕はなかったのです。掲載される作品の写真代は、建築家が払っていましたが、彼らは送られた写真に対し好き嫌いを言いました。時折、『AD』に是非掲載させて欲しいという寄稿があり、多少金銭的余裕が生まれましたが、それほどではありませんでした。ですが、テオは『AD』を建築雑誌として重要なものへと変え、常に中心的雑誌であった『アーキテクチュアル・レヴュー』誌と並び立つものとしました。そして、広告においても、『AD』は『アーキテクチュアル・レヴュー』と同等となったのです。
1956のホワイト・チャペル・アート・ギャラリーで開催された重要な展覧会『これが明日だ(This is Tomorrow)』の制作にかかわった際、テオはセントラル・スクール・オブ・アートの連中すべてを引き連れて作品を展示したのです。その展覧ではポップ・アートのリチャード・ハミルトンの素晴らしいコラージュ「what is it that makes todays different」が初めて公開されました。ご存知でしょうが、スミッソン夫妻はパヴィリオンを出品し、エルノ・ゴールドフィンガーもいました。テオはサウス・バンクで別の展覧会も企画しました。その展覧会のスポンサーはロンドンで最も大きな建設会社のひとつであるテイラー・ウッドロー社で、彼らは、ちょうど英国鉄道からユーストン駅の建て直しの依頼を受けているところでした。英国鉄道は、駅前の広場とそこにあるドーリック式の門のある土地を利用する可能性に興味を持っていました。彼らは鉄道のシステムとより長い列車の必要性はわかっていましたから、すべてを取り壊し、停車場を延長し、その上に建物を建てることを考えていました。しかし、ヴィクトリア協会やその他の人たちはひどく不満を表明していました。そうしたことから、彼らは必要な知識を持つ人物を求めており、また何かとても面白いものにするための斬新な建築にも興味を持っていました。彼らはテオにチームをつくるよう依頼しました。ピーター・スミッソンが私を訪ね、テオが仕事をくれると言ったのは、このことだったのです。ようやくそのときの話に戻りましたね。
5──ユーストン駅開発計画と計画の中止
私はロンドンに戻り、テオは私に仕事をくれ、彼はチームをつくりました。続いて参加したのは、ピーター・クック、デヴィッド・グリーン、マイク・ウエッブ、ウォーレン・チョーク、ロン・ヘロン、デニス・クロンプトンであり、彼らは皆かつてLCC(ロンドン県議会London County Council、のちのGLC)の建築部門で働いていたのです。彼らはちょうどサウス・バンクの建物を終えてからやってきて、60人ほどの大人数が、当初はメイフェアにあったオフィスにいました。われわれの事務所はICA(Institute of Contemporary Arts)にとても近く、毎日そこでランチを取りました。ICAがセント・ジェイムス・パークとマルの場所に移る前のことです。テオは彼ら全員と知り合いだったので、バンハムやICAでレクチャーをしている人たちとわれわれの事務所は繋がりました。最終的には、われわれはロンドンの北側であるユーストン駅の敷地に戻り、そこにある小屋で働きました。そして徐々に、自分たちが設計しているものは、ロンドンの新しい中心になると考えるようになりました。それは、当時としては破格の広さである30万平方メートルのオフィスや500室のホテルなどからなる、将来のすばらしい夢の都市であり、私は、ホテルやその他あらゆる娯楽施設や映画館といったものを担当していました。私には、チャールズ・フォーティというクライアントがおり、彼はバッキンガムパレスを含む、ロンドンのあらゆる場所へのケイタリング・サーヴィスを行なっていました。チャールズ・フォーティは、すべての計画、特にホテルを実現することに執着しており、つまり私は実際のクライアントとともにかなり一生懸命働いていたのです。仕事の多くは、オフィス空間の可能性を計画し、工事費や法規をチェックし、鉄道の技術者と打合せをすることといった、とても複雑なものでした。
しばらくすると、開発計画がそれ以上進められないことが私たちに明らかになりました。それは、テイラー・ウッドロー社は決して開発業者などではなく、建設会社であり、どのように資産を評価し展開すれば良いのかがわからなかったためです。そのため、彼らは金銭的側面を充分に検討できず、開発計画を提出できずにいました。また、1964年に労働党政府が成立し、風向きが変わったことに、彼らも気づいていました。民間の投機はほとんど許可されなくなり、ロンドンでは新たにオフィスビルを建てることが禁止されました。誰もが、そのようなことになると知っていましたが、テイラー・ウッドローは、彼らの計画している鉄道の敷地内では、許可の申請を出す必要がないため、免れることができると考えていました。ですが、そうした例外は鉄道関連の目的に限られていたのです。結果として、投機を目的とした高層ビルやホテルその他すべてが、希望通りに建てられなくなりました。幸運にもわれわれは案を提出する機会に恵まれ、王立財政委員会はそれを受理しましたが、やはり建設許可は下りませんでした。テイラー・ウッドローは、チームを解散したがらなかったために、われわれは何が起きるのかのんびりと座って待っていました。アーキグラムが、彼らの小さな冊子をつくったのはそうしたときでした。ピーター・クックと仲間たちはオフィスに座り──まあ話を急ぎましたが、アーキグラムのことはまた後で話しましょう──とにかく、そうして彼らはアーキグラム誌をつくったのであり、だから私は彼らのことを全員よく知っているのです。
6──『AD』誌に登場した日本の建築家たち
そしてついに、テイラー・ウッドローは「この仕事は断念せざるを得ない」として、われわれのチームは解散されることとなりました。テオはこのチームに参加するために、『AD』での仕事を1962年に辞めており、ケネス・フランプトンが彼を継いでテクニカル・エディターとして参加していました。しかし、この時点でケネス・フランプトンはプリンストンに行くために『AD』を辞めたがっており、そこでテオは私に、「行ってモニカを助けたらどうだい。彼女は助けを必要としているよ」と言いました。そこで、1964年の末、12月に、私はモニカをサポートし始めました。彼女は一緒に仕事をしにくい人でしたが、私は楽しんでモニカを助けていました。ケネス・フランプトンは、『AD』を離れる直前に、日本建築の特集を2回組んでいました。そのひとつは、1964年10月号で、丹下健三の東京計画などが初めて掲載され、もちろん黒川紀章や磯崎新などの素晴らしいものもありました。それらのすべての建築家の中でみんなの印象に特に強く残ったのは、磯崎新による、廃墟となった薄暗い柱と、筒状のタワーやスペースフレームがあるもの(訳注「孵化過程」)でした。それは、この号に掲載されたのです。そのすぐあとの12月号には、黒川による長文の論考で、『建築文化にも再掲載された、「The Architecture of Action」が掲載されました。
今村──その論考は、彼の本のタイトルにもなっていますね(『行動建築論─メタボリズムの美学』彰国社、1967)。
RM──そしてそのほか、菊竹清訓など多くの建築家がこの号に掲載されています。この2つの日本についての特集は、それまでの何よりも、アーキグラムを刺激しました。彼らはすっかり夢中になり、「これを見たか?見たか?」と言いながら、文字通り終日持ち歩いていました。彼らは、本当に興奮していたのです。これらの特集は、どれもギュンター・ニチュケ(Gunter Nitschke)経由でした。それらは、ギュンター・ニチュケによってすっかりまとめられていたのです。彼のことをご存知かわかりませんが、彼は京都にいて、庭園について研究していました。そもそも、ギュンター・ニチュケは日本に来る前は、スミッソン夫妻のもので働いていて、その繋がりで『AD』に迎え入れられ、『AD』は彼を頼ったのでした。私が1964年の12月に『AD』に参加した際、ギュンターによる日本特集があと3つ用意されていました。それらは、その後約1年おきに出版されます。一つ目は1965年の5月で、ギュンターによる論考「日本における第二英雄時代、野蛮な時代」(原題「Japan's second heroic age--The age of barbarism?」が掲載されています。失礼なタイトルに聞こえますが、いまとなってはそうでもなく、また意図されてのものではありません。彼は、検証すべき本当の問題はなにかと問いていたのです。これはいくぶん過去を振り返るもので、基本的に、坂倉準三、前川國男、丹下健三についてであり、若い人たちはそれほど含まれていませんでした。それから1966年3月の特集は「間」で、日本の場所の感覚についてでしたが、当時私は「間」という考えをよく理解していなかったようですが、とはいってもそれを判断する術もありませんでした。今日ここで、どなたか教えてくださるかもしれませんが、もはやどうでもいいことでしょう。とにかく、そこには黒川紀章と菊竹請訓他、重要な建築家たちが出ていました。
それから、1967年の5月にギュンターの3つ目の記事が掲載され(5つめとも言えますが、私の時代の3つ目ということです)、それには、マイク・ジェローム(Mike Jerome)という人物により前書きが附されていました。正直、今私はこのマイク・ジェロームという人物のことを思い出せないのですが、当時は知っていたはずで、というのも、それはギュンターの寄稿とは別のものだからです。それは、「メタボリズムに何が起ころうとも(原題:Whatever happened to the Metabolists?)」というタイトルでしたが、明らかに無礼であることを意図した、議論を喚起する記事でした。私は、これは未熟な記事だったと思いますが、一方では、『AD』がより軽量で使い捨ての建築へと向かっていた時期であり、編集の方向を変えていたという事実に応じていたのです。このころ、常に背後に控えていたバックミンスター・フラーが、ついに他の何よりも重要なものとして登場したのです。われわれは、日本のみならず、世界のどこのものであろうと実際の建物を掲載することに興味を失っており、特集を小さくして、マイク・ジェロームの記事を前のほうに持っていったことを覚えています。もちろん、ギュンターはひどく怒りましたが。彼は、われわれの方針に対して激怒する一方で、原稿料も当初のままではなくなるのではないかとひどく気にしていましたが、われわれは全額支払ったために、彼はその件に対しては文句を言えませんでした。ただ、彼はいくぶん動揺していたようでした。
もうひとつ、日本特集がありました。1970年の大阪万博についてです。このときは、モニカ・ピジョンがお金を得るために特別な許可を取ってくれ、私は日本に来る予定でした。ですが、家庭の事情で私はいけなくなり、マーティン・ポーリィに代わりを頼みました。マーティン・ポーリィはとても活動的なジャーナリストで、当時はAAにいました。彼はとても良い仕事をし、日本に行く考えをとても気に入り、ティム・ストリート・ポーターとジャネット・ストリート・ポーターといった、ファッショニスタとともに行きました。彼らはとてもいい時間を過ごし、マーティンはすべてを網羅し、私が思っていたことを書いてくれました。つまり、皆さんはどう評価しているかわかりませんが、彼はどれも気に入り、メインの建物とすべての空気膜構造にすごく興奮していました。そうしたバルーン構造は、当時流行となり、想像されるように、アーキグラムはそれを過剰に取り上げたのでした。表紙は、雑誌によりインパクトを加え、なぜなら私の友人であり、当時美術学校の学生であったエイドリアン・ジョージが、2つのロボットがセックスをしているドローイングを描いたからです。それは、ロンドンの人たちにはとても好評でしたが、日本でもそうだったかはわかりません。ですが、その号は、一冊まるごと日本で起きていることに捧げた、ある種の日本の建築との真剣な交わりの最後となったのでした。
7──オルタナティヴな建築へ──フラーとセドリック・プライス
先ほど言いましたように、そのとき『AD』は、他のものへと関心が移っていたのです。私は、安い素材でつくられた集合住宅のプロジェクトにおける数限りない細かなことに関心を持ち掲載していました。それらが、他の人たちに役に立ったかはわかりません。また、バックミンスター・フラーに関するさまざまな情報やトピックスが掲載され、そこにセドリック・プライスも加わったのでした。われわれはそれまで知らなかったわけではないのですが、セドリックが新しく注目を浴び始めたのです。当時、セドリックは私たちが掲載したあらゆるものに対して反対はせず、実際セドリックはそれらにとても興味を持ち、アーキグラムといった連中と同様に空気膜構造にとても興奮していました。ロボットがセックスをしている表紙を描いたエイドリアン・ジョージは、のちにセドリックが自身を空気膜構造のように膨らませている絵を描きました。その絵も表紙となり、それはいくぶん茶化したようなものでしたが、セドリックは気にいっていました。他にもタイトルを忘れましたが、空気膜構造についてのドイツの映像があり、そこから多くの情報を得ていました。また、フライ・オットーの軽量構造であるとか、そうしたものがすべて重要になり、なぜならわれわれは実際のところ建築を求めていなかったからです。
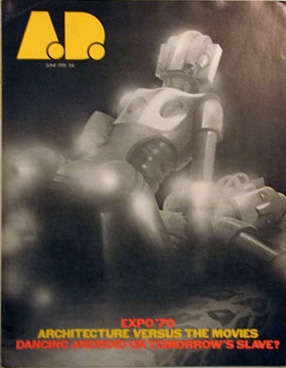
- 『Architectural Design』1970年4月号
そして1970年頃でしょうか、われわれは建築を求めておらず、建築を掲載するつもりがなく、よって広告主は、私たちの雑誌に広告を載せたがらなくなりました。われわれは経費の大半を広告により賄っていたため、広告の多くを失うと、印刷はどんどん安っぽくなりました。1970年代の中ごろには、それは、急にアングラ雑誌のようになり、イタリアの連中はとても喜んでくれました。彼らは、われわれこそ真のラディカルな雑誌だと思ってくれましたが、経営上仕方ないことだったのです。とはいうものの、実際は、われわれは経費を売り上げから賄えており、なぜならいつでも『アーキテクチュアル・レヴュー』よりも少しばかりよく売れていたからです。彼らは、より伝統的でしたが、一時期両誌は同じくらいの量の広告を載せていました。しかし、われわれの編集方針に対して、どこも広告を載せなくなり、特に英国で建設産業に携わる人々がそうでした。『AD』は、イギリスを越えた国際的な雑誌でしたが、広告主はローカルであり、そのため予算はどんどん減っていきました。そうしたことはまったく気にせず、われわれはそのまま続けていたのでした。そうした時期に、われわれはセドリックに注目したのです。彼は、最初から発想の源として影響力があり、それはアーキグラムに対しても同様でした。ご存知の通り、アーキグラムはそれほどアイデアを持っていませんでしたからね。彼らのアイデアは、バッキー(バックミンスター・フラーの愛称)やセドリックからのものであり、セドリックのアイデアのいくつかはバッキーからでした。バッキーは、父親のような存在であり、それは疑うべくもありません。バッキーは、とても魅力的な人物でした。何時間も話し続けることができ、時としてひどく退屈な話であったり、繰り返しがあったりしましたが、とにかく魅力的な人でした。
さて、セドリックについてですね。セドリックは、私より3〜4歳年下でした。彼は、ストーク・オン・トレントという街の近くの、ストーンという場所で生まれました。輸出を主とする窯業地域でした。セドリックの父親、もとは第一次世界大戦の際には海軍にいましたが、戦争が終わると海軍の大半は解散となり、RIBA(Royal Institute of British Architects)の夜間のコースで建築を学びました。父親が学位をとったかどうかわかりませんが、少なくとも建築に対して興味を持ち、知識を得たがっていたのでしょう。
しかし、セドリックにより影響を与えたのは、陶器職人であり、過激な共産主義者として窯業地域の労働者組合を組織していた彼の伯父でした。彼は発想の源として、セドリックに影響を与えました。セドリックのことを、労働者階級を背景に持つ出身だとは言えないでしょう。彼は一種の、ミドルクラスの真ん中の出身で、いい学校に行ったのです。アレンズ・スクールで学んだあと、ケンブリッジのセント・ジョン・カレッジに進み、それは私より1、2年前のことでした。
セドリックは、かなり左翼的な視点から、ケンブリッジの芸術協会を組織し始め、ケンブリッジの有名な社会学者ヘンリー・モリスが彼を少々手伝いました。ヘンリー・モリスは、エルノ・ゴールドフィンガーをケンブリッジに呼んだことがあり、私はそのレクチャーに出掛けました。そのときは、セドリックに会いませんでしたが。エルノは、プレファブ住宅のための軽量構造について話しました。イギリスの戦後の建物の多くは、プレキャストのコンクリート製であったため、とても不恰好なものでした。率直に言って、デザイン的には、かなり退屈で、かなり不細工でした。セドリックは確かに当時ケンブリッジで建築を学んでいましたが、建築学科はのちにペヴスナーやヘンリー・マーティンによって認められるようになるものの、それは後のことで、当時はそうではありませんでした。当時は、建築学科は、不動産マネージメントの学部と同等とみなされており、もし優秀ではないものの土地持ちの家族の出であれば、不動産マネージメントの学部に進んだものでした。何かを学ぶことはできましたから。しかし、建築学科は、紳士のように芸術に興味を持つ人が行くようなところでしたから、実にくだらない場所でした。ですから、セドリックがまったく気に入っていなかったことも、よく理解できることで、そこにはアイデアというものがまったくなかったのですから。コーリン・ペン(Colin Penn)という名は知らないでしょう。ほとんど名前が挙がらない人ですが、明らかにきわめて思慮深く、とても聡明で、セドリックに大きな影響を与えました。コーリン・ペンは、社会的責任といったことに関心を持っており、彼もまた共産党員でした。
セドリックがケンブリッジを離れたのは、1955年です。ケンブリッジは、3年間のコースのため、建築の学位や、RIBAの免許を取ることができませんでした。そのため、もう2年どこか他で勉強するか、もしくはケンブリッジにあと2年いることも可能でした。セドリックは、ケンブリッジには残らず、AAに行ったのです。彼は、AAにも馴染めませんでしたが、そこで、フェリックス・サミュエリ(Felix Samuely, 1902-1959)に出会ったのです。サミュエリはとても聡明であり、かつとても刺激的なエンジニアでした。彼は長年に渡り独自の方法を追及しており、少しでも興味を持つ建築家はみな、サミュエリを訪ねていました。ジェームズ・スターリングですら、サミュエリのもとに通っていたくらいです。スターリングは、構造には関心がなく、「違う、違う、俺はトラスをこう見えるようにしたいんだ。構造的に効いているかなんかどうでもいいんだよ」、などといっていたスターリングまでもがです。フェリックス・サミュエリの片腕、フランク・ニュービィ(Frank Newby, 1926-2001)のことはまた後で触れます。
当時セドリックは、ICA(The Institute of Contemporary Art、現代美術協会)での展覧会「Man Machine and Motion」という展覧会でのエルノ・ゴールドフィンガーの展示デザインを手伝っていました。ICA、いまはバッキンガム宮殿への通りであるマルに移っていますが、当時は私たちのオフィスに近かったのです。ICAでは、多くのレクチャーが企画されており、セドリックはよく出掛けていたものでした。当時、最も重要な影響力があった(ウィリアム)ロス・アッシュビィが、サイバネティックスとコミュニケーション理論について話しをしたこともありました。
さて、1956年には「This is Tomorrow」展がありました。このグループ展においても、セドリックはエルノ・ゴールドフィンガーを手伝っていました。セドリックが、ゴールドフィンガーの娘リズと付き合いだしたのがいつ頃からだったのか、おそらくこの頃でしょう。リズは家具デザイナーで、彼らは長い間一緒に住む間柄でした。エルノは、この件に関しては、曖昧な態度を取っていました。セドリックは付き合いやすい人物だったとは思えません。ですから、リズはかなり我慢をしていたと思います。
とにかく、エルノの「This is Tomorrow」での展示に取り組んでいたときに、セドリックは、フランク・ニュービィに出会ったのです。それが、ニュービィとの初めての出会いでした。先ほど話したとおり、フランク・ニュービィは、スカイロンを設計したフェリックス・サミュエリのところで働いていました。スカイロンは、1951年の英国祭の目玉だったことを知っていますか。4つ足の、筒状の彫刻のようなもので、バランスが完全に取られており、それを設計したのがフランク・ニュービィでした。彼がスカイロンを手がけたことは重要で、それはのちにセドリックと協働した際に、スカイロンで発展させた専門的知識のいくつかを使っていたからです。
1958年にAAを離れた際、セドリックの作品がどんなものだったか少しお話しましょう。それは、かなり平凡なもので、エルノ・ゴールドフィンガーの集合住宅からいくらか影響を受けていました。彼の卒業設計がどのようなものであったか知りませんが、有名な話があります。彼は、卒業設計で公共住宅を手がけ、広告や金の花輪や美しいレタリングに膨大な時間をかけていました。審査員の一人ピーター・スミッソンは「ここは、広告代理店ってところではなく、建築学校だろう」と言いって出て行ってしまいました。セドリックは、すでにあらゆることを吸収していましたが、この段階ではまだ過激なデザイナーではありませんでした。
翌年、セドリックはジョン・マッコールを通じて、バンハムとバッキーに出会ったのです。ジョン・マッコールを知らないかもしれませんが、彼はとても重要で、バッキーの評価を本当に高めたのは彼であり、バッキーに会うことができる人でした。というのも、ジョン・マッコールは長年に渡って、ロンドンでのバッキーの住所録やスケジュールを管理していたのです。そして、ジョン・マッコールとマグダ・コーレル、特にマッコールが、バンハムに『第一機械時代の理論とデザイン』に最終章としてバッキーを入れたほうがいいと説得したのです。バンハムが、ペヴスナーに学位論文として提出した際には、バッキーは含まれていませんでした。ですから、この本が1960年に出版された際には、マッコールの直接の影響があったわけであり、バッキーはそうしてこのとき本に書き加えられたのです。これが、すぐれた源泉である1959年のことであり、こうしたこれらの人々が出会ったのです。
プライスは、一時期、少しAAでも教えていました。また、ICAでも活動していました。彼は、自分の仕事を1960年に始めます。彼は、モステン・ホテル・バーという、ひどい小さなバーを手がけました。私の友人でもある、南アフリカから来たグレン・リーズという建築家が、同じホテルでデザインを手がけていましたが、それはセドリックのものと変わりなく、当時平凡な連中が手がける類ものでした。
翌年、彼はセドリックとなるのです。彼は、異なる種類のあらゆる人たちとつきあうことができました。彼は、本当に人とアイデアに強い関心を持ち、そのことについて誰とでも話しをすることができたのでした。左翼的な背景を持ちながらも、セドリックは右翼の人たちも好きでした。彼の親友の一人は、アリスター・マカルピンという、テイラー・ウッドローのライバルである、巨大な建設会社の経営者でした。セドリックとアリスター・マカルピンはすっかり気が合い、セドリックはアリスターのために建設会社の労働環境を新しくデザインし直そうとしました。マカルピンが、保守党の指導者であったように、変わった共産主義者の連中や変わった右翼の連中がセドリックの人生に入り込み、それはいつものことであり。また同じ時期にだったのです。
8──プライスとジョアン・リトルウッド──ファン・パレスへ
セドリックが、フランク・ニュービィと協働を始めたのはそのようなときでした。ロンドン動物園の鳥小屋の仕事の依頼を受けたアンソニー・アームストロング・ジョーンという人物が、セドリックに助けを求め、セドリックはフランク・ニュービィに電話をし、そうして彼らは鳥小屋を一緒に手がけたのでした。それは、セドリックの数少ない実現した建物のひとつです。このプロジェクトはうまく行き、私自身はそれほど刺激を受けませんでしたが、多くの人は面白がりました。この鳥小屋は、何か実際のものであり、完成し、ちょっとした問題を解決し、来園者を鳥たちの中に導き、その回りを鳥が飛んでいるというものでした。ずっと長くは続きませんでしたが、しばらくはうまくいっていました。鳥小屋は、しばらくたってから完成しましたが、セドリックはその前にイギリスの西バースのクラバートンにあるアメリカ博物館のために、バックミンスター・フラーのドームを建てました。その頃までに、彼はさまざまな領域の本を読んでいました。ハイゼンベルグの不確定性原理を旅行中持ち歩き、カール・ポッパー、フォン・ノイマンのゲーム理論などはみなセドリックにとってとても重要なものでした。フォン・ノイマンのゲーム理論といえば、とても面白いことに、セドリックはフランク・ニュービィから教わったのですが、ニュービィに教えたのは、チャールズ・イームズだったのです。さて、新しい人物が出てきました。
八束──イームズとは、まったく予想していなかった名前が出ましたね。
RM──そうです。一度くらいは驚かせてもいいでしょう(笑)。
フランク・ニュービィは、実際にアメリカに行った最初のイギリス人学生の一人でした。当時アメリカで起きていることに対するかなりの流行があり、アメリカはすっかり信仰の対象でした。製品に溢れた自由な社会、さまざまな仕方で明るく清潔な世界をつくり、ヨーロッパでは、みなが長いこともてなかった電機製品がありました。アメリカは新しい可能性を切り開いていたのです。フランクは、チャールズ・イームズのもとで働きました。彼は主に写真の整理をしたのですが、それでもそこにいたのです。チャールズとレイのイームズ夫妻は、とても気さくで打ち解けた人たちで、彼らのために働いたといよりも、彼らと一緒に働いたのでした。そしてイームズ夫妻は、アイデアをやり取りするのが大好きでした。
八束──ロサンゼルスでですね。
RM──そうです。フォン・ノイマンのゲーム理論はよく知られていましたが、実務家の建築家が取り上げるようになったのは、チャールズ・イームズを通してなのです。そうした時期に、セドリックは、ジョアン・リトルウッドに出会い、最初の本当に面白いプロジェクトに着手するのです。ジョアン・リトルウッドもまた、左翼の背景をもつ労働者階級の出身であり、セドリックの伯父を除いて、ここまで話題にしてきた人たちとはまったく異なる人物でした。彼女は、1914年に生まれ王立演劇学校RADA(Royal Academy of Dramatic Arts)に行き、劇場について学びました。それからパリに行き、戻ってからイワン・マッコールと出会います。イワン・マッコールは、いわゆるアジプロ劇場を始めた人物であり、それは社会主義劇場とプロパガンダが結びついたロシアではじまった考えを明らかにモデルとしていました。それらはとても重要です。彼らは結婚し、ヨーロッパを巡回し、ロシアにも行きます。戦時中はそうした活動はすべて解散させられ、男性の俳優は徴兵されていましたが、戦後になって再開され、ブレヒトの作品などを上演していました。イギリスにおける最初のブレヒトの舞台は、ブレヒトが紹介されたすぐの1933年です。戦後には「肝っ玉母さんとその子どもたち」などがロンドンで上演されています。
リトルウッドとマッコールは、ロンドンのイースト・エンドで活動を始めましたが、当時のイースト・エンドは、港湾労働者や労働者などがたむろするエリアで、彼らはそうした労働階級がいる場所でやりたかったのです。彼らは、ストラットフォード・イーストという古い劇場で活動を始めました。彼らの舞台はかなりの人気となり、誰もが地下鉄に乗って彼らの舞台へと出掛けました。なぜなら、それは本当に素晴らしいものだったからです。ジョアンは、舞台に観客が参加することを面白がりました。そうしたことは劇場のつくりからすれば難しいわけですが、彼らはとても自由な考えを持っていました。観客が、俳優たちに会って、話をすることも奨励されていました。演技をさえぎって「ねえ、そうじゃないんじゃない」ということすらできました。彼女はそうしたことを気にせず、一晩中人々が参加し楽しむことを好んでいました。ですが結局、彼女は、上演活動が大変すぎて仕事を辞め、アフリカのナイジェリアに行くことを決めます。ブレヒトのことを強調しましたが、ジョアンは当時のイギリスの俳優や脚本家も取り上げており、それらもとても良いものでした人気がありました。ジョン・オズボーンはやりませんでしたが、フランク・ノーマンは「Things Ain't What They Usedto Be(昔は良かったね)」を手がけ、それは素晴らしいものでした。シェラ・デラニー(Shelagh Delaney)の「A Taste of Honey(蜜の味)」は、若いゲイの男の子の話で、当時のイギリスの舞台では馴染みのないものでした。実際、そうしたものがウエスト・エンドでかかるようになり、ブレンダン・ビーハンの「Borstal boy」など、あらゆるものが出てきました。それらは、その次に登場するジョン・オズボーンの「Look Back in Anger(怒りを込めて振り返れ)」までは、最も面白い演劇のうちのいくつかでした。
しかし、とにかくジョアンはそうしたものを扱うことをやめ、1961年に劇場を後にしたのでした。そのほんの一年後に、彼女はナイジェリアに行きました。そして、その同じ年に、初めてセドリックに会ったのです。それは、トム・ドライバーグという下院議員の紹介でした。ドライバーグは、ケンブリッジの東の沼地に建つ、リージェンシー様式の小さなとても洒落た家に住んでいました。彼はあらゆるとっぴなことが大好きで──まあそれは重要なことではないかもしれませんが──セドリックのような人たちに興味をもって、取り上げていたのでした。彼はきわめて真っ当な紳士である一方で、エレベーター・ボーイをそそのかしていたずらをするような人物でした。このトム・ドライバーグが、ジョアン・リトルウッドにセドリックを紹介したのです。彼らはある晩、劇場の考えについて議論し、ジョアンは、観客が単に舞台を見ているだけでは本当の相互作用は発生せず、そうではないものを求めていると説明しました。ですから、それは何か劇場以上のものでしたが、彼女自身はそれがどういったものだかよくわかっていなかったのです。彼らは意見交換をはじめとても気が合い、ジョアンがアフリカにいる間は、手紙でやり取りをし、彼女が1963年に戻ったとき、セドリックは、今日ファン・パレスと呼ばれるものの最初のコンセプトを用意していたのでした。ジョアンはセドリックと相互に作用しながら働き始めたわけですが、彼らは二人とも、いわゆる建築や建築家が生み出す環境といったものを通して、人々が自分たちの生活を実際に変える可能性について興味を持っていました。彼らは、実際に建てられる形にはまったく関心がなかったのです。
プロジェクトはだんだんと本格的になり、彼らは本当に建てるつもりでした。ジョアンは、ロンドンの中心にとは望んでおらず、まずは、アイルズ・オブ・ドッグにと提案しました。そのあと、計画地はロンドンの東側の沼地リー・ヴァレーへと移されました。とはいうものの、建築法規はかなり手ごわく、構造もまた難問でした。特に、来た人たちが「これをしたい、あれをしたい、ここでこうしたい、あそこでこうしたい」というような形態的に開かれた建物の可能性の追求が基本であり、決められたプログラムというものはまったくなかったのです。そのため、この段階でゴードン・パスクが呼ばれ、というのもサイバネティックスならばそれを可能にし、この計画に必要なすべての知識が計算できるだろうと信じられていたからです。
今村──当時、ゴードン・パスクはすでにロンドンに住んでいたのですか。
RM──ええ、確かシステム・インコーポレイテッドという小さな会社を彼はすでに持っていました。こうして、ゴードン・パスクが加わり、ニュービィが加わりました。実際、鳥小屋のときと同じように、ニュービィが具体的な問題の多くを解決し、14あったタワーを7つにまとめました。彼は、耐火の問題も解決し、当時鉄の構造体を露出することはできなかったのですが、彼は、火災時に発泡して耐火性能を持つアメリカ製の塗料を見つけたのでした。こうしたこまごまとしたことをすべて解決したのは、フランク・ニュービィでした。そして、実現に向けてのすべての準備が整った時が訪れたようでした。 ですが、当時は、LCC(ロンドン県議会London County Council)の時代であり、レザビーがかつてLCCにかかわっていた際に、ロンドンの統計局をそそのかしたものがそのときまでに公開されていました。それは図表や、レザビーが手がけた住宅地計画であり、つまりレザビーが深く関係していたのです。LCCは基本的に左翼的な組織であり、もちろん政府はますます右翼化していました。戦後すぐは左翼でしたが、当時は右翼だったのです。政府は、労働党のあらゆるグループの活動を阻止しようとしており、特に一番大きな都市であるロンドン、すなわちLCCは政府に敵対するものを代表していたため、新たにGLCを設立し、あらゆるものを合併させて、労働党の支配がもはや及ばないようにしたのです。ファン・パレスの中止は、そうした再編成のあおりを受けたのです。セドリックの多くのプロジェクトは、まじめに考えられていたものの実際に建てることは想定されておらず、あくまでも計画止まりでしたが、ファン・パレスはそうではなかったのにです。
今村──実現されなかったのは、いわば許可が下りなかったためということですか。
RM──基本的に役所の都合によるものです。
今村──では、資金や技術的な問題ではなく。
RM──すべては解決済みでした。お役所や、リー・ヴァレー自然保護団体といった人たちが止めたのです。彼らは地域住民をそそのかしたりもしましたが、基本的にはお役所の問題でした。ファン・パレスは、左翼の計画だとみなされていたのです。
9──インタラクション・センター
ここでの課題は、相互作用(インタラクション)でした。もっと前の1964年にカムデンタウンのためにつくられたファン・パレスのパイロット・プランとも言えるプロジェクトがありますが、あまりきちんと取り上げられたことはありません。カムデンタウンのすぐ北にケンティッシュタウンから、セドリックは1973年にインタラクション・センターを建てるよう依頼を受けました。それは、カナダ人のエド・バウマンという人物の考えでした。彼は、ロンドンにやってきて長期間滞在し、誰もが好む様なアイデアを持っていました。彼は、まず小さな音楽テープによる月刊誌を始め、それは紙の雑誌を配布するのではなく、音や音楽など録音されたものからなり、販売するといった類のものではなく、彼のアイデアを配るようなものでした。私は、いまでもその最初のものを持っていますよ。バウマンは、ファン・パレスのアイデアを気に入り高く評価しており、1971年にセドリックにインタラクション・センターを依頼しました。インタラクション・センターは、ケンティッシュタウンに入り込んでいる鉄道線を利用し、単純な構造を用いて、キャビンなどを取り付けましたものです。いわゆるコミュニティ・センターなのですが、生涯学習を行なったり、バンドを組んだり、スタジオや食堂や保育施設などあらゆるものがありました。もし本当にうまく使われれば、まさしくセドリックが挑戦してきたものとなったでしょう。しかし建築にはまったく芸術性なく、それは意図的なものであって、彼らは芸術性といったことがないことにとても誇りを抱いていました。アートは、人々を結びつけ、何らかの方法で自分を表現することを可能とするかもしれませんが、ここでは、何らかの方法で自らを拡張し、自分が何を本当にしたいのか、何を本当にやってみたいのかが決められるのです。なにか決められた目的のために出掛けるのではありません。インタラクション・センターは何年にも渡ってうまくいっていました。想像出来るように、こうした場所は手入れがされないと汚れてきて、人々は「もっといいものが欲しい」と言い出します。セドリックも「そうだね。もっといいものがいいよね」と言ったのでした。
参加者──このプロジェクトには、何か政治的背景といったものはあったのですか。
RM──いいえ、エド・バウマンは、みなにとても慕われていました。そこは使われていない鉄道の敷地で、誰も使っておらず、何もありませんでしたが、バウマンが、組織し、運営していました。彼ははとても魅力的な面白い人物で──それと施設の成功とは関係ないかもしれませんが──成功は彼によるところが大きかったのです。考えてもみてください。何百人もの人が来て、誰かが彼らに案内をし、どう一緒にやったらいいのか、またはかかわり方について指示する必要があるわけですが、エド・バウマンは、それを何年も何年もしたのですから。彼は、1977年にここから離れました。インタラクション・センターはそのあと数年は続いていましたが、皮肉なのはアレン・パワーに関する一連の件です。アレン・パワーは、英国の建築に関するいくつかの本を書き、20世紀の社会において大きな影響力を持っており、建物や英国の遺産を救おうとしていました。彼らは、この建築的アイコンであるインタラクション・センターを、どうにか救済しようとしたのです。幸運にも、セドリック自身が建物の延命を望まず、建物は彼が亡くなる直前の2002年に解体されたのでした。
10──ポタリーズ・シンクベルト・プロジェクト
ポタリーズ・シンクベルトのプロジェクトは、1964年頃に始まりましたが、ファン・パレスが頓挫したのと同じ頃に、セドリックはポタリーズ・シンクベルトを始めたわけです。このプロジェクトはそのずっと前の1956年のクリーンエア運動というものを経ていることを考慮する必要があります。当時の冬のロンドンの「スモッグ」がどのような状況だったのかはいまでは想像もつかないでしょうが、道を歩いていると夜によってはすぐ近くの人ですら見えないような状況でした。本当ですよ。なぜならば、当時はロンドンのみならずイギリス中で石炭を燃やしていたからであり、その対策として特定された地域では石炭を焚くことが禁じられました。ポタリーズ・シンクベルトの地域では、安価な石炭に依存していました。窯業で狂ったように煙が焚かれていたのが、この時期に規制がかかり、多くの古い工場が打ち捨てられてすべては荒廃した地域と変わりました。とてつもなく整備された鉄道網と立ち枯れした木の山からなる風景──悲惨に聞こえるでしょうが──はしかし、変わった形で美しくもあり、セドリックはこの場所にとても興味を持ち、いかに活性化できるかを考えようとしたのです。私は荒廃した地域だと言いましたが、セドリックは家族を通じて現地の人たちと繋がっており、プラスチックや木や鉄のフレームでつくられたたくさんの住宅や仮設住宅ユニット、小さなカプセルのユニットからなる、学習センターを思いついたのです。
学校は、周辺のみんなによって運営されます。これは、名前を思い出せないのですが、メキシコで始められた大学と似ていると言えるでしょう。そこでは、人が集まってきて好きなものを教え、授業料は来た生徒たちによって支払われます。充分な学生がいなければ、ひとつだけ教えることになり、教師はよりつつましく暮らさなければなりませんセドリックのものはもうちょっと計画化されていたものの、自分で関わり、提供されたものに依存し、生徒を再編成する方法や彼らが将来興味を持つものは、みな選択や要望や望みによっていることとされました。そして、ひとつの教室から、他の教室へと、地下鉄のように切り替えることができ、自分の家ですら、ある地域から別の地域へと切り替えられるものでした。
※ これはとても面白いプロジェクトでしたが、明らかにすでに時代遅れのものとなっていました。コンピューターが使われ始め、充分ではないまでもその数は増え、新しいものが導入されてきました。セドリック自身も、英国政府が始めていた、オープン・ユニヴァーシティの考えに影響を受けていました。オープン・ユニヴァーシティとは、当時すでに多くの人が手にしていた家庭にあるTVを使って、家で学習ができ、レポートを提出すると、採点され戻されるというものでした。ですから、ポタリーズ・シンクベルトを葬ったのは、資金不足のためではなく、オープン・ユニヴァーシティだったのです。まあ、率直に言ってうまく行かなかったとは思いますが、ひどい失敗になったかもしれないものの、セドリックは、一本の木もない風景を再興する術を見つけ出し、何かに変えてやろうと必死だったことがわかります。
11──セドリック・プライスの人と作品、周囲の人々

- セドリック・プライス[写真=keiichi saiki]
さて、セドリック自身についてですが、彼はきわめて気さくな人で、あらゆることについて話していたものです。一方で、彼はきわめて個人的な人でもあり、それは彼の生活においても仕事においてもでした。セドリックに会うには、必ず前もって約束をしておく必要があり、ふらっと来てドアをノックしても駄目でした。言葉遣いにしても、彼は普通理解されるような話し方をせず、いつも何か不可解な意味が隠されているようでした。彼の言わんとすることを考える必要があり、あえて「どういう意味なの」と聞いても、「まあ⋯⋯⋯」などと返事をしていました。
それは一部では、彼がMITのコンピューターや官僚組織に由来する言葉を使っていたからでもあります。MITはひどい言語を生み出し、いまではアメリカ中の大学で広く用いられていますが、彼らが何を言わんとするのかを理解することは不可能であり、管理部門では彼らの目的を語るのにMITのリサーチ・プログラムの言語のようなものを用いていますが、それは理解しがたいものです。セドリックが書いた物は、組み立てられすぎており、明解ではありません。彼の基本的な意図はいつも、まったく、充分明解です。セドリックは建築が好きではなく、人々が相互にかかわり、以前自分が思っていた以上に自分を拡張できるような状況を生み出したいと思っていました。ですから、その後彼が手がけた計画は、スポーツ用の複合施設や、港湾の再建といったものでした。
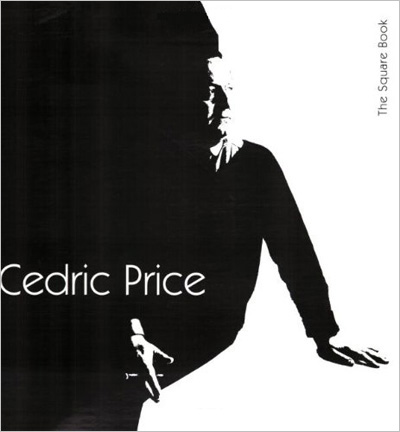
- Cedric Price, The Square Book (Architectural Monographs), Academy Press, 2003.
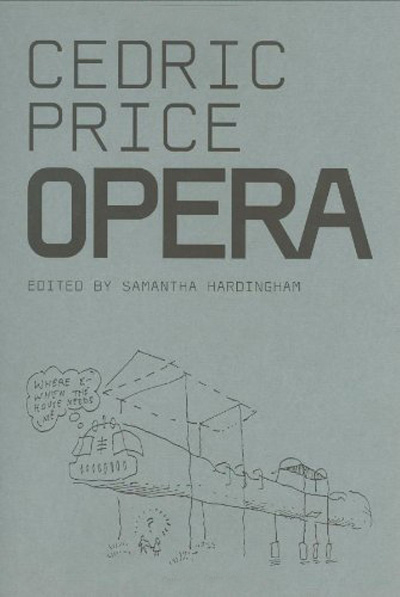
- Cedric Price, Opera (Architectural Monographs), Academy Press, 2003.
彼は運動が起き、物事が活性化されることに興味を持っていました。彼は、橋が大好きでした。セドリックは、世界中のどこの峡谷であろうとそこに橋を渡すことができ、人々はそれを使い始めるという考えが大好きでした。橋の話題だけで、ひとつの講義をすることができたほどです。
彼のすべての計画はきわめて実践的でしたが、そのどれも充分には知られていません。ドローイングはすべて残されています。彼の2冊目の作品集『OPERA』には、たくさんの計画が載っていますが、ドローイングは、1,2枚ずつです。そこから、読み取ることはできないでしょう。ですが、計画はどれも充分に練られており、そのいくつかは依頼を受けたものであり、またいくつかはコンペ案ですが、どれもがあらゆることを考慮した具体的な考えなのです。とは言うものの、毎回のこと、それらがうまく機能するためには膨大な手配が必要となります。少なくとも各プロジェクトに一人エド・バウマンが必要であり、それもエド・バウマンより、さらに明晰なエド・バウマンがです。それはグループでなくてならず、なぜなら大抵は大掛かりな計画だったからです。
最も、マジカルな提案は、ハンブルグの港湾のためのものです。ハンブルグは、第二次大戦の際にひどく爆撃を受け、いくぶんポタリーズ・シンクベルトの地域のようでした。ヨーロッパで最も重要な港のひとつでしたが、戦後は貨物船はお役御免になっており──それはオランダに移っていたために──港湾として再建する必要はありませんでした。セドリックは、コンペに招待され、それは「ドックランド」という案になりました。彼は、ハンブルグのど真ん中にある港湾を、そっくりそのまま沼地に変え、渡り鳥がやってこれるようにするというものでした。この提案は、素晴らしく詩的で、ハンブルグへの渡り鳥のために何かをし、人々が完全にいない場所をつくるというもので、他の提案よりずっと優れていました。ハンブルグの市長はこの案にとても引き付けられ、アイデアを気に入り、実現したいと考えました。しかし、残念なことに次の選挙でその市長は破れ、新しい市長は前市長が支持していたものは不要と考えていたため、実現されませんでした。
セドリックについては、たくさんの話があり、いくらでもあります。彼は、自分の似顔絵と小さな字で「全自動」と書かれた小さなボタンをもっていると話していたものでした。彼は単純なことを解決するのではなく、面倒な方法で、多くの人と関わりながら到達したいと考えていたものです。そして、スタッフが事務所で働いていた際、どの計画も終わることがなく、彼は終わらせることを毛嫌いし、いつも変更し、興味をあるものから他へと移し、それはある意味では、ひどいものでした。いくつもの実際の依頼があり、それで長年事務所を維持していましたが、ついには依頼が途絶え、事務所を諦めざるを得なくなり、そうした時期にセドリックをRIBAのカフェで見かけ、「なぜここにいるんだい。君はここをいつも毛嫌いしていたじゃないか」と言うと、セドリックは「連中のカフェを使っていれば、いつかはゴールドメダルをくれるのではないかと思って通うようになったんだよ」と言い、「ちょうど聞いたんだけれども、次に誰がゴールドメダルをもらうか知っているかい」と聞いてきました。それは、ピーター・クックでした。
今村──たいへんありがとうございました。セドリックに初めて会ったのは、ケンブリッジででしょうか。
RM──ケンブリッジでは、知り合いではありませんでした。
今村──彼との思い出について、書かれていますが、直接会ってはいなかったということですか。
RM──エルノのレクチャーのときに紹介され、一緒に夕食をともにしたことがあります。
今村──ですが、親しい友人というわけではまだなかったわけですね。それと、セドリックに会うには、予約が必要だったとのことですが、AAで気軽に会ったりはしなかったのですか。
RM──私が言ったのは、彼が後にオフィスを構えるようになってからのことで、彼が「セドリック」になってからはということです。セドリックはとても賞賛されていましたから、そういった連中が、いつも訪ねたがっていたわけです。セドリックが最も訪問を恐れていたのが、彼の兄弟でした。彼の兄弟はいつも着飾っていて、事務所に押しかけセドリックにお金をせびっていたものでした。セドリックはドアを締め切って、駄目だと言っていました。彼の事務所は、AAのすぐ裏手のアルフレッド・プレイスの4階か5階にあり、した階には二部屋があり、ですから上がっていくとすべてが白く塗られていました。上階は完璧に白くて、まるで神殿の様で、来客を入れることはめったになく、セドリックはそこで考え事をするのでした。彼は決してそうは言いませんでしたが、実際のところ瞑想といっていいでしょう。セドリックは考え事をしにそこに上がり、時として優れた会話をするために人を招きいれたのでした。
八束──日本では、セドリック・プライスとアーキグ



