建築を教えながら考える

Bernard Tschumi and Matthew Berman, INDEX Architecture, MIT Press, 2003.

Bernard Tschumi, Virtual expo 2004, Verlag der Buchhandlung Walther Konig, 2002.

モーセン・モスタファヴィ、デイヴィッド・レザボロー『時間のなかの建築』(鹿島出版会、1999)

David Leatherbarrow and Mohsen Mostafavi, Surface Architecture, MIT Press, 2002.
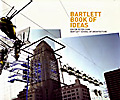
Peter Cook, Bartlett/ Book of ideas, Bartlett School of Architecture, 2000.
独立行政法人化に伴って、大学に経済競争原理が導入される。このことを巡る議論の善し悪しを論ずるには僕は役不足であるが、それでも自分の母校の前学長の相貌がどう見ても品格を欠いた商売人と思われるとき、事態は悪い方向に向かっている気がしてならない。各校の校舎も次々とオフィルビルのように建て替えられ、たまにそうした教室で建築を講義しても虚しいし、学生もそんな空間の中で建築の感動について思いを馳せろと言われても戸惑うばかりだ。それもこれも、教育の現場とまったく違う力学で、学校の運営が進められているためであろう。
20世紀には、時代を代表する建築家であるワルター・グロピウスやミース・ファン・デル・ローエは、同時に優れた教育者でもあった。今回はそうした建築教育の現役のトップによる本を取り上げてみよう。
バーナード・チュミは前回にも取り上げたが、その際言及した「マンハッタン・トランスクリプツ」のようなラディカルなプロジェクトを作っていた若手建築家が、1988年、伝統のあるコロンビア大学の建築学部のディーン(学部長)に就任したのは、ひとつの事件であった。チュミは、今年度をもってその任を降りるのであるが、約15年に渡るコロンビアでの成果をまとめたともいえる本が『INDEX Architecture』である。といっても単なる学生の作品集や論文を集めたアンソロジーというわけではなく、独特の構成でまとめるといったひねりを加えているところがチュミらしいといえようか。チュミをはじめ、スタン・アレン、アシンプトート、ジェフリー・キプニス、グレッグ・リン、ライザー・アンド・ウメモト、マーク・ウイグリーなどなどといった、この時期コロンビアに関わっていた面々の論文、新たに行われたインタヴューを、アルファベット順に並べられたキーワードで検索できるようになっている。どういったキーワードかの例として、最初の10個を書き出してみると、abstract/abstraction, aesthetics/appearanceAmerica, architectonic, architecture culture, art/artist, artifice, author, authority, autoscape となっており、これからもこの本の雰囲気がわかるかと思う。内容に関連して、学生や教師の作品の図版も多く収められているので、コンピューターの可能性を追求したコロンビア大学の90年代以降の成果というものもヴィジュアルによくわかる。
人に聞いた話で裏は取っていないのだが、チュミがコロンビア大学のディーンの座を降りることを決意したのは、来年に予定されていたパリ万博のチーフ・アーキテクトのポジションを約束されたためであり、しかしその後パリでは政権が変わって万博も中止になってしまった。結果、チュミは行き先を失ってしまったわけだが、実作の少なかったアヴァンギャルドの理論家がこれを機会に設計に専念するのも楽しみである。この幻と終わった、チュミのパリ万博の計画案をまとめた本が『Virtual expo 2004』。
AAスクールの校長、モーセン・モスタファヴィはケンブリッジ大学の大学院で、ジョセフ・リクワート、ラファエル・モネオ、アラン・コフーンに指導を受けたというアカデミックなバックグランドを持つが、当時からの友人デイヴィッド・レザボロー(ペンシルバニア大学教授)との共著が今までに2冊出版されている。1993年に出た1冊目は、槇文彦の序文とともにすでに翻訳されている『時間の中の建築』である。オリジナルのタイトル「On Weathering(風化)」の方が、この本の内容をよく表しているが、建築の完成は仕上げにではなく、その後の表面の風化にあるという視点を提示し、通常劣化と考えられている時間の経過が、反対に建築の魅力を増すことを示そうとするものである。
昨年出た2冊目『Surface Architecture』も、前著の関心を持続するもので、タイトル通り建物の表面についての本である。ただ最近多い表面のデザインのみの議論ではなく、デザインと工法の関係を追及している。トレンドともいえるテーマではあるが、2冊とも最近の流行を追っているのではなく、歴史建築から近代建築まで多くの図版を用いながら実証的に分析するものである(ちなみに、今年の2月に紹介したピーター・マークリの本も、モスタファヴィの著作である)。
チュミのコロンビア入りが事件であったように、ピーター・クックがロンドン大学バートレット校の校長となったのも事件であった。しかも、コロンビアは昔から名門であったが、世界の建築シーンでまったく無名であったバートレット校は、クック、クリスティーヌ・ホーレイの強力な指導の元、現在もっともアクティブな建築学校のひとつとなった。そのバートレット校の90年代の学生の作品をまとめたのが、クック編集による『Bartlett/ Book of Idea』である。斬新でパワフルなプロジェクトは充分刺激的であるが、コロンビアの学生に比べるとラフであり物語性を感じさせるところは、やはりクックの子供たちという感じである。クックは、グラーツの美術館が今年秋オープンを控え、クリスティーヌ・ホーレイは現在、バートレット校の新校舎の設計に取り組んでいる。また、バートレットの若手のホープ、シー・ジェイ・リムの作品集はこの連載の初回で紹介したが、現在2冊目の編集の最終段階とのことである。
[いまむら そうへい・建築家]


