Unfolding Autonomous Geometry/自律的な幾何学を開くこと──『HITOSHI ABE』書評
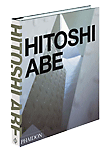
著 者:Naomi Pollock
発行日:2008年2月1日
発行元:Phaidon
版 型:290×250、ハードカバー
ISBN:978-0-7148-4665-1
→Phaidonのウェブサイト
──Abeにとって、建物の設計は幾何学からはじまる★1。
ナオミ・ポロックによるこの本は、彼女による巻頭論考と、20ばかりの阿部仁史の作品とで構成されており、作品は、Line(線)、Surface(面)、Volume(立体)と章立てられているように、造形の観点から分類されている。阿部仁史の建築には、造形のオリジナリティがすぐに見てとれるが、形態が彼の関心の上位にあり、また継続したモチーフであることは、この本の構成にも明快に示されている。
通常日本で出版される建築家の作品集であれば、たいてい建築家自身のマニフェスト的なテキスト(作品論など)があり、また作品解説も建築家自身によることが多い。しかし、この本は、阿部仁史の作品を扱っているものの、彼自身のテキストは見当たらず、テキストはすべてナオミ・ポロックによるものである。こうしたモノグラフのつくり方は、外国では珍しいことではないが、日本ではまず見られず、しかも現役の建築家を扱っているということからすると新鮮さを覚える。ポロックのテキストのなかにも、建築家の考えや言葉の引用は見られるが、それらも彼女の文章のなかに織り込まれている。これは、言い換えれば、阿部の建築なり思考が、翻訳可能であることを意味している。
話は多少それるが、日本の建築界は、いくぶんガラパゴス諸島のようなところがある。オーストラリアと言い換えてもいい。独自に進化したその生態系は、驚くべき建築を産み出している。しかし、コアラやカモノハシやカンガルーのように、外の世界からは珍しく驚嘆されても、交配することは難しい。ところが、日本とアメリカの二つのバックグランドを持つ阿部仁史は、その境界に縛られることなく自由に行き来をし、また欧米からも理解されるうる存在なのである★2。
造形の話に戻すと、阿部さんは、日本の学生であったときから、建築の形をどう決めればいいのか、煩悶していたのだという。そして、アメリカに渡った後ピーター・アイゼンマンと出会い、建築のまったく外部から造形の根拠を持ってきてもいいという彼の考えに驚いた。そのうえ、のちの師であるウルフ・プリックスは、目をつむったまま描いたスケッチを住宅の外観として採用した。つまり、建物のかたちと、機能なり、技術なり、法規なりとは切り離して考えても構わないという姿勢に巡り合ったのである。
阿部さんの建築のトポロジカルな形態は、プロジェクトごとに幾何学的ルールを持ち、それは90年代にアメリカからはじまったコンピュータを用いた立体造形の潮流とパラレルであることは明らかだ。なぜだか、このいまでは世界的な一大トレンドは日本ではほとんど顧みられていないのだが、阿部はその初期のプロジェクトから幾何学を用いた造形を一貫して試みており、それには彼のロサンゼルスでの経験があることは確かであろう。
こうした潮流に対して、先に名前を挙げたピーター・アイゼンマンは、昨今のコンピューター・モデリングによってつくられる造形を、「ネオ・アヴァンギャルド技術的決定主義」だと最近述べている★3。その発言が載せられた本のなかでは、こうした幾何学的に生成された造形は、エミール・カウフマンがルドゥーからはじまったと指摘する自律的建築をルーツに持つと議論が展開されるのであるが、確かにこうした曲面を多用した造形は一見新規には見えるものの、コンテキストやプログラムによらないという意味では、正しくヨーロッパの(近代)建築の正統な流れである自律性を持つといえる。だとすれば、さきほど、日本ではあまり試みられないと指摘したのも、そもそも日本では自律的建築の系譜というものがなく、また今日でもそれを受け入れる風土がないからだろう★4。
こうした自律的な建築の在り方は、建築をいわば英雄的にする作用があり、それは時として孤絶させてしまう欠点がある。一方で、最近の潮流は、〈流れ〉や〈スムーズな連続面〉といったことをうたうが、そこにはむしろ建築を開いていくという意思がある。
では、こうした傾向と阿部の違いはどこにあるかと考えると、阿部の強みは、こうした理論に基づいた建築を実際に多く実現している点にある。新しい試みが純粋であるほど、建ったかどうかは重要ではない、むしろ計画案のなかにこそ本質があるという議論もあるが、〈流れ〉や〈連続性〉といったテーマが、いかに現実のなかで作用するのかを見極めることの重要性は、強調してもしすぎることはない。阿部は、一昨年ロサンゼルスに渡ったが、造形的アバンギャルドのひとつの極であるかの地において、そうした思考に基づく建築を実践してきた建築家が介入することの作用というのは、今後どのような展開をもたらすのかとても興味深い。
ナオミ・ポロックによる論考は、作品論だけではなく、一種評伝のような側面も持ち合せており、阿部の設計以外のじつにさまざまな活動についても、漏らすことなく紹介している。この建築家を理解するうえでは、かれのこうしたアクティビスト(時としてはアジテーター)としての側面は欠かすことができない。たとえば、《苓北町民ホール》では、地域住民とのワークショップを通じて、建物が完成した。建物を、単なる造形的なオブジェとして捉えるのではなく、そこに人々が関わり、ダイナミックな活動を産み出すことを期待している。であるから、繰り返しとなるが、造形的に非常に先鋭化された地にこのような建築家が渡って重要なポジションを占めることによって、阿部の建築にとって、また世界の建築にとってどのような化学反応を引き起こすのか、大いに期待されるのである。
★1──Naomi Pollock, HITOSHI ABE,Phaidon, 2009, p.22.
★2──阿部さんは以前筆者に「僕は、外国でのほうがよく理解されるんだよ」と話したことがある。
★3──Anthony Vidler, Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Modernism, The MIT Press, 2008.、アイゼンマンによる前書きより。
★4──また、モダニズムの時代には、機能主義の観点から平面が重視され、立面はそれに単に白い壁かガラスを施す役割であったし、20世紀末にはやったプログラムやダイアグラムによる設計手法においても、ヴォリュームは事後的に決められる優先順位の低いものであった。なので、まずはヴォリュームの造形から始めるという態度は、まったくその逆であるし、とりわけ日本では、あまりポピュラーでない方法だといえる。
[いまむら そうへい・建築家]
1966年生まれ。建築家。アトリエ・イマム主宰。
http://www.atelierimamu.com/


