レムの原点・チュミの原点

Jeffrey Kipnis, Terence Riley, Sherri Geldin, Perfect Acts of Architecture, Museum of Modern Art, 2002.
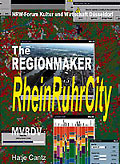
MVRDV, Daniel Dekkers, Wieland, Gouwens, The REGION MAKER Rhein Ruhr City, 2002.

Massimo Faiferri, Wiel Arets Live/Life, Logos, 2002.

Henk Doll, Jost Swarte/Mecanoo Architects: Toneelschuur Theatre Haarlem, NAI Publishers, 2003.

SeArch, SeArch, SeArch, 2003.
久しぶりにオランダに出掛けたので、今回はオランダの建築家の本を5冊紹介しようと思う。
まずは、オランダといえば昨今のオランダ建築活況を誘導したともいえるレム・コールハースであるが、ここでは彼の新作ではなく原点ともいえるプロジェクトを再見したいと思う。『Perfect Acts of Architecture』は、2001年から2002年にかけて全米各地を巡回した同タイトルの展覧会のカタログとして作られたもので、ジェフリー・キプニスのオーガナイズによるものだ。この中にレムがエリア・ゼンゲリスおよび2人の共同者とともに作成したプロジェクト《エクソダス、あるいは自発的な建築の囚人》(1972年)のドローイングがセットで収められている。話が前後するがこの展覧会は、現在世界の建築シーンをリードする建築家5人による初期の代表作のドローイングをセットで紹介しようとする意欲的なもので、レム以外には、ピーター・アイゼンマンの《ハウスVI》(1976年)、バーナード・チュミの《マンハッタン・トランスクリプツ》(1976-81年)、ダニエル・リベスキンドの《マイクロメガス》(1978年)および《チェンバー・ワークス》(1983年)、トム・メイン《6番街の住宅》(1986-87年)が収められている。それぞれ今までに、作品集等で数枚のドローイングを見たことはあっても、ほぼ完全な形で見る機会はなかなかなく、断片的な情報ではわかりにくかった各プロジェクトの構成がよくわかり興味深い。《エクソダス》にしても《マンハッタン・トランスクリプツ》にしても、そのストーリー性が重要なことがあらためて確認できる。そしてそれぞれのプロジェクトが、建築ドローイングの可能性を拡張しようとしたものであり、きわめて独創的な表現方法を獲得している。またそれぞれ初期の作品であるにもかかわらず、各建築家の思考の原点を示しているといえよう。ちなみに《エクソダス》は、『カサベラ』誌によって主催された設計競技の応募案として構想されたが、最終的にはレムのAAスクールの卒業制作となった。
『The REGION MAKER/Rhein Ruhr City』は、かつて工業地域であったドイツのRhine Ruhr地域の未来に対するMVRDVによるリサーチをまとめたものだ。今までのMVRDVによる都市プロジェクトの本は、彼ら独特のデータを操作する手法で捏造されたCGのイメージが新鮮であったが、この本では識者への6本のインタヴューやヴィニー・マースによる論文など、テキストが過半を占め、タイトルにもあるように(region maker=地方創造)、大都市ではない都市とそれを取り巻く地域の将来のあり方を調査し考察したものとなっている。もちろん、これは今号の『10+1』誌にも特集され、少しずつ関心の広がっているコンパクトシティを巡る議論に関連するものだ。またregion makerとは都市を分析しその可能性を追求するために作られた、コンピューター・ソフトの名前でもある。正直私もざっと見ただけでは、この本の意図および達成したものを理解するのに困難をおぼえているが、それはまたこの本が結論を急ぐものではなく、今まさに展開されている議論を含むものであるからではないだろうか。MVの実験と、グローバルに対応するリージョンの問題が、ライブ感を伴ってまとめられた本である。
ヴィール・アレッツの本は、このコーナーで昨年の12月にも大部の作品集を紹介したが、ここに紹介する『LIVE/LIFE』は、彼の最近の住宅、集合住宅および都市計画に集中して作られたコンパクトなものだ。先の本はすべてエレネ・ベネによる写真であることを紹介したが、この本はカヴァー写真のみ彼女のもので、中の写真はキム・ツワルツによる。まったく個性の違う写真家にそれぞれ一冊任せるというのは面白い試みだと思う。
メカノは最近あまり活動を聞いていなかったのだが、実際に事務所を訪れてみると多くのプロジェクトを抱え、非常に活気があった。代表のFrancine Houbenは、先日開催されたばかりのロッテルダムでの第一回国際建築ビエンナーレのディレクターも勤めている。彼女たちの作品集はいろいろと発行されているようだが、『Toneelschuur』は少し変わった経緯を持つプロジェクトについてまとめたキュートな本だ。というのも、このタイトルにある街に以前からあった劇場を新しく作り直すにあたって、売れっ子の漫画家Joost Swarteが絵を描き、それをメカノが実現したのである。ちょっと聞いたこともないコラボレーションによって、市民にとって親しみの持てる建物が作られたようである。
経済的にはピークを越えたといわれるオランダであるが、実際に訪れてみると、次々と新しい建築が作られているさまは圧巻であり、またそれらがみずみずしさを伴っていて気持ちがいい。すでに大御所ともいえる建築家もたくさんいるが、国際的には無名であっても興味深いプロジェクトを担当している若手建築家も多くいるようだ。そうした風通しのよい社会環境は、閉塞感の漂う日本から眺めると尚更羨ましい。SeArchもそうした若手建築家グループであり、20名ほどのスタッフで多くのプロジェクトを抱えている。その事務所名をそのままタイトルにした彼らの作品集『SeArch』は、コンパクトながら、今までのプロジェクトをまとめた自費出版によるものであることも面白い。オランダの事務所はOMAにせよMVRDVにせよ、プロジェクトごとにヴィジュアルな冊子を作ることで有名であるが、その延長として自分たちで本を作って出版してしまう。建築事務所とメデイアを巡る新しい試みといえよう。
[いまむら そうへい・建築家]


