空に浮かんだ都市──ヨナ・フリードマン

Yona Friedman, Pro Domo, ACTAR, 2006.

Yona Friedman, Hans Ulrich Obrist -The Conversation Series, Walther Konig, 2007.
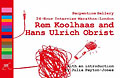
Rem Koolhaas, Hans-Ulrich Obrist, Julia Peyton-Jones, Serpentine Gallery 24-Hour Interview Marathon, Trolley, 2007.

Bartlett School of Architecture Summer Show Catalogue, Bartlett School of Architecture, UCL, 2007.
──問題はグローバリゼーションの展開が早過ぎるということなのです。人々はそうしたことを押し付けられていますが、馬鹿げたことです。ゆっくりとしたグローバリゼーションの進行には、言うなれば500年はかかるでしょう。しかし、20年でとなれば、危機が訪れるのです★1。
空中都市。簡単な模型や、ラフな手描きのスケッチ。しかし、示されているヴィジョンは明快だ。空高く持ち上げられた細いグリッド上の構造物に、間隔を置いてランダムに挟み込まれたヴォリューム。全体はところどころにある太い構造物で支えられ、地上とのアクセスを確保している。これらの宙に浮いた都市の下からの視線で描かれたパースでは、それぞれのヴォリュームは単独で浮いているかのように見え、その間には青い空が見える。あるいは、都市のモジュールは連結され連続し、それらをつなぎ支えるリング状の細い構造。あるいは、空中都市は薄いスラブ状のものが積層したもので、スラブにはいくつも大きな穴があけられており、それらはスロープでつながれている。
ヨナ・フリードマンの仕事は、こうした1958年から59年ころに作製された、「空中都市」と名づけられた、一連の模型やドローイングによって、人々に記憶されているだろう。こうした可変的であったり自由に空に浮かぶというヴィジョナリーな未来都市のイメージは、1950年代、60年代に、アーキグラムによる《インスタント・シティ》(1969)、セドリック・プライスによる《ファン・パレス》(1965)などが作られたが、これにコンスタント・ニーウウェンハイスによる《ニュー・バビロン》1963)も加えられるであろう(日本のメタボリストたちによるプロジェクト、例えば黒川紀章による「農村都市計画」(1960)、菊竹清訓の「海洋都市」(1960)も同時代の空気のもとに作られていた)。
こうした、アーキグラムやセドリック・プライス、シチュアシオニスト、メタボリズムといった、50年代、60年代のアン・ビルドの建築家たちの仕事を再評価する動きは、90年代から始まった顕著な動向として捉えることができる★2。今回は、最近まとめられた、ヨナ・フリードマンの本を紹介するが、2003年にセドリック・プライスが亡くなり、昨年黒川紀章が亡くなったという状況のなかで、まだ存命であり活動を行なっているフリードマンの最近の内容が込められた本が出ることは好ましいことだ。
ヨナ・フリードマンは、1923年生まれ。ブタペストとイスラエルにて建築を学ぶ。1956年、CIAMのドブロニクスの会議に出席し、モダニズムを批判、可動性のある社会における建築の諸原理を提示する。以降、世界各地、特に発展途上国における集住のあり方について、提案をし続ける。先に述べたように、建築界ではすでに半世紀も前のプロジェクトの製作者として有名であるが、彼の経歴およびその発言をみてみると、若くしてのCIAMでの講義からはじまって、一貫して社会のあり方に関する思考を続けてきたことがわかる。であるから、建築の実現を目的とするデザインが彼の関心ではなく、建築もしくは都市のモデルをコミュニケーションのツールとして、人々が集まって住むあり方について考えてきた。そのあたりが、一見似たようなスタンスに思える、アーキグラムやメタボリズムと一線を画するところであって、よって、未来志向の建築家にありがちな、機械的なディテールに対するフェティッシュな執着といったものはまったく見えない。
『Yona Friedman / Pro Domo』は、一昨年スペインで開催された展覧会に合わせてまとめられた本で、フリードマンの長年のプロジェクトおよびテキストが収められている。この本によって、彼の活動の全貌が明らかになるであろう。『Yona Froedman / Hans Ulrich Obrist - The Conversation Series』は、キュレーターのハンス・ウルリッヒ・オブリストによる、ヨナ・フリードマンに対する近年行なわれた7回のインタヴュー(一部公開討論を含む)をまとめたもの。フリードマンが、現役の思想家であることが彼の肉声から伝わり、またメタボリズムに対する発言などは貴重な記録でもある。
話は飛んで、下記註の中でも書いたが、ハンス・ウルリッヒ・オブリストは近年レム・コールハースとたびたび行動をともにしているようだが、2006年、レムがロンドンのサーペンタイン・ギャラリーの夏のパヴィリオンを手がけた際にふたりが企画したのが、24時間インタヴュー・マラソンである。建築界からは、ディッド・アジャイ、ザハ・ハディッド、ピーター・クック、チャールズ・ジェンクス、そのほかにもブライアン・イーノ、デミアン・ハースト、ギルバート&ジョージ、リチャード・ハミルトンなど、60名近くの文化的著名人が参加するという豪華なもの。やはり今のロンドンには、勢いがあるのか★3。
毎年、取り上げている『Bartlett School of Architecture Summer Show Catalogue』であるが、年を経るにつれて厚さをまし、また輸入されてもすぐにさばけてしまうようで、好調を維持しているようだ。誌面が増えた分だけ、さらにパワフルな印象を受けるが、毎年誉めている分今年は敢えて疑問を呈そう。ここの掲載されている学生の作品の表現の密度には感嘆すべきものがある。しかし、このショッキングともいえるプレゼンテーションを目の当たりにすると、人は驚いたのち思考を停止してしまうのではないか。この作品が産み出されるは背景には、念入りなリサーチと膨大なスタディがあることは想像できるのだが、それを誌面から読み取ることは困難だ。であるから、彼らのマニアックな傾向のみが強調され、結果、コミュニケーションされることもなく、趣味の問題として済まされてしまう。それはまずいのではないだろうか。学校でのエクササイズなので、学生の能力開発のためにこのような試みが有効というのであればそれは了解できるが、外部との接点を欠いた建築が、学校外でも通用すると信じて卒業する危険性を思わずにはいられない。
★1──ヨナ・フリードマンによる2005年の発言(『Yona Froedman / Hans Ulrich Obrist - The Conversation Series』 所収)。
★2──この連載でもこれまで、セドリック・プライスやシチュアシオニストの書籍を紹介している(変化し続ける浮遊都市の構築のために│今村創平、追悼セドリック・プライス──聖なる酔っ払いの伝説|今村創平)。また、レム・コールハースは、ハンス・ウルリッヒ・オブリストとともに、ここしばらくメタボリズムのメンバーへのインタヴューを続けていると聞いているが、それが書籍化されるのはいつなのだろうか。
★3──サーペンタイン・ギャラリーのサイト=http://www.serpentinegallery.org/。architectureのコーナーにて、2006年のレムのものも含めて、これまでの夏のパヴィリオンの記録を見ることができる。ちなみに、このインタヴュー・マラソンの記録を紹介したが、この本は写真などによる当日のドキュメントという内容のもので、インタヴューそのものは収録されていないので、念のため。
[いまむら そうへい・建築家]


