アーキラボという実験
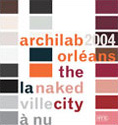
Bart Lootsma,
archilab2004 the naked city, HYX, 2004.
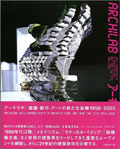
『アーキラボ 建築・都市・アートの新たな実験 1950-2005』
(平凡社、2004)

ギー・ドゥボール
『スペクタクルの社会』
(ちくま学芸文庫、2003)

Bartlett School of Architecture UCL Summer Show Catalogue,
2004.
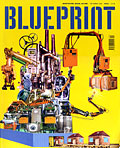
BLUEPRINT 2004 September,
2004.

山下秀之
『いろは坂、峠の茶屋と花の園、十一景』
(愛育社、 2004)
──今の時代は、既に都市環境の自己破壊の時代である。都市の爆発による「無定形に巨大化する都市残滓」(ルイス・マンフォード)に覆いつくされた農村の風景は、消費の至上命令に直接的に支配されている。
ギー・ドゥボール『スペクタルの社会』
先日森美術館で始まった「アーキラボ 建築・都市・アートの新たな実験展」は、そのスケールと内容とで、大きな話題となっている★1。この展覧会はFRAC(地域現代芸術文化振興基金)サントルのコレクションを基にしたものであり、同様のコレクション展がこれまでも世界各地で開催されてきた。一方、このアーキラボという名称は、フランスのオルレアンで開催される年に一回の特別展およびコンファレンスの名称でもある。以前、この連載でも"Archilab's Earth Building"という本を紹介したが、それは2002年のアーキラボのコンファレンスにあわせて出版されたものである★2。昨年秋には、アーキラボ2004展が開催され、そのタイトルは the naked cityであった。
森ビルでの展覧会が、ここ50年のさまざまな傾向を幅広く紹介しようといういくぶん幕の内弁当的な様相であるのに対し、オルレアンでの毎年の展覧会には明快なテーマを掲げる方針があり、昨年はオランダの建築評論家バート・ルーツマがゲスト・キュレーターとして招聘されている。ルーツマは、『スーパー・ダッチ』というオランダの現代建築を紹介する著作を2000年にものにしており、このスーパー・ダッチという言葉は、昨今のオランダ建築の傾向をよく表現するひとつのレーベルとして流通したと書くと、思いあたる方も多いかと思う。
これまでのアーキラボ展では、新しい造形的実験をしている建築を積極的に取り上げてきたが、今回はタイトルが示すとおり都市をテーマとしており、展覧会の様子もこれまでのものとはかなり雰囲気が変わっていた。そしてこの展覧会の狙いは、そのタイトル「the naked city=裸の都市」からもうかがえるように、都市そのものを新たに捕らえなおそうというものである。そもそもこのthe naked cityという用語は、ルーツマ自身も巻頭論文で述べているが、フランスの映像作家・革命思想家のギー・ドゥボールが使っていた。そして、森美術館の展覧会は、ドゥボールによる有名な図版「心理地理的なパリ・ガイド」から始められていることが示唆しているように、50年代、60年代のフランス(シチュアショニスト)、イギリス(アーキグラム)などが、そこに集められた無数のプロジェクトの端緒となっていた。そしてアーキラボ2004でも、ドゥボールがキーパーソンであり、例えばレム・コールハースの都市へのアプローチの手法が、同じくドゥボールの影響を受けているということは、かなり重要な点である。日本の建築界では、これまでドゥボールが話題になることはほとんどなかったが、今後理解が深まることを期待したい★3。
このアーキラボ2004に集められた建築家・研究者は33人(組)。MVRDV、ラウール・ブンショーテン、ペリフェリックなど、日本で多少とも知られている参加者はごくわずかである。これまでの展覧会同様、まだ世界的にはあまり知られていない建築家がほとんどであり、それはアーキラボで初めて坂茂やNOXが紹介されたときに、彼らは世界的にまったく無名であったことと同様である。ここでの都市へのアプローチはじつにさまざまである。ミューテーションズ展にも参加していたステファノ・ボエリのように、都市の状況をそのまま写し撮るドキュメンテーションを行なっているグループもあれば、EGCTのようにコンピューター解析によるきわめて論理的提案をするグループもある。
こうしたアーキラボに集められたプロジェクトに見られる実験精神というのは、本来ならば学校で育まれるべきものだろうが、実際の多くの学校というのは旧弊のプログラムと変わりばえのしない教諭陣によりまったく生産的でないという現状がある。そうしたなかで、ピーター・クックが率いるロンドン大学バートレット校はその独創的な教育で世界的名声を誇っている。そのバートレット校が、昨年度の学生作品展のカタログを発行した。これは、前々回紹介したAAスクールのプロジェクト・レヴューと同じ性格のものであるが、AAのものに比べればずっと薄いものの、全ページカラーで学生の作品を紹介している。バートレット校がすばらしい成果を上げていることは時々漏れ聞こえてきてはいても、これまではそれを確かめるすべがなかったのだが、この本を一目見れば当校と日本の建築学校とのあまりのレベルの違いに愕然とするであろう。内容においても表現力においても、どうしてこれまでの差が生まれるのか不思議に思えるほどである。ついでながら東ロンドン大学の建築学科も、今年は同様の冊子"show 04 review"を発行している。
AAスクールやバートレット校では年度の最後に学生の作品を学校全体を使って展示するエンド・オブ・イヤー・エギシビションを行ない、そのオープニングの日には有名建築家や一般の人も多く訪れお祭り騒ぎとなる。少し前だがイギリスの建築雑誌ブルー・プリントでは、昨年の9月号で学生の作品の特集を行ない、日本人の建築家、島崎威郎が上記二つの学校の展覧会についてのレヴュー'Tomorrow's Architects'を書いている。このブルー・プリント誌も昨年編集長がヴィッキー・リチャードソンという意欲的な女性に変わり、最近多少マンネリ気味であった同誌に再び活気を与えている。
日本の建築教育が停滞気味だと、部外者の私が言うのはフェアではないかもしれないが、すべての学校がだめだといっているわけではもちろんない。長岡造形大学山下研究室の学生の作品を集めた『いろは坂、峠の茶屋と花の園、十一景』は、昨年発行された『建築・微生物・地形・植生・環境』に続くものである。ここでは一貫したテーマのもとに進められたプロジェクトが、皆そろって独創的であり、プレゼンテーションがきわめて美しく、そして問題意識が明快である。ぜひ実際に手に取っていただきたい本である。ちなみに、この研究室の指導にあたっている建築家の山下秀之によるプロジェクトは、早い時期からアーキラボのコレクションとなっている。
また、昨年から行なわれている東京大学、九州大学、千葉大学とEU4カ国の大学共同による設計プロジェクトの昨年の成果が、『アウスミ・プ』という一冊にまとめられている。きわめて意欲的な試みであるが、残念ながら一般的には販売されていない。惜しいことだと思う。
★1──「アーキラボ 建築・都市・アートの新たな実験展」2005年3月13日(日)まで開催。会場は、森美術館(http://www.mori.art.museum/)。合わせて発行されたカタログは、展覧会のカタログとしてのみならず、現代建築の辞書ともいえる充実したものとなっている。
★2──その連載回はこちら(https://www.10plus1.jp/archives/2004/04/09142239.html)です。 なぜ、毎年のアーキラボのカタログを紹介しないのかというと、フランスの企画によくあることで、英語版もしくは英語併記のものが限られているためである。
FRACサントルのウェブサイト:http://www.frac-centre.asso.fr/
アーキラボ2004:http://www.archilab.org/
★3──ギー・ドゥボールの主著は、『スペクタクルの社会』(木下誠訳、ちくま学芸文庫、2003)であるが、この文庫本末尾に納められた50ページに渡る訳者解題は、ドゥボールのすぐれた手引きとしておすすめできる。1967年に書かれたこの本は、すぐさま各国語に翻訳され、68年の各地の運動に強い影響を与えた。日本語訳は遅れること93年。ヨーロッパにおいても一時期、ドゥボールおよび彼の運動であったシチュアショニストについては忘れられていたようであるが、90年前後、ロンドンのICAやパリのポンピドー・センターでシチュアショニストに関する展覧会が開かれるなど、研究・再評価が進んでいる。
[いまむら そうへい・建築家]


