戦後日本における集合住宅の風景
駒場寮の体験
現在、筆者は仙台では大学の官舎に暮らしているが、4階建てのRC造で、すでに使われなくなったダストシュートが残る、懐かしいタイプの集合住宅だ。しかも同じ形式の建物が数棟並び、いわば団地的な風景である。こうした昭和の集合住宅の思い出としては、筆者が親元を離れて最初に暮らした東京大学の駒場寮が印象深い。汚いから人の住むところではないと、高校の先輩からさんざん悪口を聞かされていたので、話のネタに見るだけのつもりで入ったら、確かに廊下はゴミ捨て場になっていたが、想像よりはマシだったため、その場で入寮を決めて、北寮29Sの部屋で2年間を過ごした(同期で浦島太郎状態となり、卒業できなくなった人もいたが)。目覚めれば、キャンパスの中だし、その気になれば、食堂、生協、ATMも構内にあるから、大学の外に出ることなく、1年を過ごすことも不可能ではない。各階の端部には共同の炊事場もある。しかも渋谷まで歩いて15分。寮費は月にわずか100円(経常費は別)。駒場寮は、関東大震災後の同潤会と近い時期に建設されたもので、1930年代半ばに竣工した頑丈なRC造の3階建てだ。これも団地的な建築だが、家族が暮らすのではなく、単身の学生のための集合住宅である。かつて一高の時代は、廊下を挟んで2部屋(数字の後に「S」がつく勉強部屋:STUDYと、「B」がつく寝る部屋:BED)をペアとして使い、フル稼働していたと聞くが、1985年当時は居住者が減り、実質的にサークル部屋やクラス部屋として占拠されているところも出現していた(当時は問題視されたが、後に廃寮の危機を迎えたとき、支持者を増やすべく積極的に奨励されていた)。今風に言えば、プライベートな集合住宅の内部に、居住専用ではない、人が集まるセミ・パブリックな空間が組み込まれていたのである。それぞれの部屋では、畳ベッドを備えた24畳の大きなワンルームを2〜3人の学生が、それぞれのルールを決めて住んでいた。例えば、内部にセルフビルドで完全な個室群をつくるクローズド、間仕切りを一切もうけないオープン、あるいは両者の中間というべきセミ・オープン。筆者が暮らしていた部屋の前には、「理論物理研究室」という古い立派な看板だけが残り、それに見合う実質的な活動はなかったが、飲み会が多い部屋、宗教系の部屋、政治活動の部屋、中島みゆきを聴く部屋(とその向かいにアンチ中島みゆきの部屋)、特定のサークルやクラスに占拠された部屋など、実にバラエティに富む。そして「総括せよ」や「グロい」など、全共闘の時代の言葉遣いが(本気ではないが)残っており、80年代の半ばとしてはアナクロな雰囲気が漂い、キャンパスの中でも時空を超えた存在となっていた。そして寮は、大学や警察が簡単に介入できない自治の場でもある。東北大学の明善寮において、禁酒を守らなかったことを理由に全員退去が求められる現代からすると、隔世の感があるだろう。
駒場寮の2年は強烈な体験だった。普通の賃貸生活ではなく、いきなり変わった暮らしをしたので、少々のことでは驚かなくなった。後に教団アレフの共同生活の場に初めて訪れたとき、ああ懐かしい空気だと感じたくらいだ。今にして思えば、駒場寮では意図せざる居住実験が行なわれていたのかもしれない。すなわち、上京して18〜20歳の男子学生に部屋を与え、話し合いによって好きなように空間をつくり、それぞれの暮らし方をさせるのだ。複数の部屋がネットワークを形成し、ここは麻雀部屋というふうに、それぞれに異なる用途を与えるケースも散見された。設計者がすべてを決めるのではなく、居住者が参加して完成させるという点では、はっきりしたスケルトン・インフィルではないが、ルシアン・クロールによるルーヴァン・カトリック大学の学生寮の試みにも近いかもしれない。おそらく、駒場寮の歴代の居住者に対し、どのように部屋を使ったかをヒアリングし、貴重なデータを収集すれば、博士論文くらいにはなるだろう。ともあれ、ハコがあって、それをどう使うかは、前提さえ変われば、いくらでも自由になりうるということを、筆者は建築を学ぶ前に刷り込まれた。
ハウジング・モデル展
2007年9月末、ウィーンで開催された世界の集合住宅の新しい動向をめぐるシンポジウム、「ハウジング・モデル」に招待された。これは展示を前提にしたワークショップであり、その翌年、討議で選ばれた集合住宅を紹介する展覧会が開催された。筆者は議論の素材として、およそ10の日本の作品を選ぶことを要請された。このときのリストは、以下の通り。妹島和世や高橋晶子による《ハイタウン北方》(1998)、山本理顕の《東雲キャナルコートCODAN》(2003)、坂本一成の《egota house》(2004)、C+Aの《スペースブロック上新庄》(1998)、ゼロ年代のメルクマール的な住宅作品となった西沢立衛の《森山邸》(2005)、岩村和夫の《世田谷区深沢環境共生住宅》(1997)、荒川修作の《三鷹天命反転住宅》(2005)などである。バランスを考え、エコロジー系やアート系なども意図的に選んだ。が、そのとき改めて思い知ったのは、日本における集合住宅の流れを説明しようとすると、やはり51C型の話まで戻らないといけなかったことだ。
- 岐阜県営住宅ハイタウン北方・妹島棟(1998)[photo:編集部]

- 岐阜県営住宅ハイタウン北方・高橋棟(1998)[photo:編集部]
すなわち、戦後の焼け野原に大量に住宅を供給すべく、日本住宅公団が1955年に設立され、標準化された集合住宅が本格的に登場したことにより、2DKの間取りが広く普及し、当時は夢の住まいとして捉えられていたこと。日本住宅公団は、ピークで年間8万4千戸、総数としては150万戸を超える住まいを供給したが、これだけの量の住まいを供給した組織は世界に例がないという。日本人が集団で暮らすというイメージを共有した戦後の風景だ。筆者が監修した埼玉県立近代美術館で開催中の「戦後日本住宅伝説」展(2014年7月5日〜8月31日)では、建築家による前衛的な個人住宅をとりあげたが、これらはあくまでも特殊解である。唯一、同展で紹介した集合住宅、黒川紀章の《中銀カプセルタワー》(1972)も、宇宙船のようなワンルームのカプセルを集積させており、ノマド的なライフスタイルを前提にしていた。ともあれ、51Cは出発点であり、模倣するにせよ、批判するにせよ、後続の集合住宅がしばしば参照する対象になっている。「ハウジング・モデル」の参加者は、畳という空間モデュールと同様、51Cの型が存在していたことに強い関心を示した。なお、《三鷹天命反転住宅》に関しては、これは「建築」なのか?という議論が白熱した。
20世紀の半ばは計画学の黄金期だった。限られた面積のなかで、合理的かつ効率的なプランを探ることが要請され、西山卯三の食寝分離論や、吉武泰水や鈴木成文の議論が、公団の51Cに結実していく。その後、nLDKという平面形式は、団地だけではなく、建売住宅やマンションにまで広がる。51Cの誕生に関わった鈴木自身はそのつもりはなかったが、表記法だけが流布し、不動産の商品としての流通システムの表記と合体してしまう。そうした背景をもとに、これらの集合住宅がつくられている。例えば、固定した戦後の家族像と結びつくnLDKシステムの解体を意識した、山本理顕の《熊本県営保田窪団地》(1991)や《東雲キャナルコートCODAN》、そして妹島や高橋の《ハイタウン北方》。これに代わる、ユニットの新しい建築的な組み合わせを模索する、小嶋一浩と坂本一成のパズル的な構成、西沢立衛、荒川修作。

- 熊本県営保田窪第一団地(1991)[photo:大野繁]
とりわけ、《森山邸》は周囲のスケール感とあう路地的な感覚をもち、同時に新しいまちの風景も生みだしている。これは巨大な開発ではなく、小規模ゆえに成立したプロジェクトだろう。居住者同士がほとんど友達関係だからこそ、居住者を集めることができ、抽象的なキューブのあいだに開放的な路地裏の風景が出現した。どこにでも通用する一般解ではないかもしれないが、ロングテール現象のごとく、ネットワーク社会の利点を生かし、似たような趣味をもつ人が数組集まれば、思い切った住み方が可能になることを示した好例だ。また2014年5月に名古屋で開催された「住まいが風景をつくる」展は、諸江一紀、studio velocity、D.I.G Architectsなど、若手建築家のプロジェクトを紹介していたが、個人住宅であってもまわりの風景に寄与することを意識している。ちなみに、土地柄なのか、親の家の敷地内に子供世帯の家をつくるケースが多かった。
ともあれ、海外の作品と比べながら、改めて戦後からの流れを眺めると、個人住宅を含む日本の集合住宅は、平面に対する強いこだわりがあることに気づく。生活像を詳細に想定し、狭い面積をいかに活用するかを追求したからだろう。オーストリア、スイス、アメリカ、セビリアなど、ほかの国の参加者から提出された平面の構成は、単純なものが多く、ファサードの操作、社会的なコミュニティの生成、増改築を主眼にしたものが目立ち、日本の建築家が展開した平面のマニエリスム的な状況が指摘できるだろう。
現代の風景をつくる集合住宅
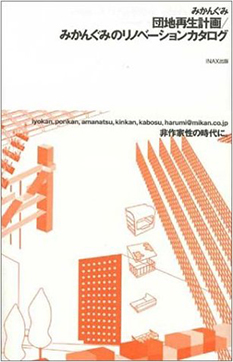
- みかんぐみ『団地再生計画/
みかんぐみのリノベーションカタログ』
(LIXIL出版、2001)
風景として集合住宅をつくる試みは、建築家も取り組んでいる。1980年代のポストモダンの動向を反映した、早川邦彦の《アトリウム》(1985)は、カラフルな舞台装置のような外部空間をもち、フィクショナルな物語性が演出した。ほかにも、SF的な実験のように思える大高正人の《坂出人工土地》(1967)、時間をかけてストリート沿いに連続的な風景を奇蹟的に形成した槇文彦の《代官山ヒルサイドテラス》(1969〜98)、形態の操作によって群の表情を豊かにした内井昭蔵の《桜台コートヴィレッジ》(1970)、敷地になじんだ低層の集合住宅を提示した現代計画研究所の《水戸六番池団地》(1976)などが挙げられるだろう。また1990年頃から、ベルリンのIBA(国際建築展)の影響も受けつつ、福岡の《ネクサスワールド》(1991〜92)、熊本アートポリスの一連の団地、《シーサイドももち》、岐阜の《ハイタウン北方》(1998-2000)、千葉の《幕張ベイタウン》、《東雲キャナルコート》のように、複数の建築家による集合住宅の競演という企画型のプロジェクトが登場し、独特の景観をもたらした。これらには独立行政法人都市再生機構(UR)が関わるものもあり、新しいライフスタイルを積極的に提案している。

- 坂出人工土地(1967)[photo:森翔太]
解体後、URの集合住宅歴史館に移築された前川國男による《晴海高層アパート》(1958)は、プランだけではなく、ル・コルビュジエの《ユニテ・ダビタシオン》のように立体的な構成のレベルにも踏み込み、(10階建ての高層の集住形式を提案した。考えてみると、そもそも日本人が、4、5階建て以上の建物に住むようになったのは、基本的には戦後からのことであり、せいぜい半世紀くらいしか歴史がない。近代以前は2階がなく、ほとんど平屋だった。ヨーロッパであれば、古代ローマの時代から6、7層の集合住宅インスラがポンペイの遺跡で認められるように、中層の集合住宅は文化的な遺伝子として組み込まれている。したがって、戦後の団地や高層アパートは、日本の歴史において高さの点から見ると、中層以上の建物に住む人の風景をもたらした画期的な事件だった。しかし、今や規制緩和によって、40、50階建てのタワーマンションがあちこちの駅前に増殖する時代を迎えている。ヨーロッパのスケール感を簡単に超える、驚くべき大変化だ。以前、東浩紀氏との対談において、建築界はなぜタワーマンションを話題にしないのかと質問されたが、なるほど不動産の論理が優先され、アトリエ系の建築家の出番はない。公共の集合住宅のような実験も起きにくい。にもかかわらず、明らかにこれは21世紀に出現した新しい集合住宅の風景である。今後、継続して考えていくべき課題だろう。

- 紀元2世紀初期のインスラ ©Nashvilleneighbor

- SHARE yaraicyo(2012)[撮影:平野太呂]

- 城西LT(2013)
撮影:西川公朗
五十嵐太郎(いがらし・たろう)
1967年生まれ。東北大学教授。建築史、建築批評。著書=『終わりの建築/始まりの建築』『新宗教と巨大建築』『戦争と建築』『過防備都市』『現代建築のパースペクティブ』『建築と音楽』『建築と植物』など。http://www.cybermetric.org/50/50_twisted_column.html


