流動する社会と「シェア」志向の諸相

- 宮台真司氏(左)、門脇耕三氏
「シェア」の概念──「純粋公共財」と「クラブ財」

- 『私たちが住みたい都市』
(山本理顕編、平凡社、2006)
いま「シェア」をめぐるさまざまな動きが注目され、建築を学んでいる学生にも「シェア」は非常に注目されています。卒業設計のテーマとしてシェアハウスやフラットシェアを選ぶ学生も多くいます。ただ建築系の学生の場合、どうしても文献的な掘り下げが追いつかず、「近代家族」という概念すら知らないまま「シェア」について語っていたりする状況があります。そこで今回は、第一に「シェア」の思想史的・社会史的な位置づけを明らかにしたい。
近代家族などの社会的・制度的な形式と空間の関係については、宮台さんも登場されている『私たちが住みたい都市』(山本理顕編、平凡社)でも、さまざまな分野の優れた議論が紹介されていますが、このなかで宮台さんは、空間創造にまつわる建築家の役割はもはや限定されていると断じ、また社会の見通しについても悲観的な書き方で結んでおられます。一方で、この本が出版されたのは2006年で、このときからすでに8年という長い時間が経っていますので、その先の宮台さんの思想についても伺いたいと思っています。
まずは議論の入り口として、「シェアハウス」や「コワーキング・スペース」などの「空間のシェア」、ネットで行なわれている二次創作などの原作改変型の創作に見られる「クリエイティヴィティのシェア」、あるいはカーシェアリングなどの「モノのシェア」などについて具体的にお話しいただき、「シェア」というやや漠然とした概念を明確にしたいと思います。
宮台真司──経済学のなかには公共財をめぐる議論があります。公共財というのはみんなでシェアする財のことです。「純粋な公共財」というときには、非排除性と非競合性──つまり誰でも使えて、誰のものも減らないこと──が前提になります。空気や花火見物などはそういう例ですね。誰かが花火を観たとしても、自分の観る分が減るということはないですから。
でも、実際に存在する公共財には、純粋なものは少ない。よくあるのが例えば「クラブ財」です。これは会員制になっていて、メンバーオンリーという意味で排除的ですが、クラブのメンバーが増えても会員の利益は減らないか、win-winの共栄的な帰結になります。一般に、僕たちが何かをシェアするという場合、だいたいが「クラブ財」です。
それとは別に、道路や橋といったインフラや、美術館のようなハコモノは、公共施設ですから誰でも使えて非排除的ですが、展覧会が混雑すると絵を鑑賞しにくくなる、橋が混むと渡れなくなる、といった事態が起こりがちです。公共施設は一般にそうした競合的な性質を帯びます。そういった財は「コモンプール財」と呼ばれます。
先の「クラブ財」ですが、会員になるために入会料を支払う場合、有料放送やペイ・パー・ヴューのように、会員が増えれば一人当たりの支払いが減ることもある。オフィスシェアの背景には、各人の支払いを下げるという動機があるし、カーシェアも、私的所有の「こだわり」を捨てるかわりに、維持管理コストを減らしたいという動機があります。
ここからが本題です。「◯◯シェア」や「シェア◯◯」と呼ばれるものは、一人当たりのコスト減を狙う「クラブ財」です。ここ10年で注目に値したのは、古くからあるルームシェアの延長線上に、シェア範囲や相互扶助範囲が更に広いシェアハウスが拡がったこと。僕は「典型家族」ならぬ「変形家族」の展開可能性を感じ、希望を抱いた時期があります。
でも、あまりうまくいっていません。僕のゼミには黎明期の「ギークハウス」★1の人たちや「渋家(シブハウス)」★2の人たちが来ていました。「渋家」の場合、創立メンバーが軒並み僕のゼミから出た経緯もあって、最初は僕も見込みがあるかもしれないと思ってコミットしたんですね。

- ギークハウス
図版提供:pha
なかなかうまくいかなかった理由として、当初、純粋な公共財に近づける方向で「来る者拒まずにしよう」「会員制にする場合も事前審査はやめて定員になるまでは申し込んだ順に入居させよう」としたところが、メンヘラ★3が来たり、他人と暮らすことが難しい性格の連中が来たり、性愛トラブルメイカーが来たり、といったことがありました。
そこで、入居者全員の利益を増進させることができる人を入居させるべきだという話になります。つまり排除性を緩和しようとする試みがうまくいかず、紹介制度やお試し期間を含めた事実上の資格審査が入るわけです。別言すれば、有料放送みたいにメンバーが増えると各人の支払いコストが下がる想定だったのが、必ずしもそうならなかった。
さらに別言すれば、会員制という意味では排除的でも、いったん会員になったらそこから先は助け合ってできるだけ非競合的にやろうという理想があったのですが、フリーライダーが来るといろんなコストが生じ、フリーライダーコストの支払いの必要から競合的事態が生じて、当初の理想に無理があったことが気づかざるをえなくなったわけです。
いまやシェアハウスは、業者がシングルマザー向けのシェアハウスを運営するとか、デベロッパーがリノベーションのコストを下げて賃貸するためにシェアハウスのかたちをとるとか、脱法ハウスを含めて業者主導のものになりつつあります。ウィキペディアを見て驚いたのですが、シェアハウスとは業者が介在するものを言うなどと書いてあるわけです。
もちろん僕が知るかぎりでも自発的なシェアハウスが残っているものの、実質的に万人に開かれたものは少なく、情報非公開で一般人にはアクセスできないものが増えています。「一定メンバーで一定の営みが持続可能であるなら公開しないほうがよい」と考えるのは、今日では合理的だと言えるでしょう。
「シェア」が目立つようになったのは5年ほど前からでしょうか。その頃の夢あふれる感じは、シェアハウスの創立に関わった人々から失われて、人の善意を信頼するだけじゃダメという認識が拡がりました。3.11震災の際、ギークハウスが帰宅困難者にスペースを提供したのを起爆剤に「シェア」の考え方が拡がればいいと思ったのですが......。
「リソースシェア」──情報的シェアと家族的シェアの関連
宮台──二次創作に関わるような情報素材の共有については、ずいぶん前からせめぎ合いが生じていると思うんです。コミケに象徴されるような二次創作市場が日本ほど大きな国はほかにありません。したがって、二次創作上の要求から一次創作に対するさまざまなニーズが生じるという現象も、日本特有のことです。そもそも著作権は、表現を生業としている者の保護が目的です。タダで享受されるとオマンマの食い上げだ、と。ところがYouTube上では、解像度の低い複製動画や、いまは誰も接する機会がない数十年前の複製動画が出回ることが、著作権者にとっての無料宣伝効果を発揮してくれるというので、著作権者が意図して放置するケースが目立ちます。
二次創作市場も、一次創作市場を侵食するより活性化している可能性があります。そこで、漫画家の赤松健さんが発案して、二次創作物の頒布を原作者が許可する「同人マーク」のライセンスが公開されました。著作者がみずからの著作物の再利用を条件付きで許可する意思表示を手軽に行なうクリエイティブ・コモンズの運動に連なる流れです。
ところが、二次創作市場が発達していない国では、コンテンツ・ユーザーの可処分時間が二次創作に奪われれば一次創作者に不利益になると意識され、著作権法の厳格な適用が要求されがちです。特にアメリカでは、著作権収入が農産物輸出収入を凌ぐ外貨収入をもたらすので、他国の二次創作市場を徹底的に潰しにかかろうとします。
今回のTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)でも、事実上日本に対し、著作権厳格化、つまり非親告罪化(親告罪の撤廃)と刑事罰化を強く要求しています。アメリカは著作権収入においてただ一国輸出超過の一人勝ち状態なので、無料でコンテンツと戯れられる余地を全て潰し、全コンテンツの利用に際しアメリカに年貢を納めさせたいわけです。
僕自身は「巨大システムへの過剰依存から、共同体自治の再構築へ」という図式で考える者です。なかでも、食の共同体自治(スローフード)、エネルギーの共同体自治(自然エネルギー)、コンテンツの共同体自治(二次創作市場)が、大切だと喧伝してきました。コンテンツは、人々が自由に創作し戯れられるプラットフォームであるべきなのです。
もともと情報は、インターネット上では誰でも見ることができますし、誰かが見ると自分が見られなくなるという事態も起こりません。そのため日本では、排除性も競合性もない「純粋公共財」に近いものとしてコンテンツが捉えられてきて、二次創作市場が形成され、それが一次創作市場をも活性化してきた歴史があります。
背景には、著作物とりわけキャラクターが、著作者の所有物というより、一人歩きして成長するものだという独特の思考があります。それはさらに、ヒトならぬモノにも魂が宿る、とする独特の伝統を背景にしています。僕はこうした文化を守りたい。こうした文化こそ、モノやカネが細っていく先行き苦しい社会での、数少ない明るい材料だからです。
門脇──「シェア」には第一に、リソースを効果的に共有しようとする目論見があるわけですが、それに加えて、シェアハウスにおいては個々人の自律的で自発的な行動がゆるやかに連帯する結果として、これまでにないかたちでコミュニティやアソシエーションが立ち上がることが夢見られた。また二次創作でも、一次創作と二次創作の無限の循環のなかから、多くの人が関わることによって創造性が発露する「集合知」的な創造が姿を現すことが期待され、事実そうなっているわけです。しかし、そのいずれもが困難に直面しているというご指摘ですね。
宮台──もともと公共財という概念やマンサー・オルソンらに代表される公共経済学★4の営みは、資源の有限性のもとで人々が共栄的に生存するために必要な条件は何かという観点から生み出されてきました。その流れで、リソースシェアは、古典的にはネガティヴィティを減らす、あるいはコストを減らす、という発想から要請されたものです。
ところが、二次創作に関わるシェアや、シェアハウスなどで見られる「変形家族」に関わるシェアの場合、コストを減らす側面はむしろ副次的だとも見なせます。二次創作に関わるシェアで言えば、グローバル化を背景とした貧困と格差が拡大するなかで、失われゆく楽しみを機能的に代替する数少ない新しい楽しみを、もたらすために要求されています。
同じく、シェアハウスに関わるシェアでいえば、社会的文脈の変化を背景として典型家族がどんどん困難になっていくなかで、家族と等価の機能を果たす血縁的ではない関係、つまり典型家族を機能的に代替する変形家族のあり方を、模索するために要求されていると見做すことができます。
そして情報に関わるシェアと家族に関わるシェアは関連し合っています。かつて典型家族のみんながお茶の間で同じ番組を観ていた時代がありました。今日では遠い過去の話になりました。2つの面でそう言えます。第一に、共住共食自体が危うくなることで、テレビ番組に限らず、典型家族のメンバーが何物かをシェアするのが、難しくなりました。
第二に、ネットは摩擦係数の低いコミュニケーションで、距離の困難、表出の困難(赤面症や手が震える等)、尊厳の困難(学校時代に大便を漏らした等)を無関連化するから、ピンポイントの趣味で仲間を見つけられます。結果、限られたクラスタ(趣味を同じくするネットユーザーの集まり)のなかで戯れるためにコンテンツが使われます。
すると、素材がひとつであっても、戯れるやり方が4種類あったら、ネットには4つのクラスタができます。こうした傾きは、最近話題の「ダイバーシティ」(性別・人種・国籍などを超えた多様性)に資するところがあります。コンテンツへの関わり方を一元化・均質化しなくてもいいので、多様な享受の仕方に開かれたものになるからです。
しかし、その分、細分化したクラスタ間のディスコミュニケーションという「島宇宙化」が生じやすくなります。みんながお茶の間で同じ番組を見てきた時代が、遠い過去の話になったという場合、「家族的シェアの困難」という先に述べた側面とは別に、家族や教室の「情報的シェアの困難」という側面も、見逃せません。
こうしたシェアの困難を、単にコストが高くつくようになったからだと考えることはできません。プラットフォームが変わったからシェアが困難になったんです。だから、コストを減らす側面とは別に、プラットフォームの変化によって不可能になったものを、埋め合わせる必要があるか、なにをもって機能的に埋め合わせるか、を考える必要があります。
門脇──リソースシェアという観点から見ると、シェアハウスも二次創作も、リソースのバランスが変わったことが、その勃興の大きな要因としてあるのではないかと思います。シェアハウスでいうと、空き家や空室の増加と世帯の小型化という背景のもと、戸建て住宅などの比較的大きな住宅が、空き家改修型のシェアハウスとして活用されていった側面があります。二次創作文化にしてもインターネットの発達と大きく関わっていて、情報の取得コストも発信コストも、いまや圧倒的に下がったことが前提としてある。リソースが量的な飽和を起こしたり、あるいはそれによってニーズとのミスマッチが生じた結果、リソースの意味を読み換え、書き換えていくユーザー側からの動きとして「シェア」は理解することができるのではないかと、いまのお話を聞いていて思いました。
宮台──そうです。「シェアハウス」と銘打たなくても、従来のルームシェアのように、一人で住むにはコストはかかるし寂しいという理由で、学生たちが居住をシェアするケースが相当増えました。よく耳にするのは、親との不和を抱える子が親元を離れる際、以前なら自立・自活したのが、何らかのシェアの輪に入って精神的安定が得られたケースです。
問題を抱えた家族といるくらいだったら、気が置けない仲間と一緒にいたいというわけです。5、6年前から聞くようになりました。「もともとニーズがあったところに、空き屋が増えたから、自然に空き屋改修型シェアが増えた」のと並行して、「もともとニーズがあったところに、シェアが目に見えて増えたから、自然にシェアの輪に入りやすくなった」んでしょう。
「近代家族」の形成と終焉

- 宮台真司氏
宮台──「近代家族」と呼ばれるものの出発点は、産業革命以降の工業化、とりわけ重工業化です。工業化のひとつの側面は、人々を土地から引きはがすことです。産業革命初期のエンクロージャー(土地囲い込み)がよく引き合いに出されますが、人々を土地から引きはがすことで、昔ながらの相互扶助的な地縁共同体が急速に解体していきます。
他方、都市に集住した人々は、職住分離、つまり工場で生産労働をし、家族で消費生活をするようになります。それに伴い、かつて地縁のなかで賄った生活上の相互扶助を、家族のなかで賄うようになります。相互扶助的な地縁共同体の空洞化を埋め合わせる機能的代替として近代家族が登場し、そのなかで家事育児を担う専業主婦の地位が確立されます。
門脇──社会分業論的には、近代化は職業が専門分化するような分業社会を発達させるわけですが、それとともに家族内での性別役割分業が起こった。近代家族における性別役割分業、すなわち男性が働きに出て、女性が家事育児を担うという構図は、「就業地としての都心」と「居住地としての郊外」という近代都市の基本構造とも一致しています。
宮台──産業革命期の使い捨て労働力を見ればわかるように、経済権力や統治権力は当初、労働力の再生産あるいはメインテナンスに配慮しませんでした。ところが資本主義社会の持続可能性が必ずしも自明ではなくなると、工場や事務所など労働現場のオフィシャル領域ならぬ、プライヴェート領域での再生産が重要にならざるをえなくなります。
労働力の再生産には2つの柱があります。ひとつは「人口学的再生産」。つまり次世代が生まれてくるようにする。もうひとつは「心身レクリエーション」。つまり明日も働けるように労働者の心身を回復させる。「人口学的再生産」も「心身レクリエーション」も、生産システムの持続に不可欠なので、経営者や政治家が関心を寄せるようになります。
そうした流れの末に、日本では1960年代の団地化や80年代のニュータウン化が生じ、それぞれの時代の家族的ニーズに合わせた集住形態が、建築や都市計画を通じて提供されるようになりました。たとえば1960年代の団地化を見ると、団地という集住形態が専ら専業主婦によるシャドウワークの存在を前提としていたことがよくわかります。
シャドウワーク概念はイヴァン・イリッチのもので、専業主婦が男性労働力を使い倒すために担うサポート機能です。根底に性別役割分業があるものの、彼によれば、女宇宙と男宇宙が比較不能なコスモロジーを構成する土俗的性別が、「男も女も同じ人間だが、女はより......で、男はより......だ」と比較可能性を軸とする近代的性別に変質しています。
彼は、土俗的性別をヴァナキュラー・ジェンダー、近代的性別をセクシズムと呼びますが、近代家族を支える性別分割分業の意識は、近代家族とともに発達したと考えるのが一般的です。たとえば日本では、団塊の世代が専業主婦割合がもっとも大きく、その上世代も下世代も小さくなります。下世代は男女雇用機会平等化だとして、上世代はなぜなのか。
お父さんもお母さんも、畑や田んぼで、あるいは海や浜辺で働いていたからです。では子どもの面倒は誰が見ていたかと言うと、爺ちゃん、婆ちゃんの果たした役割が大きかったんですね。柳田國男も強調するように、日本では隣接世代ではなく、一世代スキップして祖父母が孫の養育をし、それを地縁共同体がサポートする形が一般的でした。
出産や育児を、人口学的再生産に関わるシャドウワークなので「再生産労働」といいます。母親が再生産労働を担うのは、出産は別にして、自明でも自然でもありません。日本が近代化していくなかで、核家族化=2世代少子家族化が進んで、パパとママと子ども2人という標準型が生まれ、専業主婦役割として育児労働が要求されるようになったんです。
再生産労働において出産労働と育児労働が結びつくべき必然性はどこにもありません。子どもを産んだお母さんがそのまま育児をやるのが「自然」だろうと考えるのは、重工業化と都市化・郊外化を背景とした、近代的性別役割を支えるイデオロギーでしかありません。育児労働は、祖父母が担ってもいいし、近隣社会や乳母が担ってもいいんです。
門脇──近代の発達とともに、そういう制度設計がされたと理解してよいでしょうか。
宮台──そう。一般的に知られていなくても制度設計そのもの。日本の専業主婦は戦間期には高級官僚層や財閥系富裕層の一部に存在しただけですが、敗戦後には先進各国を観察してそれ以外の社会の回し方はないだろうと考えられたわけです。その「標準」を現実化したのが1960年代の団地化や、それに引き続く「ニューファミリー」のヴィジョンでした。
それが80年代になると、男女雇用機会均等法ないしすなわち女性も総合職に就けるようにする動きが生じ、それを前提にしてプライヴェート領域を射程に入れた男女共同参画という第2波フェミニズム以降の動きが生じるようになると、そうした新しい動きを市場や行政の新しいソーシャル・インフラストラクチャーが支えるようになっていきます。
家族は長らく共住共食集団だと考えられてきましたが、80年代半ばにコンビニエンスストアが普及すると、コンビニ弁当が大きな役割を果たすようになります。母親がわざわざご飯をつくらなくても、子どもにお金を与えておけば、勝手にコンビニ弁当を買って食べます。現在では加えて宅配のサービスも充実していて、独居老人の助けになっています。
そうしたかたちで、1960年代以降に専業主婦が提供していた便益の多くが、1980年代半ばから市場が提供できるようになりました。しかも支払いコストはたいして高くはありません。こうして、コンビニ化や宅配化に代表される市場化が、家族の生活形態の多様化や、性別役割分業の非固定化に貢献するようになります。
でも、コンビニ化や宅配化による家族の「多様化」とはモノの言いようで、子供や老人のネグレクトを含め、家族の空洞化を促進しました。60年代の団地化が「地域空洞化」とそれを埋め合せる「家族内閉化=専業主婦化」から成り立ったのに対し、80年代のニュータウン化は「家族空洞化」とそれを埋め合せる「市場化&行政化」から成り立ちました。
行政化とは、各自治体で保育所の待機児童を減らしたり、児童館を充実させたりなど、母親が働きながら子育てできるように行政的支援をしていく動きなどを指します。80年代半ば以降、こうして市場化&行政化が進むことで、専業主婦が育児労働を抱え込まなくてもよくなる動きが展開しました。こうした動きは非常に肯定的に語られました。
ですが、僕は80年代半ばから10年間あまりフィールドワーカーとして全国を周り、テレクラや援助交際のような世間にいわゆる「負の側面」を見てきたので、家族の多様化に並行した裏面にも注目せざるをえませんでした。たとえば「家族空洞化」を埋め合せる「市場化&行政化」ですが、青少年にとっては「第四空間化」を意味しました。
「第四空間」の一般化

- 『自動車絶望工場──ある季節工の日記』
(1972、現代史出版会
[講談社文庫として再版])
家の依存的暴力が家庭内暴力、学校の依存的暴力が校内暴力、地域の依存的暴力が暴走族を含めたヤンキーです。これらが80年代後半までに鎮静化したことで、「子供がいい子になった」としばしば語られました。しかし実際は子供がホームベースを第四空間にシフトさせたことで、子供の姿が見えなくなったことを意味しました。
こうした動きは少年犯罪の動機の不透明化をもたらしました。少年犯罪の暴力事犯の大半は集団暴力ですが、地域空洞化によってヤクザが不良少年集団をケツ持ちできなくなることから集団暴力の暴走が目立つようになり(89年の足立区綾瀬の女子高生コンクリ詰め殺人)、次いで個人暴力の暴走が目立つようになります(97年の酒鬼薔薇生徒事件)。
コンビニ化やネット化を含めた「市場化&行政化」が支援した「家族多様化」が、その実「家族空洞化」でもあったことは、80年代後半段階でテレクラ女性ユーザーの大半が専業主婦と中高生だったという事実に象徴されています。まさに「ひとつ屋根の下のアカの他人」状態ですが、10年後にはその事実が誰にとっても自明になっていました。
では、仮想現実・匿名メディア・ストリートが新たなホームベースになったのかというと、うまくいきませんでした。ホームベースとは、出撃基地であり帰還場所でもあるような「感情的回復」の場です。かつては地域や家にホームベースが期待されていたのが、まず地域が、次いで家がダメになりました。そこで「第四空間」に希望が託されました。
70年代末から盛り上がったコミケット(仮想現実関連)でも、80年代半ばから盛り上がったテレクラや伝言ダイヤル(匿名メディア関連)でも、80年代末から盛り上がったクラブやチーマー(ストリート関連)でも、家や地域や学校が「ウソ社会」ないし「クソ社会」であることに対する、抵抗拠点ないし代替的居場所としての意識が見られました。
ところが「第四空間」が一般化すると、家や地域や学校の空洞化はもはや反発対象にならなくなり、性愛系であれオタク系であれ、過剰であることが忌避されはじめます。96年に援交ブームがピークを超えて以降、性愛的に過剰であることがイタイとして忌避され、続いて97年以降、オタクの過剰な蘊蓄競争がイタイとして忌避されるようになります。
過剰に細分化した「島宇宙化」を背景に、"複数"の島宇宙を"緩く"掛け持ちしないと友達作りが困難になるという合理性もありましたが、それとは別にインターネット化がもたらす2種類の疑心暗鬼もありました。第一は「仲間外し」の疑心暗鬼で、過剰同調を帰結します。第二は「脳内ダダ漏れ」の疑心暗鬼で、腹を割らない表層の戯れを帰結します。
ネット化を背景とした「過剰同調的な表層の戯れ」が、性愛的過剰やオタク的過剰を抑制する一方、性愛コミュニケーションでは、ピンポイントで性欲のボタンを探すフェチ系(2人オナニー系)が増え、かわりに、互いに相手の内面に入り込んで感情を取得して反応し合うダイヴ系(相互浸透系)が減りました。総じてフラット化が進んだのです。
こうしたフラット化は、オタク差別やモテない人の劣等感を緩和する──たとえばダイヴ系ならぬフェチ系がメインになれば生身の人間にかかわる必要性が減る──ので、良いことに見えます。実際、「過剰同調的な表層の戯れ」が一般化したことが、シェアハウスのような動きを支援したのだと、僕は睨んでいます。これまた良いことに見えます。
でもマズイ面もあります。こうしたコミュニケーションの「疑似包摂」の上昇で、目に見える社会的排除から自由になる反面、自分は排除されているという被排除の意識が個人化され、連帯の期待可能性が極小化するのです。「疑似包摂」の裏返しで、被排除の意識を持つ者は社会全体を恨んで「誰でもよかった」と人を殺めがちになります。
「疑似包摂」とはジャック・ヤングの福祉学的概念で、「包摂」と違う悪い意味があります。経済弱者が、非弱者と同じシステム──マクドナルドやネットカフェ──を使えて非弱者と同じ身なりもできるので社会的排除を意識せずにすむ代わりに、個人ごとに分断され「生きづらさを自分のせいにして」生きる状態。この概念を応用させてもらいました。
さて、トヨタ自動車の期間工の悲惨を描いた『自動車絶望工場──ある季節工の日記』で知られる鎌田慧さんに、秋葉原通り魔事件(2008)について『自動車絶望工場』の期間工といまの期間工とどちらが苦しいかと伺ったことがあります。秋葉原事件の容疑者もトヨタ自動車の期間工です。
鎌田さんは、物理的貧困という点では昔のほうが圧倒的にキツかったとおっしゃる。いまは貧乏でもマクドナルドやコンビニで安く食事にありつけるし、安い服を着ても表面はそう見えない。マクドナルド難民もネットカフェ難民も、見かけは普通の人と区別できないから、排除の視線に晒されずに済む。そういう意味でも、いまのほうがキツくないわけです。
昔は、タコ部屋に寝泊まりさせられるとか、古いアパートの一室を何人かの出稼ぎ労働者で間借りするとか、誰から見てもブルーカラーに見えるとか、地方出身者に見えるとか、物理的貧困はずっとキツかった。けれども、出稼ぎ労働者の共同性、下層労働者の共同性を生きることができ、だから、みんなで共産主義革命を夢見ることもできました。
いまがキツイのはなぜか。鎌田さんは精神的孤独だとおっしゃる。タコ部屋じゃなく自分のアパートに住めて、路上生活&炊き出しじゃなくマクドナルド難民としてやれて、職業安定所に詰めなくても携帯電話で仕事を探せる。かくして人間関係を頼らなくても生きていける分、個人の孤独はより深まるから、精神的にはいまのほうがキツいとおっしゃいます。
僕も同感です。2008年に『自殺実態白書』(自殺実態解析プロジェクトチーム)が出た際に細かく分析したのですが、男性独身者は、工場城下町での自殺者数が多いんです。弘前ではなく青森、静岡ではなく浜松、福岡ではなく北九州というように。一方、女性独身者の自殺は大都市近郊──僕がいろんな本で「16号線沿線的なもの」と呼んだ地域──が多い。
そして、僕自身のフィールドワークに重ねて言うと、バブル崩壊後の工場城下町も大都市近郊も共通して売買春が多いんですね。大都市近郊も、都市部の消費や匿名的戯れから疎外され、昔ながらの町内会的つながりからも疎外された、二重に疎外された場所です。
どちらの地域も明らかに社会的要因によって希望がない状態なのに、若い世代の多くは生きづらさを自分のせいだと個人帰属化します。売買春のフィールドワークを通じてそれらの地域に窺える心象風景はキツいものがあります。このキツさを経済的貧困だけに還元するのは誤りで、「疑似包摂がもたらす個人帰属化」を主題化しなければなりません。
門脇──日本では60年頃から、家族内性別役割分業を制度的に促進させるとともに、それを前提とした近代都市計画が行なわれるようになり、そして80年代半ばには、その前提自体が内部から崩壊していった。日本における本当の意味での近代の到来と終焉は、たかだか30年弱の短い期間の出来事だったというわけですね。
宮台──まったくです。それらはすべて、僕の人生の枠内で起こった出来事にすぎない。
「生活世界」と「システム」
門脇──この30年ほどしかもたなかった日本の近代的な社会設計に、なにか思想的な裏付けはあったのでしょうか。宮台──あることはありましたが、空間構成の思想に偏っていました。ある程度知られているのが、段階構成理論、近隣住区理論、オープンコミュニティ理論、アーバニティ理論などで、それらの組み合わせが流派を構成していました。しかし、空間軸ならぬ時間軸についての発想が弱く、持続可能性の検証を経ていませんでした。
内部からの生活関連施設へのアクセシビリティや、外部からのコミュニティへのアクセシビリティなどが注目されましたが、空間的に分布する近隣のリソースをどう配置して利用するかというものでした。具体的には、コモンスペースのオープンネスをどうするか、オープンコミュニティを旨とするかクローズドコミュニティを旨とするか、などです。
たしかに、コミュニティの在り方を議論してはいましたが、時間軸上の持続可能性を考えない点では、空間設計ではあっても、門脇さんのおっしゃる社会設計としては未熟でした。たとえば71年に入居が始まった多摩ニュータウンは、東京都立大学の社会学者らも関わった計画でしたが、現在の状況はすでに有名です。社会学者がもっと機能するべきでした。
具体的には、30年も経たないうちに空洞化が進み、いまではエレベーターもない4階建ての建物に高齢者がぽつぽつと住んでいるという悲惨さです。若い夫婦が入居して、やがて子育ても一段落して経済的に豊かになれば団地から出て行き、入れ替わりに若い夫婦が入ってくるだろうと、何となく思っていた。お粗末ながらそれが時間軸上の想定でした。
当時は、そうした時間的想定がどの程度の蓋然性で妥当と言えるか、加齢しても出て行かずに永住することになった場合どうなるかなど、フィジビリティスタディ(計画通り回るかどうかの事前調査)もなされず、時間的想定が期待外れの結果に終わった場合に責任を問われる主体も決まっていませんでした。日本の官僚行政にありがちな杜撰さです。
空間的リソースをシンクロニカル(共時的)に回すことについては、非常に合理的に考えられていたと思います。僕は子供の頃に1960年代の団地に住んでいたので覚えています。団地のなかにはスーパーマーケットがあり、その周りにはクリーニング屋や中華料理屋が並び、集会所に人々が集まり、すごく活気があって、友達から羨ましがられました。
門脇──80年代半ばに起きた制度と市場の変化を端緒として、家族の解体が進み、その本当の意味に気づかないまま、行政もこの動きを後押ししていった。結果、われわれは理想的に見えた近代的世界を手放してしまうことになり、大きな喪失を感じるようになった──そういうお話だったかと思います。ではその喪失というのは、具体的にはどういうものなのでしょうか。

- 『人間蒸発』(今村昌平、1967年公開)
システムは、マニュアルに従って役割を演じられれば誰でもいいという具合に、人間を入替可能な道具として扱います。システムが導入された当初は、生活世界を生きるわれわれが、もっと便利で豊かになるための手段として、システムを使うのだと意識されました。ところが、システムが拡大し続けた結果、システム依存ゆえの本末転倒が起こります。
第一に、ハーバーマスが言うように、生活世界を生きるわれわれがシステムを使うというより、システムが生活世界を生きるわれわれを道具にすると意識され、尊厳が脅かされます。第二に、災害社会学者レベッカ・ソルニットが言うように、巨大システムが災害や原発事故で破壊されれば、システム依存的な生活世界は一巻の終わりだと意識されます。
第三に、昨今政治学領域でキャス・サンスティーンやジェームズ・フィッシュキンが言う通り、巨大システム依存と生活世界空洞化によって感情的安全を損なわれた人々の、不安と鬱屈を当て込んだ感情政治=ポピュリズムが、政治的暴走を招き寄せて、巨大システム自体をそれに依存する生活世界もろとも破壊してしまう危険が意識されます。
3.11の原発事故で明らかになった、とりわけ日本人がシステムに過剰依存しやすい問題があります。システムは本来、山があり川が流れているという自然の自明性と違い、社会的アクシデントをきっかけに回らなくなる脆弱さを内包します。だから制度や人心の空洞化や機能不全がないように絶えずモニターし、随時メインテナンスする必要があります。
ところが、丸山眞男が「日本人における作為の契機の不在」と述べたように、日本には、モニターとメンテナンスがなければ社会が回らなくなるとする発想がなく、自然がそこにあるように社会を自明なものだと見なす伝統があります。その結果、システムが災害で回らなくなる可能性が意識の外に押し出され、システムに過剰依存しがちなんです。
ただ僕は映画批評家でもあるので、システム過剰依存がもたらす本末転倒が、ある時期までドキュメンタリーやドラマで繰り返し描かれたことを指摘しておきましょう。1967年に作られた今村昌平の『人間蒸発』を皮切りに、60年代後半から「蒸発」がよく主題化されました。今村の作品は婚約者ですが、多くは家庭の父親ないし夫の蒸発でした。
父親ないし夫がある日突然いなくなって、ようやく見つけたらホームレスをやっていたといった内容です。母親ないし妻については、いわゆる団地妻の一部がやっていた「ルンルン売春」が週刊誌の誌面を賑わせていました。いずれにせよ、豊かで幸せな団地生活だったはずが、「こんなはずじゃなかった」という期待外れに打ちのめされる感覚です。
そこでは、「システムのなかに組み込まれることで顔をなくした存在」「家族や婚約者の前でも顔を取り戻せない存在」というモチーフがしばしば描かれました。ただしこうしたモチーフは、高度経済成長時代が終わる1973年以降は目立たなくなり、従来的な家族からの解放にモチーフがシフトします(『岸辺のアルバム』や『北の国から』など)。
80年代になると、さらに変化します。当時の「TIME21」や「NONFIX」といったテレビドキュメンタリーを見ればわかるように、タトゥーイング、インプランティング、リストカッティング、新興宗教といった新たな主題が扱われ、強者に虐げられた弱者、ないし、システムに蹂躙された生活世界、というモチーフが消えていくんです。
当時は学生企業を作ってそうしたドキュメンタリーの企画を出す仕事をしていたので、従来的モチーフでは視聴率がとれなくなった経緯を覚えています。要は、われわれはシステムの主体なのか客体なのかという問いかけの意味を理解してもらえなくなった。もはやシステムは見えなくなり、専ら自意識のハンドリングが主題になるように変わったんです。
こうした〈自己の時代〉が厳密には1977年から始まったというのが僕が書いてきたことで、〈秩序の時代〉(戦前~1955年頃)なら、理想的に作動するシステムを悪が攪乱するという意識、〈未来の時代〉(1955~70年頃)なら、いまは未熟なシステムも未来には完成されるという意識を伴いましたが、〈自己の時代〉にはシステムが視界から消えてしまう。
もちろん〈自己の時代〉にも、91年のバブル崩壊や97年のアジア通貨危機に端を発する平成不況深刻化など、システムが盤石ではないことが幾度も突きつけられました。にもかかわらず、1960年代末の学園闘争時代に蔓延した「こんなはずじゃなかった感」は、まったくありませんでした。むしろ「どうせこんなものだ感」が支配的だったと言えます。
この違いは時間感覚に由来します。高度成長期の当初は「未来は豊かになって諸般の問題が解決する」と信じられていたのに、60年代半ばの、先に触れた人間蒸発の時代になると挫折します。そこで「ここではないどこか」としてのキューバや北朝鮮や中共が憧れられる学園闘争の時代になりますが、これも60年代末に挫折します。「二重の挫折」です。
1969年のATGや若松プロが制作した一連の作品には、こうした「二重の挫折」ゆえに、「ここではないどこか」への強い憧憬と「どこかに行けそうでどこにも行けない」という先取された絶望の、両方が描かれます。「未来は良くなるはずだ」という期待ゆえの、「こんなはずじゃなかった」という期待外れが、そこには刻印されています。
これと比べて1990年代を振り返ると、91年にバブルが崩壊し、92年に深刻な就職氷河期が始まりますが、同時期の渋谷では援助交際のメッカとしての狂躁が始まります。狂躁ゆえにディプレッシヴ(憂鬱)になった人々が深刻なオタク差別に苦しみ、オウム真理教などカルト宗教に向かいます。そこには未来への期待などまったく見られませんでした。
代わりに見られたのは、77年以降の〈自己の時代〉に深刻化した島宇宙の細分化による分断と、分断された個人が勝ち組も負け組もネットにアクセスして戯れたり鬩ぎ合ったりする事態。つまり「個人帰属と疑似包摂」です。特徴的なキーワードは「生きづらさ」。社会は変わらない以上、問題は個人にある、という理解が蔓延するようになりました。
システムが回らなくなった後、ボトムから困難を乗り越えるために
門脇──建築の世界でも、設計者は自分の建てた建物を追跡調査して、建物を改善したり次の設計に役立てたりする習慣があまりありませんし、建築基準法等の法制度の枠組みも新築だけを前提としたもので、そもそも建物を漸進的に改変していくような回路が制度的に存在しない。それと同じようなことが制度設計者にも生活者にもあって、トップ側もボトム側も、社会の危機的状況に対して変革しようとしなかったわけですね。ところが2000年代に入ると、人口が減少していく縮小社会が到来し、経済停滞の常態化もいよいよ明らかになってくる。そのようななか、トップ、つまり政治が変わることに一時期は期待が持たれましたが、小泉内閣にはじまる自民党改革も、続く民主党政権も、自治体からの「維新」のような動きも、結局のところ最後は失望をもたらし、政治からの変革はどれも失敗に終わった。そこに追い打ちをかけるようにして3.11が起こります。これらのことが重なって、トップが変えてくれないのだったらボトムにいる者同士のつながりで、この困難を乗り越えなくてはならないという意識が強くなったと思うのです。しかも周囲を見渡してみると、使えそうなリソースはいろいろある。そうした流れのなかから出てきたのが「シェア」という動きだというのが僕の理解です。
- 門脇耕三氏
さもないと資本主義の正当性に傷がつき、いずれ革命が起こる必然性があることになってしまう。だから、むしろ主要な経済主体こそが社会の保全に関心を持ちました。現に、ニューディール政策が始まった1933年から70年代半ばくらいまで、先進各国は福祉国家政策を当たり前のように採っていました。アメリカでは「民主党の時代」と呼ばれます。
ところが政府財政が逼迫して福祉国家体制が回らなくなってくると、政府を小さくする分、社会を大きくして担って貰おうというネオリベラリズムが出てきます。レーガニズムやサッチャリズムです。当初は「社会を大きく」というと、専ら市場原理主義が想定されました。でもその結果、共同体が、政府に依存するかわりに、市場に依存するようになりました。
そのため、90年代初頭に冷戦体制が終焉し、グローバル化=資本移動自由化が進んで暫くすると、97年のアジア通貨危機を契機とした世界経済危機ゆえに、ネオリベラリズム批判の様相が変わります。第一に、資本移動自由化ゆえに「小さな政府」が不可避であることが認識されます。「小さな政府」は"選択余地のない必然"だという認識が拡がります。
第二に、「小さな政府」と「大きな社会」という場合、「大きな社会」が市場原理主義の蔓延であってはいけないと意識されます。政府財政が破綻するのと同じく市場も深刻な不況に陥ります。政府に過剰依存するのが危険なように市場に過剰依存するのも危険です。市場ならぬ相互扶助関係──狭義の社会──に包摂されない限り、個人は路頭に迷います。
ところが、こうした批判が政策に結びつく可能性が、逆に低くなっていくのです。なぜなら、グローバル化=資本移動自由化が、経済権力からも政治権力からも、社会を手当てする動機を奪うからです。一口でいえば、一方で〈社会はどうあれ、経済は回る〉状態になり、他方で、〈社会はどうあれ、政治は回る〉状態になるからです。
〈社会はどうあれ、経済は回る〉とは、社会から賃上要求や法人増税要求があれば、直ちに資本移動すれば良い──本社や工場を移転すれば良い──ので、グローバル企業が社会の手当てに関心を持てなくなることを言います。先に紹介した福祉国家政策の時代、つまり制度派経済学やケインズ派経済学が力を持った時代とは、別の時代になったんです。
〈社会はどうあれ、政治は回る〉とは、社会が格差化・貧困化しても再配分をする必要はなく、格差化・貧困化が生む不安や鬱屈を標的として〈感情の釣り〉──対内的なフリーライダー批判/対外的な覇権主義批判──を用いた〈感情の政治〉を展開すれば政権維持できるし、発達した監視テクノロジーゆえに犯罪や暴動を気に掛ける必要も縮小します。
かくして〈社会はどうあれ、経済&政治は回る〉ようになります。先の言葉を使えば〈生活世界はどうあれ、システムは回る〉ということ。そうなればなるほど、(1)主客転倒で尊厳が奪われること、(2)システムクラッシュで一巻の終わりになること、(3)〈感情の政治〉(=ポピュリズム)でシステムが暴走する危険があること、などが意識されるようになります。
論理的に考えると、これに抗う方法は、〈システムはどうあれ、生活世界は回る〉ないし〈政治&経済はどうあれ、われわれは回る〉と言えるような〈生活世界をシェアするわれわれ〉を再構築するしかありません。市場原理主義とは区別された相互扶助領域としての「狭義の社会」を──「広義の共同体」を──取り戻す他ないということです。
僕はこれを「共同体自治」と呼びます。食・エネルギー・情報の共同体自治に触れましたが、これらは安全保障ないしリスクマネジメントの基本です。これを政府や企業に「任せて」何とかできる時代は終わりました。〈社会はどうあれ、政治・経済は回る〉という状況である以上、政治権力と経済権力による公正なコミットメントが疑わしいのです。
感情の劣化
門脇──そういう悲観すべき事態のなかで出てきたのが「シェア」だとしても、この動きには希望的な側面もいろいろあると思うんです。政府や大企業を頼れないとなると、自分自身で考えて行動するしかない。つまりこうした社会は、規範準拠的ではなく、自己準拠的な生き方を人々に促すことになるだろうという期待がある。かつ、そうした自己準拠的な人たちがある種の流動性──住む場所や働く場所をシェアするような──をもつようになると、その都度自律的にある集団を形成するようになる。このことは、その集団に固有のガバナンスを模索しながら、自分の頭で考える人たちが半オープンなコミュニティを自発的に形成することにつながるのではないか。しかも、そうした集団のガバナンスはその集団に固有のものですから、それは地縁や血縁のような封建的な枠組みに縛られないかたちで、ある種の地域性や共同性を復活させるようにも思えます。以上はあくまで希望的な観測ですが、宮台さんも一時期までは「シェア」に希望をもたれていたわけですよね。しかし現在では悲観的な観測をもたれているようです。その心境の変化について、率直なご意見をお聞かせいただけますか。宮台──シェアに希望を抱けなくなったのは〈感情の劣化〉のせいです。2000年代に入るとネット上で(1)仲間外しの疑心暗鬼化、(2)プライバシー侵害の疑心暗鬼化が顕在化します。今日のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で言えば、前者はLINEでの「既読プレッシャー」に、後者はTwitterやFacebookでの「脳内ダダ漏れ」に象徴されます。
こうした疑心暗鬼化のせいで、コミュニケーションが自己防衛的になります。そうなると、コミュニケーションから、互いの内面にダイヴする類の営みが脱落して、承認とポジション取りの営みが専らになりがちです。オフラインなら「キャラを演じる」ことに象徴されているし、オンラインならFacebookの「いいね!」ボタンに象徴されています。
オンラインとオフラインに跨がる──正確にはこうしたデュアル・チャンネルがあるがゆえの──疑心暗鬼化で、対面コミュニケーションから、ネットにはない豊かな稔りが、失われます。すると対面コミュニケーションから退却しがちになり、その分ネットにアクセスするので、「仲間外しの疑心暗鬼」と「プライバシー侵害の疑心暗鬼」がより激しくなる。
こうしてコミュニケーションは離合集散の流動性を高め、低い流動性を前提とした人格的信頼に関わる「立派/浅ましい」という伝統の二項図式が機能しなくなるかわりに、「うまくやる/しくじる」という二項図式が専らになります。動機づけには損得勘定の〈自発性〉ばかり蔓延して、内から湧き上がる利他や貢献欲である〈内発性〉が珍しくなります。
浅ましい輩が後ろ指をさされるネガティブ・サンクション=罰が失われる結果、「悪貨が良貨を駆逐する」の類で、ネットにはますます〈感情の劣化〉と〈教養の劣化〉を反映したコミュニケーションが蔓延します。主題化された外交や内政の問題より、噴き上がる側の〈感情の劣化〉と〈教養の劣化〉だけが印象づけられる「2ちゃんねる」が典型です。
ネットでは、インナーサークルでは「仲間外しの疑心暗鬼」と「プライバシー侵害の疑心暗鬼」が蔓延し、アウターサークルでは「匿名に身を隠した誹謗中傷への怯え」が蔓延します。こうした疑心暗鬼や怯えが、対面コミュニケーションでの不毛な過剰同調を招き寄せ、性愛においても友愛においてもストレスフルな日常になっているんです。
大学生男子について言うと、〈感情の劣化〉は遅くとも2005年には顕在化していて、たとえばそれまで行なってきたサブゼミでの自主的グループワークも、男子間の関係が些細な契機で紛糾し破綻するようになったので、僕のゼミではやらないことにしたのです。男子から顕在化した背景には性愛から逸早く退却できた事情があるだろう、と睨んでいます。
ところが2010年に入る頃から大学生女子の〈感情の劣化〉が目立ちはじめます。2010年頃までは、各大学に有名な女子ブロガーがいて、男子ファンがつくことがありましたが、それもなくなりました。多くがFacebookに移行しましたが、醜態写真などがタグ付けされたりするので過度に自己防衛的になる一方、腐臭漂う自己アピールだらけになっています。
先ほど、男子が逸早く性愛から退却したと言いました。女子が退却せずに済んだのは、歳の差カップルという選択肢があったからです。それが、やはり2010年に入る頃から10~20歳年長の男とつきあうと同性から「ビッチ」扱いされるようになります。同性に自慢できることが選択条件になりはじめ、並行して女子の性愛からの退却が顕著になります。
女子が性愛から退却した背景には、歳の差カップルが許されなくなった以外に、重要な背景があります。昔から性愛にアクティブな人には「フェチ系」と「ダイヴ系」がいました。一般に男には女よりも「フェチ系」(学問的には対象異常)が多いことが昔から知られています。誰にも両方の焦点があるので、どちらがより強いかという話になります。
世紀末に『ダ・ヴィンチ』という雑誌のスワッピング特集(2000年9月号)に向けた取材をしました。性愛の複数プレイにはスワッピングとオージー(乱交)があります。愛し合う男女が参加するスワッピングは「ダイヴ系」、単独参加者メインのオージーは「フェチ系」です。ところが取材後、スワッピング・サークルが続々クローズドになったんです。
主催者たちに尋ねると、理由はすべて同じで、「来たがるのは単独ばかりで、愛し合うカップルがいなくなったから」というものでした。要は、年少世代から新たな「ダイヴ系」の参加者がいなくなったから、ということなんですね。昨今は複数プレイは、ハプニングバーに象徴されるように、専ら「フェチ系」の祭りになりさがっています。
性愛が「フェチ系」に傾くとマズイのは、女は男より「フェチ系」が少ないので、性愛が「フェチ系」に傾くと、「ダイヴ系」の女にとってさしたる稔りがなくなるからです。アダルトビデオの現場でも、若い頃から多様なプレイを経験する女が増えたのに、たいがい「フェチ系」の男に合わせているだけで、没入経験が乏しい事実が問題化しています。
要は、若い男子に「フェチ系」が増えていくに連れて、もともと「ダイヴ系」が多い若い女子が、性愛にさしたる稔りを見出せなくなり、それでも暫くは「歳の差カップル」の選択肢を利用してしのいでいたものの、それも難しくなってしまったので、若い女子ですら性愛から退却せざるをえなくなった、というストーリーだろうと僕は睨んでいます。
世界的にも2010年頃からFacebook離れが、最初にFacebookに飛びついたコミュニケーション能力に秀でた人の間で起こり、話題になりました。日本の古い話で言えば、1985年にテレクラができたら2年程で劣化し、最初に飛びついた人たちが離脱してNTT伝言ダイヤルに飛びつくと、そこも2年程で劣化し、そこでダイヤルQ2に......というのと同じです。
アーリーアダプター層(最初に飛びつく層)の世界的なFacebook離れに固有の特徴といえば、離れたと思ったら別の何かに飛びついて......の繰り返しというんじゃなく、FacebookだけでなくSNS全体を含めてネットの不特定者から見えないところで交流していこうという動きだということです。日本でも僕の周辺ではものすごく顕著になっています。
そこで生じているのは、冒頭申し上げた、シェアハウスで起きた問題と同じ事態です。つまり、適当におべんちゃらのポジショントークをすれば凌げるような人間関係と、お互いに脳内ダイヴし合うような濃密な人間関係とを、峻別したうえで、後者のネットワークに入れる人間を厳密に資格審査しようという動きです。当然クローズドになります。
先に申し上げたように、この動きは最初、2000年代初頭のスワッピング・サークルに見られるようになり、少し前からはシェアハウス周辺に見られるようになり、最近ではすべてのコミュニケーション領域で「シェアをやめる」ならぬ「シェアを閉じる」動き──万人からのアクセス可能性を閉ざす方向──が目立つようになってきていると感じます。
少し前にNHKの「クローズアップ現代」で、ゲーテッドコミュニティ化したアメリカの自治体の様子が伝えられました(「"独立"する富裕層 ~アメリカ 深まる社会の分断~」2014年4月22日放送)。所得再配分の不均衡と、非効率な政府機能への不満から、富裕層が合法的に「郡」から独立し「市」を形成しているという事態を紹介した番組です。
あれを見て「アメリカはすごいな、極端だな」という印象を持った視聴者が多いと思いますが、自治体だから目に見えるだけの話で、日本でもとっくに同型的な現象が起こっています。日本ではそれが、濃密な仲間のコミュニティに入れる少数者と、入れない多数者の、明らかな格差として現われています。こうした格差を解消できるでしょうか。
即効策を思いつけませんが、クローズドコミュニティのメンバーらが、メンバーになれない周囲の人々を少しでも包摂していけるように、損得勘定の〈自発性〉から内から涌く力としての〈内発性〉へのシフトを可能にする広い意味での教育をちゃんと行なおうとする積極的な包摂動機を持つ人同士の、有効な協業関係を作るのが長い目では大切です。
コミュニケーションのレイヤー化
門脇──コミュニティのブラックボックス化と分断はたしかに起きていて、SNSの話で言うと、発言が誰からも見えてしまうTwitterはだいぶ前から下火になっています。ユーザーの関心はFacebookに移り、いまはLINEですね。どんどんコミュニケーション・ネットワークがブラックボックス化している。このことと関連して、東京では地理的レベルにおいても、SNSに見られる現象と同じ意味でのコミュニティの分断が起きていると思っています。戦後の農地解放やバブル期の地価高騰などによって、東京から大地主はほぼ駆逐されており、われわれには先祖代々の土地に住むという意識がほとんどない。つまり地縁が解体されきっているので、誰しもが住む場所を自由に選べるわけですが、その選択には「収入と住居費のバランス」や「職場や実家の近さ」などといった自身の合理に加えて、個々人の趣味嗜好が強く働いてくる。小田急線と田園都市線と中央線沿いの駅が同条件にあれば、なんとなく雰囲気が好きだから中央線沿線に住もうかな、というようなことですね。個々人の文化的嗜好は、東京の地理の再編も駆動している。つまりSNSのような情報空間と実空間の両方で、趣味嗜好によるコミュニティの選択=コミュニケーション・ネットワークのブラックボックス化が起きていて、おそらくそれは人間像そのものの分断も引き起こすと思うのです。例えばグローバリゼーションは、国家という枠組みにとらわれずに世界中を渡り歩く「ハイパー・ノマド」と呼ばれる人種を生みだしましたが、一方で昨今「マイルド・ヤンキー」と呼ばれるような、地元で仲間たちとマッタリする生き方を選ぶ人たちも生み出した。両者はグローバリゼーションと主権国家システムの軋轢が生んだ双子の人種だと言ってよいと思いますが、それぞれ人生に対するまったく違った価値観をもっている。これまで曲がりなりにも共有されていたなんらか「理想的」な人間像は、もはや大きく分裂していると言っても過言ではありません。宮台──でも、「グローバル・マッチョ」も「マッタリ・ジモティ」も、両方ともまだいいほうですよね。どちらにも入れない中途半端な存在、たとえば東京大学には入ったけれど、人に好かれず、幸せそうな家族やカップルを見ると苛立ち、勉強や学問以外にもアートやスポーツやセックスを愉しめる人を見ると嫉妬する「勉強田吾作」が、一番ツライ。
門脇──そうなのでしょうね。この分断が、流動性をもった自立的・自発的行動のネガティヴな帰結だと考えています。一方で「シェア」的な動きが進むことによって、ひとつの地理的・社会的拠点に制約されず、複数のコミュニティに同時に所属できる社会が生まれる可能性も理論上はある。閉じた島宇宙がキツいのであれば、ひとつの帰属意識に縛られないという「シェア」の特性によって、島宇宙をバイパスし、全体をネットワークするようなレイヤーを、そこに上書きする必要があるのではないでしょうか。
宮台──おっしゃるとおりです。そしてそれが実際に一部で現実化しています。ただし、どういうかたちで現実化しているかが問題になります。一例としてオタク界隈の話をします。オタクが一見しただけでオタクだと判ったのは1990年代半ばまで。90年の連続幼女誘拐殺害事件をきっかけちオタク差別が深刻化して以降、オタクが次第にオシャレ化しました。
先に紹介したように、97年頃になると、オタクのコミュニケーションが、蘊蓄競争からコミュニカティブな戯れに進化し、オタクと非オタクの境界線が曖昧になりました。かくして、外見はギャルだけど、相手がそういう話をしても大丈夫だと判ったら自分はオタクだとカミングアウトするので、相手がびっくりする、といったことも頻繁になります。
やがて状況が進んで、相手によって「オタク・分野1」を出したり、「オタク・分野2」を出したり、という具合に使い分けるようになります。とりわけ女子のオタクで顕著な傾向です。こうして、相手次第でコミュニケーションを変える「隠れオタク」や「マルチオタク」の作法が拡がると、オタクであることがコミュニケーション・ツールになります。
つまり、オタクでないよりもオタクであるほうが幸せなコミュニケーションができるわけですが、その一方、コミュニケーションの見晴らしが利かなくなります。それぞれのレイヤーからは別のレイヤーが見えないんです。たとえ複数レイヤーに多重帰属していても、自分が帰属するレイヤーについてだけ人がどうなっているのかが見えるんです。
恋愛が始まっても相手がどんなレイヤー群にどう関わるのか見えません。すべてをカミングアウトしないのもありますが、カミングアウトされたところで意味がわからないのもあります。こうして、多様だが分断されている、あるいは複数レイヤーに三股四股で関与できても社会全体のレイヤー分布が分からない状況になる。多様なのに不透明な状況です。
それがいろんな現象を生みます。女を束縛したがる若い男が増えて「ソクバッキー」と呼ばれます。「1時間ごとにメールを送れ、3時間ごとに写メを送れ」とか。相互にダイヴしなくなったので互いに自分は入替可能なんじゃないかと疑心暗鬼になるのもありますが、相手が自分の知らないプライベートレイヤーをたくさん持つことへのジェラシーもあります。
女性の間でここ5年ほど、性愛に過剰コミットしているように見える同性を「ビッチ」呼ばわりするようになったと言いましたが、島宇宙の細分化が進むなかでコミュニケーションのコネクト可能性を確保するには過剰さを回避するのが合理的だという背景に加えて、相手が自分の知らないブライベートレイヤーを持つことへのジェラシーもあります。
門脇──僕が学生だった頃は、サブカルチャー好きのなかにも「オタク系」対「オシャレ系」のような対立がありましたが、いまやそんな対立はなくて、お互い普通に会話をするらしいですね。それは複数のコミュニティを横断するレイヤーが生まれているということだと思いますが、それがゆえに窮屈な状況も生まれているというわけですね。
宮台──対立がないからフラットなのだけれど、ハッピーな感じはしません。いろんなところに疑心暗鬼があったり、相互監視があるからです。「オタク系」対「ナンパ系」とか、「オタク系」対「ストリート系」という対立があったときのほうが、お互いネタは割れているということで疑心暗鬼や相互監視がなく、まだハッピーだった気がします。
近代的性愛と国家の限界

- 槇文彦+大野秀敏編著
『新国立競技場、何が問題か──
オリンピックの17日間と神宮の杜の100年』
(平凡社、2014)
宮台──同感です。僕がこの2年間やってきた性愛系ワークショップも、ボトムアップの社会の組み立てを狙ってのことです。『「絶望の時代」の希望の恋愛学』の第1章で書いたことを繰り返します。マックス・ウェーバーは、計算可能な社会領域が拡がることが近代化だと定義します。
社会の計算可能性は実質合理性ならぬ手続合理性によってもたらされます。たとえば官僚機構。だから手続合理性が貫徹する領域が広がることが近代化にほかならないとも言い換えられます。手続合理性がもたらす計算可能性の観点から見た場合、心理学で言う「変性意識状態(altered state of consciousness)」★5はノイジーなものとして排除されます。
だから近代社会は眩暈の囲い込みを行ないます。日本は先進的で江戸時代から行なわれてきました。眩暈を生じる場所を悪所と言います。芝居街と色街です。たとえば各地に宿場町が散在し、宿場町は盛り場の奥の芝居街があり、奥の院には色街がありました。これを天保の改革の際に人形町や吉原に集約して、眩暈を否定しないものの管理しやすくしました。
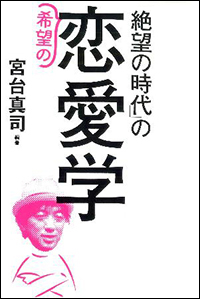
- 『「絶望の時代」の希望の恋愛学』
(KADOKAWA/中経出版、2013)
こうした動きはどの先進国でも起こりましたが、共通して例外的な領域が2つあります。性愛と国家の領域です。この2つの領域では眩暈に満ちた変性意識状態が奨励され続けているんです。性愛から見ます。近代では恋愛結婚が賞揚されます。よく考えるとありそうもないことです。僕が性愛系のワークショップでよく使うフレーズを紹介しましょう。
みなさんと性交可能な相手は日本だけで何千万人もいるし、世界大では何十億人もいます。普通に生活しているだけでも何千人も何万人もいるはずです。にもかかわらず、ある特定の人間だけを唯一の存在だと思い込むことは、合理的に考えれば馬鹿げています。こうした逆説的困難を乗り超えるための数少ない手段。それが「恋愛」なんです。
この「恋愛」は正確には「ロマンティック・ラヴ」と呼ばれ、12世紀から19世紀にかけて発展しました。2つポイントがある。第1に、ロマンティック・ラヴの源流となった「情熱愛」は制御不可能性が特徴です。そのため貴族階級の既婚男女がそれゆえの余裕のエクストラとして戯れるものでした。余裕があるから制御不可能性と戯れられたんです。
第2に「ロマンティック・ラヴ」という場合の「ロマンティック」とは「部分のなかに全体を見る」「世俗のなかに超越を見る」「俗のなかに聖を見る」という意味です。性愛の場合、ほかの男にとっては「ただの女」が俺にとっては「特別な女」だということです。日本で言う「あばたもえくぼ」に近い。それが「ロマンティック」という概念の本質です。
性愛の場合、そこで問題が生じます。第一に、自分から見た場合、その相手が本当に唯一の超越的全体なのか。第2に、相手が「あなたは私のすべてだ」という場合、その相手が本当に私を唯一の超越的全体として体験しているのか。これはフランス恋愛文学でいう「真の心」問題です。「真の心」を証すために何かが必要になるわけです。
フランス恋愛文学の伝統では「愛ゆえの病」「愛ゆえの死」が間違えのない証だと考えてきました。コデルロス・ド・ラクロの『危険な関係』(1782)からフローベールの『ボヴァリー夫人』(1857)までは、主人公は愛ゆえに死にます。しかし、「真の心」を証すために死ななくちゃいけないとすれば、ロマンチック・ラヴは実践可能ではありません。
貴族既婚者の余裕の戯れは別にして、少なくとも万人が参加できそうだとは思えません。ところが『ボヴァリー夫人』が書かれた19世紀半ばまでに印刷術の浸透で小説が世の中に広く出回り、小説の設定に憧れた大衆の実践要求が高まります。そこで「真の心」の証が、ハードルが高い病や死ではなく、結婚に変わります。「真の心」を証すための結婚です。
これが「恋愛結婚」と呼ばれたのです。これは単なる制度的な婚姻届けとは別の話で、「どこにでもいるタダの男や女を超越的な全体だと思い込むこと」を前提とした奇蹟の営みなんです。恋愛結婚の奨励とは、したがって、合理主義者から見た場合「思い違い」の奨励であって、それを可能にしている眩暈の状態が「変性意識状態」にほかならないわけです。
性愛の次に国家です。僕たちの社会で許容され、あるいは強いられている「変性意識状態」が愛国心です。流動性の高い社会では、先ほどの資本移動自由化に見られるように、不都合なら国境を超えて他国に行けばいい。恋愛と同じで、どの国だっていいはずなのに、この国だけが自分にとって唯一なのだと思い込める状態を作り出さねばなりません。
グローバル化=資本移動自由化によって、高い流動性が意識されざるをえなくなった現在だからこそ、すべての国でナショナル・コミットメントをどう作り出し維持していくのかが大きな課題になっています。だから、国民国家勃興期ならぬ国民国家落日期の現在だからこそ、「東京オリンピック」を含めたナショナル・イヴェントの重要性が増しています。
近代社会は「変性意識状態」を囲い込みますが、性愛と国家の領域に限っては必死で奨励します。近代社会は、市場自由化に従って際限なく流動性を高めていけるように見えて、実際には家族形成と国家形成の2領域で、恣意的な擬制なのにそれが必然性だと信じるための「変性意識状態」、あるいはそれを作り出す装置が、永続的に要求されているんです。
皆さんが実感するように昨今その装置が機能しなくなっています。だから、家族形成が難しくなり、国家への忠誠心も持ちづらくなった。近代社会が現在直面している乗り超えがたい困難です。このうち国家への忠誠心に関わる「変性意識状態」関連の困難については、困難の利用を企てるさまざまな政治主体があります。これについては別の機会に論じます。
それとは別に、家族形成に関わる「変性意識状態」関連の困難については、その解決を国家に委ねることは理念的にも現実的にもありえないので、民間の市民的な実践を通じて、困難のハードルを乗り超えることができる人たちを増やしていく必要があると思っています。それで性愛系ワークショップをやっている。ボトムアップからの社会の組み立てです。
損得を超えた〈内発性〉
宮台──そうした問題意識を持ってフランス恋愛文学を読むと、重要な課題の存在に気づきます。人並みに結婚したい。結婚するには恋愛しなければならない。ここまでは損得勘定が動機です。ところが恋愛の本質は自己制御が不可能な状態です。損得勘定ベースの〈自発性〉から、損得を超えた内から湧き上がる力としての〈内発性〉へとシフトする必要がある。ここに逆説があります。損得勘定の〈自発性〉を動機として、損得を超えた〈内発性〉を手に入れたがる。損得勘定をベースに、損得を超えた愛や絆を手に入れたがる。そんなことが可能なのか。これはギリシャ的主題です。損得を超えた利他性や貢献心がないとポリスが滅びる。滅びはイヤだから損得を超えた利他性や貢献心が必要だ。で、どうやって?
性愛に関わる〈自発性〉から〈内発性〉への橋渡しの困難はフランス恋愛文学の主要な主題です。これらを読むと、この橋渡しのための数少ない経路が示されています。性愛系ワークショップも同じ課題を取り上げています。君らは損得勘定でしか振る舞えていない。性愛でも損得勘定が専らだ。それでは互いにやがて用済みになる関係しか作れないぞ、と。
そう言われて怯えた若者らが、それはイヤだという損得勘定から〈内発性〉を欲しがります。そういう若者に〈内発性〉をインストールできるか。初期ギリシャでは、損得勘定を超えられない者が周囲から「浅ましい」と軽侮され、損得勘定を超える者が「立派だ」と讃えられるような「賞罰環境=損得状況」を通じて、〈内発性〉を埋め込もうとします。
やがて、揶揄し賞賛する「周囲の視線」がなくても「自分の視線」が自分を見て反応するようになります。単なる認識でなく関心(コミットメント)、単なる知識でなく動機(利他性や貢献心)、R・W・エマソンの言う「内なる光」を埋め込もうとするのがプラグマティストですが、彼らはミシェル・フーコーに似てこうした過程に注目しています。
たとえば1930年に『精神・自我・社会』(邦訳=河村望訳、人間の科学社、1995)を著したプラグマティストのG・H・ミードは有名なIとMeの概念を使います。Meとは自分が見た自分のこと。IとはMe(自分が見た自分)に対する反応のこと。自分が見た自分が「浅ましい」と感じられたら、それを回避しようと意欲するのがIです。彼はこれをゴッコ遊びの賞罰環境が育てると考えたわけです。
ミードと同時代のプラグマティストであるジョン・デューイの後継を自称するリチャード・ローティは、こうした〈内発性〉の埋め込みプロセスを「感情教育」と呼びます。なにか(Me)を見てなにかを感じる(I)ようにするからです。しかし、なにを見てなにを感じるかという感情の習得には臨界年齢があるとするのが、ルドルフ・シュタイナーの主張です。
道徳感情の認知的発達を研究したL・コールバーグも同様に主張します。だから、感情の習得の臨界年齢を超えた者に対しては、アルフレッド・アドラーが提唱する、フロイト的な「過去の引力」ならぬ「未来の引力」、アリストテレスの「最終目標」をプライマーとするプライミング──認知的整合化メカニズムを利用した優先順位変更──を用います。
シェアハウスがうまくいかなくなるとすれば、その理由は畢竟、損得勘定を超える動機づけが乏しいからでしょう。〈自発性〉が優位で〈内発性〉が欠けるからでしょう。街づくりと同じで、人々がより便利で低コストならどこにでも転居しようと思っている場合、フリーランディングへの疑心暗鬼から、予めコミュニケーションをセーブしがちになります。
僕は、周りの人たちが被ったシェアハウスの失敗を思考の材料にしているので、小手先の弥縫策はともかく、最終的には動機づけの形式を焦点化しない限り、さして稔りのある共同生活にはならないと思っています。先ほどの言い方を使えば、コスト低減が目的となるばかりで、かつての家族では不可能になったものを取り戻すことは目的になりえません。
僕がやるワークショップが現実に提供できるのは、性愛コミュニケーションに稔りがない理由、シェアハウスに稔りがない理由、学校や会社でのグループワークに稔りがない理由を、洞察する力を与える所までです。大半の理由は損得勘定を超える動機の不足ですが、損得勘定を超えた動機とはどんなものか、「感じ」を摑んでもらうのも追加の目的です。
門脇──「シェア」の動きが理想的に展開していくためには超越性が必要だということですが、その超越性は合理主義的な観点からは説明がつかない計算不可能なものだということですね。宮台さんはワークショップで「感じ」を摑むように言っているとおっしゃいましたが、具体的にそれはどのようなかたちで達成できるものなのでしょうか。
宮台──「〈内発性〉の不足を理解することや〈内発性〉の「感じ」を摑むこと」と「実際に〈内発性〉を自らのものとすること」の間に、距離があります。僕らの性愛ワークショップは、巷のナンパ講習と違い、〈内発性〉の不足を理解させ、〈内発性〉の「感じ」の感得をさせ、距離を架橋するヒントを与えることを、こちら側の目的としています。
とはいえ、来る人たちの層は巷のナンパ講習と同じです。率直に言って、どう考えてもナンパなんて無理だと思える人たち、言葉は悪いですが「イケてない」人たちが来ます。そこが僕らの狙い目です。そもそもナンパ講習を訪れる若者の大半が「このままではマトモな人間関係すら作れないので、ナンパを切口になんとかしよう」という人たちだからです。
それとは別に、僕は最近、カンパニー松尾さん、バクシーシ山下さん、二村ヒトシさんといったアダルトビデオ監督たちと、しばしばトークイベントをやるのですが、この手のイベントだと参加者の過半が女子です。彼女たちは、ナンパ講習に訪れる男子と違って、人間関係が作れない云々じゃなく、日頃のセックスやデートがつまらないから来ています。
この違いが、現時点における若い男子と女子が置かれている状況のギャップを示しています。これを僕は「男子は承認を求め(がゆえに理解に届かず)、女子は(承認をクリアして)理解を求める」という具合にここ10年ほど表現し続けてきました。ここでいう理解は「ダイヴ」と言ってきたことと同じです。男子の多くは「ダイヴ」以前の段階です。
実際に〈内発性〉を自らのものとすること、ミード的には「相手に生じている感情を自らの内で引き起こし、それに内発的に反応できるようにすること」の達成には、とりわけ感情プログラムのインストールに関わる臨界年齢を過ぎた人の場合、アドラー的なプライミング(未来の最終目標による現在の優先順位変更)を用いるにせよハードルがあります。
門脇──具体的な方法がなかなか見えてないということでしょうか。
宮台──具体的方法は見えていますが、時間がかかるという点と、マイクロなプロセスによってしか伝えられない点が、ハードルなんです。「感じ」を摑むというだけでも、ワークショップに参加した数十名から100名くらいの規模の連中に伝達できるかどうかです。マクロにみれば「焼け石に水」です。
ただ、「やらないよりはやったほうが少しはマシ」というのと「やがてそれが同心円状に拡がるのを待つしかない」という思いでやっています。これは、性愛ワークショップと並行して、ときどき僕が関わっている住民投票や熟議関連の政治ワークショップにおいても、まったく同じことが言えます。
門脇──なるほど、超越性(全体性)の経験がある種の特別性として、一回限りのものとして立ち現われてくるのだとすると、その手続きには反復不可能性があって、マイクロなプロセスによって個別に伝えるしかないわけですね。
宮台──そのとおりです。
門脇──しかし、それは生活社会をシステムに仮託しすぎてしまった近代社会の喪失を乗り超える方法になりうる。つまり生活社会がもっていた具体個別性を、一つひとつシステムから奪い戻す試みだというわけですね。そのように考えると、建築における設計者の概念も大きく変わりそうです。近代的な意味での建築家や設計者は、合理的に働くだろう全体を仮定して、その全体像から演繹的にモジュールや要素機能のあり方を導く思考フォーマットを持っていて、それこそが設計だと思われてきました。あるいは近代都市計画も、土地利用目的を面的に制限する「ゾーニング」をその根幹に据えているわけですが、これも地域を分割し、いったん機能分担させたうえで、それらを道路網や鉄道網によって再び連結することによって、都市全体をあたかもひとつのシステムのように高効率で稼働させようとする発想に基づいています。一方で、今回の「10+1 web site」の「特集=シェアの思想」では若い建築家にも文章を書いていただいていますが、おそらく彼らはそういう思考をする方々ではありません。これは最近の潮流としても感じることですが、若い建築家には、むしろ具体個別の話から、全体をいかに組み立てていけるかを遡及的に考える人たちが多い。それは時として建築家の後退であると批判されるわけですが、いまのお話を聞いていると、これからの時代の設計者としては正しい姿勢だと思えてきます。
宮台──そう言えると思います。僕は青山学院大学大学院の研究コースで非常勤で10年近くコミュニケーション・デザインについて教えています。「コミュニケーション・デザイン」というのはいい言葉です。僕は長らく「ソーシャル・デザイン」という言葉を使ってきたけど、その中核はコミュニケーション・デザインにならざるをえません。
そこで思うのが、日本ではコミュニケーション・デザインを教えることができる人材が皆無に近いこと。以前から山本理顕さんや隈研吾さんや磯崎新さんなど建築家の方とお話をさせていただいてきた理由のひとつは、社会学者だけでもできないし、建築家や都市計画家だけでもできない領域があると思ってきたからです。
その領域とは、「実際にインフラを伴ったコミュニケーション・デザインの世界」です。僕たち社会学者は、デザインの理念的な方向づけを出せるし、マイクロなデザイン実践をすることもできます。ただ、それをなんらかの制度的次元に上昇させるには、建築家や広い意味でのアーキテクトの協力が絶対に必要なのです。
同じように、広い意味でのアーキテクトの方々が、自分たちがつくったハコやコンピュータプログラムのなかで、想定したコミュニケーションが起こるかどうか、そうした想定が妥当かどうかを、彼らだけで考え尽くすことは、将来に渡ってできないだろうと思います。であれば、社会学者と、建築家を含む広義のアーキテクトの、ジョイントが必要です。
でも、そういうジョイントはなかなか実現してきませんでした。今日ここで門脇さんと僕がお話しているという事実が示すように、マイクロなレベルではいろいろな可能性が開かれる兆しがありますし、現に僕たちにはこうして目にも見えるわけですが、おそらくそれが見えている人はまだわずかしかいないし、それを一朝一夕にも広げられません。
同じような事態が、昨今では社会の各所で見られます。最近の政治学でしばしば耳にするのが、「どんな方法を用いればこの社会を存続させられるかはっきりしている。ただ、その方法が行なえないのもはっきりしている」(笑)という物言いです。「物理的には行なえるのに、人々がそうしないのははっきりしている」という意味です。
たとえば財務省の役人にとって、年間2%ずつ消費税を上げて、2020年までに最悪でも16%、ゆくゆくは35%まで上げないと財政が破綻することは、基本的な了解事項です。しかし他方で、それが絶対に実現できないこともわかりきっている。なぜなら日本は民主主義社会だからです。いまは至るところでこういう事態にぶつかっているんです。
その意味では、できることならマクロな規模でいろいろなジョイントが起こって、コミュニケーション・デザインを広範に現実化していくプロセスが、一刻も早く進められていかなければいけないと痛感しますが、うまくいきません。とすれば、時間がかかっても同心円状に波及することが期待できる有効なマイクロ・プロセスとはどんなものでしょうか。
この部分では明るい話ができます(笑)。僕は昭和30年代前半の生まれなので、自分の子供の頃を思い出し、当時の自分たちの成育環境と機能的に等価な環境を、どう実現できるかをいつも考えます。たとえば、よその家の子供たちを呼んでメシを食わせたり、逆に自分の子供を友達の家で食べさせたり、出入り自由にしたいと考えています。
登校する小学生の子供たちと一緒に歩きながら、電柱にウンコの絵を描くこともやっています。小学生は昔もいまもウンコが大好きですから(笑)、僕は「ウンコのおじさん」ということになります。それで僕が授業参観に行くと「あっ、ウンコのおじさんが来た」となって、休み時間になると子供たちが大勢飛びかかってきて僕は下敷きになります。
僕はそういうふうに考えて実践してきたので、3年前の3.11震災のときにも、よそんちの子も連れて、僕の山荘に避難させました。昔だったらそれが当たり前だと思うからです。でも、多くの親は自分の子供だけを疎開させました。親によって持っている社会的リソースも人間関係資本も違い、子供は親を選べない以上、よその子も連れていくべきなんです。
どうしてこんな当たり前のことができなくなったんだろうと疑問に感じます。僕には小学生以下の子供が3人いますが、いまの小学生たちの親は僕よりも20歳は若いので、たぶん育ち方が悪かったんだろうと推測するんです。そこで子供たちをいまの親が育ったみたいに育てちゃだめだと思い、1960年代テレビシリーズのDVDボックスを買いまくっています。
巷の親たちと違って、僕は悪影響を恐れて「テレビを視るな」とは言いません。かわりに「どうせ見るならこっちのほうが面白いぜ」と言って60年代コンテンツを見せまくる(笑)。日本の60年代コンテンツには勧善懲悪モノがありません。怪獣も社会の悪が作り出したものだとか、犯人は悪い奴に見えて本当に悪かったのは社会のほうだったとか。
こういうのを見せていると、僕がそういうフレーズを教え込んだわけでもないのに、「私はね、悪い人は悪いっていう話は好きじゃないんだよ」と言うようになるんです。これを僕は実証実験を通じて確かめることができた(笑)。70年代に入って勧善懲悪モノに覆われたことが、〈感情の劣化〉を被ったヘイトスピーカーらを育てたんだと思っています。
大人は誰もが自分が育った時代の記憶を持ちます。自分がなにをどう体験をしたのかを吟味し、子供から奪ってはいけない体験がなんなのか気づく必要があります。むろん社会的リソースが違うので、かつて自分が体験できたものをそのまま再現はできませんが、いま使えるリソースをどう組み合わせて機能的に等価な体験をデザインできるかがポイントです。
コミュニケーションにおける「課題の分離」
──日本ではコミュニケーション・デザインを教える人材がいないとのことですが、宮台さんが考える理想的なコミュニケーション・デザインとはどのようなものでしょうか。宮台──コミュニケーション・デザインの中核は、いま申し上げたような体験のデザインです。体験のデザインには「ダイヴ」が必要です。人々が相互にダイヴし合える頻度が上昇するように、デザイナーも人々にダイヴしながら体験をデザインするんです。行為のデザインは、体験のデザインから派生的に帰結されることです。まず、これがポイントです。
次に、コミュニケーションがなしえることの凄まじさを人々に知ってもらうことです。70年代のアメリカで「アウェアネス・トレーニング」と呼ばれる、いまのコーチングにつながる手法が編み出され、70年代末に日本に導入されました。やがてこれが「自己啓発セミナー」と呼ばれ、やがて「人格改造セミナー」とネガティブな呼称に変わっていきます。
僕の世代は、僕自身や、麻原彰晃を含めたオウム教団幹部や、苫米地英人さんなど多くの人がこのトレーニングを1980年前後に受けています。僕らは、3分で言葉を通じて人を気絶させたり嘔吐させたり、そうやってパニックになった人を同じ時間で元に戻すといったワザを、目の当たりにさせられています。口伝えでも凄まじさを教える必要があります。
第三に、ダイヴを奨励する場合に必ず踏まえなければいけないガイドラインがあります。それはアルフレッド・アドラーがいう「課題の分離」の達成です。当時のセッションは手法のベースがフロイト心理学とアドラー心理学の組み合わせから成り立っていたと思います。というのは、そこで「責任」の概念が強調されていたからです。
メンヘラやリストカッターには〈親への恨み〉を抱えた人が多数います。彼らに対して大半のカウンセラーは「キミは悪くない」と言う。親から受けたりしたトラウマを発見させてソレが悪いんだというわけです。アドラーによれば──あるいは当時のセミナーによれば──これは問題を過去に帰属させて自分の「責任」を免除させる姑息な方法です。
そうではなく、自分が最終的にどうなりたいのかを吟味してそれを最終目標とし、それによって現在の優先順位を変更すれば、トラウマどうたらこうたらに関わる営みの優先順位も下げられるだけでなく、前に進む〈内発性〉──アドラーの「勇気」──を獲得できます。これが当時のセミナーのアドラー的な教示です。しかし、そこに大きな問題があるんです。
最終目標を他人によってインストールされれば、それは洗脳されることを意味するからです。実際に昨今企業経営者でアドラーを使おうとする人がいますが、そこには企業に都合がいい勇気をインストールしようとする目論みを感じます。最終目標の設定は、瞑想による過去のリマインドなどを通じ、自分にとって真に幸いなものにしなければなりません。
そして実際、こうした洗脳のプロセスが日常に生じています。それがアドラーの言う「課題の分離」の失敗です。親には親の人生課題があります。子供には子供の人生課題があります。人それぞれに使える人格リソースや時代的地域的社会リソースが違うので、同一の課題はありません。ところが愚かな親は、自分の人生課題と子供の人生課題を混同します。
すると子供は、自分の人生課題と親の人生課題を混同するようになります。これが先に申し上げた「最終目標の他人によるイストール=洗脳」に当たります。しかし実際、いま述べたリソースの違いゆえに、親が達成できると思うことを子供は達成できません。達成に失敗した子供は必ず〈親への恨み〉を懐胎します。これは「課題の分離」の失敗の帰結です。
僕は人を動機づけるような本を書きまが、ファンの一部が「宮台のようになれるかと思ってやってみたけれど、うまくいかないじゃないか」となりがちです。その場合、15年ほど前までは自罰的になる人が多かったのですが、それ以降は他罰的になって「宮台がいけないんだ」という具合になる人が目立つ昨今です(笑)。
でもアドラーによれば、僕が使えるリソースとその人が使えるリソースは人格的にも社会的にも違うので、「宮台のようになる」が最終目標になった時点で、目標混乱があります。つまり「課題の分離」の失敗です。子供は自分と親の課題を分離せねばならず、ファンは自分と宮台の課題を分離せねばなりません。こうした目標混乱が昨今は蔓延しています。
門脇──リソースは固有なもので、そこから組み立てられる目標も個別に違うというのは、「シェア」の話と完全につながりますね。
宮台──そうです。コミュニケーション・デザインは、先に紹介したミード=ローティ的な「感情教育」のプログラムと、いま紹介したアドラー的な「個人心理学」のプログラムを、踏まえなければなりません。「個人心理学」はアドラーの自称ですが、その柱はすでに述べたように、過去のせいにしない「未来の引力」と、自立に不可欠な「課題の分離」です。
20年前に僕が世間に援助交際の存在を知らしめたとき、性の自己決定が大切だ、なにごとも自己決定が大切だと説き、『〈性の自己決定〉原論──援助交際・売買春・子どもの性』(宮台真司、山本直英、藤井誠二、速水由紀子、宮淑子、平野広明、金住典子、平野裕二、紀伊國屋書店、1998)という本もコーディネイトしました。すると各所で「ならば、親は子どもに何も言えないのですね」言われました。愚昧な理解です。そうじゃなく、最終的には自己決定なのだから、何を言ってもいいんですよ。
僕は自分の子供に、「僕が言うことはだいたい間違ってるから、いろいろ言わせて貰うけど、最後は自分で判断してね。僕が言ったようにして失敗しても、僕は知らないからね」と繰り返し言い続けています。これは、アドラーの言う「課題の分離」に相当するコミュニケーションです。
同じく僕は、「細かいヤツは人を不幸にする、特に過去をグジグジ言うヤツはそうだ。自分がやりたいことに比べれば全ては小さい」と繰り返し言い続けています。これは「未来の引力」に相当します。おかげで、僕が子供を叱ると、「パパの言うこと、いつも間違ってるもんねー」「パパ、それって細かいよー」と返すようになりました。成功です(笑)。
時間のデザイン
──最後に、いま建築家という職能の問い直しがさまざまな場面で求められていますが、空間やモノのデザインを再考するうえで、いま決定的に不足していると感じられている要素があれば教えていただけますか。宮台──僕はもともと京都で育ったのですが、児童演劇運動の影響もあって、村芝居や旅芸人の芝居などをたくさん観てきているんですね。僕が通った学校は一燈園というコミューンに芝居を観に行くことが多かったのですが、長い時間歩いてそこに行く。それで歩いているうちに「変性意識状態」に入っていくわけです。
建築は一般的に空間のデザインと考えられていますが、僕はこれを時間のデザインと結びつけてほしいと思っています。僕はキース・ヘリングが好きなのですが、北川原温さんが山梨の小淵沢に設計された《中村キース・ヘリング美術館》は、開館当初、受付から中に入ると、10m以上続く通路が真っ暗でなにも見えなくなっていました。
壁を手探りして長い時間をかけて歩いていくと、行き止まりを右折するようになっていて、すると急に視界が開けて、仄暗い最初の展示室に出るんです。明らかに子宮を通って生まれてくることのメタファーになっていました。そこでは時間がデザインされていたわけです。ちなみに、真っ暗が恐すぎるというので、いまは真っ暗ではない薄暗さです(笑)。
コミュニケーション・デザインのもうひとつの側面が、実はこうした「時間のデザイン」なんです。だんだん引き寄せられるとか、だんだん温まるとか、だんだん息が合うとか、溜めて解放するとか。そういう経験を生み出すのに必要な時間軸のデザインがないがしろにされていて、それゆえに、時間感覚についての極度の劣化が生じているように感じます。
松本雄吉さんが演出する維新派という劇団がありますが、公演を離島で演ったり山奥で演ったりします。その場所に行くだけで何時間もかかります。ヘトヘトになって夕暮れ時にたどり着くと、遠くに明かりの灯った飯場が見えてきて、近づくと飲めや歌えの大騒ぎ。昔の祭を「時間的に」再現しているんです。それで公演自体が濃密な体験になります。
また、結城座という糸あやつり人形劇団が1999年に《アンチェイン・マイ・ハート》というアヴァンギャルド芝居を演りました。演出家の芥正彦さんは、濃密な「変性意識状態」への助走路をどうするかということで、灰野敬二さんに開演30分以上前から大音響のノイズミュージックを演奏させたんですね。
それがホールの外に響き渡る大音量で、おかげで芝居が始まる頃には、観客は、耳がキーンとしていることも含めて、完全にできあがった状態になっていました。実際その後の芝居もすごい経験でした。松本雄吉さんにしても、芥正彦さんにしても「時間の設計」を意識しておられた。アーキテクトの「体験のデザイン」の中核も「時間のデザイン」です。

北川原温建築都市研究所《中村キース・ヘリング美術館》
左上:「闇へのスロープ」(写真 ©Takeshi YAMAGISHI)
右上:「闇へのスロープ」(写真 太田拓実)
左下:「展示室闇」(写真 ©Takeshi YAMAGISHI)
右下:「展示室希望」(写真 太田拓実)
〈クリックで拡大〉

- 北川原温建築都市研究所《中村キース・ヘリング美術館》
「ミュージアムステージ」(写真 Shigeru Ohno)

- 維新派《MAREBITO》(2013) 撮影:井上嘉和、図版提供:維新派

- 結城座《アンチェイン・マイ・ハート》(1999) 図版提供:結城座
──「温まる」とありましたが、それはひとりで温まるわけではなくて、その場全体が温まる、自分はそのなかのひとりであるという、全体性の体験ですよね。
宮台──そう。コミュニケーション・デザインの中核は、体験のデザインで、体験のデザインの中核は、時間のデザインです。時間軸への敏感さが不可欠です。「人間万事塞翁が馬」「終わりよければすべてよし」「雨降って地固まる」という諺があります。昨今の若い男女は、浮気バレですぐに関係が解消してしまうでしょう。ありえないことです。
そうやって泡だったカオスの波が、時間が経って収束したとき、2人は以前とは違った場所に着地している。そのとき「あれがあったから、いまがあるんだな」と思えるようになります。そう思えるようになった関係は、すでに取り替え不可能なものになっています。そういう関係の履歴こそが唯一性という全体性を保証するんです。
でも、昨今では多くの人がそうは考えず、「シロかクロか、いますぐ決着するぞ」とばかりに結果を欲しがります。あるいは、長い時間待つ場合にも「いい結果が出ること」への証明書を欲しがってしまいます。そこがとても大きな問題だと思っています。建築家はそうしたニーズに応えず、むしろ徹底的に介入的に振る舞っていただきたいと思っています。
門脇──今日は「シェア」をキーワードとして、われわれの社会が置かれている状況についての広範なお話しを伺うことができました。そして、それはなかなかキツい状況にある。そのキツさとは、この社会が抱えている困難な状況そのものにあるというよりも、むしろその困難を脱する道のりがあまりに遠いことが見えてしまっていることにある──そんなことを、今日のお話を伺って思いました。しかし、その困難な道のりへの歩みをなんとか進めるにあたっては、この社会が制度や市場ばかりではなく、空間や人の生き方によっても規定されているがゆえに、われわれ建築や都市に携わる人間にも、あるいはこの社会に生きるひとりの人間としても、なにかしら役立てる場面がある。それがわかったことは、ひとつの希望になりうるだろうとも思いました。宮台さんがおっしゃるように、これから互いに力を合わせられる機会も増やしていきたいですね。今日は長い時間ありがとうございました。
註
★1──ギークハウス:PCやエンジニアリングに精通したギーク(技術オタク)が集まるシェアハウスとして2008年に始動。
★2──渋家(シブハウス):渋谷を拠点とするシェアハウス。家を24時間365日開放することで新しい関係性を生み出すことを試みている。
★3──メンヘラ:メンタルヘルスの略称。自傷行為を行なう、気分の浮き沈みが激しいなど、精神的に不安定な人を指す。
★4──公共経済学:市場原理のあてはまらない公共分野において経済分析を行なうことで、公益事業と民間事業との連関を促す分野。
★5──変性意識状態(Altered state of consciousness):覚醒していない意識の状態。変性意識状態の一種として睡眠麻痺(金縛り)やトランス状態がある。
[2014年5月14日、LIXIL:GINZAにて]
宮台真司(みやだい・しんじ)
1959年生まれ。首都大学東京教授、社会学。主な著書=『権力の予期理論』(1989)、『終わりなき日常を生きろ』(1995)、『まぼろしの郊外』(1997)、『絶望から出発しよう』(2003)、『14歳からの社会学』(2008)、『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』ほか。http://miyadai.com
門脇耕三(かどわき・こうぞう)
1977年生まれ。建築計画、建築構法、建築設計。東京都立大学助手、首都大学東京助教を経て、現在、明治大学専任講師。http://www.kkad.org/


